 ホームページへ |
 目次に戻る |
| |
▼600年前のアジア人鄭和の大遠征航海▼
2005年は鄭和の大遠征航海から600周年に当たる。中国明朝の3代目皇帝永楽帝(在位1402-24)は、15世紀前半、鄭和(1371?-1433?、宦官、その長、三保太監)を指揮者として、7回にわたって東南アジア・インド洋・ペルシア湾からアフリカ東岸に、海上遠征を行う。この鄭和の大遠征航海は、いうまでもなく、マルコ・ポーロが元から帰国してから約100年後、またイブン・バットゥータが元を訪問(?)してから約50年後、そしてバスゴ・ダ・ガマのカリカット到着の約60年前に行われた遠征航海事業である。その7回にわたる遠征は、その時期や範囲から、大きく次にように分けられる。
(1) 第1-3次遠征:東南アジアから南インドまでの遠征、
(2) 第4-6次遠征:南インドを越えてアラビア半島、アフリカ東海岸までの遠征、
(3) 第7次遠征:第6次遠征から9年後に行われた遠征
この鄭和大遠征より前に、永楽帝は1403(永楽元)年に聞良輔らを使者として、爪哇国(ジャワ)・満刺加(マラッカ)・蘇門答刺(スマトラ)・柯枝(コーチン)・西洋(チョーラ、南インド・コロマンデル海岸)の諸国に出立させている。これは鄭和大遠征の準備外交あるいは予備調査であったとみられる。
7回の遠征の出立と帰還の年次は、次の通りである。
2005年は鄭和の大遠征航海から600周年に当たる。中国明朝の3代目皇帝永楽帝(在位1402-24)は、15世紀前半、鄭和(1371?-1433?、宦官、その長、三保太監)を指揮者として、7回にわたって東南アジア・インド洋・ペルシア湾からアフリカ東岸に、海上遠征を行う。この鄭和の大遠征航海は、いうまでもなく、マルコ・ポーロが元から帰国してから約100年後、またイブン・バットゥータが元を訪問(?)してから約50年後、そしてバスゴ・ダ・ガマのカリカット到着の約60年前に行われた遠征航海事業である。その7回にわたる遠征は、その時期や範囲から、大きく次にように分けられる。
(1) 第1-3次遠征:東南アジアから南インドまでの遠征、
(2) 第4-6次遠征:南インドを越えてアラビア半島、アフリカ東海岸までの遠征、
(3) 第7次遠征:第6次遠征から9年後に行われた遠征
この鄭和大遠征より前に、永楽帝は1403(永楽元)年に聞良輔らを使者として、爪哇国(ジャワ)・満刺加(マラッカ)・蘇門答刺(スマトラ)・柯枝(コーチン)・西洋(チョーラ、南インド・コロマンデル海岸)の諸国に出立させている。これは鄭和大遠征の準備外交あるいは予備調査であったとみられる。
7回の遠征の出立と帰還の年次は、次の通りである。
| |
|
|
|
|
| 第1次 夢2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 |
永楽3年冬(1405) 永楽5年冬(1407) 永楽7年9月(1409) 永楽11年冬(1413) 永楽15年冬(1417) 永楽19年春(1421) 宣徳5年12月(1430) |
永楽5年9月(1407) 永楽7年夏(1409) 永楽9年6月(1411) 永楽13年7月(1415) 永楽17年7月(1419) 永楽20年8月(1422) 宣徳8年7月(1433) |
62 48 63 61 |
27800 27000 27670 27550 |
| 出所:宮崎正勝著『鄭和の南海大遠征 永楽帝の世界秩序再編』、p.91-2、中公新 書、1997、典拠:中国航海史研究会編『鄭和下西洋』、人民交通出版社、1985。 |
これら遠征によって、明の使節が訪れた国は、その正史の『明史』によれば、30余か国に及 んでいる。そのなかには、いくつかの訪問国の過不足があるようであるが、地域別に整理すれ ば、次の通りである。ここで重要なことは、それら国々のほとんどが鄭和の遠征隊に同道する などして、明に朝貢して来るようになったことである。
| |
|
| |
占城(チャンパ)・爪哇(ジャワ)・真臘(カンボジア)・旧港(パレンバン)・暹羅(シャム)・彭享(バハン)・急蘭丹(ケランタン)・渤泥(ボルネオ)・満刺加(マラッカ)・阿魯(アルー)・蘇門答刺(スマトラ)・南巫里(ランブリ)・喃渤里(ランブリ)・沙里汚泥(ナガバタン)・那孤児(ナクール)・黎伐(リディ) |
| |
西洋瑣里(チョーラ)・瑣里(チョーラ)・加異勒(カヤール)・錫蘭山(セイロン)・溜山(モルディフ)・大葛蘭(キーロン)・小葛蘭(キーロン)・柯枝(コーチン)・古里(カリカット)・甘把里(カンペリ) |
| |
忽魯謨厮(オルムズ)・祖法児(ズファール)・阿撥把丹(アーメダバード、阿丹(アデン)のこと)・天方(メッカ) |
| |
木骨都刺(束)(モガディシオ)・竹歩(ジューブ)・比刺(ブラワ)・麻林(マリンディ)・孫刺(マンダ) |
なお、元・明の時代において、東洋と西洋はマラッカ海峡を境にして、区切られていた。した がって、鄭和の大遠征あるいは大航海は、「下西洋」すなわち「西洋下り」とされる。
▼鄭和大遠征に関する限られた記録▼
鄭和の大遠征あるいは大航海といわれながら、それに関する史料は乏しい。それはいうまで もなく、成化帝(在位1464-87)の時代に入ると、海外遠征の負担に耐えられなくなり、ベトナム進攻に猛烈に反対した劉大夏の手によって、鄭和の航海に関する記録や文書はすべて焼き払われてしまったからである。
そのなかにあって、『皇明実録』や『明史』の他、第4、6、7次遠征に参加した馬歓の『瀛涯勝覧』(1416年記)や第3、4、7次遠征に参加した費信の『星槎勝覧』(1436年記)、第7次遠征に参 加した鞏珍の『西洋番国志』(1434年記)という史料がある。しかし、これらとて、不十分である。例えば、『瀛涯勝覧』でさえアフリカ東岸に関する記事は皆無である。
ここで取り上げる馬歓の『瀛涯勝覧』は、7次にわたる遠征のうち、主として第4次遠征を記録し、永楽14(1416)年に書き記したとされる。馬歓は、鄭和と同じイスラーム教徒であり、その航海の通訳として参加したが、それ以上は不明のようである。
▼鄭和大遠征に関する限られた記録▼
鄭和の大遠征あるいは大航海といわれながら、それに関する史料は乏しい。それはいうまで もなく、成化帝(在位1464-87)の時代に入ると、海外遠征の負担に耐えられなくなり、ベトナム進攻に猛烈に反対した劉大夏の手によって、鄭和の航海に関する記録や文書はすべて焼き払われてしまったからである。
そのなかにあって、『皇明実録』や『明史』の他、第4、6、7次遠征に参加した馬歓の『瀛涯勝覧』(1416年記)や第3、4、7次遠征に参加した費信の『星槎勝覧』(1436年記)、第7次遠征に参 加した鞏珍の『西洋番国志』(1434年記)という史料がある。しかし、これらとて、不十分である。例えば、『瀛涯勝覧』でさえアフリカ東岸に関する記事は皆無である。
ここで取り上げる馬歓の『瀛涯勝覧』は、7次にわたる遠征のうち、主として第4次遠征を記録し、永楽14(1416)年に書き記したとされる。馬歓は、鄭和と同じイスラーム教徒であり、その航海の通訳として参加したが、それ以上は不明のようである。
 |
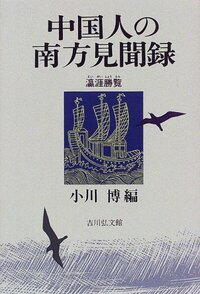 |
| 雲南省昆陽の鄭和公園に 航海図を手に握って立つ |
この『瀛涯勝覧』は、小川博氏によって1969年に翻訳と注解が行われていたが、現在、『中国人の南方見聞録―瀛涯勝覧―』(吉川弘文館、1998)として容易に利用できる。瀛涯(えいがい)とは大海のはてというほどの意味である。瀛西といえば、西洋となる。小川博氏の書物には、『瀛涯勝覧』とともに、『星槎勝覧』の該当箇所が訳出、挿入されている。なお、ここで取り上げる訪問国の順序は、『瀛涯勝覧』の通りではない。 馬歓は、その序において、まず「わたくしは、かつて島夷誌[元代の旅行家・汪大淵『島夷志略』(1349年頃記)をいう]を読んで、天の時、気候の別、地理、人物の異(ちがい)が書かれているのに感嘆して」いたという。そして、「永楽11年癸巳(1413)の年、太宗文皇帝の勅命により正使太監鄭和は宝船を指揮して西洋諸番国に赴き、皇帝のお言葉や賜わり物を伝えられました。わたくしも通訳の任をうけて使節のはしに加えられ、随行してまいり、見渡すかぎりの海や波をこえ、その幾千万里かもしれないかなたに至り、諸国を歴巡して、その天の時、気候、地理、人物をこの目で見、我が身で経験しました」。また、かの「島夷誌に書き誌されていることに嘘でないばかりか、それよりもさらに奇怪なることがあることを知り得たのであります」という(小川前同、p.1)。
馬歓の『瀛涯勝覧』に立ち入る前に、それには第4次遠征以外の記事も含まれていることでもあり、7次にわたる鄭和の大遠征の概要をなぞることとする。なお原文の「宝船」は「西洋派遣船隊」と意訳されている。
馬歓の『瀛涯勝覧』に立ち入る前に、それには第4次遠征以外の記事も含まれていることでもあり、7次にわたる鄭和の大遠征の概要をなぞることとする。なお原文の「宝船」は「西洋派遣船隊」と意訳されている。
 |
| 鄭和の第4次遠征ルート |
▼鄭和第1-3次遠征の概要▼
第1次遠征は、1405(永楽3)年6月に命令が下ったが、冬モンスーンを利用する必要から、いずれの遠征と同じように、その年の冬に出帆したとされる。このときの艦隊は62隻・27800余人であった。まず、長江河口の劉家港より、福建の五虎門(五虎島の海門)に立ち寄って、解纜する。
その後、占城(チャンパ)を経て、さらにシナ海を南下し、爪哇(ジャワ)に入る。そこで、王位継承にからんだ内乱に巻き込まれ、鄭和の士卒170人が戦死する。東王を破った西王は明に謝罪使を送り、黄金6万両の賠償を課せられることとなった。しかし、払ったのは1万両だけで、その残りは免除される。
そこから西に向かい、旧港(パレンバン)に入るが、そこで定住する華僑の頭目争いに介入する(詳細は後述)。その後、満刺加(マラッカ)・阿魯(アルー)・蘇門答刺(スマトラ)に立ち寄り、ベンガル湾に出でて、錫蘭山(セイロン)・小葛蘭国(キーロン)を経て、最終目的地の古里(カリカット)に至る。このカリカットでは建碑したという。
分遣隊はシャムに向かい、シャムのアユタヤ朝やジャワのマジャパイト朝から圧迫されていた、マラッカを冊封体制に組み込むことで保護することとなった。そして、鄭和はマラッカに「官廠」を建設して、艦隊の集結地あるいは遠征の中継地とした。これによりマラッカは東南アジアにおける有力な港市国家として発展することとなる(詳細は後述)。
鄭和は、錫蘭山(セイロン)において、朝貢の招諭に失敗する。「帰途、再びセイロンに寄ると、[王は]鄭和を誘い、その際に兵50000を発し、船隊を襲い、鄭和の帰路を断たんとした。鄭和はこの謀計をさとり……自ら手兵2000(あるいは3000)を率いて、不意に王城を攻め、攻戦6日、国王を生け捕りにし」(小川前同、p.213-4)、さらに中国まで連れ帰る。永楽帝はセイロン王の帰国を許す。それ以後、その間に友好関係が築かれる。なお、この戦闘は7次の大遠征のなかで、唯一の本格的な戦闘であったとされる(詳細は後述)。
この第3次遠征の招諭の結果として、「古里(カリカット)・柯枝(コーチン)・蘇門答刺(スマトラ)・阿魯(アルー)・彭享(バハン)・急蘭丹(ケランタン)・南巫里(ランブリ)・加異勒(カヤール)・爪哇(ジャワ)の新村(グリッセ)の国々の使者がやって来た」という(小川前同、p.216)。
▼鄭和第4-6次遠征の概要▼
第4次遠征に入ると、その遠征範囲は東南アジアや南インドを越えて、アラビア半島、アフリカ東海岸に及ぶこととなる。それに伴って、遠征の出立は2年間隔から4年間隔となる。第4次遠征は、馬歓が『瀛涯勝覧』を書くこととなる、最初の遠征であった。
第4次遠征は、前年に命令は下っていたが、第3次遠征後少し期間をおいた1413(永楽11)年冬、63隻27670人の艦隊として出立する。従来通り、東南アジアを歴訪するが、蘇門答刺(スマトラ)で王位継承争いに巻き込まれる(詳細は後出)。
この蘇門答刺(スマトラ)から、鄭和の本隊は南インドを経て、最終目的地の忽魯謨厮(オルムズ)まで行くこととなる。第4次遠征において、初めて本格的な分遣隊が編成されることとなる。それは、蘇門答刺(スマトラ)から溜山(モルディフ)を経て、西に向かい、木骨都刺(束)(モガディシオ)・卜比刺あるいは不刺哇(ブラワ)・麻林(マリンディ)を歴訪し、そして北上して、阿丹(アデン)・刺撤(ラサ)・祖法児(ズファール)を経て、忽魯謨厮国(オルムズ)に至り、その後帰国したとされる。
これら第5、6次遠征に関する情報は極めて少ないが、『瀛涯勝覧』にはいくつかの記事があるが、そのなかでも阿丹(アデン)の記事は興味深い(詳細は後述)。
▼鄭和最後の第7次遠征、倒れて後やむ▼
1424(永楽22)年、鄭和大遠征を推進してきた永楽帝が死に、その後を洪熙帝が継ぐが、対外遠征は停止される。その後を、1425(洪熙元)年宣徳帝(在位1425-35)が継ぐ。
第7次遠征は、第6次遠征より9年後に、命令が下る。その命は永楽帝ではなく宣徳帝から受けることとなる。この遠征については出使官の氏名、主な宝船の船名、艦隊の編成、航海の行程などについて、いままでになく記録が残っている。いま、明代の文人である祝允明(1460-1526)の『前聞記』の下西洋の条には、遠征本隊の航海行程が、次のように書き留められている。
第1次遠征は、1405(永楽3)年6月に命令が下ったが、冬モンスーンを利用する必要から、いずれの遠征と同じように、その年の冬に出帆したとされる。このときの艦隊は62隻・27800余人であった。まず、長江河口の劉家港より、福建の五虎門(五虎島の海門)に立ち寄って、解纜する。
その後、占城(チャンパ)を経て、さらにシナ海を南下し、爪哇(ジャワ)に入る。そこで、王位継承にからんだ内乱に巻き込まれ、鄭和の士卒170人が戦死する。東王を破った西王は明に謝罪使を送り、黄金6万両の賠償を課せられることとなった。しかし、払ったのは1万両だけで、その残りは免除される。
そこから西に向かい、旧港(パレンバン)に入るが、そこで定住する華僑の頭目争いに介入する(詳細は後述)。その後、満刺加(マラッカ)・阿魯(アルー)・蘇門答刺(スマトラ)に立ち寄り、ベンガル湾に出でて、錫蘭山(セイロン)・小葛蘭国(キーロン)を経て、最終目的地の古里(カリカット)に至る。このカリカットでは建碑したという。
| 第1次遠征隊は、1407(永楽5)年9月に帰還するが、その際、満 刺加(マラッカ)・阿魯(アルー)・蘇門答刺(スマトラ)・小葛蘭国(キ ーロン)・古里(カリカット)・爪哇(ジャワ)の使者が同行し、明の宮 廷に入貢させている。 第2次遠征は、鄭和が帰還するとすぐ命令が下され、1407(永楽 5)年冬古里(カリカット)を目的地として出立し、1409(永楽7)年夏 帰還する。この遠征の記録は乏しい。この遠征の特異さは、第1 次遠征になかった暹羅(シャム)に訪問したこと、そして錫蘭山(セ イロン)の別羅里(ペルワラ、ガレまたはゴールの近郊)に、漢文、 タミル語、ペルシア語で書かれた記念碑を建設していたことで、そ の遠征が確認されえたことであった。 明は、マラッカやスマトラを圧迫するシャムのアユタヤ朝の行動 を抑えるために、1408(永楽6)年張原を派遣して、厳重な警告を与 えていた。この張原の行動に鄭和の第2次遠征が連動して、シャ ムに圧力をかけていたのである。それに屈したシャムは明の冊封 体制に組み込まれる。 第3次遠征は、帰還するとすぐ命令が下され、1409(永楽7)年9 月古里(カリカット)を目的地として、48隻27000人で出立し、1411 (永楽9)年6月帰還する。この遠征では、鄭和の本隊はジャワ、 |
 |
| ゴールに建てた石碑 コロンボ国立博物館蔵 |
鄭和は、錫蘭山(セイロン)において、朝貢の招諭に失敗する。「帰途、再びセイロンに寄ると、[王は]鄭和を誘い、その際に兵50000を発し、船隊を襲い、鄭和の帰路を断たんとした。鄭和はこの謀計をさとり……自ら手兵2000(あるいは3000)を率いて、不意に王城を攻め、攻戦6日、国王を生け捕りにし」(小川前同、p.213-4)、さらに中国まで連れ帰る。永楽帝はセイロン王の帰国を許す。それ以後、その間に友好関係が築かれる。なお、この戦闘は7次の大遠征のなかで、唯一の本格的な戦闘であったとされる(詳細は後述)。
この第3次遠征の招諭の結果として、「古里(カリカット)・柯枝(コーチン)・蘇門答刺(スマトラ)・阿魯(アルー)・彭享(バハン)・急蘭丹(ケランタン)・南巫里(ランブリ)・加異勒(カヤール)・爪哇(ジャワ)の新村(グリッセ)の国々の使者がやって来た」という(小川前同、p.216)。
▼鄭和第4-6次遠征の概要▼
第4次遠征に入ると、その遠征範囲は東南アジアや南インドを越えて、アラビア半島、アフリカ東海岸に及ぶこととなる。それに伴って、遠征の出立は2年間隔から4年間隔となる。第4次遠征は、馬歓が『瀛涯勝覧』を書くこととなる、最初の遠征であった。
第4次遠征は、前年に命令は下っていたが、第3次遠征後少し期間をおいた1413(永楽11)年冬、63隻27670人の艦隊として出立する。従来通り、東南アジアを歴訪するが、蘇門答刺(スマトラ)で王位継承争いに巻き込まれる(詳細は後出)。
この蘇門答刺(スマトラ)から、鄭和の本隊は南インドを経て、最終目的地の忽魯謨厮(オルムズ)まで行くこととなる。第4次遠征において、初めて本格的な分遣隊が編成されることとなる。それは、蘇門答刺(スマトラ)から溜山(モルディフ)を経て、西に向かい、木骨都刺(束)(モガディシオ)・卜比刺あるいは不刺哇(ブラワ)・麻林(マリンディ)を歴訪し、そして北上して、阿丹(アデン)・刺撤(ラサ)・祖法児(ズファール)を経て、忽魯謨厮国(オルムズ)に至り、その後帰国したとされる。
| 本隊は1415(永楽13)年7月、分遣隊は1416(永楽14)年に 帰国したとみられる。 この遠征で、「永楽14年(1416)11月戊子朔条の皇明実録 には、古里(カリカット)・満刺加(マラッカ)・占城(チャンパ)・ 蘇門答刺(スマトラ)・南巫里(ランブリ)・沙里汚泥(ナガバタ ン)・彭享(バハン)・錫蘭山(セイロン)・木骨都刺(束)(モガデ ィシオ)・溜山(モルディフ)・喃渤里(ランブリ、南巫里と重複)・ 不刺哇(ブラワ)・阿丹(アデン)・麻杖(マリンディ)・刺撤(ラ サ)・忽魯謨厮(オルムズ)・柯枝(コーチン)の諸国と旧港国 (パレンバン)宣慰司が、貢物を献じた」とされる(小川前同、 p.21)。 第5次遠征は、前年に命令は下っていたが、1417(永楽15) 年冬出立する。この遠征の特徴は、第4次遠征の帰還した 際連れ帰っていた、満刺加(マラッカ)など19か国の使節を 帰国させることにあった。そして、本隊は1419(永楽17)年7 月帰還するが、その際17か国の使節や阿魯(アルー)・喃渤 里(ランブリ)の王子が連れ帰ったという。なお、馬歓はこの 遠征に参加していない。 この遠征でも分遣隊が編成され、第4次遠征と同じ地方に 向かった。彼らは1421(永楽19)年帰還するが、忽魯謨厮国 (オルムズ)が獅子・金銭豹(金線のあるひょう)・大西馬(大 天馬のことか)、阿丹国(アデン)の麟麟(きりん)・長角馬喰 獣を、木骨都刺(モガディシオ)国の花福鹿(しまうま)と獅子、 不刺哇国(ブラワ)の駱駝と駝鶏、爪哇国(ジャワ)・古里国 (カリカット)の糜黒羔獣といった献上品を持ち帰る。 第6次遠征も、第5次遠征と同じようなかたちとなり、1419 (永楽17)年に命令は下り、その春か秋に15か国の使節とと もに出立し、本隊は1422(永楽20)年8月、分遣隊は1423(永 楽21)年に帰還する。その結果として、暹羅(シャム)の他、 15か国1200人の使節が来朝したことになっている。 |
 |
| 持ち帰ったとされるキリン 永楽帝が沈度 (1357-1434)に描かせた フィラデルフィア美術館蔵 なお、第5次遠征はアデン、第7次遠征はメッカからも、持ち帰っている。 |
▼鄭和最後の第7次遠征、倒れて後やむ▼
1424(永楽22)年、鄭和大遠征を推進してきた永楽帝が死に、その後を洪熙帝が継ぐが、対外遠征は停止される。その後を、1425(洪熙元)年宣徳帝(在位1425-35)が継ぐ。
第7次遠征は、第6次遠征より9年後に、命令が下る。その命は永楽帝ではなく宣徳帝から受けることとなる。この遠征については出使官の氏名、主な宝船の船名、艦隊の編成、航海の行程などについて、いままでになく記録が残っている。いま、明代の文人である祝允明(1460-1526)の『前聞記』の下西洋の条には、遠征本隊の航海行程が、次のように書き留められている。
鄭和の第7次遠征本隊の航海行程
| 宣徳5年(1430 )閏12月6日 竜湾(南京の北)を開航[つくりは工](出船)。 閏12月10日 徐山に到る。打囲(注1) 閏12月20日 附子門に出る。 閏12月21日 劉家門(劉家港)に到る。 宣徳6年(1431) 2月26日 長楽港(福建)に到る。 11月12日 福斗山に到る。 12月9日 五虎門を出る。行くこと16日。 12月24日 占城(チャンパ)に到る。 宣徳7年(1432) 正月11日 開航。行くこと25日。 2月6日 爪哇(ジャワ)の斯魯馬益(スラバヤ)に到る。 6月16日 開航。行くこと11日。 6月27日 旧港に到る。 7月1日 開航。行くこと7日。 7月8日 満刺加(マラッカ)に到る。 8月8日 開航。行くこと10日。 8月18日 蘇門答刺(スマトラ)に到る。 10月10日 開航。行くこと26日。 11月6日 錫蘭山(セイロン)の別羅里(ペルワラ)に到る。 11月10日 開航。行くこと9日。 11月18日 古里国(カリカット)に到る。 |
11月22日 船を開き、行くこと35日。 12月26日 忽魯謨厮(オルムズ)に到る。(注2) 宣徳8年(1433) 2月18目 船を開きて洋を回る。行くこと23日。 3月11日 古里に到る。 3月26日 大宗船(船隊)、洋に回り、行くこと17日。 4月6日 蘇門搭刺に到る。 14月2日 船を開き、行くこと9日。 4月20日 満刺加に到る。 5月10日 回りて崑崙洋(プロ・コンドル諸島)に到る。 5月23日 赤坎(?)に到る。 5月26日 占城に到る。 6月1日 開航。行くこと2日。 6月3日 外羅山に到る。 6月9日 南澳山を見る。 6月10日晩、望郎回山を望見す。 6月14日 崎頭洋に到る。 6月15日 碗喋嶼に到る。 6月20日 大小赤を過ぎ、 6月21日 大倉に進む。後程、録せず。 7月6日 京に到る。 7月21日 奨衣宝鈔を関賜さる |
(注2) この間、天方(メッカ)への分遣隊が合流したとされる。
1430(宣徳5)年12月、艦隊61隻27550人でもって出立する。この第7次遠征は忽魯謨厮(オルムズ)をはじめ20か国の朝貢を促して、朝貢交易の衰微を盛り返すことにあった。さらに、ベトナム経営に失敗するなかで、その冠たる威光を再びアジアに知らしめる必要に駆られたからであった。その本隊は、1433(宣徳8)年6月帰還している。その際、真臘(カンボジア)をはじめ11か国の使節を連れ帰ったとみられ、彼らは入京後、対外遠征がなくなったため留め置かれる。1436(正統元)年6月になって、爪哇(ジャワ)使節の帰還船に便乗することとなったが、その帰途、嵐に遭難し、溺死者56人、生存者83人という被害を受けている。
▼第4次遠征隊、華僑が定住する国々に入る▼
これ以下が『瀛涯勝覧』が示す海上交易に関する記事である。
すでに述べたように、第4次遠征から鄭和の遠征は、新しい段階に入る。それにより西アジアのイスラーム教徒のインド洋交易圏により深く分け入ることとなる。
鄭和の第4次遠征の艦隊は63隻27670人であった。彼らは、大倉(江蘇・揚子江江口附近)の劉家港より出帆し、そして「福建の福州府長楽県五虎門から船を出して、西南に向かい風向がよければ10日ばかりで着くことができ」、広東、海南島の南にある、占城国(チャンパ、Champa)に入る(小川前同、p.7)。この国は「後漢末に興起してから明の中期に滅亡するまで、1300年にわたって独立を続けてきた。そして、中国においては林邑(2-8世紀)・環王(8-9世紀)・占城(9-17世紀)と呼ばれ……中国の朝貢国としてその関係は保たれてきた」と解説される(小川前同、p.13)。
「この国の東北100里に海港があり、新洲港という」。この新洲港は、現在の越南平定省の帰仁(クニヨン)である。「ここでの売買交易には7分金かあるいは銀を使用する。中国の青磁の皿や碗などの品、緞子、綾絹、焼珠(ビーズ)などは大事にされていて、7分金と交換する。いつも犀角、象牙、伽藍香(伽羅木)などの物を中国に進貢してくる」という(小川前同、p.12)。
チャンパを出て、順風20昼夜で、古くは闇婆国といった爪哇国(ジャワ、Java)に入る。外国の船が来ると、杜板(トバン)と、新村(グリッセ)、蘇魯馬益(スラバヤ)に入港する。さらに、満者伯夷(マジャパイト)というところには、マジャパイト王朝の国王が居住していた(小川前同、p.21)。
トバンには「約1000軒余あり、2人の頭目が治めている。ここには沢山の中国の広東、章州の人が流れて来ている」という。「伝説では元代の史弼、高興[1292(至元29)年、フビライ・ハーンが敗退したジャワ遠征の中国人指揮者。モンゴル人指揮者は亦黒迷矢]が闇婆を攻めたときに、幾月も上陸できなくて船中の飲料水が尽きようとして、兵士たちは困った」ところでもあった。また、グリッセは砂洲であった土地に、「中国の人々がここにやって来て始めて住みついたことにより新村と名づけられ、今に至るまで村主は広東人である。約1000軒余りあり、各地の人々がここに来て売買する。金や宝石などいろいろの品物が売られ甚ださかんな所である」(小川前同、p.23)。
このように、ジャワの海港には華僑が定住しているが、そればかりか「この国には三種の人々がいる。一種はイスラム教徒(回回人)でみな西方諸国の商人であり、この地に流れて来たもので、衣食その他は洗練されている。一種は中国人(唐人)でみな広東、章州、泉州の人々のここに逃れて来たもので、日常生活は清潔で、多く(ママ、は?)イスラム教を信じおつとめをしている。一種は原住民で顔かたちはみにくく、もじゃもじゃ髪であかはだしで鬼教を信じている」(小川前同、p.26)。これからみれば、華僑はディアスポラ(離散)したイスラーム教徒ということになる。
「土地の人で物持ちは甚だ多く、売買交易には歴代の中国の銅銭が使われている」。「この国の人たちは中国の青花磁器、麝香、金糸布、ビーズの類を喜び、銅銭でもって買いとる。国王は常に頭目を差し遣わし、船に献上物をのせて中国に進貢している」(小川前同、p.28、29)。
ジャワ島からスマトラ島に向かって、順風8昼夜で、旧港国(パレンバン、Palembang)に着く。そこは室利仏逝とか三仏斉とか呼ばれ、栄えていたところであった。いまでは「爪哇国が管轄している……あちこちの船が来ると、まず淡港[河畔]に入り、船を岸につなぎ……小舟に乗りかえて港内に入り、この国に至るのである。この国には広東、章州、泉州の人々の逃げこんできているものが多い」(小川前同、p.42)。
ここにも華僑が住み着いていた。彼らは紛争を起こしていたが、鄭和は1405(永楽3)年冬に出発した第1次遠征の際、それに介入している。その経過を、馬歓は、次のような挿話としてまとめる。「昔、洪武年間(明の太祖、朱元璋の年号、1368-98年)に広東の人、陳祖義が家をあげてここに逃げこみ、ついに頭目となり、勢威を振るい、およそここを通る客船があれば、その貨財の物を奪い取っていた。永楽5年(1407)に明の朝廷は太監鄭和たちを統領とし、西洋派遣船隊を率いて差し遣わして、ここに至らしめた。
ここには施進卿というものがおった。彼は広東の人であったが、陳祖義の横暴の状況を報告したので、太監鄭和は陳祖義などを生けどりにし、〔明の〕朝廷に連れて帰り、処罰した。そして、施進卿には冠帯を賜い、旧港に帰して大頭目としてそこの『たいしょう』[旧港宣慰司のこと]にした。本人は死んだが位は子に伝わらず、その娘の施二姐が大頭目となったが、一切の賞罰や進退は前のとおりであった」(小川前同、p.43)。
パレンバンの「市中の売り買いには中国の銅銭を使うが、布きれなども使われている。国王はいつも貢納物を明の朝廷に献じていたが、今に至るまで途絶えたことはなかった」(小川前同、p.45)。この国の「物産は黄熟香、速[連]香[健胃剤]、降[真]香[焚香類]、沈香、黄蝋(蜜蝋)、ならびに鶴頂鳥[犀鳥の一種]の類である。交易には五色のビーズや青白磁器、銅鼎、五色の色絹、色段子(どんす)、大小の磁器、銅銭などを使う」という(『星槎勝覧』、小川前同、p.49)。
▼シャム、それから自立した、マラッカ▼
ここで、1407(永楽5)年冬に出立した第2次遠征の記録が挿入される。「占城より西南に向かって船で行くこと、7昼夜(あるいは10昼夜)ばかりで順風なら新門台(シンメンタイ)に至る。江口に入港してわずかばかり行くと、この国に行き着く」という(小川前同、p.51)。この国とは暹羅国(シャム、Siam)である。さらに、「この国の西北に去ること200余里ばかりの所に交易都市があり、上水(シャンスイ)といわれている。雲南の後門に通ずることができる……中国の宝船(西洋派遣船隊)が暹羅にくると、小舟に乗り換えて〔上水に〕行って売買してくる」(小川前同、p.53)。
また、『星槎勝覧』によれば、「中国の歴代の銅銭は使われていない。ここの王様はいつも頭目を差し遣わし、蘇木、降真香などを中国に貢献している」(小川前同、p.54)。交易品としては、中国向けには「羅斜香……つぎは沈香で、つぎはすおう(蘇木)、犀角、象牙、翠毛[かわせみの毛]、黄蝋、大風子油[駆虫剤]などがあり、[シャム向けには]青白花磁器(青い紋様のある磁器で、日本でいう染付け磁器)、印花布[サラサ]、色絹、緞子、金銀銅鉄、ビーズ、水銀、雨傘などである」という(小川前同、p.61)。
文面ではマラッカ海峡に入っているが、再び「占城から真南に向かって風がよければ船で8日ばかりかかって竜牙門[シンガポール海峡の南、ビンタン島とバタム島の間にある、リオウ海峡]に着く。[さらに]竜牙門より西に向かって2日ばかりで」、満刺加国(マラッカ、Malaka)に着くことができる。
ここはもと、国になっておらず、国王もおらず、「暹羅の所轄しているところで、毎年金40両を差し出している。そうしないと征伐されるのである。永楽7年(己丑・1409)に、[第3次遠征]正使の太監鄭和〔等〕が明の皇帝の命を奉じて、西洋派遣船隊を率いて来たり、詔勅をもたらし、ひとそろいの銀印と冠帯、袍服を頭目に賜い、碑を建て城を封じて、満刺加国と名づけた」ところであった。
「その後、暹羅は敢て侵入することはなかった。その頭目は恩を蒙って王となり、妻子を伴って明の都に来たり感謝して貢物を献じたので、明の朝廷は船舶を与えて国に帰らせそこを守らせたのである」。ここの人々は王をはじめ、すべてイスラーム教徒である(以上、小川前同、p.62)。
鄭和の第3次遠征艦隊は、「ここに来航して、城垣のような柵を作り、4つの門、物見櫓(更鼓楼)などを設け、夜は鈴を鳴らして巡羅し、中には二重に柵に立てて、小城のようである。そして、倉庫を作って一切の銭や食糧を入れておき、各地に行く船舶がここに来ると交易物を取り出し、そろえてから船に積み込み、南の風の具合を窺って、5月中旬に航海を開始し中国に向かったのである。そして、ここの国王も自ら進物をととのえ妻子を伴い、頭目たちを引き連れ、鄭和の船隊につき従って明の都にやって来て貢献をした」(小川前同、p.65-6)。
こうしたマラッカの成立とその朝貢について、小川博氏は「建設者パラメスワラ[?-1414](マレイ語では王女より身分の低い配偶者を意味する)邦里迷蘇刺は、シャム(暹羅)の圧迫に抗するため明の勢威を借りんとした。明史満刺加伝(巻325)によると永楽元年(1403)宦官伊慶が派遣された。そして、永楽3年(1405)に使を遣わして朝貢し来たり、満刺加国王に封ぜられた。その後、永楽5年(1407)にも遣使入貢があり、6年(1408)には鄭和が赴き、9年(1411)には満刺加国王は妻子陪臣540余人を率いて入朝し、10年(1412)には王の姪が謝礼のため入朝したとある。その後、12年(1414)には王子イスカンダル・シャー母幹撤干的児沙が来朝してその父の訃を告げたので、襲封を命じ、更に17年(1419)にも妻子を率いてまた来朝し、暹羅の侵略を訴えたので、暹羅に勅諭をもたらし、暹羅はその命を奉じたとある。この後もマラッカとの朝貢関係は続くのである。
このように、マラッカはパラメスワラの建国以来、明の勢威を借りることによって前代の三仏斉の貿易港の位置に代わり、パラメスワラもイスラム教徒であったことから、イスラム商人のインド洋商業活動の東の交易中心点になり、西の交易中心地、アフリカの東岸のキルワとインド洋をはさんで似通った発展を遂げたのである。そしてやがてヨーロッパ勢力の登場とともに変貌を遂げてゆくのである」と解説している(以上、小川前同、p.68)。
▼スマトラ島のイスラーム教徒の国々▼
スマトラ島北岸のメダン北方にあるアルー湾に、唖魯国(アルー、Aru)という小さな国があり、「満刺加国よりともづなをとき、風向がよければ4昼夜で着くことができる」。この国の「物産は鶴頂鳥、片米糖脳で、商船に売り、交易品としては色段、色絹、磁器、ビーズなど」である(小川前同、p.72、75)。
また、同じくスマトラ島北岸に、蘇門答刺国(スマトラ、Samatra)がある。元史は蘇木都刺、マルコ・ポーロはサマトラ、イブン・バットゥータはスムトラ(その都をスムトラ・パサイ)と記している。蘇門答刺はスマトラ島の北端の一地方であったが、やがて島の大部分を指すようになる。
そこは西洋と意識されており、「西洋の要会」と呼ばれ、当時イスラーム教徒の商人の拠点となっていた。「ここは西洋の幹線水路で、西洋派遣船隊は満刺加国から西南(訳注
地図上よりみれば西北にあたる)に向かい、風向きがよければ5昼夜で、ひとまず海沿いのある村に着く」という。
このスマトラで、鄭和は王の後継争いに介入している。王が、那児孤(後出)の王との戦闘で、毒矢にあたって死ぬ。王の妻は、王子が幼いので夫の敵は討てないとし、それを討った者の妻になるとした。老漁師が奮い立って、敵の王を討ち滅ぼし、老王となる。彼は、「永楽7年(1409)にはひとたび朝貢して天恩に浴し、永楽10年(1412)にはまた朝貢した」。先王の子が成長し、老漁師を殺して王位を奪う。しかし、老漁師には蘇幹刺という嫡子がおり、手下を率いて、父の敵を討たんとする。そのとき、「永楽13年(1415)に、正使の太監鄭和などが西洋派遣船隊を率いてここに到着し、兵を出して蘇幹刺をとりこにし、明の都に送ってその罪を明らかにしたので、王子は聖恩に感じ、明の朝廷に朝貢を続けるようになった」(以上、小川前同、p.77)。
なお、『星槎勝覧』では、「永楽11年、偽王蘇幹刺がこの国を纂奪した。国王は使を遣わして明の朝廷に至り救援を願ったのである。そこで、皇帝は正使太監鄭和などに兵を率いて討たしめ、偽王を生け捕りにして永楽13年に帰国し、朝廷に献じたので諸番はみな服した」となっている(小川前同、p.86)。いずれにしても、明あるいは鄭和は蘇幹刺を偽王と退け、血統を支持したのである。
この国の胡椒について、「山あいに住む人々が農園で作っている……黄白色の花が咲き、胡椒の実が結ぶ。若いうちは青く、熟すれば紅くなる。その半ば熟しかかったころに摘みとり、晒し干して売りに出す。この胡椒の粒の大きいのがここの胡椒である。中国秤100斤ごとに金銭80、銀になおして1両で売られる」と、珍しくも、その価格を示す(小川前同、p.78)。
「ここは沢山の船舶が往来するところで、国中のいろいろな交易品が沢山売られる。この国で使われるのは金銭や錫銭である。金銭は底那児(ディナール)といわれ、7分金で鋳造される。それは円くて、1個ごとの直径は中国寸で5分あり、裏面には模様がある。中国秤では2分3厘あり、48個ごとに重さは金で1両4分ある。錫銭はここでは加失といわれ、およその売買は普通は錫銭を使用し、国内の一応の売買交易はみな16両をもって1斤とし、その時の相場で通用している」とする(小川前同、p.79-80)。
このスマトラへの交易品としては「青白磁器、銅銭、金銀、爪哇布[ジャワ・サラサ?]、色模様の絹などがある」となっている(『星槎勝覧』、小川前同、p.86)。
スマトラ島の北部には、スマトラに攻め入った那孤児国(ナクール、Nakur)があり、「物産は香味、青蓮花近布……硫黄を産する。我が明朝の船隊が蘇門答刺に駐まっているとき、その山でとれた硫黄を船にまで送ってきた。交易品には、段帛、磁器の類」であった(『星槎勝覧』、小川前同、p.89)。さらに、黎代国(リディ、Lide)という小国があり、蘇門答刺国に随って中国に進貢してきているという(小川前同、p.90)。
さらに、スマトラ島の西北端には、「蘇門答刺から真西に向かって、風向きがよければ、3昼夜で到着することができる」ところに、南孛里国(ランブリ、Lambri)があり、国王をはじめ人々は誰もがイスラーム教徒である。この国の王は「西洋派遣船隊(宝船)にしたがって、降真香などの貢物を持って中国にやって来た」という(小川前同、p.93)。
▼インド洋航海の要石、セイロン、モルディブ▼
第4次遠征はベンガル湾の奥に入っていない。そこに行ったのは第7次遠征の分遣隊である。榜葛刺国(ベンガル、Bengal)は「蘇門答刺国(スマトラ)より出帆し、帽山(ウエー島)や翠藍島(ニコバル諸島)を通り、西北方に向かって風向がよければ20日[あるいは12日]ばかりで、まず淅地港(チッタゴン)に着き、船を泊め、小船を用いて入港し、500里あまり行くと鎖納児港(ソナルガオン)という所に到着する」。その岸に上がって行くとこの国があり、「国を挙げてみなイスラム教徒であり……物持ち連中で船を造り、諸外国に赴いて経営するものはすこぶる多いが、外に出て傭われているものもまた多い」(小川前同、p.157)。
蘇門答刺国(スマトラ)の西端から、セイロン島の南を回り、インド洋に入るが、その模様はいままでになく具体的である。まず、スマトラ島の北端のウエー島である(小)「帽山より南に向かって航海し、よい風向きに乗り、東北[西北の間違いとされる]に3日ばかり行くと、翠藍山(ニコバル諸島)が海中にあらわれる。この山島は3つ4つあり」という。そして、「ここを過ぎ、西に向かって船で行くこと7日で、鴬歌囁山(セイロン島の山)が見え、また2、3日して仏堂山[セイロン島南端のドンドラ岬]に着き、そこでやっと錫蘭国(セイロン、Ceylon)の波止場、別羅里(ペルワラ)に着く」という(小川前同、p.96-7)。なお、ニコバル・アンダマン(Nicobar Andaman)は裸形国と呼ばれている。
『星槎勝覧』によれば、この国の「物産は細布、撤哈刺[羅紗の一種]、絨毯、兜羅綿[とろめん]、水晶、瑪瑙、珊瑚、真珠、宝石、糖蜜、酥油(乳脂肪)、翠毛、色どりのある顔にかぶる布があり、交易品には金銀、布緞、色絹、青白花磁器、銅銭、麝香、銀珠、水銀、草蓆、胡椒のたぐいを用いる」とある(小川前同、p.169)。
この国は仏教国であって、ペルワラの「海ぎわの山の麓にきれいな石があり、その上に一足跡がある。長さは2尺ばかりで、お釈迦様が翠藍山からやって来てここから上陸した折にこの石を踏んだので、その跡が残ったのだといわれる」(小川前同、p.97)。「国王は金で銭貨を造り通用させている」。「中国の麝香、生糸、綿、青磁の皿や碗、銅貨、樟脳などが歓迎され、宝石や真珠と取り換えられるのである。国王は、いつも宝石などを携えた使者を、西洋派遣船隊(宝船)に随行させて、中国に進貢してきた」(小川前同、p.100)。
なお、このセイロンでは、第3次遠征において、鄭和の一行はセイロンの王の攻撃に遭って、反撃している。その件について、『星槎勝覧』は「永楽7年、皇帝の命令で正使太監鄭和などは、詔勅を捧げ持ち、さらに金銀の供え物、美しく色どり金を織りこんだ幡(はた)を寺に布施し、石碑を建て、皇帝のおぼしめしを崇め、国王や頭目にお言葉と賜わり物を与えた。しかし、その王、亜烈苦奈児はもとから恭順でなく、船隊を害せんと謀った。そこで、我が正使太監鄭和等は深く機密のうちに策をめぐらし、ひそかに兵器を用意して、何回も命令をくり返し、兵士たちに枚[ばい]を含ましめて[音を立てずに]進軍し、夜半に至り、号砲一声、勇敢に突入し、その王を生け捕りにし、永楽9年に明の朝廷に連れ戻ったのである。しかし、皇帝のお許しによって国に帰らしめたので、四方の夷どもはことごとくしたがった」と記録している(小川前同、p.106)。
溜山国(モルディブ、Maldive Islands)は、「蘇門答刺(スマトラ)から出帆し、小帽山を過ぎ、西南に向かって、よい風向きならば10日ばかりで着くことができる」という。この環礁群を、「海中に天にそびえ立つ石門」とか、「8つばかりの大きな溜[礁湖をいう]」とかで表現している。この海域は、「海や風の難にあって船頭が磁針や舵をこわし、船がここの溜にぶつかったり、溜に入りこむとだんだんと力をなくし、沈没してしまうので、たいがいの航海する船はみなここを避ける」という(以上、小川前同、p.134-5)。そして、この国は椰子がはなはだ多い。「椰子の実の外皮の繊維を編んで細縄を作り、家々に積ねておくと各地の商船に乗って来た人が買って行き、別の国に売るが、造船などに用いられる。つまり、このあたりの地方で船を造るには、みな釘などを用いないで孔をあけてから、みなこの縄で縛りつけ、木くさびを加えて、そのあとで土産の瀝青を塗りつけると水が漏れなくなるのである」。縫合船ダウにおける椰子の使用例が示される。
その他、竜涎香や子安貝(貝貨として利用される)が特産品となっている。特に、竜涎香の「値はとても高いので、買いたいものは銀で交易する」。「国王は銀で小銭を鋳して使用する。中国の西洋派遣船隊(宝船)が1・2隻ここに行き、竜涎香や椰子などの物を買い集めた」とある(以上、小川前同、p.135-6)。
▼マラバール海岸のコーチン、カリカット▼
セイロンのガレから西北に向かって、風向きがよければ6昼夜ばかりで、この国に着くことができる。この国は、インドのマラバール海岸にある小葛蘭国(キーロンあるいはクイロン、Quilon)で、以前はクーラム・マライ(故臨)と呼ばれていた。マルコ・ポーロはコイラム、イブン・バットゥータはカウラムと呼んでおり、宋元時代、インド洋の交易港として賑わっていた。「この国は小国であるけれども、国王はまた贈り物を調え、使を遣わして中国に朝貢してきた」(小川前同、p.107)。
『星槎勝覧』によれば、この国の「物産の胡椒は下里[カリカット、後出]に次いでいる。乾檳榔、波羅蜜[パンの樹の一種]、色布、其木香、乳香、真珠、珊瑚、酥油(乳脂肪)、孩児茶、梔子花は、みな他国より来る[が、それを東方に中継する]。交易品としては丁香、荳寇、蘇木、色段、麝香、金銀銅器、鉄線、黒鉛などの類である」(小川前同、p.110)。
次に、柯枝国(コーチン、Cochin)は、「キーロンから船を出し、山に沿うて西北に向かって風向きがよければ1昼夜で港に着き、停泊できる」。このコーチンは、ヴァスコ・ダ・ガマが1502年に商館を建て、ヨーロッパ人がインドで初めて居留した町である。1503年にはアルブケルクが要塞を築いたところである。フランシスコ・デ・ザビエルは1545年頃立ち寄っている。
この国の人々は5つのカーストに分かれているという。「第1等は南毘と名づけられ王と同類である……第2等はイスラム教徒(回回人)である。第3等は哲地と名づけられ、金持ちである。第4等は革令と名づけられ、もっぱら仲買をする。第5等は木瓜と名づけられる。木瓜はいたって賎しい人で、今に至っても、かれらは海浜に居住している」(小川前同、p.112)。
そのうち、第3等の哲地について、彼らは「みな物持ちであり、もっぱら宝石、真珠、香薬の類を買い集めている。中国の西洋派遣船隊(宝船)やよその国の船の客が来て買うのを待ち、真珠などは分でもってしばしば価を決めて売買する。もし真珠の1粒ごとに重さ3分半のものは、そこで売れば金銭では1800個、銀貨に直せば100両になる」(小川前同、p.114)。この国への交易品として、「色段、白綿、青白花磁器、金銀などのものが用いられている。この酋長は聖恩に感じ、いつも貢物を献じてきた」(『星槎勝覧』、小川前同、p.119)。
キーロンやコーチンの国の王や住民は、いずれも鎖里(ソリ、Soli)の人であるという。鎖里は、「南インドに9世紀から13世紀後半まで続いた王朝チョーラから由来し、インド東岸地方より始まった名称だともいわれている」という(小川前同、p.114)。
コーチンの「港から出帆し、西北に行くこと、3日ばかりで到着できる」ところに、「西洋の大国」古里国(カリカット、Calicut)がある。イブン・バットゥータはカーリクート、島夷志略は下里となっており、1498年ポルトガル航海者ヴァスコ・ダ・ガマというヨーロッパ人が、初めてアジアに到達した場所でもある。
第2次遠征の際、「永楽5年(1407)、明の朝廷は正使太監鄭和等に詔勅を持たせて、ここの国王に詔と銀印を賜い、各頭目には位階に応じた冠帯を賜わり、西洋派遣船隊を統べて、ここに到着したおりには建碑をした。その碑文には、『この国、中国を去ること十万余里、民物みな熙光同風のごとし。石に刻して、ここに万世に永示す』と刻した」とされる(小川前同、p.120)。カリカットの王はヒンズー教徒である。彼は「大頭目の2人に国事をつかさどらせている。2人ともイスラム教徒であり、国中の大半はみなイスラム教を信じている」。ここの住民にもコーチンと同じカーストがあるという。
商品の取り引きについて、詳しい説明が加えられる。「この2人の大頭目は中国(明)の朝廷の賞詞を受けたので、西洋派遣船隊(宝船)がここに到着すると、2人が主として売買をしたし、国王も頭目と哲地未訥几[貴金属を扱う御用商人とみられる]、すなわち役所の書記役と仲買人をよこして、船頭と取引きの日を決め、その日にはまず錦綺(あやにしき)などの物の荷をほどき、いちいち値段を決めて、個数と価格を書きとり、あれこれと取引きをする。頭目と哲地は太監鄭和や船頭たちと手を打ってしめる。
そこで、仲買人は某月某日手を打って定めたのだから高くても安くても、もう悔まないという。
それから、哲地や物持ちなどがだんだん宝石や真珠、珊瑚などの物を持って来て取引きをするが、1日ぐらいでは定まらない。早くても1カ月、おそければ2、3カ月はかかるし、もし値段が定まれば、買う方は真珠などのものを価に応じて、頭目や未訥几の書記役の手を経て、布や糸などのものと交換するが、少しも違うことはない。彼等の計算法はそろばんはなく、ただ両手両足の20指を合わせて計算するのであるが、少しも違うことがないのは珍しいことである」(小川前同、p.122-3)。
ここでいう「船頭たち」とはどういう役職か不明である。それは後出の「船長(ナーホダー)」と同じなのか。
このカリカットの項では、通貨や西洋布[カネキンの類]、胡椒、椰子などといった産品について、詳しい説明がみられる。しかし、ここでの交易品の記載はない。『星槎勝覧』は、次のように詳しいが、『島夷志略』からの引用とされる。
この国の「物産は胡椒で、下里[?!]に次いでいる。ともに倉庫があり貯えておき、商人が来るのを待って販売する。薔薇露[水]、波羅蜜、孩児茶、花模様の布がある。ここにも、珊瑚、真珠、乳香、木香、金箔の類があるが、みな別の国より持ち来たったものである。この国には好い馬が養われている。西番(蕃)より持ち来たされたものである。金銭1100で1疋の価とする。
この国ではもし西番(蕃)の馬を持ち来たされると本国の馬は持って来ても買わない。むだだというのである。交易品としては金銀、色段、青花白磁器、真珠、麝香、水銀、樟脳などが用いられる。酋長は聖恩を感じ、いつも使を遣わし、金華の表文を捧げ、贈り物を貢献してきた」(小川前同、p.133)。
| 第7次遠征の本隊は、従来通り、古里国(カリカット)から忽魯謨厮(オルムズ)に向かった。ここでも分遣隊が編成されたが、それ以前とは違っていた。1つの分遣隊は、従来通り、蘇門答刺(スマトラ)からアフリカ東岸に向かった。さらにもう1つの分遣隊が編成され、それには7人の通事が配置された。古里国(カリカット)に入り、そこからアラビア半島を経て、天方(メッカ)に向かった。この分遣隊は蘇門答刺(スマトラ)から榜葛刺国(ベンガル)に立ち寄ったとも、また忽魯謨厮(オルムズ)で本隊と合流したともされる。 鄭和は、この遠征の帰還中の古里国(カリカット)で、1433年63歳(あるいは64歳)で病死したことになっている。帰還後の翌年に死んだとの説もある。こうして、7次にわたる鄭和の大遠征は終わることになり、その後、中国の西洋への遠征事業や使節の派遣もなくなり、西洋諸国との使節の来訪も少なくなっていった。 |
 |
| 中国・南京市 |
これ以下が『瀛涯勝覧』が示す海上交易に関する記事である。
すでに述べたように、第4次遠征から鄭和の遠征は、新しい段階に入る。それにより西アジアのイスラーム教徒のインド洋交易圏により深く分け入ることとなる。
鄭和の第4次遠征の艦隊は63隻27670人であった。彼らは、大倉(江蘇・揚子江江口附近)の劉家港より出帆し、そして「福建の福州府長楽県五虎門から船を出して、西南に向かい風向がよければ10日ばかりで着くことができ」、広東、海南島の南にある、占城国(チャンパ、Champa)に入る(小川前同、p.7)。この国は「後漢末に興起してから明の中期に滅亡するまで、1300年にわたって独立を続けてきた。そして、中国においては林邑(2-8世紀)・環王(8-9世紀)・占城(9-17世紀)と呼ばれ……中国の朝貢国としてその関係は保たれてきた」と解説される(小川前同、p.13)。
「この国の東北100里に海港があり、新洲港という」。この新洲港は、現在の越南平定省の帰仁(クニヨン)である。「ここでの売買交易には7分金かあるいは銀を使用する。中国の青磁の皿や碗などの品、緞子、綾絹、焼珠(ビーズ)などは大事にされていて、7分金と交換する。いつも犀角、象牙、伽藍香(伽羅木)などの物を中国に進貢してくる」という(小川前同、p.12)。
チャンパを出て、順風20昼夜で、古くは闇婆国といった爪哇国(ジャワ、Java)に入る。外国の船が来ると、杜板(トバン)と、新村(グリッセ)、蘇魯馬益(スラバヤ)に入港する。さらに、満者伯夷(マジャパイト)というところには、マジャパイト王朝の国王が居住していた(小川前同、p.21)。
トバンには「約1000軒余あり、2人の頭目が治めている。ここには沢山の中国の広東、章州の人が流れて来ている」という。「伝説では元代の史弼、高興[1292(至元29)年、フビライ・ハーンが敗退したジャワ遠征の中国人指揮者。モンゴル人指揮者は亦黒迷矢]が闇婆を攻めたときに、幾月も上陸できなくて船中の飲料水が尽きようとして、兵士たちは困った」ところでもあった。また、グリッセは砂洲であった土地に、「中国の人々がここにやって来て始めて住みついたことにより新村と名づけられ、今に至るまで村主は広東人である。約1000軒余りあり、各地の人々がここに来て売買する。金や宝石などいろいろの品物が売られ甚ださかんな所である」(小川前同、p.23)。
このように、ジャワの海港には華僑が定住しているが、そればかりか「この国には三種の人々がいる。一種はイスラム教徒(回回人)でみな西方諸国の商人であり、この地に流れて来たもので、衣食その他は洗練されている。一種は中国人(唐人)でみな広東、章州、泉州の人々のここに逃れて来たもので、日常生活は清潔で、多く(ママ、は?)イスラム教を信じおつとめをしている。一種は原住民で顔かたちはみにくく、もじゃもじゃ髪であかはだしで鬼教を信じている」(小川前同、p.26)。これからみれば、華僑はディアスポラ(離散)したイスラーム教徒ということになる。
「土地の人で物持ちは甚だ多く、売買交易には歴代の中国の銅銭が使われている」。「この国の人たちは中国の青花磁器、麝香、金糸布、ビーズの類を喜び、銅銭でもって買いとる。国王は常に頭目を差し遣わし、船に献上物をのせて中国に進貢している」(小川前同、p.28、29)。
ジャワ島からスマトラ島に向かって、順風8昼夜で、旧港国(パレンバン、Palembang)に着く。そこは室利仏逝とか三仏斉とか呼ばれ、栄えていたところであった。いまでは「爪哇国が管轄している……あちこちの船が来ると、まず淡港[河畔]に入り、船を岸につなぎ……小舟に乗りかえて港内に入り、この国に至るのである。この国には広東、章州、泉州の人々の逃げこんできているものが多い」(小川前同、p.42)。
ここにも華僑が住み着いていた。彼らは紛争を起こしていたが、鄭和は1405(永楽3)年冬に出発した第1次遠征の際、それに介入している。その経過を、馬歓は、次のような挿話としてまとめる。「昔、洪武年間(明の太祖、朱元璋の年号、1368-98年)に広東の人、陳祖義が家をあげてここに逃げこみ、ついに頭目となり、勢威を振るい、およそここを通る客船があれば、その貨財の物を奪い取っていた。永楽5年(1407)に明の朝廷は太監鄭和たちを統領とし、西洋派遣船隊を率いて差し遣わして、ここに至らしめた。
ここには施進卿というものがおった。彼は広東の人であったが、陳祖義の横暴の状況を報告したので、太監鄭和は陳祖義などを生けどりにし、〔明の〕朝廷に連れて帰り、処罰した。そして、施進卿には冠帯を賜い、旧港に帰して大頭目としてそこの『たいしょう』[旧港宣慰司のこと]にした。本人は死んだが位は子に伝わらず、その娘の施二姐が大頭目となったが、一切の賞罰や進退は前のとおりであった」(小川前同、p.43)。
パレンバンの「市中の売り買いには中国の銅銭を使うが、布きれなども使われている。国王はいつも貢納物を明の朝廷に献じていたが、今に至るまで途絶えたことはなかった」(小川前同、p.45)。この国の「物産は黄熟香、速[連]香[健胃剤]、降[真]香[焚香類]、沈香、黄蝋(蜜蝋)、ならびに鶴頂鳥[犀鳥の一種]の類である。交易には五色のビーズや青白磁器、銅鼎、五色の色絹、色段子(どんす)、大小の磁器、銅銭などを使う」という(『星槎勝覧』、小川前同、p.49)。
▼シャム、それから自立した、マラッカ▼
ここで、1407(永楽5)年冬に出立した第2次遠征の記録が挿入される。「占城より西南に向かって船で行くこと、7昼夜(あるいは10昼夜)ばかりで順風なら新門台(シンメンタイ)に至る。江口に入港してわずかばかり行くと、この国に行き着く」という(小川前同、p.51)。この国とは暹羅国(シャム、Siam)である。さらに、「この国の西北に去ること200余里ばかりの所に交易都市があり、上水(シャンスイ)といわれている。雲南の後門に通ずることができる……中国の宝船(西洋派遣船隊)が暹羅にくると、小舟に乗り換えて〔上水に〕行って売買してくる」(小川前同、p.53)。
また、『星槎勝覧』によれば、「中国の歴代の銅銭は使われていない。ここの王様はいつも頭目を差し遣わし、蘇木、降真香などを中国に貢献している」(小川前同、p.54)。交易品としては、中国向けには「羅斜香……つぎは沈香で、つぎはすおう(蘇木)、犀角、象牙、翠毛[かわせみの毛]、黄蝋、大風子油[駆虫剤]などがあり、[シャム向けには]青白花磁器(青い紋様のある磁器で、日本でいう染付け磁器)、印花布[サラサ]、色絹、緞子、金銀銅鉄、ビーズ、水銀、雨傘などである」という(小川前同、p.61)。
文面ではマラッカ海峡に入っているが、再び「占城から真南に向かって風がよければ船で8日ばかりかかって竜牙門[シンガポール海峡の南、ビンタン島とバタム島の間にある、リオウ海峡]に着く。[さらに]竜牙門より西に向かって2日ばかりで」、満刺加国(マラッカ、Malaka)に着くことができる。
ここはもと、国になっておらず、国王もおらず、「暹羅の所轄しているところで、毎年金40両を差し出している。そうしないと征伐されるのである。永楽7年(己丑・1409)に、[第3次遠征]正使の太監鄭和〔等〕が明の皇帝の命を奉じて、西洋派遣船隊を率いて来たり、詔勅をもたらし、ひとそろいの銀印と冠帯、袍服を頭目に賜い、碑を建て城を封じて、満刺加国と名づけた」ところであった。
「その後、暹羅は敢て侵入することはなかった。その頭目は恩を蒙って王となり、妻子を伴って明の都に来たり感謝して貢物を献じたので、明の朝廷は船舶を与えて国に帰らせそこを守らせたのである」。ここの人々は王をはじめ、すべてイスラーム教徒である(以上、小川前同、p.62)。
鄭和の第3次遠征艦隊は、「ここに来航して、城垣のような柵を作り、4つの門、物見櫓(更鼓楼)などを設け、夜は鈴を鳴らして巡羅し、中には二重に柵に立てて、小城のようである。そして、倉庫を作って一切の銭や食糧を入れておき、各地に行く船舶がここに来ると交易物を取り出し、そろえてから船に積み込み、南の風の具合を窺って、5月中旬に航海を開始し中国に向かったのである。そして、ここの国王も自ら進物をととのえ妻子を伴い、頭目たちを引き連れ、鄭和の船隊につき従って明の都にやって来て貢献をした」(小川前同、p.65-6)。
こうしたマラッカの成立とその朝貢について、小川博氏は「建設者パラメスワラ[?-1414](マレイ語では王女より身分の低い配偶者を意味する)邦里迷蘇刺は、シャム(暹羅)の圧迫に抗するため明の勢威を借りんとした。明史満刺加伝(巻325)によると永楽元年(1403)宦官伊慶が派遣された。そして、永楽3年(1405)に使を遣わして朝貢し来たり、満刺加国王に封ぜられた。その後、永楽5年(1407)にも遣使入貢があり、6年(1408)には鄭和が赴き、9年(1411)には満刺加国王は妻子陪臣540余人を率いて入朝し、10年(1412)には王の姪が謝礼のため入朝したとある。その後、12年(1414)には王子イスカンダル・シャー母幹撤干的児沙が来朝してその父の訃を告げたので、襲封を命じ、更に17年(1419)にも妻子を率いてまた来朝し、暹羅の侵略を訴えたので、暹羅に勅諭をもたらし、暹羅はその命を奉じたとある。この後もマラッカとの朝貢関係は続くのである。
このように、マラッカはパラメスワラの建国以来、明の勢威を借りることによって前代の三仏斉の貿易港の位置に代わり、パラメスワラもイスラム教徒であったことから、イスラム商人のインド洋商業活動の東の交易中心点になり、西の交易中心地、アフリカの東岸のキルワとインド洋をはさんで似通った発展を遂げたのである。そしてやがてヨーロッパ勢力の登場とともに変貌を遂げてゆくのである」と解説している(以上、小川前同、p.68)。
▼スマトラ島のイスラーム教徒の国々▼
スマトラ島北岸のメダン北方にあるアルー湾に、唖魯国(アルー、Aru)という小さな国があり、「満刺加国よりともづなをとき、風向がよければ4昼夜で着くことができる」。この国の「物産は鶴頂鳥、片米糖脳で、商船に売り、交易品としては色段、色絹、磁器、ビーズなど」である(小川前同、p.72、75)。
また、同じくスマトラ島北岸に、蘇門答刺国(スマトラ、Samatra)がある。元史は蘇木都刺、マルコ・ポーロはサマトラ、イブン・バットゥータはスムトラ(その都をスムトラ・パサイ)と記している。蘇門答刺はスマトラ島の北端の一地方であったが、やがて島の大部分を指すようになる。
そこは西洋と意識されており、「西洋の要会」と呼ばれ、当時イスラーム教徒の商人の拠点となっていた。「ここは西洋の幹線水路で、西洋派遣船隊は満刺加国から西南(訳注
地図上よりみれば西北にあたる)に向かい、風向きがよければ5昼夜で、ひとまず海沿いのある村に着く」という。
このスマトラで、鄭和は王の後継争いに介入している。王が、那児孤(後出)の王との戦闘で、毒矢にあたって死ぬ。王の妻は、王子が幼いので夫の敵は討てないとし、それを討った者の妻になるとした。老漁師が奮い立って、敵の王を討ち滅ぼし、老王となる。彼は、「永楽7年(1409)にはひとたび朝貢して天恩に浴し、永楽10年(1412)にはまた朝貢した」。先王の子が成長し、老漁師を殺して王位を奪う。しかし、老漁師には蘇幹刺という嫡子がおり、手下を率いて、父の敵を討たんとする。そのとき、「永楽13年(1415)に、正使の太監鄭和などが西洋派遣船隊を率いてここに到着し、兵を出して蘇幹刺をとりこにし、明の都に送ってその罪を明らかにしたので、王子は聖恩に感じ、明の朝廷に朝貢を続けるようになった」(以上、小川前同、p.77)。
なお、『星槎勝覧』では、「永楽11年、偽王蘇幹刺がこの国を纂奪した。国王は使を遣わして明の朝廷に至り救援を願ったのである。そこで、皇帝は正使太監鄭和などに兵を率いて討たしめ、偽王を生け捕りにして永楽13年に帰国し、朝廷に献じたので諸番はみな服した」となっている(小川前同、p.86)。いずれにしても、明あるいは鄭和は蘇幹刺を偽王と退け、血統を支持したのである。
この国の胡椒について、「山あいに住む人々が農園で作っている……黄白色の花が咲き、胡椒の実が結ぶ。若いうちは青く、熟すれば紅くなる。その半ば熟しかかったころに摘みとり、晒し干して売りに出す。この胡椒の粒の大きいのがここの胡椒である。中国秤100斤ごとに金銭80、銀になおして1両で売られる」と、珍しくも、その価格を示す(小川前同、p.78)。
「ここは沢山の船舶が往来するところで、国中のいろいろな交易品が沢山売られる。この国で使われるのは金銭や錫銭である。金銭は底那児(ディナール)といわれ、7分金で鋳造される。それは円くて、1個ごとの直径は中国寸で5分あり、裏面には模様がある。中国秤では2分3厘あり、48個ごとに重さは金で1両4分ある。錫銭はここでは加失といわれ、およその売買は普通は錫銭を使用し、国内の一応の売買交易はみな16両をもって1斤とし、その時の相場で通用している」とする(小川前同、p.79-80)。
このスマトラへの交易品としては「青白磁器、銅銭、金銀、爪哇布[ジャワ・サラサ?]、色模様の絹などがある」となっている(『星槎勝覧』、小川前同、p.86)。
スマトラ島の北部には、スマトラに攻め入った那孤児国(ナクール、Nakur)があり、「物産は香味、青蓮花近布……硫黄を産する。我が明朝の船隊が蘇門答刺に駐まっているとき、その山でとれた硫黄を船にまで送ってきた。交易品には、段帛、磁器の類」であった(『星槎勝覧』、小川前同、p.89)。さらに、黎代国(リディ、Lide)という小国があり、蘇門答刺国に随って中国に進貢してきているという(小川前同、p.90)。
さらに、スマトラ島の西北端には、「蘇門答刺から真西に向かって、風向きがよければ、3昼夜で到着することができる」ところに、南孛里国(ランブリ、Lambri)があり、国王をはじめ人々は誰もがイスラーム教徒である。この国の王は「西洋派遣船隊(宝船)にしたがって、降真香などの貢物を持って中国にやって来た」という(小川前同、p.93)。
▼インド洋航海の要石、セイロン、モルディブ▼
第4次遠征はベンガル湾の奥に入っていない。そこに行ったのは第7次遠征の分遣隊である。榜葛刺国(ベンガル、Bengal)は「蘇門答刺国(スマトラ)より出帆し、帽山(ウエー島)や翠藍島(ニコバル諸島)を通り、西北方に向かって風向がよければ20日[あるいは12日]ばかりで、まず淅地港(チッタゴン)に着き、船を泊め、小船を用いて入港し、500里あまり行くと鎖納児港(ソナルガオン)という所に到着する」。その岸に上がって行くとこの国があり、「国を挙げてみなイスラム教徒であり……物持ち連中で船を造り、諸外国に赴いて経営するものはすこぶる多いが、外に出て傭われているものもまた多い」(小川前同、p.157)。
蘇門答刺国(スマトラ)の西端から、セイロン島の南を回り、インド洋に入るが、その模様はいままでになく具体的である。まず、スマトラ島の北端のウエー島である(小)「帽山より南に向かって航海し、よい風向きに乗り、東北[西北の間違いとされる]に3日ばかり行くと、翠藍山(ニコバル諸島)が海中にあらわれる。この山島は3つ4つあり」という。そして、「ここを過ぎ、西に向かって船で行くこと7日で、鴬歌囁山(セイロン島の山)が見え、また2、3日して仏堂山[セイロン島南端のドンドラ岬]に着き、そこでやっと錫蘭国(セイロン、Ceylon)の波止場、別羅里(ペルワラ)に着く」という(小川前同、p.96-7)。なお、ニコバル・アンダマン(Nicobar Andaman)は裸形国と呼ばれている。
『星槎勝覧』によれば、この国の「物産は細布、撤哈刺[羅紗の一種]、絨毯、兜羅綿[とろめん]、水晶、瑪瑙、珊瑚、真珠、宝石、糖蜜、酥油(乳脂肪)、翠毛、色どりのある顔にかぶる布があり、交易品には金銀、布緞、色絹、青白花磁器、銅銭、麝香、銀珠、水銀、草蓆、胡椒のたぐいを用いる」とある(小川前同、p.169)。
この国は仏教国であって、ペルワラの「海ぎわの山の麓にきれいな石があり、その上に一足跡がある。長さは2尺ばかりで、お釈迦様が翠藍山からやって来てここから上陸した折にこの石を踏んだので、その跡が残ったのだといわれる」(小川前同、p.97)。「国王は金で銭貨を造り通用させている」。「中国の麝香、生糸、綿、青磁の皿や碗、銅貨、樟脳などが歓迎され、宝石や真珠と取り換えられるのである。国王は、いつも宝石などを携えた使者を、西洋派遣船隊(宝船)に随行させて、中国に進貢してきた」(小川前同、p.100)。
なお、このセイロンでは、第3次遠征において、鄭和の一行はセイロンの王の攻撃に遭って、反撃している。その件について、『星槎勝覧』は「永楽7年、皇帝の命令で正使太監鄭和などは、詔勅を捧げ持ち、さらに金銀の供え物、美しく色どり金を織りこんだ幡(はた)を寺に布施し、石碑を建て、皇帝のおぼしめしを崇め、国王や頭目にお言葉と賜わり物を与えた。しかし、その王、亜烈苦奈児はもとから恭順でなく、船隊を害せんと謀った。そこで、我が正使太監鄭和等は深く機密のうちに策をめぐらし、ひそかに兵器を用意して、何回も命令をくり返し、兵士たちに枚[ばい]を含ましめて[音を立てずに]進軍し、夜半に至り、号砲一声、勇敢に突入し、その王を生け捕りにし、永楽9年に明の朝廷に連れ戻ったのである。しかし、皇帝のお許しによって国に帰らしめたので、四方の夷どもはことごとくしたがった」と記録している(小川前同、p.106)。
溜山国(モルディブ、Maldive Islands)は、「蘇門答刺(スマトラ)から出帆し、小帽山を過ぎ、西南に向かって、よい風向きならば10日ばかりで着くことができる」という。この環礁群を、「海中に天にそびえ立つ石門」とか、「8つばかりの大きな溜[礁湖をいう]」とかで表現している。この海域は、「海や風の難にあって船頭が磁針や舵をこわし、船がここの溜にぶつかったり、溜に入りこむとだんだんと力をなくし、沈没してしまうので、たいがいの航海する船はみなここを避ける」という(以上、小川前同、p.134-5)。そして、この国は椰子がはなはだ多い。「椰子の実の外皮の繊維を編んで細縄を作り、家々に積ねておくと各地の商船に乗って来た人が買って行き、別の国に売るが、造船などに用いられる。つまり、このあたりの地方で船を造るには、みな釘などを用いないで孔をあけてから、みなこの縄で縛りつけ、木くさびを加えて、そのあとで土産の瀝青を塗りつけると水が漏れなくなるのである」。縫合船ダウにおける椰子の使用例が示される。
その他、竜涎香や子安貝(貝貨として利用される)が特産品となっている。特に、竜涎香の「値はとても高いので、買いたいものは銀で交易する」。「国王は銀で小銭を鋳して使用する。中国の西洋派遣船隊(宝船)が1・2隻ここに行き、竜涎香や椰子などの物を買い集めた」とある(以上、小川前同、p.135-6)。
▼マラバール海岸のコーチン、カリカット▼
セイロンのガレから西北に向かって、風向きがよければ6昼夜ばかりで、この国に着くことができる。この国は、インドのマラバール海岸にある小葛蘭国(キーロンあるいはクイロン、Quilon)で、以前はクーラム・マライ(故臨)と呼ばれていた。マルコ・ポーロはコイラム、イブン・バットゥータはカウラムと呼んでおり、宋元時代、インド洋の交易港として賑わっていた。「この国は小国であるけれども、国王はまた贈り物を調え、使を遣わして中国に朝貢してきた」(小川前同、p.107)。
『星槎勝覧』によれば、この国の「物産の胡椒は下里[カリカット、後出]に次いでいる。乾檳榔、波羅蜜[パンの樹の一種]、色布、其木香、乳香、真珠、珊瑚、酥油(乳脂肪)、孩児茶、梔子花は、みな他国より来る[が、それを東方に中継する]。交易品としては丁香、荳寇、蘇木、色段、麝香、金銀銅器、鉄線、黒鉛などの類である」(小川前同、p.110)。
次に、柯枝国(コーチン、Cochin)は、「キーロンから船を出し、山に沿うて西北に向かって風向きがよければ1昼夜で港に着き、停泊できる」。このコーチンは、ヴァスコ・ダ・ガマが1502年に商館を建て、ヨーロッパ人がインドで初めて居留した町である。1503年にはアルブケルクが要塞を築いたところである。フランシスコ・デ・ザビエルは1545年頃立ち寄っている。
この国の人々は5つのカーストに分かれているという。「第1等は南毘と名づけられ王と同類である……第2等はイスラム教徒(回回人)である。第3等は哲地と名づけられ、金持ちである。第4等は革令と名づけられ、もっぱら仲買をする。第5等は木瓜と名づけられる。木瓜はいたって賎しい人で、今に至っても、かれらは海浜に居住している」(小川前同、p.112)。
そのうち、第3等の哲地について、彼らは「みな物持ちであり、もっぱら宝石、真珠、香薬の類を買い集めている。中国の西洋派遣船隊(宝船)やよその国の船の客が来て買うのを待ち、真珠などは分でもってしばしば価を決めて売買する。もし真珠の1粒ごとに重さ3分半のものは、そこで売れば金銭では1800個、銀貨に直せば100両になる」(小川前同、p.114)。この国への交易品として、「色段、白綿、青白花磁器、金銀などのものが用いられている。この酋長は聖恩に感じ、いつも貢物を献じてきた」(『星槎勝覧』、小川前同、p.119)。
キーロンやコーチンの国の王や住民は、いずれも鎖里(ソリ、Soli)の人であるという。鎖里は、「南インドに9世紀から13世紀後半まで続いた王朝チョーラから由来し、インド東岸地方より始まった名称だともいわれている」という(小川前同、p.114)。
コーチンの「港から出帆し、西北に行くこと、3日ばかりで到着できる」ところに、「西洋の大国」古里国(カリカット、Calicut)がある。イブン・バットゥータはカーリクート、島夷志略は下里となっており、1498年ポルトガル航海者ヴァスコ・ダ・ガマというヨーロッパ人が、初めてアジアに到達した場所でもある。
第2次遠征の際、「永楽5年(1407)、明の朝廷は正使太監鄭和等に詔勅を持たせて、ここの国王に詔と銀印を賜い、各頭目には位階に応じた冠帯を賜わり、西洋派遣船隊を統べて、ここに到着したおりには建碑をした。その碑文には、『この国、中国を去ること十万余里、民物みな熙光同風のごとし。石に刻して、ここに万世に永示す』と刻した」とされる(小川前同、p.120)。カリカットの王はヒンズー教徒である。彼は「大頭目の2人に国事をつかさどらせている。2人ともイスラム教徒であり、国中の大半はみなイスラム教を信じている」。ここの住民にもコーチンと同じカーストがあるという。
商品の取り引きについて、詳しい説明が加えられる。「この2人の大頭目は中国(明)の朝廷の賞詞を受けたので、西洋派遣船隊(宝船)がここに到着すると、2人が主として売買をしたし、国王も頭目と哲地未訥几[貴金属を扱う御用商人とみられる]、すなわち役所の書記役と仲買人をよこして、船頭と取引きの日を決め、その日にはまず錦綺(あやにしき)などの物の荷をほどき、いちいち値段を決めて、個数と価格を書きとり、あれこれと取引きをする。頭目と哲地は太監鄭和や船頭たちと手を打ってしめる。
そこで、仲買人は某月某日手を打って定めたのだから高くても安くても、もう悔まないという。
それから、哲地や物持ちなどがだんだん宝石や真珠、珊瑚などの物を持って来て取引きをするが、1日ぐらいでは定まらない。早くても1カ月、おそければ2、3カ月はかかるし、もし値段が定まれば、買う方は真珠などのものを価に応じて、頭目や未訥几の書記役の手を経て、布や糸などのものと交換するが、少しも違うことはない。彼等の計算法はそろばんはなく、ただ両手両足の20指を合わせて計算するのであるが、少しも違うことがないのは珍しいことである」(小川前同、p.122-3)。
ここでいう「船頭たち」とはどういう役職か不明である。それは後出の「船長(ナーホダー)」と同じなのか。
このカリカットの項では、通貨や西洋布[カネキンの類]、胡椒、椰子などといった産品について、詳しい説明がみられる。しかし、ここでの交易品の記載はない。『星槎勝覧』は、次のように詳しいが、『島夷志略』からの引用とされる。
この国の「物産は胡椒で、下里[?!]に次いでいる。ともに倉庫があり貯えておき、商人が来るのを待って販売する。薔薇露[水]、波羅蜜、孩児茶、花模様の布がある。ここにも、珊瑚、真珠、乳香、木香、金箔の類があるが、みな別の国より持ち来たったものである。この国には好い馬が養われている。西番(蕃)より持ち来たされたものである。金銭1100で1疋の価とする。
この国ではもし西番(蕃)の馬を持ち来たされると本国の馬は持って来ても買わない。むだだというのである。交易品としては金銀、色段、青花白磁器、真珠、麝香、水銀、樟脳などが用いられる。酋長は聖恩を感じ、いつも使を遣わし、金華の表文を捧げ、贈り物を貢献してきた」(小川前同、p.133)。
 ホームページへ |
 目次に戻る |
 先頭に戻る |