 ホームページへ |
 目次に戻る |
| |
船員職業の特殊性の1つとして、雇用の断続性が上げられる。船員は、その船に乗っている
間だけ、雇用されているにすぎず、下船すれば失職の状態になる。他方、船主は航海を始め
るごとに、船員を探す必要があった。そこで船員周旋業という口入れ屋がはびこることになる。
また、船員は苛酷な職業でありながら、すでにのべたように軍事的な配慮から、船員を補充し
つづける必要があったので、特殊な船員の供給方式も発達せざるをえなかった。
1 修業期間7年の徒弟制
★単なる低賃金労働者★
イギリスの海運が、本格的に膨張し始めるのは、エリザベス朝末期からである。1582年の
全船舶は、1215隻、6万6000トンで、乗組員は1万7157人であった。そのうち80トン以上
の商船は、たった228隻にすぎなかった。その当時、もっとも発達していたのは、ニューファン
ドランド漁業とニューキャスル/ロンドン港間の石炭輸送、そしてグリーンランド漁業であり、そ
れらが遠洋海運に乗り出す船員の供給源となっていた。すでにのべたように、1651年航海条
例が出され、また海軍の増強とともに、海運も急速に発達して行った。全船舶は、1629年の
1万8000トンから1686年には3.4万トンと、約3倍も増加した。軍艦とその乗組員も、1633
年の50隻9470人から1688年の173隻4万2003人に増加していた。このように、海運・海
軍の膨張は多数の船員を必要とするところとなった。しかし、船員は次のような状態におかれ
ていた。
フェイル氏は、17世紀にはすでに「中世とは異なって、乗組員のうち商人または船舶持分所
有者を兼ねている者が存在しなくなった。大洋航路も当初の冒険企業的魅力を失っていた際
とて、教養または身分のあるもので平船員になろうとするものはほとんどなかった。海員たち
は、単なる『労働者』(hands)となってしまっていた。ペティによれば船員の給与は……農業労
働者の3倍に相当したと計算されているけれども、彼らの地位は、いまや陸上での比較的割の
よい職業と比較すればずっと低下してしまった。彼等は、不況期、しがない低賃金労働者が取
扱われるような仕方で、船主から非道な取扱いをうける」(同1911−2ページ)という状態にな
っていたとのべている。
したがって、港には、ぶらぶらしている連中が多数いても、船には乗ろうとしなかった。それで
も、多くの人びとが船員になり、海軍の徴発後も船員を続けた。
★海事徒弟制★
中世、イギリスの船員もギルド(同業組合)規制の下におかれていた。コース氏によると、「1
4、5世紀、5つの船員ギルドがあった。……タリストルのギルドは1445年に設立されたようで
あり、船長(master mariner)、下士官(yeoman)、召使(servant)という3つの階級を設けてい
た。下士官と召使は、現在の有能船員(able seaman)や一般船員(ordinary Seaman)と、有技
船員(efficient deck hand)や甲板少年(deck boy)に当る。下士官はいままで3年間海上で働
き、仲間を指揮できる船員と、そうした資格のない船員に分れていた。……資格のない成人
も、船員になって学びながら稼げた。少年も同様であった。他方、年季奉公の徒弟(apprentice)
もいた。彼らは、正式にギルド組合に加入しており、その年季奉公契約書は記録保存所に出
すことになっていた」(同27ページ)。単に水夫で終ろうとする人間はともかく、船長、士官そし
て大工や砲手、銅工になろうとする人間は、船長や職人船員と年季奉公契約を結び、徒弟
(apprentice)にならなければならなかった。その場合、その親は船長に謝礼金(premium)を支
払った。
徒弟契約の文面は、次のようになっていた。「徒弟は、誠実に船長に仕え、真剣に船長の秘
伝を守り、船長の正当な命令を実行し、船長の持物を浪費せず、また許しもなく貸し出しては
ならない。徒弟は私通の罪を犯したり、結婚を約束してはならない。徒弟はカード遊びやダイス
遊び、あるいは船長が許可していない不法なゲームに参加してはならない。徒弟は品物の売り
買いをしてはならない。徒弟は居酒屋や芝居小屋に立ち入ってはならず、船長への奉公は
昼、夜を問わずなまけてはならない。そして、何事につけても誠実な徒弟として振舞うよう、自
分に仕向けなければならない。その代償として、船長当人あるいは契約引継ぎ人、契約管理
人はこの契約を履行し、徒弟が船員としての技能を身につけられるよう、できるかぎり最良の
手段を用いて教え導くことに合意し、約束する。徒弟には、十分な食料、飲物、寝具そして衣服
の他、必需品を支給する」(同197ページ)。
海事徒弟制は、1563年の職人規制法で明文化された。J・ウェップ氏が、1596年から165
1年におけるイプスウィッチの徒弟契約の記録を分析したところ、386人のうち、実に299人
が海事関係の徒弟であったという。その構成は、船員(mariners士官を目指す徒弟とみられ
る)203人、水夫(sailors)28人、漁船員17人、船大工・防水工51人であった。彼らはイプス
ウィッチのあるサフォーク州を中心にして、多くの州から来ているが、彼らの家は海岸や河川
の周辺にあった。
イブスウィッチ生まれの81人の船員徒弟のうち、3分の1は海事家族の出身者であり、8分
の1は織物家族、その他は手職人または工業家族の出身者であった。その他の地方の徒弟
は、農業家族の出身者が多かった。こうしたイギリス船員の出身背景は、現代においてもみら
れるところであるが、この時代にすでに船員職業の世代継続がみられたことは、注目に値す
る。
徒弟期間は、たとえば船員徒弟についてみれば3年半から12年にまたがっているが、陸上
と同じように7年がもっとも多く、また24歳になると打ち切られていたようである。なお、時代が
下がると4年と短かくなる。
修業が終わった時に贈物があったが、賃金は支払われなかった。それでも、時代が下がる
につれて、必需品の支給や贈物の代わりに、賃金を支払うようになった。いま1つの例をあげ
ると、ある親方は最初の5年間は衣服の支給だけ、さらに続けて働けば上陸着など多種類の
衣類の支給、そして6年目には40シリング、7年目には50シリング、8年目には55シリング、
最後には3ポンド支払うという徒弟契約を結んでいた(「海事職業の徒弟制」『船員の鏡』、196
0)。
2 救貧少年の強制乗船
★救貧徒弟の配乗義務★
商船への少年船員の供給は、こうした本来の徒弟制度によるものばかりではなかった。16
01年エリザベス救貧法は、市長が教区における救貧少年や救貧者の子供を見つけてきて、
年季奉公契約させて海上に追いやることを認めていた。その場合、教区が船長に謝礼金を支
払った。その規模が、どれくらいであったかは、不明である。
イギリスの海軍と海運は、すでにのべたように17世紀末にかけて膨張したため、船員不足
が激しくなった。そこで1703年船員増殖航海奨励法が制定され、救貧海事徒弟制が大いに
奨励された。翌年、さらに強化されて「教区委員や救貧委員は、10歳以上になる少年であっ
て、救貧を受けまた受けざるをえない少年、彼らが住む教区の負担となっている、またなるお
それのある少年、あるいは施物を受けざるをえない少年なら誰でも縛って、臣下である大船・
小船の船長や船主に引渡し……その少年が21歳になるまで……海上勤務の徒弟とすること
を……法的に認める」。
また、「積荷30トンから50トンの船の船長または船主は、徒弟を1人採用する義務があり、
50トンから100トンまではさらに1人、そして100トン増す毎に1人追加されるものとする」とさ
れた。そして、それを船長や船主が拒否すれば、10ポンドの罰金が科せられた。さらに、すで
に陸上で徒弟になっている救貧少年を、海事徒弟に切り替えることもできるようになった。この
規定は、救貧徒弟ばかりでなく、一般の徒弟を含めた配乗義務規定となっており、イギリス船
員の増殖を意図している。この規定は、航海条令が廃止された1849年に廃止されている。
E・G・トーマス氏は、貧困少年が海事徒弟に出されて行った事例を、数多く紹介している。そ
の徒弟先は、教区によって違いがあるが、石炭船、外航船、漁船、はしけ、そして軍艦であっ
た。たとえば、ブリストルでは1704年10月18日の1日だけで、28人の少年が船長の徒弟に
出されているし、ロンドンでは1802年から1811年にかけて徒弟に出した2484人のうち48
4人が、海事徒弟になっている。また、労役場に入れられていた少年が、軍艦に送り込まれた
例も紹介されている。すでに紹介した海員協会は、教区委員によって大いに利用されたという
(「旧救貧法と海事徒弟」『船員の鏡』、1977)。
ロイド氏は、18世紀に入ると、すでにのべたような「古来の形式での徒弟制は海運では少な
くなったが(外国人船員を雇用しはじめたこともある、引用者注)、海軍は名誉と権威ある状態
になりだしたにもかかわらず、救貧徒弟が多くなり、苦役の期間中、賃金は支払われず、ただ
2者のスーツを支給されるだけで、長期間拘束されるようになった」(同119ページ)とのべてい
る。
★いじめられる徒弟★
こうして海運に入った救貧徒弟が、どれぐらいの規模であったかは明らかではないが、かなり
の数であったことは、先にロンドンの例でもあきらかである。1835年商船船員法が通過した
時、救貧徒弟を含む全徒弟は5000人で、本来であれば1万4000人いなければならなかっ
たという(コース205ページ)。すでに、この頃になると、大方の船は徒弟雇用義務を無視して
いたのである。
徒弟の労働と生活は、楽なものではなかった。一般の徒弟は船首楼で水夫と一緒に食事を
し、召使の仕事もやらされていた。徒弟になるやいなや厳しい仕事をさせられ、士官や下士官
にいつもいじめられ、船員のいいなりにこき使われ、船員たちの衣服や食器も洗わせられ、奴
隷とあまり変らなかった。当時の商船にあっては、善悪のけじめといったものはなかったので、
ただ服従するかそれとも反乱を起こすしかなかった。すべての命令が仕事であって、それを拒
否して仕事をしないと反乱とみなされ、鞭打たれることになった。もちろん、船長が残忍に取り
扱われないよう、徒弟を保護する船もあったし、高度な航海術を船長から教えてもらう機会を
持てた少年がいなかったわけではない。徒弟がその船で仕事をやりとげ、徒弟期間が終れ
ば、士官の職務につける資格があると認定されることになった(コース183ページ)。
したがって、それら徒弟が一人前の船員になったかどうかは、きわめてうたがわしい。彼ら
も、陸上の徒弟と同様に、船から逃げ出したとみられる。船員増殖改正法が出されて2年後に
は、船長は13歳以下の少年や、病気または虚弱の少年は受け入れなくても良いという法律が
出されている。船長のなかには、救貧少年を使用することを好まず、10ポンドの罰金を支払う
ものさえあったといわれる。救貧少年にとって海上は陸上の親方や労役場から逃げ出す良い
機会であり、また真面目に働こうとする貧困少年にとっては好運をつかむ機会であったかも知
れないが、海上はやはり陸上よりも悲惨であったのである。
浮浪者取締法、救貧法や割当法といった法律は、イギリスの資本主義の本源的蓄積期にお
いて生み出された、おびただしい数の乞食・浮浪者・孤児のうち、労働能力のある者の浮浪を
刑罰で禁止するとともに、労働を強制しようとする「血の立法」であった。軍艦や商船は、その
船員が不足するところから格好の排出先として選ばれ、多くの貧困成人や少年が送り込まれ
たのである。救貧費用を負担する教区にとって、軍艦や商船は貧困成人・少年を連れ去ってく
れる点で、大いに好都合であったにちがいない。救貧徒弟は1890年代初めまで送り込まれ
ていた。
3 船員周旋業、大いに繁昌
★船員周旋業の役割★
船員は、その船の航海(帆船時代は、1年、2年はざらであった)毎に雇用契約を結んで、乗
船して行った。それを、属船雇用あるいは航海雇用という。船員がある船を下船して陸の生活
をし、また船に乗ろうとする場合、その都度、雇い先を探さなければならなかった。また、船主
や船長もその度毎に船員を探さねばならなかった。そこに登場するのが船員周旋業(crimps)
である。
J・S・キッチェン氏は、次のように要約している。「18、9世紀、多くの船員は、周旋業者を通
じて、乗組員が欲しい船主に雇われることになっていた。
周旋業者は、海港にある酒場(ale houses)や簡易宿泊所(lodging-houses、日本の周旋業者
は boarding-housesを鈍って、ボーレンという言葉で呼ばれていた、引用者注) の経営者であ
って、船員に安い寝床を、流れ者に仮のねぐらを提供していた。彼らの目的は、船員に金を使
い果させたうえで船員を脅し、商船に売り込むことにあった。
船員は、周旋業者に借金を抱え込まされ、船に連れ込まれることになった。その船で署名を
して、賃金の前渡しを受けるが、そこでばかばかしいほど安い交換率で、前渡金証(advanced
note)を割り引かれ、船員は借金を清算したことになる。
また、船が入港すると船員は引きずり降ろされるか、酒場に行かざるをえないようにされるの
で、いずれにしても周旋業者に従わざるをえない。船員は、いつもそうした方法でだましつづけ
られ、まったく不利な状況におかれ、周旋業者から逃げ出す機会を奪われつづけた」(同149
―150ページ)。
船員が、いくら金を持って下船しても、馬鹿遊びするのが常であったので、金はすぐになくな
った。それがなくなれば、どこか借金させてくれるところにころがり込むほかはなかった。たとえ
田舎に帰っていたとしても、港で寝泊りして職探しをせざるをえなかった。また、船に乗る前に
は、身仕度もしなければならなかった。船員は賭博場やダンスホール、売春宿に引っ張り込ま
れ、「楽しい時間」を付けで過していた。借金しないかぎり、誰も取り合ってくれなかった。船員
装身具屋は喜んで掛け売りしてくれたが、普通の値段の2倍だった。それについても周旋屋は
25%の手数料を取っていた。船員は支払われる賃金以上の借用証を、周旋屋から突き付け
られることになった。周旋屋が船員に船を見つけて乗せると、手数料として1ポンド取っていた。
雇用が決まると、1、2か月の前渡金証が発給されるが、周旋屋や売春婦、居酒屋のおやじ
は、前渡金証を25−30%割引いて買い取っていた(コース241ページ)。
船員周旋業は、19世紀に入って、イギリスのみならず、各国の海運が多数の船員を必要に
なるにつれて、盛んになった。そのなかでも、アメリカは悪徳な周旋業者がいることで有名であ
った。そうした周旋業と闘ったことで著名なJ・フェルという、元ボクサーで船員伝道教会(the
Mission to Seamen)の牧師は、19世紀末のサンフランシスコの状況について書き残している。
まず、周旋業者について、「彼らは、特に好況期に船員を脱船するよう誘うことは罪深いとは思
っているが、そうするのが船員のためになると、疑問を持たずにやっている。また、不景気にな
ると、多数の船員が数週間も下宿し、何はともあれ食事をし、寝泊りできる。それは、他に道が
ないので、一応道理にかなっている。しかし、そうしたことが周旋システムの計り知れない悪徳
ぶりを許すことにはならない」(『サンフランシスコのイギリス人商船船員』69ページ、エドワー
ド・アーノルド社、1899)。
間だけ、雇用されているにすぎず、下船すれば失職の状態になる。他方、船主は航海を始め
るごとに、船員を探す必要があった。そこで船員周旋業という口入れ屋がはびこることになる。
また、船員は苛酷な職業でありながら、すでにのべたように軍事的な配慮から、船員を補充し
つづける必要があったので、特殊な船員の供給方式も発達せざるをえなかった。
1 修業期間7年の徒弟制
★単なる低賃金労働者★
イギリスの海運が、本格的に膨張し始めるのは、エリザベス朝末期からである。1582年の
全船舶は、1215隻、6万6000トンで、乗組員は1万7157人であった。そのうち80トン以上
の商船は、たった228隻にすぎなかった。その当時、もっとも発達していたのは、ニューファン
ドランド漁業とニューキャスル/ロンドン港間の石炭輸送、そしてグリーンランド漁業であり、そ
れらが遠洋海運に乗り出す船員の供給源となっていた。すでにのべたように、1651年航海条
例が出され、また海軍の増強とともに、海運も急速に発達して行った。全船舶は、1629年の
1万8000トンから1686年には3.4万トンと、約3倍も増加した。軍艦とその乗組員も、1633
年の50隻9470人から1688年の173隻4万2003人に増加していた。このように、海運・海
軍の膨張は多数の船員を必要とするところとなった。しかし、船員は次のような状態におかれ
ていた。
フェイル氏は、17世紀にはすでに「中世とは異なって、乗組員のうち商人または船舶持分所
有者を兼ねている者が存在しなくなった。大洋航路も当初の冒険企業的魅力を失っていた際
とて、教養または身分のあるもので平船員になろうとするものはほとんどなかった。海員たち
は、単なる『労働者』(hands)となってしまっていた。ペティによれば船員の給与は……農業労
働者の3倍に相当したと計算されているけれども、彼らの地位は、いまや陸上での比較的割の
よい職業と比較すればずっと低下してしまった。彼等は、不況期、しがない低賃金労働者が取
扱われるような仕方で、船主から非道な取扱いをうける」(同1911−2ページ)という状態にな
っていたとのべている。
したがって、港には、ぶらぶらしている連中が多数いても、船には乗ろうとしなかった。それで
も、多くの人びとが船員になり、海軍の徴発後も船員を続けた。
★海事徒弟制★
中世、イギリスの船員もギルド(同業組合)規制の下におかれていた。コース氏によると、「1
4、5世紀、5つの船員ギルドがあった。……タリストルのギルドは1445年に設立されたようで
あり、船長(master mariner)、下士官(yeoman)、召使(servant)という3つの階級を設けてい
た。下士官と召使は、現在の有能船員(able seaman)や一般船員(ordinary Seaman)と、有技
船員(efficient deck hand)や甲板少年(deck boy)に当る。下士官はいままで3年間海上で働
き、仲間を指揮できる船員と、そうした資格のない船員に分れていた。……資格のない成人
も、船員になって学びながら稼げた。少年も同様であった。他方、年季奉公の徒弟(apprentice)
もいた。彼らは、正式にギルド組合に加入しており、その年季奉公契約書は記録保存所に出
すことになっていた」(同27ページ)。単に水夫で終ろうとする人間はともかく、船長、士官そし
て大工や砲手、銅工になろうとする人間は、船長や職人船員と年季奉公契約を結び、徒弟
(apprentice)にならなければならなかった。その場合、その親は船長に謝礼金(premium)を支
払った。
徒弟契約の文面は、次のようになっていた。「徒弟は、誠実に船長に仕え、真剣に船長の秘
伝を守り、船長の正当な命令を実行し、船長の持物を浪費せず、また許しもなく貸し出しては
ならない。徒弟は私通の罪を犯したり、結婚を約束してはならない。徒弟はカード遊びやダイス
遊び、あるいは船長が許可していない不法なゲームに参加してはならない。徒弟は品物の売り
買いをしてはならない。徒弟は居酒屋や芝居小屋に立ち入ってはならず、船長への奉公は
昼、夜を問わずなまけてはならない。そして、何事につけても誠実な徒弟として振舞うよう、自
分に仕向けなければならない。その代償として、船長当人あるいは契約引継ぎ人、契約管理
人はこの契約を履行し、徒弟が船員としての技能を身につけられるよう、できるかぎり最良の
手段を用いて教え導くことに合意し、約束する。徒弟には、十分な食料、飲物、寝具そして衣服
の他、必需品を支給する」(同197ページ)。
海事徒弟制は、1563年の職人規制法で明文化された。J・ウェップ氏が、1596年から165
1年におけるイプスウィッチの徒弟契約の記録を分析したところ、386人のうち、実に299人
が海事関係の徒弟であったという。その構成は、船員(mariners士官を目指す徒弟とみられ
る)203人、水夫(sailors)28人、漁船員17人、船大工・防水工51人であった。彼らはイプス
ウィッチのあるサフォーク州を中心にして、多くの州から来ているが、彼らの家は海岸や河川
の周辺にあった。
イブスウィッチ生まれの81人の船員徒弟のうち、3分の1は海事家族の出身者であり、8分
の1は織物家族、その他は手職人または工業家族の出身者であった。その他の地方の徒弟
は、農業家族の出身者が多かった。こうしたイギリス船員の出身背景は、現代においてもみら
れるところであるが、この時代にすでに船員職業の世代継続がみられたことは、注目に値す
る。
徒弟期間は、たとえば船員徒弟についてみれば3年半から12年にまたがっているが、陸上
と同じように7年がもっとも多く、また24歳になると打ち切られていたようである。なお、時代が
下がると4年と短かくなる。
修業が終わった時に贈物があったが、賃金は支払われなかった。それでも、時代が下がる
につれて、必需品の支給や贈物の代わりに、賃金を支払うようになった。いま1つの例をあげ
ると、ある親方は最初の5年間は衣服の支給だけ、さらに続けて働けば上陸着など多種類の
衣類の支給、そして6年目には40シリング、7年目には50シリング、8年目には55シリング、
最後には3ポンド支払うという徒弟契約を結んでいた(「海事職業の徒弟制」『船員の鏡』、196
0)。
2 救貧少年の強制乗船
★救貧徒弟の配乗義務★
商船への少年船員の供給は、こうした本来の徒弟制度によるものばかりではなかった。16
01年エリザベス救貧法は、市長が教区における救貧少年や救貧者の子供を見つけてきて、
年季奉公契約させて海上に追いやることを認めていた。その場合、教区が船長に謝礼金を支
払った。その規模が、どれくらいであったかは、不明である。
イギリスの海軍と海運は、すでにのべたように17世紀末にかけて膨張したため、船員不足
が激しくなった。そこで1703年船員増殖航海奨励法が制定され、救貧海事徒弟制が大いに
奨励された。翌年、さらに強化されて「教区委員や救貧委員は、10歳以上になる少年であっ
て、救貧を受けまた受けざるをえない少年、彼らが住む教区の負担となっている、またなるお
それのある少年、あるいは施物を受けざるをえない少年なら誰でも縛って、臣下である大船・
小船の船長や船主に引渡し……その少年が21歳になるまで……海上勤務の徒弟とすること
を……法的に認める」。
また、「積荷30トンから50トンの船の船長または船主は、徒弟を1人採用する義務があり、
50トンから100トンまではさらに1人、そして100トン増す毎に1人追加されるものとする」とさ
れた。そして、それを船長や船主が拒否すれば、10ポンドの罰金が科せられた。さらに、すで
に陸上で徒弟になっている救貧少年を、海事徒弟に切り替えることもできるようになった。この
規定は、救貧徒弟ばかりでなく、一般の徒弟を含めた配乗義務規定となっており、イギリス船
員の増殖を意図している。この規定は、航海条令が廃止された1849年に廃止されている。
E・G・トーマス氏は、貧困少年が海事徒弟に出されて行った事例を、数多く紹介している。そ
の徒弟先は、教区によって違いがあるが、石炭船、外航船、漁船、はしけ、そして軍艦であっ
た。たとえば、ブリストルでは1704年10月18日の1日だけで、28人の少年が船長の徒弟に
出されているし、ロンドンでは1802年から1811年にかけて徒弟に出した2484人のうち48
4人が、海事徒弟になっている。また、労役場に入れられていた少年が、軍艦に送り込まれた
例も紹介されている。すでに紹介した海員協会は、教区委員によって大いに利用されたという
(「旧救貧法と海事徒弟」『船員の鏡』、1977)。
ロイド氏は、18世紀に入ると、すでにのべたような「古来の形式での徒弟制は海運では少な
くなったが(外国人船員を雇用しはじめたこともある、引用者注)、海軍は名誉と権威ある状態
になりだしたにもかかわらず、救貧徒弟が多くなり、苦役の期間中、賃金は支払われず、ただ
2者のスーツを支給されるだけで、長期間拘束されるようになった」(同119ページ)とのべてい
る。
★いじめられる徒弟★
こうして海運に入った救貧徒弟が、どれぐらいの規模であったかは明らかではないが、かなり
の数であったことは、先にロンドンの例でもあきらかである。1835年商船船員法が通過した
時、救貧徒弟を含む全徒弟は5000人で、本来であれば1万4000人いなければならなかっ
たという(コース205ページ)。すでに、この頃になると、大方の船は徒弟雇用義務を無視して
いたのである。
徒弟の労働と生活は、楽なものではなかった。一般の徒弟は船首楼で水夫と一緒に食事を
し、召使の仕事もやらされていた。徒弟になるやいなや厳しい仕事をさせられ、士官や下士官
にいつもいじめられ、船員のいいなりにこき使われ、船員たちの衣服や食器も洗わせられ、奴
隷とあまり変らなかった。当時の商船にあっては、善悪のけじめといったものはなかったので、
ただ服従するかそれとも反乱を起こすしかなかった。すべての命令が仕事であって、それを拒
否して仕事をしないと反乱とみなされ、鞭打たれることになった。もちろん、船長が残忍に取り
扱われないよう、徒弟を保護する船もあったし、高度な航海術を船長から教えてもらう機会を
持てた少年がいなかったわけではない。徒弟がその船で仕事をやりとげ、徒弟期間が終れ
ば、士官の職務につける資格があると認定されることになった(コース183ページ)。
したがって、それら徒弟が一人前の船員になったかどうかは、きわめてうたがわしい。彼ら
も、陸上の徒弟と同様に、船から逃げ出したとみられる。船員増殖改正法が出されて2年後に
は、船長は13歳以下の少年や、病気または虚弱の少年は受け入れなくても良いという法律が
出されている。船長のなかには、救貧少年を使用することを好まず、10ポンドの罰金を支払う
ものさえあったといわれる。救貧少年にとって海上は陸上の親方や労役場から逃げ出す良い
機会であり、また真面目に働こうとする貧困少年にとっては好運をつかむ機会であったかも知
れないが、海上はやはり陸上よりも悲惨であったのである。
浮浪者取締法、救貧法や割当法といった法律は、イギリスの資本主義の本源的蓄積期にお
いて生み出された、おびただしい数の乞食・浮浪者・孤児のうち、労働能力のある者の浮浪を
刑罰で禁止するとともに、労働を強制しようとする「血の立法」であった。軍艦や商船は、その
船員が不足するところから格好の排出先として選ばれ、多くの貧困成人や少年が送り込まれ
たのである。救貧費用を負担する教区にとって、軍艦や商船は貧困成人・少年を連れ去ってく
れる点で、大いに好都合であったにちがいない。救貧徒弟は1890年代初めまで送り込まれ
ていた。
3 船員周旋業、大いに繁昌
★船員周旋業の役割★
船員は、その船の航海(帆船時代は、1年、2年はざらであった)毎に雇用契約を結んで、乗
船して行った。それを、属船雇用あるいは航海雇用という。船員がある船を下船して陸の生活
をし、また船に乗ろうとする場合、その都度、雇い先を探さなければならなかった。また、船主
や船長もその度毎に船員を探さねばならなかった。そこに登場するのが船員周旋業(crimps)
である。
J・S・キッチェン氏は、次のように要約している。「18、9世紀、多くの船員は、周旋業者を通
じて、乗組員が欲しい船主に雇われることになっていた。
周旋業者は、海港にある酒場(ale houses)や簡易宿泊所(lodging-houses、日本の周旋業者
は boarding-housesを鈍って、ボーレンという言葉で呼ばれていた、引用者注) の経営者であ
って、船員に安い寝床を、流れ者に仮のねぐらを提供していた。彼らの目的は、船員に金を使
い果させたうえで船員を脅し、商船に売り込むことにあった。
船員は、周旋業者に借金を抱え込まされ、船に連れ込まれることになった。その船で署名を
して、賃金の前渡しを受けるが、そこでばかばかしいほど安い交換率で、前渡金証(advanced
note)を割り引かれ、船員は借金を清算したことになる。
また、船が入港すると船員は引きずり降ろされるか、酒場に行かざるをえないようにされるの
で、いずれにしても周旋業者に従わざるをえない。船員は、いつもそうした方法でだましつづけ
られ、まったく不利な状況におかれ、周旋業者から逃げ出す機会を奪われつづけた」(同149
―150ページ)。
船員が、いくら金を持って下船しても、馬鹿遊びするのが常であったので、金はすぐになくな
った。それがなくなれば、どこか借金させてくれるところにころがり込むほかはなかった。たとえ
田舎に帰っていたとしても、港で寝泊りして職探しをせざるをえなかった。また、船に乗る前に
は、身仕度もしなければならなかった。船員は賭博場やダンスホール、売春宿に引っ張り込ま
れ、「楽しい時間」を付けで過していた。借金しないかぎり、誰も取り合ってくれなかった。船員
装身具屋は喜んで掛け売りしてくれたが、普通の値段の2倍だった。それについても周旋屋は
25%の手数料を取っていた。船員は支払われる賃金以上の借用証を、周旋屋から突き付け
られることになった。周旋屋が船員に船を見つけて乗せると、手数料として1ポンド取っていた。
雇用が決まると、1、2か月の前渡金証が発給されるが、周旋屋や売春婦、居酒屋のおやじ
は、前渡金証を25−30%割引いて買い取っていた(コース241ページ)。
船員周旋業は、19世紀に入って、イギリスのみならず、各国の海運が多数の船員を必要に
なるにつれて、盛んになった。そのなかでも、アメリカは悪徳な周旋業者がいることで有名であ
った。そうした周旋業と闘ったことで著名なJ・フェルという、元ボクサーで船員伝道教会(the
Mission to Seamen)の牧師は、19世紀末のサンフランシスコの状況について書き残している。
まず、周旋業者について、「彼らは、特に好況期に船員を脱船するよう誘うことは罪深いとは思
っているが、そうするのが船員のためになると、疑問を持たずにやっている。また、不景気にな
ると、多数の船員が数週間も下宿し、何はともあれ食事をし、寝泊りできる。それは、他に道が
ないので、一応道理にかなっている。しかし、そうしたことが周旋システムの計り知れない悪徳
ぶりを許すことにはならない」(『サンフランシスコのイギリス人商船船員』69ページ、エドワー
ド・アーノルド社、1899)。
 |
 |
| (ハドソン画、1789年) 妻や子供と別れて船に乗る水夫 |
(モズレイ画、1774年) 船員宿の客引き、売春婦が寄りそい、 水夫をくどいているかにみえる |
★周旋屋のだましの手口★
それでは、船員はどのようにして、だまされるのか。
「その船が錨を入れると、下宿屋やその客引きが一団となって、水夫のところに寄って来る。
棍棒や短剣は持っていないが、舌先参寸とウイスキーは持っている」。彼らは、威勢よく、陸で
楽しめる話や物めずらしい話を始めるが、水夫たちはいつものことよと、それほど驚きもしな
い。次第に、話の種がなくなってくると、「ウイスキーがやおら取り出され、これこそが"話したこ
との中身よ"といって見せびらかす。毒は入っていないよといって、陸の紳士はまず一杯あお
る。それまで、どうせいつものことよと思っていた水夫も、動揺し始める。一杯やりはじめると、
どの水夫にも、心から満足した表情が顔にあふれ出る。彼らは次第に気持ちがなごみ、もの
わかりが良くなる」が、まだ脱船する決心はつかない。
陸の紳士は、そろそろ引き揚げるかといいながら、「おやおや忘れるところだった。古い1級
品のスコッチがポケットに残っていたよ」「これが本物、前のは安物」といってぶらぶらさせる。
水夫たちは、もう一杯と飛びつくと、「頑なさもはぐれ、迷いもふっきれ、誰もが船は地獄、陸は
天国だということに納得し、自分の着物にとりついて、バックやチェストにつめ始める」。何のこ
とはない、「最初のボトルは純正だったが、2本目に薬が仕込まれていたのである」(フェル86
−90ページ)。
なお、船員不足が激しくなると、麻薬などを仕組んだ酒を飲ませて、船員を乗船させたり、陸
の人間を船員に仕立てた。そうした誘拐まがいの方法は、上海(shanhai)と呼ばれていた。4
本マストのパーク型帆船スプリングバーン号の徒弟たちは、シヤンハイ・ブラウンという名のサ
ンフランシスコきっての周旋屋の手で麻薬をかがされ、他の船に乗せられている。徒弟が生気
にかえったところ、その船の航路は喜望峰回りでしかも冬分の航海になることがわかり、ショッ
クを受けている。船員周旋屋の手で船に乗せられるのは水夫ばかりではなかった。船員が不
足していて、乗組員を集めるため滞船しているような時は、わなに引っ掛ってくる男なら、誰彼
を問わず麻薬をかがせていた。ジミー・ザ・ドラマーという悪名高い周旋屋は、陸の男をつかま
えようとしたが、それにも失敗した。そこで死体置き場に行って係の男を抱き込み、男の死体
をもらい受け、麻薬で酔った男と一緒にポートに投げ入れ、船まで運び込んだ。死者の分の周
旋謝礼金(bloody money)をちゃんと受け取っていた。それが多い時は1人当り20ポンドにな
ることもあった(コース243−4ページ)。
船員は、賃金の高いアメリカ船や住み心地の良いカルフォルニアの陸の仕事に魅了されて、
周旋屋の手をわずらわされずに、脱船していた。そればかりか、船長が脱船を奨励する場合
もあった。特に船が積荷のため長期間滞船せざるをえない時に発生した。船長はこづかいも
洋服屋の付けも認めないよと宣言した上で、船長と士官は何か仕事はないかとあら捜しをし
て、乗組員を奴隷のようにこき使う。そうされると、乗組員は高い賃金が稼げる船に雇われたく
なったり、陸で「楽しい時間」を過したくなったりして、やすやすと脱船に追い込まれてしまう。船
長や船主は支払わなければならない賃金を支払わず、自分の取り前にしてしまう。その後制
定された海運法では、船主に対して脱船者の賃金を商務省に差し出させるように命令したが、
脱船がなくなるわけはなかった(同246ページ)。.
それでは、船員はどのようにして、だまされるのか。
「その船が錨を入れると、下宿屋やその客引きが一団となって、水夫のところに寄って来る。
棍棒や短剣は持っていないが、舌先参寸とウイスキーは持っている」。彼らは、威勢よく、陸で
楽しめる話や物めずらしい話を始めるが、水夫たちはいつものことよと、それほど驚きもしな
い。次第に、話の種がなくなってくると、「ウイスキーがやおら取り出され、これこそが"話したこ
との中身よ"といって見せびらかす。毒は入っていないよといって、陸の紳士はまず一杯あお
る。それまで、どうせいつものことよと思っていた水夫も、動揺し始める。一杯やりはじめると、
どの水夫にも、心から満足した表情が顔にあふれ出る。彼らは次第に気持ちがなごみ、もの
わかりが良くなる」が、まだ脱船する決心はつかない。
陸の紳士は、そろそろ引き揚げるかといいながら、「おやおや忘れるところだった。古い1級
品のスコッチがポケットに残っていたよ」「これが本物、前のは安物」といってぶらぶらさせる。
水夫たちは、もう一杯と飛びつくと、「頑なさもはぐれ、迷いもふっきれ、誰もが船は地獄、陸は
天国だということに納得し、自分の着物にとりついて、バックやチェストにつめ始める」。何のこ
とはない、「最初のボトルは純正だったが、2本目に薬が仕込まれていたのである」(フェル86
−90ページ)。
なお、船員不足が激しくなると、麻薬などを仕組んだ酒を飲ませて、船員を乗船させたり、陸
の人間を船員に仕立てた。そうした誘拐まがいの方法は、上海(shanhai)と呼ばれていた。4
本マストのパーク型帆船スプリングバーン号の徒弟たちは、シヤンハイ・ブラウンという名のサ
ンフランシスコきっての周旋屋の手で麻薬をかがされ、他の船に乗せられている。徒弟が生気
にかえったところ、その船の航路は喜望峰回りでしかも冬分の航海になることがわかり、ショッ
クを受けている。船員周旋屋の手で船に乗せられるのは水夫ばかりではなかった。船員が不
足していて、乗組員を集めるため滞船しているような時は、わなに引っ掛ってくる男なら、誰彼
を問わず麻薬をかがせていた。ジミー・ザ・ドラマーという悪名高い周旋屋は、陸の男をつかま
えようとしたが、それにも失敗した。そこで死体置き場に行って係の男を抱き込み、男の死体
をもらい受け、麻薬で酔った男と一緒にポートに投げ入れ、船まで運び込んだ。死者の分の周
旋謝礼金(bloody money)をちゃんと受け取っていた。それが多い時は1人当り20ポンドにな
ることもあった(コース243−4ページ)。
船員は、賃金の高いアメリカ船や住み心地の良いカルフォルニアの陸の仕事に魅了されて、
周旋屋の手をわずらわされずに、脱船していた。そればかりか、船長が脱船を奨励する場合
もあった。特に船が積荷のため長期間滞船せざるをえない時に発生した。船長はこづかいも
洋服屋の付けも認めないよと宣言した上で、船長と士官は何か仕事はないかとあら捜しをし
て、乗組員を奴隷のようにこき使う。そうされると、乗組員は高い賃金が稼げる船に雇われたく
なったり、陸で「楽しい時間」を過したくなったりして、やすやすと脱船に追い込まれてしまう。船
長や船主は支払わなければならない賃金を支払わず、自分の取り前にしてしまう。その後制
定された海運法では、船主に対して脱船者の賃金を商務省に差し出させるように命令したが、
脱船がなくなるわけはなかった(同246ページ)。.
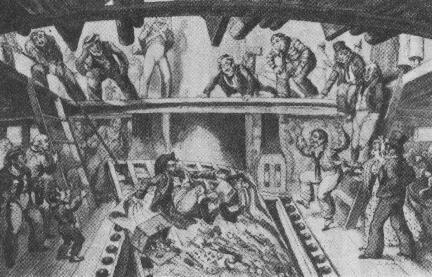 |
| (G・クリクシャンク・1792−1878年、画) 品物もろ共、船倉にひっくり返されている |
★船長・船主もぐるだった★
このようにして、船員は脱船し、何か月かの賃金を失ってしまう。そして周旋業者に借金を抱
え込まされて、別の船に売り込まれることになるが、前渡金は自分の手元には1ペンスも残ら
ない。それでは、船員がそうしたわかりきった好計にひっかかるかといえば、フェル師がいうよ
うに「水夫たちは、大都市に入港する前に、何か月も海上にいたので興奮し、感じやすい状態
におかれていた」し、また船員は海上で肉体的にも精神的にも、飢えの状態で入港してくるか
らであった。
こうした周旋屋の脱船そそのかしで、船長が困らないわけはなかったが、それを妨害すれ
ば、出帆時にどこからも乗組員を補充できなくなり、要員不足になるおそれがあった。それは
普通の言い訳であって、船長のなかにはすでにみたように、脱船者の賃金を横領した上に、新
しい乗船者を受け入れる際に、周旋業者から心付けを受け取っていた。悪徳な船長は、いつも
周旋業者とつるんでいた。それでは、船主はどうかといえば、船員が奸計に陥っているかぎり、
賃上げなど要求して来ないと安心していた。要するに、船員は周旋業を媒介にした属船雇用と
いう形態のもとで、労働者の権利は奪われ、いつも素寒貧(船員言葉では「頭なし」という)の状
態におかれていたのである。
4 船員周旋業の規制とその困難
★前渡金の直接支給★
こうした船員周旋業に対する社会的な批判は、19世紀に入ってそれが盛んになるにつれて
強まらざるをえなかった。
1845年、船員が船から逃げることをやめないかぎり、船に船員を乗り組ませるためには、
周旋業者を通じて行う以外に方法はないというある下院議員の反対にかかわらず、船員保護
法(the Seamen's Protection Act)がようやく議会を通過した。
その前文には、「ここ数年間、乗り組んでも利益にならないような船に、船員が乗り組まざる
をえないように仕向けるある種の人びとによって、イギリス連合王国の船員は重い負担と大変
な不正のもとにおかれている」と書かれていた。
この法律は、商船のために船員を準備し、供給し、乗船させることを事業とする人びとに免
許制度を導入して、その状況を改善しようとするものであった。免許を受けずに周旋を行った
り、免許のない者から船員の供給を受けたり、また仕事を見つけてもらおうとする船員から金
を受け取ったり、要求したりすることは違反となった。また、法律は前渡金を船員に直接に手
渡し、しかもそれを船員が雇人契約に署名した6時間後に行うよう明文化した。
それは、周旋業者の前渡金証の割引きを防止するとともに、船員が酔いをさます前に、周旋
業者が前渡金を持ち去ってしまわないようにするために設けられたものであった。
さらに、船が確実にドックに入る前に、周旋業者が船長の許可を受けずに、船に乗り込んでく
ることを禁止した。また、入港後24時間以上もたたないうちに訪船して、無免許人の下宿人に
なって借金するようそそのかしたり、あるいは持ち主や船長の許可をえずに持物を運び出した
りすることも違反となった。そして、船員に過大な宿泊料をふっかけたり、借金の代わりに持物
を取る場合、不当に割り引いたりしてはならないことになった。
このようにして、船員は脱船し、何か月かの賃金を失ってしまう。そして周旋業者に借金を抱
え込まされて、別の船に売り込まれることになるが、前渡金は自分の手元には1ペンスも残ら
ない。それでは、船員がそうしたわかりきった好計にひっかかるかといえば、フェル師がいうよ
うに「水夫たちは、大都市に入港する前に、何か月も海上にいたので興奮し、感じやすい状態
におかれていた」し、また船員は海上で肉体的にも精神的にも、飢えの状態で入港してくるか
らであった。
こうした周旋屋の脱船そそのかしで、船長が困らないわけはなかったが、それを妨害すれ
ば、出帆時にどこからも乗組員を補充できなくなり、要員不足になるおそれがあった。それは
普通の言い訳であって、船長のなかにはすでにみたように、脱船者の賃金を横領した上に、新
しい乗船者を受け入れる際に、周旋業者から心付けを受け取っていた。悪徳な船長は、いつも
周旋業者とつるんでいた。それでは、船主はどうかといえば、船員が奸計に陥っているかぎり、
賃上げなど要求して来ないと安心していた。要するに、船員は周旋業を媒介にした属船雇用と
いう形態のもとで、労働者の権利は奪われ、いつも素寒貧(船員言葉では「頭なし」という)の状
態におかれていたのである。
4 船員周旋業の規制とその困難
★前渡金の直接支給★
こうした船員周旋業に対する社会的な批判は、19世紀に入ってそれが盛んになるにつれて
強まらざるをえなかった。
1845年、船員が船から逃げることをやめないかぎり、船に船員を乗り組ませるためには、
周旋業者を通じて行う以外に方法はないというある下院議員の反対にかかわらず、船員保護
法(the Seamen's Protection Act)がようやく議会を通過した。
その前文には、「ここ数年間、乗り組んでも利益にならないような船に、船員が乗り組まざる
をえないように仕向けるある種の人びとによって、イギリス連合王国の船員は重い負担と大変
な不正のもとにおかれている」と書かれていた。
この法律は、商船のために船員を準備し、供給し、乗船させることを事業とする人びとに免
許制度を導入して、その状況を改善しようとするものであった。免許を受けずに周旋を行った
り、免許のない者から船員の供給を受けたり、また仕事を見つけてもらおうとする船員から金
を受け取ったり、要求したりすることは違反となった。また、法律は前渡金を船員に直接に手
渡し、しかもそれを船員が雇人契約に署名した6時間後に行うよう明文化した。
それは、周旋業者の前渡金証の割引きを防止するとともに、船員が酔いをさます前に、周旋
業者が前渡金を持ち去ってしまわないようにするために設けられたものであった。
さらに、船が確実にドックに入る前に、周旋業者が船長の許可を受けずに、船に乗り込んでく
ることを禁止した。また、入港後24時間以上もたたないうちに訪船して、無免許人の下宿人に
なって借金するようそそのかしたり、あるいは持ち主や船長の許可をえずに持物を運び出した
りすることも違反となった。そして、船員に過大な宿泊料をふっかけたり、借金の代わりに持物
を取る場合、不当に割り引いたりしてはならないことになった。
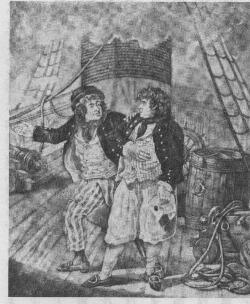 |
| いいところがありやすよ (イネス版、1795年) |
★海運局で雇入契約★
1850年、船員保護と船舶安全に関する最初の本格的な法律である商船法(the Mercantile
Marine Act)が制定された。それは、この国の海事従業者を虐待し、圧迫している「周旋業」に
終止符を打つための「第2段の重要な原則」を提示しようとするものであった。
海港に、地方海運局を設置し、それを通じて海運の業務や法律の施行を監督しようとした。
雇人契約の様式を改善し、それを海運局長の面前で読み上げ、説明したうえで、船員が納得
して署名させるようにした。そして、局長は法定の手数料以外に報酬を要求したり、受け取って
はならないことになった(以上、キッチェン149-152ページ)。これもあまり役に立たなかった。
1854年海運法(the Merchant Shipping Act)は、周旋業そのものを禁止したが、それがなく
なったわけではない。S・ジーンズ氏は、「ある領事は、いまや周旋業は"世界規模のシステム"
となっている。……このシステムの毒素は、船長が脱船者の賃金を交代船員の補充費用に充
てることを認めている海運法の規定にあると、非難している。どの船も、港で停泊せざるをえな
いが、その時、周旋業者は(士官がそれに失敗した場合)男たちを陸に追いやるために雇わ
れており、船主は費用を節約し、船長は金をもうけ、船員もすぐに別の船に再雇用されている
という。
また、1869年、ロンドンとカーデフが最悪の周旋業者がいる港であるとしているが、海運局
の記録もそうなっている。その年、カーデフにほ150軒の船員宿があった。……周旋業者は弁
護士を雇って……自らを守っている」(同434ページ)とのべている。
周旋システムの根源が、前疲金あるいは前波金証にあるという批判が強まり、1880年に前
渡金証は廃止されたが、周旋屋で借金を重ねた船員は月づきの宅渡金ノート(Allotment
Notes)を作る際に、周旋業者をすすんで親戚に入れた(同上435ページ)。
キッチェン氏は、「あからさまにいって、船員周旋業は法律の威信によって消滅したわけでは
ない。同時代人によれば、周旋業は19世紀末まで船員生活の一側面であったと強調されてい
る。事実、リバプールで全国合同水火夫組合が最初のストライキを行った際、周旋業者たちは
船主側について活動していた……海運連盟が1890年に設立され、それが同事務所において
船員の雇入れるようにすると主張したことが、この国で周旋の慣行を終らせることになった」
(同153ページ)とのべている。
しかし、真の意味で船員周旋が終るのは、海員組合が力を持ち始め、1947年に船員常置
制度が設立されたからであるとみられる。
★現在も続く周旋業★
日本にも、ボーレンと呼ばれた船員周旋屋がいた。それ自身はイギリスやアメリカほど悪ら
つではなかったようであるが、船内高利貸や船内賭博との結びつきがあり、船員はいつも素寒
貧になっていた。その実態は、浦島光雄「海のシャイロック―あるいはガジの掠<かす>り―」
『中央公論』(昭和4年3月号)にも示されている(ガジとは高利貸をする水夫長、火夫長のこ
と)。
戦前から海員組合が結成されており、また1922(大正12)年には周旋業を禁止する船員
職業紹介法が制定され、それを実施する海事協同会も設置されたが、周旋業はなくなることは
なかった。それは、戦時海運統制機関の船舶運営会を経過し、戦後、船員の会社専属雇用が
一般化するまでなくならなかった。
第2次世界大戦後、先進海運国において、船員周旋業はおおむねなくなったかにみえたが、
1960年代以降の便宜置籍船の発達とともに、ふたたび栄えつつあるかにみえる。もちろん、
それは戦前のイギリスなどにみられたような「中間搾取」を目的とするようなものは少なく、船員
の募集や採用、契約の船主業務を代行するマンニング代理店というかたちをとっている。そう
した新しい様相をみせながらも、船員が労働力の再生産のための乗船と下船を繰り返さざる
をえず、その職探しと労働条件をめぐって、船員が競争を行っているという弱い立場につけい
った事業であり、その結果として船員がつねに不安定な雇用のもとにおかれ、無権利な状態に
さらされているという本質は、いっこうに変わっていない。
しかも、それが便宜置籍船の乗組員をめぐる国際的な周旋となっているため、船員の雇用
の継続性、船主と船員の権利義務、周旋業に対する規制などの面で、事態は深刻になってい
るかにみえる。さらに、それが開発途上国ばかりでなく、先進国においても再形成されつつあ
ることは、船主にとってそれが船員費の節減のためにきわめて有効な手段であることを知らせ
てくれるとともに、そうした手段をなくし、船員の雇用安定をはかることが、国内的にも国際的に
も、海員組合にとって日常的にも長期的にもきわめて重要な事業であることを教えてくれる。
1850年、船員保護と船舶安全に関する最初の本格的な法律である商船法(the Mercantile
Marine Act)が制定された。それは、この国の海事従業者を虐待し、圧迫している「周旋業」に
終止符を打つための「第2段の重要な原則」を提示しようとするものであった。
海港に、地方海運局を設置し、それを通じて海運の業務や法律の施行を監督しようとした。
雇人契約の様式を改善し、それを海運局長の面前で読み上げ、説明したうえで、船員が納得
して署名させるようにした。そして、局長は法定の手数料以外に報酬を要求したり、受け取って
はならないことになった(以上、キッチェン149-152ページ)。これもあまり役に立たなかった。
1854年海運法(the Merchant Shipping Act)は、周旋業そのものを禁止したが、それがなく
なったわけではない。S・ジーンズ氏は、「ある領事は、いまや周旋業は"世界規模のシステム"
となっている。……このシステムの毒素は、船長が脱船者の賃金を交代船員の補充費用に充
てることを認めている海運法の規定にあると、非難している。どの船も、港で停泊せざるをえな
いが、その時、周旋業者は(士官がそれに失敗した場合)男たちを陸に追いやるために雇わ
れており、船主は費用を節約し、船長は金をもうけ、船員もすぐに別の船に再雇用されている
という。
また、1869年、ロンドンとカーデフが最悪の周旋業者がいる港であるとしているが、海運局
の記録もそうなっている。その年、カーデフにほ150軒の船員宿があった。……周旋業者は弁
護士を雇って……自らを守っている」(同434ページ)とのべている。
周旋システムの根源が、前疲金あるいは前波金証にあるという批判が強まり、1880年に前
渡金証は廃止されたが、周旋屋で借金を重ねた船員は月づきの宅渡金ノート(Allotment
Notes)を作る際に、周旋業者をすすんで親戚に入れた(同上435ページ)。
キッチェン氏は、「あからさまにいって、船員周旋業は法律の威信によって消滅したわけでは
ない。同時代人によれば、周旋業は19世紀末まで船員生活の一側面であったと強調されてい
る。事実、リバプールで全国合同水火夫組合が最初のストライキを行った際、周旋業者たちは
船主側について活動していた……海運連盟が1890年に設立され、それが同事務所において
船員の雇入れるようにすると主張したことが、この国で周旋の慣行を終らせることになった」
(同153ページ)とのべている。
しかし、真の意味で船員周旋が終るのは、海員組合が力を持ち始め、1947年に船員常置
制度が設立されたからであるとみられる。
★現在も続く周旋業★
日本にも、ボーレンと呼ばれた船員周旋屋がいた。それ自身はイギリスやアメリカほど悪ら
つではなかったようであるが、船内高利貸や船内賭博との結びつきがあり、船員はいつも素寒
貧になっていた。その実態は、浦島光雄「海のシャイロック―あるいはガジの掠<かす>り―」
『中央公論』(昭和4年3月号)にも示されている(ガジとは高利貸をする水夫長、火夫長のこ
と)。
戦前から海員組合が結成されており、また1922(大正12)年には周旋業を禁止する船員
職業紹介法が制定され、それを実施する海事協同会も設置されたが、周旋業はなくなることは
なかった。それは、戦時海運統制機関の船舶運営会を経過し、戦後、船員の会社専属雇用が
一般化するまでなくならなかった。
第2次世界大戦後、先進海運国において、船員周旋業はおおむねなくなったかにみえたが、
1960年代以降の便宜置籍船の発達とともに、ふたたび栄えつつあるかにみえる。もちろん、
それは戦前のイギリスなどにみられたような「中間搾取」を目的とするようなものは少なく、船員
の募集や採用、契約の船主業務を代行するマンニング代理店というかたちをとっている。そう
した新しい様相をみせながらも、船員が労働力の再生産のための乗船と下船を繰り返さざる
をえず、その職探しと労働条件をめぐって、船員が競争を行っているという弱い立場につけい
った事業であり、その結果として船員がつねに不安定な雇用のもとにおかれ、無権利な状態に
さらされているという本質は、いっこうに変わっていない。
しかも、それが便宜置籍船の乗組員をめぐる国際的な周旋となっているため、船員の雇用
の継続性、船主と船員の権利義務、周旋業に対する規制などの面で、事態は深刻になってい
るかにみえる。さらに、それが開発途上国ばかりでなく、先進国においても再形成されつつあ
ることは、船主にとってそれが船員費の節減のためにきわめて有効な手段であることを知らせ
てくれるとともに、そうした手段をなくし、船員の雇用安定をはかることが、国内的にも国際的に
も、海員組合にとって日常的にも長期的にもきわめて重要な事業であることを教えてくれる。
 ホームページへ |
 目次に戻る |
 |
 |