 ホームページへ |
 目次に戻る |
| |
多数の人びとが、同じ場所に集って計画的な協働作業をしようとする場合、そこにはオーケス
トラと同じようになんらかの指揮が必要となる。この多数の働く人の協業とそれにともなう指揮
は、マニュファクチュアが普及するまでは、奴隷の大土木工事や農奴の季節的な農作業、さら
に軍隊の戦闘などどく一部にみられただけであった。そうしたなかで、古代からそれなりに大型
の漕ぎ船や帆船にあっては、多数の船員が乗り組み、多種多様な作業を行っていた。また、
船はただ単に労働の場であるだけでなく、船員の生活の場でもあった。しかも、船は同じ船員
を何十日、何か月も船に閉じ込めながら、航海をつづける。したがって、そこには陸上ではとう
ていみられない協業と指揮、それをめぐる制度が必要とならざるをえなかった。どのような方法
で、船内規律が保たれてきたかである。
1 近世における処罰の強化
★オレロン海法★
商品の売買とその輸送は、陸上よりも海上でより発達した。そのため、船舶の所有、海上で
の輸送、損害の賠償、船員の雇用など海商法は古代よりみられ(たとえばロードス海法)、中
世になると、海港都市を中心にいろいろな海事慣習法が集録されている。そのなかでもオレロ
ン海法は、1194年頃、ぶどう貿易の商人や船主が大勢集り、冬分には船を係留させていた
フランス西海岸のオレロン島でまとめられたもので、船員の労働や生活を規制していた。イギ
リスは、オレロン海法をまず取り入れていたとされる。
★乗組仲間が処罰決定★
オレロン海法は、指揮をまかされた船長は船内のあらゆることに責任があり、預かった船を
完ペきに航海させる能力がなければならないと定めていた。船長は士官や船員を監督するこ
とを要求され、また士官や船員は船長の許可がなければ下船できなかった。船長に生意気な
口をきこうものなら、船員は8ペンスの罰金が科せられた。船長から殴られる時、1発目は身
構えることなく、それを甘んじて受けなければならなかった。2発目になれば、自分をかばうこと
が船員の権利として認められていた。しかし、水夫が殴り返せば5シリングの罰金を払うか、片
手を切り落されるか、そのどちらかを選ばねばならなかった。たいへん変った規定もあった。
船長に酷使された場合、その船員は自分の部屋に隠れても良い、また船長が追いかけてきた
場合、その船員は自衛することができるとされていた。
船長とある船員との間で紛争が持ち上った場合、乗組仲間(the ship's company)が協議して
船員の償い方を決定することになっていた。ただ、その仲裁を待たずに、その船員を下船させ
た場合、船長はその船員に賃金を支払う責任があり、また乗組員不足が原因でその船が損
害を受けた場合、それを償う責任があった。そればかりでなく、乗組仲間はあらゆる船内規律
にかかわる事柄を分け入って取り上げる権利があった。また、出帆の期日はその船に乗って
いる商人を含め、船内の多数の合意がなければ決められなかった。船長がその決定を無視し
た場合、その結果起きた損害は自らかぶらなければならなかった。他方、乗組員が海難にあ
たって、船体や貨物を救う努力をまったくしなかった時は、彼らは賃金を没収されることになっ
ていた。
また、水夫が休日でもないのに下船していて船に損害が生じた場合、その水夫は1年間、パ
ンと水だけで監禁となった。そのために致命的な事故となると、その懲罰は鞭打ち(flogging)で
あった。脱船した船員は顔に焼きどてを当てられた。泥酔や決闘、けんかも処罰された。乗船
中、船員が自分のせいでなく病気になった場合、毎日の食事ばかりでなく、その航海の賃金が
すべて保障された。また、その船員が乗船中に仕事をしていて負傷すれば、その費用は船主
の負担となった。乗船中、病気の治療の機会がなかった場合、その船員は船のボーイを連れ
て上陸し、看護の婦人を雇ってもらえると、オレロン海法は決めていた(以上、コース20−1ペ
ージ)。
トラと同じようになんらかの指揮が必要となる。この多数の働く人の協業とそれにともなう指揮
は、マニュファクチュアが普及するまでは、奴隷の大土木工事や農奴の季節的な農作業、さら
に軍隊の戦闘などどく一部にみられただけであった。そうしたなかで、古代からそれなりに大型
の漕ぎ船や帆船にあっては、多数の船員が乗り組み、多種多様な作業を行っていた。また、
船はただ単に労働の場であるだけでなく、船員の生活の場でもあった。しかも、船は同じ船員
を何十日、何か月も船に閉じ込めながら、航海をつづける。したがって、そこには陸上ではとう
ていみられない協業と指揮、それをめぐる制度が必要とならざるをえなかった。どのような方法
で、船内規律が保たれてきたかである。
1 近世における処罰の強化
★オレロン海法★
商品の売買とその輸送は、陸上よりも海上でより発達した。そのため、船舶の所有、海上で
の輸送、損害の賠償、船員の雇用など海商法は古代よりみられ(たとえばロードス海法)、中
世になると、海港都市を中心にいろいろな海事慣習法が集録されている。そのなかでもオレロ
ン海法は、1194年頃、ぶどう貿易の商人や船主が大勢集り、冬分には船を係留させていた
フランス西海岸のオレロン島でまとめられたもので、船員の労働や生活を規制していた。イギ
リスは、オレロン海法をまず取り入れていたとされる。
★乗組仲間が処罰決定★
オレロン海法は、指揮をまかされた船長は船内のあらゆることに責任があり、預かった船を
完ペきに航海させる能力がなければならないと定めていた。船長は士官や船員を監督するこ
とを要求され、また士官や船員は船長の許可がなければ下船できなかった。船長に生意気な
口をきこうものなら、船員は8ペンスの罰金が科せられた。船長から殴られる時、1発目は身
構えることなく、それを甘んじて受けなければならなかった。2発目になれば、自分をかばうこと
が船員の権利として認められていた。しかし、水夫が殴り返せば5シリングの罰金を払うか、片
手を切り落されるか、そのどちらかを選ばねばならなかった。たいへん変った規定もあった。
船長に酷使された場合、その船員は自分の部屋に隠れても良い、また船長が追いかけてきた
場合、その船員は自衛することができるとされていた。
船長とある船員との間で紛争が持ち上った場合、乗組仲間(the ship's company)が協議して
船員の償い方を決定することになっていた。ただ、その仲裁を待たずに、その船員を下船させ
た場合、船長はその船員に賃金を支払う責任があり、また乗組員不足が原因でその船が損
害を受けた場合、それを償う責任があった。そればかりでなく、乗組仲間はあらゆる船内規律
にかかわる事柄を分け入って取り上げる権利があった。また、出帆の期日はその船に乗って
いる商人を含め、船内の多数の合意がなければ決められなかった。船長がその決定を無視し
た場合、その結果起きた損害は自らかぶらなければならなかった。他方、乗組員が海難にあ
たって、船体や貨物を救う努力をまったくしなかった時は、彼らは賃金を没収されることになっ
ていた。
また、水夫が休日でもないのに下船していて船に損害が生じた場合、その水夫は1年間、パ
ンと水だけで監禁となった。そのために致命的な事故となると、その懲罰は鞭打ち(flogging)で
あった。脱船した船員は顔に焼きどてを当てられた。泥酔や決闘、けんかも処罰された。乗船
中、船員が自分のせいでなく病気になった場合、毎日の食事ばかりでなく、その航海の賃金が
すべて保障された。また、その船員が乗船中に仕事をしていて負傷すれば、その費用は船主
の負担となった。乗船中、病気の治療の機会がなかった場合、その船員は船のボーイを連れ
て上陸し、看護の婦人を雇ってもらえると、オレロン海法は決めていた(以上、コース20−1ペ
ージ)。
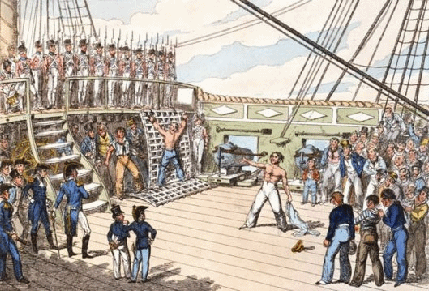 |
| (ジョージ・クルックシャンク画) 本文で示された処刑の模様通りである。 甲板中央の水夫は、彼は無罪だと抗議している |
★近世、残忍さを増す★
その他にいろいろな中世の慣習法があるが、それについてフェイル氏は、全体として次のよ
うな評価を与えている。「オレロン海法では、『船員間の平和を保持して彼等の争いを調停する
こと』をもって、船長の義務と定めている」ように、「船長は同輩のうちの一指導者にすぎず、彼
と乗組員との間柄は、どちらかと言えば独裁的よりも親爺的であった」。「地中海の諸海法によ
ると、窃盗、口論、その他の犯行をなした者は解雇処分に附する旨を規定しているけれども、
それ以外に規律強化に関する規定はほとんど見あたらない。また、笞<むち>刑を認めてい
る海法にあっても、時々、流血にいたらざることと定めており、したがってそれは18世紀の海
上笞刑とは大いに趣きを異にしている」。そして、「概括的に言って、これら中世地中海諸国の
海法は、海員の権利に関する規定において、また海員の疫病或いは死亡のごとき不慮の事
故に関する規定において多大の考慮を払っており、この点18世紀さらには19世紀前半期の
船舶における条件よりは明白に進歩を示していた」(以上、同63−5ページ)。
このように、中世の船にあっては、船長の権威は認めてはいるもの〆、船内規律は乗組仲
間の自主規制でもって維持されていたといえる。後世とちがって、そうしたいわば民主的な方
法が事足りたのであるが、それは「船員自身がしばしば船舶または積荷の持分所有者(part-
owner)であって、同船している誰とも同等の社会的地位を持っていた。当時の航海は、全く実
地の経験に基づいて行なわれたため、雇われた海員といえども、仕事について船長とほぼ同
じくらいに弁<わきま>えていた」(フェイル62ページ)からである。しかし、海運経営が小生産
者の共同経営から資本経営となり、いまだ賃金労働者としての訓練を受けるにいたっていない
船員が増加してくると、そうした民主的で穏健な方法では事足りなくなってくる。そのなかでも、
いやいやながら海軍に強制徴発された船員が乗る軍艦の船内規律は、中世さながらの残虐さ
をみせることになる。
なお、小門和之助氏は「中世紀におけるヨーロッパ船員社会」(『船員問題の国際的展望』、
日本海事振興会、1958年)で、船員労働の慣習法を詳しくまとめている。
2 海軍の典型的な処罰・鞭打ち刑
★中世的な処罰★
イギリスにおいて、海軍が不評判であった1つの理由は、船内の規律が厳しく、それに違反
すると酷い処罰を受けることにあった。1530年ごろへンリー8世が公布した海軍規律令によ
ると、船内で殺人を犯した場合、その者に偉業があっても、その者を生きたまま死体に縛って
海中に投げ棄てる……船内で艦長を武器で突き刺した場合、その者の右手を切り落とす……
船内で自分の当直中に居眠りした場合、……4度目には……その者をビール1缶、肉1片そし
て磨いだナイフと一緒にカゴに入れ、バウスプリット(斜檣)に吊し、そこで餓死するか、それを
切って海中に入水をするかを選ばせる……船内で酔って、船の食事を食べなかった場合……
艦長は鉄製の足かせで縛って入牢させ、その者がみずからの罪を悔いるまで放っておく……
となっていた。これらは、中世の処罰を踏襲するものであった。海軍の規模が大きくなり、「世
の中のくず」が多数、海軍に徴発されて来るようになると、処罰はよりいっそう激しいものとなっ
た。
1661年法は、いままでの犯罪や処罰を集大成したものであるが、39条のうち25条は死刑
と規定していた。殺人、横領、間謀<スパイ>、脱走、反乱、士官殴打、放火、強盗または当
直中の常習居眠りは、死刑であった。悪口、泥酔、その他公序良俗に反する行為は、鞭打ち
または罰金となっていた。ただ、死刑については、いままで艦長や司令官が執行していたの
を、海軍裁判所で裁決することにした。
1731年に海軍本部規則が制定された。それは、いままでの処罰を繰り返したものであった
が、それを軽減しまたその手続きを詳細に定めた。死刑といった処罰は、次第に実行されなく
なったが、鞭打ち刑は19世紀中頃まで多くの軍艦では日常行事であった。
★船底くぐり刑★
海軍における著名な処罰を挙げれば、次のようなものがあった。なお、海軍における絞首刑
は、ヤーダム(桁端)に吊した。
1 船内餓死刑、前述通り。
2 くすぐりの刑(tarring and feathering:全身にタールを塗りつげ、その上を羽毛で覆う刑)
3 海中突入刑(ducking at the yard arm:ヤードの端に吊し、そこから一気に海中に落とす
刑)
4 船底くぐり刑(hauling under the keel:船員を縛って、船底を左舷から右舷へくぐらせる刑)
5 艦隊回し鞭打ち刑(fogging round the fleet:船員が艦隊の各艦を回って鞭打たれる刑)
などであるが、日常的に数多く行われた処罰は、鞭打ちであった。非公認の鞭打ちとして、次
のような処罰もあった。その1つは、
6 並び打ち刑(running the gauntlet)で、結び目のある、いらくさまたは細引きで武装した全乗
組員を一定の間隔で並ばせ、その列の間を裸になった男を走らせ、鞭打つやり方であった。
それは1806年に禁止された。他の1つは、
7 藤の鞭打ち(starting with a rattan)で、当時は荒あらしい時代であったので、それはひん
ばんに用いられた処罰であった。横暴なボースンや見習士官に打たれると、命を落としかねな
かった(以上、ロイド241ページ)。
3 海軍での鞭打ち刑の実態
★艦隊回し鞭打ち刑★
軍艦における処罰は、艦長自身が判事かつ陪審員となって決定され、通常、月曜日の朝み
せしめのために、乗組員を全員集めて、ボースンの手で行われた。
海軍の処罰のなかで、もっとも残酷で野蛮な刑罰だといわれた艦隊回し鞭打ち刑は、18世
紀に入り死刑が次第に実施しえなくなるなかで、艦長が大いに用いた処罰であった。ロイド氏
によれば、その最初の例は1698年に発生した。2人の下士官が反乱計画書をかくし持ってい
た罪に問われ、「彼らに支払われるべき賃金をすべて没収し、ロチェスターからギリングハム
に停泊している全艦の舷側で、各6回、鞭打ちする」という判決が下された。オーストリア継承
戦争中(1740−48年)、100回鞭打ちよりも、この鞭打ちが20回も行われた……すべての
軍艦のリギンには、その処罰に立合うために人があふれ、受刑者を足場に縛ったボートが横
付けされると、軍楽隊が放逐曲(rogues march)を鳴らし、ボースンの助手がその側に行って、
所定の回数の鞭打ちを執行した。この処罰で、その男はほとんど廃疾になったとのべている
(同240−1ページ)。
ハゲット氏は、鞭打ちの規定回数は500回とした上で、目撃者の手記を引用している。仲間
の1人が、乗船している軍艦から5シリングを盗んだため、艦隊回し鞭打ち刑を受けた。不幸
な受刑者はポートに据えられ、艦から艦へと漕ぎ回って各艦の舷側で別々の船員から、同じ回
数だけ鞭を食らった。苦痛をやわらげようと処罰を受ける前に、ラム酒をほぼ1瓶飲んでい
た。たった2艦回ったところで、受刑者が酔払い出したという声を聞きつけた艦長は、酔いがさ
めるまで鞭打ちを中止するよう命令した……その男の背中はふくれあがって青黒くなっていた
が、青い薄紙に酢をひたし、その何枚かが張り付けられた。すると、男は悲鳴を上げて、気を
失ってしまった。自分の艦で気を取りもどしたところで、拷問は再開された(同57ページ)。
★海中突入刑★
さらに、海中突入刑や船底くぐり刑をみると、メンマストのヤーダムからの海中突入刑は、受
刑者の胴と尻をロープで縛って、ヤードの先端につるし、そこから一気に海中に落とすやり方
で、3、4回続けて行われた。そして、その罪が重い場合、受刑者は船底くぐり刑となり、船底の
キールの下を潜らされた。海中に潜っている時、大砲が頭の上で適宜、撃たれた。それは砲
撃の振動で受刑者が気を失わずに潜らせ、また乗組員が処罰を見て、慎重に働くよう注意を
呼びさますために撃たれた(同40ページ)。
ロイド氏は、普通の鞭打ち刑について、次のように書いている。ギャング・ウェイまたは後部
上甲板にかけられたジャコブ・ラダーのあるところで、鞭打ちが行われた。それをみせしめとす
るため、「総員、処罰に立合え」という命令が、ほとんどの場合に出された。士官はスバーデッ
キに、乗組員はメンデッキに、海兵はクオータデッキに、集められた。使われる鞭は、1インチ
ほどの太さがあり、1フィートの長さの、荒織りの布でおおわれた棒についた9尾のねこ鞭(cat
-o-nine-tails)であった。受刑者は、胸をむき出しにした上で、手すりに手首と膝を縛り付けられ
た。ボースンの助手が、鞭打ちを命じられた。6回または12回打つと、他の助手がそれをつづ
けるため呼ばれた。
艦長のやめろという言葉があるまで、打ちつづけられた。艦長のなかには気まぐれに、1ダー
スから5ダースまで打たせたが、通常3ダースであった。艦長が、その男に悪意を抱いて毎日
鞭打ちすることがあっても、咎められはしなかった。暴君の艦長はしばしばもっと強く鞭打ちす
るよう、ボースンの助手に命じた。そうしなければ、その助手が鞭打たれることになった。
こうした処罰は軍法会議で審議されず、艦長の裁量として実施される場合が、やはりあった
(同241ページ)。
その他にいろいろな中世の慣習法があるが、それについてフェイル氏は、全体として次のよ
うな評価を与えている。「オレロン海法では、『船員間の平和を保持して彼等の争いを調停する
こと』をもって、船長の義務と定めている」ように、「船長は同輩のうちの一指導者にすぎず、彼
と乗組員との間柄は、どちらかと言えば独裁的よりも親爺的であった」。「地中海の諸海法によ
ると、窃盗、口論、その他の犯行をなした者は解雇処分に附する旨を規定しているけれども、
それ以外に規律強化に関する規定はほとんど見あたらない。また、笞<むち>刑を認めてい
る海法にあっても、時々、流血にいたらざることと定めており、したがってそれは18世紀の海
上笞刑とは大いに趣きを異にしている」。そして、「概括的に言って、これら中世地中海諸国の
海法は、海員の権利に関する規定において、また海員の疫病或いは死亡のごとき不慮の事
故に関する規定において多大の考慮を払っており、この点18世紀さらには19世紀前半期の
船舶における条件よりは明白に進歩を示していた」(以上、同63−5ページ)。
このように、中世の船にあっては、船長の権威は認めてはいるもの〆、船内規律は乗組仲
間の自主規制でもって維持されていたといえる。後世とちがって、そうしたいわば民主的な方
法が事足りたのであるが、それは「船員自身がしばしば船舶または積荷の持分所有者(part-
owner)であって、同船している誰とも同等の社会的地位を持っていた。当時の航海は、全く実
地の経験に基づいて行なわれたため、雇われた海員といえども、仕事について船長とほぼ同
じくらいに弁<わきま>えていた」(フェイル62ページ)からである。しかし、海運経営が小生産
者の共同経営から資本経営となり、いまだ賃金労働者としての訓練を受けるにいたっていない
船員が増加してくると、そうした民主的で穏健な方法では事足りなくなってくる。そのなかでも、
いやいやながら海軍に強制徴発された船員が乗る軍艦の船内規律は、中世さながらの残虐さ
をみせることになる。
なお、小門和之助氏は「中世紀におけるヨーロッパ船員社会」(『船員問題の国際的展望』、
日本海事振興会、1958年)で、船員労働の慣習法を詳しくまとめている。
2 海軍の典型的な処罰・鞭打ち刑
★中世的な処罰★
イギリスにおいて、海軍が不評判であった1つの理由は、船内の規律が厳しく、それに違反
すると酷い処罰を受けることにあった。1530年ごろへンリー8世が公布した海軍規律令によ
ると、船内で殺人を犯した場合、その者に偉業があっても、その者を生きたまま死体に縛って
海中に投げ棄てる……船内で艦長を武器で突き刺した場合、その者の右手を切り落とす……
船内で自分の当直中に居眠りした場合、……4度目には……その者をビール1缶、肉1片そし
て磨いだナイフと一緒にカゴに入れ、バウスプリット(斜檣)に吊し、そこで餓死するか、それを
切って海中に入水をするかを選ばせる……船内で酔って、船の食事を食べなかった場合……
艦長は鉄製の足かせで縛って入牢させ、その者がみずからの罪を悔いるまで放っておく……
となっていた。これらは、中世の処罰を踏襲するものであった。海軍の規模が大きくなり、「世
の中のくず」が多数、海軍に徴発されて来るようになると、処罰はよりいっそう激しいものとなっ
た。
1661年法は、いままでの犯罪や処罰を集大成したものであるが、39条のうち25条は死刑
と規定していた。殺人、横領、間謀<スパイ>、脱走、反乱、士官殴打、放火、強盗または当
直中の常習居眠りは、死刑であった。悪口、泥酔、その他公序良俗に反する行為は、鞭打ち
または罰金となっていた。ただ、死刑については、いままで艦長や司令官が執行していたの
を、海軍裁判所で裁決することにした。
1731年に海軍本部規則が制定された。それは、いままでの処罰を繰り返したものであった
が、それを軽減しまたその手続きを詳細に定めた。死刑といった処罰は、次第に実行されなく
なったが、鞭打ち刑は19世紀中頃まで多くの軍艦では日常行事であった。
★船底くぐり刑★
海軍における著名な処罰を挙げれば、次のようなものがあった。なお、海軍における絞首刑
は、ヤーダム(桁端)に吊した。
1 船内餓死刑、前述通り。
2 くすぐりの刑(tarring and feathering:全身にタールを塗りつげ、その上を羽毛で覆う刑)
3 海中突入刑(ducking at the yard arm:ヤードの端に吊し、そこから一気に海中に落とす
刑)
4 船底くぐり刑(hauling under the keel:船員を縛って、船底を左舷から右舷へくぐらせる刑)
5 艦隊回し鞭打ち刑(fogging round the fleet:船員が艦隊の各艦を回って鞭打たれる刑)
などであるが、日常的に数多く行われた処罰は、鞭打ちであった。非公認の鞭打ちとして、次
のような処罰もあった。その1つは、
6 並び打ち刑(running the gauntlet)で、結び目のある、いらくさまたは細引きで武装した全乗
組員を一定の間隔で並ばせ、その列の間を裸になった男を走らせ、鞭打つやり方であった。
それは1806年に禁止された。他の1つは、
7 藤の鞭打ち(starting with a rattan)で、当時は荒あらしい時代であったので、それはひん
ばんに用いられた処罰であった。横暴なボースンや見習士官に打たれると、命を落としかねな
かった(以上、ロイド241ページ)。
3 海軍での鞭打ち刑の実態
★艦隊回し鞭打ち刑★
軍艦における処罰は、艦長自身が判事かつ陪審員となって決定され、通常、月曜日の朝み
せしめのために、乗組員を全員集めて、ボースンの手で行われた。
海軍の処罰のなかで、もっとも残酷で野蛮な刑罰だといわれた艦隊回し鞭打ち刑は、18世
紀に入り死刑が次第に実施しえなくなるなかで、艦長が大いに用いた処罰であった。ロイド氏
によれば、その最初の例は1698年に発生した。2人の下士官が反乱計画書をかくし持ってい
た罪に問われ、「彼らに支払われるべき賃金をすべて没収し、ロチェスターからギリングハム
に停泊している全艦の舷側で、各6回、鞭打ちする」という判決が下された。オーストリア継承
戦争中(1740−48年)、100回鞭打ちよりも、この鞭打ちが20回も行われた……すべての
軍艦のリギンには、その処罰に立合うために人があふれ、受刑者を足場に縛ったボートが横
付けされると、軍楽隊が放逐曲(rogues march)を鳴らし、ボースンの助手がその側に行って、
所定の回数の鞭打ちを執行した。この処罰で、その男はほとんど廃疾になったとのべている
(同240−1ページ)。
ハゲット氏は、鞭打ちの規定回数は500回とした上で、目撃者の手記を引用している。仲間
の1人が、乗船している軍艦から5シリングを盗んだため、艦隊回し鞭打ち刑を受けた。不幸
な受刑者はポートに据えられ、艦から艦へと漕ぎ回って各艦の舷側で別々の船員から、同じ回
数だけ鞭を食らった。苦痛をやわらげようと処罰を受ける前に、ラム酒をほぼ1瓶飲んでい
た。たった2艦回ったところで、受刑者が酔払い出したという声を聞きつけた艦長は、酔いがさ
めるまで鞭打ちを中止するよう命令した……その男の背中はふくれあがって青黒くなっていた
が、青い薄紙に酢をひたし、その何枚かが張り付けられた。すると、男は悲鳴を上げて、気を
失ってしまった。自分の艦で気を取りもどしたところで、拷問は再開された(同57ページ)。
★海中突入刑★
さらに、海中突入刑や船底くぐり刑をみると、メンマストのヤーダムからの海中突入刑は、受
刑者の胴と尻をロープで縛って、ヤードの先端につるし、そこから一気に海中に落とすやり方
で、3、4回続けて行われた。そして、その罪が重い場合、受刑者は船底くぐり刑となり、船底の
キールの下を潜らされた。海中に潜っている時、大砲が頭の上で適宜、撃たれた。それは砲
撃の振動で受刑者が気を失わずに潜らせ、また乗組員が処罰を見て、慎重に働くよう注意を
呼びさますために撃たれた(同40ページ)。
ロイド氏は、普通の鞭打ち刑について、次のように書いている。ギャング・ウェイまたは後部
上甲板にかけられたジャコブ・ラダーのあるところで、鞭打ちが行われた。それをみせしめとす
るため、「総員、処罰に立合え」という命令が、ほとんどの場合に出された。士官はスバーデッ
キに、乗組員はメンデッキに、海兵はクオータデッキに、集められた。使われる鞭は、1インチ
ほどの太さがあり、1フィートの長さの、荒織りの布でおおわれた棒についた9尾のねこ鞭(cat
-o-nine-tails)であった。受刑者は、胸をむき出しにした上で、手すりに手首と膝を縛り付けられ
た。ボースンの助手が、鞭打ちを命じられた。6回または12回打つと、他の助手がそれをつづ
けるため呼ばれた。
艦長のやめろという言葉があるまで、打ちつづけられた。艦長のなかには気まぐれに、1ダー
スから5ダースまで打たせたが、通常3ダースであった。艦長が、その男に悪意を抱いて毎日
鞭打ちすることがあっても、咎められはしなかった。暴君の艦長はしばしばもっと強く鞭打ちす
るよう、ボースンの助手に命じた。そうしなければ、その助手が鞭打たれることになった。
こうした処罰は軍法会議で審議されず、艦長の裁量として実施される場合が、やはりあった
(同241ページ)。
4 厳罰の時代背景とその減少
★強制徴発の結果★
現代からみれば、イギリスの帆船時代の海軍の処罰は、きわめて残酷なものであった。海軍
が、なぜそのように残酷であったかについては、まず当時の社会はまだまだ封建時代の習慣
を身につけており、主人は召使に平手打ちをくわしたし、また雇主は使用人を鞭で打つことも
まれではなく、学校でも鞭打ちも教育方法であったし、国家も放浪者に焼印を押したり、鞭打ち
をしていた。そして、ロイド氏は「強制徴発の結果、雑多な人びとが乗艦しているため、規律を
厳しくせざるをえず、サディストになる誘惑も大きかった」(同242ページ)とのべているように、
海軍の強制徴発が貧民の強制労働の重要な方法として実施されていたからにほかならない。
それでも時代が下がるにつれて、死刑といった処罰は重罰にかぎってしか行われなくなった。
1731年に制定された海軍本部規則は、それまでの軍艦での処罰を整理するとともに、艦長
は、「海上での古来からの慣行に従い、ねこ鞭による裸の背中の鞭打ちを12回以上命ずるこ
とはできないとし、さらにその過失が厳罰に値しても、違反者は軍法会議に呼び出されるまで
監禁しておく」という規定になった。こうした規定は、おおむね無視された。怠け者、泥酔者、士
官嘲笑者、利敵行為者には3、4ダースの鞭打ちが行われていた。
★横暴艦長の裁判★
それでも、艦長の横暴や残忍に対する批判が高まり、艦長が裁判にかけられる例も出て来
た。その例をあげると、1808年末に、東インド艦隊の司令官は、ボンベイにいるネレイド号の
乗組員から請願書を受取った。それには、「ロバート・コルベット艦長の指揮のもとで、いままで
経験したこともないような苛酷な使われ方で働かされ、ささいなことでもその気まぐれな感情を
むき出しにして、大きな棒でわれわれをぶった」と、不満がのべられてあった。
マダガスカルで反乱が起きたが、それ以前に23人が脱船していた。反乱は鎮圧され、180
9年軍法会議が設けられたが、それが起きた状況が証言により確認されたため、1人が絞死
刑、2人が有罪になっただけであった。
同年2月6日、コルベット艦長の軍法会議で、その詳細があきらかになった。起訴状によれ
ば、「同艦長は他艦では窃盗を罰する時に使う習慣になっていたねこ鞭を使ったばかりか、肌
がむけたところで塩漬ピクルスを背中にかけたり、……普通使ってはならないとされている棒
切れでぶっていた」。法廷は残忍の 容疑が部分的に証明されたとして、戒告処分を勧告した
(ロイド243−4ページ)。
1835年、議会は海軍に処罰の報告書を出すよう要求した。それにともない鞭打ち刑も減少
して行き、1861年には1000件、1878年には2件になった。最後の鞭打ちは1880年に実
施されたことになっている。しかし、海軍では、鞭打ちは公的には廃止されなかった。それはさ
ておき1862年、海軍はいままでの残虐な処罰にかえて海軍刑務所を設置し、悪質な違反者
を厳格な条件のもとで監禁することとした。また、海軍から追放して市民刑務所で懲役刑にし
たり、あるいは艦内の監房に押し込める判決が出される場合もあった。さらに、艦内での処罰
は、従来罪滅ばしとして行われていた不潔で不快な作業と同じものになっていたが、若者には
竹鞭で尻を数回打つ判決が出されることもあった(ハゲット87ページ)。
1866年に海軍規律法が制定され、いままでの中世的な規律維持をあらため、それを人間
的なものにし、軍法会議の手続きを改革したり、懲罰にいろいろな制限を加え、艦内における
独断的な暴君を押えた。
5 商船における船員の処罰
★慣習としての処罰★
キッチェン氏は、イギリス商船における処罰の法的根拠について、「1700年私掠法は脱船
者の賃金は没収するという規定を設けていたし、1729年法は脱船者の逮捕と送還また拘禁
を認め、さらに休暇でなく怠業した場合、賃金2か月分の罰金としていた。こうした措置は18世
紀に通過した法律のなかにも再掲されている。それらすべてにわたって注目すべきことは、船
員は処罰を加えられる前に、弁明する機会があたえられていたことである。
……1824年以降になると、ストウェル卿によれば『とんでもない不正行為があった場合で
も、非行船員に体罰を加える権限を商船の船長にあたえるかどうかについて、激しい論争が
あった』とのべている。彼は、翌年、他の事件について『海上職務は多くの人びとの生命や運
命を左右するので、身体に危害を加えてでも、規律を維持することは不可欠である』と付け加
えている。主人が召使にふるっている慣習上の権限はさておき、鞭打ち刑に関する法的根拠
は商船については特に定めていなかった」(同553−4ページ)が、それが行われていたとまと
めている。
★ささいなことで処罰★
それでは、商船での処罰の実態は、どうなっていたのであろうか。ハゲット氏は、商船の船長
は軍艦の艦長のように独裁者になることはできなかった。彼らはイギリスに帰った時訴えられ
た。それに反論したとしても、損害はまぬがれえなかった。それでも、ある種の体罰は規律を
維持する方法として、商船でもいつでも用いられていたという。
トーマス・ガーロック船長は、1700年中央刑事裁判所で、数人の乗組員を鞭打ったところ反
乱を起され、他の乗組員や船客とともに小さな島に置き去りにされたと証言した。
船長は懲罰のため、ハム、エッジル、ウェザエルをこらしめたことを認めた。エッジルは操舵
手であったが、箱を破って約12ポンドの白砂糖を盗んだ。ハムは豆についた緑青に文句をい
った。船長は料理室に出向いた鍋のふちから大量の緑青を取り除いた。船長は日本の竹でハ
ムを鞭打った。ウェザエルはボースンをなぐったので鞭打たれた。
そうした場合処罰を行わなくても、船内の秩序は維持されたし、混乱に陥るようなことはなか
った(同32ページ)。
さらにつづけて、商船の乗組員に対する処罰がいつも軽かったわけではない。多くの船長が
故意に残酷でサディスティックであったことは、誰がみても公平な船員や観察者が書き残して
いることで、十分にあきらかである。「わたしの知っている船長は悪意をみなぎらせて、小股す
くいを掛けたり、陸ではいえないようなくだらないことをいったりした。そして、乗組員にボートを
降させて、船尾から半マイルのところから漕がせたりした。その途中で出帆して、どんどん先に
行ってしまい、乗組員に5、6時間も漕がせたり、日没前まで捨ておいて引上げたりした」。
また、ささいなことでも、鞭打たれた。コックは、生木以外にかまどにくべるものがなかったの
で、食事を時間通りに作ることができなかった。そのことでコックは船長に馬用の鞭でまともに
打ちすえられた(同32−3ページ)。
★乗組員に訴えられる★
鞭打ちで、士官が訴訟を起こされ、罰金を払わせられた例がある。例のバーローが主席士官
として乗船していた船が入港すると、ある船員の妻が訪船してきて、夫の死についてバーロー
をなじった。藤の束の積み付けが悪いにかかわらず、それが間違っていないと抗弁したので、
バーローはその男を藤のむちで打った。そうした仕打ちをされて男が苦情をいったり、船医に
診断してもらったこともなかった。病気にかかったのは、それから10か月もたってからであっ
た。船員の妻の弁護士は、過失致死罪が証明されれば左手にM印(murdererのMか、引用者
注)の焼印を押し、さらに現金や財産を没収することができるといっていた。バーローは法廷で
争うことを望んだが、親せきがこんな事件で名前に傷つけることはないと、彼を説得した。そこ
で、彼は50ポンド出すことにしたが弁護士に拒否された。さらに5ポンド引き上げるといったと
ころ、示談が成立してしまった(コース138−9ページ)。
また、時代はかなり下るが、1867年、ロックスリー・ハル号の船長バーンズは、アレンという
船員を治安判事パゲット氏のところに連行し、公海上で主席士官に暴行を加え、命令にまった
く従わず、命令を拒否しつづけたため、処罰したと報告した。他方、アレンは手錠をはめられた
上に、不法な暴行を受けたとして、バーンズ船長を告訴した。治安判事は船長の陳述は完全に
立証されたと判断し、アレンに職務拒否について禁固2日、暴行についてさらに1日という名目
的な処罰を言渡した。他方、バーンズ船長は罰金にせずに監禁したとして、22日間の禁固の
判決を言渡した。この事件を憤慨する声が、ロンドンの海運界に巻き起った。先任船長の大物
代表がデイズレーリ首相に面会し、不当判決に抗議を表明した。内務大臣が仲裁に入り、バ
ーンズ船長は釈放され、治安判事は更迭されたという(同236ページ)。
6 海運法、処罰規定を設ける
★処罰の合法化★
商船においても、軍艦ほど残酷でないとしても、かなり激しい体罰が行われていたのである。
それが、海軍のように一定の秩序のもとで実施されていないところに、1つの問題があった。次
のような法律が制定されたことで、船長の気ままな横暴は抑えられたが、逆に船長に処罰の
権限を法的にあたえ、それを通じて船員に雇用契約の履行を強制し、また船員の反抗を抑え
るのに役立てられることになった。
キッチェン氏によれば、「その時代も、普通のイギリス刑法がイギリスに登録している商船に
適用されていたことはいうまでもない。それにもかかわらず、船員に関係のある19世紀の法
律は、昔からの船員に対する処罰の伝統を受け継いでいた。1844年の一般商船船員法は、
船内で犯された暴行や殴打について陸上で効力のあるイギリス法にしたがって、即座に処分
することができると規定し、そして窃盗については起訴すべきであるという特別の規定も設けて
いた。
当時、その法律は脱船者に対する拘禁、休暇でない怠業に対する賃金の減額または没収に
関する規定を、繰り返し設けている。しかし、規律制度の大変革が、1850年、54年に制定さ
れた精巧な法律のなかで行われることになった」。
「1850年海運法は……第1に、適格証明書の採用にともない、この法律に違反した士官、
『不適格あるいは洒びたり、暴君癖により義務をはたしえない』士官の証明書の取消しまたは
一時停止を行う権限をあたえた。
第2に、休暇でない脱船や怠業の処置について、詳細な規定を設けるよう示唆している(これ
については次項、引用者注)。
第3に、乗船契約書の形式は、……それを適用してよいと商務省が認可しかつ雇用者と被
用者がそれを採用することに合意したものでなければならないとした。
第4に、この法律は船内で適当な処罰を実施してよい特殊な刑罰について、数多く規定して
いる。船舶を直ちに喪失、破壊したりあるいは大きな損害を及ぼすような職務怠慢、また船内
の人間の生命または身体を危険にさらすような職務怠慢についてもふれている。……
最後に、船長は船員の素行について解雇証明書に裏書きし、航海終了時に報告を提出する
よう定めた」(キッチェン553−5ページ)。
★船員の猛反対★
ところが、この1850年法が契機となって、北東海岸のいくつかの港でペニー・ユニオンと呼
ばれる労働組合が結成され、1851年1月にはサンダーランドでそれに盛られた船内規律条
項に反対する大規模な抗議集会が組織された。
それら条項は、命じられた時間まで在船する、休日が終れば帰船する、船長や士官に横柄
で侮辱的な言動をはかない、乗船者または船の関係者にストライキや暴行を働いてはならな
い、けんかをしたり、そそのかしたりしてはならない、言い争ったり、無作法な言葉を使っては
ならない、船内に強い酒を持ち込んだり、飲んだりしてはならず、また酔払ってはならない、見
張り中に居眠りしたり、はなはだしい不注意をおかしてはならない、命じられた時間以外は灯
火を消す、メンデッキ以外で喫煙してはならない、持ち物を持ち出し、開け拡げて通気をするこ
とを拒んではならない、命じられた時間に就寝しなければならない、日曜日は仕事や病気でな
いかぎり礼拝式に参加しなければならない、礼儀に反する礼拝式を行ってはならない、日曜日
には清潔にし、ひげをそり、体を洗うこと、そして衣服を洗濯するという内容が含まれていた。
こうしたことを守らないと軽罪となった。そのいくつかは1850年法以前から存在したが、あれ
これと織り込まれたことが船員を怒らせてしまった。
この法律は、「船員を奴隷に退歩させ、船員を脅迫、威圧し、船員から苛酷に税金(海運局
での雇人雇止手数料、引用者注)を取り立てる法律だ」といって反対していた。こうした不満に
加えて賃上げを要求した。サンダーランド、サウスシールズウエストハートルプールやブライス
では、それら要求を獲得するため、ストライキに入った。3、4週間たって、関係の港の船主は
要求通りの賃金を、船員に支払うことに合意したが、1850年法は反対通りにならなかった。
船員たちは、大きな労働組合を組織することに決し、組合員は毎週1ペンス拠出することにし
た。組合支部が、北東海岸の全部の港やハル、ヤーマス、ピーターヘッド、リバプールに設置
された。ペニー・ユニオンの代表はロンドンの商務省に出向き、自分たちの言い分を申し立て
ることになった。商務長官は新法は公正な試みだと主張したが、ペニー・ユニオンの嘆願は受
け入れられ、22か条の規則はその効力を一時停止され、以前の状態に戻ることになった。ま
た、海運局での雇人・雇止手数料は、それを引き下げるという譲歩がえられた(コース222−
3ページ)。
1880年になると、休暇でない脱船や怠業に対する逮捕は廃止された。その代りに、そうした
船員に罰金や没収の処罰は行うものの、退船の意思を48時間前に通告すれば逮捕はまぬ
がれることになった。それは単なる法律の変更であって、現実には脱船者は船主の代理人に
逮捕され、そして彼らが契約をやりとげるよう、船に連れ戻されていた。また、この規定は、雇
用契約の履行の強制になっても、「その契約が奴隷契約に転化するおそれはない」とみていた
裁判所の見解と反するものであった。そのため、1894年統合法はこの改正を否定した。それ
により1894年の状態が、その後1970年海運法が制定されるまで、80年間も続いたのであ
る(キッチェン555ページ)。
★イギリスに習う日本★
明治政府は、早くも1876(明治9)年に西洋形商船船長、運転手及機関手試験免状規則、
1879(同12)年に西洋形商船海員雇人雇止規則を制定している。それらはイギリス海運法
に学んだとされる。後者には、次のような規定があった。
第10条 船長ノ指図二背ク者、許可ヲ得スシテ上陸シ又ハ許可ノ時限ヲ過キテ帰船スル者
(第11条ノ脱船者ニアラス)、本務ヲ怠ル者、喧嘩口論ヲナス者、銘打スル者、私二銃器刀槍
或ハ酒類ヲ船中二貯フ者ハ、毎日其給金3日分ヨリ多カラサル額ヲ違約金トシテ雇主之ヲ収
メ、且其銃器刀槍或ハ酒類ヲ取上クルヲ得へシ
第11条 船中二於テ徒党ヲ諜ル者、船長ヲ劫カス者、脱船スル者(雇入期限内二逃亡スル者
ヲ云フ)ハ其事情二因り百日以内ノ懲役二処ス、若シ船体船具ヲ毀傷シ又ハ載貨ヲ私用スル
者ハ、其実価ヲ償ハシムルノ外、本条2依テ其罪ヲ科スヘシ
その後、1899(明治32)年に船員法、1937(昭和12)年に改正船員法、そして1947(同
22)年に戦後船員法が制定されているが、明治初めの雇人雇止規則の意図が貫らぬかれて
いるばかりか、船内規律規定はさらに詳細を極めるようになり、罰則はさらに強化されて行っ
た。戦後船員法は、たとえば「上長の職務上の命令に」従わなかったといった軽罪に対する懲
戒を上陸禁止や戒告にかぎり、監禁や加役、減給を廃止したが、なお「上長に対し暴行又は
脅迫したときは、3年以下の懲役……」、人命、船舶、積荷が危険になっている場合に、船長
の許可なく船舶を去ったり、必要な作業の命令に服従あるいはそれに従事しなかったとき、あ
るいは外国において脱船したとき、1年以下の懲役と規定している。
イギリスにおいても、日本においても、資本主義海運が発達するにつれて、法制上の船内規
律規定は強化されている。しかし、それとは逆に、船員の規律違反は減少している。その減少
は、法律が強化されたから減少したのではなく、船員が賃金労働者として暴力の規律によらず
とも飢えの規律で訓育されたからである。それにもかかわらず、なぜ法律が強化されたかであ
るが、それは船員がいままでのように個人的で一時的な反抗をやめ、海員組合という労働組
合を作り、組織的に反抗するようになったからである。そして、それ以前とはちがって賃金労働
者となった船長を通じてしか、船内規律を維持できなくなり、それに成文化した法的権限を与え
る必要が生じたからである。いわば、資本家の恐怖の増大のあらわれであった。
 ホームページへ |
 目次に戻る |
 |
 |