 ホームページへ |
 目次に戻る |
| |
船員は、その労働や生活が決してなまやさしいものでないことは良く承知していたが、楽しみ
を奪われたなかにあって、食事そして酒は船内では満たされない欲望のはけ口であった。それ
だけに、食事に対する不満はいつもつのらざるをえなかった。船員は、陸の人間とちがって大
酒を飲み、まずかったとはいえ大量の肉を食べていた。
1 帆船時代の船員の不満
★大航海時代前の食卓★
コース氏は、近世初期の状態について、次のようにまとめている。「14世紀の船員は、おそ
らく、日曜日、火曜日、木曜日には生肉が支給され、他の日は濃いオートミールだけですまさ
れていたようである。そうだったとしても、出帆してしまうと、船内でどんな生肉が支給されたか
は想像にあまりある。濃いオートミールは8世紀から10世紀にいたるバイキング時代にまでさ
かのぼることができるが、20世紀までの帆船の当り前の食事であった。中世の船では、船長
と士官や船員は同じテーブルで食事を取っていたし、階級や等級によって食事に差別をつける
ようなことはなかった。
15世紀、塩漬け肉、塩漬けまたはくん製の魚、パンやビールが、船員の海上での食品にな
った。ぜいたくは入港中にできるだけであった。1487年、マーガレット・セリイ号がロンドンに
入港していた時、乗組員は週3回鮮魚また週1回生肉が支給されていた。卵とバターが週1回
まとめて支給され、また小量の紫貝やいちじく、干しぶどうが増配されていた。
イギリス船の食事も次第に改善されて行った。1545年、ベーコン、えんどう豆、塩入りバタ
ーそしてコショウが出されるようになったが、それはそれら日用品を取引する船に限られてい
た。それでも、イギリス船で働く船員は他の国の船より良い食事をとっていたといわれる。この
時代のあるスペイン大使は、イギリス船は乗組員に支給する食料を大量に積込むため、荷物
はそれと同じくらいしか積んでいなかったと報告している」(同26ページ)。
★大洋航海で条件悪化★
ところが時代が下がり、イギリス船が地中海や北海から大西洋に乗り出して行くにつれて、
食事の不満は高まって行った。
アメリカ植民地ニュー・プリマスの建設者として有名な艦長フェルデナント・ゴージス郷は、17
世紀前半の船員の不満を、次のように列挙している。
第1には、われわれは上陸して気分を一新する機会をあたえられないまま、艦内に犬のよう
に閉じ込められ、扱われている。
第2に、寒さをしのいだり、健康を保つために衣服を手に入れるだけの蓄えもない。ましてあ
われな妻や子供を助けようもない。
第3に、病気に見舞われた時、体に元気をつける新鮮な食料や、治療に役立つ薬を買える
だけの手当も支給されていない。
第4に、何人かの病人は、陸上の病院に入れられたが、何の面倒もみてもらえないので死に
かかっており、足指や足首が腐って落ちかかっている。それがあまり匂うので、その部屋には
誰も入ることが出来ない。
第5に、艦内に積み込まれている食料は適当でないだけでなく、それだけでは生きていけな
い。
第6に、そうした扱われ方をされるなら、吊るされる方がましだといっている(ロイド71ペー
ジ)。
18世紀末における軍艦の乗組員の不平を、ロイド氏は次のようにまとめている。
「第1に、彼らの賃金は家族を養えないほど安いと、不満を鳴らしている。
第2に、事務長に食料1ポンドにつき2オンスの手数料を取られること、そして入港中でも新
鮮な野菜や肉がないことに抗議している。
第3に、病気になった時、丁寧に治療してほしいと要求している。
そして、最後にわれわれを、自分たちの国の防衛のために立ち上がっている男たちと認め、
われわれが軍艦で義務を果たし、海上から帰って来た時、入港中、さらに陸上で純粋な自由
を味わえる許可と機会をあたえてほしい。要望の多くは、(1797年の大反乱があってのことだ
が、引用者注)議会の法律や海軍本部の規則で受け入れられたが、最後の要望は認められ
なかった」(同247−8ページ)。
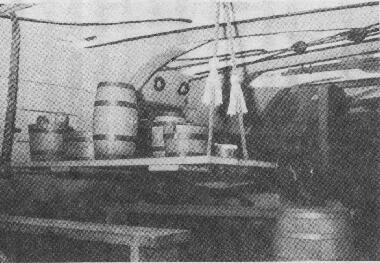 |
| 4人から8人で使用 |
★食料の欠乏と劣化★
これら不満は、商船乗組員にとっても同じで、それらのなかで粗末な食事と悪臭の飲み物の
2つは、今世紀まで続いている船員の最大の不満であった。
長期航海になって食料が欠乏してくると、6人の水夫は4人分の支給量で生きていかねばな
らなかった。探検航海では、乗組員は上陸してネズミ、猿、鳥をはじめペンギンさえも捕まえね
ばならない時もあった。食料の質はいつもどうにもならないものであった。馬肉は牛肉の代用
物であった。人の爪や馬のひずめは良い道具として用いられた。
ビールは気が抜けて酸っぱくなり、チーズはモスリンで包まれてはいたが固くなっていた。水
夫はそれでモデル・シップを作った。それが軟らかい時は蛆がわいていた。バターは木箱に入
れられていたが腐って匂っており、パンは伝統的に堅パンだった。船のビスケットは鉄のように
固かった(ハゲット10−1ページ)
バーローは、軍艦より商船を好んだが、それでも不満があった。商船は1人1日当たり1クオ
ートの水を積み込むよう義務づけられていた。それがなくなり、雨水を貯めることになったが、
それほど降らなかった。目的地の半分にもならない地点で、大変なことになってしまった。黄道
に入って気温は上がる一方であった。食料は余裕がなくなり、1人あてで7日分の5ポンドのパ
ン、1週問のうち、4日分の小さな干し魚、スプーン2杯の油、そして少々の塩漬け牛肉や豆、
かびた米が残っているだけであった。
それは軍艦で経験したよりも、はるかに厳しいものであった。そうしたことは、イギリスの商人
や船主にとって、その当時当たり前になっていた。それでもって他の国民と競争し合っていた。
彼らの船を出帆させる時、食料や飲み物を順調な航海日数に必要な量以上に積み込もうとは
しなかった。そこで、航海距離が伸びたり、向かい風に出合うと、船員はあわれにも腹をすか
し、飢えねばならなかった(同30ページ)
なお、帆船時代、航海中、カツオ、マグロ、サメなどを釣っていたし、北大西洋横断中、ニュー
ファンドランドでタラを採取している。また、にわとり、豚なども飼っていたとされる。
2 食料積込量1肉1日1ポンド
★1日1ガロンのビール★
イギリスの海軍では、17世紀から200年間、普通の軍艦の1人当たりの食料は変化せず、
隔日に1ポンドの塩漬け豚肉または2ポンドの牛肉、1日当たり1ポンドのビスケット、1ガロン
のビール、1週間当たり2パイントの豆、3パイントのオートミール、8オンスのバター、1ポンド
のチーズであった(単位換算は、別表注参照)。
南方航路では、ビールは長期に保存出来ないので、1パイントのワインまたは2分の1パイン
トのブランデー(ラム酒もあった、引用者注)に代えられた。オートミールの代わりに米、バター
の代わりにオリーブ・オイルが支給されることもあった。
入港中は生肉が普通支給されたが、新鮮な野菜は18世紀末まで支給される規則になって
いなかった。すべての品目について、総量の8分の1は消耗または浸出するものとして、事務
長に保障があたえられていた。普通の人が陸上で食べている食料にくらべ、その内容が不均
衡であるとしても、その量に不足はなかった。なお、陸上では肉はそれほど頻繁には食べてい
なかった(ロイド254−5ページ)。
ロイド氏によれば、食料の量についてはあまり批判が出なかったが、その質については防腐
剤は塩にかぎられていたため、どうにもならなかった。さらに問題は、すぐ後でのべるように、
食料補給について不正がみられたことである。そして、船員も保守的な嗜好や偏見を持ってい
た。
「現代の感覚からいえば、船員が好んだ食事は、吐き気を催させほものであった。薄いか
ゆ、船員特有のシチュー、濃いオートミールまたはスコッチピー、肉の塊が浮いたオートミール
の煮がゆ、それには砂糖を少し入れたり、酢で味付けしたものもあった」(同255ページ)
キャベツや石けんは、人間の体には悪いと信じられていた。
| |
|
| バソ 1日当たり1ポンド ビール 1日当たり1ガロン 牛肉 火・土曜日に2ポンドずつ 豚肉 日・木曜日に1ポンドずつ えんどう豆 日・水・木・金曜日に1/2パイント ずつ オートミール 月・水・金曜日に1パイントずつ バター 日・水・土曜日に2オンスずつ チーズ 月・水・金曜日に4オンスずつ |
(左下より) 1日当たり 生肉 3/4ポンド 野菜 1ポンド |
| |
|
| 1日当たり ビスケット 1-1/4ポンドまたは柔らかいパソ 1-1/2ポンド 酒 1/8パイント 砂糖 2オンス チョコレート 1オンス 紅茶 1/4オンス 1週当たリ オートミール 3オンス からし 1/2オンス こしェう 1/4オンス 酢 1/4パイント 1日当たり(それが入手出来るかぎり) 生肉 1ポンド 野菜 1/2ポンド |
水 1日当たり3クオート パソ 1日当たり1ポンド 牛肉 日・火・木・土曜日に1-1/2ポンドずつ 豚肉 月・水・金曜日に1-1/4ポンドずつ 小麦粉 日・火・木曜日に1/2ポンドずつ えんどう豆 月・水・金曜日に1/2ポンドずつ 米 土曜日に1/2ポンド 紅茶 1日当たり1/8lオンス コーヒー 1日当たり1/2オンス 砂糖 1日当たり2オンス 酒 不支給 |
| |
|
| 1日当たり ビスケットまたは柔らかいバン 1-1/4ポンド ジャム 2オンス 酒 1/8パイント コーヒー 1/2オンス 砂糖 3オンス コーソビーフ 4オンス 普通のチョコレート 3/8オンス、そのうち溶 解チョコレート 3/4オンス 濃縮ミルク 3/4オンス 紅茶 3/8オンス 1日当たり 塩 1/4オンス 1週当たり からし 1/2オンス こしょう 1/4オンス 酢 1/4オンス (右上に続く)
|
飲料水 7ガロン 柔らかいバン 7ポンド 小麦粉 1ポンド 米 6オンス オートミール 6オンス 生肉 7-1/lポンド ハムまたはベーコン 12オンス レソズ豆、えんどう豆、そら豆など 1-1/2ポンド たまねぎ 8オンス バター 10-1/2オンス スエットおよび脂肪 6オンス 砂糖 1-1/2ポンド 赤すぐり、干ぷどうなど 3オンス 果物 6オンス ジャム 8オンス チーズ 5オンス 紅茶 4-1/4オンス コーヒー 2オンス |
| ー(Kcal) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4,791
|
158.4
|
110.9
|
483
|
647
|
19.1
|
3,682
|
3.54
|
2.89
|
17
|
| |
5,059
|
129.5
|
129.0
|
483.2
|
338
|
20.6
|
3,742
|
1.96
|
1.54
|
61
|
| |
4,225
|
134.2
|
130
|
527.5
|
444
|
26.8
|
3,223
|
1.66
|
1.62
|
93
|
| |
3,453
|
179.7
|
118.7
|
262.4
|
291
|
22.4
|
4,821
|
3.21
|
2.03
|
32
|
| |
4,268
|
179.2
|
182.5
|
495.1
|
476
|
22.8
|
4,745
|
3.02
|
1.89
|
33
|
★高熱量、ビタミンC不足★
そこで、具体的に軍艦や商品の食料表についてみてみると、別表の通りである。なお、この
食料表は、積込量と考えられる。したがって、損耗や浸出をはじめ、不正によって、その量が
全部テーブルに出たわけでない。
これら食料表について、船内給食の権威である小石泰道氏(元海上労働科学研究所主任研
究員)に分析してもらったところ、細部については省略するが、およそ次の通りであった。
まず、積込量を給与量とみなした上で、「現在のイギリスの重い労作を行う男子(18−35
歳)の1人1日当たり摂取栄養所要量(1969年)ほ、エネルギー3600カロリー、蛋白質90グ
ラム、カルシウム500ミリグラム、鉄10ミリグラム、ビタミンB1:1.4ミリグラム、B2:1.7ミリグ
ラム、C30ミリグラムとなっている。
これと比較して、エネルギーは19世紀末の帆船食料表以外はいちじるしく大きい。1729
年、1867年の軍艦食料表は特に大きいが、船内保存中の損耗が見込まれているかも知れ
ない。蛋白質は、それをかなり上回っているが、日本の現行船員法は120グラムであるので、
極端に多くはない。無機質は肉量が多いので、鉄分は十分であるが、カルシウムは不足して
いる。
ビタミンは肉量が多いので、A、B1は十分であり、B2もまあまあである。えんどう豆などはB1
対策のように思える。それに反し、Cは不足している。1729年の軍艦、19世紀末の帆船、戦
争直後の商船においては、その食料表だけでは壊血病になるおそれがある」。
つぎに、栄養バランスについて、エネルギーをどういった要素から摂取しているか、あるいは
摂取要素の相対比率はどうなっているかであるが、「食料表を年代順に計算してみると、穀類
エネルギー比は、39.5%、44.2%、48.4%、48.0%、38.0%となり、全体として低い。今日
でも欧米で問題となっているところである。
脂肪エネルギー比は、33.1%、22.9%、27.7%、31.0%、38.5%で、1867、1907年の
軍艦は適当であるが、他は高い。
動物性脂肪比は、77.0%、53.7%、56.8%、87.7%、59.1%で、1729年の軍艦、19世
紀末の帆船は高い。現在では50%以下が望ましいとされている。
動物性蛋白比は、54.9%、59.8%、61.6%、60.3%、59.5%で、現在の欧米人に比較し
て低いとみられる」。
そして、最後に、「全体として、高エネルギー、高蛋白質であり、野菜・果物・乳類の不足によ
るアンバランス、カルシウム、その他無機質、そしてビタミンCの不足がみられる。19世紀末の
帆船を除き、砂糖が多いのは食生活の違いによるが、それだけの量を当時に規定していたこ
とは、注目される。現在では、砂糖消費量の増大は低血糖症、糖尿病の増加を生むものとし
て指摘されている」と解説している。
3 食料の質の悪さと不正
★検査官がピンハネ★
食事が悪いのは、食料が航海で次第に悪くなっていくのではなく、最初から悪かった。例のバ
ーローは、1665−67年のオランダ戦争の際、フリゲート艦での経験を次のように書いてい
る。「冬の間チャタムにいたが、その時わけても霧が深く、寒く、川は2度、3度と凍りついた。
われわれもイギリスの軍艦が入港中に用いるピータ・ワーレン食を食べていた。それは検査官
が発行する支給証明書の片券を、毎週あるいは5日ごとに食料供給業者に持って行って、手
に入れる食料である。検査官と業者は本艦の事務長と組んで、所定の支給分の一部をだまし
取っていた。
それは出来の悪い小麦で作った少し黒いパンと、訳のわからない水のようになった、飲むに
耐えない少量のビールであった。船員には次のような言い習わしがあった。
"2ペックの大麦を刈り取って来て、それをロンドン橋からテムズ河口のグレープズエンドまで
船外につるし、洗ったり泳がしたりしてみよう。その後で、それを引き上げてみれば、いままで
飲んだこともないようなうまーいビールが飲める"
誰も、船員のように炎天下では激しく働けないし、長生きもできないし、酷使されもしないであ
ろう。そんなことは征服地に連れて来られた奴隷にしかやれたものではない。しかし、海軍が
あるかぎり、それもけっしてなくならない……」(ハゲット41ページ)
1586年、ドレイクのカデイス遠征では、ある船の乗組員が航海を続けることを拒否し、イギリ
スに向けて帰港するという反乱が起こったが、その原因は食事であった。
その時、彼らは、「マーチャウント艦長に要求する。艦長の名に恥じないよう、われわれを人
間として扱い、食料不足でひもじい思いをさせるな。その支給があまりに少ないので、もはや生
き延びていくことができない。夕食は4人に2分の1ポンドの牛肉一切れが支給されているだけ
だ。1週間のうち、4日は半身の干し魚があるだけで、そのはかに何もない。そのうえ、ポンプ
水よりも悪い水を飲まされている。
われわれは女王陛下の徴発隊に連れてこられ、陛下のために働いているが、ここではその
ように扱われていない。お前は、われわれの長ではなく、人でなしだ」と抗議している(同24ペ
ージ)。
★船内食料の改善★
その他、18世紀中頃以降、食事その他について、いろいろな改革が行われるようになった。
味覚の追加は、船医の必需品または病人用の特殊な食事として始まった。食事が徐じょでは
あったが改善されていったが、これは船医の提案によるところが大きかった。そのなかには砂
糖、干ぶどう、ガーリック、その他スパイスをはじめ、ランの球根で作り、壊血病に効くと考えら
れていた有名なサロップ(salop)があった。
もっとも重要な変革は、固型石けんの採用であった。それは1756年にデュボイス夫人が発
明したものであった。リンド博士(後述)やジョージ3世(治世1760−1820)が推薦していた塩
漬けキャベツあるいはピクルス・キャベツも変革であり、新鮮な野菜の代わりになった。長い歴
史のなかで、食料を完全に変化させた発明は、肉や野菜の缶詰であった。1815年、海峡艦
隊ではじめて取り入れられた(ロイド257ページ)
また、19世紀もかなりたつと、軍艦には酒保(Canteen)が次第に設けられるようになり、バタ
ー、ジャム、ケーキなど嗜好品が売られることになった。
商船も、19世紀後半に入って、食料の改善がみられるようになった。1844年議会法は、食
料の所定支給量を船長と乗組員との乗船契約書に記載させ、また乗組員3人以上から食事
の不満が税関や領事館に申し立てられると、その取り調べが行われ、量が不足していたり、質
が劣っていると、それを是正させることになった。そして、乗組員が航海中減量措置を受けた
場合1日につき3ペンス、減量が3分の1以上であった場合8ペンスの払い戻しを受けられるよ
うにした。さらに、船員は1日1ポンドという制限はあったが、それを無駄にしないかぎり、硬い
ビスケットは欲しいだけ食べることができるとも規定していた。
1854年海運法は、船長は乗組員に支給している食料の種類や量目を明示し、また所定通
り支給できるよう、あらかじめ積込み量を増量しておかなければならないと規定した。その後制
定された1892年海運法では、船舶食料検査官を配置したが、それを供給する商店まで行っ
て食料を検査する権限までは与えなかった。さらに、1906年法は食料の最低積込み量を定
め、政令でもって修正できるようにした。そして、先の検査官が必要と認めれば、船に積まれて
いる清水や食料を検査できるようにした。ただ、長期航海に従事する船の水桶、塩漬け肉、肉
や野菜を貯蔵するブリキ缶そして小麦粉やビスケットの樽は、必ず検査することになった(コー
ス217ページ)。この最低食料積込量は1939年まで変らなかったが、多くの船主は法定献立
以外の各種の食料を支給するようになっていた。
清水の確保・維持も大きな問題であったが、19世紀になって清水タンクに雨水が貯えられる
ようになり、それに過マンガン酸カルシウム(カルキ)を入れるようになっている。なお、ブリスト
ルの水は、小量の生石灰が含まれていたので長持ちし、そのおかげで船員は便秘にならず、
赤痢も防げたといわれる。
4 うさのはけ口は酒
★上陸休暇のない軍艦★
イギリスの海軍における乗組員の不満の1つとして、入港中、上陸休暇(shore leaves)がな
かったことがあげられる。海軍が、それを許可しようとしなかったのは、いうまでもなく強制徴発
でつれてきた船員が脱走してしまうおそれがあったからである。
したがって、軍艦の乗組員にとっては乗艦したかぎり、契約や戦争が終わるまで、艦内に監
禁されているのと同じ状態となった。それから逃れるには、脱走するはかはなかった。すでに
みたように、多数の乗組員が脱走した。上陸休暇に対する乗組員の不満はいつもくすぶって
いたとみられる。クロムウェル共和政のもとでは、自由の請願というかたちではっきり要求が出
されるようになってきたが、当局はそれは認めようとはしなかった(ロイド87−9ページ)。それ
でも、艦長のなかには、その許可を与えるものもいた。
ネルソン時代、ボスコーエン艦長は、ナムア号では上陸休暇を与えようとはしなかった。乗組
員はカトラスをかざし、"自由、自由、そのために闘い、それをかち取ろう"と叫んで反乱を起こ
した。それでも、翌日の朝、全員が任務につくため、帰艦していた。57人の反乱者が告訴さ
れ、そのうち3人が絞首刑、4人が500回、2人が400回、3人が300回、1人が100回の鞭
打ち刑をいいわたされ、その残りは無罪となった。上陸休暇がないことは、乗組員の不満の1
つであり、1797年の反乱の際、大きく取り上げられた。しかし、脱走の危険があったので、母
港ではどくたまにしかあたえられなかった。艦長と乗組員との間に、並み外れた信頼関係がな
いかぎり、脱走は避けがたかった。ペンローズ提督は、1797年、スピットヘッドに入港中、各
分隊を交互に上陸許可を与えたが、2人しか脱走しなかったと誇らしげに回想している。181
1年、グリフィス艦長はそれを許可したところ、300人のうち11人を失っただけだった(同245
ページ)。
 |
| (ベレンジャー画、1818年) 借金取りの老女、女に誘われている男、ガードをする男たち、 砲弾の上に腰をおろしたバイオリンをひく片足の男、 男と女が抱きあっている姿など、さまざまな風景 |
★入港船の大騒ぎ★
上陸休暇が与えられないもとで軍艦が入港してくると、船内は大変な騒ぎになったことは想像
にあまりある。船が港に着けば妻や売春婦が群れをなして、乗船してきた。下甲板では、その
すべてを書くことのできないようなショッキングで、恥ずべき状態がみられた。下劣で、不潔で、
気分の悪くなるようなありさまになっていた。いたるところで愛想のつきる会話が飛びかい、み
だらで獣のような行為や、身の毛のよだつような光景が繰りひろげられていた。そして、どんち
ゃん騒ぎ、口喧嘩、なぐり合いが起きていた。何百人の男や女が、ごちゃごちゃと同じ部屋に
詰め込まれていた(ハゲット68ページ)。
それでも、19世紀初めになって、艦長は48時間の上陸休暇を許可することができるように
なった。多くの艦長はそれを実施した。そして、1890年から水兵が規律違反を犯さないかぎ
り、無条件に3か月ごとに与えられることになった(同88ページ)。
★船方の馬鹿騒ぎ★
商船の船員は、雇われているかぎり、入港中であっても常時在船しているのが原則であった
が、軍艦のように上陸禁止ということはなく、船長の許可をえて適宜上陸していた(現在でも同
じ)。上陸するとおさだまりの仕儀となる。それについては、すでにいくつかの例が上がっている
が、さらに補足してみよう0エリザベス1世時代の船員の行状の評判は悪く、彼らの肩を持ちよ
うもないほどであった。彼らは「無知で野卑だ」と描かれている。しかし、次のようなことを勘案し
なければ、そうした評価はおかしなものとなる。船員は海上の生活から陸上の生活に突然変る
ことは、船内での拘禁状態から陸上の自由な状態に変ることである。そのため「船方の馬鹿騒
ぎ」(Jack Ashore)とさげすまれることになる。ホーキンズは、その時代の船員を「盗っ人で信
義がない」と非難している。1593年の航海に先立って、ホーキンズと治安判事は下宿屋や居
酒屋から、適当な船員を選び出すのに2日間かかっている(コース32ページ)。
例のクレーマーは、レグホーンで停泊中船員の乱闘に出合っている。それは国民性を示すも
のとしておもしろい。酔払ったイギリス人水夫が衣服を盗まれたといって、フランス人水夫とわ
めきあっているのに出合った。オランダ人船員がその様子を見ていて、そうなったのはイギリ
ス人がフランス人にやにわに切りつけたのが、事の始まりだといっていた。他の船員たちも集
ってきて、「乱闘」になってしまった。イタリアの警官が止めにかかったけれども、喧嘩は2時間
もつづいた。オランダ人はナイフ、フランス人は刀、イギリス人ははうきの柄を振り回していた。
イタリア人とスペイン人は背後から石を投げつけていた(同159ページ)。また、クレーマーがミ
ノルカのマホン港で、女を奪い合っている。クレーマーと大工が上陸したところ、町外れにスペ
イン人のいかがわしい家があり、その隣には教会があった。肌の色は黒いが、美しい若い娘
に目が止った。娘たちはすでにその夜、イギリス人士官に予約されていた。それを知らなかっ
たので、娘たちが2時間ほど遊んで行けと誘うので、それに応じることにした。運の悪いこと
に、当の士官が2時間もしないうちにやってきて、女を出せといい始めた。いさかいが起った
が、娘が止めに入ったので、クレーマーと大工は裏口から逃げ、無事、船に帰っている(同16
2ページ)。
 |
| (ハギンズ画、1855年) 妻や子供が中心に描かれている。物売人、黒人、料理人が注目される |
★軍艦での酒の支給★
イギリスの軍艦では、ビールが、早朝、昼食、午後、そして夕食時に1クオート(1136ミリリッ
トル)ずつ出されていた。軍艦の所定の支給食料のなかにビールあるいは酒が入っていること
は、いささか驚くべきことではあるが、飲酒がまん延している当時にあって、海軍が要員を確保
しておくには、それらを支給せずにはすまなかったのであろう。それをやめれば、すぐにでも、
反乱になったにちがいない。
ところが、船員はしばしば泥酔し、鞭打たれることになった。鞭打ちの半分は泥酔が原因とな
っていた。しかし、強制徴発された船員、病気におびえる船員、生活に楽しみのない船員にと
って、酒をやめるわけにはいかなかった。
イギリスでは、18世紀初頭よりビールに代えて、安価なラム酒が広く飲まれるようになった。
ラム酒は強い酒であったので、すぐに酔っ払ってしまった。1740年、バーノン提督は船員の
致命的な悪弊であった深酒をやめさせるため、2分の1パイント(142ミリリットル)のラム酒に
4分の1パイントの水で薄めたものを、午後と夜6時の2回に分けて支給するよう命令した。こ
の酒は、バーノンの外套の服地がグログラム地であったところから、グログ酒(grog)と呼ばれ
ることになった。また、グロッギー(groggy)という言葉も生まれた。
それでも深酒し、健康をそこねたり、鞭打ちの原因になるところから、さらに薄められて行っ
た。しかし、それは逆効果であった。ラム酒の支給量を減らすことは、反乱の原因になりかね
ないとみられていたので、長い間変更はなかった。
しかし、1824年には夜の支給は廃止され、遂に1850年には支給量は半分になり、4分の
1パイントとなった。それ以前の1780年にはココア、1790年には紅茶が支給されるようにな
り、酒に取り替わりつつあった。
イギリス船員の飲酒癖は、海軍仕込みであったが、商船で酒が支給されることはなかった。
東インド会社船では、軍艦の流れをくんでか、昼食時と土曜日の夜、そして悪天候時にグログ
酒が支給されていた。一般の商船でも、船長の判断で、多忙時や悪天候時に、船員を元気づ
けるため、酒を出す場合はあった。そうしたことで、商船の船員は自分の金で酒を買い込まな
ければならなかったが、おおむね乗船する前に酒に金を使いはたしていたので、船長から高
い金を払って買うしかなかった。それで、船長は結構な稼ぎをしていた。船員の飲酒癖のた
め、いろいろと失敗をやらかしていたが、海難の原因の1つにまで取り上げられる仕束であっ
た。戦前、日本の船員は上陸すれば酒を浴びるほど飲んだが、船内には酒を持ち込まなかっ
たとされる。
 |
| (G・クリクシャンク画、1815年) 大砲の側に板を降ろして酒を飲んでいる。黒人の顔もみられる。 |
 ホームページへ |
 目次に戻る |
 |
 |