 ホームページへ |
 目次に戻る |
| |
and Strait PartTrading
 |
| 東南アジア島嶼部のマラッカ海峡・ジャワ海区 |
古代アジアの海上交易において、東南アジアがどのような地位を占めたかは、それほど明白になっているとはいいがたい。それでも、ローマ、インド、そして中国を結ぶ「海のシルクロード」の中間にあって、中継交易の役割を果たしただけでなく、それ自身が犀角、象牙、玳瑁、香料などといった産品を輸出していたし、高級工芸品などを輸入していた。そのとき、扶南や林邑が中継交易都市として栄えた。しかし、それらを含む東南アジアの船(崑崙船)がどのように活躍したかもそれほど明らかでない。
東南アジアの海上交易に衝撃を与えたのは、7世紀、東では隋と唐による中国の再統一であり、西ではイスラーム世界の成立であった。それに応じて海上交易需要もいままでなく増加したであろう。その多くを東南アジアの産品が満たしたとみられる。そして、それらの輸送にあたってマレー半島横断ではなく、マラッカ海峡経由が利用されるようになり、それに伴って中継交易都市が盛衰することになる。そうしたことがどのように展開されたかついては、東南アジアがようやく歴史時代に入ったこともあり、中国人やイスラーム人の史料によらざるをえない。
西方アジア諸国の中国への朝貢は、漢代からはじまり、隋と唐の時代に入っても続く。その隋唐時代(607-904年)における朝貢回数を整理すると、下記のようになる。朝貢回数は、初唐期の7世紀後半に入って増加し、盛唐期の8世紀前半に最多となるが、その後減少して、中唐期の8世紀末には初期状態となる。その間、朝貢国には大きな変動がみられる。7世紀後半から8世紀後半まで、南アジア・西アジア諸国が東南アジア島嶼部諸国に代わって増加するが、それ以後は再び後者が取って代わる。それでも、前者の入貢回数は後者の2倍強となっている。
| |
|
|
|
||||
| |
|
|
|
|
|||
| 南アジア・ 西アジア |
天竺 波斯 大食 南天竺 西天竺 中天竺 東天竺 北天竺 獅子 大食舎麿 黒衣大食 黒衣 |
3
1 - - - - - - - - - - 4 |
-
5 4 4 1 1 1 1 1 - - - 18 |
2
10 9 3 1 6 1 1 2 1 - - 36 |
-
4 2 - - - - - 2 - 10 1 19 |
5
20 15 7 2 7 2 2 5 1 10 1 77 |
|
| 東南アジア 島嶼部 |
盤盤 赤土 詞陵 婆利 波羅 摩羅游 尸利仏誓 闇婆 占卑 三仏斉 |
4
3 2 2 1 1 - - - - 13 |
-
- 1 - 1 - - - - - 2 |
-
- - - - - 6 - - - 6 |
-
- 2 - - - - - - - 2 |
-
- 4 - - - - 3 2 1 10 |
4
3 9 2 2 1 6 3 2 1 33 |
| |
17
|
20
|
42
|
21
|
10
|
110
|
|
| 資料:石澤良昭・生田滋著『世界の歴史13 東南アジアの伝統と発展』、p.132-3、中 央公論社、1998)。 |
生田滋氏は、「630年代の末から640年代の初めにかけてインド洋貿易圏で大きな変化が起こり、その結果インド船、アラブ船、ペルシア船が中国に直接来航するようになった」。その原因として、「多量の銀が西アジアに出回るようになった……さまざまな贅沢品に対する需要が急に高まった」からとする(石澤良昭・生田滋著『世界の歴史13 東南アジアの伝統と発展』、p.134、中央公論社、1998。この文献は以下、石澤前同または生田前同とする)。
他方、東南アジア島嶼部諸国にあっては、盤盤(マレー半島のチャイヤー)や赤土(同南部)などは8世紀以降、朝貢を止めているが、詞陵(ジャワ島のプカロンガン)はおしなべて朝貢しており、尸利仏誓(スマトラ島のパレンバン)が8世紀後半に現れて消える。闍婆(ジャワの意味)や占卑(ジャンビ)、三仏斉は、9世紀以降において、南アジア・西アジア諸国に代わって朝貢しはじめる。なお、日本は遣隋使を2-3回、遣唐使を15回、合計17-18回出しており、その朝貢回数は異常に多いといってよい。
そして、「群島部の諸国からの朝貢があった年には南アジア、西アジア諸国の朝貢がなく……[また、それが逆になる]という関係……は偶然の一致ではない」という(生田前同、p.134)。この朝貢状況から出てくる論点は、東南アジアの朝貢国の顔ぶれが隋唐時代の始めと終わりとで激変し、その間、朝貢回数が激減したのは、なぜか、また7世紀後半から8世紀後半にかけて南アジア・西アジア諸国は争うかのように朝貢するが、9世紀になると朝貢しなくなるのはなぜかであろう。これら論点は順次明らかとなる。
なお、インド人や、アラブ人、ペルシア人がそれぞれの国において船を建造し、遠路はるばる航海して、中国に直接に来訪したようになっているが、はたしてそうであろうか。そうしたこともなかにはあったであろうが、その多くは東南アジア船やようやく進出した中国船に乗り換えてやってきたのではなかったのか。そればかりでなく、インドやアラブ、ペルシアの産品を携えることで、それら国々の使節と名乗って入貢していたのではないのか。
▼中継交易都市、扶南の衰退、チャンパの隆盛▼
古代東南アジアにおいて、メコン河デルタにあった扶南は交易によって約500年も栄えたが、6世紀以降、中国との交易が減少し、東西交易がマレー半島横断ではなく、マラッカ海峡経由になるにつれ、凋落を余儀なくされる。扶南は、6世紀後半、内陸部のアンコール・ボレーに遷都し、7世紀前半には真臘(カンボジア)に併合される。
それに対して、扶南とともに中継交易都市として栄えたチャンパは、190年代林邑として建国するが、7世紀から自らチャンパと呼ぶようになる。中国では8-9世紀環王、9世紀末以降占城と呼ばれた。チャンパは単一の国家ではなく、現在のベトナムのハイヴァン峠より南の、山脈が張り出した狭くて長い沿岸線に点在する、交易都市のゆるやかな連合体であった。
生田滋氏は、チャンパの交易について「山脈と峠、陸路に守られて[いたが]……後背地に広い平野部がないことが、人口の増加とその国力に限界を与えてきた。かれらは『水』に強い民族であったので、東南アジア各地の沿岸や内陸の河畔に小拠点をつくっていた。……この地方では沈香や黒檀などの香木はとくに有名であった。一時は中国の海南島にも貿易拠点を持っていた。インド・東南アジア・中国をつなぐ海上交易ルートの中で、シャム湾から広東(番禺)までの地域間交易路の搬送と仲買人的役割を果たしていた。9世紀ころから貿易陶磁の扱いが始まり、越窯青磁、定窯白磁などを運送していたらしい」とまとめる(生田前同、p.134)。なお、チャンパの交易拠点のありようは興味深いが、いまだ明らかにしえない。
チャンパは、マラッカ海峡や島嶼部から中国の広州に至るルートの中間に位置しており、また東南アジア各地に交易拠点を持っていたことで、扶南のように、東西交易がマラッカ海峡経由に移行したことによる影響は免れたとみられる。チャンパは、総体として国力が拡張したことはなく、特に北から外圧に受けていた。10世紀までは中国と戦い、10世紀以降はベトナムとカンボジアに挟撃され、その後はベトナムといつも戦闘を交えてきた。この北や西の敵との戦いは「メコン河流域、それに南シナ海から東シナ海にかけての貿易をめぐる争いでもあった」(石澤前同、p.116)。
これに対して、1000年チャンパは交易の中心地を、ダナンやホイアンを抱えるチャキエウから、南のメコン河流域との交易ルートを開設しょうとして、現在のビンディン市の南にあるヴィジャヤに移す。そこでの交易について、弘末雅士氏は1225年に泉州の提挙市舶(交易官)であった趙汝活が著した『諸蕃志』から、「官は民を督促して山にいれ、香木を伐採させて税として納入させた。納入分以上の収穫は食物などと交換されて生計のもとになる。占城の都に商船がくると、王は宮人を派遣して舶載品の数量を記録し、その20パーセントを関税とし、残りを交易させた。……もうひとつの輸出品は奴隷である」という(同稿「交易の時代と近世国家の成立」池端雪浦編『世界各国史6・東南アジア史2島嶼部』、p.71、山川出版社、1999)。
| しかし、かれらも北や西に攻撃を仕掛けていた。チャンパ水軍は、1177年にはメコン河をさかのぼって、アンコール都城を攻略している。「アンコール・トム」のバイヨン寺院第1南面の浮き彫りに描かれている「チャンパ水軍の戦舟は一段櫂座の漕ぎ手と陸兵を乗せ、速力と機動性において当時大きな威力を発揮していた」という。なお、14世紀に入ってであるが、チャンパはベトナムに押し入り、ハノイを攻略している。 「かれらは、東南アジア各地の沿岸や大河川の河岸に拠点を持ち、森林の物産や特産品を収集して運搬し、メコン河流域からシャム湾および南シナ海から中国にかけての貿易により大きな利益を上げていた。別の言い方をすれば、拠点のネットワーク化により域内の物産を取り扱っていたのである。ベトナムとの交戦の度に多くのチャム人が国外の拠点へ逃れたが、これらの国外の拠点網はそのまま機能していた」(以上、石澤前同、p.117)。 |
 |
| アンコールワット・トムのバイヨン寺院第1南面の浮彫 12世紀以降 カンボジア |
チャンパは、17世紀後半ベトナムに吸収される。しかし、その後もチャンパ人は「海の民」とし
て、国外に離散あるいは拠点を移して活躍したとされる。
▼シュリヴィジャヤの登場、東南アジア交易圏の成立▼
| 東西交易において、マレー半島を陸路で横断するか、マラッカ海峡を下って迂回するかは、その交易品、交易の担い手、輸送の安全性などの面から、それなりに大きな意味を持つ。すでにみたように(Webページ【2・1・3 古代アジアにおける海上交易】参照)、この2つのコースは当然なことながら、早くから知られており、それぞれの需要に応じて、そのどちらも用いられたことであろう。7世紀には、マラッカ海峡を下るコースが主流となったとみられる。それは、一般論ではあるが、海上交易の増加、海峡部の交易都市の発達、そして船舶の改良などの結果であったとみられる。 東晋の入竺僧法顕(337?-422?)は、411年スリランカからインドの船に乗って、マラッカ海峡を下ったかどうかは不明であるが、海路中国に帰国している。唐の入竺僧義浄(635-713)をはじめとして、多くの入竺僧や天竺僧が、海路を利用しており、その記録が残っている(長澤和俊著『海のシルクロード』、中公新書、1989、参照)。 |
 |
| |
671年、義浄は広州からペルシア船に乗って、シュリヴィジャヤに着く。そこでシュリヴィジャヤの王の接待を受け、王の船に乗り替えて、インドのガンジス河にあるタームラリプティに着いている。その帰途は、シュリヴィジャヤからその国の商人の船に乗って帰国している。また、同じスマトラ島のジャンビ(占卑)やマレー半島のケダ(羯茶、クダともいう)にも立ち寄っているが、それらの国々はシュリヴィジャヤの支配地で、いずれも仏教国であった。
7世紀に入ると、東南アジアを経由する東西交易は、東からであろうと、西からであろうと、マラッカ海峡を経由するのが一般的なり、マラッカ海峡の出入り口に交易地や寄港地が求められることとなった。そこに興ったのがシュリヴィジャヤ王国であった。その政治の中心地は、現在のスマトラ島パレンバンに当たるとされる。そこは、ムシ川の河口から約90キロメートルさかのぼったところにある。その勢力範囲は8世紀にかけ、スマトラ島、ジャワ西部、ボルネオ島西部、そしてマレー半島に及んだとされる。それらのそこここに交易港があったとみられる。
このシュリヴィジャヤ王国の成立について、生田滋氏は「東南アジア群島部の歴史にとって画期的なことであった。……同地を中心とする東南アジア貿易圏が成立したということができる」と高く評価する(生田前同、p.141)。なお、この時代の最初の大きな交易都市となったシュリヴィジャヤについて、それほど多くのことがわかっているわけではなく、またその王国の位置づけや中心地をめぐって議論がある。
シュリヴィジャヤにはインド船やペルシア船、アラブ船が来航し、東南アジア産品を仕入れた上で、中国に向かった。また、それら西方の船が下ろした西方の産品は、シュリヴィジャヤなど東南アジアの船や、その後登場する中国船に積み替えられて、中国に向かった。その逆も行なわれた。そうした東西交易の中継ばかりでなく、生田滋氏はシュリヴィジャヤが「東南アジア群島部の各地との間[…の…]貿易を行う中継貿易の基地であった」ことを強調する。しかし、その実態について、多くは語らない。
さらに、シュリヴィジャヤは当然ながら、地元産物の輸出港でもあった。その点については、「山地部の産物の輸出港としての機能を果たすことになった。輸出品としては国際貿易の商品となる金や林産物、それに食糧としての米、サゴ澱粉、果実などが考えられる。食糧のほうは来航した外国の貿易船のほか……汀線地帯で海産物をもとめて活動する人びと、いわゆる海民のためのものでもあった」。
「この2つの点[群島部の各地間と後背地との交易]で、シュリヴィジャヤはのちの東南アジア群島部、および大陸部の沿岸地帯の港市の原型となった」という(以上、生田前同、p.142)。
▼中国船の登場、南アジア・西アジアの後退▼
こうして、すでにのべた隋唐時代の朝貢状況から出てくる論点のうち、東南アジアに関する論点は7世紀のマラッカ海峡経由の普及と8世紀のシュリヴィジャヤの登場によって、およその回答がえられた。それでは、もう一つの論点である南アジア・西アジア諸国については、どうか。
古代交易では、需要国が供給国に出向いて、おおむね贅沢品を手に入れることにあった。その典型が朝貢交易である。そうした朝貢国として、7世紀後半から8世紀後半にかけて、伝統的な南アジアばかりでなく、新興国の西アジア諸国が本格的に登場したことに争いはない。そのとき、かれらは目の色を変えて東南アジアに現れ、中国と往来したことであろう。これが「アラブ船・ペルシア船の来航」や「イスラーム船の東漸」と呼ばれた中身であった。
そのとき、東南アジア諸国はどうしていたかであるが、それら諸国が中国産品をいらなくなったわけでは、毛頭ない。東南アジア諸国にとって、インド船、アラブ船、ペルシア船が、東南アジアに寄港しながら、中国と往来せざるをえないとき、かれらから中国産品を調達すれば良かったのである。その調達に当たって、東南アジア産品を提供した。そうしたもとで、特にマラッカ海峡部において、いままでなく中継交易が発達したとみられる。
次ぎに、南アジア・西アジア諸国が、9世紀以降、朝貢しなくなったのは、それら諸国が中国産品を朝貢交易に依存せずに入手できるようになったからである。それは、いまみた海峡部における中継交易の発達と、そのもとでの中継交易の拠点国家―その代表がシュリヴィジャヤである―が成立したことにあろう。新たな中継交易拠点国家の成立によって、その後の東南アジアの朝貢国はそれ以前にマレー半島地峡部のシャム湾周辺ではなく、マラッカ海峡部周辺の国々が取って代わったのである。
そして、決定的なことは、東南アジアへの中国船の登場である。生田滋氏は、「黒衣大食の最後の入貢である798年から、その次に詞陵国が入貢した813年までの間は……アッバース朝の最盛期である。したがって西アジアのほうに、こうした変化をひきおこした原因があるとは思われない。……こうした変化はこのころ、つまり9世紀の初めから中国船の海外への進出が始まったこと」にある(生田前同、p.145)。
その原因について「それまでに西アジアと日本から輸入された金銀が蓄積されて、しだいに貨幣経済が復活し、国内で外国から輸入された賛沢品に対する需要が高まったことを挙げたい。その結果、インド船、アラブ船、ベルシア船によって輸入される商品だけでは需要を満たすことができなくなり、そのギャップをうめるために中国船が海外に進出するようになったのであろう」。そして、「シュリヴィジャヤが貿易港として繁栄したのは、むしろ中国船の来航が始まってからではないかと思われる」とまでいう(生田前同、p.146、147)。中国船が、まずもってシュリヴィジャヤまで来航し、そしてケダまで航海したという。これはまさに長足の進歩ではある。
この時期、アラブ人はアジアについて、多くの記録を残している。当面するケダに限れば、10世紀初め、アブ・サイドは『シナ・インド物語』において、そこが「沈香、樟脳、白檀、象牙、錫、黒檀、蘇木、あらゆる種類の香料、およびその他もろもろの品々の交易の中心地で、オマンから出発する貿易船はここを目的地」とする。また、10世紀中頃、地理学者マスーディは『黄金の牧場と宝石の鉱山』において、そこは「中国[とインド]との間のほぼ中間にある。今日ではここが、シーラーフやオマンからくるイスラーム教徒の船の最終到達地点である。かれらは、そこで中国から来た船に出会う。以前[875-884年の黄巣の乱]はそうではなかった。……この商人はキッラ市[ケダのこと]で中国船に乗ってカーンフー[広府、すなわち広州]に向かった」と書き残している(生田前同、p.147)。後者については、長澤前同、p.102がさらに詳しい。
中国船が、9世紀半ば南シナ海に登場し、10世紀半ばマレー半島にまで進出してことは、東南アジア交易圏にとって画期となった。南アジア・西アジアの商人は中国に入貢せずとも、またマラッカ海峡の西の入口まで来れば、東方の産品を入手できるようになった。さらに、10世紀以降の後述するチョーラ朝の勃興と、そのマラッカ海峡への進出が、それに大きく関与していよう。なお、中国船は12-13世紀、南インドまで進出する。
▼三仏斉としての新シュリヴィジャヤ▼
唐は907年に滅び、916年契丹帝国の成立、五代十国の混乱を経て、960年には宋王朝が生まれる。その首都は、華中、華南の中心にある、開封となった。宋は、北から遼や金が侵入を受け、また西北は西夏に押さえられていた。そのため、西域との陸路交通は途絶していたので、東西交易は海上交易に大きく依存せざるをえなくなった。宋は南海に生きるしかなかった。
宋、さらに元の時代、内外の商船の往来は原則自由となったが、朝貢は相変わらず行なわれた。すでにみたように、唐の末期、南アジア・西アジア諸国は朝貢を止めていたが、宋の時代に入ると大食(アラブ)が再び入貢しはじめる。東南アジアの朝貢国では、三仏斉、そして闍婆が入貢を繰り返す。960年から1178年までの入貢回数は、大食34、大食麻羅抜国など4、合計38、そして三仏斉30、闍婆13、勃泥(仏泥、ブルネイ)3、三仏斉せん畢1、合計47である。
この大食の再開について、生田滋氏は「このころ、西アジアにあった銀の鉱山での銀の生産がストップしているので、これ以後の大食国の朝貢はいずれも西アジア産の商品を中国にもたらして、銀を入手しようとしたものと考えられる」という(生田前同、p.220)。それに対して、尸利仏誓が入貢しなくなり、三仏斉が激しく入貢するようになる。この三仏斉については議論がある。
中国史料では、三仏斉は10世紀にあらわれ、15世紀初めまで使われたという。通説は、それを尸利仏誓の後継国、すなわちシュリヴィジャヤの新旧交代とみている。それに対して、深見純正氏は「三仏斉は単一の国家や帝国ではなく……マラッカ海峡地域の交易国家の総称と考える。何百年も連綿と栄えたシュリーヴイジャヤ帝国という従来の大国イメージを否定して、多数の港市国家の変遷としてマラッカ海峡の歴史像を再構成して」みるべきだとする(同稿「古代の栄光」池端雪浦編前同、p.33、山川出版社、1999、さらに同稿「海峡の覇者」『岩波講座・東南アジア史3』、岩波書店、2001も詳しい)。
この三仏斉に関して、いずれの説もその成立についての根拠を示さないが、マラッカ海峡部に政治勢力がその力を大きく延ばした時期に成立していたことに争いはない。そうした状況を作ったマラッカ海峡部の政治勢力を、中国側が三仏斉としたといえよう。ここでは三仏斉を、便宜上、新シュリヴィジャヤとして書く。新シュリヴィジャヤ王国あるいはマラッカ海峡諸国家としての三仏斉は、10-11世紀に最盛期を迎え、東西交易の独占したとされる。「その商人たちは広州や汕頭、ベンガル湾に面したコロマンデル海岸に商館を持っていた」という(レイ・タン・コイ著、石澤良昭訳『東南アジア史』増補新版、p.35、36、白水社、2000)。
石澤良昭氏は、中国から三仏斉とされた「シュリーヴィジャヤが繁栄したのは、第1にその勢力範囲がマレー半島・スマトラ・西ジャワを中心に属国15か国に及んでいたこと、第2に東西海上交通の要衝にあって、アラビア・インドから中国への往来には必ずこの国を経由したこと、第3に通過する商船を必ず入港させる武力があったこと、第4に香辛料や真珠・象牙・琥珀などの南海の諸物産の集散地であったこと、などがあげられる」という(石澤良昭稿「1-13世紀まで」桜井由躬雄他著『地域からの世界史4・東南アジア』、p.76、朝日新聞社、1993)。
1178年、周去非が著わした『嶺外代答』には、この「三仏斉国は南海にあって、海上交通の要衝である。東は闍婆の諸国から、西は大食〔西アジア〕や故臨〔南インド〕の諸国から、その境域を通らないで中国に来るものはない。この国には産物はないが、人々は戦いに習熟していて、薬が効いている間は刀も傷つけることができず、陸に攻め、水に戦い、その力戦奮闘は前例がない。それゆえ隣国はすべて服属している。外国船が通り過ぎて、その港に入らなかったりすると、必ず海軍を出して皆殺しにする。そういう理由でこの国には犀角、象牙、真珠、香薬が豊富なのである」とある。
これについて、深見純正氏は「要するに、地の利を生かして海軍力によって外国船から交易商品を入手している。これらは交易品、朝貢品として中国などにもたらされる。海賊・国家・商人の三位一体となった姿がよく描かれている。『諸蕃志』にも同様の叙述があるが、この国自身の産物として沈香等々多数の品目が列挙されるのが異なっている」と解説する(以上、深見「海峡の覇者」、p.123)。
▼はたまた三仏斉としてのジャンビ▼
850年頃、南インドに前1世紀にあった王朝と同じ名のチョーラ朝が成立する。そのラージエンドラ一世(在位1012-44年)は、1015年宋に入貢して東西交易に乗り出してくる。その障碍となっている新シュリヴィジャヤに、1017年頃から数回にわたり艦隊を派遣する。特に、1025年にはそれを徹底的に略奪する。それにより、ベンガル湾はチョーラ朝の海、ケダはマラッカ海峡部の拠点となる。その結果、三仏斉、さらに大食国までもが40、50年にわたって朝貢できなくなる。
このチョーラ朝も1080年頃からマラッカ海峡の支配力を失う。それに代わって、パレンバンより少し北にあるバタン・ハリ川の河港のジャンビが、中継交易都市として台頭してくる。このジャンビ王国も『諸蕃志』において三仏斉として記述されているが、その領域はジャワ島のスンダ地方からスマトラ島の北端のランブリに拡がっていた。そのなかに、パレンバンが含まれるが、ジャンビに相当する地名が見当たらないという。それらから、生田滋氏は「パレンバンにあった[シュリヴィジャヤ]王国の勢力が衰え、それに代わってジャンビ王国が勃興した」とし、しかもその成立を1178年の三仏斉の最後の朝貢の直後とみている(生田前同、p.224)。
このジャンビ王国は新たな海上交易センターとはなりえず、それまであった海峡部における交易秩序は崩れたままになったとみられている。その本格的な再構築は、13世紀になって海峡部にイスラーム交易都市が、新しく建設されるのを待つこととなる。
それはともかく、生田滋氏はその交易を下記にように整理してくれている。そのうち、土地の物産となっているものには「丁香(丁字)、肉荳蒄(にくずく)のようにマルク諸島、バンダ諸島から輸入されたものがあり、ジャンビ周辺の産物は海産物である玳瑁(たいまい)と、あとは香、香木の類で、いずれも熱帯落葉樹林の林産物[である]……大食諸国からの輸入品には、西アジア、南アジアの産品が広範囲に含まれている……中国からの輸入品には、金銀、磁器、絹織物のほか鉄、砂糖、酒がみられる」と特徴づける(生田前同、p.225)。
| |
| 1 土地の物産 海産物:玳瑁 香:脳子(竜脳樹の樹脂)、沈香、速香(沈香の一種)、暫香(同左)、粗熟香、降真香(ツルシタ ンの芯材) 香木:檀香(紫檀、白檀、黄檀など) 香料:丁香(丁字)、荳蒄(肉荳蒄) |
| 2 大食諸国の物産 香:乳香、没薬、阿魏(大茴香から採取したゴム樹脂)、蘇合油 香水・薬種:薔薇水、梔子花(クチナシの花を乾燥させたもの。香りをつけるのに用いる)、膃 肭臍(オットセイのことであるが、実際はジャコウネコの香袋)、蘆薈(アロエ)、木香(キク科のトウ ヒレンの根) 宝石類:真珠、象牙、珊瑚樹、猫児晴(猫目石)、琥珀 手工業製品:番布(綿織物、毛織物)、番剣 |
| 3 中国から三仏斉への輸出品 貴金属:金、銀 磁器 絹織物:錦、綾、纈絹 砂糖 鉄 食料品:酒、米 薬種:乾良薑、大黄、樟脳 |
| 出所:生田前同、p.223。 |
なお、『諸蕃志』上巻の「志国」には、交趾国(トンキン地方)にはじまって倭国まで、実に黄海、東シナ海からマラッカ海峡を経て、インド洋、アラビア海、そして地中海に至る、実に45か国におよぶ地理・風俗・産物が記載されている。
▼ジャワ島のクディリ、マジャパヒト王国の海上交易▼
このシャイレンドラ朝(詞陵)はすでにみたように中国にこまめに朝貢を繰り返していた。しかし宋の時代には入貢しなくなる。ジャワ島中部では仏教に代わってヒンドゥー教が栄えはじめ、シャイレンドラ朝は9世紀末には古マタラム朝に追い払われ、姿を消す。それに代わって、唐の末期から闍婆が朝貢しはじめる。それは古マタラム朝が闍婆の名において朝貢していたとみられている。その交易について、『諸蕃志』には「周辺の地域や南アジア、西アジア地域からの輸入品も見られるが、とくに農産物としての胡椒が重要であったし、綿織物、絹織物もあった。胡椒はスンダ方、ジャワから中国向けの輸出品として重要であった」と記されている(生田前同、p.232)。
▼ジャワ島のクディリ、マジャパヒト王国の海上交易▼
| ジャワ島中部では、5世紀頃から国造りが起き、750年頃に現在のプカロンガンに、シュリヴィジャヤシャ勢が進出して、シャイレンドラ朝すなわち詞陵という国家が築かれる。8世紀後半から9世紀にかけて、アウトリガーを持つ大型交易船の浮き彫りが施された、壮大な仏塔遺跡「ポロブドゥール」が建立される。その勢いを示すがごとく、8世紀後半、インドシナ半島東岸のベトナムやチャンパ、カンボジア南部に海路遠征隊を派遣している。この動きは、シュリヴィジャヤ王国と連携して、南シナ海の制海権を握ることにあったとみられている。 |  |
| |
| |
| 1 外国からの輸入品と思われるもの 海産物:玳瑁 宝石類:象牙、真珠 香:竜脳、降真香 香木:檀香 香料:茴香、丁香、荳蒄 薬種:犀角、暈澄茄、紅花 工芸品:花箪、番剣 染料:蘇木 白鸚鵡 |
| 2 ジャワの産品と思われるもの 農産物:胡椒、檳榔 鉱産物:硫黄 絹・綿製品:繍糸、吉貝、綾布 |
| 3 中国からの輸入品 貴金属製品:金・銀のまざりもの、金製、銀製の器皿 絹織物:五色の纈絹、白綾 薬種:川弓(おんなかずら)、白止(セリ科の植物の根)、朱砂(辰砂に同じ、酸化水銀)、白礬(明 礬)、緑礬(酸化鉄の硫酸塩)、鵬砂(棚砂に同じ)、鵬霜(硫黄と砒素の化合物) 工芸品:漆器、鉄鼎、青磁、白磁 |
| 出所:生田前同、p.232。 |
その交易港である「スラバヤおよびトゥバンの港市は、インドネシア東部やスマトラ、それにインドシナ半島部との交易を伸張し、そこにはカリンガ(南インド)、北インド、ベンガルなどのインド人、シンハリー、チョ-ラ、マラバール、タミールの人たち、チャム人、モン人、クメール人など、諸国の商人が来航した」、「アラブ人およびグジャラート人は、ジャワやモルツカ諸島の丁香、肉荳蒄、胡椒、香木などと交換するために、織布やインド製の金属器を持って来た」。このジャワの活況はシュリヴィジャヤに匹敵したという(コイ前同、p.39、40)。
『諸蕃志』は、蘇吉丹(スカダナ、現在の東ジャワのグルシク)について「ここの特徴は稲作がさかんに行われるとともに、胡椒の生産がさかんなことである。米も重要な輸出商品であったようであるが、これはもっぱら群島部の各地向けの商品であって、胡椒は中国向けの商品として生産されている」とある。また、大闍婆(ジャンガラ)について「つまりクディリ王国の東半分の……地域の産物としては、青塩(上質の塩)、綿羊、鸚鵡が挙げられているだけで、穀物の類が見えない。また現地の役人が周辺の島々の海賊と親しくしているということである。これらの島々ではサゴ澱粉が食糧とされている」としている。(以上、生田前同、p.233)。
このクディリ朝に代わって、13世紀初め、マジャパヒト王国が成立する。この王国は元軍の来寇を利用して成立するが、その脅威をしのぐとジャワ島を統一する。そして瞬く間にスマトラ島、マレー半島、カリマンタン南・西海岸にその勢力を広げ、古来のシュリヴィジャヤの流れをくむ、マラッカ海峡の政治勢力にとどめを刺したとされる。14世紀中頃には、ジャワ島を中心とした東南アジア交易のネットワークを築くことになる。
その後、「15世紀中葉までの時期、ジャワ島に広く影響力を行使していたのは、東部ジャワに根拠地をおいたマジャパヒト王国であった。この王国は、ジャワの豊かな米をもとに、マルク諸島の香料やティモールの白檀を集荷し、その港トゥバン、グルシク、スラバヤに、中国やインド、西アジアの商人を引きつけ繁栄していた」(弘末前同、p.92)。
ジャワ人商人たちの強みは、東南アジアのしかも東インドネシア特産の香辛料である、バンダ諸島だけに産するナッツメッグ(肉荳蒄、ニクズク)やその仮種皮のメース、そしてモルッカ諸島だけに産するクローヴ(丁字)を独占して、世界に向けては供給していたことにある。それらをマラッカ海峡に運び込み、グジャラードからりムラカ(マラッカ、後述)に持ち込まれた綿織物を持ち帰った。そして、東インドネシアには、それが作れない米や綿織物などを運び込み、香辛料の支払いに当てた。
しかし、ジャワ北岸において海上交易港が栄えると、それらの中小都市はマジャパヒト王国から独立しはじめる。それらがイスラーム交易都市に変貌するようになると、マジャパヒト王国は15世紀末には内陸部に後退したとされる。それに取って代わるのがムラカである。
▼インドシナ半島の交易王朝アユタヤが生まれる▼
13世紀に入ると、東南アジアはいまジャワ島でみたように、新旧勢力の交代の激動を迎える。インドシナ半島にあってもヨーロッパと同じように、北の人々が南に押し出してきて、新興国家が次々と建設される。その激動の契機は元軍の東南アジアへの来寇にあった。
新興国家の先駆けはクメール人(真臘)であった。すでにみたように、7世紀前半扶南を崩壊させ、9世紀から15世紀にかけアンコール王国として栄える。ベトナムは、長年にわたって中国の支配下に置かれていたが、唐が没落すると独立し、李朝(1009-1226)という長期王朝が築かれる。その間、李朝は1044年、1069年チャンパに遠征して略奪する。李英宗(在位1137-75)の治世、その交易は中国ばかりでなく、南海諸国にも拡がった。1226年、陳氏が李朝を終わらせる。
| 中国では、1127年より南宋の時代に入る が、1271年フビライ=ハン(在位1260-90)は 元朝を興し、1279年には南宋を滅亡させ る。この元は他のモンゴル勢と同じように勢 いが強く、南宋の元艦隊や新造艦隊をもっ てインドシナ半島、さらに日本に遠征する。 それは、インドシナ半島にとっていままでに ない脅威となった。元軍は、13世紀後半、イ ンドシナ半島に海陸から侵攻してくる。陳朝 ベトナム(1225-1400)は海陸からの攻撃を 撃退し(特に、1288年海路侵入軍との白藤 江の戦いは有名)、またチャンパは海路か らの侵入を敗走させるが、アンコール王国 は恭順の使節を送る。その海路遠征はジャ ワ島にも及んだ。 |
 |
| 壁画の一部 ベトナム歴史博物館蔵 |
| |
興道王チャン・クオック・トゥアン(陳国峻)が白藤江で元朝水軍を撃破した。
チャンは、内地から湾へ抜けようとする元軍を待ち受け、あらかじめ川の中に杭を打ち込み、草でおおい隠しておき、満潮時に戦闘を仕掛けて逃げるふりをして元軍をおびきよせた。まんまと罠にはまった元の水軍は、杭に引っ掛かって壊滅的な打撃をこうむった。そのさいチャン軍は、400あまりの船を捕獲し、指揮官らを捕虜とした。 このたびの作戦は、300年以上前、この場所でゴ・グェン(呉権)が南漢を撃退し中国からの自立を手に入れたのとまったく同じやり方だったのである。 じつは、これより先の2月に、元軍は総退去を決めていた。ベトナムに出兵して3か月、紅河デルタの中央部は押さえたものの、補給路を断たれ、伝染病に苦しむ元軍は、すでベトナム側のゲリラ戦に耐えきれなかったのである。しかし、国土を蹂躙されたベトナムは、簡単には帰してくれなかった。陸路で撤退した元軍も主要路線をベトナム軍に押さえられ、間道を通り多くの損害を出しながらようやく帰ることができたのである。 こうして、南海交易支配の野望に燃えるフビライの2度めの遠征も、大失敗に終わった。 元成立以前も含め、3度に及ぶモンゴルの侵攻をチャン朝は撃退した。いずれも、いったんハノイをあけ渡してから相手の補給を断ち、ゲリラ的に反撃を加えるという作戦である。このゲリラ戦の原動力は、チャンら地方に勢力を築いた皇族だった。彼らはデルタ開拓の担い手として力を蓄えていたのである。 |
| 出所:『クロニック世界全史』、p.321、講談社、1994. |
| スコータイ朝とそのサワンカローク焼も、1351年チャオプラヤー河の下流にアユタヤ朝が興ると、それに飲み込まれていく。石澤良昭氏は、「こうした13世紀の大変動に際して発展拡大したのはタイ人系諸族であった。アユタヤ朝はスコータイ朝に取って代わり、チャオプラヤー河デルタまでタイ人を一気に南下させ、アユタヤが東西交易の中継地として発展をとげていく」ことになったという(石澤前同、p.250)。 その中流域と下流域を押さえた「商港アユタヤには、中小河川や水路を通じて、内陸部の広い地域の物産、綿花・象牙・蜜蝋・各種の香辛料・漆器などが集まった。これに加えて自国でとれる米や獣皮などを取りそろえ、近隣へ輸出していた。日本からは銀 |
 |
| サワン・ウォラナヨック国立博物館(タイ・スコータイ)蔵 |
▼東南アジア初のイスラーム交易都市、パサイ▼
元(モンゴル)は、東南アジア諸国から朝貢を受入れるだけでなく、遺使をかなり送っている。その特徴は、従来の朝貢国よりさらに以西の国々や、従来の関係のなかった国々を入貢させることにあった。それは、元(モンゴル)王朝が積極的に海上交易に参入し、その広がりを求めたことの現われであった。それに対して、西からも、新しい組織だった交易勢力が登場してくる。それはイスラーム教の浸透であった。それによって、13世紀は東西交易が飛躍した世紀とされる。
イスラーム教は、8世紀西インドへの征服活動とともにアジアに入ってくる、その本格的な浸透は11世紀の北インドへの征服活動後であった。東南アジアへは、その出現後、700年もかかる。それは、東南アジアにはアニミズムやインド伝来の仏教やヒンドゥー教などの既存宗教が根を下ろしており、イスラーム商人が東南アジアに布教しようとしても、それを受容するには至らなかった。しかし、イスラームが西さらに北インドに浸透しはじめ、その地のグジャラート人商人が改宗したことで事態は大きく変化する。
東南アジアは、この時代になってもインドに宗教の威信を仰いでいたので、グジャラート人商人を媒介として、インド的な色彩を持ったイスラーム教を受容するようになる。この宗教は、高温多湿の東南アジアの人々にとって贅沢品かつ必需品となる、綿織物とともに持ち込まれる。
この「ムスリムであるグジャラート人が、極東や中東、地中海とインドとの貿易において、指導的な地位にたつ貿易業者として登場し始めた。彼らは、インドの商品の直接の輸出業者であり、同時に極東、インド、中東の市場間の仲介者としても活躍した。そして、グジャラート地方で成長しつつあった織布業の存在は、彼らにその仕事をやってのけられるだけの、十分な物質的基盤を与えていた。つまりその産業は、グジャラート人に、それ自体高い内在的価値をもつ商品であると同時に、他のアジア諸国の市場(例えば東南アジアの香辛料市場)における交換媒介物ともなる『織布』を与えたのである」(ブライアン・ハリソン著、竹村正子訳『東南アジア史』、p.50、みすず書房、1967)。
東南アジアにおいて、最初にイスラーム教に改宗としたのが、スマトラ島北端のパサイ(サムドラ)であった。この時代東方になじみのある西方の人々のアジアの記録が残される。1270年から73年にかけて、マルコ・ポーロよりも早く、しかも海路で中国に入ったユダヤ人の記録によれば、スマトラ島北端のパサイ(サムドラ)はイスラーム教の王をいただく国だったという。マルコ・ポーロの『東方見聞録』にみえる1292年のフビライの西方使節や、1346年インドから中国に向かったイブン・バットゥータもまたパサイ(サムドラ)に訪れ、いずれも記録を残している。イブンがサムドラを出発する際、その国王は船を準備し、食糧を贈ってくれたとしている。
パサイ(サムドラ)の住民はこれまた何とジャンビやパレンバンからの移住者であったという。こうしたところに、東南アジアにおけるイスラーム教の布教とそれに結びついた交易のための、橋頭堡が築かれたのである。イスラーム化について、生田滋氏は個人的な接触による任意な改宗と支配者の強制による改宗とがあるが、「もちろん両者は同時並行的に進んだことであろう。前者の場合、イスラーム商人がイスラームに改宗することを条件にして珍奇な商品を分配したり、あるいはイスラームに改宗した人びとだけに商品を売却したりしたことがあったに違いない」という(生田前同、p.296)。
このパサイ(サムドラ)は交易都市として繁栄したが、その近くのアル・ラムリともども、「この地域の輸出品としては金があるが、ほぼこのころからこの地域で胡椒の栽培が開始された。おそらくインドから来航する商人が胡椒の産地であるマラバル海岸から移植したのであろう」。さらに、パサイ(サムドラ)は東南アジアにおけるイスラーム信仰の中心地かつ「メッカ巡礼の出発点となり、スエズ河が開通して、ヨーロッパ諸国の船会社が安くて早いメッカ巡礼ツアーを提供するようになるまで続いた」とされる(生田前同、p.294)。
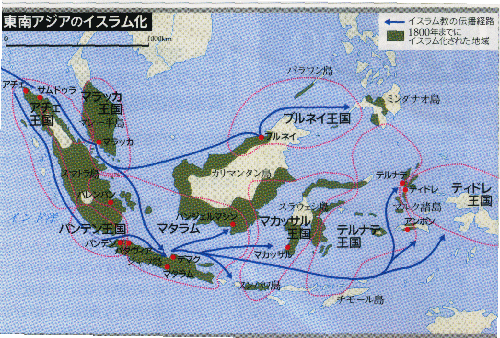 |
| 樺山 紘一他編集『クロニック世界全史 』、p.355、 講談社、1994 |
元(モンゴル)王朝は、各地の叛乱を鎮圧することができず、中国から追い出される。1368年、朱元璋(洪武帝、在位1368-98)は明をたて、南京を首都とする。かれは海上交易を独占しようとして、海禁令を施行する。それによって、中国船はインドのカリカットまで航海することがなくなり、東南アジアにあった中国人街の人口は減少していった。こうした元の凋落と明の海禁によって、特に東西交易の東半分、シナ海交易は一挙に縮小したとされる。
永楽帝(在位1402-24)は、海禁政策を維持しながら、海上交易を回復させようとする。その壮大
な試みが鄭和(1371?-1434?)の南海大遠征であった。それは再度詳細に取り上げるが、その目的は朝廷必需品の獲得および朝貢の督促にあった。その詳細は、Webページ【鄭和西洋下りを『瀛涯勝覧』から読む】を参照されたい。
後者の意味合いは、「チャンパに味方してヴェトナムを牽制し、マジャバヒトの両王対決に干渉してマラッカの領域を確保し、タイの[ムラカ]侵略を防ぐなど、14世紀に成長してきた東南アジアの諸『大国』から港市国家群を保護し、東南アジアの政治地図を固定化することを目的とし……朝貢体制の強制による東南アジア秩序の再編」にあった(桜井由躬雄稿「14-19世紀」同他著『地域からの世界史4・東南アジア』、p.110、朝日新聞社、1993)。
14世紀末か15世紀初めに、マレー半島にムラカ(マラッカ)王国が成立したとされる。その建国者は、生田滋氏に従えば、マジャパヒト王国が侵攻してきた時、これまたパレンバンから逃れてきた、王族とそれに従ったとされる海民たちであった。この海民は「汀線地帯で活動し、漁業、海産物の採集、 あるいは海賊行為を行う人びとのことで……海民はそうした庇護を与えてくれる代償として、かれ[王]に服従し、戦争に際しては舟と人員を提供し、貢物や奴隷を献上する」ような人々であった(生田前同、p.299)。
ムラカでは、その2代王イスカンダル・シャー(在位1414-22)が、1414年にイスラーム改宗したという。それを、鄭和の大遠征の第4回航海に参加し、『瀛涯勝覧』を残した馬歓が確認している。さらに、5代ムザファール・シャー(在位1445-59)の時代、王室規模の改宗が進み、マラッカ王室がイスラームを受容したことをはっきり示した。こうした改宗は、まずはムラカが中継交易港として成長したことで起きた、パサイ(サムドラ)との摩擦を解消するためにあったが、アラブやインドのイスラーム商人が好んでムラカに訪れるように仕向けるためでもあった。ムラカの支配者が海峡部の覇者となるには、イスラーム教徒になることにおいて他になかった。
パサイにしろ、ムラカにしろ、それらの支配者が、一方においてシュリーヴィジャヤ王国ゆかりの人物を名乗り、他方において外来新興宗教のイスラーム教徒になることについて、弘末雅士氏は彼らの「果たす役割を考えるとき、港市を拠点に2つの空間ができあがっていることがわかる。1つは、多様な地域からの来訪者が滞在する国際都市であり、もう1つは支配者と内陸民や海上民とが在地の原理をもとに形成した地元社会である」という(同稿「東南アジアにおけるイスラームの展開」『岩波講座世界歴史』6、p.190、1999)。
ジャワ(爪哇)には、その記録から、15世紀初め西・南アジアのイスラーム商人が来訪しており、来訪中国人のなかにはイスラームになったものもいたが、現地住民はそうではなかった。東南アジアのイスラーム化は、15世紀半ばからムラカがジャワから米を輸入するようになると、マラッカ海峡から島嶼部全域に向けていままでにない早さで拡がり、イスラーム商人が居留する交易都市に布教され、イスラーム都市になっていく。
| 鄭和の遠征は7回行なわれるが、このムラカを主要な寄港地として利用しただけでなく、パサイ(サムドラ)、そしてモルジブとともに、「官廠」と呼ばれた軍事基地を建設している。そうしたことは、マラッカ海峡が交通の要衝であったからだけでなく、そこに現在も残る「三宝井」と呼ばれる大きな井戸があったからでもある。さらに、ムラカは例えばスマトラ島のパレンバンやジャンビのような、マングローブ林に覆われた河岸からはるかに奥まった河港ではなく、交易ルートに面したアクセスが容易な海港であった。 このムラカ王国は、当初、マレー半島南部に進出していたアユタヤ王国に服従していた。それは朝貢国が朝貢国を支配するというもので、中国の冊封体制からすれば許されないことであった。そこへ鄭和の大遠征が来る。かれは、第2-3回航海の際、詔勅により国王をムラカ(満刺加)王とし、シャム(せん羅)王と対等の地位を与えた。しかしその後も、アユタヤ王国はムラカを圧迫し続ける。 |
 |
| 三宝井 マラッカ(マレーシア) |
しかし、その伸長はとどまるところを知らなかったものの、「この地域に安定した勢力の均衡がもたらされることはなかった。全くマラッカは、服属諸国とのほとんど絶えまのない戦争にまきこまれていたようである。そして服属諸国も、また互同志で交戦していた。イスラム教はたしかに、マラッカ海峡に平和も、またはその海沿いにある多くのムスリム諸国や諸港に対して、何らかの意味での統一ももたらしはしなかった。……したがってマラッカの戦争は本質的に商業戦争」(ハリソン前同、p.65-66)、あるいは交易センター防衛戦争であったのである。
▼ムラカ王国の交易管理、交易民の頭取▼
ムラカ王国は、国王、王族、貴族、そして武士を支配者とし、そのもとに平民と奴隷がいた。貴族は建国者に従った海民の子孫とされ、様々な官職に就いていた。そのうち、プングフル・ブンダハリという官職は、「王国の徴税、外国人の管理、貿易などを管轄する官職で、元来は王家の家産を管理する官職であったと思われる」という(生田前同、p.308)。
ムラカ王国は、海上交易の中継国として生きていくために、長期的には「強制力によって利益を得ようとするのではなく、中立政策と低関税政策で、あらゆる交易を引きつけようとした」。「マラカ政府は、倉庫のスペースや船との間の荷役のための象を含む、さまざまなサービスを提供した。また、関税を低く抑えようとした。広東では商人は荷価の20-30パーセントも税金を払わざるをえなかったのに対し、マラカ政府は『贈り物』と手数料を合わせて3-6パーセントに抑えていた。見積りを公正にするため、荷価はクリン[インド人商人のカースト名]5人とその他の共同体からの5人とからなる委員会が決めた」(フイリップ・D・カーティン著、田村愛理他訳『異文化間交易の世界史』、p.184、185、NTT出版、2002)。
ムラカには、商人をはじめ水先案内人や船員など、多数の外国人が居住していた。ムラカ王国は、かれらを(1)グジャラート、(2)マラバール、コロマンデル、ベンガル、ペグー(バゴー)、パサイ、(3)ジャワ、マルク、バンダ、パレンバン、タンジョン・プラ、ブルネイ、ルソン、(4)中国、琉球、チャンパという出身グループにまとめて居住させ、自治を認めていた。
そして、それぞれのグループから、シャーバンダル(交易民の頭取で、交易・港湾管理を委ねられていた)を任命した。シャーバンダルは普通1人であるが、ムラカでは4人となった。シャーバンダルはそれぞれの出身者を管轄するとともに、その代表としてムラカ政府との折衝や、他のグループとの交渉や調停に当たらせた。また、自らのグループの商船がくると、ムラカ政府から提供された倉庫を割りあて、また荷役の象を手配した。
ムラカの中継交易は、こうした外国人交易にまったく依拠していたわけではない。「マレー人貴族は軍人出身で商業を軽蔑していたが、マラカのスルタンや高級官僚は大々的に交易を営んでいた。スルタンは船を何隻か所有していたが、さらに何隻かチャーターし、貨物を分載させて代理人とともに送り出したりした。貴族のなかにはとてつもない金持ちもいて、ある者は140ポルトガル・キンタル、つまり8.2トン(21万7617トロイオンス)の金に換算できる富を保有していた。民間の商人も大資本をもっており、自分はマラカに在住しながら、代理人を旅行に出して自分自身のために取り引きさせた。クリンやジャワ出身の共同体がなかでも裕福だった。港を利用する船の約3分の1はマラカ船籍だった」という(カーティン前同、p.186)。
このムラカ王国は2000人規模で都市づくりがはじまったが、16世紀初めには人口10万人前後の巨大な交易都市国家(港市国家)となった。ポルトガル人旅行家トメ・ピレス(1468?-1540?)が、1512-15年ムラカに滞在したときに著わした『東方諸国記』よれば、ムラカの来訪あるいは居留外国人は60の都市や国、地方に及び、なかでもグジャラート人商人は1000人ほどが居留し、またグジャラートの船乗りが毎年5000人ほどが来訪したとする。
| |
||
| カイロ メッカ アデンからのムーア人(ムスリ ム) アビシニア人 キルワ マリンディ ホルムズの人々 ペルシア人 ルーム人 トルコ人 トルクメン人 アルメニア・キリスト教徒 グジャラート人 デカン王国の人々 チャウル ダボル ゴアからの人々 マラバル人 クリン人 オリッサ |
セイロン ベンガル アラカン ペグーからの商人たち シャム人 クダ人 ムラユ人 パハン パタニ カンボジア チャンパ コーチシナの人々 中国人 琉球人 ブルネイ人 ルソン人 タンジュンプラ ラヴェ バンカ リンガと周辺の千もの島々 |
マルク バンダ ビマ ティモール マドゥラ ジャワ スンダ パレンバン ジャンビ トゥンカル インドラギリ 〔カンポカン、カンパル〕 ミナンカバウ シアック [ルバト] アルカト アル タミアンの国であるバタ パサイ ペディル モルディブの人々 |
| 出所:カーティン前同、p.185。 資料:トメ・ピレス『東方諸国記』(生田滋他訳注、p.455、岩波書店、1966参照)。 注:地名は、イギリス名となっている。 |
桜井由躬雄氏は、ムラカの地位について「マラッカ海峡は、通行税をとるための税関を超えて、東西交易の中心点になった。マラッカ・ネットワークの誕生によって、東南アジアの『大国』群は、その農業生産力、熱帯産物の供給地、過大な人口という点で、小さな港市国家マラッカに勝っていたにもかかわらず、マラッカへ従属する構造が生まれた」と整理する(桜井前同、p.113)。
このムラカ王国は、1511年これまたイスラーム教徒と同根のキリスト教徒のポルトガル人に占領され、その地位を奪われる。それによって東南アジアの島嶼部は新しい時代に入る。
▼若干のまとめ▼
東南アジアは、6世紀以降歴史段階に入り、特に島嶼部においては、海上交易をめぐって大小様々な交易都市が興亡を繰り返しながら、15世紀以降の「交易の時代」に突入していく。
7世紀、西からイスラーム商人がダウ船に操って東南アジア経由して、中国まで進出し、遅れて9世紀になって東から中国人商人がジャンクを使って、直接、東南アジアに進出してくるようになった。そのなかで、東西の交易ルートはマレー半島横断からマラッカ海峡経由となり、その海峡部に大小の交易都市が築かれるが、マラッカ海峡諸国と総称されるような交易都市が主導するようになる。
東南アジアの海上交易センターがマラッカ海峡にあったことは明らかであるが、それがある一つの交易港におかれることはなく、いくつかの交易港にまたがっていたとみられる。そして、いくつかの大きな拠点港に40、50くらいの中小の港が結びつくことで、一つの交易ネーとワークを形成していた。
このマラッカ海峡を経由する交易ネットワークを、スマトラ島の政治勢力すなわちシュリヴィジャヤを旋回軸としながら、マレー半島やジャワ島、時には南インドといった、様々な政治勢力が興亡を繰り返しながら支配したが、長期の支配とはなりえなかった。その支配に当たって、それら政治勢力は基本的には海軍力によって維持したとみられるが、それとともに中国との朝貢を行うことでその威信を高めながら、それを維持し、朝貢交易を含む海上交易を運営していた。
東南アジア交易圏は、8世紀にシュリヴィジャヤ(尸利仏誓)が興隆したことで成立したとされるが、それは東南アジアを中継地とした東西交易を念頭においたものである。その成熟は、10世紀以降における中国人商人の直接進出、ジャワにおけるクディリ王朝やその東インドネシアとの交易、そして新シュリヴィジャヤ(三仏斉)の登場を待たねばならなかった。それは、東西交易に対する交易圏としてだけではなく、東南アジアの大陸部と島嶼部を結びつける南北交易、そしてきわめて多数の島嶼を結びつける島間交易として発達し、いわば圏内交易の密度が著しく高まったことにある。
さらに、13世紀にあっては元の来寇による東南アジアの政治地図の塗り替え、そしてモンゴル帝国の分裂による遠距離交易の海上輸送への特化といった、国際的な要因に突き動かされて、東南アジアの交易圏は交易需要が増加させ、全方向の海上交易圏として拡大していった。それを運営したのはいち早く世界宗教となったイスラーム教であった。その最大の結果は、伝統仏教ではなく新興イスラーム教をいただくムラカが興隆したことであった。しかも、このムラカはシュリヴィジャヤなどと違って、今日のシンガポールのように、巨大で単純な中継交易拠点都市として特化したことであった。
これらの時代、東南アジア交易圏は交易品目を増加させ、その構成を変化させる。古代の西方商人が求めてやまなかった金、銀、錫、象牙、黒檀などだけではなく、いまや東南アジア特産品としての林産品、すなわち香辛料の需要がアジアやヨーロッパの国々で増加したことであった。従来、インドのマラバール海岸が胡椒の需要を満たしていたが、東南アジアは別種の長胡椒をも供給することになった。それら胡椒はいわばますます換金作物として栽培されていった。そして、東南アジア限定の香辛料(ナッツメッグやメース、クローヴ)がバンダ諸島やモルッカ諸島から供給されるようになった。
それ以外では、10世紀以後、東西交易に中国からの輸出品として、従来の絹や絹織物ばかりでなく、陶磁器が加った。それらは中国人商人を通じて、東南アジアばかりでなくインド、ペルシア、さらにトルコなどに持ち込まれることとなった。イスラーム商人は、東南アジアに中国の産品を持ち込んで商いをしていた。特に、香辛料を買うにあたっては、中国で購入した磁器ばかりでなく、インドで仕入れた綿織物をもって、その支払いとした。このことは、一面では東南アジアから購入する香辛料が大量になり、また東南アジアが次第に富裕となり、新奇なものを需要するようになったことを示そう。
こうした東西交易における交易品の構成変化によって、シルクロードはいまや中国からみればセラミックロードともなり、東南アジアからみればスパイスロードとなったことを意味しよう。しかし、中国の産品の見返りとしての東南アジアの産品や、さらに西方の産品に決定的な大きな変化があったとはみられない。
これらは東南アジアを経由する東西交易品であるが、それ以外に圏内交易品として米をはじめ、サゴ澱粉、果実などの生活必需品や綿花、獣皮といった原料品が加ったことは見落とせない。それは東南アジア交易圏がいままでの贅沢品交易から脱皮したこと、すなわち交易圏として成熟したことを意味しよう。なお、この米は生活必需品であるが、前述の贅沢品である陶磁器とともに、重量貨物として底荷貨物(ベースカーゴ)として、海上輸送の安全、確実さを高める役割を果たしたことであろう。
すでに前章でも述べたことであるが、東南アジアの歴史は海上交易の歴史そのものであるにもかかわらず、それに参入した交易国や交易ネートワーク、交易品目についてはそれなりに明らかとなるが、それを担った商人や官僚、その交易の仕組みについては一部しか知ることができない。海上交易の数理はほぼ皆無である。そのため、朝貢交易とともに民間交易が行なわれたことになっているが、その交易の分担や実務が不明であるため、その時代の交易の性格は総体として明らかとなったとはいいがたい。
いま上でみたように、マラッカ海峡を経由する交易ネットワークを、多くの政治勢力が興亡を繰り返しながら支配してきたが、その支配のための海軍力がどのように編成され、どのように遠征したかについて大いに知りたいものである。また、冒頭に述べたように西・南アジアの船が中国にまで航海したとか、中国船もインドまで航海したとかのようにいわれているが、それがどのような船で、どのような交易をしたかもまた判然としない。
こうした無い物ねだりはさておき、東南アジア交易圏は14世紀末にはその交易ネートワークの面でも交易品目の上でも、来る「交易の時代」を完全に準備することとなった。