 �z�[���y�[�W�� |
 �ڎ��ɖ߂� |
| |
3�E1�E4�E4 �I�����_��nj����āA�C��e����ڎw��
3.1.4.4 Pursuing Netherlands, aiming for Maritime Supremacy
���`��������̑嗧�ĎҁA�������Ŏ��S��
�@�C���O�����h�̗A�o��16���I���ɂ����Ď�A�������A����͏��Ƃ��̂��̂łȂ����Ƃ̗��D�ɂ����̂ł������B1580�N��͎��������̃u�[���ƂȂ����B�A���}�_�͑��̗��P���3�N�ԁA���Ȃ��Ƃ�236�ǂ��̃C���O�����h�D�������������s���Ă������A���D�̂قƂ�ǂ�����ɓ]�����Ă����B���Ȃ��Ƃ�299�ǂ�40������ނ̏��i�ƂƂ��ɁA�ߊl���Ă���B�N�Ԃ̕ߊl�z��10������ނ��Ă���A�A���}�_�C��O�̃C�x���A�Ƃ̌��Պz�Ƃقړ����������B
�@�u�����ɂ������́A�C���O�����h�̑S�A���z�̖�10-15�߰��Ăł������B�����������A���������ς|���g�K���̃J���b�N��ߊl�ł����킯�ł͂Ȃ��A1589�N����1591�N�ɂ����Ă�271��̉����͂���ƁA���ϗ��v�͓������ꂽ�Œ莑�{��60�߰��Ă��܂��Ȃ����x�ł������c�c�����A�푈�͑D���A�������ՁA�����đD���̖����]���ɂ��A�����̌o�ϓI�Ȑ��ʂU�������B�Љ�I��p�͌X�̊�ƉƂ̊���̂Ȃ��ɂ́A�قƂ�Ǔ����Ă��Ȃ������v�i�z�[�v��9�́Ap.150�j�B
�@1589�N���Ȃ킿�A���}�_�͑���j�������N�A�C���O�����h�̓C�M���X�C����ʉ߂��邷�ׂĂ̑D���ɁA�C�R�����s�̒ʍs����Ȃ���Β�D�����邱�ƂƂ����B����ɂ��A�o���g�C����C�x���A�����Ɍ������n���U�����̑D���A��60�ǝ\�߂��Ă���B�܂��A����2�N�ԂɁA���Ȃ��Ƃ�10������ޑ����̍������A�C���O�����h�̎����D�����D�����������Ń����h���̍����̒l�i��������A�V�����H�K�������ݏo���ꂽ�Ƃ����B
�@���̂悤�ɁA�A���}�_�͑��̔s�k�ɂ���Ĥ���������͂���Ȃ�g����݂��邪��������v���オ��킯�ł͂Ȃ�������h���C�N�Ƃ����ǂऎ����q�C�Ɏ��s���悤���̂Ȃ礏������碐_�Ȃǂ��͂��Ȃ��B���̔n���͕��m�Ƃ��ďo�����A�q�t�ɂȂ��ċA���Ă�����ƁA������������n���ł������B
�@1591�N�A�O�����r���͖�15�ǂ̑D���𗦂��A�X�y�C���̍���D��r���ŒD�����߁A�A�]���X�������Ɍ������B53�ǂ̃X�y�C���D�����������̍���D����q���Ȃ���߂Â��Ă����B�C���O�����h�̑D���͑ދp����B�O�����r���͓����x��đD�c���痣��Ă��܂����A����ɉ����邱�ƂȂ��A�X�y�C���D�̐��ɓ˓������Ƃ����B15�ǂ̃K���I����5000�l�̕��͂ƁA15���Ԃɂ킽��ڌ���̌�A190�l���g�݂̃��x���W�����ߊl�����B������A����ꂽ�O�����r���̓X�y�C���̊��D�̂Ȃ��ŁA���𗎂��B���̃��x���W���́A�X�y�C���Ƃ̑S��Ԋ��Ɏ���ꂽ�A�B��̉����D�ƂȂ����B
�@���[���[�́A1591�N�������Ăт͂��߁A600�݁A300�݂Ƃ�������^�D���܂�25�ǂ̑�D�c���v�����[�g����B��92�N8���A�|���g�K���Ђ̍���D�}�h���E�f�E�f�B�I�X�i�_�̕�j����ߊl����B���̐ωׂ̊z�́A�M�����A�Ӟ��A�����ȂǁA���z20������ށA����14������ނƂ������z�������B1�ǂ̑D����̗��D�z�Ƃ��āA�j��ō��z�ł������Ƃ����B
�@���[���[��������z�͌���31,380����ނł���A���̂���14,740����ނ������Ƃɕ��z���ꂽ�B������p��2500����ގ�ł������B���̌��ʂɂ��āA���[���[�͢�킸���Ȍ��Ԃ肾�B�ނ�ɋ��Ǝ�点�Ă��A����ȏ�҂����͂�����ƒQ�����Ƃ����B
�@����ɂ͗��R���������B���[���[���G���U�x�X�����̎����Ɣ閧���Ɍ������Ă������Ƃ����o����B�����Ƃ̌����͏����ւ̗���ł������̂ŁA�ނ̓����h�����ɗH����Ă����B�����ŁA�����q�C�ł��������O�̗��v�̈ꕔ�������o�����ƂŁA�A�����Ɋ��C�������Ă����������ł������B
�@���[���[�̒����ɉ����1595�N�z�[�L���Y��h���C�N�Ƃ������A�X�y�C���̃A���}�_�͑��Ƃ̊C��������ɓ����ƂƂ��ɁA�`��������𐔑�ɂ킽���Ĉꑰ�̉ƋƂƂ��A�܂������l���̂Ȃ��ŃV���W�P�[�g��g��ł����嗧�Ď҂������A�������Ŏ��S���顔ނ�͢�C�̉p�Y��Ƃ��ē����Ă���������̎��ɕ��͑���̑D�������Ɠ����悤�ɁA�D���ł̕a���ł�������X�Ȃ邩�Ȃł���B�Ȃ��A���[���[�͒��������邪�A�V���̑��ʂ�j�~�����Ƃ����l�߂ŁA1618�N���Y�ƂȂ��Ă���B
�@1588�N�A�L���x���f�B�b�V���̓h���C�N�ɑ����A3�l�ڂ̐��E���q��B�����Ă���B�܂��A1593�N���`���[�h�E�z�[�L���Y�����E���q�Ɍ��������A�y���[���ŃX�y�C���͑��ɐ���ĕߗ��ƂȂ��Ă���B���̃z�[�L���Y�̐��E���q�v��ɂ��āA���i���h��z�[�v���w�V�C�M���X�C�^�j�x��9�͂��A���Ȃ�ڍׂɏЉ�Ă���B
���n���C���Ղ̍ĊJ�A�ΒY�̍����O���Ձ�
�@�C���O�����h�ƃX�y�C���Ƃ̐푈���I���ƁA���̂������̌��Ղ��ĊJ����A�n���C�Ƃ̌��Ղ�����B�����̌��ՂɃC���O�����h�̐��C�݂̏��l���Q�����Ă���B����ɂƂ��Ȃ��A�������Ղ͓�����Ђ����ɔC���Ă����ׂ����Ƃ���������h���ƊE�̏]������̎咣�͌��������ɂ��炳��A1604�N�X�y�C����t�����X�Ƃ̌��Ղ͂��ׂẴC���O�����h�l�ɊJ�������Ɛ錾�����
�@�O�\�N�푈�i1618-48�j���N����B�C���O�����h�l�̊S�̓t�����X�Ƃ̏@���푈�ɂ���āA1620�N��O���Ɏ��������Q�i300�Ǥ���̂���100�g���ȏ�̑D100�ǁj���A1620�N��㔼�ɉ��邱�Ƃɂ�������������A��x���������Q�ͤ�ĂѓG���痩�D���邱�ƂŒ������ł�����̂ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���������ɂ�����t�����X�Ƃ̌��Ղ��d�v�ɂȂ��Ă�������ł���B
�@�C���O�����h�̒n���C���Ղ́A�����@���g��Ђ̎�ōs���Ă����B���̂����A�C�^���A��M�V���A�Ƃ̌��Ղ́A�Ǝ��̔��f����A���F�l�c�B�A�̓������ɓ��邱�Ƃōs���Ă����B�܂��A���A�W�A��V���A�Ƃ̌��Ղ�����ɍs���Ă����B17���I���Έȍ~�A���R�`�̃��O�z�[���i�����H���m�j���o�R���āA�C�^���A�����ɖѐD����A�o����悤�ɂȂ�B
�@�����@���g��Ђ́A1600�N29�ǂ̑D��n���C���ՂɎg�p���Ă������A���̂���17�ǂ��p�D�ł��褎c���12�ǂ͎��БD��100�g������350�g���܂ł̑傫���ł�������C���O�����h�D�́A�������ǂ������̂Œn���C�ōD�܂ꤒn���C�̍`�X��n������ģ�1�N��2�N���߂����̂���ł����������͌��ݤ��O���Ԍ��ՂƌĂ����Ղł���
�@�����@���g��Ђͤ���O�z�[����W�F�m���@�ɉ�����}���Z�[����U���e��Z�t�@�[�j�A�i�C�I�j�A�����̌��P�t�@���j�[�A���j��N���^��R���X�^���`�m�[�v����A���N�T���h���b�^(�A���b�|�̊O�`�ł��錻�C�X�P���f�������邢�̓X�J���f���[��)��X�~���i��L�v���X��g���|����A���N�T���h���A������ăA���W�F�Ɗ�`���Ă�����ނ�́A�C���O�����h�Y�̖ѐD�������X�Y������Đ����g���R��y���V�A�Y�̖��n�̌��z��ȕz����w�A������u�h�E������Ă���������傭��(�v�H�q)�ƌ������Ă����
�@1605�N�A�W�F�[���Y1���̓����@���g��Ђɓ�������X�V���āA���̊������i��Ƃ����B���̉�Ђ͑����̏n���D���ݏo�����^�D����Ă��Ƃ����Ă���B1615�N�̃C���O�����h�̐����@�߂ͤ��̍q�C����\�������顂���ͤ�C���O�����h�D�܂��͒n���C�̓��Y�`�̑D�ɂ���ėA�����Ȃ���Τ�n���C����̗A���͋֎~����Ƃ������̂ł������B�����A�n���C�̍��̑D�͂قƂ�ǃC�M���X�C���ɓ����Ă��Ȃ��Ȃ��Ă����B
�S��Ό��������r�[����Ζ�ȂƂ̐����H��̈�ʓI�ȔR���ƂȂ�B���̔R���]���ɂ���čH�ꐻ�i�̗ʎY�����\�ƂȂ�B����͑����Y�Ɗv���ƌĂ�邱�ƂƂȂ�B
�@�C���O�����h�̖c���͐ΒY����łȂ����Ƃ̔��B�ɂ������Ă���A�D����D���̑�K�͂Ȏg�p�҂ƂȂ��Ă����B1614�N�A�C���O�����h�̓��C�݂̍`�����ŁA100�ǂ̑D���A�C�X�����h�̋��Ƃɏ]�����Ă����B�����菬�^�̑D���k�C�ł͑�ʂɎg���Ă����B�f�{����R�[���E�H���A�h�[�Z�b�g����A�j���[�t�@���h�����h�̐̃^�����Ƃ�200�Ljȏ�̑D��������Ă����B
���I�����_�A�t���C�g�̊J���ƑS���ʓI�Ȑi�o��
�@�G���U�x�X�����̌�p�҂ł���W�F�[���Y1���́A���l��D���̌�돂�ɂȂ�C���Ȃ��A�C�R���܂������������������ł������B���̐Ղ��`���[���Y1���i�݈�1625-49�j���p�����A����獑���̎���A�I�����_���S�����ɂ߂邱�ƂƂȂ�B15���I�ȍ~�A�I�����_�l�͉��͂Ƃ�����A��݂��o���ς݂���D��t���C�g���J�����Ă����B����͑�ʂ̉ݕ���A������悤�ɍ���A�����̊C��ł������ł������A���Ƃɂ��g����D�ł������B
�@16���I�ɂȂ�ƁA�o�X��200�݈ȏ�̋���ς�ŋA�`���邱�Ƃ��ł����B�������I��Ήݕ��D�Ƃ��Ďg��ꂽ�B16���I���ɂ́A�t���C�g���o�ꂷ��B���̃t���C�g�́A�C���O�����h�̑��D�ƂɌv��m��Ȃ��e����^�����B�^���p�o�X�̒����ƃr�[�����̔䗦��4:1�ł��������A1610�N�̃t���C�g�̔䗦��6:1�ƂȂ�A�ݕ����ő���A�ς݂���悤�Ȑv�ƂȂ����B�����̃t���C�g�͖�150�݂��炢�ł��������A���̃g�����͋}����200�݂Ƒ傫���Ȃ�A400�݈ȏ�����������悤�ɂȂ����B
�@17���I�A�I�����_�̓n���U��������o���g�C�̔e����D�������ƂŁA�C���O�����h�Ƃ̋����ɐS�z����K�v���Ȃ��Ȃ����B�I�����_�D�́A�Ⴂ�����̎�������āA��D���Ō��������D���g���āA�C���O�����h�D��3����1�̔�p�ʼn^�q�����B�I�����_��1600�N�ɂ�1000�Ljȏ�̏��D�Ƃ��̖�3�{�̋��D��ۗL���Ă����B17���I���܂ŁA�C���O�����h�l�̓o���N�ݕ����I�����_�D�ɐς�ŁA�A�����Ă����B
�@�I�����_�̊C����Ղ́A�o���g�C�̍����Ɩ؍ށA�����Ėk�C�̋��Ƃɂ���Ďx�����A�C���O�����h���D�ʂɗ����Ă����B1550-1650�N�A�I�����_�l���X�J�Q���N�C����ʉ߂���ݕ��ʂ̖�3����2�������悤�ɂȂ�A1200�ǂ̃I�����_�D�����N�o���g�C�Ŋ�������悤�ɂȂ����B�����A�o���g�C�ɓ���C���O�����h�D�́A16���I�㔼2�{�ɂȂ������A1604-1624�N�ɂ͔N���ς킸��100�ǒ��x�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�I�����_�l�͓Ɨ��푈���͂��߂�ƁA�����ɐ��C���h�����ɂ����Ď���������W�J����B����ɁA1595�N�����疈�N100�ǂ��̑D�����x�l�Y�G���̃A�������ɉ�������A���������o���悤�ɂȂ�B�܂��A16���I���A�I�����_�̖��A�Ǝ҂��u���W�����Ɍ���͂��߁A�I�����_�̓z��D��1606�N�g���j�_�b�h���Ɍ����B
�@�z�[�v���ɂ��A�u�C���O�����h�ƃI�����_�Ƃ̊W�͂��܂�ϖe���A���ɊC�m�ɂ��Ă͎��i�A���S�A�����ēG�̊W�ƂȂ����B�C���O�����h�̊C�O�ɑ���o�ϓI�ȊS���[�܂�ɂ�A�����Ƃ��Ă̌ւ肪���܂��Ă������B�I�����_�Ƃ̍ŏ��̐푈�̎�Ȍ����ƂȂ����A�C���O�����h�l�̍����ɑ���h���S�ͤ����ȃi�V���i���Y���̌���ł������v�i�z�[�v��10�́Ap.171�j�B
���I�����_�ɑR���āA���C���h��Ђ̐ݗ���
�@�A���}�_�Ƃ̊C����10�N�Ԃ͕����オ��10�N�Ԃł͂Ȃ������B�������A�����͑����̒j�������C�Ɉ������ꂽ�B�G���U�x�X����̐����Ƃ́A�D�ƑD�����A���Ə�̕x�Ɨ͂̌��Ƃ݂Ȃ��Ă����B
�@�X�y�C���Ƃ̒����̐푈�̂������ɁA�C���O�����h���\�߂����D��1000�ǂ��\���ɉz���A����ɂ���Ď��������̑D�����������Ă����B����́A1�ǂ�50�݂Ƃ����50,000�݁A��g��15�l�Ƃ����15,000�l�Ƃ����傫���ł���B1582-1629�N�ԁA�C���O�����h�ۗ̕L���D�D����70�߰��Ĉȏ��������115,000�݂ɂȂ�A200�݈ȏ�̐ǐ����킸��18�ǂ���145�Ljȏ�ɑ��������B
�@�C���O�����h�́A�C�x���A�Ɍ������n���U�D�����I�ɍS�����Ă����B����ɑ��āA�h�C�c�͍�������C���O�����h���Րl��Ǖ�����B���̕Ƃ��āA1597�N�A�C���O�����h�̓n���U�����̋��_�ł����������h���̃X�e�B�����[�h�������B�������A1579�N�ɐݗ����ꂽ�C�[�X�g�����h��Ђ̃����o�[�̓o���g�C�̌��Ղ𑱂��Ă���A�_���c�B�q��|�[�����h�̃G���u�����O�A���V�A�̃P�[�j�r�X�x���O�̏��l�����ƁA�D�p�i��⋋���邽�߁A������ѐD���ƌ������Ă����B�|�[�����h�����̐����[���b�p�ւ̗A�o�́A�قƂ�ǂ��f���}�[�N�D�ɐς܂�A���̒n���L���ɂ��Ă����B
�@�C���O�����h�̌��Ղ͂܂��܂��C���O�����h�l�̎�ōs����悤�ɂȂ����B����ɂ�����C���O�����h�ƃI�����_�̏㏸�A�����ɂ�����X�y�C���ƃ|���g�K���̑��ΓI�Ȑ��ނ��N����B��҂̐��ނ́A��������n���C�ɂ����鑢�D�p�؍ނ̌����ȕs���Ɋ�Â��Ă����B�C���O�����h�ƃf���}�[�N�Ƃ́A���D�p�̖؍ނ⎑�ނ��o�ϓI�Ɋm�ۂł���A���[���b�p�̖k���C��ɂ���Ƃ����i�D�̈ʒu���߂Ă����B
�@1594�N�A�I�����_�̃A���X�e���_���ʼn�����Ђ��ݗ�����A�R���l���X��h��n�E�g�}���i1560-99�j��Ɏw�����ꂽ3�ǂ̃K���I�����A�W�A�Ɍ������B1596�N6���W�����̍`���o���^���i���݂̃o���e���j�ɓ������1597�N8����3��89�l���A�����額��h���̎���͏����ł͂Ȃ���������A�W�A�ւ̍q�H�J��ɐ�������
�@����Ɏh������āA1598�N���玟�X�ƃt�H�[���E�R���p�j�[�G��(��쏔���)�ƌĂꂽ��Ђ��ݗ������B1601�N�܂ł�15�D�c65�ǂ��A�W�A�Ɍ������Ă���B�C���O�����h�͂킸��1��ł������B�I�����_�l�́A�|���g�K���̃A�W�A�i�o���_�����X�Ɣj�āA�|���g�K���l�̃X�p�C�X�Ɛ肪������B1600�N�ɁA��q�̃����h�����C���h��Ђ��ݗ����ꂽ���Ƃ̓I�����_�ɂƂ��ċ��ЂƂȂ�A1602�N��쏔��Ђ��������āA�I�����_�A�����C���h��Ђ��ݗ������B
�@�I�����_�����C���h�ɐi�o�������Ƃ́A�A�W�A�̍��h����n���C�o�R�ň����Ă��������@���g��ЂɂƂ��āA�傫�ȋ��Ђł������B�C���O�����h�́A�I�����_�̓��C���h�i�o���d�����āA1598�N�W������f�[���B�X�i1550?-1605�j���I�����_�̐���Ђɏo��������B
�@�ނ́A�I�����_��2��ڂ̓��C���h�ւ̍q�C�ɂ������Ȑ���ē��l�Ƃ��Čق��A1600�N6���ɃC���O�����h�ɖ߂��ė���B�ނ́A1585-87�N3��ɂ킽��f�[���B�X�C����T�����Ă��������ȍq�C�҂ł���A�܂�1591�N�̎��s�ɏI������L���x���f�B�b�V���̓��C���h�����ɂ��Q�����Ă����B
�@���̃f�[���B�X�́A���ɏq�ׂ郉���J�X�^�[���w�����铌�C���h��Ђ̉����̐���ē��l�ƂȂ�A1605�N�V���K�|�[���C���ɂ��錻�C���h�l�V�A�̃r���^�����Ř`���ɏP���āA���S�����Ƃ����B�܂��A�ނ�1594�N�ɂ́w�U��V�[�}���Y��V�[�N���b�g�x(�D���̉��`)�����s���Ă���B���̎������ɂ����āA�C���O�����h�l�͑��̍����ɂ��Ȋw�I�Ȓm���ɗ���Ă���ƒQ���Ă���B���̖{��1594�N����1647�N�ɂ�����8������肳��Ă���B
�@1599�N9���A1000�l�ȏ�̃����h���̏��l��3������ނ�p�ӂ��A�u���N���ɓ��C���h�����Ƃ��̑��̓��⍑�Ɍ������A���n�Ō��Ղ���q�C���d���Ă�v���Ƃɂ����B1599�N12��31���A�G���U�x�X�������碎�t�����̂��ׂĂ̓y�n��Ɋւ��钺�����t�����B
�@�C���O�����h�̗A�o��16���I���ɂ����Ď�A�������A����͏��Ƃ��̂��̂łȂ����Ƃ̗��D�ɂ����̂ł������B1580�N��͎��������̃u�[���ƂȂ����B�A���}�_�͑��̗��P���3�N�ԁA���Ȃ��Ƃ�236�ǂ��̃C���O�����h�D�������������s���Ă������A���D�̂قƂ�ǂ�����ɓ]�����Ă����B���Ȃ��Ƃ�299�ǂ�40������ނ̏��i�ƂƂ��ɁA�ߊl���Ă���B�N�Ԃ̕ߊl�z��10������ނ��Ă���A�A���}�_�C��O�̃C�x���A�Ƃ̌��Պz�Ƃقړ����������B
�@�u�����ɂ������́A�C���O�����h�̑S�A���z�̖�10-15�߰��Ăł������B�����������A���������ς|���g�K���̃J���b�N��ߊl�ł����킯�ł͂Ȃ��A1589�N����1591�N�ɂ����Ă�271��̉����͂���ƁA���ϗ��v�͓������ꂽ�Œ莑�{��60�߰��Ă��܂��Ȃ����x�ł������c�c�����A�푈�͑D���A�������ՁA�����đD���̖����]���ɂ��A�����̌o�ϓI�Ȑ��ʂU�������B�Љ�I��p�͌X�̊�ƉƂ̊���̂Ȃ��ɂ́A�قƂ�Ǔ����Ă��Ȃ������v�i�z�[�v��9�́Ap.150�j�B
�@1589�N���Ȃ킿�A���}�_�͑���j�������N�A�C���O�����h�̓C�M���X�C����ʉ߂��邷�ׂĂ̑D���ɁA�C�R�����s�̒ʍs����Ȃ���Β�D�����邱�ƂƂ����B����ɂ��A�o���g�C����C�x���A�����Ɍ������n���U�����̑D���A��60�ǝ\�߂��Ă���B�܂��A����2�N�ԂɁA���Ȃ��Ƃ�10������ޑ����̍������A�C���O�����h�̎����D�����D�����������Ń����h���̍����̒l�i��������A�V�����H�K�������ݏo���ꂽ�Ƃ����B
�@���̂悤�ɁA�A���}�_�͑��̔s�k�ɂ���Ĥ���������͂���Ȃ�g����݂��邪��������v���オ��킯�ł͂Ȃ�������h���C�N�Ƃ����ǂऎ����q�C�Ɏ��s���悤���̂Ȃ礏������碐_�Ȃǂ��͂��Ȃ��B���̔n���͕��m�Ƃ��ďo�����A�q�t�ɂȂ��ċA���Ă�����ƁA������������n���ł������B
�@1591�N�A�O�����r���͖�15�ǂ̑D���𗦂��A�X�y�C���̍���D��r���ŒD�����߁A�A�]���X�������Ɍ������B53�ǂ̃X�y�C���D�����������̍���D����q���Ȃ���߂Â��Ă����B�C���O�����h�̑D���͑ދp����B�O�����r���͓����x��đD�c���痣��Ă��܂����A����ɉ����邱�ƂȂ��A�X�y�C���D�̐��ɓ˓������Ƃ����B15�ǂ̃K���I����5000�l�̕��͂ƁA15���Ԃɂ킽��ڌ���̌�A190�l���g�݂̃��x���W�����ߊl�����B������A����ꂽ�O�����r���̓X�y�C���̊��D�̂Ȃ��ŁA���𗎂��B���̃��x���W���́A�X�y�C���Ƃ̑S��Ԋ��Ɏ���ꂽ�A�B��̉����D�ƂȂ����B
�@���[���[�́A1591�N�������Ăт͂��߁A600�݁A300�݂Ƃ�������^�D���܂�25�ǂ̑�D�c���v�����[�g����B��92�N8���A�|���g�K���Ђ̍���D�}�h���E�f�E�f�B�I�X�i�_�̕�j����ߊl����B���̐ωׂ̊z�́A�M�����A�Ӟ��A�����ȂǁA���z20������ށA����14������ނƂ������z�������B1�ǂ̑D����̗��D�z�Ƃ��āA�j��ō��z�ł������Ƃ����B
�@���[���[��������z�͌���31,380����ނł���A���̂���14,740����ނ������Ƃɕ��z���ꂽ�B������p��2500����ގ�ł������B���̌��ʂɂ��āA���[���[�͢�킸���Ȍ��Ԃ肾�B�ނ�ɋ��Ǝ�点�Ă��A����ȏ�҂����͂�����ƒQ�����Ƃ����B
�@����ɂ͗��R���������B���[���[���G���U�x�X�����̎����Ɣ閧���Ɍ������Ă������Ƃ����o����B�����Ƃ̌����͏����ւ̗���ł������̂ŁA�ނ̓����h�����ɗH����Ă����B�����ŁA�����q�C�ł��������O�̗��v�̈ꕔ�������o�����ƂŁA�A�����Ɋ��C�������Ă����������ł������B
�@���[���[�̒����ɉ����1595�N�z�[�L���Y��h���C�N�Ƃ������A�X�y�C���̃A���}�_�͑��Ƃ̊C��������ɓ����ƂƂ��ɁA�`��������𐔑�ɂ킽���Ĉꑰ�̉ƋƂƂ��A�܂������l���̂Ȃ��ŃV���W�P�[�g��g��ł����嗧�Ď҂������A�������Ŏ��S���顔ނ�͢�C�̉p�Y��Ƃ��ē����Ă���������̎��ɕ��͑���̑D�������Ɠ����悤�ɁA�D���ł̕a���ł�������X�Ȃ邩�Ȃł���B�Ȃ��A���[���[�͒��������邪�A�V���̑��ʂ�j�~�����Ƃ����l�߂ŁA1618�N���Y�ƂȂ��Ă���B
�@1588�N�A�L���x���f�B�b�V���̓h���C�N�ɑ����A3�l�ڂ̐��E���q��B�����Ă���B�܂��A1593�N���`���[�h�E�z�[�L���Y�����E���q�Ɍ��������A�y���[���ŃX�y�C���͑��ɐ���ĕߗ��ƂȂ��Ă���B���̃z�[�L���Y�̐��E���q�v��ɂ��āA���i���h��z�[�v���w�V�C�M���X�C�^�j�x��9�͂��A���Ȃ�ڍׂɏЉ�Ă���B
���n���C���Ղ̍ĊJ�A�ΒY�̍����O���Ձ�
�@�C���O�����h�ƃX�y�C���Ƃ̐푈���I���ƁA���̂������̌��Ղ��ĊJ����A�n���C�Ƃ̌��Ղ�����B�����̌��ՂɃC���O�����h�̐��C�݂̏��l���Q�����Ă���B����ɂƂ��Ȃ��A�������Ղ͓�����Ђ����ɔC���Ă����ׂ����Ƃ���������h���ƊE�̏]������̎咣�͌��������ɂ��炳��A1604�N�X�y�C����t�����X�Ƃ̌��Ղ͂��ׂẴC���O�����h�l�ɊJ�������Ɛ錾�����
�@�O�\�N�푈�i1618-48�j���N����B�C���O�����h�l�̊S�̓t�����X�Ƃ̏@���푈�ɂ���āA1620�N��O���Ɏ��������Q�i300�Ǥ���̂���100�g���ȏ�̑D100�ǁj���A1620�N��㔼�ɉ��邱�Ƃɂ�������������A��x���������Q�ͤ�ĂѓG���痩�D���邱�ƂŒ������ł�����̂ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���������ɂ�����t�����X�Ƃ̌��Ղ��d�v�ɂȂ��Ă�������ł���B
�@�C���O�����h�̒n���C���Ղ́A�����@���g��Ђ̎�ōs���Ă����B���̂����A�C�^���A��M�V���A�Ƃ̌��Ղ́A�Ǝ��̔��f����A���F�l�c�B�A�̓������ɓ��邱�Ƃōs���Ă����B�܂��A���A�W�A��V���A�Ƃ̌��Ղ�����ɍs���Ă����B17���I���Έȍ~�A���R�`�̃��O�z�[���i�����H���m�j���o�R���āA�C�^���A�����ɖѐD����A�o����悤�ɂȂ�B
�@�����@���g��Ђ́A1600�N29�ǂ̑D��n���C���ՂɎg�p���Ă������A���̂���17�ǂ��p�D�ł��褎c���12�ǂ͎��БD��100�g������350�g���܂ł̑傫���ł�������C���O�����h�D�́A�������ǂ������̂Œn���C�ōD�܂ꤒn���C�̍`�X��n������ģ�1�N��2�N���߂����̂���ł����������͌��ݤ��O���Ԍ��ՂƌĂ����Ղł���
�@�����@���g��Ђͤ���O�z�[����W�F�m���@�ɉ�����}���Z�[����U���e��Z�t�@�[�j�A�i�C�I�j�A�����̌��P�t�@���j�[�A���j��N���^��R���X�^���`�m�[�v����A���N�T���h���b�^(�A���b�|�̊O�`�ł��錻�C�X�P���f�������邢�̓X�J���f���[��)��X�~���i��L�v���X��g���|����A���N�T���h���A������ăA���W�F�Ɗ�`���Ă�����ނ�́A�C���O�����h�Y�̖ѐD�������X�Y������Đ����g���R��y���V�A�Y�̖��n�̌��z��ȕz����w�A������u�h�E������Ă���������傭��(�v�H�q)�ƌ������Ă����
�@1605�N�A�W�F�[���Y1���̓����@���g��Ђɓ�������X�V���āA���̊������i��Ƃ����B���̉�Ђ͑����̏n���D���ݏo�����^�D����Ă��Ƃ����Ă���B1615�N�̃C���O�����h�̐����@�߂ͤ��̍q�C����\�������顂���ͤ�C���O�����h�D�܂��͒n���C�̓��Y�`�̑D�ɂ���ėA�����Ȃ���Τ�n���C����̗A���͋֎~����Ƃ������̂ł������B�����A�n���C�̍��̑D�͂قƂ�ǃC�M���X�C���ɓ����Ă��Ȃ��Ȃ��Ă����B
| �@�j���[�J�b�X����A�|����^�C���́A�k�����[���b�p�Ƃ̌��Ղɓ������čD�ʒu���߂Ă����B��w�n����Y�o�����C���Y�̂قƂ�ǂ͓�Ɍ������A���̖��������h���ɑ���ꂽ�B�j���[�J�b�X���̐ΒY�̔N�ԑD�ϗʂ́A16���I�㔼�A4�{����������14���݁A������1634�N�ɂ�40���݈ȏ�ƂȂ����B���̑S���̂T����4���C���O�����h�̊C�݈�тɗA������A���̎c��͊O���D�ɂ���đ嗤�Ɍ��������B �@�ΒY�A�o�ɂ͏d�ł��ۂ����Ă���A����͒�R�X�g�̊O���D�łȂ���Ή^�ׂȂ��قǂ̍����ł������B�n���U�����̑D���ΒY���t�����h���ɉ^�сA�܂��t�����X�l��50�ǂ̑D�c��g��ŗ��K���A�ΒY���t�����X�Ɏ����A���Ă����B1615�N�A400�Ljȏ�̃C���O�����h�D���ΒY���Ղɏ]�����Ă���A1606�N1�ǂ������h���Ɉړ������ΒY�͕���73�݂ł��������A1638�N�ɂȂ��2�{�ɑ���139�݂ƂȂ����B �@16���I�㔼����17���I���ɂ����A�C���O�����h�ł͐ΒY���H�ƔR���Ƃ��ĕ��y���͂��߂�B17���I���߂ɂ́A�ΒY�͗��������K���X��| |
 |
| |
|
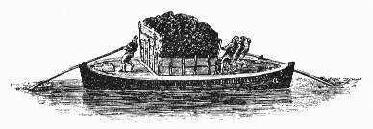 |
|
| �Y�z����`�܂ŁA�ΒY���~�낷��D ���{�����ł́A��Ђ炽�Ƃ����� |
�@�C���O�����h�̖c���͐ΒY����łȂ����Ƃ̔��B�ɂ������Ă���A�D����D���̑�K�͂Ȏg�p�҂ƂȂ��Ă����B1614�N�A�C���O�����h�̓��C�݂̍`�����ŁA100�ǂ̑D���A�C�X�����h�̋��Ƃɏ]�����Ă����B�����菬�^�̑D���k�C�ł͑�ʂɎg���Ă����B�f�{����R�[���E�H���A�h�[�Z�b�g����A�j���[�t�@���h�����h�̐̃^�����Ƃ�200�Ljȏ�̑D��������Ă����B
���I�����_�A�t���C�g�̊J���ƑS���ʓI�Ȑi�o��
�@�G���U�x�X�����̌�p�҂ł���W�F�[���Y1���́A���l��D���̌�돂�ɂȂ�C���Ȃ��A�C�R���܂������������������ł������B���̐Ղ��`���[���Y1���i�݈�1625-49�j���p�����A����獑���̎���A�I�����_���S�����ɂ߂邱�ƂƂȂ�B15���I�ȍ~�A�I�����_�l�͉��͂Ƃ�����A��݂��o���ς݂���D��t���C�g���J�����Ă����B����͑�ʂ̉ݕ���A������悤�ɍ���A�����̊C��ł������ł������A���Ƃɂ��g����D�ł������B
�@16���I�ɂȂ�ƁA�o�X��200�݈ȏ�̋���ς�ŋA�`���邱�Ƃ��ł����B�������I��Ήݕ��D�Ƃ��Ďg��ꂽ�B16���I���ɂ́A�t���C�g���o�ꂷ��B���̃t���C�g�́A�C���O�����h�̑��D�ƂɌv��m��Ȃ��e����^�����B�^���p�o�X�̒����ƃr�[�����̔䗦��4:1�ł��������A1610�N�̃t���C�g�̔䗦��6:1�ƂȂ�A�ݕ����ő���A�ς݂���悤�Ȑv�ƂȂ����B�����̃t���C�g�͖�150�݂��炢�ł��������A���̃g�����͋}����200�݂Ƒ傫���Ȃ�A400�݈ȏ�����������悤�ɂȂ����B
�@17���I�A�I�����_�̓n���U��������o���g�C�̔e����D�������ƂŁA�C���O�����h�Ƃ̋����ɐS�z����K�v���Ȃ��Ȃ����B�I�����_�D�́A�Ⴂ�����̎�������āA��D���Ō��������D���g���āA�C���O�����h�D��3����1�̔�p�ʼn^�q�����B�I�����_��1600�N�ɂ�1000�Ljȏ�̏��D�Ƃ��̖�3�{�̋��D��ۗL���Ă����B17���I���܂ŁA�C���O�����h�l�̓o���N�ݕ����I�����_�D�ɐς�ŁA�A�����Ă����B
�@�I�����_�̊C����Ղ́A�o���g�C�̍����Ɩ؍ށA�����Ėk�C�̋��Ƃɂ���Ďx�����A�C���O�����h���D�ʂɗ����Ă����B1550-1650�N�A�I�����_�l���X�J�Q���N�C����ʉ߂���ݕ��ʂ̖�3����2�������悤�ɂȂ�A1200�ǂ̃I�����_�D�����N�o���g�C�Ŋ�������悤�ɂȂ����B�����A�o���g�C�ɓ���C���O�����h�D�́A16���I�㔼2�{�ɂȂ������A1604-1624�N�ɂ͔N���ς킸��100�ǒ��x�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�I�����_�l�͓Ɨ��푈���͂��߂�ƁA�����ɐ��C���h�����ɂ����Ď���������W�J����B����ɁA1595�N�����疈�N100�ǂ��̑D�����x�l�Y�G���̃A�������ɉ�������A���������o���悤�ɂȂ�B�܂��A16���I���A�I�����_�̖��A�Ǝ҂��u���W�����Ɍ���͂��߁A�I�����_�̓z��D��1606�N�g���j�_�b�h���Ɍ����B
�@�z�[�v���ɂ��A�u�C���O�����h�ƃI�����_�Ƃ̊W�͂��܂�ϖe���A���ɊC�m�ɂ��Ă͎��i�A���S�A�����ēG�̊W�ƂȂ����B�C���O�����h�̊C�O�ɑ���o�ϓI�ȊS���[�܂�ɂ�A�����Ƃ��Ă̌ւ肪���܂��Ă������B�I�����_�Ƃ̍ŏ��̐푈�̎�Ȍ����ƂȂ����A�C���O�����h�l�̍����ɑ���h���S�ͤ����ȃi�V���i���Y���̌���ł������v�i�z�[�v��10�́Ap.171�j�B
���I�����_�ɑR���āA���C���h��Ђ̐ݗ���
�@�A���}�_�Ƃ̊C����10�N�Ԃ͕����オ��10�N�Ԃł͂Ȃ������B�������A�����͑����̒j�������C�Ɉ������ꂽ�B�G���U�x�X����̐����Ƃ́A�D�ƑD�����A���Ə�̕x�Ɨ͂̌��Ƃ݂Ȃ��Ă����B
�@�X�y�C���Ƃ̒����̐푈�̂������ɁA�C���O�����h���\�߂����D��1000�ǂ��\���ɉz���A����ɂ���Ď��������̑D�����������Ă����B����́A1�ǂ�50�݂Ƃ����50,000�݁A��g��15�l�Ƃ����15,000�l�Ƃ����傫���ł���B1582-1629�N�ԁA�C���O�����h�ۗ̕L���D�D����70�߰��Ĉȏ��������115,000�݂ɂȂ�A200�݈ȏ�̐ǐ����킸��18�ǂ���145�Ljȏ�ɑ��������B
�@�C���O�����h�́A�C�x���A�Ɍ������n���U�D�����I�ɍS�����Ă����B����ɑ��āA�h�C�c�͍�������C���O�����h���Րl��Ǖ�����B���̕Ƃ��āA1597�N�A�C���O�����h�̓n���U�����̋��_�ł����������h���̃X�e�B�����[�h�������B�������A1579�N�ɐݗ����ꂽ�C�[�X�g�����h��Ђ̃����o�[�̓o���g�C�̌��Ղ𑱂��Ă���A�_���c�B�q��|�[�����h�̃G���u�����O�A���V�A�̃P�[�j�r�X�x���O�̏��l�����ƁA�D�p�i��⋋���邽�߁A������ѐD���ƌ������Ă����B�|�[�����h�����̐����[���b�p�ւ̗A�o�́A�قƂ�ǂ��f���}�[�N�D�ɐς܂�A���̒n���L���ɂ��Ă����B
�@�C���O�����h�̌��Ղ͂܂��܂��C���O�����h�l�̎�ōs����悤�ɂȂ����B����ɂ�����C���O�����h�ƃI�����_�̏㏸�A�����ɂ�����X�y�C���ƃ|���g�K���̑��ΓI�Ȑ��ނ��N����B��҂̐��ނ́A��������n���C�ɂ����鑢�D�p�؍ނ̌����ȕs���Ɋ�Â��Ă����B�C���O�����h�ƃf���}�[�N�Ƃ́A���D�p�̖؍ނ⎑�ނ��o�ϓI�Ɋm�ۂł���A���[���b�p�̖k���C��ɂ���Ƃ����i�D�̈ʒu���߂Ă����B
�@1594�N�A�I�����_�̃A���X�e���_���ʼn�����Ђ��ݗ�����A�R���l���X��h��n�E�g�}���i1560-99�j��Ɏw�����ꂽ3�ǂ̃K���I�����A�W�A�Ɍ������B1596�N6���W�����̍`���o���^���i���݂̃o���e���j�ɓ������1597�N8����3��89�l���A�����額��h���̎���͏����ł͂Ȃ���������A�W�A�ւ̍q�H�J��ɐ�������
�@����Ɏh������āA1598�N���玟�X�ƃt�H�[���E�R���p�j�[�G��(��쏔���)�ƌĂꂽ��Ђ��ݗ������B1601�N�܂ł�15�D�c65�ǂ��A�W�A�Ɍ������Ă���B�C���O�����h�͂킸��1��ł������B�I�����_�l�́A�|���g�K���̃A�W�A�i�o���_�����X�Ɣj�āA�|���g�K���l�̃X�p�C�X�Ɛ肪������B1600�N�ɁA��q�̃����h�����C���h��Ђ��ݗ����ꂽ���Ƃ̓I�����_�ɂƂ��ċ��ЂƂȂ�A1602�N��쏔��Ђ��������āA�I�����_�A�����C���h��Ђ��ݗ������B
�@�I�����_�����C���h�ɐi�o�������Ƃ́A�A�W�A�̍��h����n���C�o�R�ň����Ă��������@���g��ЂɂƂ��āA�傫�ȋ��Ђł������B�C���O�����h�́A�I�����_�̓��C���h�i�o���d�����āA1598�N�W������f�[���B�X�i1550?-1605�j���I�����_�̐���Ђɏo��������B
�@�ނ́A�I�����_��2��ڂ̓��C���h�ւ̍q�C�ɂ������Ȑ���ē��l�Ƃ��Čق��A1600�N6���ɃC���O�����h�ɖ߂��ė���B�ނ́A1585-87�N3��ɂ킽��f�[���B�X�C����T�����Ă��������ȍq�C�҂ł���A�܂�1591�N�̎��s�ɏI������L���x���f�B�b�V���̓��C���h�����ɂ��Q�����Ă����B
�@���̃f�[���B�X�́A���ɏq�ׂ郉���J�X�^�[���w�����铌�C���h��Ђ̉����̐���ē��l�ƂȂ�A1605�N�V���K�|�[���C���ɂ��錻�C���h�l�V�A�̃r���^�����Ř`���ɏP���āA���S�����Ƃ����B�܂��A�ނ�1594�N�ɂ́w�U��V�[�}���Y��V�[�N���b�g�x(�D���̉��`)�����s���Ă���B���̎������ɂ����āA�C���O�����h�l�͑��̍����ɂ��Ȋw�I�Ȓm���ɗ���Ă���ƒQ���Ă���B���̖{��1594�N����1647�N�ɂ�����8������肳��Ă���B
�@1599�N9���A1000�l�ȏ�̃����h���̏��l��3������ނ�p�ӂ��A�u���N���ɓ��C���h�����Ƃ��̑��̓��⍑�Ɍ������A���n�Ō��Ղ���q�C���d���Ă�v���Ƃɂ����B1599�N12��31���A�G���U�x�X�������碎�t�����̂��ׂĂ̓y�n��Ɋւ��钺�����t�����B
| �@���̉�Ђ͓����̌��\�ȏ�̎��{���ł����ďo�������B72,000����ނɂ���1��50����ނƂ��āA�V�F�A�̗\�����邱�ƂƂȂ����B�ŏ��̍q�C���Ƃł́A215�l�̏o���҂���68,373�|���h�̎��Ǝ������W�܂����B�ނ犔�傠�邢�͏o���ҁA�����Ė����́A�����@���g��Ђ̂����Ƃ��Ȃ�d�����Ă���A�܂����㑍�كg�[�}�X��X�~�X (���A1558-1625)�̓����@���g��Ђ̑��قł��������B �@�����Ƀ����h�����C���h��Ђ��a�����A�C���O�����h�l�̐��E���x���ł̍ی��̂Ȃ����Ղւ̎Q���̍��C�ł������B�����A����́A���̑O�r�����ʂ��Ȃ��Ȃ��Ă��郌���@���g���Ղ��A�V�K��Ђł����đ�ւ��悤�Ƃ������̂ł������B�Ȃ�������@���g��Ђ����U����͓̂��C���h��Ђ�葁�����̤̂1825�N�ɂȂ��Ă���ł������ |
 |
 |
| 1617�ANational Portrait Gallery�iLondon�j�� |
1596 �����C�������فi�����h���j�� |
�������J�X�^�[�A���C���h�q�C�ɏo����
�@�����h�����C���h��Ђ̍ŏ��̍q�C�̎w���́A�W�F�[���Y������J�X�^�[�i���A1554?-1618�j�Ɉς˂�ꂽ�B�ނ́A�Ⴂ������|���g�K�����Ղɏ]�����A�܂��A���}�_�͑��Ƃ̐킢�ɎQ�����Ă���B����ɁA���C���h���������s���Ă����B
�@�W�F�[���Y������J�X�^�[�̓I�����_�l��葁���A1591�N3�ǂ̑D�𗦂��ē��C���h��ڎw���B���̑D���́A�A�t���J��[�����A�C���h�œ�[�̃R�����������o�āA�C���h�l�V�A�̃X�}�g�����A�����ă}���b�J�Ɏ������Ƃ���邪�A�A�r�A�����B�����c�����l�X�́A���C���h��������t�����X�D�ɏ���āA1594�N5���A������B����ł��A�ނ͗L�p�Ȓm�������Ƃ����B
�@�����h�����C���h��Ђ̍ŏ��̓��C���h�ւ̍q�C���J�n�����B�W�F�[���Y������J�X�^�[�̓��b�h��h���S�����A�w�N�^�[���A�A�b�Z�V�������A�����ăX�U�����Ƃ����ӋC���V��4�ǂƐH���⋋�D�M�t�g��(130��)������ď�g���⏤�l��500�l�������A��A1601�N2��13���A�E���E�C�b�`����o������B
�@�D�c���W�F�[���Y������J�X�^�[�̓h���S�����ɏ�D�A�f�[���B�X����Ȑ���ē��l�ƂȂ�B�h���S�����̓J���o�[�����h������3700����ނŔ������ꂽ�D�ŁA����܂Ń}���X��X�J�[�W���Ƃ������B���̑D��600�݁A��g��202�l�̑�1���̌R�͂ł������B�W������~�h���g���͕��D�c���Ƃ��āA�w�N�^�[��(300��)��108�l�ƂƂ��ɏ�D�����B�E�B���A����u�����h���w������A�b�Z�V��������260�݂ŁA��g��82�l�ł������B�X�U����(240��)�̓W������w�C���[�h���w�����A���̏�g����88�l�ł������B�����3�ǂ͂���������������̃����@���g���ՑD�ł������B
�@������̑D�͐l���̂ق��A20�������̐H���ƕ���A�e��ł��ӂꂩ����A�܂�7000����ޑ����̏��i��20,000����ޑ����̃X�y�C���d�݂��ςݍ��܂ꂽ�B���̑��D�q�̗]����A�C���ɗZ����������q�C�O�Ɏx�����ꂽ�����ł����Ĕ����t����ꂽ�ݕ��A��ЊW�҂̉ݕ��A�����ĕK���i�ȂǂŖ��ߐs������Ă�����B�S���i�A�X�Y�A���A���L���n�A�f�{���V���Y�J�[�W�[�D�A�����ċ����A����A���ݕ��ł������B
�@�����J�X�^�[�̐����ɂ��A���C���h���ɂ����Ď��R�Ɍ��Ղ���ƂƂ��ɁA�ł��̎Z���ǂ��Ƃ���ʼn��q�̉ݕ����y�b�p�[��X�p�C�X�ƌ������Ă悢�Ƃ�����������Ă����B����́A���ʂ��l���A�������A���b�N�X�A���]�A���ЁA���A�����ċM���悤�S�|���Ă���B
�@7�����������āA��A�t���J�E�P�[�v��^�E���̃e�[�u���p�ɂ��ǂ蒅�����B�ʏ��蒷�����Ԃ��������̂́A�ԓ��̖k���̖����тŁA�����̎��Ԃ��₵�������ł������B���^�D�ł�100�l�ȏ�̒j�������a�Ŏ���ł������A�����J�X�^�[�̃h���S�����͖����ł������B����͈�l��l�ɖ���3�����̃�������W���[�X��^����ƂƂ��ɁA���߂ɂȂ�܂ł͏�g���ɍd���H�����o�����Ƃ��ւ��Ă����B��������W���[�X�̓n�t��v���b�g�i���A1552?-1611�j���p�ӂ������̂ł������B
�@�D�c�́A�a�l�𗤏�Ŏ��Â��邽�߁A�e�[�u���p�ɕd�����Ă���B�Ĕ�����O�A1000�C�̗r��42�C�̗Y�����Z�����炦�āA�H���Ƃ��Đςݍ���ł���B����8����̓S�_1�{�Ɨr1�C�A�S�_2�{�ƗY��1�C���������Ă���B�C���h�m�̂������̓��Ő���⋋���Ă��邪�A����1�̓���13�l�����ꂽ��������Ŏ���ł���B�ނ炪�A�k�X�}�g���̃A�`���i���o���_��A�`���j�ɒ������Ƃ��A�����h���o�Ă��炷�ł�1�N���o���Ă����B
�@�A�`���̉��ɁA�����J�X�^�[�̓G���U�x�X��������̐e���Ƒ��蕨�������o���A��������A�łȂ��̌��ՁA�~��A�ٔ����A�s�ߕߓ����A�����ĐM�̎��R��F�߂鋦��ɏ�����������Ă���B���l�����̓y�b�p�[�����Ǝ��݂����A�����ɂ���͂����Ȃ������B
�@�����J�X�^�[�̓}���b�J�C�������q���A900�݂̃|���g�K���̃J���b�N��\�߂��Ă���B���̑D�̓C���h�̃x���K���n������}���b�J�Ɍ�����600�l�̗��q�Ƌ��ڂ̉ݕ����ڂ����Ă����B�C���O�����h�l�́A�L�����R��s���^�[�h(�ʐF�z�A�o�e�B�b�N�j����������950�������������̑D�Ɉڂ��ւ�����A�J���b�N���ߕ����A�q�C�𑱂��A�A�`���ɖ߂��Ă���B�y�b�p�[���킸�������ς�ł��Ȃ������D���L�����R��ς�Ŗ��D�ƂȂ�A�A�����Ă���B����1�ǂ́A���̃X�}�g�����ł����y�b�p�[�ƃO���[�u�����Ŗ��D�ƂȂ�A����܂��A�����Ă���B
�@���b�h��h���S�����ƃw�N�^�[���̓J���b�N�̎c��ݕ���ς�ŁA�W�������̃o���^���Ɍ����A�������Ă���B�����́A�I�����_�l��1596�N�Ƀ|���g�K���l��ǂ��o�����Ƃ���ł������B�����J�X�^�[�̓o���^���̏Z����I�����_�l�ɉ������}�����A�o���^���̎x�z�҂���C���O�����h�l�͓��n�ŒN�ɂ��ז����ꂸ�Ɍ��Ղł���ƍ������Ă���B�����̏��l�́A�}���[�V�A��C���h�l�V�A�̊e�n�Ɠ����悤�ɁA���łɃo���^���ł���b���ł߂Ă����B
�@5�T�Ԃ�����ƁA�����h�����玝���ė������i��276�܂̃y�b�p�[�ƌ������A����2�ǂ����D�ƂȂ��Ă���B�܂��A�����J�X�^�[�́A�o���^���Ɍ��Պ�n��ݗ����邽�߁A3�l�̏��l�ƒj����8�l���c���Ă���B�܂��A�s���l�X�ɐ��l�̏��l�ƒj�������悹�A�}���b�J�ŏ��ق���낤�Ƒ���o���Ă���B�ނ�2�ǂ̑D�́A1603�N2��21���o���^�����o�����A����9��11���Ƀe���Y��ɋA�����Ă���B
�@�����J�X�^�[���4�ǂ̑D��1�ǂ��������ƂȂ��A�����Ĥ100������ވȏ�ɑ�������y�b�p�[�������A��A�����ɓ����������l��95�߰��Ă̗��v�������炵���B���̊�ՓI�Ȑ����ɂ���āA�C���O�����h�ɂƂ��ē��C���h���Ղ����v�̌����܂����ՂƂ݂Ȃ���邱�ƂƂȂ���������J�X�^�[�͏��C����A�����h�����C���h��Ђ̗����ɂȂ�����A�ސE���Ă���i���̍��A�z�[�v��10�͂ɂ��j�B
�����C���h��ЁA���БD����p�D�ɐ�ւ��遥
�@�����h�����C���h��Ђ́A���ꂪ��������ꏊ���C���O�����h���痣��A�܂��C���h�m�ł̓��[���b�p���痈�Ă���O���D�Ƃ́A�����Փ˂��N����댯�����\������Ƃ��������R����A���܂܂łɂȂ��Ǝ��̋@�\�𐮂��Ă����B
�@���C���h��Ђ́A�����C�R��K�v�Ƃ���ꍇ�͕ʂƂ��āA�500�l�̊C�������g��6�ǂ̗ǑD��6�ǂ̃s���l�X��Ƃ����C���͂ł����āA���Ђ̑D������q���邱�Ƃ��F�߂��Ă����B�܂��A���̉�Ђ��A���������i�͎��炪�B��̔����ƂȂ�A�l�̌��Ղ��֎~����K���������Ă����B�������A���̋K����1635�N�܂Ŏ{�s����Ȃ������B���̉�Ђɓ�������ꍇ�A���l�͑����ʂ̋��z���x�o����K�v���������B
�@1601�N����1612�N�ɂ����Ă̍q�C�̗��v��155�߰��Ăł��������A���̌��30�N�Ԃɂ���3����1�ȉ��܂łɗ������݁A1617-32�N�͓���12�߰��ĂƒႩ�����B�g�D���Ҍ�A1671�N����1681�N�ɂ����Ďx����ꂽ�z�����͗����ō��v240�߰��ĂɂȂ�A1691�N�܂ł�10�N�ԂŔz�������͍��v450�߰��ĂƂȂ����Ƃ����B
�@�����̓��C���h��Ђ��g�p�����D�́A���łɂ݂��悤�ɂقƂ�ǂ������@���g��Ђ̏��l���甃��������D�ł������B�����͑�^�ŕ������ǂ������B�ŏ��̃V���W�P�[�g�ł́A�D���Ƃ��̔��i��45,000����ށA�����ĉ��q�ݕ���27,000����ނł������B���̎x�o���z�́A1553�N�ɖk���q�H�T���̓����z�̖�6�{�ł���A1988�N���i�Ŗ�600������ނƌ��ς����铊���z�ł������B
�@1607�N�A�����h�����C���h��Ђ̓����h�������̃f�v�g�t�H�[�h��u���b�N�����̑��D���ŁA���БD�������A�C�����͂��߂�B���̑�^�̑�1�D�̓U��g���C�h��C���N���[�Y���A��1000�݂ł������B��������A���D������������Ƃ��������Ă���A�����q�C�̓r��A�W�������œ�j���Ă���B�D�͓G�̍U�������킹�邾���̑傫�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�C���O�����h�l�ɂ����Ղ̋K�͂͑�^�̑D�D�ł���قǂɂ͑傫���Ȃ��Ă��Ȃ������B
�@1615�N�A�g�p����D�͍Œ�300�݂���傫����600�A700�݂��炢�̑D���œK�Ƃ���A��͑D��300�݂���350�݂ɐݒ肳�ꂽ�B���̉�Ђ̑D�́A�����̃C���O�����h�D�Ƃ��čŗǂ̕��ނɑ����Ă���A1601�N����40�N�܂ł�168��77,175�݂������Ɍ����������A1640�N�܂łɋA�������̂�104��54,314�݂ł������B
�@���̎j���ł́A�o�������D��60�߰��Ă��߂������A����͑�^�D���قƂ�ǂł������B�A�����Ȃ������D�����ׂĎ��̂ɑ������킯�ł͂Ȃ��B���ǂ��͓����Ɏc���čq�C���Ă���A�܂����ǂ��͌��n�Ƒ��̗̓y�̌��Ղɏ]�����Ă����B���̃A�W�A�n��Ԍ��Ղ͌��Օi���W�ׂ�������v�̑傫�ȕ���ł͂�������������h�����C���h��Ђ͌�q�̂悤�ɓ���A�W�A�Ⓦ�A�W�A�Ɍ��Ջ��_�����݂ł��Ȃ��������ߤ1661�N�ɂ͂��ƓP�ނ��Ă��܂�����̌�͎����ՂɈς˂���
�@1629�N�ɂȂ�ƁA�����h�����C���h��Ђ͎��БD����p�D�ɐ�ւ��A1654�N�ɂ̓u���b�N�����̑��D���蕥���A�f�v�g�t�H�[�h�̑��D���̈ꕔ��q�ɂ�C���h�b�N�Ƃ��Ĉێ�����悤�ɂȂ�B���̌��ʁA���C���h��Ђ̎�Ȋ���͉�Ќ�p�D�������Ō������A�����ŏ��L����D��ɂȂ�A�������Ђɗp�D�ɏo���悤�ɂȂ����B
�@���C���h��Ђ̎Љ��͂����ނ˃����h����V�e�B�̃r�V���b�v��Q�C�g�\���[�f���z�[����X�g���[�g�̋��ɂ������B���̋��́A���N�ɂ킽���ăC�M���X�C�^�̍����n�ł������B
�@18���I��ʂ��āA���C���h��Ђ͕K�v�ȑD�����A����̊ē̉��Ō������ꂽ�D���I�g�p�D���邱�ƂŊm�ۂ����B�p�D�_��͑D���Ƃɗ\�肳�ꂽ�D���ƑD�����Ƃ��Č���A���̑D�̑ϗp�N���ɉ��������̍q�C�ɑ���^������茈�߂��B���̔N�Ԃ̍q�C��1773�N4��A1790�N6��A1803�N8��ƒ�߂Ă���B
�@���C���h��ЂƂ̗p�D�_��͎��R���J�̋������D�Ō���邱�ƂɂȂ��Ă������A���ۂɂ͏A�q���Ă���D�̑D�傪�V������D��p�ӂ��č����o���A�����p�D���Ă��炤���Ƃ����s�ƂȂ����B����ɂ��A���C���h��ЂɑD�����p�����Ē��邱�Ƃ�1�̌����ƂȂ�A�}�����E�C���^���X�g(�C�^��)�Ƃ��������D��O���[�v�����܂ꂽ�B���̂��߉^���͍����ƂȂ����B1783�N�̉����^����1�ݓ�����33����ނł��������A1785�N�ɂ�26-9����ނɒቺ�����B���̌p���p�D���́A1796�N��35������ޕ⏞�����āA�p�~�����B
�����C���h��ЁA�I�����_�ɔs��āA�C���h�ɋ��_��
�@�I�����_���C���h��Ђ́A1605�N�ɂȂ��ă}���N�i�����b�J�j�����̃A���{����(�A���{�C�i��)����|���g�K���l����|���ėv�ǂ�z���B�������A�����̓A�W�A���Ջ��_�ɂȂ肦�������B�I�����_���C���h��Ђ́A1619�N�W�������̃o�^���B�A�ɍP�v�I�Ȍ��Ջ��_�����݂��邱�Ƃɐ����A����ɂ���ăC���h�l�V�A���ׂ̍��h���̌��Ղ�Ƃ��߂��悤�Ƃ���B
�@����ɁA�����h�����C���h��Ђ��Q�����悤�Ƃ��邪�A�I�����_����җ�Ȓ�R�ɏo��B1623�N�A�W�������̃o���^���Ƃ��̎��ӂɂ��������Ջ��_����A1�T�Ԃ������Ȃ������ɁA�C���O�����h�l�͒ǂ��o�����B�����āA�����N�A�C���O�����h�̂����菤�l���}���N�����̌��A���{���̃A���{�C�i�ŁA�I�����_�l�ɂ���đ�s�E�����B���̃A���{�C�i�����ɕꍑ�̃X�`�����[�g�����{�͎�����܂˂��Ă������ł������B1623�N�ɂͤ�����h�����C���h��Ђ͒��肩�礓P�ނ���
�@�������Ĥ�����h�����C���h��Ђ͓���A�W�A�A����ɓ��A�W�A����P�ނ��邪�A�����ɂ����Ă��ł��d�v�Ȓn��ƂȂ����̂̓C���h�ƃC�����ł������B
�@�����h�����C���h��Ђ́A1-2���̍q�C�͓���A�W�A�Ɍ������A�Ӟ��ȂǍ��h���������A�������A���ꂪ��ʂł��������ߔ���s���s�U�ƂȂ����B�����ŁA1607�N��3���q�C�̓{���x�C�ߍx�̃X�[���g�Ɍ�����ꂽ�B����������K�[���c�邩����Փ����͂����Ȃ��������1611�N��g�[�}�X��x�X�g�D�����A�܂�1614-15�N�j�R���X�E�_�E���g���D�����|���g�K���͑���ł��j�邱�ƂŤ�X�[���g�ɂ�������Ղ��\�ƂȂ����
�@1612�N�X�[���g�ɏ��ق��ݒu���ꂽ���ƂɂȂ��Ă��顂��̌�A�C���h�嗤���C�݉����̍`������ɂ��ɁA���C���h��Ђ̏��ق����X�ƌ��݂���顂܂���C���f�C�A����}�����ƌĂꂽ�R��10�ǂ̑D�����X�[���g����n�Ƃ��Ĕz�u���꤃A���r�A�C���|���g�K���̃J���^�X��V�X�e���ɑ����ăp�X�|�[�g��V�X�e���ł����Ă��������Ƃ����B
�@�����A�C���h�嗤���C�݂łͤ�I�����_�̂悤�ɖ\�͂ɗ��邱�Ƃ���������C�݂��������~���ɐi�o����������h�����C���h��Ђ̓S�[���R���_�����̋������Ĥ1611�N�}�X���p�g�i���i���}�`���p�g�i���j�ɤ�C���h�ōŏ��̏��ق�ݒu���顂����Ĥ1639�N�ɂ͌��n�̎�̏������Ĥ�}�h���X�ɏ��ق�v�ǂ̌��݂��F�߂�꤂���Ɋł̖Ə��Ƒ��҂̊ł̔��z�̕t�^�Ƃ����j�i�̓��������顂��̌����ɂ���Ĥ�}�h���X�͍ő勒�_�ƂȂ顂����̋��_�͂�������ȕz�̏W�U�n�ł���������S�[���R���_�����ɂ͓������E�B��̃_�C�A�����h�z�R���������
�@�}�h���X��X�[���g�����ɂ��Ȃ�x��Ĥ1699�N�̏��ق����݂��ꂽ�x���K��(�J���J�b�^)�̏��ْ��̓v���W�f���g����̗^����ꂽ�Nj�̓v���W�f���V�[�ƌĂ꤂�����NJ�������Ȃ���X�[���g�̓}���[�^�A��(�����K�[������A��)�ɍU�����ꂽ���ߤ1687�N�|���g�K������1661�N�ɈϏ�����Ă�����{���x�C(�������o�C)�ɊNj�̒n�ʂ�����
�@�C�����łͤ�����h�����C���h��Ђ̓T�t�@���B�[���̃V���[�E�A�b�o�[�X1���i�݈�1578-1629�j�ɋ��͂��Ĥ1622�N�܂Ń|���g�K���̊������_�ł������z�����Y�����U�����顂����Ĥ�A�b�o�[�X1�������݂�����z�����Y���̑Ί݂ɂ��餃o���_���E�A�b�o�[�X�����_�Ƃ���y���V�A�p���̌��ՂƊŖƏ��̓���������B�����������ɂ���ė��v�������̂̓C���O�����h�ł͂Ȃ�����N�ɘp���̌��Ղ�F�߂�ꂽ�I�����_�ł������Ƃ���顂���ɂ�褏��Ȃ��Ƃ�10���I����17���I�܂Ńz�����Y�����̂��ƂŔɉh���ɂ߂��z�����Y����C�`�s�s�Ƃ��čċ����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ����
�@16���I�Ō��10�N�A�₪���L�V�R�����m�݂̃A�J�v���R���瑾���m�����f���āA���t�B���s���̃}�j���Ɏ������܂��悤�ɂȂ��Ă�������A�W�A�ł͋�̓��[���b�p�ȏ�ɍی��Ȃ��s�����Ă����B�A�W�A�l�̓��[���b�p�Y�i���قƂ�ǔ������Ƃ͂��Ȃ��������A������͗~���������B���C���h��Ђ́A�ŏ���33�N�ԁA753,336����ނ̋�����A�o�������A���i�͂킸��351,236����ނł������B�����Ɛ����̃o�����X������悤�Ȕ������m�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
���A�����J�A���n�ɁA�N�G����l��z��𓊓���
�@�C���O�����h�́A��q�C�������łȂ��A�A��(�n)���Ƃ��Ă��Ō�̓o��҂ł������B���łɂ݂��悤�ɁA�C���O�����h�l�͐A���Ɏ��s���Ă����B1606�N�A�����o�[�W�j�A��Ђ��ݗ������B���̉�Ђ͑Η��������s�s�̏��l�������Q������g�D�ł������B�����h���̏��l�̑g�D�͓�o�[�W�j�A�A�v���}�X��u���X�g���A�G�Z�N�^�[�̏��l�̑g�D�͖k�o�[�W�j�A�ɐA�����邱�ƂƂȂ����B
�@�����h�����l�̑g�D�́A�N���X�g�t�@��j���[�|�[�g�i1565?-1617�j��c���Ƃ���D�c�ɓ������āA1607�N�k�A�����J�嗤�ōŏ��̊m�łƂ����C���O�����h�l�̓��A�n�ƂȂ����A�W�F�[���Y�^�E�������݂���B���̌���A�A�����J�ւ̐A�����{�i������B
�@�j���[�|�[�g�̑D�c�́A�X�[�U����R���X�^���g��(120��)�A�S�b�h�X�s�[�h��(40��)�A�����ăs���l�X�̃f�B�X�J�o���[���ō\������Ă���A�D�c���̓`�F�T�s�[�N�p�ɒ����ł���W�F�[���Y�����A�n�Ƃ��đI�ԁB���̃o�[�W�j�A�A���n�̓^�o�R�͔|�n�ƂȂ邪�A1619�N�ɂ͍ŏ��̃j�O�����A��Ă�����B1623�N�A�����@�͐A���n�̊Ǘ����茳�ɒu���A���̂Ƃ���B
�@���C�t�����[���i180���g���j���A1620�N9��16���s���O�����E�t�@�[�U�[�Y102�l�̈ڏZ�҂��悹�ăv���}�X���o�q���A�o�[�W�j�A��Ђ̔��s�������A����ɂ��������āA�o�[�W�j�A�Ɍ������B�������A���V��Őj�H������A�o�[�W�j�A����k����800��Ұ�ٗ]������ꂽ�A���݂̃}�T�`���[�Z�b�c�B�v���r���X�^�E���ɓ��`����B���̌�A���C�t�����[���������A�����ڏZ�҂��A�R�b�h���̐�[�ɋ߂��ꏊ�ɏ㗤���āA�����A���n�ƂȂ�v���}�X�A���n�����݂���B
�@�W�F�[���Y�^�E���ɓ��A���Ă���30�N�ԂɁA�k�A�����J�̊C�݂ɉ����ă}�T�`���[�Z�b�c�A�����[�����h�A���[�h��A�C�����h�ɁA�����ȓ��A�n�����݂����B1620�N��ɂȂ�Ɛ��C���h�����ɂ����A���͂��܂�B���̏����̓��A�n���A1624�N�Z���g��N�X�g�t�@�[��l�r�X�̃Z���g��L�b�c���ɍ��ꂽ�B1632�N�ɂ́A����Ƀo���o�h�X�A�l�r�X�A�����Z���[�g�ɍ����B
�@����珉���̓��A�n�́A�D���A�є珤�i�A���̑��H�ꐻ�i�A���A�r�[���A���C�����A�C���O�����h�ɂقڑS�ʓI�Ɉˑ����Ă������A���C���h�����ɂ̓C���O�����h��X�R�b�g�����h����H�Ƃ��^�э��܂ꂽ�B���A�n�̘J���͂̂قƂ�ǂ���Ⴂ���l�̔N�G����l�i�n�q����ق��Ă��炢�A���N�ԗꑮ�J�����s���J���ҁA17�18���I�̔��l�ږ���3����2�����������j�ł���A�������A�C�������h�l�����������B1626�N�A�Z���g��L�b�c����60�l�̃j�O�����������܂�邪�A�C���O�����h�̖{�i�I�ȓz����Ղ̂͂��܂�ł͂Ȃ������B
�@1635�N�����A�o�[�W�j�A�ƃ����[�����h�̃^�o�R�̎��n���́A�����̑�^�D1�ǂő������x�ł������B���̌�A�o�[�W�j�A�ȓ�͔M�ѐA���n�Ƃ��Đ������Ă������A���̑��傷��z��̋����ƎY�i�̗A�o�̓I�����_���l�Ɋ��S�Ɉ����A�A���n�Ƃ��Ă̂ɗ��v�̓C���O�����h�l�̎�ɓ���Ȃ������B���������̂��̂Ƃ���ɂ́A�s���[���^���v����̏d����`����i�q�C���j�ɂ܂��˂Ȃ�Ȃ������B
��17���I�A2�x�̊v����3�x�̃I�����_�푈��
�@17���I�́A�Q�[��y�X�g�̎S�ЁA�O�\�N�푈�Ȃǐ푈�̘A���A�����Ė\���┾���A�v���̔����Ȃǂ��N����A�S�ʓI��@�̐��I�Ƃ����B17���I�̃C���O�����h�̓X�e���A�[�g�����ɓ����邪�A���[���b�p�����ɘR�ꂸ�A2�x�̊v�����o������B
�@�W�F�[���Y1���́A���炪�g�b�v�ł��鍑����Ƃ̈�̉������߁A������ɏ]��Ȃ��s���[���^�����k��e������B���̒e����āA����ł݂��悤�ɁA1620�N���C�t�����[���ɏ�����s���O�����E�t�@�[�U�[�Y�̈�����A�A�����J�嗤�ɓn��B
�@�����Ƌc��̑Η��́A���łɃG���U�x�X1���̎���ɂ����������A�X�e���A�[�g���̂��Ƃł���ɐ[�܂�B����́A�e���[�_�[���̎���ɁA�_�H�Ƃ���Ղ̋����̒S����ƂȂ��Ă����A�W�F���g���[�ƌĂꂽ�Љ�K�w�������͂����߂Ă����B������~�߂��A�����͋c������A�Վ��ł��ۂ�����ł������B
�@�`���[���Y1���́A1628�N�u��������v������Ȃ���c������U���āA�ꐧ�x�z�ɏ��o���B�ނ́A�c����J���Ȃ��܂܁A�ł̋���������̗����A�����̎�藧�Ă��s�����B1634�N�A�ނ͕��̃W�F�[���Y1����30�N�ԕ��u���Ă����C�R�𗧂Ē������Ƃ��āA����܂ŊC�`�s�s�����ɉۂ����Ă����D���Łi���͐Łj��S���Ɋg�債�悤�Ƃ���B���̎x�����A�����ƃW�����E�n���f���i1594-1643�j�����ۂ���ƁA�D���Ŕ��Ή^�����S���I�ɍL����A�W�F���g���[�ȂNjc��x�z�w���������͂��߂�B
�@���̎������N����1637�N�A�`���[���Y1�����X�R�b�g�����h�ɍ�����̃V�X�e���������������߁A�������N����B1640�N�ɂȂ�ƁA�X�R�b�g�����h�R���N�U���Ă���B������ċc����ĊJ����A�����̉��\��j�~�����A�̉��v�@�i�D���ł�s���Ƃ���Ȃǁj���ʉ߂���B�������A���̑ԓx�͕ς�炸�A1642�N�c��Ƃ̑Η��͌���I�ƂȂ�B
�@1642�N8���A�C���O�����h�̎x�z�w�͉��}�h�i��ɋM���A�����n��A�������l�j�Ƌc��h�i��ɔ_�Ǝ��{�ƁA�����l�A�Ɨ����c�_���j�ɕ�����āA���킪�u������B�����͉��}�h���D�ʂɂ��������̂́A�c��h�̓X�R�b�g�����h�̔������͂ƌ��сA����ɃW�F���g���[�o�g�̃I���o�[�E�N�����E�F���i1599-1658�j������S�R���Ȃǃj���[�E���f���R���o�ꂷ��ƁA���}�h�͗Ɋׂ�B
�@�s���[���^���v�����N����ƁA�ѐD���H�ƒn���C�`�s�s�͍����̓G�ƂȂ����B�����C�R�͕ϐ߂��ċc��h�̑��ɑ���A�C�`�͋c��ɏ��D���������C���O�����h�̊C����Ղ͑��s���ꔽ�t�҂̕x�𑝂������A�������͊C�O���畐���A������̂�����ƂȂ����
�@1646�N�A�`���[���Y�͕߂炦���邪�E�o�A�Ăѕ߂炦���A1649�N�ɏ��Y�����B���̐�������A���a�����錾����A�s���[���^���v���͏I���B
�@�I���o�[�E�N�����E�F���́A���v���̋��_�ƂȂ����A�C�������h�ƃX�R�b�g�����h�Ɏc�s�ȉ�������Ă�B�܂��A�ނ͋c������U���āA�s���[���^���ƌR���ɂ��ƍِ�����z���B�g�����F���A�����ɂ��A�W�F�[���Y1���ƃ`���[���Y1���̎���Ɏ���ꂽ�u�C�㌠�������A�C�R���i�v�I�Ȕ\���̊�b�̏�ɂ��������_�́A�����U�t�Ґ��{���̂��̂ł���v�B�����āA���̐����̓��o�[�g�E�u���C�N�i1599-1657�j���C�R�i�ߊ��ɂ������Ƃɂ���A�܂��u���C�N�̓h���C�N��l���\���i��A1758-1805�j�Ɠ����̒n�ʂɂ���Ƃ����i�g�����F���A��2���Ap.155�A1974�j�B
�@�I���o�[�E�N�����E�F�������ʂƁA���̐����͂����Ɋ�������B1660�N�A�t�����X�̃��C14�����瑽��Ȕ���āA�I�����_�ɖS�����Ă����`���[���Y�̎q���`���[���Y2���i�݈�1660-85�j�Ƃ��đ��ʁA�������Â��Ȃ�B�ނ͋c��Ƌ������āA2��ɂ킽���ăI�����_�ɐ푈���d�|����B
�@�`���[���Y2���ɂ͒��q�����炸�A��̃��[�N���W�F�[���Y�����ʂɂ��悤�Ƃ��邪�A�ނ��܂��J�g���b�N�ł������B���̃W�F�[���Y2���i�݈�1685-88�j�̑��ʂ��߂����āA�c���2�吭�}�̌��^�Ƃ�����g�[���[�ƃz�C�b�O�ɕ������B���̑��ʂ��x������g�[���[�ɌR�z��������A�v���e�X�^���g�̍��C���O�����h���J�g���b�N�̉����}���邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��A�z�C�b�O�͊C�O�Ƃ̌��ՂɊS���������B
�@���̃W�F�[���Y2�����������q���Ȃ��������A���܂̃��f�i�����c���̂������ɒj�q���a������B�J�g���b�N�����������Ƃ��������c��̓g�[���[�ƃz�C�b�O���c�����āA�W�F�[���Y�r���ɓ����B�c��́A�W�F�[���Y�̖����A���[�̕v�ŁA�v���e�X�^���g�̍��Ƃ��ăt�����X�ɑR���Ă����I�����_���I���j�G���E�B����3��������R�c�������āA�W�F�[���Y�ƑΌ�����B�W�F�[���Y�͂�������ƃt�����X�ɖS������B���̖����v���𖼗_�v���Ƃ����B
�@�c��͍����Ƃ��ă��A���[�ƃE�B�����̕v�Ȃ��w�����A�����͋c��@�̗D�ʂ𖾕��������u�����͓T�v�ɏ������đ��ʂ���B����܂őΗ����Ă����C���O�����h�ƃI�����_�́A1689-1702�N���A���[�i�݈�1689-94�j�ƃE�B���A��3���i�݈�1689-1702�j�̓��N�A���ƂȂ�B
�@���̖��_�v���ɂ���āA�C���O�����h�̌��͍͂P�v�I�ɋc��ɌX�����ƂƂȂ����B�����āA���_�v���Ȍ�A�C���O�����h�̌o�ϐ����͔��̒i�K�ɓ��邱�ƂƂȂ�B
���C�M���X�鍑�̎�q�A�����ƐA���A���Ձ�
�@17���I�O���̃C���O�����h�́A�]���ʂ�_�ƍ��̂܂܂ł��褃A���g���[�v��I�����_�����̃~�b�f���u���N����b�e���_�����礃C���O�����h�l���K�v�Ƃ���K���X�����L�����o�X����l����s������Ƃ�����������̍H�ꐻ�i��A�����Ă�����܂���D���Ƃ��K�v�Ƃ��������}���ܤ�I�C����E�[���J�[�h�i�r�т����j�������A�����Ă�����؍ނ͑��D����z��M������z�b�v�̓r�[������͋��̕ۑ��Ɏg�����ߗA�����ꂽ�����ʕ�������ăX�p�C�X�͎�ȗA���H�i�ł��邪����C���̓��[�}����ȑO����ŏd�v�ȗA���i�ł������
�@�C���O�����h�̌��Ղ�16���I�㔼�ɕϖe���邪�A����͉ߋ��ɐݗ����ꂽ���[�g����O�ꂽ�Ƃ���ɁA�V�����i�̐V�����s������o�����Ɠw�͂������ʂł������B�������A���V�A��A�t���J�A�A�����J�A�����@���g�A�����ē��C���h�Ƃ̐V�������Ղ́A�C���O�����h�̊O���Ƃ̌��Ց��ʂɑ傫�ȉe�����y�ڂ��قǂł͂Ȃ������B����ł��A�C���O�����h�̒ʏ��⊔���g�D�ɐV�������͂�^���A�܂����Z���̉����ɑ��i���邱�ƂƂȂ����B
�@�z�[�v���́A�����̃C���O�����h�l�̊C���v�z�ɂ��āA���̂悤�ɂ܂Ƃ߂�B�u16���I�A���[���b�p�̑����̍��ɂ����č��ƈӎ������g���A�C�m�헪�̏d�v�����\�ɔF�������悤�ɂȂ������v�A�u16���I�̃C���O�����h�l�̓X�y�C�����N�����Ă��鋰�ꂪ�������̂ŁA�C���͂傳����ׂ����ƍl���Ă����B17���I�ɂȂ�ƁA���̈ӌ��̓��C�o���ƂȂ����I�����_�̂������ŋ��܂�A[�R���ゾ���ł͂Ȃ�]���Տ�̖ړI������A�C�m���������ׂ��Ƃ����~���ɂȂ����v�Ƃ���B�ʏ��H�ێ���j��Ƃ����C�m�헪�̓o��ł���B
�@�������A�u17���I�O���A���{�̖���A�N��̖��S�A�����ĊC��퓬�ɂ��Q��v���݂�ꂽ�Ƃ��邪�A����ɂ�������炸�C�M���X�鍑�̎�q�͈炿�A�u�������Ă��̂̓R���L�X�^�h�[���X[16���I�̃X�y�C����|���g�K���̓�A�����J������]�ł͂Ȃ��A���v����Րl�A�����Đ�����@���̑Η��҂ł������v�B
�@�u1649�N���Ȃ킿���a�������܂łɁA500������ނ��C�O�`���̂��߂ɂ����܂�A6���l�ȏオ�A�����J�Ɍ����A��5000�l�\�C���O�����h�̐l����500�l��1�l�\���C�O�ɓ������Ă����B�������A���̑ǂ̓g�[�}�X��X�~�X�i���A�����h�����C���h��Ђ̏��㑍��20�N�A�o�[�W�j�A��Ђ̏��㑍��9�N�j�Ƃ������古�l�������Ă����Ƃ��Ă��A��Ȑ��i�͂́u������Ђ⎄����������K�^��͂��l�������A���݂��Ɏh�������������ʂł������B1649�N�A�C�M���X�鍑�̎�q�̓C���h�ƃA�����J�ő傫���J�Ԃ���v�i�ȏ�A�z�[�v��10�́Ap.186�j�B
���N�����E�F���̏��l�̗��Q���т��ꂽ����
�@�C���O�����h�͗r�їA�o���ł��������A15���I�̂����ɖѐD���Ƃ��}���ɔ��B���16���I�O���ɂ͖ѐD���̑�֏o���ƂȂ����1530�40�N�㤉��������̊�@�ŊJ��Ƃ��Ēʉ݂���������A�|���h�̈בփ��[�g���\�����āA�C���O�����h�Y�̖ѐD���͈����ɂȂ褂��̗A�o�ʂ͂����܂��{������
�@�ѐD���̗A�o����������Ƥ�K�R�I�ɗr�щ��i���㏸����q�r�Ƃ����v�̑����Y�ƂɂȂ�15���I�㔼�A�q�r�Ƃ��g�傳���邽�߁A�y�n�͂����݁i�G���N���[�W���j�^�����N����B������A�g�}�X����A�i1478-1535�j�́w���[�g�s�A�x�ɂ����āA��r���l�Ԃ�H����ƕ]�����B���̈͂����݂����H�����W�F���g���[��[�}���i�Ɨ����c�_���j�͂܂��܂��x�T�ɂȂ�A��_�Ƃɂ�����o���悤�ɂȂ����B
�@16���I�㔼�A�G���U�x�X1�����ʉ݂����ǂ���ƁA�C���O�����h�̗A�o�͌�������B�����āA1568�N�I�����_�Ɨ��푈���͂��܂�ƁA�A���g���[�v�̓X�y�C���̍U���ɂ��炳��A�}���ɐ��ނ���B����ɂ��A�����h���\�A���g���[�v�̊�͕��āA�C���O�����h�̖ѐD���H�Ƃ͐[���ȕs���Ɋׂ�B�����ŁA�ѐD���̐V�����s����J�邱�ƂŁA���̊�@��ŊJ���悤�Ƃ��āA�܂������Y�i�ڂɓ��肵�悤�Ƃ��āA���X�Ɠ�����Ђ��ݗ�����Ă������B
�@16���I�㔼�A�C���O�����h�̓t�����h������̖S���҂��琻�@���K���Ĕ���̞��іѐD���Y���āA���[���b�p�����ɗA�o����悤�ɂȂ�B����͖����H�̕��L�̖a�іѐD���ɑ��ĐV�ѐD���ƌĂꂽ�B�܂��A�������A�K���X�����A���������������ȂǁA�V���������H�Ƃ������o������B�ΒY�Ƃ����������W���݂��顂����V���Y�Ƃ̑����ͤ�����A�ґ�i�ł������A���i�����Y���悤�Ƃ�����̂ŁA�W�F���g���[�w���͂��߂����̂ł������
�@�C���O�����h�̐l���́A1522�N�̖�230���l����1603�N�ɂ�310���l�ȏ�ɂȂ����Ƃ���A���̐l�������̈��͂�_�Ƃ͎x���ꂸ���@�I�ȏƂȂ顂��̊�@��w�i�Ƃ��ăs���[���^���v�����N���Ă����B1660�N�̉������ÈȌ�A�C���O�����h�̔_�Ƃ͐��Y�������サ�A�C����Ղ��܂���������B�������_�@�Ƃ��āA1656�N�̌㌩�ٔ����̔p�~�Ȃǂ������āA�㋉�̎�̌������ے肳�ꤒn��̎��L���Y�����m�F�����
�@�����ȗ���C���O�����h�ł͍����A�o��}���������ҕی쐭�Ƃ��Ă������A�������Ì��1663�N����89�N�܂ō����̏������i�����ȉ��ɂȂ�A�����A�o��������x�����鐧�x���������顂���͒n��x�z�̐��̐������ے����鐧�x�ł������B
�@17���I���A�ϋɓI�ȏd����`�����{�����B���a������1651�N��������Ì��1660�N�A1663�N�ɍq�C��Ⴊ���肳���B����͏]���ƈ���āA�C���O�����h���l�ɃC���O�����h�D�̎g�p���`���Â��邾���ł͂Ȃ��A�C���O�����h�̌��Ղ���I�����_�ȂNJO�����͂�r�����悤�Ƃ������̂ł������B�܂��A�����200�l����̓����I�ȏ��l�̗��v��ی삷��̂ł͂Ȃ��A���ꂼ��̎Y�Ƃɂ����ċN�ƉƂ̎Q����ۏႵ�悤�Ƃ���A�{���̏d����`����̈�ł������B
�@�N�����E�F���̎��㤃A�C�������h�̐�����A���A1655�N�̃W���}�C�J�̐�z�A1657�N�̃����h�����C���h��Ђ̊g�[����g�Ȃǂ��s����1655�N�A�N�����E�F���̐����v��̈�Ƃ��āA�E�B���A���E�y��(1621-70��y���V���x�j�A�A���n�̑n�ݎ҂̕������)�ɗ�����ꂽ�C�M���X�͑����W���}�C�J���̂���B�W���}�C�J�́A1670�N�̃}�h���[�h���Ő����ɃX�y�C������C�M���X�ɏ��n����A�z��ɂ�鍻���v�����e�[�V�����A�����ăA�t���J�l�z����Ղ̒��S�n�ƂȂ�B
�@�s���[���^���v�����̏��ƥ�A���n����ͤ���J�g���b�N�Ƃ����@���I��M����ړI����o�Ă͂������A�˂Ƀ����h�����l�̗��Q���т���Ă����B
���q�C��ᐧ��A�I�����_�Ƃ�3���̐푈��
�@�����́A�C�M���X�Ƃ��̊C�O�̓y�̗A������O���D��r�����A������C�M���X�D�ɓƐ肳���悤�Ƃ�����̂ł������B���̈�Ƃ��āA�B�O���D�̓C�M���X�̉����Ղɏ]�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ����B���̉����Ղ̎����D���ۍ�(�J�{�^�[�W���Ƃ���)�͒����Ɍ��ʂ��グ�A�O���D�͔r�����ꂽ�B�Ȃ��A�������{�ł́A1899�i����32�j�N�������ɉ����Đ��肳�ꂽ�D���@�ɂ���āA����𗯕ۂ���B
�@�C���O�����h�̍q�C���̑傫�ȖړI�́A�I�����_�̒��p���ՂƃI�����_�D�̗A���ɑŌ���^���邱�Ƃɂ������B�����ŁA�C�O���ŎY�o���ꂽ���i�́A���̌��Y�n�܂��͍ŏ��ɑD�ς݂��ꂽ�`����łȂ���A���Ƃ��C�M���X�D�ł����Ă��C�M���X�ɗA�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�D���V�A��g���R�̏��i�́A�C�M���X�D�܂��͌��Y���̑D�܂��͍ŏ��ɑD�ς݂��ꂽ�`�̑D�łȂ���A�C�M���X�ɗA�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ����B
�@���̑��A�E������^�o�R�A�����A�ȉԁA���I�Ƃ��������l�̂���A���n�Y�i�i���i�Ƃ��ꂽ�j�́A�C�M���X�₻�̗̓y�ȊO�̒n�Ɍ����đD�ς݂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�F���Y���̑D�܂��͍ŏ��ɑD�ς݂��ꂽ�`�̑D�ŗA�����邱�Ƃ��F�߂�ꂽ�ݕ��́A�O���l�A���ł��x����Ȃ���Ȃ炢�A�Ƃ����B
�@�܂��A�q�C���͗i������X�e�C�v�����ɂ���ĕ⋭����Ă����B�������Ì��1663�N�̃X�e�C�v�����́A���[���b�p�����̎Y�i�̓C�M���X�o�R�łȂ���A�A���n�ɗA�o�ł��Ȃ��Ƃ����B
�@�C���O�����h�ɂƂ��āA�I�����_�͉ߋ�1����̊ԂɁu�k���[���b�p��A�����J�̊C��Ť�܂��A�t���J��C���h�̑�m�Ť�����Ή������̏���Ȃ���킪���̊�Ő����������Ŗ���������C���O�����h�Ƃ��̃A�����J�A���n�Ƃ̉^���Ƃ��قƂ�ǓƐ肵�Ă��܂��Ă����v�̂ł���i�g�����F���A��2���Ap.156�j�B�C���O�����h�͖{�C�ɂȂ��āA�I�����_�ɗ����������K�v���������B�I�����_�Ƃ̊C��e�����߂��鑈���́A18���I�����܂Ō����������Ƃ͂Ȃ��������A���̑������͂��߂��̂͑��ł��Ȃ����a�����{�ł������B
�@�q�C���́A���E�̒��p���Րl�Ƃ��Ă̒n�ʂ��ւ��Ă����I�����_�ɂƂ��āA�傢�Ȃ鋺�ЂƂȂ����B�I�����_�Ƃ̊W�́A�C���O�����h�����Y�����`���[���Y1���̖����I���j�G���E�B����2���̍ȂƂȂ��Ă������ߤ�₦���Ă����1651�N��Ⴊ���肳���ƁA���̊W�͔j�]���āA��1���C���O�����h�E�I�����_�푈�i1652-54�j���͂��܂�B
�@��1���푈�ͤ���o�[�g�E�u���C�N�ɗ�����ꂽ�C���O�����h�͑��Ƥ�t�@���E�g�����v�i1597-1653�j������I�����_�͑��̑����ƂȂ����B1652�N�̃h�[�o�[���C��ł̓g�����v�A1653�N�̃e�Z�����C��ł̓u���C�N�����������߂邪������͂��Ȃ������B�����A���̐킢�ɂ��A�I�����_�̔�Q�͑傫���A�C���O�����h�Ɏ��v�͂����邱�Ƃ������ꂽ�Ƃ����B�I���o�[�E�N�����E�F���́A1654�N�ɃC�M���X�D�ʂ̍u�a�����ԡ
�@1663�N�̍q�C���͊O���l���L�̑D�͂����Ƃ��āA�험�i�łȂ��O�������D�̎g�p�𐧌����A������^�D�ɑ���⏕�����A��^�D�̒�`��ύX������ŕ����������B����́A�������ÈȌ�A�C���O�����h�l�������őD����������̂ł͂Ȃ��A�C�O����D���ʂɔ����t����Ƃ������Ԃ����P���邱�Ƃɂ������B����ɂ��A�C���O�����h�̑��D�Ƃ��}���ɕ������邪�A���̌�̃I�����_�Ƃ̐푈�ɂ���ēڍ�����B
�@17���I�O���́A�t���C�{�[�g�̓C���O�����h�ł�1300����ނ����������A�I�����_�ł�800����ނŌ�������Ă����B1676�N�ɂȂ��Ă��A�C���O�����h��250�݂̏��D��1�ݓ�����7�����2��ݸ�6��ݽ�����������A�I�����_�Ō������ꂽ200�݂̃t���C�g��4�����10��ݸނł������B�I�����_�l�͔N��700-800�ǂ��o���g�C�ɑ���o���A�܂�1000�Ljȏ�̃j�V���D���g�p���Ă������A���̂���600�ǂ͑�^�ł������B
�܂ܐ��ڂ��āA1667�N�̍u�a���ł͖k�A�����J�̃j���[��A���X�e���_��(��Ƀj���[���[�N�Ɖ���)���l���������̤̂�q�C���̓K�p�ɘa��F�߂邱�ƂƂȂ�
�@17���I�̍q�C���́A�ꌾ�ł����Ύ����ݎ����D��`�Ƃ�������̂ŁA�C���O�����h�Ƃ��̗̒n�ւ̗A�����Ղ���I�����_�̒��p���Ղ�r�����A�C���O�����h�ƌ��Y�n���̑D��ɂ���Ď��d�낤�Ƃ������̂ł������B���ɁA����̃A�����J�A���n�Ƃ̌��Ղ͗A�o�A�A���Ƃ��ɁA���̗A���̓C�M���X�D�Ɍ���Ƃ�������ł������B
���C���O�����h�ƃI�����_�̒n�ʂ��t�]��
�@���̋ɒ[�Ƃ�����C����Ղ̎����ی쐭��ɂ�������炸�A���[���b�p�����������Ƃ��������Ƃ͂Ȃ������B���[���b�p�����́A�I�����_�̒��p���ՂɈˑ����Ă͂������A���̐���s���ɂ͊S���Ȃ������B�܂��A���[���b�p�������܂�����̐A���n���Ղɂ��āA�C���O�����h�Ɠ����悤�ɕ��I�Ȑ�����̗p���Ă����B�����������āA�q�C���̐��ۂ͂��̐�����x�����Ď��s���悤�Ƃ����A�C���O�����h�̏��l��D�傽���̈ӗ~�ɂ������Ă����B
�@�I�����_�Ƃ̑�3���푈�i1672-74�j���N����B����ͤ�`���[���Y2���Ɩ�������t�����X�̃��C14�����I�����_�ւ̐N�����͂��߂��̂Ɍĉ����Ĥ�C���O�����h���Q�킵�����̂ł�������I�����_�R�͕��킵�A�܂����Ă��f����C�e����ɘA���͑��͌��j����A�t�����X��C�M���X�̕�����ƂȂ�B�������A�I�����_�̔������Q�͐[���ł����Ĥ���̒����������v���ƂȂ�
�@�C���O�����h��3���ɂ킽��I�����_�Ƃ̐푈��ʂ��āA����߂Ėc��Ȑ��̃I�����_�D��ߊl���A�험�i�Ƃ����B��1���I�����_�푈�ł�1000�ǂ���1700�ǂ܂ł̃I�����_�D��ߊl���A��2���푈�ł͖�500������ނ̐������������ߊl�D��500�ǁA��3���푈��500�ǂł������B�����A�C���O�����h���I�����_�Ƃ̐푈�Ŏ������D�͂킸����500�ǂł������B1655-60�N�ɂ�����X�y�C���Ƃ̐푈��400�Ljȏ��ߊl�������̂́A�C���O�����h�D��1000�ǂ���1500�ǂقǂ��ߊl�܂��͔j�ꂽ�B
�@�C���O�����h�́A1652�N����1674�N�܂ł�22�N�ԁA���S�ǂ̗ǑD����������Ă���A���̂����ߊl���邢�͍w�����ꂽ�O���D���C���O�����h�l�ۗ̕L�D����3����1�ȏ�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ������B�������A�����푈���I���1675�N�ɂ́A����2����1�𐔂���܂łɂȂ����B�C���O�����h�̑D���́A17���I�㔼�A3�{�����������Ƃ����B
�@�q�C���{�s��A�C���O�����h�D�ɂ��A���͍��R�X�g�ɂȂ������A�C���O�����h�̊C����Ղ͉������Â����ɂ��Ċ����ɂȂ�A���̗A�o�͐��I���܂ł�3�{�ɂ��Ȃ�B���̂Ȃ��ł��C���O�����h�̃J���u�C��k�A�����J�ɂ���A���n�Ƃ̌��Ղ�����������������B����Ɍ�������āA���R�X�g�̃C���O�����h�D�ɑ��Ă����v�����܂�B
�@1664�N�A�����h������26�ǂ��m���E�F�[�ցA������22�ǂ��o���g�C�ɏo�����Ă������A1686�N�ɂ͂�����111�ǂ�65�ǂɑ�������B�܂��A���C���h�����ɂ�45�ǂ���133�ǁA�܂��k�A�����J�ɂ�43�ǂ���111�ǂւƑ������Ă���B�C���O�����h�̍`����o�������D�̔N�ԏo���g������1663-69�N����9.3���݂ł��������A1700-12�N�ɂ�27���݂ɑ�������B���̂����C���O�����h�D����߂�䗦��65�߰��Ă���86�߰��ĂɌ��シ��B
�@��3���I�����_�푈��A���[���b�p�����̓t�����X��I�����_�ȂǂƐ푈�𑱂��Ă����̂ŁA�C���O�����h�ɍD�@���K���B�C���O�����h�͒������Ƃ��āA�펞���ɕ������������Č��Ղ��L����ƂƂ��ɁA�I�����_���s���Ă����o���g�C�ƃC�x���A�����Ƃ̌��ՁA���ɉ��̌��Ղ�����肷��B�܂��A�C���O�����h����|���g�K���ɏ����𑗂�A�A��ׂƂ��ĉ���ς݁A�����g�r�A�̃��K��y�e���u���O�ɉ^�сA���∟���A�S�������A��悤�ɂȂ����B
�@�C���O�����h�C�^�̐����͑��D���ނ̎��v�����N�����B����ɂ���āA�C���O�����h�ł̓J�V��j�����s������悤�ɂȂ�A���̑�ւƂ��ă��~�A�}�c�A�G�]�}�c��A������������Ȃ��Ȃ����B����ɁA1666�N�̃����h���̑�Ȃǂ��؍ނ̎��v���������B1673�N����1700�N�ɂ����āA�N��200�ǂ���300�ǂ̑D���o���g�C����C���O�����h�Ɍ������Ă������A���I���ɂ͂����̑D�̔������C���O�����h�D�ł������B�����A�m���E�F�[����̖؍ނ̗A���́A���^���̃C���O�����h�D�͊�������A�����m���E�F�[���x�z���Ă����f���}�[�N�D�Ɉς˂��邱�ƂƂȂ����B
�@�C���O�����h�́A3���ɂ킽��I�����_�Ƃ̐푈��킢�����A���Ɍ����u�a���̂��тɗL���ɂȂ�Ȃ��ŁA�C�m�鍑�̑����ݏo���B����ɑ��āA�I�����_�͐푈�ɂ����Ղɑς����ꂸ�A����ɔ敾���āA�C����Ղ̔e�����C���O�����h�ɏ��炴������Ȃ��Ȃ�B�C���O�����h�́A18���I�Ō�̎l�������邢�̓A�����J�̓Ɨ��܂ŁA�q�C��Ⴊ���҂������ʂ�����B
�@�������A18���I���Έȍ~�A�q�C���̋K��͑ΊO�푈�����邽�тɁA���X�Ɗɂ߂�ꂽ�B����́A�������̑D��p�D���邱�ƂŌ��Ղ��ێ����Ȃ���Ȃ炸�A�܂��푈�Ɏ�肾���ꂽ���p�D�̑�֑D��K�v�Ƃ�������ł������B�܂��A�C�M���X�l�̑D�������p���ꂽ�̂ŁA���̌����߂ɊO���l�D�������܂܂łɂ��܂��Čٗp���ꂽ�B�Ⴆ�A�C�M���X����o������O���D�̃g�����䗦�́A���N�푈���A������7-8�߰��Ă���20�߰��Ăɑ��債���B
�@�����āA�q�C��Ⴊ���҂������ʂ��グ�����C���h������k�A�����J�̐A���n���Ղ̓����҂ɂƂ��āA���̏�Ⴊ���������ς�����̂Ƃ��Ĕr�˂���邱�ƂƂȂ�B����ɁA18���I�㔼�ɂ͂��܂�Y�Ɗv���ɂ���đ�ʂɉ����o����Ă���H�Ɛ��i���A�C�M���X�͐��E�I�K�͂ʼn���̐�������ɔ���J���K�v�ɔ�����B���̂Ƃ��A�q�C���͎��R�Ȍ��ՂƂ��̊g��ɂƂ��Ă̏�Q�ƂȂ�A1849�N�ɔp�~�����B
�����C���h��Ђ̕���ƍ����A�C���h�̖ȐD����
�@���C���h��Ђ́A���a�����A�傫�ȉ��v����B�܂��A�����Ƃ̌��Ղ͎����I�ɂ��ׂĂ̐l�ɊJ����Ă��܂����B1657�N�A�N�����E�F���̓�����ɂ���āA���呍��ō��@�ւƂȂ����B�܂���I�����_�Ɠ����悤�ɤ�����u�a����̌������^����ꤌ��n���{�ƂȂ����
�@�����āA��Бg�D�͍q�C���Ƃ̓����g�D����A���قƗ������ݒu���āA�o�c�̎�������ۂA�P�v�I�ȑg�D�ɉ��ς��ꂽ�B�o�������J����A����͑����ʂ��ĉ�Ќo�c�ɎQ�悵�A����ɂ͔z�������x������悤�ɂȂ����B1662�N�A�L���ӔC���̊�����ЂƂȂ�A�������{�͕ԍς��Ȃ������Ƃ��Ď�舵���邱�ƂƂȂ����B
�@�`���[���Y2�������ʂ��ĐV���������t�^�����ƁA���C���h��Ђ͒P�Ȃ���Չ�ЂłȂ��Ȃ�A���܂܂ňȏ�ɐ����I��i�@�I�Ȍ��͂�U�邤�悤�ɂȂ����B���̐��I�̍Ō��10�N�Ԃɗp�D���ꂽ�x�[�J���C��J�b�X�����A�x�h�t�H�[�h���A�^���B�X�g�b�N���A�X�g���[�g�T�����A�z�[�����h���A���V�A���A�}�[�V�����A�t���Q�[�g�̃U����b�Z�����A�E�F�����[�X���A�r���[�t�H�[�g���A�}�b�V���O�o�[�h���Ƃ������D���́A�ǂ��������n���œ������ꂽ�D�ł��邩���킩��B�����n���̋M���K�����C�^���i�D�̓�����Ƃ݂Ȃ��悤�ɂȂ����B
�@���̂Ƃ��ȍ~�A���̉�Ђ͋��Ȃ��Ă�����̉��ז_�������o�����Ƃ��F�߂�ꂽ���ƂŁA���Ղ͊i�i�ɑ�������悤�ɂȂ�B�܂��A1650�N�J���J�b�^�ߍx�̃t�[�O���A1662�N�{���x�C�A������1686�N�J���J�b�^�Ƃ����悤�ɁA���X�ƃC���h�̋��_���ݗ�����Ă������B�����A�W�������̃o���^���ł̓I�����_�Ƃ̕����������A1682�N�C���O�����h�l�͓P�ނ�]�V�Ȃ�����A����ɑウ�ăx���N�[�����i�X�}�g�����암�A���x���N���j���J���B
�@�C�M���X���C���h��Ђ̌��Պz�͎���ɑ������邪�A18���I�̍ŏ���3����1�܂ł̑����͂ق�̂킸���ł������B�X�p�C�X�ȂǓ������ґ�i�́A�]���ʂ�n���C�o�R�Ŏ������܂�Ă������A���łɃC���O�����h�͊�]��o�R�œ��肵����A����珤�i��n���C�����ɋ�������܂łɂȂ��Ă����B
�@���̂���A�X�p�C�X�͕ꍑ�����ݕ��Ƃ��Ă̗D�z���������Ă���A�ݕ��̉��z��70�߰��Ă���80�߰��Ă͖ȐD���ƂȂ��Ă����B�y���V�A��x���K������̃V���N�ƁA�p�L�X�^������̃��z�[���̃C���f�B�S�����l����ݕ��ƂȂ�A�܂����C���h��}���o�[������̃y�b�p�[�ƁA�x���K������̏ɐ⍻������@�ݕ��ƂȂ��Ă������B���̂����A�ȐD���̗A�������́A�ѐD���H�ƂƂ̑Η����������B
�@�x�[�J���C��J�b�X�����́A1681�N�C���O�����h�����ɋA�������Ƃ��A�}�h���X�n������o�������ł����ȑD�Ƃ����A�ωׂ̋��z��8�������(1988�N���i��500������ވȏ�)�̒l�ł��ł������B�������A���̐ς݃g���̔����ȏオ�ɐł��������A���ꂪ�S�̂ɐ�߂鉿�z�͂����킸���ł������B
�@�C���h�ւ̗A�o�i�͂킸�������Ȃ������B�ѐD���A�S���i�A�����i�A�r�[���͂��Ă����A����S�͒ʏ�A��ׂƂ��ĉ^�ꂽ���A���̑����������ނ˕ꍑ�Ɏ����A����ꂽ�B1680�N��A���C���h��Ђͤ�C���O�����h�ւ̗A�����z�̖�14�߰��Ă������A��ƂȂ��Ă���A�܂��N�Ԃɔz�����Ƃ���20�߰��Ă��x�����Ă����B
�@�����h�����C���h��Ђ́A1680�N�Ȍ�����菤�l��C���Ƃ̋����ɂ��炳��Ă������A1698�N����1708�N�ɂ����Ă��̓Ɛ茠����~�����B����̓W�F�[���Y2�������r���āA�V���������ɃE�B���A��3�����o�ʂ���Ƥ�C���h���Ղ̓Ɛ�ɔ�����c��̐��͂������Ȃ��������Ɍĉ����Ĥ1698�N��E�B���A��3�����V��Ђ̐ݗ��𖽗߂��A����Ђ̓����������������̂ł���B
�@���̌�10�N�Ԥ����Ђ͂��̑������F�߂�ꂽ���Ƃ���A�V������Ђ̂��ꂼ�ꂪ�����Ȃ��礓��C���h���Ղ��s�����ƂƂȂ�����ނ�ͤ������Ԃ����Ɛ����H��ɑ����̋��i�������A�܂����݂��������c�邽�߂̐Ղ��s��ꂽ����̌��ʤ1708�N���C���h�ƌ��Ղ���C���O�����h���l�̍�����ЁA�ʏ̃C�M���X���C���h��Ђ��ݗ������B����������̊���͑��ς�炸�����h���̏��l���������S�Ť�u���X�g����n���Ȃǂ̒n���̏��l�͏��O����Ă����
�@����Б��قŌo�ϊw�҂̃W���T�C�A�E�`���C���h�i1630-99�j�́A����Ђ̓�����i�삷�邽�߁A10������ޔ�������Ƃ����B�g�����F���A�����ɂ��A���̍R���ɂ��āA�u�����̕x�͂��͂�A���r�A�̂����b�ł͂Ȃ��A�m���Ȏ����ł����āA���̏�ɔN1�N�ƃV�e�B�̍��Y���z����A�n���̐V�������傪�n�݂������̂��Ƃ����m���v�Ɋ�Â��Ă����Ƃ����B
�@�����āA���̗�Ƃ��ăg�}�X�E�s�b�g�i1653-1726�j���グ�A�u���߂͖��҂Ƃ��Ĥ���ɂ͗�Ԑl�Ƃ��Ĥ���Ȃ킿����߂͂�����̖f�Տ��l�Ƃ��Ĥ���ɂ͓��C���h��Ђ̃}�h���X�m���Ƃ��Ĥ�C���h�ō��𐬂����̂���ނ͌̍��ŃI�[���h��Z�A�����̋c��I����ƂƂ��ɒn�����w�������v�i�ȏ�A�g�����F���A��2���Ap.217�A1974�j��܂��A�ނ̓}�h���X�m���ݔC���ɋ��z�̃_�C�A�����h���W�߁A������t�����X�����ɔ��������Ƃł��L���ł���B
�@�����h�����C���h��Ђ́A����̂Ȃ��ŗ��v���̎��ɂ��āA�����g�p���Ă���700-800�݂Ƃ�����^�D��400-600�݂Ƃ����D�Ɏ��ւ��Ă���B��������������������ɂ�������炸�A�C���O�����h�̌��Ղ͏��߂Ē����ɂ܂ōL����A�����C��ł�150-200�݂̑D�����g�p���ꂽ�B
�@�C�M���X���C���h��Ђ́A��ʂ̃R�[�q�[���C�G�����̃��J����A�����Ă������A1736�N�ɂȂ�ƒ����R�[�q�[���]�����ǂ��Ȃ�B�������A���ł͖��A�𖠉��点�A���C���h��Ђ̌��Ղ̏����ɂ��Ȃ�Ȃ������B�܂��A�V���N�ⓩ����𒆍�����A�����Ă������A�ł����l�̂��铌���̏��i�̓x���K���p�̏����ȃV���N�ƃR�b�g�����i�ł������B�����͗T���Ȑl�X�̍����ȃt�@�b�V�����ł������B�����ݕ��̉^������1�ݓ�����20����ނł������B
�@���C���h����̗A���i�̍\���́A18���I�����Ɣ��ł́A�傫�ȈႢ���݂���B1699-1701�N�̗A���z��75������ނ���109������ނւ̑������A�A���i�̍\���͑@�ەi69.2�A�Ӟ�13.6�A���E�R�[�q�[2.2�A�����E���1.9�߰��Ăł��������A1752-54�N�ɂȂ��54.4�A2.9�A35.4�A4.1�߰��ĂƂȂ�B
���C���O�����h�A�z����Ղɖ{�i�I�ɎQ����
�@�C���O�����h�́A1680�N��Ȍ�A�X�y�C������ނ���ƁA�z����Ղɖ{�i�I�ɎQ�����顓z��D�̕�`�ͤ�����h������u���X�g������o�v�[���ɍL�����Ă�������A�t���J����A�����J�ւ̓z����Ղ̋K�͂́A300�N�ԂŖ�1500���l�Ƃ����Ă��邪����̂����C�M���X�͖�200���l���邢��300���l�����Ղ����Ƃ����B�܂��A�C�M���X��18���I���ɂ����ēz����Ճu�[���ƂȂ�A���̌��ʂ͑���傫�����������A�N�ԕ���7���l�ł������Ƃ����B�ŏ����爫�Ƃ݂Ȃ���Ă��Ȃ��礂�߂���킯���Ȃ������B�z����Ղ͢���̈�Y��ł��邽�߂��A�C�M���X�l�͑������ӂ�Ȃ��
�@�z��́A�L���ȃA�����J�ւ̒��ԍq�H�̓r���ɂ����Đ��v����A��������ł��邪�A���̐��͓z��̐��ɉ����đ�ʂƂȂ����B�z����Ղ́A�z��̎��S�����Ⴏ��Τ���ׂ̖��͂���߂đ傫�����̂ƂȂ�����z�ꂪ���ʂƁA2�����10��ݸނ���3�����10��ݸނ̑����ƂȂ����B���̊z�͒j���z��̓����̒ʗ�̍w�����i�ł���A���C���h�����ł�18����ނŔ����Ă����B���v�����˂Β����͐��ƂƂ��ɗ��ꂽ�B
�@�`���[���Y2���̒�ŁA��̃W�F�[���Y2���i�݈�1685-88�j�ƂȂ郈�[�N���́A�z����Ղ����ł���Ƃ͍l���Ă��Ȃ������B1660�N�A�A�t���J�ƌ��Ղ��Ă����C���O�����h�����`����ЂƂ�����Ђ͔ނɌh�ӂ�\���A����̓������ؖ����邽�ߤ�z���DY�iDuke of Yoke�̗��j�Ƃ��������̏Ă�����������ƂƂȂ����B���̉�Ђ́A�N�ԂɍŒ�3000�l����������_����A�����E�^�o�R�A���n�Ɍ���ł����B
�@�����́A�C���O�����h�����`����Ђɓ������Ă���A���̉�Ђ��`���邽�߁A��M�j�[��Ƃ����V�����R�C���܂Ŕ��s�����B���̃R�C���̓M�j�A�C�݂���A�����ꂽ���Œ�������Ă����B�C���O�����h���I�����_�푈�ɏ����Ă��A�z����Ղ̂قƂ�ǂ��I�����_�l�̎�Ɉς˂�ꂽ�܂܂ł��������߁A�������芪���Ȃǂ̓����Ƃ͓������������Ă���B
�@����ɂ�������炸�A1672�N�ɉ����A�t���J��Ђ��ݗ�����A�l�X�Ȃ��Ƃ������オ��B1680-88�N�ԁA�����A�t���J��Ђ͖�250��̓z��q�C����悵�A60,783�l��D�ς݂����Ƃ���Ă���B���̂����A46,396�l���邢��4�l��3�l���A���̍q�C�Ő����c�����B
�@��������A�����A�t���J��Ђ̓C���O�����h�l�̂����菤�l�Ƒ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B1698�N�A�z����Ղ͂��ׂẴC���O�����h���l�ɊJ�������B���̏ꍇ�A10�߰��Ẳݕ��ł������A�t���J��Ђ̎�蕪�Ƃ��Ďx�����K�v���������B1680-1700�N�ԁA30���l�̓z��A�V���E�ł̉��i�ł�����300������ވȏオ�A�����A�t���J��Ђ�����菤�l�ɂ���ăC���O�����h�D�ɐςݍ��܂ꂽ�ƕ]������Ă���B
�@�Ȃ��A18���I���߂܂ł̃C���O�����h�l�̓z����Ղ́A���̑S�̂�10�߰��Ăɂ��y��ł��炸�A����ȊO�͐��X�y�C���l�A�|���g�K���l�A�I�����_�l�A�����ăt�����X�l���A�����Ă����B
���ݕ����l�̗̍p�A�p�D�_�L���遟
�@���L�D�̊Ǘ��D��́A�ʏ�A���̑D�̌o�c�̕����Â��������Ō��肷��悤�ȏꍇ�A���̑D�̍ő�V�F�A�����D��̓��ӂ����߂�ꂽ�B���̓��ӂ̂Ȃ��ɂ͑D���̎w���ƂƂ��ɁA���ƕs���ɂȂ����ꍇ�̑D�̏��u���܂�ł����B�Ǘ��D��͏�g�����ق��A�ݕ���T���A�^�����W�����A�����ďC������z���Ă����B�����q�C�̏ꍇ�A���ꂪ�I����Ă���A�D�傽���͔z������������Ȃ邩������邱�ƂɂȂ����B
�@�D�������ɂ͋���Ȋ��҂����Ă����B�D���Ƃ����E�͑D��Ɛe�����W�����Ԃɓ�����������D���́A�ݕ������Ƃ��A�D�傠�邢�͗p�D�҂ɂ���Ďw�����ꂽ���悷��Ǘ��l�A�������A���邢�͑㗝�l�̖��߂ɏ]���悤�A�w������邱�Ƃ��������B���������E����17���I���ɂ͉ݕ����lsupercargo(�ωē�)�Ƃ����p��ɒu��������ꂽ�B
�@�������A�o���g�C�ł́A�D���͍q�C�Ɠ����悤�ɐωׂɂ��Ă��A�I�n�A�ӔC���������B���̒n���̌��Ղ͌��܂肫�������ՂɂȂ��Ă����̂ŁA�D�ς݂ɂ��炩���ߐӔC�����X�[�p�[�J�[�S�Ȃ��ł��܂���Ă����B�n���C�ł́A�D���͂����ނˁA������A�Ǘ��D�傪�Ȃ��Ă���A���̐ӔC�͍q�C���Ԃ������Ȃ�قǑ傫���Ȃ����B
�@�Ǘ��D�傪�A�ǂ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�v�Ȍ���́A���ꂼ��̖ړI�ɑ����ėp�D�_������Ԃ��Ƃł���B�p�D�_��́A�ʂ̍q�C���Ɍ����̂��قƂ�ǂł���������^�q�҂��q�C�̐����x������ςݍ��ݗʂ̑��ǂŌv��悤�ɂȂ������߁A���ԗp�D�_��time charter�͑D���p�D�_��tonnage charter��A���C���⍻���A�I�C���A���̑��ݕ�����葽���ςނ��Ƃ����߂鋦��i���ʗA���_��j�ɒu���������Ă������B
�@1650�N�Ȍ�A���ԗp�D�͂܂�Ƀ^�o�R���ՂɎg���邾���ɂȂ�A�܂�1680�N�Ȍ�A�����̗A���ɂ܂�ɗp����ꂽ�B����̊���炢���Θ_�O�ł��邪�A�ז����Ԃ͑�ϐ�������Ă����B����̎��Ԉȓ��ɑD�ς݂��I���Ȃ��ꍇ�A�p�D�҂͑D���1���P�ʂőؑD�����x����˂Ȃ�Ȃ������B1660�N�Ȍ�A��g���̌ٗp��x�����͑D��̕��S�ƂȂ�A�p�D�҂͊W���Ȃ��Ȃ��Ă������B
�@�㗝�l�̃l�b�g���[�N���C�O�ɂ�����ɍL�����Ă������B�Ǘ��D��́A�p�D�_�Ȃ��ꍇ�A�ݕ����l�����Ă��ꂻ���Ȓ����l��㗝�l������Ƃ���ɁA����Ɏ����̑D�������čs���悤�ɂȂ����B
�@�D��͉��炩�̑��Q���Ă��A�ی����L���s���킽��悤�ɂȂ��Ă����B�ی����̕������[�g�͕ی�����3�߰��Ă�����ȉ��ł���A�펞�댯���[�g��6-14�߰��Ăł��������A���ɂ�35�߰��Ĉȏ�ɂ��������邱�Ƃ��܂�ɂ݂�ꂽ�B�펞�ɂȂ�ƁA10���1����͏��Ȃ��Ƃ��Ă��A�˂ɝ\�߂����댯���������B17���I���ɁA�C���͎�����A��������Ă����̂ŁA�ی����ɗǂ��e�����y�ڂ��Ă����B
�@�C�^�Ƃ́A1580�N�Ȍ�}���ɐ������邪�A�킯�Ă�1660�N����1689�N�ɂ����āA�����̎��ɑ���Ȃ��Y�Ƃ���A�C���O�����h�̋}���ɔ��B����Y�Ƃ�1�ɂ̂��オ���Ă������B1582�N����1686�N�܂ł̖�1���I�̂������ɁA�g������6.7���݂��班�Ȃ��Ƃ�34���݂ƁA5�{�ȏ�����������B���̊ԁA�l���͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ���A2�{�قǑ��������B�C�^�Ƃ�1�̎Y�ƂƂ��āA���܂�_�ƁA�D���ƁA�����Č��ƂɎ����Y�ƂƂȂ����B
�@�C���O�����h�̗A�o�ƍėA�o�̉��z��3�{�ƂȂ�A�C�^�Ƃ̓����h���̔ɉh�ɍv������悤�ɂȂ����B1689�N�ɂ́A�l��150���l�̂���5���l���邢��30����1�̐l�X���C�^�Ƃɏ]�����Ă������A���̐���ɂȂ�Ƃ��̎Y�Ƃ̔��B�̃y�[�X�̓X���[�_�E������B
�@�����h�����C���h��Ђ̍ŏ��̍q�C�̎w���́A�W�F�[���Y������J�X�^�[�i���A1554?-1618�j�Ɉς˂�ꂽ�B�ނ́A�Ⴂ������|���g�K�����Ղɏ]�����A�܂��A���}�_�͑��Ƃ̐킢�ɎQ�����Ă���B����ɁA���C���h���������s���Ă����B
�@�W�F�[���Y������J�X�^�[�̓I�����_�l��葁���A1591�N3�ǂ̑D�𗦂��ē��C���h��ڎw���B���̑D���́A�A�t���J��[�����A�C���h�œ�[�̃R�����������o�āA�C���h�l�V�A�̃X�}�g�����A�����ă}���b�J�Ɏ������Ƃ���邪�A�A�r�A�����B�����c�����l�X�́A���C���h��������t�����X�D�ɏ���āA1594�N5���A������B����ł��A�ނ͗L�p�Ȓm�������Ƃ����B
�@�����h�����C���h��Ђ̍ŏ��̓��C���h�ւ̍q�C���J�n�����B�W�F�[���Y������J�X�^�[�̓��b�h��h���S�����A�w�N�^�[���A�A�b�Z�V�������A�����ăX�U�����Ƃ����ӋC���V��4�ǂƐH���⋋�D�M�t�g��(130��)������ď�g���⏤�l��500�l�������A��A1601�N2��13���A�E���E�C�b�`����o������B
�@�D�c���W�F�[���Y������J�X�^�[�̓h���S�����ɏ�D�A�f�[���B�X����Ȑ���ē��l�ƂȂ�B�h���S�����̓J���o�[�����h������3700����ނŔ������ꂽ�D�ŁA����܂Ń}���X��X�J�[�W���Ƃ������B���̑D��600�݁A��g��202�l�̑�1���̌R�͂ł������B�W������~�h���g���͕��D�c���Ƃ��āA�w�N�^�[��(300��)��108�l�ƂƂ��ɏ�D�����B�E�B���A����u�����h���w������A�b�Z�V��������260�݂ŁA��g��82�l�ł������B�X�U����(240��)�̓W������w�C���[�h���w�����A���̏�g����88�l�ł������B�����3�ǂ͂���������������̃����@���g���ՑD�ł������B
�@������̑D�͐l���̂ق��A20�������̐H���ƕ���A�e��ł��ӂꂩ����A�܂�7000����ޑ����̏��i��20,000����ޑ����̃X�y�C���d�݂��ςݍ��܂ꂽ�B���̑��D�q�̗]����A�C���ɗZ����������q�C�O�Ɏx�����ꂽ�����ł����Ĕ����t����ꂽ�ݕ��A��ЊW�҂̉ݕ��A�����ĕK���i�ȂǂŖ��ߐs������Ă�����B�S���i�A�X�Y�A���A���L���n�A�f�{���V���Y�J�[�W�[�D�A�����ċ����A����A���ݕ��ł������B
�@�����J�X�^�[�̐����ɂ��A���C���h���ɂ����Ď��R�Ɍ��Ղ���ƂƂ��ɁA�ł��̎Z���ǂ��Ƃ���ʼn��q�̉ݕ����y�b�p�[��X�p�C�X�ƌ������Ă悢�Ƃ�����������Ă����B����́A���ʂ��l���A�������A���b�N�X�A���]�A���ЁA���A�����ċM���悤�S�|���Ă���B
�@7�����������āA��A�t���J�E�P�[�v��^�E���̃e�[�u���p�ɂ��ǂ蒅�����B�ʏ��蒷�����Ԃ��������̂́A�ԓ��̖k���̖����тŁA�����̎��Ԃ��₵�������ł������B���^�D�ł�100�l�ȏ�̒j�������a�Ŏ���ł������A�����J�X�^�[�̃h���S�����͖����ł������B����͈�l��l�ɖ���3�����̃�������W���[�X��^����ƂƂ��ɁA���߂ɂȂ�܂ł͏�g���ɍd���H�����o�����Ƃ��ւ��Ă����B��������W���[�X�̓n�t��v���b�g�i���A1552?-1611�j���p�ӂ������̂ł������B
�@�D�c�́A�a�l�𗤏�Ŏ��Â��邽�߁A�e�[�u���p�ɕd�����Ă���B�Ĕ�����O�A1000�C�̗r��42�C�̗Y�����Z�����炦�āA�H���Ƃ��Đςݍ���ł���B����8����̓S�_1�{�Ɨr1�C�A�S�_2�{�ƗY��1�C���������Ă���B�C���h�m�̂������̓��Ő���⋋���Ă��邪�A����1�̓���13�l�����ꂽ��������Ŏ���ł���B�ނ炪�A�k�X�}�g���̃A�`���i���o���_��A�`���j�ɒ������Ƃ��A�����h���o�Ă��炷�ł�1�N���o���Ă����B
�@�A�`���̉��ɁA�����J�X�^�[�̓G���U�x�X��������̐e���Ƒ��蕨�������o���A��������A�łȂ��̌��ՁA�~��A�ٔ����A�s�ߕߓ����A�����ĐM�̎��R��F�߂鋦��ɏ�����������Ă���B���l�����̓y�b�p�[�����Ǝ��݂����A�����ɂ���͂����Ȃ������B
�@�����J�X�^�[�̓}���b�J�C�������q���A900�݂̃|���g�K���̃J���b�N��\�߂��Ă���B���̑D�̓C���h�̃x���K���n������}���b�J�Ɍ�����600�l�̗��q�Ƌ��ڂ̉ݕ����ڂ����Ă����B�C���O�����h�l�́A�L�����R��s���^�[�h(�ʐF�z�A�o�e�B�b�N�j����������950�������������̑D�Ɉڂ��ւ�����A�J���b�N���ߕ����A�q�C�𑱂��A�A�`���ɖ߂��Ă���B�y�b�p�[���킸�������ς�ł��Ȃ������D���L�����R��ς�Ŗ��D�ƂȂ�A�A�����Ă���B����1�ǂ́A���̃X�}�g�����ł����y�b�p�[�ƃO���[�u�����Ŗ��D�ƂȂ�A����܂��A�����Ă���B
�@���b�h��h���S�����ƃw�N�^�[���̓J���b�N�̎c��ݕ���ς�ŁA�W�������̃o���^���Ɍ����A�������Ă���B�����́A�I�����_�l��1596�N�Ƀ|���g�K���l��ǂ��o�����Ƃ���ł������B�����J�X�^�[�̓o���^���̏Z����I�����_�l�ɉ������}�����A�o���^���̎x�z�҂���C���O�����h�l�͓��n�ŒN�ɂ��ז����ꂸ�Ɍ��Ղł���ƍ������Ă���B�����̏��l�́A�}���[�V�A��C���h�l�V�A�̊e�n�Ɠ����悤�ɁA���łɃo���^���ł���b���ł߂Ă����B
�@5�T�Ԃ�����ƁA�����h�����玝���ė������i��276�܂̃y�b�p�[�ƌ������A����2�ǂ����D�ƂȂ��Ă���B�܂��A�����J�X�^�[�́A�o���^���Ɍ��Պ�n��ݗ����邽�߁A3�l�̏��l�ƒj����8�l���c���Ă���B�܂��A�s���l�X�ɐ��l�̏��l�ƒj�������悹�A�}���b�J�ŏ��ق���낤�Ƒ���o���Ă���B�ނ�2�ǂ̑D�́A1603�N2��21���o���^�����o�����A����9��11���Ƀe���Y��ɋA�����Ă���B
�@�����J�X�^�[���4�ǂ̑D��1�ǂ��������ƂȂ��A�����Ĥ100������ވȏ�ɑ�������y�b�p�[�������A��A�����ɓ����������l��95�߰��Ă̗��v�������炵���B���̊�ՓI�Ȑ����ɂ���āA�C���O�����h�ɂƂ��ē��C���h���Ղ����v�̌����܂����ՂƂ݂Ȃ���邱�ƂƂȂ���������J�X�^�[�͏��C����A�����h�����C���h��Ђ̗����ɂȂ�����A�ސE���Ă���i���̍��A�z�[�v��10�͂ɂ��j�B
�����C���h��ЁA���БD����p�D�ɐ�ւ��遥
�@�����h�����C���h��Ђ́A���ꂪ��������ꏊ���C���O�����h���痣��A�܂��C���h�m�ł̓��[���b�p���痈�Ă���O���D�Ƃ́A�����Փ˂��N����댯�����\������Ƃ��������R����A���܂܂łɂȂ��Ǝ��̋@�\�𐮂��Ă����B
�@���C���h��Ђ́A�����C�R��K�v�Ƃ���ꍇ�͕ʂƂ��āA�500�l�̊C�������g��6�ǂ̗ǑD��6�ǂ̃s���l�X��Ƃ����C���͂ł����āA���Ђ̑D������q���邱�Ƃ��F�߂��Ă����B�܂��A���̉�Ђ��A���������i�͎��炪�B��̔����ƂȂ�A�l�̌��Ղ��֎~����K���������Ă����B�������A���̋K����1635�N�܂Ŏ{�s����Ȃ������B���̉�Ђɓ�������ꍇ�A���l�͑����ʂ̋��z���x�o����K�v���������B
�@1601�N����1612�N�ɂ����Ă̍q�C�̗��v��155�߰��Ăł��������A���̌��30�N�Ԃɂ���3����1�ȉ��܂łɗ������݁A1617-32�N�͓���12�߰��ĂƒႩ�����B�g�D���Ҍ�A1671�N����1681�N�ɂ����Ďx����ꂽ�z�����͗����ō��v240�߰��ĂɂȂ�A1691�N�܂ł�10�N�ԂŔz�������͍��v450�߰��ĂƂȂ����Ƃ����B
�@�����̓��C���h��Ђ��g�p�����D�́A���łɂ݂��悤�ɂقƂ�ǂ������@���g��Ђ̏��l���甃��������D�ł������B�����͑�^�ŕ������ǂ������B�ŏ��̃V���W�P�[�g�ł́A�D���Ƃ��̔��i��45,000����ށA�����ĉ��q�ݕ���27,000����ނł������B���̎x�o���z�́A1553�N�ɖk���q�H�T���̓����z�̖�6�{�ł���A1988�N���i�Ŗ�600������ނƌ��ς����铊���z�ł������B
�@1607�N�A�����h�����C���h��Ђ̓����h�������̃f�v�g�t�H�[�h��u���b�N�����̑��D���ŁA���БD�������A�C�����͂��߂�B���̑�^�̑�1�D�̓U��g���C�h��C���N���[�Y���A��1000�݂ł������B��������A���D������������Ƃ��������Ă���A�����q�C�̓r��A�W�������œ�j���Ă���B�D�͓G�̍U�������킹�邾���̑傫�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�C���O�����h�l�ɂ����Ղ̋K�͂͑�^�̑D�D�ł���قǂɂ͑傫���Ȃ��Ă��Ȃ������B
�@1615�N�A�g�p����D�͍Œ�300�݂���傫����600�A700�݂��炢�̑D���œK�Ƃ���A��͑D��300�݂���350�݂ɐݒ肳�ꂽ�B���̉�Ђ̑D�́A�����̃C���O�����h�D�Ƃ��čŗǂ̕��ނɑ����Ă���A1601�N����40�N�܂ł�168��77,175�݂������Ɍ����������A1640�N�܂łɋA�������̂�104��54,314�݂ł������B
�@���̎j���ł́A�o�������D��60�߰��Ă��߂������A����͑�^�D���قƂ�ǂł������B�A�����Ȃ������D�����ׂĎ��̂ɑ������킯�ł͂Ȃ��B���ǂ��͓����Ɏc���čq�C���Ă���A�܂����ǂ��͌��n�Ƒ��̗̓y�̌��Ղɏ]�����Ă����B���̃A�W�A�n��Ԍ��Ղ͌��Օi���W�ׂ�������v�̑傫�ȕ���ł͂�������������h�����C���h��Ђ͌�q�̂悤�ɓ���A�W�A�Ⓦ�A�W�A�Ɍ��Ջ��_�����݂ł��Ȃ��������ߤ1661�N�ɂ͂��ƓP�ނ��Ă��܂�����̌�͎����ՂɈς˂���
�@1629�N�ɂȂ�ƁA�����h�����C���h��Ђ͎��БD����p�D�ɐ�ւ��A1654�N�ɂ̓u���b�N�����̑��D���蕥���A�f�v�g�t�H�[�h�̑��D���̈ꕔ��q�ɂ�C���h�b�N�Ƃ��Ĉێ�����悤�ɂȂ�B���̌��ʁA���C���h��Ђ̎�Ȋ���͉�Ќ�p�D�������Ō������A�����ŏ��L����D��ɂȂ�A�������Ђɗp�D�ɏo���悤�ɂȂ����B
�@���C���h��Ђ̎Љ��͂����ނ˃����h����V�e�B�̃r�V���b�v��Q�C�g�\���[�f���z�[����X�g���[�g�̋��ɂ������B���̋��́A���N�ɂ킽���ăC�M���X�C�^�̍����n�ł������B
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
|
�@���C���h��ЂƂ̗p�D�_��͎��R���J�̋������D�Ō���邱�ƂɂȂ��Ă������A���ۂɂ͏A�q���Ă���D�̑D�傪�V������D��p�ӂ��č����o���A�����p�D���Ă��炤���Ƃ����s�ƂȂ����B����ɂ��A���C���h��ЂɑD�����p�����Ē��邱�Ƃ�1�̌����ƂȂ�A�}�����E�C���^���X�g(�C�^��)�Ƃ��������D��O���[�v�����܂ꂽ�B���̂��߉^���͍����ƂȂ����B1783�N�̉����^����1�ݓ�����33����ނł��������A1785�N�ɂ�26-9����ނɒቺ�����B���̌p���p�D���́A1796�N��35������ޕ⏞�����āA�p�~�����B
�����C���h��ЁA�I�����_�ɔs��āA�C���h�ɋ��_��
�@�I�����_���C���h��Ђ́A1605�N�ɂȂ��ă}���N�i�����b�J�j�����̃A���{����(�A���{�C�i��)����|���g�K���l����|���ėv�ǂ�z���B�������A�����̓A�W�A���Ջ��_�ɂȂ肦�������B�I�����_���C���h��Ђ́A1619�N�W�������̃o�^���B�A�ɍP�v�I�Ȍ��Ջ��_�����݂��邱�Ƃɐ����A����ɂ���ăC���h�l�V�A���ׂ̍��h���̌��Ղ�Ƃ��߂��悤�Ƃ���B
�@����ɁA�����h�����C���h��Ђ��Q�����悤�Ƃ��邪�A�I�����_����җ�Ȓ�R�ɏo��B1623�N�A�W�������̃o���^���Ƃ��̎��ӂɂ��������Ջ��_����A1�T�Ԃ������Ȃ������ɁA�C���O�����h�l�͒ǂ��o�����B�����āA�����N�A�C���O�����h�̂����菤�l���}���N�����̌��A���{���̃A���{�C�i�ŁA�I�����_�l�ɂ���đ�s�E�����B���̃A���{�C�i�����ɕꍑ�̃X�`�����[�g�����{�͎�����܂˂��Ă������ł������B1623�N�ɂͤ�����h�����C���h��Ђ͒��肩�礓P�ނ���
�@�������Ĥ�����h�����C���h��Ђ͓���A�W�A�A����ɓ��A�W�A����P�ނ��邪�A�����ɂ����Ă��ł��d�v�Ȓn��ƂȂ����̂̓C���h�ƃC�����ł������B
�@�����h�����C���h��Ђ́A1-2���̍q�C�͓���A�W�A�Ɍ������A�Ӟ��ȂǍ��h���������A�������A���ꂪ��ʂł��������ߔ���s���s�U�ƂȂ����B�����ŁA1607�N��3���q�C�̓{���x�C�ߍx�̃X�[���g�Ɍ�����ꂽ�B����������K�[���c�邩����Փ����͂����Ȃ��������1611�N��g�[�}�X��x�X�g�D�����A�܂�1614-15�N�j�R���X�E�_�E���g���D�����|���g�K���͑���ł��j�邱�ƂŤ�X�[���g�ɂ�������Ղ��\�ƂȂ����
�@1612�N�X�[���g�ɏ��ق��ݒu���ꂽ���ƂɂȂ��Ă��顂��̌�A�C���h�嗤���C�݉����̍`������ɂ��ɁA���C���h��Ђ̏��ق����X�ƌ��݂���顂܂���C���f�C�A����}�����ƌĂꂽ�R��10�ǂ̑D�����X�[���g����n�Ƃ��Ĕz�u���꤃A���r�A�C���|���g�K���̃J���^�X��V�X�e���ɑ����ăp�X�|�[�g��V�X�e���ł����Ă��������Ƃ����B
�@�����A�C���h�嗤���C�݂łͤ�I�����_�̂悤�ɖ\�͂ɗ��邱�Ƃ���������C�݂��������~���ɐi�o����������h�����C���h��Ђ̓S�[���R���_�����̋������Ĥ1611�N�}�X���p�g�i���i���}�`���p�g�i���j�ɤ�C���h�ōŏ��̏��ق�ݒu���顂����Ĥ1639�N�ɂ͌��n�̎�̏������Ĥ�}�h���X�ɏ��ق�v�ǂ̌��݂��F�߂�꤂���Ɋł̖Ə��Ƒ��҂̊ł̔��z�̕t�^�Ƃ����j�i�̓��������顂��̌����ɂ���Ĥ�}�h���X�͍ő勒�_�ƂȂ顂����̋��_�͂�������ȕz�̏W�U�n�ł���������S�[���R���_�����ɂ͓������E�B��̃_�C�A�����h�z�R���������
 |
 |
| �����E�t�@���E���C����A1754 ��p�}���وψ�� |
�����E�t�@���E���C���i1712-60�j�� �����C�����فi�����h���j�� |
�@�C�����łͤ�����h�����C���h��Ђ̓T�t�@���B�[���̃V���[�E�A�b�o�[�X1���i�݈�1578-1629�j�ɋ��͂��Ĥ1622�N�܂Ń|���g�K���̊������_�ł������z�����Y�����U�����顂����Ĥ�A�b�o�[�X1�������݂�����z�����Y���̑Ί݂ɂ��餃o���_���E�A�b�o�[�X�����_�Ƃ���y���V�A�p���̌��ՂƊŖƏ��̓���������B�����������ɂ���ė��v�������̂̓C���O�����h�ł͂Ȃ�����N�ɘp���̌��Ղ�F�߂�ꂽ�I�����_�ł������Ƃ���顂���ɂ�褏��Ȃ��Ƃ�10���I����17���I�܂Ńz�����Y�����̂��ƂŔɉh���ɂ߂��z�����Y����C�`�s�s�Ƃ��čċ����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ����
�@16���I�Ō��10�N�A�₪���L�V�R�����m�݂̃A�J�v���R���瑾���m�����f���āA���t�B���s���̃}�j���Ɏ������܂��悤�ɂȂ��Ă�������A�W�A�ł͋�̓��[���b�p�ȏ�ɍی��Ȃ��s�����Ă����B�A�W�A�l�̓��[���b�p�Y�i���قƂ�ǔ������Ƃ͂��Ȃ��������A������͗~���������B���C���h��Ђ́A�ŏ���33�N�ԁA753,336����ނ̋�����A�o�������A���i�͂킸��351,236����ނł������B�����Ɛ����̃o�����X������悤�Ȕ������m�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
���A�����J�A���n�ɁA�N�G����l��z��𓊓���
�@�C���O�����h�́A��q�C�������łȂ��A�A��(�n)���Ƃ��Ă��Ō�̓o��҂ł������B���łɂ݂��悤�ɁA�C���O�����h�l�͐A���Ɏ��s���Ă����B1606�N�A�����o�[�W�j�A��Ђ��ݗ������B���̉�Ђ͑Η��������s�s�̏��l�������Q������g�D�ł������B�����h���̏��l�̑g�D�͓�o�[�W�j�A�A�v���}�X��u���X�g���A�G�Z�N�^�[�̏��l�̑g�D�͖k�o�[�W�j�A�ɐA�����邱�ƂƂȂ����B
�@�����h�����l�̑g�D�́A�N���X�g�t�@��j���[�|�[�g�i1565?-1617�j��c���Ƃ���D�c�ɓ������āA1607�N�k�A�����J�嗤�ōŏ��̊m�łƂ����C���O�����h�l�̓��A�n�ƂȂ����A�W�F�[���Y�^�E�������݂���B���̌���A�A�����J�ւ̐A�����{�i������B
�@�j���[�|�[�g�̑D�c�́A�X�[�U����R���X�^���g��(120��)�A�S�b�h�X�s�[�h��(40��)�A�����ăs���l�X�̃f�B�X�J�o���[���ō\������Ă���A�D�c���̓`�F�T�s�[�N�p�ɒ����ł���W�F�[���Y�����A�n�Ƃ��đI�ԁB���̃o�[�W�j�A�A���n�̓^�o�R�͔|�n�ƂȂ邪�A1619�N�ɂ͍ŏ��̃j�O�����A��Ă�����B1623�N�A�����@�͐A���n�̊Ǘ����茳�ɒu���A���̂Ƃ���B
�@���C�t�����[���i180���g���j���A1620�N9��16���s���O�����E�t�@�[�U�[�Y102�l�̈ڏZ�҂��悹�ăv���}�X���o�q���A�o�[�W�j�A��Ђ̔��s�������A����ɂ��������āA�o�[�W�j�A�Ɍ������B�������A���V��Őj�H������A�o�[�W�j�A����k����800��Ұ�ٗ]������ꂽ�A���݂̃}�T�`���[�Z�b�c�B�v���r���X�^�E���ɓ��`����B���̌�A���C�t�����[���������A�����ڏZ�҂��A�R�b�h���̐�[�ɋ߂��ꏊ�ɏ㗤���āA�����A���n�ƂȂ�v���}�X�A���n�����݂���B
�@�W�F�[���Y�^�E���ɓ��A���Ă���30�N�ԂɁA�k�A�����J�̊C�݂ɉ����ă}�T�`���[�Z�b�c�A�����[�����h�A���[�h��A�C�����h�ɁA�����ȓ��A�n�����݂����B1620�N��ɂȂ�Ɛ��C���h�����ɂ����A���͂��܂�B���̏����̓��A�n���A1624�N�Z���g��N�X�g�t�@�[��l�r�X�̃Z���g��L�b�c���ɍ��ꂽ�B1632�N�ɂ́A����Ƀo���o�h�X�A�l�r�X�A�����Z���[�g�ɍ����B
�@����珉���̓��A�n�́A�D���A�є珤�i�A���̑��H�ꐻ�i�A���A�r�[���A���C�����A�C���O�����h�ɂقڑS�ʓI�Ɉˑ����Ă������A���C���h�����ɂ̓C���O�����h��X�R�b�g�����h����H�Ƃ��^�э��܂ꂽ�B���A�n�̘J���͂̂قƂ�ǂ���Ⴂ���l�̔N�G����l�i�n�q����ق��Ă��炢�A���N�ԗꑮ�J�����s���J���ҁA17�18���I�̔��l�ږ���3����2�����������j�ł���A�������A�C�������h�l�����������B1626�N�A�Z���g��L�b�c����60�l�̃j�O�����������܂�邪�A�C���O�����h�̖{�i�I�ȓz����Ղ̂͂��܂�ł͂Ȃ������B
�@1635�N�����A�o�[�W�j�A�ƃ����[�����h�̃^�o�R�̎��n���́A�����̑�^�D1�ǂő������x�ł������B���̌�A�o�[�W�j�A�ȓ�͔M�ѐA���n�Ƃ��Đ������Ă������A���̑��傷��z��̋����ƎY�i�̗A�o�̓I�����_���l�Ɋ��S�Ɉ����A�A���n�Ƃ��Ă̂ɗ��v�̓C���O�����h�l�̎�ɓ���Ȃ������B���������̂��̂Ƃ���ɂ́A�s���[���^���v����̏d����`����i�q�C���j�ɂ܂��˂Ȃ�Ȃ������B
��17���I�A2�x�̊v����3�x�̃I�����_�푈��
�@17���I�́A�Q�[��y�X�g�̎S�ЁA�O�\�N�푈�Ȃǐ푈�̘A���A�����Ė\���┾���A�v���̔����Ȃǂ��N����A�S�ʓI��@�̐��I�Ƃ����B17���I�̃C���O�����h�̓X�e���A�[�g�����ɓ����邪�A���[���b�p�����ɘR�ꂸ�A2�x�̊v�����o������B
�@�W�F�[���Y1���́A���炪�g�b�v�ł��鍑����Ƃ̈�̉������߁A������ɏ]��Ȃ��s���[���^�����k��e������B���̒e����āA����ł݂��悤�ɁA1620�N���C�t�����[���ɏ�����s���O�����E�t�@�[�U�[�Y�̈�����A�A�����J�嗤�ɓn��B
�@�����Ƌc��̑Η��́A���łɃG���U�x�X1���̎���ɂ����������A�X�e���A�[�g���̂��Ƃł���ɐ[�܂�B����́A�e���[�_�[���̎���ɁA�_�H�Ƃ���Ղ̋����̒S����ƂȂ��Ă����A�W�F���g���[�ƌĂꂽ�Љ�K�w�������͂����߂Ă����B������~�߂��A�����͋c������A�Վ��ł��ۂ�����ł������B
�@�`���[���Y1���́A1628�N�u��������v������Ȃ���c������U���āA�ꐧ�x�z�ɏ��o���B�ނ́A�c����J���Ȃ��܂܁A�ł̋���������̗����A�����̎�藧�Ă��s�����B1634�N�A�ނ͕��̃W�F�[���Y1����30�N�ԕ��u���Ă����C�R�𗧂Ē������Ƃ��āA����܂ŊC�`�s�s�����ɉۂ����Ă����D���Łi���͐Łj��S���Ɋg�債�悤�Ƃ���B���̎x�����A�����ƃW�����E�n���f���i1594-1643�j�����ۂ���ƁA�D���Ŕ��Ή^�����S���I�ɍL����A�W�F���g���[�ȂNjc��x�z�w���������͂��߂�B
�@���̎������N����1637�N�A�`���[���Y1�����X�R�b�g�����h�ɍ�����̃V�X�e���������������߁A�������N����B1640�N�ɂȂ�ƁA�X�R�b�g�����h�R���N�U���Ă���B������ċc����ĊJ����A�����̉��\��j�~�����A�̉��v�@�i�D���ł�s���Ƃ���Ȃǁj���ʉ߂���B�������A���̑ԓx�͕ς�炸�A1642�N�c��Ƃ̑Η��͌���I�ƂȂ�B
�@1642�N8���A�C���O�����h�̎x�z�w�͉��}�h�i��ɋM���A�����n��A�������l�j�Ƌc��h�i��ɔ_�Ǝ��{�ƁA�����l�A�Ɨ����c�_���j�ɕ�����āA���킪�u������B�����͉��}�h���D�ʂɂ��������̂́A�c��h�̓X�R�b�g�����h�̔������͂ƌ��сA����ɃW�F���g���[�o�g�̃I���o�[�E�N�����E�F���i1599-1658�j������S�R���Ȃǃj���[�E���f���R���o�ꂷ��ƁA���}�h�͗Ɋׂ�B
�@�s���[���^���v�����N����ƁA�ѐD���H�ƒn���C�`�s�s�͍����̓G�ƂȂ����B�����C�R�͕ϐ߂��ċc��h�̑��ɑ���A�C�`�͋c��ɏ��D���������C���O�����h�̊C����Ղ͑��s���ꔽ�t�҂̕x�𑝂������A�������͊C�O���畐���A������̂�����ƂȂ����
�@1646�N�A�`���[���Y�͕߂炦���邪�E�o�A�Ăѕ߂炦���A1649�N�ɏ��Y�����B���̐�������A���a�����錾����A�s���[���^���v���͏I���B
�@�I���o�[�E�N�����E�F���́A���v���̋��_�ƂȂ����A�C�������h�ƃX�R�b�g�����h�Ɏc�s�ȉ�������Ă�B�܂��A�ނ͋c������U���āA�s���[���^���ƌR���ɂ��ƍِ�����z���B�g�����F���A�����ɂ��A�W�F�[���Y1���ƃ`���[���Y1���̎���Ɏ���ꂽ�u�C�㌠�������A�C�R���i�v�I�Ȕ\���̊�b�̏�ɂ��������_�́A�����U�t�Ґ��{���̂��̂ł���v�B�����āA���̐����̓��o�[�g�E�u���C�N�i1599-1657�j���C�R�i�ߊ��ɂ������Ƃɂ���A�܂��u���C�N�̓h���C�N��l���\���i��A1758-1805�j�Ɠ����̒n�ʂɂ���Ƃ����i�g�����F���A��2���Ap.155�A1974�j�B
�@�I���o�[�E�N�����E�F�������ʂƁA���̐����͂����Ɋ�������B1660�N�A�t�����X�̃��C14�����瑽��Ȕ���āA�I�����_�ɖS�����Ă����`���[���Y�̎q���`���[���Y2���i�݈�1660-85�j�Ƃ��đ��ʁA�������Â��Ȃ�B�ނ͋c��Ƌ������āA2��ɂ킽���ăI�����_�ɐ푈���d�|����B
�@�`���[���Y2���ɂ͒��q�����炸�A��̃��[�N���W�F�[���Y�����ʂɂ��悤�Ƃ��邪�A�ނ��܂��J�g���b�N�ł������B���̃W�F�[���Y2���i�݈�1685-88�j�̑��ʂ��߂����āA�c���2�吭�}�̌��^�Ƃ�����g�[���[�ƃz�C�b�O�ɕ������B���̑��ʂ��x������g�[���[�ɌR�z��������A�v���e�X�^���g�̍��C���O�����h���J�g���b�N�̉����}���邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��A�z�C�b�O�͊C�O�Ƃ̌��ՂɊS���������B
�@���̃W�F�[���Y2�����������q���Ȃ��������A���܂̃��f�i�����c���̂������ɒj�q���a������B�J�g���b�N�����������Ƃ��������c��̓g�[���[�ƃz�C�b�O���c�����āA�W�F�[���Y�r���ɓ����B�c��́A�W�F�[���Y�̖����A���[�̕v�ŁA�v���e�X�^���g�̍��Ƃ��ăt�����X�ɑR���Ă����I�����_���I���j�G���E�B����3��������R�c�������āA�W�F�[���Y�ƑΌ�����B�W�F�[���Y�͂�������ƃt�����X�ɖS������B���̖����v���𖼗_�v���Ƃ����B
�@�c��͍����Ƃ��ă��A���[�ƃE�B�����̕v�Ȃ��w�����A�����͋c��@�̗D�ʂ𖾕��������u�����͓T�v�ɏ������đ��ʂ���B����܂őΗ����Ă����C���O�����h�ƃI�����_�́A1689-1702�N���A���[�i�݈�1689-94�j�ƃE�B���A��3���i�݈�1689-1702�j�̓��N�A���ƂȂ�B
�@���̖��_�v���ɂ���āA�C���O�����h�̌��͍͂P�v�I�ɋc��ɌX�����ƂƂȂ����B�����āA���_�v���Ȍ�A�C���O�����h�̌o�ϐ����͔��̒i�K�ɓ��邱�ƂƂȂ�B
���C�M���X�鍑�̎�q�A�����ƐA���A���Ձ�
�@17���I�O���̃C���O�����h�́A�]���ʂ�_�ƍ��̂܂܂ł��褃A���g���[�v��I�����_�����̃~�b�f���u���N����b�e���_�����礃C���O�����h�l���K�v�Ƃ���K���X�����L�����o�X����l����s������Ƃ�����������̍H�ꐻ�i��A�����Ă�����܂���D���Ƃ��K�v�Ƃ��������}���ܤ�I�C����E�[���J�[�h�i�r�т����j�������A�����Ă�����؍ނ͑��D����z��M������z�b�v�̓r�[������͋��̕ۑ��Ɏg�����ߗA�����ꂽ�����ʕ�������ăX�p�C�X�͎�ȗA���H�i�ł��邪����C���̓��[�}����ȑO����ŏd�v�ȗA���i�ł������
�@�C���O�����h�̌��Ղ�16���I�㔼�ɕϖe���邪�A����͉ߋ��ɐݗ����ꂽ���[�g����O�ꂽ�Ƃ���ɁA�V�����i�̐V�����s������o�����Ɠw�͂������ʂł������B�������A���V�A��A�t���J�A�A�����J�A�����@���g�A�����ē��C���h�Ƃ̐V�������Ղ́A�C���O�����h�̊O���Ƃ̌��Ց��ʂɑ傫�ȉe�����y�ڂ��قǂł͂Ȃ������B����ł��A�C���O�����h�̒ʏ��⊔���g�D�ɐV�������͂�^���A�܂����Z���̉����ɑ��i���邱�ƂƂȂ����B
�@�z�[�v���́A�����̃C���O�����h�l�̊C���v�z�ɂ��āA���̂悤�ɂ܂Ƃ߂�B�u16���I�A���[���b�p�̑����̍��ɂ����č��ƈӎ������g���A�C�m�헪�̏d�v�����\�ɔF�������悤�ɂȂ������v�A�u16���I�̃C���O�����h�l�̓X�y�C�����N�����Ă��鋰�ꂪ�������̂ŁA�C���͂傳����ׂ����ƍl���Ă����B17���I�ɂȂ�ƁA���̈ӌ��̓��C�o���ƂȂ����I�����_�̂������ŋ��܂�A[�R���ゾ���ł͂Ȃ�]���Տ�̖ړI������A�C�m���������ׂ��Ƃ����~���ɂȂ����v�Ƃ���B�ʏ��H�ێ���j��Ƃ����C�m�헪�̓o��ł���B
�@�������A�u17���I�O���A���{�̖���A�N��̖��S�A�����ĊC��퓬�ɂ��Q��v���݂�ꂽ�Ƃ��邪�A����ɂ�������炸�C�M���X�鍑�̎�q�͈炿�A�u�������Ă��̂̓R���L�X�^�h�[���X[16���I�̃X�y�C����|���g�K���̓�A�����J������]�ł͂Ȃ��A���v����Րl�A�����Đ�����@���̑Η��҂ł������v�B
�@�u1649�N���Ȃ킿���a�������܂łɁA500������ނ��C�O�`���̂��߂ɂ����܂�A6���l�ȏオ�A�����J�Ɍ����A��5000�l�\�C���O�����h�̐l����500�l��1�l�\���C�O�ɓ������Ă����B�������A���̑ǂ̓g�[�}�X��X�~�X�i���A�����h�����C���h��Ђ̏��㑍��20�N�A�o�[�W�j�A��Ђ̏��㑍��9�N�j�Ƃ������古�l�������Ă����Ƃ��Ă��A��Ȑ��i�͂́u������Ђ⎄����������K�^��͂��l�������A���݂��Ɏh�������������ʂł������B1649�N�A�C�M���X�鍑�̎�q�̓C���h�ƃA�����J�ő傫���J�Ԃ���v�i�ȏ�A�z�[�v��10�́Ap.186�j�B
���N�����E�F���̏��l�̗��Q���т��ꂽ����
�@�C���O�����h�͗r�їA�o���ł��������A15���I�̂����ɖѐD���Ƃ��}���ɔ��B���16���I�O���ɂ͖ѐD���̑�֏o���ƂȂ����1530�40�N�㤉��������̊�@�ŊJ��Ƃ��Ēʉ݂���������A�|���h�̈בփ��[�g���\�����āA�C���O�����h�Y�̖ѐD���͈����ɂȂ褂��̗A�o�ʂ͂����܂��{������
�@�ѐD���̗A�o����������Ƥ�K�R�I�ɗr�щ��i���㏸����q�r�Ƃ����v�̑����Y�ƂɂȂ�15���I�㔼�A�q�r�Ƃ��g�傳���邽�߁A�y�n�͂����݁i�G���N���[�W���j�^�����N����B������A�g�}�X����A�i1478-1535�j�́w���[�g�s�A�x�ɂ����āA��r���l�Ԃ�H����ƕ]�����B���̈͂����݂����H�����W�F���g���[��[�}���i�Ɨ����c�_���j�͂܂��܂��x�T�ɂȂ�A��_�Ƃɂ�����o���悤�ɂȂ����B
�@16���I�㔼�A�G���U�x�X1�����ʉ݂����ǂ���ƁA�C���O�����h�̗A�o�͌�������B�����āA1568�N�I�����_�Ɨ��푈���͂��܂�ƁA�A���g���[�v�̓X�y�C���̍U���ɂ��炳��A�}���ɐ��ނ���B����ɂ��A�����h���\�A���g���[�v�̊�͕��āA�C���O�����h�̖ѐD���H�Ƃ͐[���ȕs���Ɋׂ�B�����ŁA�ѐD���̐V�����s����J�邱�ƂŁA���̊�@��ŊJ���悤�Ƃ��āA�܂������Y�i�ڂɓ��肵�悤�Ƃ��āA���X�Ɠ�����Ђ��ݗ�����Ă������B
�@16���I�㔼�A�C���O�����h�̓t�����h������̖S���҂��琻�@���K���Ĕ���̞��іѐD���Y���āA���[���b�p�����ɗA�o����悤�ɂȂ�B����͖����H�̕��L�̖a�іѐD���ɑ��ĐV�ѐD���ƌĂꂽ�B�܂��A�������A�K���X�����A���������������ȂǁA�V���������H�Ƃ������o������B�ΒY�Ƃ����������W���݂��顂����V���Y�Ƃ̑����ͤ�����A�ґ�i�ł������A���i�����Y���悤�Ƃ�����̂ŁA�W�F���g���[�w���͂��߂����̂ł������
�@�C���O�����h�̐l���́A1522�N�̖�230���l����1603�N�ɂ�310���l�ȏ�ɂȂ����Ƃ���A���̐l�������̈��͂�_�Ƃ͎x���ꂸ���@�I�ȏƂȂ顂��̊�@��w�i�Ƃ��ăs���[���^���v�����N���Ă����B1660�N�̉������ÈȌ�A�C���O�����h�̔_�Ƃ͐��Y�������サ�A�C����Ղ��܂���������B�������_�@�Ƃ��āA1656�N�̌㌩�ٔ����̔p�~�Ȃǂ������āA�㋉�̎�̌������ے肳�ꤒn��̎��L���Y�����m�F�����
�@�����ȗ���C���O�����h�ł͍����A�o��}���������ҕی쐭�Ƃ��Ă������A�������Ì��1663�N����89�N�܂ō����̏������i�����ȉ��ɂȂ�A�����A�o��������x�����鐧�x���������顂���͒n��x�z�̐��̐������ے����鐧�x�ł������B
�@17���I���A�ϋɓI�ȏd����`�����{�����B���a������1651�N��������Ì��1660�N�A1663�N�ɍq�C��Ⴊ���肳���B����͏]���ƈ���āA�C���O�����h���l�ɃC���O�����h�D�̎g�p���`���Â��邾���ł͂Ȃ��A�C���O�����h�̌��Ղ���I�����_�ȂNJO�����͂�r�����悤�Ƃ������̂ł������B�܂��A�����200�l����̓����I�ȏ��l�̗��v��ی삷��̂ł͂Ȃ��A���ꂼ��̎Y�Ƃɂ����ċN�ƉƂ̎Q����ۏႵ�悤�Ƃ���A�{���̏d����`����̈�ł������B
�@�N�����E�F���̎��㤃A�C�������h�̐�����A���A1655�N�̃W���}�C�J�̐�z�A1657�N�̃����h�����C���h��Ђ̊g�[����g�Ȃǂ��s����1655�N�A�N�����E�F���̐����v��̈�Ƃ��āA�E�B���A���E�y��(1621-70��y���V���x�j�A�A���n�̑n�ݎ҂̕������)�ɗ�����ꂽ�C�M���X�͑����W���}�C�J���̂���B�W���}�C�J�́A1670�N�̃}�h���[�h���Ő����ɃX�y�C������C�M���X�ɏ��n����A�z��ɂ�鍻���v�����e�[�V�����A�����ăA�t���J�l�z����Ղ̒��S�n�ƂȂ�B
�@�s���[���^���v�����̏��ƥ�A���n����ͤ���J�g���b�N�Ƃ����@���I��M����ړI����o�Ă͂������A�˂Ƀ����h�����l�̗��Q���т���Ă����B
���q�C��ᐧ��A�I�����_�Ƃ�3���̐푈��
| �@1651�N�A�N�����E�F���̋��a�����{�i1649-60�j�͍q�C���𐧒肷��B����́A���܂܂ł̐�����������̂ł������B�������Ì�A����ɏڍׂ�1660�N�q�C��Ⴊ�ʉ߂���B�����͌�������200�N�ԗL���ƂȂ�B �@1660�N�q�C���́A�C���O�����h�A�E�F�[���Y�A�A�C�������h�A�܂��͐A���n�ɂ����Đ^���ɏ��L����A���D������я�g����4����3���b���ł���D�i�ȉ��A�C�M���X�D�j�ɂ��Ȃ���A�@�C���O�����h�̃A�W�A�A�A�t���J�A�܂��̓A�����J�ɂ���̓y�ɁA���i��A�o���邢�͗A�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�A�����̓y�ɂ����ĎY�o���ꂽ���i���C�M���X�ɗA�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ����B |
 |
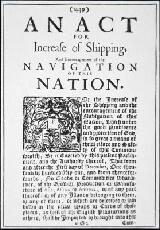 |
| ���o�[�g�E�E�H�[�J�\��A1649 National Portrait Gallery�� |
�̕\�� �i�ʐ^�j |
�@�C���O�����h�̍q�C���̑傫�ȖړI�́A�I�����_�̒��p���ՂƃI�����_�D�̗A���ɑŌ���^���邱�Ƃɂ������B�����ŁA�C�O���ŎY�o���ꂽ���i�́A���̌��Y�n�܂��͍ŏ��ɑD�ς݂��ꂽ�`����łȂ���A���Ƃ��C�M���X�D�ł����Ă��C�M���X�ɗA�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�D���V�A��g���R�̏��i�́A�C�M���X�D�܂��͌��Y���̑D�܂��͍ŏ��ɑD�ς݂��ꂽ�`�̑D�łȂ���A�C�M���X�ɗA�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ����B
�@���̑��A�E������^�o�R�A�����A�ȉԁA���I�Ƃ��������l�̂���A���n�Y�i�i���i�Ƃ��ꂽ�j�́A�C�M���X�₻�̗̓y�ȊO�̒n�Ɍ����đD�ς݂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�F���Y���̑D�܂��͍ŏ��ɑD�ς݂��ꂽ�`�̑D�ŗA�����邱�Ƃ��F�߂�ꂽ�ݕ��́A�O���l�A���ł��x����Ȃ���Ȃ炢�A�Ƃ����B
�@�܂��A�q�C���͗i������X�e�C�v�����ɂ���ĕ⋭����Ă����B�������Ì��1663�N�̃X�e�C�v�����́A���[���b�p�����̎Y�i�̓C�M���X�o�R�łȂ���A�A���n�ɗA�o�ł��Ȃ��Ƃ����B
�@�C���O�����h�ɂƂ��āA�I�����_�͉ߋ�1����̊ԂɁu�k���[���b�p��A�����J�̊C��Ť�܂��A�t���J��C���h�̑�m�Ť�����Ή������̏���Ȃ���킪���̊�Ő����������Ŗ���������C���O�����h�Ƃ��̃A�����J�A���n�Ƃ̉^���Ƃ��قƂ�ǓƐ肵�Ă��܂��Ă����v�̂ł���i�g�����F���A��2���Ap.156�j�B�C���O�����h�͖{�C�ɂȂ��āA�I�����_�ɗ����������K�v���������B�I�����_�Ƃ̊C��e�����߂��鑈���́A18���I�����܂Ō����������Ƃ͂Ȃ��������A���̑������͂��߂��̂͑��ł��Ȃ����a�����{�ł������B
�@�q�C���́A���E�̒��p���Րl�Ƃ��Ă̒n�ʂ��ւ��Ă����I�����_�ɂƂ��āA�傢�Ȃ鋺�ЂƂȂ����B�I�����_�Ƃ̊W�́A�C���O�����h�����Y�����`���[���Y1���̖����I���j�G���E�B����2���̍ȂƂȂ��Ă������ߤ�₦���Ă����1651�N��Ⴊ���肳���ƁA���̊W�͔j�]���āA��1���C���O�����h�E�I�����_�푈�i1652-54�j���͂��܂�B
�@��1���푈�ͤ���o�[�g�E�u���C�N�ɗ�����ꂽ�C���O�����h�͑��Ƥ�t�@���E�g�����v�i1597-1653�j������I�����_�͑��̑����ƂȂ����B1652�N�̃h�[�o�[���C��ł̓g�����v�A1653�N�̃e�Z�����C��ł̓u���C�N�����������߂邪������͂��Ȃ������B�����A���̐킢�ɂ��A�I�����_�̔�Q�͑傫���A�C���O�����h�Ɏ��v�͂����邱�Ƃ������ꂽ�Ƃ����B�I���o�[�E�N�����E�F���́A1654�N�ɃC�M���X�D�ʂ̍u�a�����ԡ
�@1663�N�̍q�C���͊O���l���L�̑D�͂����Ƃ��āA�험�i�łȂ��O�������D�̎g�p�𐧌����A������^�D�ɑ���⏕�����A��^�D�̒�`��ύX������ŕ����������B����́A�������ÈȌ�A�C���O�����h�l�������őD����������̂ł͂Ȃ��A�C�O����D���ʂɔ����t����Ƃ������Ԃ����P���邱�Ƃɂ������B����ɂ��A�C���O�����h�̑��D�Ƃ��}���ɕ������邪�A���̌�̃I�����_�Ƃ̐푈�ɂ���ēڍ�����B
�@17���I�O���́A�t���C�{�[�g�̓C���O�����h�ł�1300����ނ����������A�I�����_�ł�800����ނŌ�������Ă����B1676�N�ɂȂ��Ă��A�C���O�����h��250�݂̏��D��1�ݓ�����7�����2��ݸ�6��ݽ�����������A�I�����_�Ō������ꂽ200�݂̃t���C�g��4�����10��ݸނł������B�I�����_�l�͔N��700-800�ǂ��o���g�C�ɑ���o���A�܂�1000�Ljȏ�̃j�V���D���g�p���Ă������A���̂���600�ǂ͑�^�ł������B
| �@�����h���́A1665�N�̃y�X�g�嗬�s�66�N�̃����h����Ƃ����A�傫�ȍЖ�Ɍ������邪�A������O����A�C���O�����h��1664�N����A���n���߂����ăI�����_�Ƒ�2���푈�i1664-67�j���Ăт͂��߂Ă����B���̐틵�͓��R�̂悤�ɃC���O�����h�s���ƂȂ�A1666�N6���̊C��ŃC���O�����h�͑��̓f����C�e����i1607-76�j������I�����_�͑��Ɋ��s���āA6000�l�̕�������� �@�����āA��1667�N�ɂ͍u�a�������ɁA�����s�����̃C���O�����h�l���v�Ɉē�����āA�e���Y��ƃ��h�E�F�C���k���Ă����I�����_�͑��ɁA�`���^����`�F�X�^�[���U�����ꤍŗǂ̐�͂ȂǑ����̊͑D�������B�I�����_�D�ʂ� |
 |
| Pieter Cornelisz. van Soest��A1667 �����C��������(�����h��)�� |
�@17���I�̍q�C���́A�ꌾ�ł����Ύ����ݎ����D��`�Ƃ�������̂ŁA�C���O�����h�Ƃ��̗̒n�ւ̗A�����Ղ���I�����_�̒��p���Ղ�r�����A�C���O�����h�ƌ��Y�n���̑D��ɂ���Ď��d�낤�Ƃ������̂ł������B���ɁA����̃A�����J�A���n�Ƃ̌��Ղ͗A�o�A�A���Ƃ��ɁA���̗A���̓C�M���X�D�Ɍ���Ƃ�������ł������B
���C���O�����h�ƃI�����_�̒n�ʂ��t�]��
�@���̋ɒ[�Ƃ�����C����Ղ̎����ی쐭��ɂ�������炸�A���[���b�p�����������Ƃ��������Ƃ͂Ȃ������B���[���b�p�����́A�I�����_�̒��p���ՂɈˑ����Ă͂������A���̐���s���ɂ͊S���Ȃ������B�܂��A���[���b�p�������܂�����̐A���n���Ղɂ��āA�C���O�����h�Ɠ����悤�ɕ��I�Ȑ�����̗p���Ă����B�����������āA�q�C���̐��ۂ͂��̐�����x�����Ď��s���悤�Ƃ����A�C���O�����h�̏��l��D�傽���̈ӗ~�ɂ������Ă����B
�@�I�����_�Ƃ̑�3���푈�i1672-74�j���N����B����ͤ�`���[���Y2���Ɩ�������t�����X�̃��C14�����I�����_�ւ̐N�����͂��߂��̂Ɍĉ����Ĥ�C���O�����h���Q�킵�����̂ł�������I�����_�R�͕��킵�A�܂����Ă��f����C�e����ɘA���͑��͌��j����A�t�����X��C�M���X�̕�����ƂȂ�B�������A�I�����_�̔������Q�͐[���ł����Ĥ���̒����������v���ƂȂ�
�@�C���O�����h��3���ɂ킽��I�����_�Ƃ̐푈��ʂ��āA����߂Ėc��Ȑ��̃I�����_�D��ߊl���A�험�i�Ƃ����B��1���I�����_�푈�ł�1000�ǂ���1700�ǂ܂ł̃I�����_�D��ߊl���A��2���푈�ł͖�500������ނ̐������������ߊl�D��500�ǁA��3���푈��500�ǂł������B�����A�C���O�����h���I�����_�Ƃ̐푈�Ŏ������D�͂킸����500�ǂł������B1655-60�N�ɂ�����X�y�C���Ƃ̐푈��400�Ljȏ��ߊl�������̂́A�C���O�����h�D��1000�ǂ���1500�ǂقǂ��ߊl�܂��͔j�ꂽ�B
�@�C���O�����h�́A1652�N����1674�N�܂ł�22�N�ԁA���S�ǂ̗ǑD����������Ă���A���̂����ߊl���邢�͍w�����ꂽ�O���D���C���O�����h�l�ۗ̕L�D����3����1�ȏ�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ������B�������A�����푈���I���1675�N�ɂ́A����2����1�𐔂���܂łɂȂ����B�C���O�����h�̑D���́A17���I�㔼�A3�{�����������Ƃ����B
�@�q�C���{�s��A�C���O�����h�D�ɂ��A���͍��R�X�g�ɂȂ������A�C���O�����h�̊C����Ղ͉������Â����ɂ��Ċ����ɂȂ�A���̗A�o�͐��I���܂ł�3�{�ɂ��Ȃ�B���̂Ȃ��ł��C���O�����h�̃J���u�C��k�A�����J�ɂ���A���n�Ƃ̌��Ղ�����������������B����Ɍ�������āA���R�X�g�̃C���O�����h�D�ɑ��Ă����v�����܂�B
�@1664�N�A�����h������26�ǂ��m���E�F�[�ցA������22�ǂ��o���g�C�ɏo�����Ă������A1686�N�ɂ͂�����111�ǂ�65�ǂɑ�������B�܂��A���C���h�����ɂ�45�ǂ���133�ǁA�܂��k�A�����J�ɂ�43�ǂ���111�ǂւƑ������Ă���B�C���O�����h�̍`����o�������D�̔N�ԏo���g������1663-69�N����9.3���݂ł��������A1700-12�N�ɂ�27���݂ɑ�������B���̂����C���O�����h�D����߂�䗦��65�߰��Ă���86�߰��ĂɌ��シ��B
�@��3���I�����_�푈��A���[���b�p�����̓t�����X��I�����_�ȂǂƐ푈�𑱂��Ă����̂ŁA�C���O�����h�ɍD�@���K���B�C���O�����h�͒������Ƃ��āA�펞���ɕ������������Č��Ղ��L����ƂƂ��ɁA�I�����_���s���Ă����o���g�C�ƃC�x���A�����Ƃ̌��ՁA���ɉ��̌��Ղ�����肷��B�܂��A�C���O�����h����|���g�K���ɏ����𑗂�A�A��ׂƂ��ĉ���ς݁A�����g�r�A�̃��K��y�e���u���O�ɉ^�сA���∟���A�S�������A��悤�ɂȂ����B
�@�C���O�����h�C�^�̐����͑��D���ނ̎��v�����N�����B����ɂ���āA�C���O�����h�ł̓J�V��j�����s������悤�ɂȂ�A���̑�ւƂ��ă��~�A�}�c�A�G�]�}�c��A������������Ȃ��Ȃ����B����ɁA1666�N�̃����h���̑�Ȃǂ��؍ނ̎��v���������B1673�N����1700�N�ɂ����āA�N��200�ǂ���300�ǂ̑D���o���g�C����C���O�����h�Ɍ������Ă������A���I���ɂ͂����̑D�̔������C���O�����h�D�ł������B�����A�m���E�F�[����̖؍ނ̗A���́A���^���̃C���O�����h�D�͊�������A�����m���E�F�[���x�z���Ă����f���}�[�N�D�Ɉς˂��邱�ƂƂȂ����B
�@�C���O�����h�́A3���ɂ킽��I�����_�Ƃ̐푈��킢�����A���Ɍ����u�a���̂��тɗL���ɂȂ�Ȃ��ŁA�C�m�鍑�̑����ݏo���B����ɑ��āA�I�����_�͐푈�ɂ����Ղɑς����ꂸ�A����ɔ敾���āA�C����Ղ̔e�����C���O�����h�ɏ��炴������Ȃ��Ȃ�B�C���O�����h�́A18���I�Ō�̎l�������邢�̓A�����J�̓Ɨ��܂ŁA�q�C��Ⴊ���҂������ʂ�����B
�@�������A18���I���Έȍ~�A�q�C���̋K��͑ΊO�푈�����邽�тɁA���X�Ɗɂ߂�ꂽ�B����́A�������̑D��p�D���邱�ƂŌ��Ղ��ێ����Ȃ���Ȃ炸�A�܂��푈�Ɏ�肾���ꂽ���p�D�̑�֑D��K�v�Ƃ�������ł������B�܂��A�C�M���X�l�̑D�������p���ꂽ�̂ŁA���̌����߂ɊO���l�D�������܂܂łɂ��܂��Čٗp���ꂽ�B�Ⴆ�A�C�M���X����o������O���D�̃g�����䗦�́A���N�푈���A������7-8�߰��Ă���20�߰��Ăɑ��債���B
�@�����āA�q�C��Ⴊ���҂������ʂ��グ�����C���h������k�A�����J�̐A���n���Ղ̓����҂ɂƂ��āA���̏�Ⴊ���������ς�����̂Ƃ��Ĕr�˂���邱�ƂƂȂ�B����ɁA18���I�㔼�ɂ͂��܂�Y�Ɗv���ɂ���đ�ʂɉ����o����Ă���H�Ɛ��i���A�C�M���X�͐��E�I�K�͂ʼn���̐�������ɔ���J���K�v�ɔ�����B���̂Ƃ��A�q�C���͎��R�Ȍ��ՂƂ��̊g��ɂƂ��Ă̏�Q�ƂȂ�A1849�N�ɔp�~�����B
�����C���h��Ђ̕���ƍ����A�C���h�̖ȐD����
�@���C���h��Ђ́A���a�����A�傫�ȉ��v����B�܂��A�����Ƃ̌��Ղ͎����I�ɂ��ׂĂ̐l�ɊJ����Ă��܂����B1657�N�A�N�����E�F���̓�����ɂ���āA���呍��ō��@�ւƂȂ����B�܂���I�����_�Ɠ����悤�ɤ�����u�a����̌������^����ꤌ��n���{�ƂȂ����
�@�����āA��Бg�D�͍q�C���Ƃ̓����g�D����A���قƗ������ݒu���āA�o�c�̎�������ۂA�P�v�I�ȑg�D�ɉ��ς��ꂽ�B�o�������J����A����͑����ʂ��ĉ�Ќo�c�ɎQ�悵�A����ɂ͔z�������x������悤�ɂȂ����B1662�N�A�L���ӔC���̊�����ЂƂȂ�A�������{�͕ԍς��Ȃ������Ƃ��Ď�舵���邱�ƂƂȂ����B
�@�`���[���Y2�������ʂ��ĐV���������t�^�����ƁA���C���h��Ђ͒P�Ȃ���Չ�ЂłȂ��Ȃ�A���܂܂ňȏ�ɐ����I��i�@�I�Ȍ��͂�U�邤�悤�ɂȂ����B���̐��I�̍Ō��10�N�Ԃɗp�D���ꂽ�x�[�J���C��J�b�X�����A�x�h�t�H�[�h���A�^���B�X�g�b�N���A�X�g���[�g�T�����A�z�[�����h���A���V�A���A�}�[�V�����A�t���Q�[�g�̃U����b�Z�����A�E�F�����[�X���A�r���[�t�H�[�g���A�}�b�V���O�o�[�h���Ƃ������D���́A�ǂ��������n���œ������ꂽ�D�ł��邩���킩��B�����n���̋M���K�����C�^���i�D�̓�����Ƃ݂Ȃ��悤�ɂȂ����B
�@���̂Ƃ��ȍ~�A���̉�Ђ͋��Ȃ��Ă�����̉��ז_�������o�����Ƃ��F�߂�ꂽ���ƂŁA���Ղ͊i�i�ɑ�������悤�ɂȂ�B�܂��A1650�N�J���J�b�^�ߍx�̃t�[�O���A1662�N�{���x�C�A������1686�N�J���J�b�^�Ƃ����悤�ɁA���X�ƃC���h�̋��_���ݗ�����Ă������B�����A�W�������̃o���^���ł̓I�����_�Ƃ̕����������A1682�N�C���O�����h�l�͓P�ނ�]�V�Ȃ�����A����ɑウ�ăx���N�[�����i�X�}�g�����암�A���x���N���j���J���B
�@�C�M���X���C���h��Ђ̌��Պz�͎���ɑ������邪�A18���I�̍ŏ���3����1�܂ł̑����͂ق�̂킸���ł������B�X�p�C�X�ȂǓ������ґ�i�́A�]���ʂ�n���C�o�R�Ŏ������܂�Ă������A���łɃC���O�����h�͊�]��o�R�œ��肵����A����珤�i��n���C�����ɋ�������܂łɂȂ��Ă����B
�@���̂���A�X�p�C�X�͕ꍑ�����ݕ��Ƃ��Ă̗D�z���������Ă���A�ݕ��̉��z��70�߰��Ă���80�߰��Ă͖ȐD���ƂȂ��Ă����B�y���V�A��x���K������̃V���N�ƁA�p�L�X�^������̃��z�[���̃C���f�B�S�����l����ݕ��ƂȂ�A�܂����C���h��}���o�[������̃y�b�p�[�ƁA�x���K������̏ɐ⍻������@�ݕ��ƂȂ��Ă������B���̂����A�ȐD���̗A�������́A�ѐD���H�ƂƂ̑Η����������B
�@�x�[�J���C��J�b�X�����́A1681�N�C���O�����h�����ɋA�������Ƃ��A�}�h���X�n������o�������ł����ȑD�Ƃ����A�ωׂ̋��z��8�������(1988�N���i��500������ވȏ�)�̒l�ł��ł������B�������A���̐ς݃g���̔����ȏオ�ɐł��������A���ꂪ�S�̂ɐ�߂鉿�z�͂����킸���ł������B
�@�C���h�ւ̗A�o�i�͂킸�������Ȃ������B�ѐD���A�S���i�A�����i�A�r�[���͂��Ă����A����S�͒ʏ�A��ׂƂ��ĉ^�ꂽ���A���̑����������ނ˕ꍑ�Ɏ����A����ꂽ�B1680�N��A���C���h��Ђͤ�C���O�����h�ւ̗A�����z�̖�14�߰��Ă������A��ƂȂ��Ă���A�܂��N�Ԃɔz�����Ƃ���20�߰��Ă��x�����Ă����B
�@�����h�����C���h��Ђ́A1680�N�Ȍ�����菤�l��C���Ƃ̋����ɂ��炳��Ă������A1698�N����1708�N�ɂ����Ă��̓Ɛ茠����~�����B����̓W�F�[���Y2�������r���āA�V���������ɃE�B���A��3�����o�ʂ���Ƥ�C���h���Ղ̓Ɛ�ɔ�����c��̐��͂������Ȃ��������Ɍĉ����Ĥ1698�N��E�B���A��3�����V��Ђ̐ݗ��𖽗߂��A����Ђ̓����������������̂ł���B
�@���̌�10�N�Ԥ����Ђ͂��̑������F�߂�ꂽ���Ƃ���A�V������Ђ̂��ꂼ�ꂪ�����Ȃ��礓��C���h���Ղ��s�����ƂƂȂ�����ނ�ͤ������Ԃ����Ɛ����H��ɑ����̋��i�������A�܂����݂��������c�邽�߂̐Ղ��s��ꂽ����̌��ʤ1708�N���C���h�ƌ��Ղ���C���O�����h���l�̍�����ЁA�ʏ̃C�M���X���C���h��Ђ��ݗ������B����������̊���͑��ς�炸�����h���̏��l���������S�Ť�u���X�g����n���Ȃǂ̒n���̏��l�͏��O����Ă����
�@����Б��قŌo�ϊw�҂̃W���T�C�A�E�`���C���h�i1630-99�j�́A����Ђ̓�����i�삷�邽�߁A10������ޔ�������Ƃ����B�g�����F���A�����ɂ��A���̍R���ɂ��āA�u�����̕x�͂��͂�A���r�A�̂����b�ł͂Ȃ��A�m���Ȏ����ł����āA���̏�ɔN1�N�ƃV�e�B�̍��Y���z����A�n���̐V�������傪�n�݂������̂��Ƃ����m���v�Ɋ�Â��Ă����Ƃ����B
�@�����āA���̗�Ƃ��ăg�}�X�E�s�b�g�i1653-1726�j���グ�A�u���߂͖��҂Ƃ��Ĥ���ɂ͗�Ԑl�Ƃ��Ĥ���Ȃ킿����߂͂�����̖f�Տ��l�Ƃ��Ĥ���ɂ͓��C���h��Ђ̃}�h���X�m���Ƃ��Ĥ�C���h�ō��𐬂����̂���ނ͌̍��ŃI�[���h��Z�A�����̋c��I����ƂƂ��ɒn�����w�������v�i�ȏ�A�g�����F���A��2���Ap.217�A1974�j��܂��A�ނ̓}�h���X�m���ݔC���ɋ��z�̃_�C�A�����h���W�߁A������t�����X�����ɔ��������Ƃł��L���ł���B
�@�����h�����C���h��Ђ́A����̂Ȃ��ŗ��v���̎��ɂ��āA�����g�p���Ă���700-800�݂Ƃ�����^�D��400-600�݂Ƃ����D�Ɏ��ւ��Ă���B��������������������ɂ�������炸�A�C���O�����h�̌��Ղ͏��߂Ē����ɂ܂ōL����A�����C��ł�150-200�݂̑D�����g�p���ꂽ�B
�@�C�M���X���C���h��Ђ́A��ʂ̃R�[�q�[���C�G�����̃��J����A�����Ă������A1736�N�ɂȂ�ƒ����R�[�q�[���]�����ǂ��Ȃ�B�������A���ł͖��A�𖠉��点�A���C���h��Ђ̌��Ղ̏����ɂ��Ȃ�Ȃ������B�܂��A�V���N�ⓩ����𒆍�����A�����Ă������A�ł����l�̂��铌���̏��i�̓x���K���p�̏����ȃV���N�ƃR�b�g�����i�ł������B�����͗T���Ȑl�X�̍����ȃt�@�b�V�����ł������B�����ݕ��̉^������1�ݓ�����20����ނł������B
�@���C���h����̗A���i�̍\���́A18���I�����Ɣ��ł́A�傫�ȈႢ���݂���B1699-1701�N�̗A���z��75������ނ���109������ނւ̑������A�A���i�̍\���͑@�ەi69.2�A�Ӟ�13.6�A���E�R�[�q�[2.2�A�����E���1.9�߰��Ăł��������A1752-54�N�ɂȂ��54.4�A2.9�A35.4�A4.1�߰��ĂƂȂ�B
���C���O�����h�A�z����Ղɖ{�i�I�ɎQ����
�@�C���O�����h�́A1680�N��Ȍ�A�X�y�C������ނ���ƁA�z����Ղɖ{�i�I�ɎQ�����顓z��D�̕�`�ͤ�����h������u���X�g������o�v�[���ɍL�����Ă�������A�t���J����A�����J�ւ̓z����Ղ̋K�͂́A300�N�ԂŖ�1500���l�Ƃ����Ă��邪����̂����C�M���X�͖�200���l���邢��300���l�����Ղ����Ƃ����B�܂��A�C�M���X��18���I���ɂ����ēz����Ճu�[���ƂȂ�A���̌��ʂ͑���傫�����������A�N�ԕ���7���l�ł������Ƃ����B�ŏ����爫�Ƃ݂Ȃ���Ă��Ȃ��礂�߂���킯���Ȃ������B�z����Ղ͢���̈�Y��ł��邽�߂��A�C�M���X�l�͑������ӂ�Ȃ��
�@�z��́A�L���ȃA�����J�ւ̒��ԍq�H�̓r���ɂ����Đ��v����A��������ł��邪�A���̐��͓z��̐��ɉ����đ�ʂƂȂ����B�z����Ղ́A�z��̎��S�����Ⴏ��Τ���ׂ̖��͂���߂đ傫�����̂ƂȂ�����z�ꂪ���ʂƁA2�����10��ݸނ���3�����10��ݸނ̑����ƂȂ����B���̊z�͒j���z��̓����̒ʗ�̍w�����i�ł���A���C���h�����ł�18����ނŔ����Ă����B���v�����˂Β����͐��ƂƂ��ɗ��ꂽ�B
�@�`���[���Y2���̒�ŁA��̃W�F�[���Y2���i�݈�1685-88�j�ƂȂ郈�[�N���́A�z����Ղ����ł���Ƃ͍l���Ă��Ȃ������B1660�N�A�A�t���J�ƌ��Ղ��Ă����C���O�����h�����`����ЂƂ�����Ђ͔ނɌh�ӂ�\���A����̓������ؖ����邽�ߤ�z���DY�iDuke of Yoke�̗��j�Ƃ��������̏Ă�����������ƂƂȂ����B���̉�Ђ́A�N�ԂɍŒ�3000�l����������_����A�����E�^�o�R�A���n�Ɍ���ł����B
�@�����́A�C���O�����h�����`����Ђɓ������Ă���A���̉�Ђ��`���邽�߁A��M�j�[��Ƃ����V�����R�C���܂Ŕ��s�����B���̃R�C���̓M�j�A�C�݂���A�����ꂽ���Œ�������Ă����B�C���O�����h���I�����_�푈�ɏ����Ă��A�z����Ղ̂قƂ�ǂ��I�����_�l�̎�Ɉς˂�ꂽ�܂܂ł��������߁A�������芪���Ȃǂ̓����Ƃ͓������������Ă���B
�@����ɂ�������炸�A1672�N�ɉ����A�t���J��Ђ��ݗ�����A�l�X�Ȃ��Ƃ������オ��B1680-88�N�ԁA�����A�t���J��Ђ͖�250��̓z��q�C����悵�A60,783�l��D�ς݂����Ƃ���Ă���B���̂����A46,396�l���邢��4�l��3�l���A���̍q�C�Ő����c�����B
�@��������A�����A�t���J��Ђ̓C���O�����h�l�̂����菤�l�Ƒ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B1698�N�A�z����Ղ͂��ׂẴC���O�����h���l�ɊJ�������B���̏ꍇ�A10�߰��Ẳݕ��ł������A�t���J��Ђ̎�蕪�Ƃ��Ďx�����K�v���������B1680-1700�N�ԁA30���l�̓z��A�V���E�ł̉��i�ł�����300������ވȏオ�A�����A�t���J��Ђ�����菤�l�ɂ���ăC���O�����h�D�ɐςݍ��܂ꂽ�ƕ]������Ă���B
�@�Ȃ��A18���I���߂܂ł̃C���O�����h�l�̓z����Ղ́A���̑S�̂�10�߰��Ăɂ��y��ł��炸�A����ȊO�͐��X�y�C���l�A�|���g�K���l�A�I�����_�l�A�����ăt�����X�l���A�����Ă����B
���ݕ����l�̗̍p�A�p�D�_�L���遟
 |
 |
| �����F�W���������ʁA���F�D��A�E�F�D�� ���o�[�g�E�h�b�h��@ 18���I�㔼 �����C�������فi�����h���j�� |
����D�� �n���V�ɍ����u���A�E����f�B�o�C�_�[�������Ă��� ��ҕs���A1690? �����C�������فi�����h���j�� |
�@�D�������ɂ͋���Ȋ��҂����Ă����B�D���Ƃ����E�͑D��Ɛe�����W�����Ԃɓ�����������D���́A�ݕ������Ƃ��A�D�傠�邢�͗p�D�҂ɂ���Ďw�����ꂽ���悷��Ǘ��l�A�������A���邢�͑㗝�l�̖��߂ɏ]���悤�A�w������邱�Ƃ��������B���������E����17���I���ɂ͉ݕ����lsupercargo(�ωē�)�Ƃ����p��ɒu��������ꂽ�B
�@�������A�o���g�C�ł́A�D���͍q�C�Ɠ����悤�ɐωׂɂ��Ă��A�I�n�A�ӔC���������B���̒n���̌��Ղ͌��܂肫�������ՂɂȂ��Ă����̂ŁA�D�ς݂ɂ��炩���ߐӔC�����X�[�p�[�J�[�S�Ȃ��ł��܂���Ă����B�n���C�ł́A�D���͂����ނˁA������A�Ǘ��D�傪�Ȃ��Ă���A���̐ӔC�͍q�C���Ԃ������Ȃ�قǑ傫���Ȃ����B
�@�Ǘ��D�傪�A�ǂ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�v�Ȍ���́A���ꂼ��̖ړI�ɑ����ėp�D�_������Ԃ��Ƃł���B�p�D�_��́A�ʂ̍q�C���Ɍ����̂��قƂ�ǂł���������^�q�҂��q�C�̐����x������ςݍ��ݗʂ̑��ǂŌv��悤�ɂȂ������߁A���ԗp�D�_��time charter�͑D���p�D�_��tonnage charter��A���C���⍻���A�I�C���A���̑��ݕ�����葽���ςނ��Ƃ����߂鋦��i���ʗA���_��j�ɒu���������Ă������B
�@1650�N�Ȍ�A���ԗp�D�͂܂�Ƀ^�o�R���ՂɎg���邾���ɂȂ�A�܂�1680�N�Ȍ�A�����̗A���ɂ܂�ɗp����ꂽ�B����̊���炢���Θ_�O�ł��邪�A�ז����Ԃ͑�ϐ�������Ă����B����̎��Ԉȓ��ɑD�ς݂��I���Ȃ��ꍇ�A�p�D�҂͑D���1���P�ʂőؑD�����x����˂Ȃ�Ȃ������B1660�N�Ȍ�A��g���̌ٗp��x�����͑D��̕��S�ƂȂ�A�p�D�҂͊W���Ȃ��Ȃ��Ă������B
�@�㗝�l�̃l�b�g���[�N���C�O�ɂ�����ɍL�����Ă������B�Ǘ��D��́A�p�D�_�Ȃ��ꍇ�A�ݕ����l�����Ă��ꂻ���Ȓ����l��㗝�l������Ƃ���ɁA����Ɏ����̑D�������čs���悤�ɂȂ����B
�@�D��͉��炩�̑��Q���Ă��A�ی����L���s���킽��悤�ɂȂ��Ă����B�ی����̕������[�g�͕ی�����3�߰��Ă�����ȉ��ł���A�펞�댯���[�g��6-14�߰��Ăł��������A���ɂ�35�߰��Ĉȏ�ɂ��������邱�Ƃ��܂�ɂ݂�ꂽ�B�펞�ɂȂ�ƁA10���1����͏��Ȃ��Ƃ��Ă��A�˂ɝ\�߂����댯���������B17���I���ɁA�C���͎�����A��������Ă����̂ŁA�ی����ɗǂ��e�����y�ڂ��Ă����B
�@�C�^�Ƃ́A1580�N�Ȍ�}���ɐ������邪�A�킯�Ă�1660�N����1689�N�ɂ����āA�����̎��ɑ���Ȃ��Y�Ƃ���A�C���O�����h�̋}���ɔ��B����Y�Ƃ�1�ɂ̂��オ���Ă������B1582�N����1686�N�܂ł̖�1���I�̂������ɁA�g������6.7���݂��班�Ȃ��Ƃ�34���݂ƁA5�{�ȏ�����������B���̊ԁA�l���͊ԈႢ�Ȃ��Ƃ���A2�{�قǑ��������B�C�^�Ƃ�1�̎Y�ƂƂ��āA���܂�_�ƁA�D���ƁA�����Č��ƂɎ����Y�ƂƂȂ����B
�@�C���O�����h�̗A�o�ƍėA�o�̉��z��3�{�ƂȂ�A�C�^�Ƃ̓����h���̔ɉh�ɍv������悤�ɂȂ����B1689�N�ɂ́A�l��150���l�̂���5���l���邢��30����1�̐l�X���C�^�Ƃɏ]�����Ă������A���̐���ɂȂ�Ƃ��̎Y�Ƃ̔��B�̃y�[�X�̓X���[�_�E������B
