 ホームページへ |
| 海上交易の世界史 【総目次】 |
| |
| このe-Bookは、『帆船の社会史』の第1、2章の全面改訂版である。この連載は、近世までを予定してきたが、それも終えた。 ただ、基本的に未定稿なので、新しい知見が得られ次第、逐次、内容を補正することになっている。更新を確認していただきたい。 なお、Webページから引用した図版の出典は、リンクしたアドレスでもって示すこととする。 |
| |
| (前30世紀頃−後6世紀頃) 第1章 海上交易圏の模索 ―文明発祥の地― 1・1・1 エジプト―外国人商人に依存― 1・1・2 オリエント―遠隔地交易人の登場― 1・1・3 インダス―海上交易圏の登場― 第2章 海上交易圏への架橋 ―東地中海の世界― 1・2・1 ビブロス、ウガリット―古代文明の十字路― 1・2・2 キプロス、クレタ―地中海世界への橋脚― 第3章 海上交易圏の形成 ―フェニキア、ギリシア、ローマ― 1・3・1 フェニキア―海上交易国の誕生― 1・3・2 ギリシア―エーゲ海限りの海上帝国― 1・3・3 カルタゴ、アレクサンドリア―地中海の棲み分け― 1・3・4 ローマ―単一支配の海上交易圏― 結章 古代海上交易論 1・4・1 古代の海上交易の形態 1・4・2 古代の船の発達―技術史的意味― 1・4・3 古代の航海、航海術、そして船員 (6世紀頃−16世紀頃) ―インド洋・海峡部・シナ海の交易― 2・1・1 ギリシア・ローマ時代のエジプトの東方交易 2・1・2 『エリュトラー海案内記』にみる海上交易 2・1・3 古代アジアにおける海上交易 第2章 アジア交易圏の結合 ―イスラームと中国の進出― 2・2・1 西アジア・イスラームの海上交易 2・2・2 インド洋の交易都市とイスラーム交易民 2・2・3 東南アジア交易圏の成立と海峡部の交易 2・2・4 東アジア世界、宋代までの海上交易 第3章 ヨーロッパ進出前のアジア交易圏 ―アジア大交易時代― 2・3・1 元の海上帝国という仮構、倭寇の登場 2・3・2 15-16世紀 朝貢と密貿易、琉球の世界 2・3・3 ポルトガル進出前後の西・南アジア 第4章 南北ヨーロッパ交易圏 ―2つの異質な交易圏― 2・4・1 ビザンツ、西ヨーロッパの血肉となる 2・4・2 西ヨーロッパを揺さぶるヴァイキング 2・4・3 ハンザ同盟、ニシンと毛織物で稼ぐ 2・4・4 中世イタリア、地中海交易の掉尾を飾る 結章 中世海上交易論 ―大量・嵩高な必需品の買い付け― 第3部 近世―世界海上交易圏の成立 (16世紀頃−18世紀頃) 第1章 世界海上交易圏の形成 ―植民地交易の開始― 3・1・1 スペイン、その破壊と略奪の交易 3・1・2 オランダ、世界最後の中継交易人 3・1・2 増補:母なる貿易=バルト海穀物交易 3・1・3 港市まかせのフランスの海上交易 3・1・4 イギリス、後発の利益を享受して覇権 第2章 ヨーロッパ進出後のアジア ―交易港から領土の支配へ― 3・2・1 東南アジアの港市とヨーロッパの進出 3・2・2 ポルトガルの「大航海時代」と東アジア交易 3・2・3 スペインのマニラと中国・日本との交易 結章 近世海上交易論 ―加工再輸出交易のはじまり― フェニキアと交易ディアスポラ再考 日本の新羅や渤海との交易の形態 大航海時代の東南アジア人船員 中世イタリアの商人群像 アマルフィ海法―過渡期の海法― 拉致の海、ココヤシの島―オセアニア 「シンドバッドの7つの航海」を読む 「マルコ・ポーロの東方見聞録」を読む 「円仁・入唐求法巡礼行記」を読む 「イブン・バットゥータの大旅行記」を読む 鄭和西洋下りを『瀛涯勝覧』から読む トメ・ピレス『東方諸国記』を読む 近世ヨーロッパ船員の22年間の海上人生 世界を遍歴したフィレンツェ商人カルレッティ |
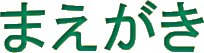 |
海上交易の世界史を概説するに当たって、少々長めの前置きが必要のようである。まず、ここで取り上げる海上交易とは何か、海上交易の世界史をどのような視点からみるか、海上交易の世界史にはどのような時代区分があるか、そしてここで海上交易の世界史をどのように展開するか、を示しておきたい。なお、従来、海商という用語を用いていたが、同義語として、海上交易を用いることとした。いささか理屈をこねることになるので、うとましいとおもう方は、飛ばしてもらって結構である。
1 ここでいう海上交易とは何か
世界史を貫き、世界大に展開し、世界を結び続けている産業は、そうざらにはない。その数少ない産業が海上交易あるいは海運である。海上交易史あるいは世界海運史は、「産業の世界史」として、その名を辱めないものである。それとほぼ同じ意味合いで、それぞれの国の海上交易あるいは海運を「一国の産業史」として語りうる。
海運とか海運業はともかく、海上交易さらに海上交易業はそれほどなじみのある用語ではない。まず、海運業をいま一度整理してみる。それを交通論風にいえば、「交通路」を主として海上におき、船舶を「交通手段」として使って、「交通対象」である人々や貨物を、ある地点から他の地点に「場所移動」させるという、交通サービスの一つとしての海運サービスを供給する産業である。
交通サービスは、その需要が発生しなければ、供給されようがない。すなわち、交通対象である人々や貨物が登場して、そのサービスを需要する状態になってはじめて供給されるという、特殊なサービスである。そうしたことから交通需要は派生的需要とされてきた。そのため、交通サービスは、そのサービスの需要者が自ら供給し、かつ自ら需要することが起こりうる。現在でも、交通業によって交通サービスは広く供給されており、それを需要すれば事足りるにもかかわらず、たとえば自家用車を運転して通勤や観光したり、あるいは自家用トラックを利用して商品の集配送を行ったりしている(以下、船を車、海運サービスをトラック輸送サービスに置き換えれば、理解しやすい)。
これらを、また交通論風ではなく海運論風にいえば、前者のある人が他人のために供給し、他人がそれを需要する形態の交通サービスを、「他人輸送」(おおむねcommon
carriage)という。それに対して、後者の自らが自らのために供給かつ需要する形態の交通サービスを、「自己輸送」(private carriage、海上交易にあっては merchant carriage と呼ぶことができる)という(なお、回りくどいが、前者を交通サービスの他人生産・他人消費、後者を交通サービスの自己生産・自己消費ともいいうる)。
さて、海運業においても、同様であって、その歴史を過去にさかのぼるほどに、特に貨物輸送にあっては、「自己輸送」が広汎にみられた。その担い手はいうまでもなく商業あるいは貿易業であった。そこでの海運サービスは、商業あるいは貿易業の業務の一部として行われていた。その場合の商業あるいは貿易業においては、商業取引が不安定であり、かつ海上輸送が不確実であるため、前者から後者を切り離すことができない状態にあった。
こうした特殊な業態にある産業を「海上交易業」と呼びうるであろう。しかし、商業あるいは貿易業にとって、海運サービスは本来の業務ではなく、またそれが業務の一部でなくても、商業あるいは貿易業でなくなるわけではないので、海上交易業と呼ばれる筋合いはないであろう。したがって、ここでここ取り上げるのは海上交易業そのものではなく、商業あるいは貿易業の業務の一部として行われている海運サービス、すなわち海上交易である。それに伴い、ここで取り上げる海上交易史は海上交易業の歴史そのものではなく、「海上交易業」において海運サービスがどのように自己需要・供給されてきたかの歴史となる。
この海上交易史は、本論において明らかになるが、古代から近世にかけ、長中距離の海上交易においてみられた業態であった。また、こうした「海上交易業」も海運サービスが汽船によって提供されるようになると、海上交易業は商業あるいは貿易業と海運業としてほぼ完全に分離する。それまでの期間が海上交易史となる。
なお、海上交易史は、海運史からみればその一部であるが、その長さは海運史の95%を占めていよう。
2 海上交易の世界史の視点
海上交易の世界史を、ただ史実を羅列するのでなく―どのような史実を抽出するのことも、大仕事であるが―、史実を記述する―史実を分析、総合する―からには、一定の視点がなくてはならないであろう。
(1) 海運サービス需要の視点
冒頭でみたように、海運サービスは、交通対象を、場所移動させることにある。その交通対象とは何か。いうまでもなく、旅客と貨物である。そのうち、旅客は海運サービス需要者それ自身である。貨物に関する海運サービスの需要者は、通常、荷主、さらにはその代理人である。
旅客は、商人、官僚、軍隊(十字軍)、巡礼者、旅行者、植民・移民、流刑者、奴隷などである。また、荷主としては、商人、豪商、政商、商館、商社、農民、職人、工業者、王室、政府、軍隊などである。このうち、商人、豪商、政商、商館、商社などは、海上交易史にあっては海上交易業者(海上交易人、sea-trader)として、海運サービスを自己生産・自己消費することになる。
旅客のうち、あらゆる時代を通じて登場し続けるものもいれば、ある時代に限って登場し、退場するものもいる。前者は商人や軍隊、巡礼者である。後者の典型は植民・移民、流刑者、奴隷であろう。これら海運サービス需要者が、海上交易史、さらには特定地域において、どのように登場し、退場するかを確かめたいものである(ここでいう「どのように」とは、5つのWを意味している)。
次に、荷主とそれが持ち込んでくる貨物は、きわめて多種多様である。荷主には、すでにみた商人、豪商、政商、商館、商社などが上げられる。貨物の分類もいろいろあるが、大分類としては、生産種別からみると農産品、鉱産品、工業品、また消費種別からみると消費財(最終消費のための必需品、奢侈品)、生産財(農工業生産のための原材料、燃料)、軍需品となろう。
海上交易史、さらには特定地域において、それらの具体的な品目のある貨物がどのように登場し、退場してゆくかは、その時代の海上交易のありようを、それなりにまざまざと物語ってくれる。それら交易品目を知ることは海上交易史の醍醐味であろう。それら品目は、大筋において、農産品、鉱産品、工業品の順で、あるいは奢侈品、必需品、原材料、燃料の順で登場してきたといえる。
最後に、海運サービスの需要は、ある地点(交易地)から他の地点(交易地)の場所移動を、技術的な内容としている。この移動は一定の地理的方向をもって行われる。この一定の方向を持つ場所移動(交易地間の移動)が繰り返し行われると、そこに航路(リンクとノードの組み合わせ)が生まれる。さらに、その航路が一定の海域において広がると、海上交易圏(海上交易ネットワーク)が形成される。それら航路や海上交易圏が、海上交易史においてどのように形成され、発展あるいは衰退したかが問われる。
(2) 海運サービス供給の視点
冒頭でみたように、海運サービスは海上を主たる交通路におき、船舶を交通手段として使って供給されるサービスである。
海上という交通路は、河川や沼湖とは違って、沿岸(海)、近海、遠洋という広がりを持っている。それは、いくつかの大陸を隔てるものであるが、それを結びつけるものでもある。また、陸上輸送における道路や軌道と違って、天然の開かれた交通路である。海運サービスの交通路が、海上交易史、さらには特定地域において、沿岸、近海、遠洋の順で拡げられていったことは、見やすい流れである。
船舶という交通手段は、周知のように、手こぎ舟から帆船、そして汽船、すなわち道具としての発達と、それから機械への飛躍として発展してきた。その発展は船舶の推進動力の転換にあった。しかし、手こぎ舟と帆船はいずれも何千年という長い歴史を持っており、史料の上ではほぼ同時に登場している。ただ、それらの発達には、個別地域において大きな時間差がみられ、しかも独特な形態を持つものとなってきた。なお、汽船は産業革命後期に、先進国でほぼ一斉に登場したといっていい。
いま、手こぎ舟と帆船とは、全体として、簡単な道具から複雑な道具への発展としてみると、動力の面では櫨・櫂(ろ・かい)やオールの舟から多段櫂のガレー船や帆装船へ、帆装面では1本マスト船から3本マスト船へ、構造の面ではあし(葦)舟や丸木舟から構造船へ、材質の面ではあしや木材から木鉄、鉄へ、操船の面では側面舵から船尾舵へ、また航海用具の面では羅針盤の有無、時計の精度の向上などとして発展してきたといる。
こうした発達に伴って、船型は次第に大型化していく。しかし、一様に大型化するわけではない。
いま、海運サービス供給の視点として、船舶発達史はきわめて重要である。いまのべた以外の面(なかでも港湾とその施設)でも、また海運サービスに直接には関わりない面でも、様々な改良がある。その詳細は、船舶史や帆船史、航海史などを参考されたい。
次に、海運サービスの供給者はさしあたって海上輸送人(sea-carrier)である。この海上輸送人はおおむね船主であるが、船主から船舶をレンタルあるいはリース(通常、用船という)して、海上輸送人になるものもいる。前者は船主兼輸送人(owner-carrier)、後者は単なる輸送人である。
船舶所有者としての船主は、専業船主(これとて、単なる専業船主のほか、単なる資産家としての船主もいる)ばかりでなく、兼業船主としての商人船主船長(merchant skipper)、商人船主(merchant shipowner)、船主船長(shipowner-skipper)、さらに王室や政府である場合がある。また、船舶の所有形態は単独所有と共同所有に分かれる。さらに、共同所有は持ち分所有や会社所有に分かれる。
海上交易史において、海上交易業から海運サービスが切り離されていくにつれ、商人船主船長や商人船主は縮小し、船主船長や単なる船主が増大する。また、その所有形態も持ち分所有から単独所有、そして会社所有へと比重が移行していくといえるが、具体的にはどのように見て取れるであろうか。
海運サービスを現実に生産するのは船員である。船員は、最古の職業の一つといわれ、おおむね雇われ労働者であったが、一部には単なる奴隷や債務奴隷、捕虜、救貧少年などもいた。さらに、船員のなかには船舶所有の持ち分があり、それに伴う利益にあずかる船員もいるし、船員に報酬の一部として与えられた貨物スペースを使って、商品を売買する船員もいる。
(3) 海運サービス需給の視点
海運サービス供給と需要を総括する視点として、海運サービスの規模が考えられる。それは、旅客と貨物の輸送量とそれらが場所移動した距離との積、すなわち人・キロメートルやトン・キロメートルの総和でもって計られる。この人・キロやトン・キロが、海上交易史において、どのように増加していったか、またそれらが飛躍をみせる時点がいつだったかを、見極めなければならない。
しかし、現在においても、トン・キロの測定はままならない。われわれの海上交易史においては、海運サービス供給=需要の規模を、旅客と貨物の輸送量、船舶の隻数やトン数の総計、入港船の隻数やトン数、そして航路の長さや海上交易圏の広がり、従事する船舶の量をもって推し量るしかない。
最後に、海上交易圏(海上交易ネットワーク)についてみると、一般に海上交易は国内交易、近隣国(地)交易、そして遠隔国(地)交易に分かれ、またそれに対応して短距離、中距離の、長距離輸送が行われよう。ここでいう海上交易圏は、近隣国(地)交易や遠隔国(地)交易が航路網を通じて、一定の海域で日常的に行われるような面的な交易圏を指すこととしたい。
この交易圏は単なる交易地(港)や航路網の寄せ集めではなく、その核となる交易国や交易地(港)があり、一定の航路網のもとで、それなりの数の品目や数量の交易品が輸送されていよう。その形成された交易圏であっても、盛衰、吸収、変形、分離など、様々な推移をたどろう。
なお、交易圏という用語は、語感からすれば遠隔国(地)との交易圏となるが、大方はそれに収まろう。
(4) 海運サービス実務の視点
海運サービスの供給や需要に伴って、そこに海上交易実務が発生する。この海上交易実務は貿易実務と海運実務に分かれるが、そのあいだには密接な関係がある。
当面している海運サービスは、商業あるいは貿易業の業務の一部、すなわち海上交易として行われるので、まず商品の買い付け資金、そして船舶の調達資金が必要となる。それらを合わせたものが当面の海上交易資金となる。
海上交易事業が、個人事業として行われる場合はともかく、共同事業として行われる場合、何を出資するか(金銭か、船舶か、労務か)、出資の返済や配当、利益の配分、事業に伴う損害の分担や補償をめぐって実務が発生する。また、その海上交易資金が自己資金だけではまかなえず、他人資金が必要となる場合、最寄りの人々に海上交易事業に参画してもらう必要が生じる。その参画のあり方をめぐっても、同様の実務が発生する。
そうした海上交易事業に限らず、単なる海運事業においても、船舶の建造、売買や貸借(用船)が行われる。船舶の建造や売買においては、船舶の検査、船舶代金の支払い、船舶の引き渡しについて、様々な実務が発生する。また、船舶の貸借においては、それが船員労務付きの貸借であるかないかによって(すなわち裸用船と定期用船に分かれ)、その用船実務の内容が大きく異なってくる。
いま上でみたような海上交易事業は一つのモデルであって、現実にはその事業の一環として、また時代が下がれば下がるほど、海運サービスが現代にみるような単なるサービス商品として売買されるようになる。こうした今日的な海運サービスの取引はあくまで商業取引を完結させるためにある。この商業取引と海運サービスの取引をめぐり、海上交易事業においては表に出なかった実務が発生するようになる(例えば、船荷証券B/L)。
この海運サービスの取引にあっては、船主の貨物輸送というサービスに対して、荷主は対価運賃を支払う。その貨物がわずかな場合は輸送契約が結ばれ、運賃が収受されるが、そうでない場合(例えば、船の5分の1、あるいは船1隻分)は用船契約が結ばれ、用船料(実質は運賃)が収受されるというように、実務のありようが異なってくる。
さらに、海難事故が起きた場合、船舶や貨物の損害の分担、各種損害に対する補償や賠償、海上保険の加入や保険金の支払いについて、これまた様々な実務が発生する。こうした海上交易あるいは海運事業をめぐる実務が、海上交易史、さらには特定地域において、どのようなかたちをとって立ち現れるのであろうか。
なお、これら海上交易実務は、現代の海運・貿易実務はもとより、陸上輸送や航空輸送の実務の基礎となっている。
(5) 海上交易政策の視点
海上交易は、海上を交通路とし、自国の海域を越えて、複数の国家にまたがって行われる。したがって、海上交易にとって、国家は前提として立ち現れる。国家は、海上交易を促進あるいは抑制する政策、すなわち海上交易政策を実施する。
第1に、海上交易そのものを自由に認めるか、制限(禁止もありうる)を加えるかである。後者の場合、輸出入、交易品目、交易量、交易先などについて、直接的に制限を加えたり、あるいは関税や為替管理でもって、間接的に加えたりする。
第2に、海上交易の分担者を自由に認めるか、制限するかである。すなわち、海上交易の一部あるいは全部を、国営とするかあるいは民営とするかである。その全部を民営としない場合、特定人あるいは特定組織に委ねることになる。それはいま上で述べた海上交易の制限と結びつく
第3に、海上交易やその分担者を支援するか、しないかである。前者の場合、補助金・奨励金の支給、低金利融資、租税優遇、貨物先取り権の付与、関税や為替管理が行われる。
第4に、海上交易を対外的に円滑に進めていくために、交易路や交易拠点の確保あるいは破壊、植民地の建設、移植民の実施が進められる。さらに、それらの必要に応じて、戦争・鎮圧の実行、要塞の建設、軍隊の駐留、官吏の派遣、支配統治などが行われる。
第5に、海上交易の終始点にある港湾をどのように発展させるのか、また海上交易に船舶を供給する造船を必要とするのか、しないのかである。それぞれに応じて政策が実施される。
これら政策のなかには、自国人のみならず、外国人にも適用されるものがある。例えば、海上交易を外国人にはどの範囲で認めるのか、認めないのか、外国産の交易品の関税をどのように定めるか。さらには、外国人の居留を認めるのか、認めないのかといったことを上げうる。
これら海上交易政策は、歴史あるいは経済体制の発展によって、その政策理念が決定的に変化してくるので、その具体的な内容やその構成は大きく異なることはいうまでもない。
3 海上交易の世界史の時代区分
海上交易の世界史には、どのような時代区分が考えられるのであろうか。
数少ない海運史はさておき、いくつかの商業史をみると、経済システムにもとづく伝統的な時代区分の上に、商業大国や交易大国、経済大国と呼ばれた国々の興亡あるいは盛衰を付け加えて、時代区分としていることである。
商業史とはいえ、世界史や世界経済史の一側面にすぎないし、さらにその一側面でしかない海上交易史からとすれば、それらの時代区分をもって良しとすべきであろう。それではあまり芸がないので、いま上でのみた海上交易史の視点を手がかりに、時代区分を試みてみよう。
まず、明白な時代区分は、いうまでもなく前近代と近代との区分である。なお、前近代にあっては、特殊な取引として、支配者への貢納や支配者間の贈答によって、財貨が移動や交換が行われる。
前近代商業においては、商人は、それを取引することで、はじめて商品となった財貨あるいははじめて商品とした財貨を、不等価交換することで利益(譲渡利潤)をえている。それに対して、近代商業にあっては、商人はそのはじめから商品として生産された財貨を取引し、等価交換で利益(商業利潤)をえている。
言い換えれば、前近代商業は商品市場における取引ではなく、基本的には非市場取引として行われる。その典型がいま上でみた貢納品や贈答品の受け渡しである。しかし商業と交通の発達により、非市場取引は崩され、市場取引もどきの様相を呈するようになる。それに対して、近代商業は商品市場における取引として行われている。
こうした商業における前近代と近代に対応、あるいはそれらを画期として、海上交易業もまた大きく前近代史と近代史に分かれる。それは、海上交易業の海運業と商業への分離、船舶の帆船から汽船への転換に対応している。
前近代海上交易史においては、いまみたような決定的な区分―経済システムの移行にもとづく変化―はないといえるが、海上交易業者、貨物の種別と量、輸送距離、そして船舶、さらにその時代の海上交易を主導する国々について、それなりの画期が認められるし、それらのあいだには切り離しえない関連がある。
そこで、それらを概括する視点として海上交易圏を採用し、その形成、発展を軸とし、また通説に大きく違わないかたちで、海上交易の世界史の時代区分とすることとする。なお、この区分は記述の流れにしたがって修正される。
[1] 古代―海上交易圏の形成(前30世紀頃−後6世紀頃)
1 海上交易圏の模索―文明発祥の地―
前30世紀頃から、オリエントやエジプトに様々な古代王朝が成立した。その支配者が必要とする奢侈品の近隣国との陸上交易が中心となり、その量もわずかであった。海上交易は、支配者の必要に応じて行われる場合もあったが、そのほとんどがフェニキア人に委ねられていた。また、すでに早い時期からインドや中国においても王朝が誕生して、その交易も広まる。しかし、それら文明発祥の地において、それらの海域を越えて海上交易が行われるようなネットワークが、本格的に形成されることはなかった。
2 海上交易圏の形成―フェニキア、ギリシア、ローマ―
前12世紀前後から、フェニキアが台頭して東地中海、さtらに西地中海の海上交易を一手に引き受ける。それに少し遅れて、西地中海に前6世紀前後ギリシアが、そして西地中海にローマが勃興し、征服戦争や植民地建設に繰り広げる。そのなかで、地中海を横断するかなり大きな海上交易圏が形成される。この地中海交易圏は、西アジアにおけるヘレニズム王国の発展、そして地中海世界の覇者となったローマ帝国により、その範囲を拡げ、興隆をみせ、他の海上交易圏は陸上交易を媒介として結びつくようになる。
[2] 中世―海上交易圏の結合(6世紀頃−16世紀頃)
1 海上交易圏の盛衰―イスラム海上交易圏の形成―
6世紀頃になると、ゲルマンなど民族大移動、ササン朝ペルシャの拡大などにより、ヨーロッパの商業は衰退し、既存の海上交易圏は混乱・萎縮する。他方、同時期、アラブにイスラム国家が成立すると、イスラム世界はその領土を短期間のうちに東・西地中海、さらに西アジアにまで拡大する。それに加え、東アフリカ・インド洋、東南アジア、そして東シナ海に、イスラム海上交易圏が形成される。これによって、世界の人口集中地域のすべてに、個別海上交易圏が設けられることになる。
2 海上交易圏の拮抗―東西の海上交易圏の分立―
これら個別の海上交易圏は、イスラム教のそれら地域への伝播と、イスラム商人の海陸にわたる活躍によって結びつけられていった。それに後れを取っていたヨーロッパにおいても、10、11世紀なると、地中海、そしてバルト海・北海で「商業の復活」が起こる。さらに、13世紀に入ると、モンゴル帝国が西アジアから中国にかけて支配地を拡張する。これによって、当時の世界先進地域(ユーラシア全域)に、世界大の陸上交易圏が張り巡らされることになるが、海上交易圏として結合したわけではなかった。
[3] 近世―世界海上交易圏の成立(16世紀頃−18世紀頃)
ヨーロッパの一方における経済成長、他方における反イスラム運動は、非ヨーロッパへ向かわせる。16世紀、その最初の挑戦者はポルトガル、スペインであった。それら国々は、一方では新大陸において強制労働によって金銀を略奪し、他方アジアの海上交易圏に暴力的に参入し、香辛料など生活必需品を持ち帰ろうとするものであった。
それによって、それまでの個別の海上交易圏は一つの海上交易圏として結びつけられ、世界海上交易圏が成立する。このポルトガル、スペインの世界の海上交易圏への進出は、ヨーロッパに商業革命を呼び起こす。
それ以後、世界海上交易圏の支配をめぐって、まずイスラム国家やイスラム商人、そして現地支配者と、ヨーロッパの国々やその商人とのあいだで争いが起きる。さらに、先発のポルトガル、スペイン、後発のオランダ、イギリス、フランスといった、ヨーロッパの国々やその商人はお互いに争いを繰り広げる。ヨーロッパの国々は世界各地に植民地を建設して、そこに奴隷を持ち込み、砂糖、タバコ、そして綿花といった植民地産品を作らせ、輸入する。それによりヨーロッパでは生活革命が起きる。そして手工業製品を輸出するようになる。
[4] 近代―世界海上交易圏の支配(18世紀以降)
世界海上交易圏の支配をめぐる争いは、イギリスの勝利となる。その勝利を基盤として、イギリスは18世紀半ば以降の産業革命にいち早く成功し、資本主義を確立すると、世界海上交易圏を支配して覇権国となり、世界を席巻する。そのもとで、イギリスの海運業は海上交易業から分離し、いまや商業にではなく、広く産業にその主たる輸送需要を見いだし、工業原料と工業製品を世界の隅々に輸送するようになる。それ以外のヨーロッパの国々においても、海運業は自国貿易の維持、植民地との交易、軍事輸送の手段として発達することとなる。
4 海上交易の世界史の展開
最後に、海上交易の世界史をどのように記述するかである。まず、数少ない海運史をベースにおき、いくつかの商業史や経済史を参考にし、そして様々な歴史書をひもとき、それぞれの時代における世界の海上交易活動を概説する。
そのなかにあって、イギリス海上交易史はイタリア、スペイン・ポルトガル、オランダといった国々それら先進国に後れを取ったものの、それらの挑戦者として登場し、ついに覇権国としての地位を揺るぎないものとした。自らも「七つの海」を支配したと言わしめたし、他の国々とは違って、最近に至るまで、有数の海運国としての地位を保持し続けてきたからである。そうした位置づけを持つイギリスの海上交易史は、一国の産業史としてばかりでなく、海上交易の世界史の主要な側面を形作っている。
最後に、海上交易の世界史をヨーロッパに限って、中世を中心にして古代から現代までの、交易から海運、漁業、宗教、さらに海に関わる文学、芸術までを概説した著書として、ミシェル・モラ・デュ・ジュルダン著、深沢克己訳『ヨーロッパと海』(平凡社、1996)に注目しておきたい。このe-Bookの最初あるいは最後に読んでもらいたい。
このe-Bookが一応の完結をみた頃、ウィリアム・バーンスタイン著、鬼澤忍訳『華麗なる交易―貿易は世界をどう変えたか』(日本経済新聞出版社、2010)が刊行されていた。それは「世界交易通史」(ヨーロッパが中心ではある)といえるもので、文献を縦横無尽に切り込んだ読み物となっている。その最大のメリットは交易図版が多数あることで、われわれの不足をほぼ補ってくれる。
それに加え、フィリップ・パーカー編著、蔵持不三也、嶋内博愛訳『世界の交易ルート大図鑑 陸・海路を渡った人・物・文化の歴史』(柊風舎、2015)という、大著が刊行された。ウィリアム・バーンスタインのものとは違い、それぞれの時代の研究者が20人で、海陸にまたがる交易について蘊蓄を極めてくれている。また、書名の通り、交易ルートの図版が豊富である。
【追記】
なお、貿易、交易、通商といった用語には、それぞれ意味合いがあるが、ここでは言葉の流れで取り混ぜて使用する。
【主な参考文献】
C.E.フェイル著、佐々木誠治訳『世界海運業小史』、日本海運集会所、1957(原著、1933)
Ronald Hope:A NEW HISTORY OF BRITISH SHIPPING,JOHN MURRAY, 1990
(ロナルド・ホープ著『新イギリス海運史』、ジョン・ムリー社、1990)(抄訳・解説、e-Book【イギリス海運史】)
伊藤 栄著『商業史』、東洋経済新報社、1971年
石坂昭雄ほか著『商業史』、有斐閣双書、1980年
『世界の歴史』、中公文庫版、全16巻、1960年代前半以降刊行(以下、旧版『世界の歴史』という)
『世界の歴史』、全30巻、中央公論社、1990年代後半以降刊行(以下、新版『世界の歴史』という)
『生活の世界歴史』、全24巻、河出書房新社、1970年代前半以降刊行
『クロニック世界全史』、講談社、1994年(以下、『世界全史』という)
ピエール・ヴィダル=ナケ編、樺山絃一訳『世界歴史地図』、三省堂、1995年
『世界大地図帳』、平凡社、1990年(地名は、主として同書によっている)
【凡例】
[ ]内は、引用者の補足や注釈である。
(02/12/26記、08/10/01補正)
 ホームページへ |
 トップに戻る |