 �z�[���y�[�W�� |
 �ڎ��ɖ߂� |
| |
�|What was the seamen's union for the seafarers of the world?�|
�@���@�z�@��
| �܂�����
�P�@�wNUS100�N�j�x�̒��҂Ƃ��̍\�� �@�@1�@���҂̗��� �@�@2�@�͕ʍ\�� �@�@3�@�Y�ƕʘJ���g���j�̈Ӌ` �Q�@�wNUS100�N�j�x�̎�ȓ��e �@�@1�@�D�����P�A���ݕ}����1850�N�C�^�@ �@�@�@�@1)�@�D���ɑ��鎜�P �@�@�@�@2)�@�D���̑��ݕ}�� �@�@�@�@3)�@1850�N�C�^�@�̐��� �@�@2�@�g���ݗ��Ƃ�����߂���U�h �@�@�@�@1)�@�E�B���\���ANAS&FU��ݗ� �@�@�@�@2)�@�C�^�A���̖ړI�A��i �@�@�@�@3)�@NAS&FU�̔C�Ӊ��U �@�@3�@�g���̍Č��A�S���X�g�A�D��̑g���F�m �@�@�@�@1)�@�g���Č��A�����̒����Ǘ� �@�@�@�@2)�@�O���l�D�����ƍ��ۑg�D �@�@�@�@3)�@1911�N��X�g���C�L�̐��� �@�@4�@�E�B���\���̎w���H���A�펞NMB�̐ݗ� �@�@�@�@1)�@�Ό��d�����A���x�d���� �@�@�@�@2)�@�푈�ɂ��Ë��̎Y���ANMB �@�@5�@1906�N�C�^�@�����Ƌc���E�B���\���̗��� �@�@�@�@1)�@1906�N�C�^�@�����̓w�� �@�@�@�@2)�@���Љ��`�I�ȘJ���g����` �@�@6�@1920�N��̒������ATUC����̏��� �@�@�@�@1)�@NMB�̑D�������Ƃ��̖��� �@�@�@�@2)�@�������������Ƃ��̔��Ή^�� �@�@�@�@3)�@�E�B���\���̐����M���Ƒg�D�Η� �@�@7�@��2�����E��펞�̑D����Q�Ɛ����v �@�@�@�@1)�@�D���̎����I�Ζ��A���S��50% �@�@�@�@2)�@���ۑD�����͂̐���ƑD����u���x�̊m�� �@�@8 ����F�X�g���C�L�Ƃ��̑Ή� �@�@�@�@1)�@1947�A55�A60�N����F�X�g���C�L �@�@�@�@2)�@�g�������̑Ή��A�D����\���̗̍p �@�@9�@1966�N��X�g���C�L�ƊC�^�@���� �@�@�@�@1)�@��������̂��Ƃł̑�X�g���C�L �@�@�@�@2)�@1970�N�C�^�����@�A�J�g�W�@�Ƃ̑Ή� �@�@�@�@3)�@�J�g�W�@�ɋ����ATUC����̏��� �@�@10�@�g����@�̂��Ƃł̑n��100���N �@�@�@�@1)�@�V�����D�����x�̍��� �@�@�@�@2)�@�C�O�u�Ђɂ��g�����̌��� �@�@�@�@3)�@�h���Ƌ�Y�̑n��100���N �R�@�wNUS100�N�j�x��NUS100�N�̕]�� �@�@1�@�wNUS100�N�j�x�̓����Ɛ��� �@�@�@�@1)�@���̓��� �@�@�@�@2)�@���̐��� �@�@2�@NUS100�N�̕]�� �@�@�@�@1)�@�D���̑�O�g�D�Ƃ��Ă�NUS �@�@�@�@2)�@�D���̖���g�D�Ƃ��Ă�NUS �@�@�@�@3)�@�o�ώ���c�̂Ƃ��Ă�NUS �@�@�@�@4)�@�Љ���v�c�̂Ƃ��Ă�NUS �@�@�@�@5)�@NUS100�N�̋��P |
�@1980�N��ɓ����āA���E�̑D���J���͑傫���l�ς�肵���B����́A��i���̊C�^��Ƃ�
�����БD���팸���A�����X�u�БD�Ɉڍs���������Ƃɂ���āA���E�̑D������i���l�D
������r�㍑�l�D���ɒu��������ꂽ���Ƃɂ���B���̂��ƂŁA��i�C�^���̊C���g���͂�
�̉^�����s���l�܂�A�g��������啝�Ɍ��炵�����Ƃɂ����āA���̑��݂��̂��̂������
���ƂƂȂ����B
�@����́A���E�̑D���ɂƂ��āA���܂܂ł̊C���g���͉��ł������̂��A����̊C���g����
�ǂ��Ȃ��Ă����̂��Ƃ������Ƃł��낤�B�����ŁA�ߋ��̒~�ς̏�ł����A���������肦�Ȃ��Ƃ�
��A�ߋ���U��Ԃ�A����Ȃ��邱�Ƃł����āA���̉�������ł��낤�Ƃ�����
�̂ł���B
�@�����������E�̑D���J���̑傫�ȍ\���ω��ƁA���̂��Ƃł̐�i���̊C���g���̊�@��
�̂��Ȃ��ɂ����āA�C�M���X�C���g��(the National Union of Seamen�A�ȉ��ANUS�Ƃ���)�́A
1987�N�A�n��100���N���}�����BNUS�́A���E�̊C���g���̂Ȃ��Ŏw���I�Ȓn�ʂ��ߑ���
�Ă��������ɁA���̗��j��U��Ԃ邱�Ƃ́A�傢�ɍ����I�Ӌ`������Ƃ�����B
�@NUS�́A�n��100���N�ɓ�����A�J�g�W�_�̐��Ƃł���A�[�T�[��}�[�V���ƃr�N�g���A�
���C�A���ɈϏ����āA100�N�j�����M�����A���̂悤�ȏ��������s�����B
| �@���̑啔�Ȓ���(�ȉ��A�wNUS100�N�j�x�Ƃ���)�̊� �P�ȗv��́A���łɑS���{�C���g���@�� ����C��� (1991.9�|1992.2����)�ɁA�J�{�m�i���ƈɓ����u�� (��������A�����A�x�R���D�������w�Z����)�Ƃ� ���Ɍf�ڂ��Ă����B �@�������A����͓��e�𒉎��ɂ������ɒ[�ɗv�� �ɂƂǂ܂�A���ꂼ��̎���ɂ�����j ���₻�̋L �q�ɂ��ĉ���A�]�����邱�Ƃ��Ȃ��������A�J���g ���j������̘_�_�ɂ��� �O���ɂ�����Ă��Ȃ� �����B �@�����ŁA�wNUS100�N�j�x���e�͖��ɏЉ�Ȃ���A �����̉ۑ� ��Njy���A�����ʂ��Đ��E�̑D���� �Ƃ��āA���܂܂ł̊C���g���͉��ł��������𖾂� ���� ���Ă݂����B���̏ꍇ�A�C�M���X�̊C���g���� એ�ɏ�邱�ƂɂȂ邪�A���{�̊C���g���̗� �j�� �̊֘A�Â����s���y1�z�y2�z�B �m���n �y1�z�@NUS�́A�ߋ��� The Story of the Seamen:A Short History of the National Union of Seamen, 1964�s���Ă���B���̖M��́A�w�S�p�C���g�� ���̂�����x�A�S���{�C���g������p���t���b�g62�A 1967�ł���B �y2�z�@���{�Ɋւ��鎖��ɂ��Ă̎Q�l�������A�� ��グ�邱�Ƃ͏ȗ�����B����ɂ��� �́A�w�S�� �{�C���g��40�N�j�x�A�w�S���{�C���g���������� �W�x�A1986���Q�Ƃ��ꂽ���B |
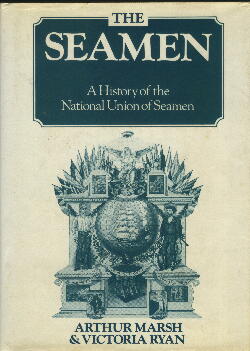 |
�@1�@���҂̗���
�@�ӔC���M�҂Ƃ݂���A�[�T�[��}�[�V�����́A1964�N�ȗ��A�I�b�N�X�t�H�[�h�ɂ���J�g��
�W�������̎�C�������ł���B��2�����E���ɏ]�R��A�I�b�N�X�t�H�[�h��w�ŋߑ�j��
PPE(�N�w������w��o�ϊw)���w�сA1948�N����w�̓��ʉۊO�����ψ���̏�u�t�ƂȂ�A
���̌�16�N�ԁA�J���g���A�ŐV�̌o�c�Ǘ��A�J�g�W������������Ă����B�܂��A�h�m�o����
����[�J���g���ƌٗp�Ғc�̂Ɋւ��鉤���ψ���A1965-68�A�M�Ғ��A�ȉ��A�����[�@]�ɂ���
�Ď���]�ɎQ�悵�����Ƃ�����A�����̘J�g�W�̐R���⒇�قɊ֗^���Ă����B�����āA�@�B�H
�ƁA�S�|�ƁA�����E�Ȃǂ̑����̎Y�ƂɊւ��钲�������ɏ]�����Ă����B�����Ƃ��āA�w�@�B
�H�Ƃ̘J�g�W�x�A�w�J�g�W�厫�T�x�A�w�J���g���n���h�u�b�N�x�A�w�J���g���j���T�x(�r�N�g��
�A����C�A���Ƌ���)�A�w�]�ƈ��W��ƈӎu����x�Ȃǂ�����B�������M�҂̃r�N�g���A����C
�A�����́A���X�L����w(�I�b�N�X�t�H�[�h)�𑲋ƌ�A1971�N���O�o�̘J�g�W�������̒�
���������E���ł���B
���̂悤�ɁA�����̓C�M���X�ɂ�����J�g�W�_�̐��Ƃ̂悤�ł���A���ɂ��̃G���T�C�N
���y�f�B�X�g�Ƃ��ċƐт��グ�Ă���悤�ł���B���������āA�L�����삩��A�J���g���j����
�����闧��ɂ���B�����A�C�^��D���Ɋւ�����m���ɂ��Ă͕s���ł��邪�A����Ȃ��
���������M�������B
�@�ӔC���M�҂Ƃ݂���A�[�T�[��}�[�V�����́A1964�N�ȗ��A�I�b�N�X�t�H�[�h�ɂ���J�g��
�W�������̎�C�������ł���B��2�����E���ɏ]�R��A�I�b�N�X�t�H�[�h��w�ŋߑ�j��
PPE(�N�w������w��o�ϊw)���w�сA1948�N����w�̓��ʉۊO�����ψ���̏�u�t�ƂȂ�A
���̌�16�N�ԁA�J���g���A�ŐV�̌o�c�Ǘ��A�J�g�W������������Ă����B�܂��A�h�m�o����
����[�J���g���ƌٗp�Ғc�̂Ɋւ��鉤���ψ���A1965-68�A�M�Ғ��A�ȉ��A�����[�@]�ɂ���
�Ď���]�ɎQ�悵�����Ƃ�����A�����̘J�g�W�̐R���⒇�قɊ֗^���Ă����B�����āA�@�B�H
�ƁA�S�|�ƁA�����E�Ȃǂ̑����̎Y�ƂɊւ��钲�������ɏ]�����Ă����B�����Ƃ��āA�w�@�B
�H�Ƃ̘J�g�W�x�A�w�J�g�W�厫�T�x�A�w�J���g���n���h�u�b�N�x�A�w�J���g���j���T�x(�r�N�g��
�A����C�A���Ƌ���)�A�w�]�ƈ��W��ƈӎu����x�Ȃǂ�����B�������M�҂̃r�N�g���A����C
�A�����́A���X�L����w(�I�b�N�X�t�H�[�h)�𑲋ƌ�A1971�N���O�o�̘J�g�W�������̒�
���������E���ł���B
���̂悤�ɁA�����̓C�M���X�ɂ�����J�g�W�_�̐��Ƃ̂悤�ł���A���ɂ��̃G���T�C�N
���y�f�B�X�g�Ƃ��ċƐт��グ�Ă���悤�ł���B���������āA�L�����삩��A�J���g���j����
�����闧��ɂ���B�����A�C�^��D���Ɋւ�����m���ɂ��Ă͕s���ł��邪�A����Ȃ��
���������M�������B
�@2�@�͕ʍ\��
�@�wNUS100�N�j�x�́A���̂悤�ȏ͗��Ăō\������Ă���B
�����@ NUS���L���T����}�N���X�L�[
�@��1�́@��������҂���
��2�́@�n�x���b�N��E�B���\���ƐV�g���^�� 1887-94
��3�́@�g���̍Č��ƐV�n�� 1894-1911
��4�� ��1�����E���ƊC��������
��5�� �n�x���b�N��E�B���\���ƘJ���^�� 1
��6�́@�n�x���b�N��E�B���\���ƘJ���^�� 2
��7�́@�E�B���\���̈�Y
��8�� ��ʑg�����^��
��9�� 1966�N��X�g���C�L
��10�� �C�^��J���s��ƑD��
�@��� �@�o���n�ЂƂ̑Ό�
�r��
�t�^�@(NUS�A���̑��D���g���̑g�������Ǝ��Y)
�@�wNUS100�N�j�x�́A���̂悤�ȏ͗��Ăō\������Ă���B
�����@ NUS���L���T����}�N���X�L�[
�@��1�́@��������҂���
��2�́@�n�x���b�N��E�B���\���ƐV�g���^�� 1887-94
��3�́@�g���̍Č��ƐV�n�� 1894-1911
��4�� ��1�����E���ƊC��������
��5�� �n�x���b�N��E�B���\���ƘJ���^�� 1
��6�́@�n�x���b�N��E�B���\���ƘJ���^�� 2
��7�́@�E�B���\���̈�Y
��8�� ��ʑg�����^��
��9�� 1966�N��X�g���C�L
��10�� �C�^��J���s��ƑD��
�@��� �@�o���n�ЂƂ̑Ό�
�r��
�t�^�@(NUS�A���̑��D���g���̑g�������Ǝ��Y)
����I�ɂ́A��1�͂����3�͂���1�����E���ȑO�������ANUS���J���g���Ƃ��Ċm�����A
�D��c�̂ɂ���āA�悤�₭�F�m�����܂ł̌o�߂��L�q����Ă���B��4�͂����7�͂͗���
��Ԋ��ɓ�����A�n���҃E�B���\���g�����̔���`�Ƒ勰�Q���O��ɂ�����������z��
�߂����āA���̑g���̓��O�Ő������Η��A�R�����L�q����Ă���B��8�͂����₪��2����
�E���ȍ~���猻�݂܂łŁA�E�B���\�����z�����`�������@����A�V����NUS�ɕϐg���Ă���
�ߒ����L�q����Ă���B�����I�ɂ́A��1�͂����6�͂܂ł��A�S�̂̉ߔ����߂Ă���B��
��́A�n���҃E�B���\���g�������g���ݗ������ӂ��A���S����܂ł̎����ɓ�����B�����
�ǂɁANUS�Ƃ��̗��j�ɂƂ��āA�E�B���\���g���������Ӌ`���傫�����̂����������Ƃ�����
����B
�Ȃ��A�r���͎���75�߰�ނɂ��y��ł��邪�A����͒P�Ȃ�Q�l�A���p�����̗���ł͂Ȃ��A
���łɂ݂��悤�ɒ��҂������J�g�W�_�̃G���T�C�N���y�f�B�X�g�ł��邱�Ƃ���A�J���g����
���𒆐S�Ƃ���������j�����ӂ�ɐ��荞���̂ƂȂ��Ă���A����ɐ[������w�i��m
�肽�����̂ɂƂ��ẮA�D�̈ē������ƂȂ��Ă���B
�D��c�̂ɂ���āA�悤�₭�F�m�����܂ł̌o�߂��L�q����Ă���B��4�͂����7�͂͗���
��Ԋ��ɓ�����A�n���҃E�B���\���g�����̔���`�Ƒ勰�Q���O��ɂ�����������z��
�߂����āA���̑g���̓��O�Ő������Η��A�R�����L�q����Ă���B��8�͂����₪��2����
�E���ȍ~���猻�݂܂łŁA�E�B���\�����z�����`�������@����A�V����NUS�ɕϐg���Ă���
�ߒ����L�q����Ă���B�����I�ɂ́A��1�͂����6�͂܂ł��A�S�̂̉ߔ����߂Ă���B��
��́A�n���҃E�B���\���g�������g���ݗ������ӂ��A���S����܂ł̎����ɓ�����B�����
�ǂɁANUS�Ƃ��̗��j�ɂƂ��āA�E�B���\���g���������Ӌ`���傫�����̂����������Ƃ�����
����B
�Ȃ��A�r���͎���75�߰�ނɂ��y��ł��邪�A����͒P�Ȃ�Q�l�A���p�����̗���ł͂Ȃ��A
���łɂ݂��悤�ɒ��҂������J�g�W�_�̃G���T�C�N���y�f�B�X�g�ł��邱�Ƃ���A�J���g����
���𒆐S�Ƃ���������j�����ӂ�ɐ��荞���̂ƂȂ��Ă���A����ɐ[������w�i��m
�肽�����̂ɂƂ��ẮA�D�̈ē������ƂȂ��Ă���B
�@3�@�Y�ƕʘJ���g���j�̈Ӌ`
�����Ŏ�グ��J���g���j�̓C�M���X�́A���������̊C���g���j�ł���B������������̎Y
�ƕʘJ���g���j�̈Ӌ`�́A�ǂ��������Ƃ���ɂ���̂��B���̓_�ɂ��āA���炩���ߊm�F��
�����B
�@�C�M���X���{��`�Ƃ��̂��Ƃł̘J���g���́A�����̗��O�^�Ƃ��ĂƂ炦���A�����ȊO
�̔�r�̑ΏۂƂ���Ă����B�C�M���X�́A���{��`�̕ꍑ�Ƃ��āA�������ŏ��̔e�����ƂƂ�
�āA���E�o�ς��x�z���Ă����B���̃C�M���X�C�^�́A�C�M���X���{��`�̐����̊�Ղ��Ȃ��A
��������E�C�^�ɂ����Ē��R����n�ʂ�z���Ă����B���̂Ȃ��ŁA�C�M���X�C���g���͑���
�����ɐݗ�����A���E�̑D���̎Љ�I�n�ʂ̌���ɁA�w���I�Ȗ������ʂ����Ă����B
�@�������A�C�M���X�C�^�̒n�ʂ͌�i�C�^�����i�o����ɂ�ቺ���A�C�M���X�l�D���̒�
�क़J�����������E�Ɍւ肤��ł͂Ȃ��Ȃ�B�����āA�ŋ߂ɂ������ẮA�X�u�БD�̑�
���Ɠr�㍑�l�D���̐i�o�ɂ���āA�C�M���X�C�^�͢��������A�C�M���X�l�D���͒�������������
���܂����B�����������j�����C�M���X�C�^�Ƃ��̂��Ƃɂ���C���g���ɂ��āA����100�N��
�U��Ԃ邱�Ƃ́A�C�^�Y�Ƃɂ�����J��������������ꍇ�A�i�D�̎����Ƃ�����
�@���{��`�̂��ƂŁA�J�����͌ʎ��{���J���҂��ٗp���邱�Ƃ�ʂ��Ĕ�������B����
���A���{��`�͐��Y��i���قɂ���e��̎Y�Ƃɂ���č\������Ă���A�ʎ��{�͂��̕�
����Ȃ��Ă���ɂ����Ȃ��B���ꂼ��̎Y�Ƃ̂���悤�́A�����P�ɂ��̎Y�Ǝ��g�̐����
������łȂ��A���̍��̎��{��`�̐����Ƃ̊W��A���ꂪ���̍��̎Y�ƍ\���ɐ�߂�n
�ʁA���ꂪ���ƂƎ�茋�ԊW�A����ɂ��̍��₻�̎Y�Ƃ̍��ۏ�̒n�ʂƂ̊W�Ȃǂ���
�Ȃ��Ă���B
�@����ɔ����āA���ꂼ��̎Y�Ƃɂ�����J���҂̘J���\�͂�C���A�J���ԗl�͂��Ƃ��Ƃ�
�āA�ʎ��{�̎w����ēA�J���҂̋�����J���s��̂�����A�J�g�̌��ƑΗ��A���̌�
�ʂƂ��Ă̒��क़J�������̐����A����ɂ͂��̘J�g�W�ւ̍��Ɖ���̂�����Ȃǂ��قȂ�
�Ă���B�m���ɁA�J�����͂��ׂĂ̎Y�Ƃɋ��ʂ��鐫�i�����Ƃ͂����A��̓I�ɂ͎Y��
����I�Ȑ��i�������̂Ƃ��Ă������ꂦ�Ȃ��B���������āA�J���g���j����������Ƃ�������
�́A�܂������ĎY�ƕʘJ���g���j����グ��Ƃ������ƂɂȂ炴�邦�Ȃ��B�����ʂ��āA����
���̘J���g���j���܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���Ƃ������̂ł���A�܂����̍��ɂ����邻�ꂼ��̎Y
�ƕʘJ���g���j�̓��ꐫ���܂����炩�ɂ��邱�Ƃ��ł���y1�z�y2�z�B
�m���n
�@�y1�z�@�C�M���X�J���^���j�̌����Ɋւ���M���͏��Ȃ��Ȃ����A�����ʗ��ł�����̂Ƃ�
�āA�x���w�J���ƍ��Ɓ|�C�M���X�J���g����c�j�|�x�A��g���X�A1980������B
�y2�z�@�܂��A�wNUS100�N�j�x�ɑ������鎞��̃C�M���X�C�^�j�ɂ��ẮA�D�s���Ȃ��ƂɁA
Ronald Hope, A New History of British Shipping, John Murray, 1990 �̑�O��(����)���A�O��
�Ǒ����ɂ�袉p���C�^�̐��ޣ�Ƃ��āA�G���w�C�^�x��1992.2���A�ڒ��ł���̂ŁA�Q�Ƃ���
�����B�Ȃ��A���̏���ɂ́A�wNUS100�N�j�x�ł��܂���グ���Ă��Ȃ��A�C�M���X�l�D����
���क़J�������̎��Ԃ���A�Љ��Ă���B
�Q�@�wNUS100�N�j�x�̎�ȓ��e
1�@�D�����P�A���ݕ}����1850�N�C�^�@
�@���1�� ��������҂�����́A�����I�ɂ̓E�B���\����1887�N�ɑg����ݗ�����܂łł�
��A��Ƃ���17�A8���I�ɂ�����C�M���X�l�D���̎Y�݂̋ꂵ�݁A�����Ȑ��v��ɑ��鎜�P��
�����̔��R�A���ݕ}���c�̂̊����A�c���֎~�@���߂��铮���A�{�i�I�ȊC�^�@�Ƃ���ɑ�
����J�g�̔����A�����đD���J���g�D�̐������L�q����Ă���B�����ł́A�D���ɑ��鎜
�P��D���̑��ݕ}���A�����̒c�́A����ѐ��E�̑D���@�̊�b�ƂȂ���1850�N�C�^�@�Ƃ�
��ɑ���J�g�����ɂ��āA���̋L�q���e���Љ�A�����������B
�@���̎����́A�C�M���X���{��`���Y�Ɗv���𐬌������A���E�̔e���������������A�܂�1849
�N�ɍq�C��Ⴊ�p�~���ꂽ�悤�ɁA�C�M���X�C�^���܂����D����D�D�ɕς��A���S�Ɏ��{��
�`�����������ɓ�����B�܂��A���̎����̎Љ�J���^���́A�`���[�`�X�g�^����10���Ԗ@�^
�����݂�ꂽ�����ł�����B�����A�����ƑD������т��̘J�g�W�ɋy�ڂ����e���ɂ���
�́A�قƂ�NJ�����Ă��Ȃ��B
1)�@�D���ɑ��鎜�P
�@���҂́A18���I�̑D���ɂ��āA������̓��̍����ɂ́A�������鐫�i�����l�Ԃ�
����B���Ȃ�l�ƍߐ[���l�A�~��ꂵ�҂ƂȂ炸�ҁA�d���ɏ��������l�Ƃ���ɋ��������l
���A����ł���B����琫�i���A�킪���v�قǐF�Z�������Ă��鍑�����܂��ƂȂ��B���h�Ǝ�
�i�A������Ɠ���A���낢��Ȋ����ŁA�����̕]���ƂȂ��Ă����(����1�߰�ށA�ȉ�����)
�Ɨv�Ă���B�������������́A����ɂ����Ă��܂����{�ɂ����Ă��A��Ȃ菬�Ȃ�݂����
����ł���A�D�����������p�^�[���ƂȂ��Ă���B
�C�M���X�ɂƂ��āA�D���͕K�v�s���ȐE�Ƃł���Ȃ���A���̒u����Ă����Ԃ͔ߎS��
�܂���̂��������B�����������ƂɁA���S�ł͂����Ȃ������B�����Ŏ��P�������B�����
���āA���̂悤�ȋL�q���݂���B
�@�1696�N�́w�D�����㑝�i�@�x�Ƃ����c��@�́A�����铙���̑D�����疈����������6��ݽ
�����A�O���j�W�����a�@���^�c���邱�ƂƂ����B����͋���ł̋~�ς��ւ��悤�Ƃ�����
�̂ł������B�������A���̕X�𐅕v���������Ǝv���Ă��A�قƂ�ǂ��Ȃ����Ȃ������B����
�a�@�́A�����ɕa�C��ЊQ�A�V���Ɋׂ�����Q�҂��킯�ւ��ĂȂ��A�ʓ|�݂邱�Ƃ��ł��Ȃ���
�����B�����āA���D�D���������C�R�ɏ]�����Ă��Ă��A����ɓ��鎑�i�����������悤�ɂ�
�����B����ɑ���[�u���K�v�ł������B1747�N�A�S�����D�D��������ݗ����ꂽ�B����
�́A�O���j�W�Ɠ��l�A�D���̊�t�ɂ���ĉ^�c���ꂽ�B����ɂ́A�Z���Ԃ̋��t�ł͂�����
���A�D���̔N����Ǖw�̋~�ςƂ������x���܂܂�Ă���A�����Ƃ��Ă͐i�@�\�ł������B
�����͑�ς��܂������Ă������A���ǂ͎x�������Ɉ��|����Ă��܂��A19���I�A�C�^���g�債
�Ă���ɂ�������炸�A1851�N�ɔp�~����Ă���B���̏��D�D������́A�����̎��I�Ȏ��P�c
�̂��a�C�ɂ��������D���̋~�ς�A�D���Z��A���v�̎q���̋�������{����ɂ������ẮA
��̎���ƂȂ�܂��h���ƂȂ����B�����c�̂�19���I�܂Ŏ��Ƃ��Â�����Ƃ���(4-5�߰
��)�B
�@���̑D���ɑ��鎜�P�̋L�q�́A����߂Ċȗ�������Ă��邪�A���{�������P�Ƃ���
�̓����́A�ꉞ������Ă���B1601�N�~�n�@�̐���ɔ����A�D���̋~�n������Ɉς˂���
�������A1696�N�@�ɔ������ꂩ��藣���ꂽ�B���̗��R�́A�ٗp�̓��ꐫ����A��������
�܂炸�A�����Ōٗp��������Ȃ��D�����������A�ꎞ�̋����ƂȂ鋳�悪�~�n���Ȃ��Ȃ�����
�߂Ƃ݂���B���̌��ʂƂ��Ăł͂��邪�A�O���j�W�����a�@�A����ɑS�����D�D���������
������A���ꂪ�D���̋��o���ł����ĉ^�c����Ă����̂́A���{��D�傪����̔�p����
���ĕ��S���悤�Ƃ��Ȃ��������߁A�D���ɋ��o�����邵���Ȃ���������Ƃ݂���B
�@�����̎{�݂́A�C�M���X�ŏ��̋��o����Â��邢�͔N�����ł���Ƃ����Ă��邪�A����
��͑D���̑��ݕ}��(����)�ɂ������A���ꂪ���{�ɂ���ĉ^�c���ꂽ���Ƃ����P�ł�������
���A���������Ȃ��͂Ȃ��B���������{�݂��D���ɍL�͂ɗ��p�����킯�͂Ȃ������B������
�I�{�݈ȊO�ɁA���R���鎄�I���P���Ȃ������킯�ł͂Ȃ��A���̗����ʎ{�݂�1860�N���
��A���B�����̂ɔ�ׂ�A����炪�����ɔ��B���Ă����Ƃ����邪�A���{��`�I�ȊC�^��
���B���邢�͂��̂��Ƃł̑D���̑����ƂƂ��ɐ��ނ���������Ȃ������̂́A���R�̐���s��
�������y1�z�B
2)�@�D���̑��ݕ}��
�@�����������P�̂������A�D���͑��̘J���҂Ɠ��l�ɁA����̖��͎��炪��������Ƃ�
�āA�����N���u����������ƂƂ��ɁA�18���I�ɓ���ƁA�D���͂��̂�����Ă��鈫����Ԃɑ�
����s�����A������Ƃ���ŁA�������ꋓ�ɔ���������(5�߰��)�B�������������f���͂�����
�˖\���ƂȂ�B
�C�M���X�̖k���C�݂́A�D���g�D�̗h�Ղ̒n�ł���A�E�B���\���̏o�g�n�ł�����B���̈�
�p�̃T�E�X�V�[���Y�ŁA1798�N�ɐ��v������ݗ�����A������\�߁A���邢�͕a�C��\��
���ʕs�K�A����A�V��Ɋׂ����D�����������飂��Ƃɂ��Ă���B�܂��A�������A�m�[�X�V�[���Y
�ŁA1824�N�ɑD����������@(the Seamen's Loyal Standard Association)���ݗ������B����
�͂�����ρA��S�I�ȗF���c�̂������Ƃ��Ă���B���̑D����������̢�ړI�́A�k���C��
�́c�c�����̑D���g�D�̊����ƘA�W���A�ސE���t����a�C�A���S�̋��t���Ǘ����邱
�Ƃɂ������B�������A����D���[1824�N]�c���֎~�@�̔p�~���āA����ȊO�̏d�v�ȖړI
���������J���]�c���ł��o�����Ƃ��Ă��飂Ƌ���Ă���(8�߰��)�y2�z�B
�@���̑g�D�́A�D��ɗv�������o������A�N���[�Y�h�V���b�v��ڎw������͂��Ă��Ȃ��������A
�Œ�����𐧒肵����A�D���̋�����グ��Ӑ}�������A���̒n���̒��グ�X�g���C�L��
�֗^���Ă����B�܂��A������͑��̘J���ґg�D�ƂƂ��ɁA�c���֎~�@�̔p�~�ɓ������āA����
�ȋ}�i��`�҃X�����V�X��v���C�X����A�c��̈ψ���ɑ��铭�������₻���ł̐����̎d
���ɂ��Ďw�����A���̂���ɢ�T1��ݽ�̊�t���W�߂Ĕ������Ƃ����A�`�̂悢���
�ԕr������Ƃ���(9�߰��)�B
�@���̂悤�ɁA��i�I�Ȓn��ɂ����āA�c���֎~�@������������Ȃ���A���ݕ}������b�ɂ�
�āA�����ƘA�g����邱�ƂŁA�J���g���̖�����S�����Ƃ���g�D���݂�ꂦ��悤�ɂȂ���
���A�����͒��҂������悤�ɑD���̏���ʂ�g�D����ɂƂǂ܂�A�S���g�D�ɔ��W����_�@
�Ƃ͂Ȃ�Ȃ������y3�z�B
3)�@1850�N�C�^�@�̐���
�C�M���X�́A1849�N�q�C����p�~���A���R�f�Ղɐi�ށB����ɔ����āA���̊C�^�����E��
�����T�[�r�X�����������Ȃ��Ȃ����B�1836�N�A������ψ���̓C�M���X�D�̌����s
�ǁA�����s���S�A�D���Ǝm���̓D������\�͂��w�E���Ă�������A�܂��1846�N�c�c�A����ψ�
��c�c�b�ς݂̉ݕ��͌Ŕ����邱�ƁA���q�D�̌����͋����Ƃ���A�܂�100�݈ȏ�̓S
�D�͊u�ǂ�2�݂��邱�ƁA�����āw�^���͒����̌����x�Ƃ����i���ɂ��ƂÂ��A�D�������͉�
�����A������A�D�傪�^������������Ɍ����Ďx�����Ă������A����͉ݕ��̗A����
�L���ɂ�����炸�A�Ζ�����ɂ��Ďx�������ƣ����������(10)�B�߰�ނ������A�����Ƃ̕ω�
���N���Ȃ������B
�@1850�N�ɂȂ��āA���{�͊C�^�@�𐧒肷��B���̐���ɓ������āA��C�^�T�[�r�X�Ɍٗp��
��Ă���j�������ȏ�Ԃɂ���Ƃ����A���E�e�n�̗̎�����̕��傫�ȉe�����y��
���Ă�����B���̖@���́A��V�[�}����V�b�v�̊�A�����Ďm���̋s�҂�D��̈��s���玩�q
�ł���Ƃ������A���܂܂łƂ͈�������ʂ̖������グ�Ă�����B����́A�D����m���̔\
�͎����Ƃ��̎��i�̎������A��D�_�Ɂu�q�C�̎�ʂƋ����A��D���ԁA��g���̒�
���A�������z��ςݍ��ݐH���A�����ď�D���̋K���Ɛ��ق��L�ڂ�����(11�߰��)�B�܂��A�n
���C�^�ǂ�z�u���āA�D����m���̎�����D���̏扺�D���Ǘ����邱�ƂƂ����y4�z�B
�@���̖@���ɑ��āA��ǂ�Ȃ킸���ȋK���ł��A�������邱�Ƃ̓C�M���X�D�̉ݕ����^�Ԍ�
���Ȃ킹�邱�ƂɂȂ飂ƁA�D�傪�s�����ƂȂ����̂͂��Ƃ��ł��������A�D���ɂƂ��Ă�
�s���͢�扺�D���邽�і��ɊC�^�ǂɎ����萔���ƁA���{���@���ɐ��荞�D���K��
�ɂ�������B�����ŁA����܂��k���C�݂̃m�[�X�V�[���Y�ȂǂŁA�D���A���ی�g��(the
Seamen's United Protection Society)�Ə̂���g������������A���グ�Ɩ@�����������߂�X
�g���C�L���s���B����̓����h���A���o�v�[���ɂ��g����A����ɋc��ɐ�����o���܂łɂȂ�B
����ɂ���āA�22�����ɋy�ԋK���ᔽ�̏͂��̎{�s����~����A�����Čٓ����َ~
�߂̍ۂ̎萔���ɂ��Ă��������s�Ȃ���(13�߰��)�B���̕����ɂ��āA�^�C���Y����
1797�N�����C�R�̃m�A�̑唽���̃~�j�`���A�ł��ƕ]�����Ƃ����B
�@���̖@���́A���E�ɂ�����D���@�̐�삯�Ƃ�������̂ł���B���҂́A�����ł�1972�N
�ٗp�_��@�̂��Ƃł͂��߂ďڍׂ��߂�ꂽ���̂��A�C��ł͂��ł�122�N�O�ɐ�������
������ƕ]�����Ă���(12�߰��)�B���̖@���́A�D���g�D�̗v���Ɋ�Â����̂ł͂Ȃ��A�C�M���X
�D�ƃC�M���X�l�D�����S�������߂Ă������߁A���{���C�M���X�̈АM��ۂƂ��Ƃ��āA����
�I�ɖ@�����������̂ł������B���������āA�{�i�I�ȘJ���ی�@�Ƃ�������̂ł͂Ȃ��A�D���J
���\�͂ƘJ���K���̕W������ڎw�������̂ł������B�D��ɑ����āA���{���D���������
�낤�Ƃ���������������@���ɁA�D�����������A�����p�~�����悤�ƁA�����鐧�x�I����
��S���K�͂œW�J�����Ӌ`�͌������Ȃ��B�������A�D���K���̖{�i�I�Ȑ����́A��q��
�悤�ɁA1970�N�C�^�@�̐���܂ő҂��˂Ȃ�Ȃ������B
�m���n
�@�y1�z�@�ߐ��܂ł̃C�M���X�l�D���̗��j�A�Ȃ��ł��D�����P��D���ٗp�A�D�������ɂ���
�́A�ْ��w���D�̎Љ�j�|�C�M���X�D���̏،��|�x�A�������o�ŎЁA1983���Q�Ƃ��ꂽ���B
�@�y2�z�@�w�����[��y�����O���A��O��Y�A��O �^��w�V�ŃC�M���X�J���g���^���j�x�A25�߰
�ށA���m�o�ϐV��ЁA1983�ɂ́A���̒c�̂́A�ق���̐N�Q�ɑR���邽�߂̒c���̌�����
�i�삵�A��g�����Ə�D���邱�Ƃ����₵�悤�Ƃ��Ă����ƏЉ��Ă���B
�@�y3�z�@�V�h�j�[��E�G�b�u�A�r�A�g���A�X��E�G�b�u���A�r�������Ė�A�ѓc �C�A���� ����w�J��
�g���^���̗��j�x�㊪�A467�߰�ށA���{�J������A1963�ɂ́A��q��NAS&FU�ݗ��O�ɁA�k
���C�݂őg�D���ꂽ�D���̑g���ɂ��ċL�q����Ă���B
�y4�z�@����a�V���w�D�����̍��ۓI�W�]�x�A426-464�߰�ށA���{�C���U����A1958�́A
1850�N�C�^�@�Ɏ���ߒ��Ƃ��̐�����e���ڍׂɏЉ�Ă���B
�@���1�� ��������҂�����́A�����I�ɂ̓E�B���\����1887�N�ɑg����ݗ�����܂łł�
��A��Ƃ���17�A8���I�ɂ�����C�M���X�l�D���̎Y�݂̋ꂵ�݁A�����Ȑ��v��ɑ��鎜�P��
�����̔��R�A���ݕ}���c�̂̊����A�c���֎~�@���߂��铮���A�{�i�I�ȊC�^�@�Ƃ���ɑ�
����J�g�̔����A�����đD���J���g�D�̐������L�q����Ă���B�����ł́A�D���ɑ��鎜
�P��D���̑��ݕ}���A�����̒c�́A����ѐ��E�̑D���@�̊�b�ƂȂ���1850�N�C�^�@�Ƃ�
��ɑ���J�g�����ɂ��āA���̋L�q���e���Љ�A�����������B
�@���̎����́A�C�M���X���{��`���Y�Ɗv���𐬌������A���E�̔e���������������A�܂�1849
�N�ɍq�C��Ⴊ�p�~���ꂽ�悤�ɁA�C�M���X�C�^���܂����D����D�D�ɕς��A���S�Ɏ��{��
�`�����������ɓ�����B�܂��A���̎����̎Љ�J���^���́A�`���[�`�X�g�^����10���Ԗ@�^
�����݂�ꂽ�����ł�����B�����A�����ƑD������т��̘J�g�W�ɋy�ڂ����e���ɂ���
�́A�قƂ�NJ�����Ă��Ȃ��B
1)�@�D���ɑ��鎜�P
�@���҂́A18���I�̑D���ɂ��āA������̓��̍����ɂ́A�������鐫�i�����l�Ԃ�
����B���Ȃ�l�ƍߐ[���l�A�~��ꂵ�҂ƂȂ炸�ҁA�d���ɏ��������l�Ƃ���ɋ��������l
���A����ł���B����琫�i���A�킪���v�قǐF�Z�������Ă��鍑�����܂��ƂȂ��B���h�Ǝ�
�i�A������Ɠ���A���낢��Ȋ����ŁA�����̕]���ƂȂ��Ă����(����1�߰�ށA�ȉ�����)
�Ɨv�Ă���B�������������́A����ɂ����Ă��܂����{�ɂ����Ă��A��Ȃ菬�Ȃ�݂����
����ł���A�D�����������p�^�[���ƂȂ��Ă���B
�C�M���X�ɂƂ��āA�D���͕K�v�s���ȐE�Ƃł���Ȃ���A���̒u����Ă����Ԃ͔ߎS��
�܂���̂��������B�����������ƂɁA���S�ł͂����Ȃ������B�����Ŏ��P�������B�����
���āA���̂悤�ȋL�q���݂���B
�@�1696�N�́w�D�����㑝�i�@�x�Ƃ����c��@�́A�����铙���̑D�����疈����������6��ݽ
�����A�O���j�W�����a�@���^�c���邱�ƂƂ����B����͋���ł̋~�ς��ւ��悤�Ƃ�����
�̂ł������B�������A���̕X�𐅕v���������Ǝv���Ă��A�قƂ�ǂ��Ȃ����Ȃ������B����
�a�@�́A�����ɕa�C��ЊQ�A�V���Ɋׂ�����Q�҂��킯�ւ��ĂȂ��A�ʓ|�݂邱�Ƃ��ł��Ȃ���
�����B�����āA���D�D���������C�R�ɏ]�����Ă��Ă��A����ɓ��鎑�i�����������悤�ɂ�
�����B����ɑ���[�u���K�v�ł������B1747�N�A�S�����D�D��������ݗ����ꂽ�B����
�́A�O���j�W�Ɠ��l�A�D���̊�t�ɂ���ĉ^�c���ꂽ�B����ɂ́A�Z���Ԃ̋��t�ł͂�����
���A�D���̔N����Ǖw�̋~�ςƂ������x���܂܂�Ă���A�����Ƃ��Ă͐i�@�\�ł������B
�����͑�ς��܂������Ă������A���ǂ͎x�������Ɉ��|����Ă��܂��A19���I�A�C�^���g�債
�Ă���ɂ�������炸�A1851�N�ɔp�~����Ă���B���̏��D�D������́A�����̎��I�Ȏ��P�c
�̂��a�C�ɂ��������D���̋~�ς�A�D���Z��A���v�̎q���̋�������{����ɂ������ẮA
��̎���ƂȂ�܂��h���ƂȂ����B�����c�̂�19���I�܂Ŏ��Ƃ��Â�����Ƃ���(4-5�߰
��)�B
�@���̑D���ɑ��鎜�P�̋L�q�́A����߂Ċȗ�������Ă��邪�A���{�������P�Ƃ���
�̓����́A�ꉞ������Ă���B1601�N�~�n�@�̐���ɔ����A�D���̋~�n������Ɉς˂���
�������A1696�N�@�ɔ������ꂩ��藣���ꂽ�B���̗��R�́A�ٗp�̓��ꐫ����A��������
�܂炸�A�����Ōٗp��������Ȃ��D�����������A�ꎞ�̋����ƂȂ鋳�悪�~�n���Ȃ��Ȃ�����
�߂Ƃ݂���B���̌��ʂƂ��Ăł͂��邪�A�O���j�W�����a�@�A����ɑS�����D�D���������
������A���ꂪ�D���̋��o���ł����ĉ^�c����Ă����̂́A���{��D�傪����̔�p����
���ĕ��S���悤�Ƃ��Ȃ��������߁A�D���ɋ��o�����邵���Ȃ���������Ƃ݂���B
�@�����̎{�݂́A�C�M���X�ŏ��̋��o����Â��邢�͔N�����ł���Ƃ����Ă��邪�A����
��͑D���̑��ݕ}��(����)�ɂ������A���ꂪ���{�ɂ���ĉ^�c���ꂽ���Ƃ����P�ł�������
���A���������Ȃ��͂Ȃ��B���������{�݂��D���ɍL�͂ɗ��p�����킯�͂Ȃ������B������
�I�{�݈ȊO�ɁA���R���鎄�I���P���Ȃ������킯�ł͂Ȃ��A���̗����ʎ{�݂�1860�N���
��A���B�����̂ɔ�ׂ�A����炪�����ɔ��B���Ă����Ƃ����邪�A���{��`�I�ȊC�^��
���B���邢�͂��̂��Ƃł̑D���̑����ƂƂ��ɐ��ނ���������Ȃ������̂́A���R�̐���s��
�������y1�z�B
2)�@�D���̑��ݕ}��
�@�����������P�̂������A�D���͑��̘J���҂Ɠ��l�ɁA����̖��͎��炪��������Ƃ�
�āA�����N���u����������ƂƂ��ɁA�18���I�ɓ���ƁA�D���͂��̂�����Ă��鈫����Ԃɑ�
����s�����A������Ƃ���ŁA�������ꋓ�ɔ���������(5�߰��)�B�������������f���͂�����
�˖\���ƂȂ�B
�C�M���X�̖k���C�݂́A�D���g�D�̗h�Ղ̒n�ł���A�E�B���\���̏o�g�n�ł�����B���̈�
�p�̃T�E�X�V�[���Y�ŁA1798�N�ɐ��v������ݗ�����A������\�߁A���邢�͕a�C��\��
���ʕs�K�A����A�V��Ɋׂ����D�����������飂��Ƃɂ��Ă���B�܂��A�������A�m�[�X�V�[���Y
�ŁA1824�N�ɑD����������@(the Seamen's Loyal Standard Association)���ݗ������B����
�͂�����ρA��S�I�ȗF���c�̂������Ƃ��Ă���B���̑D����������̢�ړI�́A�k���C��
�́c�c�����̑D���g�D�̊����ƘA�W���A�ސE���t����a�C�A���S�̋��t���Ǘ����邱
�Ƃɂ������B�������A����D���[1824�N]�c���֎~�@�̔p�~���āA����ȊO�̏d�v�ȖړI
���������J���]�c���ł��o�����Ƃ��Ă��飂Ƌ���Ă���(8�߰��)�y2�z�B
�@���̑g�D�́A�D��ɗv�������o������A�N���[�Y�h�V���b�v��ڎw������͂��Ă��Ȃ��������A
�Œ�����𐧒肵����A�D���̋�����グ��Ӑ}�������A���̒n���̒��グ�X�g���C�L��
�֗^���Ă����B�܂��A������͑��̘J���ґg�D�ƂƂ��ɁA�c���֎~�@�̔p�~�ɓ������āA����
�ȋ}�i��`�҃X�����V�X��v���C�X����A�c��̈ψ���ɑ��铭�������₻���ł̐����̎d
���ɂ��Ďw�����A���̂���ɢ�T1��ݽ�̊�t���W�߂Ĕ������Ƃ����A�`�̂悢���
�ԕr������Ƃ���(9�߰��)�B
�@���̂悤�ɁA��i�I�Ȓn��ɂ����āA�c���֎~�@������������Ȃ���A���ݕ}������b�ɂ�
�āA�����ƘA�g����邱�ƂŁA�J���g���̖�����S�����Ƃ���g�D���݂�ꂦ��悤�ɂȂ���
���A�����͒��҂������悤�ɑD���̏���ʂ�g�D����ɂƂǂ܂�A�S���g�D�ɔ��W����_�@
�Ƃ͂Ȃ�Ȃ������y3�z�B
3)�@1850�N�C�^�@�̐���
�C�M���X�́A1849�N�q�C����p�~���A���R�f�Ղɐi�ށB����ɔ����āA���̊C�^�����E��
�����T�[�r�X�����������Ȃ��Ȃ����B�1836�N�A������ψ���̓C�M���X�D�̌����s
�ǁA�����s���S�A�D���Ǝm���̓D������\�͂��w�E���Ă�������A�܂��1846�N�c�c�A����ψ�
��c�c�b�ς݂̉ݕ��͌Ŕ����邱�ƁA���q�D�̌����͋����Ƃ���A�܂�100�݈ȏ�̓S
�D�͊u�ǂ�2�݂��邱�ƁA�����āw�^���͒����̌����x�Ƃ����i���ɂ��ƂÂ��A�D�������͉�
�����A������A�D�傪�^������������Ɍ����Ďx�����Ă������A����͉ݕ��̗A����
�L���ɂ�����炸�A�Ζ�����ɂ��Ďx�������ƣ����������(10)�B�߰�ނ������A�����Ƃ̕ω�
���N���Ȃ������B
�@1850�N�ɂȂ��āA���{�͊C�^�@�𐧒肷��B���̐���ɓ������āA��C�^�T�[�r�X�Ɍٗp��
��Ă���j�������ȏ�Ԃɂ���Ƃ����A���E�e�n�̗̎�����̕��傫�ȉe�����y��
���Ă�����B���̖@���́A��V�[�}����V�b�v�̊�A�����Ďm���̋s�҂�D��̈��s���玩�q
�ł���Ƃ������A���܂܂łƂ͈�������ʂ̖������グ�Ă�����B����́A�D����m���̔\
�͎����Ƃ��̎��i�̎������A��D�_�Ɂu�q�C�̎�ʂƋ����A��D���ԁA��g���̒�
���A�������z��ςݍ��ݐH���A�����ď�D���̋K���Ɛ��ق��L�ڂ�����(11�߰��)�B�܂��A�n
���C�^�ǂ�z�u���āA�D����m���̎�����D���̏扺�D���Ǘ����邱�ƂƂ����y4�z�B
�@���̖@���ɑ��āA��ǂ�Ȃ킸���ȋK���ł��A�������邱�Ƃ̓C�M���X�D�̉ݕ����^�Ԍ�
���Ȃ킹�邱�ƂɂȂ飂ƁA�D�傪�s�����ƂȂ����̂͂��Ƃ��ł��������A�D���ɂƂ��Ă�
�s���͢�扺�D���邽�і��ɊC�^�ǂɎ����萔���ƁA���{���@���ɐ��荞�D���K��
�ɂ�������B�����ŁA����܂��k���C�݂̃m�[�X�V�[���Y�ȂǂŁA�D���A���ی�g��(the
Seamen's United Protection Society)�Ə̂���g������������A���グ�Ɩ@�����������߂�X
�g���C�L���s���B����̓����h���A���o�v�[���ɂ��g����A����ɋc��ɐ�����o���܂łɂȂ�B
����ɂ���āA�22�����ɋy�ԋK���ᔽ�̏͂��̎{�s����~����A�����Čٓ����َ~
�߂̍ۂ̎萔���ɂ��Ă��������s�Ȃ���(13�߰��)�B���̕����ɂ��āA�^�C���Y����
1797�N�����C�R�̃m�A�̑唽���̃~�j�`���A�ł��ƕ]�����Ƃ����B
�@���̖@���́A���E�ɂ�����D���@�̐�삯�Ƃ�������̂ł���B���҂́A�����ł�1972�N
�ٗp�_��@�̂��Ƃł͂��߂ďڍׂ��߂�ꂽ���̂��A�C��ł͂��ł�122�N�O�ɐ�������
������ƕ]�����Ă���(12�߰��)�B���̖@���́A�D���g�D�̗v���Ɋ�Â����̂ł͂Ȃ��A�C�M���X
�D�ƃC�M���X�l�D�����S�������߂Ă������߁A���{���C�M���X�̈АM��ۂƂ��Ƃ��āA����
�I�ɖ@�����������̂ł������B���������āA�{�i�I�ȘJ���ی�@�Ƃ�������̂ł͂Ȃ��A�D���J
���\�͂ƘJ���K���̕W������ڎw�������̂ł������B�D��ɑ����āA���{���D���������
�낤�Ƃ���������������@���ɁA�D�����������A�����p�~�����悤�ƁA�����鐧�x�I����
��S���K�͂œW�J�����Ӌ`�͌������Ȃ��B�������A�D���K���̖{�i�I�Ȑ����́A��q��
�悤�ɁA1970�N�C�^�@�̐���܂ő҂��˂Ȃ�Ȃ������B
�m���n
�@�y1�z�@�ߐ��܂ł̃C�M���X�l�D���̗��j�A�Ȃ��ł��D�����P��D���ٗp�A�D�������ɂ���
�́A�ْ��w���D�̎Љ�j�|�C�M���X�D���̏،��|�x�A�������o�ŎЁA1983���Q�Ƃ��ꂽ���B
�@�y2�z�@�w�����[��y�����O���A��O��Y�A��O �^��w�V�ŃC�M���X�J���g���^���j�x�A25�߰
�ށA���m�o�ϐV��ЁA1983�ɂ́A���̒c�̂́A�ق���̐N�Q�ɑR���邽�߂̒c���̌�����
�i�삵�A��g�����Ə�D���邱�Ƃ����₵�悤�Ƃ��Ă����ƏЉ��Ă���B
�@�y3�z�@�V�h�j�[��E�G�b�u�A�r�A�g���A�X��E�G�b�u���A�r�������Ė�A�ѓc �C�A���� ����w�J��
�g���^���̗��j�x�㊪�A467�߰�ށA���{�J������A1963�ɂ́A��q��NAS&FU�ݗ��O�ɁA�k
���C�݂őg�D���ꂽ�D���̑g���ɂ��ċL�q����Ă���B
�y4�z�@����a�V���w�D�����̍��ۓI�W�]�x�A426-464�߰�ށA���{�C���U����A1958�́A
1850�N�C�^�@�Ɏ���ߒ��Ƃ��̐�����e���ڍׂɏЉ�Ă���B
�@2�@�g���ݗ��Ƃ�����߂���U�h
���2�� �n�x���b�N��E�B���\���ƐV�g���^�� 1887-94��́A�O���[�g�u���e����A���h��A�C����
���h�S���������Εv�g��(the National Amalgamated Sailors' and Firemen's Union of Great
Britain and Ireland�A�ȉ��ANAS&FU �Ƃ���)�̓�Y�ƁA������߂���D��Ƃ̍U�h�A�D��̐�
���g�D=�C�^�A���̌����A���̈����̂��Ƃł�NAS&FU�̔C�Ӕj�Y�ɂ��āA�L�q����Ă�
��B���̊��Ԃ́A�C�M���X�J���g���̉���ƂȂ����V�g���^�����䓪���������ɓ�����B����
�ł́ANAS&FU�̐ݗ��A�C�^�A���̖ړI�Ǝ�i�A������NAS&FU�̉��U�ɂ��Ď�グ��B
1)�@�E�B���\���ANAS&FU��ݗ�
�@�wNUS100�N�j�x�̑O�������́A�n�x���b�N��E�B���\��(J.Havelock Wilson�A1860-1929)�̗��j
���Ƃ����Ă��A�����ĉߌ��ł͂Ȃ��B�����ŁA����̏o����NAS&FU�ݗ��̌o�߂ɂ��āA����
�ڂ����ӂ��B
�@����́A1860�N�A�T���_�[�����h�̕��n�E�l���̎q���Ƃ��Đ��܂�A���e�����S�������ƂŁA
����H��ΔōH�̓k��ɏo�����B13�̎��A�C��ɏo�āA11�N�ԁA���܂��܂ȑD�̎i�~�{
�[�C�A�L�\�D���A�b��(���Ȏm������)�A���ɂ͒�����Ƃ��ē����A1879�N�Ɍ�������3�N
��A�T���_�[�����h�Ţ�E�B���\���̏h���ƐH���̋֎�X��ƌĂ�鏬���ȐH�����J���B����
�́A��C�㐶���𑗂��Ă������ƂŎ����Ă����O�q�D���Ƒ��ɑ��邱������A�����Ƃ�
���N�̂������̂Ȃ��ŁA�J���g���^���ɂ��ĊS��s��������A���̉��P���K�v�ƍl��
��悤�ɂȂ����B�����Ő��܂�炿�A���Ԃ̂���y�n�ŁA�őP��s�������ƂƂ�����Ƃ���(18�߰
��)�B
�@�E�B���\���́A1880�N���碃T���_�[�����h�̑g����ɂ����Ċ������A�h�����̐���ɑ傫��
�������ʂ��������@�c���T�~���G����v�����]��(1824-1898)���͂��߁y1�z�A�S���I�ɐM�]�̂�
��g��������g���o�g�c���A�ٌ�m����g���^���A�c��H��A��O��`�̎d�����w��ł�
��B�����A���̑g����S���g�D�ɐ�ւ��悤�Ɠw�͂��邪�A���ꂪ������Ȃ������B
���ꂪ�g�D�����x���̏�]�����A�{���Ɏ�n���Ȃ��������Ƃ��Ƃ��߂���B������_�@�ɂ�
�āA���O�̑g���̐ݗ��ɓ��ݐ�B1887�N7���A�T���_�[�����h��NAS&FU�̐ݗ��̉���J
�����A����ɎQ�������̂͂�����l�ł������B����ɂ��������A���N8���ɍēx�J�Â����Ƃ���A
12�l�ƂȂ����B
�@���̐ݗ��ɂ��āA�����h���̃f�B���[��e���O���t���́A��c�c���̑g���͉���ڎw�����Ƃ���
����̂��B�܂����ׂĂ̘J�����������P���邱�ƁA���Œ������邢�͕�������S�ۂƂ��āA
���������q�Ȃ��őO�n�������x���킹�邱�ƁA�����ēK���ȘJ�����Ԃƌ����Ȓ������l������
���w�͂��邱�Ƃł���B�܂��A�a�C�ɂȂ����g������D��ɕ}�{�����邱�ƁA�N�i����ė����
�S�����ꂽ�g�����ɁA������ٔ���A�}�{��Ɋւ���~�ύ���u���邱�Ƃł���B����ɁA��
�̑g���͊C�^�T�[�r�X�ɍŗǂ̑D�������悤�ɓw�͂��A�܂���g�������߂�ꂽ����
�ɂ���ӂŏ�D����悤�Ď����邱�Ƃɂ���B�����āA�C��ɂ������D���̋~�ρA���E���s����
�D���̉����A���a���t�⌋���j�����̂��߂̊���̐ݗ��Ȃǂ��������邱�Ƃɂ��Ă���B��
���������x�͂��ׂď^�A���тɒl���悤�B�c�c�h���������Ƃ₢�₾�������Ƃ�Y��Ă��܂�
�قǁA�����ԁA�ʓ|�����Ă��炦�Ȃ������l�X�����ܖڊo�߂āA�g����������킯�ł��邪�A
�Ŕʂ�̂��Ƃ���萋������ł��낤���B�D���̗F�B�́A���˂��ˁA���낢��Ɛs�͂���
���������ɗ����Ȃ������ƁA��]���Ă���ł͂Ȃ����B���v���g���A�����Ȃ�Ȃ����Ƃ�]�ށB
�����āA���̃T���_�[�����h�̑S���D���g���Ƃ������h�ȃv���W�F�N�g���A�����Ȃ����������Ƃ�
�����ƂɂȂ�Ȃ��悤��]���飂Ƃ������҂ƕs�����L���Ƃ��Ă���(22�߰��)�B
����NAS&FU�̐ݗ��ɂ����Ē��ڂ��ׂ����Ƃ́A�܂��㏬�̒n���g�D������������̂ł͂�
���A�ŏ����狐��ȑS���g�D��ڎw�������Ƃɂ���B���ꂪ���������̂́A���łɑS�������g
�����g������݂��Ă�����ƂŁA��ʑD���ɂ����Ă��������]���镵�͋C������A������E
�B���\��������Ő��͓I�Ɋ��������B�������A����ɓ������ĐV���L���ɂ��݂���悤�ɁA
��ʑD���̓���I�̐؎��ȗv�����L�͂���̓I�Ɏ�グ�A���̉�����ڎw�������Ƃɂ�
��B����ɁANAS&FU�Ƃ��čŗǂ̑D�����������邱�Ƃ����ƂƂ������Ƃ��A�ʒi���ڂ����
�y2�z�B
�@�Ȃ��ANAS&FU�A���̌�g�̑g�����A�m���⋙�D���̑g�D�������݂Ă��邪�A���v�A�Εv�A
�������A�i�~���Ƃ������A�قځA����ɂ����D�������̒P��g�D���葱�����B���̓_�ŁA��O
���{�̊C���g���Ɠ����ł��邪�A�D���E�����܂ސ��̂���Ƃ͑傫���قȂ��Ă���B�܂��A
NAS&F�Ƃ��̌�g�̑g���ɂ́A���{�Ɠ��l�A1900�N�ォ��20�N��ɂ����āA�������A�i�~��
�𒆐S��3�قǂ̂��Ȃ�L�͂ŁA�D��I�ȃ��C�o���g�����������B�����g�����A1920�N��
���ɂ͉��U���邩�A�E�B���\���̑g���ɋz������邱�ƂɂȂ�B
�@���{�̑D���g�D�́A�C�M���X�ɒx��邱��25�N���1912(����45)�N�̓��{�D�����u���
��Ƃ��邪�A�{�i�I�ȑg�D�͓�����34�N���1921(�吳10)�N�̓��{�C���g���ł������B����
�g���́AILO��2��C������ɂ����č̑����ꂽ�C���Љ���ɂ��L���E�ƏЉ�֎~��
�ꂽ���Ƃ��_�@���āA���g�D����ނȂ��������Đݗ����ꂽ���̂ł���A�܂�������{�[��
���A�C�M���X�ł����N�����v(Crimp)�ƌĂ��D�������ƂƓ������߂ɐݗ����ꂽ�킯�ł�
�Ȃ������B���������_�ŁA��O�̓��{�C���g���̓E�B���\���̑g���Ƃ͂��Ȃ�傫������Ă�
��B�Ȃ��A��N�A���̑g�����ƂȂ����l�c�����Y�̓E�B���\���ƂȂ��炦�邱�Ƃ��ł��悤�B
2)�@�C�^�A���̖ړI�A��i
�@NAS&FU�̑g�D�����i�ނɂ�āA�D���͑g�����̃E�B���\���̎v�f���Đ퓬�I�ɂ�
��A�e�n�Œ��グ�₻�̂��߂̃X�g���C�L�A�D�������A�C�^�ǂ̃s�P�b�e�B���O���s���悤�ɂ�
��B1889�N�A�V�g���^��[�������߂�悤�ɂȂ����s�n���H�̑g��]���ے����郍���h����h�b
�N��X�g���C�L���N����B������x�����āA���v��Εv�̓s�P�b�e�B���O��f���s�i�ɎQ�����A
NAS&FU�͑��z�̊�t���W�߁A���̐����Ɋ�^����B���������Ȃ��ŁANAS&FU�̓���������
�����߁A���Ȃ�I���ǂ܂�Ă��邪�A�g��������1889�N���ɂ�60,000�l�ƂȂ�B
�D�傽���͍ŏ��A�E�B���\���̑g�����Ă������A����ɖ��S�ł͂����Ȃ��Ȃ�B����
�ɁA1870�N�㔼����A�k���C�݂ł͑D��g�D���ݗ�����Ă����B1890�N�ɂȂ��NAS&FU
�ɑR���邱�Ƃ�ړI���āA���o�v�[���ɂ����Čٗp�ҘJ������A�����ă����h���őS���g�D
�̊C�^�A��(the Shipping Federation)���ݗ������(���o�v�[���̋���́A1967�N�܂ŁA����
�ɉ������Ȃ�)�B�����g�D�̖ړI���i�ɂ��āA�D�厩�g�̌��t���܂ތ������A��������
���A���p���������B
�@��C�^�A���ɂƂ��āA����̑g�D���������i���u���ĕ��X�ɂȂ�܂Ŕj�A���̋��Ђ�
�I�~����ł��ƈȊO�ɁA���̖ړI���Ȃ������B���̎�Ȏ�i�́w�C�^�A���x�ƃX�g�j��ł�
�����B�O�҂����ĂA�D���͊C�^�A���̉����D��ɗD��I�Ɍٗp����邪�A���̌��Ԃ�Ƃ�
�Ĕ�g�����ƈꏏ�ɓ������Ƃ���ꂽ�B�܂��A���́w�r�玆�̏؏��x�������Ă���A
���a�Ȃǂ̍ۋ��t���鎑�i���������B�w�D���g�����s�̏ؖ������Ȃ���Γ������Ƃ͂���
�����F�߂�ꂸ�A�܂��D�����ؖ������쐬���Ȃ���A�C�M���X����o�`����D�D�ɏ��g��
���Ƃ͋�����Ȃ��B�����������Ƃ͉��\�Ƃ����邩������Ȃ��B���̍l���͊m���ɑe�G�ł���
���A�����ł��邩�炱���͂���������B�����̑g���Ɠ����悤�ɁA���������\�Ɉ�����
���B���ɁA�����ɑR������@���Ȃ���A���\���D�ꂽ���̂Ƃ�����x[�D�厩�g�̌�
�t]�B�ǂ̍`�ł��A�X�g���C�L�͂����ĂȂ��قǖ��c�ɉ����Ԃ���Ă������B����͘J�g�푈
�̂悤�ɂȂ����B�c�c�w���R��g���x�͑S�����ǂ����͂Ƃ������A�肪���₩���_���g���āA�X�g
���C�L�D�ɏ�荞�݁A���ɂ��悤���Ȃ���Ζ\�͂����ӂ�����B����ɑg�������A�����悤��
�R�����B�c�c�E�B���\���̑g�D�́A���������ҍU���Ɋ����邾���̗͗ʂ��Ȃ������(31�߰
��)�y3�z�y4�z�B
�@�������������ɔ�����D����������A�吨�Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B�C�^�݂̂Ȃ炸�A�ʎ��{
���J���g���𐧓x�I�ɔF�m���Ȃ����ƂŁA����ɑR����ꍇ�̑ԓx����@�̌��^���݂�v
���ł���B������������Ύ�r����i�́A�C�^�A�����g����F�m���A�E�B���\���Ƃ̋������i
�ނȂ��łȂ��Ȃ�B�������A���Ŏ��グ���Ă���P&O�t�F���[�����ɍۂ��āA��ʂ̃X�g�j
��ƒc�̌��̉�����݂���悤�ɁA����ɂ����Ă��A����炪�����ĂȂ��Ȃ����킯�ł͂�
���A���{��`�̊�@�̂��Ƃł́A���ꂪ���ۓI�ȘJ���͂̓���ւ����Ȃ���A�Č����Ă�
��Ƃ�����B
�@�Ȃ��A���{�̑D��g�D��1892(����22)�N���{�C�^�Ɠ������Ƃ��A���ꂪ1920(�吳9)
�N�ɑ��Ƃ��܂ޓ��{�D�勦��ƂȂ�B�C�M���X�ɔ�ׂ�A���{�̑D��͑D���̑S���g�D
�����������O����A����ɐ���ł`�Ŏ���̑g�D���������Ă������ƂƂȂ�B
3)�@NAS&FU�̔C�Ӊ��U
1890�N��ɓ���ƁANAS&FU�͊C�^�A���̍U���̂��ƂŁA�X�g���C�L�͎��X�Ǝ��s���Ă����A
�E�B���\���̐l�C�͒ቺ���A�g��������1893�N�ɂ�15,000�l�Ɍ�������B�����āANAS&FU��
�ٔ��Ɏ�荞�܂�A���̍����͕N�����Ă����B���ꂪ�֑�Ɏ��グ���A�E�B���\���͂���
�G�Ύ҂���A�g�����̗��v�ɂȂ�Ȃ��X�g���C�L��g�D���āA�����G�c�Ɏg���͂����Ă���
�Ɣᔻ�����悤�ɂȂ�B�����āA�s�@�W��Ɩ\���̗e�^�ōS�����ꂽ��A�E�D�����������
���邢�͖��_��ʑ������Ƃ��āA�����Y���o�����B1893�N�A����C�^��ЂƏ��Ǝ��̍��i��
��Â��ANAS&FU�ɔj�Y�鍐�A�����ăE�B���\���ɍ���藧�Ă̗ߏo�����B
�@�����ŁA������́A���_����J���g�������҂��獐�i����A�����I�ɉ��U�������
�āA���̉^���ɒv���I�Ȕ�Q���o�邨���ꂪ���炩�ƂȂ������Ƃ��A�F�߂�������Ȃ��B���
���́A�G�̋@��𐧂��āA1894�N�O���[�g��u���e����A���h��A�C�������h�S���������Εv�g
����C�Ӊ��U���飂��Ƃ����ӂ���ɂ�����(35�߰��)�B
�@�����������ނ�NAS&FU�����ł͂Ȃ��A���Ȃ�̐V�g���ł��݂�ꂽ���A���̌����ɂ��āA
�D�傽���̑g�D�������拭�Ȓ�R����łȂ��A���Ȃ葽���̂��Ƃ��w�E����Ă���B������
�������ĉ������B�܂��A�����̎���Ƃ��ẮA��V�g���̃��[�_�[�������A����̑g�D�̐���
�X�s�[�h�ɂ��Ă������Ƃ�����ł������B�g�����s�����͈��Â��ŌP�����ꂽ�ɂƂǂ܂�A
���������ĊǗ����@���Ԃɍ��킹�������Ƃ���ł������B�c�c���������ӔC�Ɋ����A�L���ȑg
�D�^�c���s�Ȃ���l���͂킸�����������Ȃ�������BNAS&FU�̎���Ƃ��ẮA��C�^�Y�Ƃ�
�́A���Y�Ƃ̂悤�ɍH�꒷�Ən���H�g���Ƃ̂������ň��̊W������Ă��Ȃ�������
�߁A�ٗp�҂̔����͉ߕq�ŁA�Ë��̂Ȃ����̂ƂȂ�����B�܂��A����ɁA�D���̑g���͑��̑g��
�Ɣ�r���āA���̐E�Ƃ̓��ꐫ����A�����̃t���^�C���E���������������Ȃ��_�ŁA�s����
����ɂ������B��������������̗p����ƁA�����������Ƃ����������肷����Ƃ��������R
�����ŁA���ق��邱�Ƃ͕s�\�ł������(33�߰��)�B
�@�����������s�����ɂ��āA�E�B���\���͂��̎���ᔻ����ƂƂ��ɁA����炪��w���Ȃ��̑D
���ɁA�N������Ȃ��A����������Ƃ���n���~�όW�x�ɂȂ��Ă���B�����āA�g���x���͍ŏ���
���p�̂����鑛�������A���Ɏ�荞�܂�A�c�c�����g�������Ă�����Ƃ��Ă����B����������
���ƂȂ������Ƃɂ��āA�������F�߂Ă���悤�ɁA�g�������͒����Ǘ����Ȃ��Ƃ����A����
�̍l�����Ђ����Ă����(32-33�߰��)�B�����������_�́A���݂ɂ����Ă������ł͂Ȃ��B
�m���n
�@�y1�z�@G.D.H.�R�[���w�C�M���X�J���^���j�x�Q�A153-154�߰�ށA��g���X�A1953�ɂ́A�v�����]
���̋c��������Ȃ�ڍׂɏЉ��Ă���B
�y2�z�@�R�[���O�f���Q�A185�߰�ނɂ����āANAS&FU�͐V�g����`(�^��)�̍ċ��Ƃ����傫��
����̂��ƂŌ������ꂽ�ƂƂ炦���Ă���B
�y3�z�@�C�^�A���̗��j���Ƃ��āA L.H.Powell, The Shipping Federation �@1890-1950, 1950��
����A���̏�����a�V����w�C�M���X�ɂ�����J���W�j�x�A�^�A�ȑD���ǁA1952�ł�
��B
�@�y4�z�@�y�����O�O�f���A124�߰�ނɂ́A�C�^�A���̍D��I�Ȑ��i�Ƃ��̗��p���_�@�ƂȂ���
�ݗ����ꂽ�E�B���A����R���\���̎��R�J���ҋ���ɂ��āA��A�ڂ����Љ��Ă���B
�@3�@�g���̍Č��A�S���X�g�A�D��̑g���F�m
�@���3�� �g���̍Č��ƐV�n�� 1894-1911��́A�E�B���\�����g�����Č����A���ۑg�D�̌���
�Ɏ�g�݁A1911�N�̑�X�g���C�L�𐬌������A�����ʂ��đD�傽���ɁA�S�����Εv�g��(
the National Seamen's and Firemen's Union of Great Britain and Ireland�A�ȉ� NSFU�Ƃ���)
��F�m������ߒ��A�����ă��C�o���g���Ƃ̍R�����L�q����Ă���B�����ł́A�g���Č��̎d
���A�O���l�D�����ƍ��ۑg�D�A������1911�N�̑�X�g���C�L�̌o�߂ɂ��Ď�グ��B
1)�@�g���Č��A�����̒����Ǘ�
�@NAS&FU���ǂ̂悤�ɉ��U����ANSFU���ǂ̂悤�ɐݗ����ꂽ���́A���łɒm��悵���Ȃ���
�������A���ꂪNSFU�Ƃ���1894�N���ďo�������悤�ł���B����ɓ������āA�E�B���\���͎�
�s�̐��̍ĕҐ����s���Ă���B�g������ ���� 5,000�l�������ԂƂȂ��Ă������Ƃɉ����āA
�O���ȊO�̎��s�ψ�20�l����8�l�ɁA�S����7�̒n��ɕ������A���ꂼ��̒n��̎x����
����2����7�ɏW�A�܂����ꂪ�ᔻ���Ă�܂Ȃ������n�����s��������ߏo���A���s
�������w�����錠����g���������悤�ɉ��߁A����Ɏ��s�����͑g�����ɑ��ĐӔC��
�킹�邱�ƂƂ����B�����āA�g�������͒����ŊǗ����邱�ƂƂ����B
�@�����������v�́A��ʂł͋ߑ�I�ȑg�D�ɍ��ւ��悤�Ƃ������̂ł͂��������A���ʂł͂�
��̑g�����Ƃ��Ă̌����������߂悤�Ƃ������̂ł������B����́A���̌�ɂ�����g����
���̓������ʑg�����Ƃ̑Η��̗v���ƂȂ��Ă����B�Љ�J���^���̑g�D�ɂ����āA�����W
�����͕K�v�s���ł͂����Ă��A�����ɑg�������`���т���Ă��Ȃ���A���ꂪ�g����
���̓ƍق��邢�͊������ւƓ]�����邱�Ƃ͔������Ȃ��B�E�B���\���́A�g���Č��ɂ�����
�āA���������z��������قǂɂ́A�J���^���͐��n���Ă��Ȃ��������A���̗]�T���Ȃ������ł�
�낤�B
�@���̍Č����ꂽ�g�����؋��܂݂�ŁA�E���̒����͖������A�ƒ��͑ؔ[�A�ŋ��͖��[�A�g
�����͋����Ȃ��Ȃ��ăj���[���[�N�ő��~�߂�H���Ƃ�������Ԃ������B�����āANAS&FU�̐�
�ނ̂��ƂŁA���C�o���g�������܂ꂽ��A�g���̕��N����A�Č���A�����Ƃ̍R���ɂ�
������킳��邱�ƂƂȂ�B�g�������������ɉ��Ȃ��������A1910�N�ɂȂ�Ƒg�D�Ώ�90,
000�l�ɑ��ď����Ȃ̐�����12,000�l�ƂȂ�B���̈���A�C�^�A����NAS&FU�����|������
�ƂŐM�p�����܂�A������⎑���ʂ������A��v36�`�ɓo�^��������u���A�X�g�j�������
�������ł���̐��𐮂��Ă����Ƃ����B
2)�@�O���l�D�����ƍ��ۑg�D
�@�E�B���\���́A�g���ݗ�������A�O���l�D�����ɊS�������Ă����B�C�^�A�����͂���
��Ȃ��ŁA�D�傽���͊O���l�D���̌ٗp�����炷��葝�₷�悤�ɂȂ����B���̖��ɑ���
�����̂���̍l���́A�O���l�D�����������J���͂Ƃ��ċ�������A�܂��g�����̔z���j
�~���鐭��̋����̎�i�Ƃ��ė��p����Ă��������A������͂킪�g���̉��Q�҂ƂȂ��Ă�
��Ƃ�������Ƃɂ�����(50-51�߰��)�B���̌�A�l�������߁ANAS&FU��1889�N����A���ꂪ�x
����ꂻ���ɂȂ��Ƃ킩���Ă��Ȃ���A�C�M���X�D�ɏ��Ȃ��Ƃ�2�N�ԋΖ������O���l�D���̑g
���������20����ނƒ�߁A���̑g�D���Ɏ�g�ނ悤�ɂȂ�B�^�U�̂قǂ͖��炩�ł͂Ȃ�
���A1891�N�ɂ͊O���l�g������20,000�l�ɂȂ��Ă����Ƃ����B
�@���̏�ŁA�E�B���\���́A����Ţ�C�M���X�D�Ɍق���O���l�D���̐��Ǝ����K�����Ă���
���s�@�K������ɋ����A�g�[���ׂ����ƁA��Ɉӌ���\�����Ă����B���ɁA�D�傪�O���̍`��
�C�M���X�l�D�������ق��A���̑���Ƃ��Ē�����̊O���l��g�����ٗp���鈫�K��A�D��
���C�M���X�l�D����舫�������Ń��X�J��[���C���h�l�̑���]���̗p�ł���悤�ɂ��Ă���C��
�h�C�^�@��p�~����K�v���������Â�����B����ɁA�����ŁA��O���l�D���́A�C�M���X�l�D
���ɂƂ��đ傫�ȍЂ��̌��ɂȂ��Ă���Ǝv���Ă������A����͂��ȍl���������Ƃ킩�����B
���N�ɂ��킽��A�`�����X���Ă����B���܂ł́A�O���l���C�M���X�l�Ɠ����悤�ɁA���̐���
�������Ă䂭�������������Ă��邱�ƂɋC�Â�����Ƃ���(51�߰��)�B
����ɑ����āA�E�B���\���͑g���Č���A�����Ă������ێx�����ĊJ���A����ł�NSFU��
���ۓI�ȉe���͂����߁A�����ł͊O���̑D�����g�D����邱�Ƃ��������邽�߁A���ۊ�����
��O����悤�ɂȂ�B���̏d�v�Ȃ��Ȃ߂Ƃ��āA1896�N�A�E�B���\���̌Ăт����̂��ƂŁA����
�^�A�J�A( the International Transport Workers' Federation�A�ȉ��AITF)�ɔ��W�������J
�����B����́A�E�B���\���̍l���ɂ��������āA������̈����グ�ƘJ�������̉��P�̂���
�ɁA�D���A�`�p�A�͐�̘J���҂�S���A�g�D���邱�ƂɑS�͂��X����B�����āA���ׂĂ̍`��
����̘J���҂ɂ��āA�\�ł���Γ��������ݒ肵�A����ɐ��E�e�`�ɂ����ĘJ������
���Ȃǂ̋K�����m�����邱�Ƃ�ڎw�����Ƃɂ������(52�߰��)�B�������A���̏����ƂȂ���
�V�g���^���̎w���҃g����}���Ȃǂ́A���ێЉ��`��O�i�����悤�Ƃ��Ă����B
�@�E�B���\�����A�O���l�D�����ɂ��čl�������߂����Ƃ́A���M�ɒl���悤�B���̐��ʂ́A
�����̃X�g���C�L�̐����̌��ƂȂ�AILO�̍Œ��������J�����Ԑ��̌_�@�ƂȂ邪�A���̖{
�i�I�ȉ����͌��݂܂Ŏ����z���ꂽ�܂܂ł���B
3)�@1911�N��X�g���C�L�̐���
�@�E�B���\���́A���N�����āA�C�M���X�����݂̂Ȃ炸�A�A�����J�A���[���b�p�����ɏo�����āA
���ۃX�g���C�L���Ăт����ĉ���Ă���B����́A��������̓��������ɍs�Ȃ����̂Ƃ��A�c�̌�
�̌����Ɠ���������A�D���A�J�����̊m���ɂ��āA�g���������Ɋm�F����܂łÂ�
�飂Ƃ������̂ł�����(52)�B�߰�ނ�����Ƃ���ŁA�M���I�Ȏx�������Ƃ����B����ɂ���
����炸�A�E�B���\���̍��ۍs���ɂ��āA�C�^�A���͂��ꂪ�s������̂ł͂Ȃ��Ƃ��āA�x
�����������Ȃ������Ƃ����B
���̃X�g���C�L�̌o�߂����ǂ�A1910�N7���ɗv�����D��ɏo����邪�A�C�^�A���̓E�B
���\���̗\�z�ʂ�A�����悤�Ƃ����Ȃ������B���̗v���́A��S���Œ�����̐ݒ�A�b�¥�@
�֥�i�~���̏�g������̊m���A�C�^�A��������I�Ɏw��������҂ɂ�錒�N�����̔p
�~�A�C�^�A���������ł̌ٓ��ꎖ���̔p�~�A���`���ɕ�����������錠���A�_��
�㗝�l�𗧂���킹�錠���A�J�����Ԑ��Ǝ��ԊO�蓖�̊m���A�D�Z�{�݂̉��P�ł���
���B1910�N7���A��100�l�قǂ̉��@�c����NSFU�̊�����A��āA�S���ϔC�c�Ƃ��ď�����
�b�Ɩʉ�Ă���B��b�́A���̗v���̎戵����@�ւɈς˂邱�ƂƂ����(54�߰��)�B
NSFU�́A�e�n�ő�O�W����J������A����ܐ���z������|1911�N6��14���|�D���̃X�g
���C�L�͋��ł��|���R�̂��߃X�g���C�L��ł���������Ƃ���������D���Ƃ��������f����B��X
�g���C�L�͖�̂悤�ɁA�C�M���X�̍`�����͂B�X�g���C�L���T�U���v�g������e�`�Ɋg��
��͂��߂�ƁA�D�傽���͏������͂��߂�B���ꂪ���̍`�̃X�g���C�L��������A�܂��ٗp�҂�
���ӂ�݂点�邱�ƂɂȂ������(58�߰��)�B��E�B���\�������M�������Ă����ʂ�A2�T�ԉ߂�
��ƑD���e�n�̋���͎��X�ƒ��グ��F�߂邱�ƂŁA�X�g���C�L�����߂�悤�ɂȂ����B6��
28���ɂ́A��100�Ђ̑D�傪�����h���ɏW�܂��āA�e�`�̕W��������ݒ肷�邱�Ƃ����肵��
���飁B�����āA�1911�N11��17���A�C�^�A���͑�\�҉�c���J���A�wNSFU�����F���邱�Ƃ͌_
��̎��R�ɂ��Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�܂����v��Εv��g�����A��g�����̕ʂȂ��ٗp���邱�Ƃ�
�W������̂łȂ��x�Ƃ������_�ɒB���c�c���ɁA���̑g���͌��R���鑶�݂ƂȂ�A������������
�ɏI�~�����ł���飂��ƂƂȂ�(57-58�߰��)�B
�@���̑S���I�ȃX�g���C�L�̐����ƊC�^�A����NSFU�F�m�̔w�i�ɂ��āA���҂͓��ʂɐ���
���Ă���킯�ł͂Ȃ����A����Ţ�m���ɂ����邱�Ƃ́A�J���͕s�����݂�ꂽ�Ȃ��ŁA�X�g��
�C�L���}�����L�͈͂ɍs�Ȃ�ꂽ���Ɓc�c���̓��������ׂĂ̍`����ۂƂȂ��āA������
�����Ɏ��{���ꂽ���ƣ(60�߰��)�A�����Ģ1911�N6������N���܂łɁA�D����`�p�œ����J��
�҉���27���l�����ځA���̑��c�ɎQ�����Ă�������Ƃ��グ����(56�߰��)�B
�����ŁA����R�J���҂��\�ɗp�ӂ���Ă����͂��ł��������A����͌֒��ɂ����Ȃ���
������ƁA���{������s���@�ւɂ����Ģ��Ë��I�ȑD��ƑΌ����Ă���J���g���ɓ���
�݂��A�D��̂Ȃ��ɂࢎ��{�ƘJ���͓G������A�������������Ƃ���ƍl���飂悤�ɂ�
���Ă������Ƃɂ���(60�߰��)�B����̐Ϗd�˂Ɨ͂̌��W�A�����Ď���̗���ɂ��������ƂŁA
���������Ƃ����悤�y1�z�B
�@�Ȃ��A��O���{�̊C���g���̑呈�c�́A1928(���a3)�N�̎ЊO�D�[�l�����X�g���C�L�ł���
���A���̂Ƃ���q�̓��{��NMB(�C��������)�ɂ�����c�̌���ʂ��āA���ʑD���W������
���z������l�����Ă���B���������S����������́A����Ȃ�̎d�|���Ȃ����Ċl�������Ȃ���
�Ƃ�m�肤��B
�m���n
�@�y1�z�@�R�[���O�f���R�A97-99�߰�ނɂ́A1911�N�X�g���C�L�̌o�߂��Љ��Ă���B��@����
��`�ł̘J���g�������۔F�������Ă����C�^�A���́A�C���̒c�������F���邱�Ƃ�[�D����]
�K�����낤��������̂ł���Ƃ̌����̉��ɁA�����̗v���ɂ��ē��c���悤�Ƃ������Ȃ���
���B�g���́A�c�c�S���X�g���C�L��錾�����B�������o�ʒ��ɁA�S���̎�v�ȍ`�s�́A���̔�
�Ƃɂ���Ėw��Nj@�\���������B�D�傽���́A�c�c�g�D�I�ɃX�g���C�L�j��̘J���҂ɗ����
��������ŏ�ɑΏ����ė������A���̏ꍇ�����l�̎�i�ł����ؔ����悤�Ƃ����B�c�c��Ƃ�
���B
�@�Ȃ��A�����̒���ɂ����āA1911�N�X�g���C�L��������Ă��邪�A�E�G�b�u�O�f�������A586
�߰�ނɂ݂�悤�ɁA���ꂪ�����h���`�p�J���҂̓����̉��������ƂƂ̊֘A�Ŏ��グ��
��Ă���̂��A�قƂ�ǂł���B
�@4�@�E�B���\���̎w���H���A�펞NMB�̐ݗ�
�@���4�� ��ꎟ���E���ƊC�������́A�E�B���\���̓X�g���C�L�𐬌���������A���x�d
���ɓ]�����A���p�ȑ��c��������A�C�^�A���ɒc�̌����x�������悤����������A
���ꂪ��ꎟ���E���ɂ�����NSFU�̋��͂��m�ۂ���K�v����A�C��������(the National
Maritime Board�A�ȉ��ANMB)�̐ݗ��Ƃ��ĒB�����ꂽ���Ƃ��L�q����Ă���B�����ł́A�E�B��
�\���̘J���g���^����J�g�W�ɂ��Ă̍l���ƁA��1�����E���̂��Ƃł̊C���������
�ݗ��ɂ��Ď�グ��B
1)�@�Ό��d�����A���x�d����
�@1911�N�ɁA�g����}����V�g���^���w���҃x����e�B���b�g�����������S���^�A�J���ҘA����
���N�A�S���^�A�X�g���C�L�ɓ���BNSFU�͑g�����̈�ʓ��[�ɂ����āA����ɓ������邱��
�����߁A�X�g���C�L�ɓ���B�������A�X�g���C�L�ɓ����Ă���g���̃��[�_�[�͎v���v���œ�����
�����B�����ŁA�E�B���\���́A���̒��~���Ăт�����������Ȃ������B����ɁA1913�N�A�A�C����
���h�^�A��ʘJ���g���̃X�g���C�L���N����B����̓T���f�B�J���X�g(�}�i�I�g����`��)�W�F
�C���Y����[�L���Ɏw������Ă������A���̉ߌ��ȉ^���̂�����͑��̑g����������x����
�����B
�@�E�B���\���́A���Ƀ��[�L���Ȃǂ̍D��I�Ȃ����ɂ��āA���̂悤�ɔᔻ���Ă���B�����
�������ɘJ���g���^���̐��ۂ��ς˂Ă��܂��Ă���l�X�́A����犲���̐ӔC�̏d�傳�ɂ�
���āA���ꂱ�ꔭ�����邱�Ƃ������Ă��A�q�����݂����������݂�����������Ȏg�k�̌�����
��ɂȂ�A�y�͂��݂Ȍv��̂��Ƃő�����ɂȂ��Ă��A������d�����Ȃ������Ǝ������g����
���Ă��܂�����B��J���w�c�̈�悪�������ƁA�S�̂��キ�Ȃ��Ă��܂��B�������A�������̕�
��łƂ��Ă����O���킵�������ɁA���ׂĂ̕������������܂ꂱ�Ƃ͗ǂ����Ƃł��A����
�����Ƃł��Ȃ��B�c�c���[�_�[�Ƃ������̂͂��߂�킸�Ɍ��f������A�܂������Ɉ�����������
����l�X�ƁA�K�v�ɉ����Ď���ׂ��ł���B����́A���̓������s�ꂻ���ȏꍇ�����ł�
���A�w���݂̏�Ԃ���ނ��邢�͊댯�ɂ��炳�ꂻ���ȏꍇ���܂܂��x�(67�߰��)�B
�@�����������s�̂������A�1913�N�ɖڗ����đ��������g������ی�A�ێ����邽�߁c�c�E�B
���\���ȊO�̃��[�_�[���A�ٗp�҂ƍ����Œ��⥒��ً@�\������āA�e���ȊW����茋�Ԃ�
����ɂȂ��Ă����B����́A�E�B���\���ɂ����ẮA���ꂪ��ЂƂ�̘J���g�������ƂƂȂ�����
����������Â��Ă����l�����ł������B����́A�ٗp�҂��邢�͘J���g���̂ǂ��炩����
�p�̎d�g�݂�����I�Ɏx�z����̂ł͂Ȃ��A�o�������钲��@�\��ݗ����āA�ٗp�ƘJ����
���A����ɂ͋x�ɁA�����ĉݕ�����q�^���܂ł��A�����Ō��肵�Ă������Ƃ�����̂ł�������B
���Ȃ킿�A���p�҂̑�\�ƌٗp�҂̑�\�ɂ��c�̌����m�����邱�Ƃɂ������B���̂���
�ɂ́A���͂ȑg���Ƌ��͂Ȍٗp�҂̑g�D���K�v�ƍl���Ă�����Ƃ���(59�߰��)�B
�@���������l���́A����ł݂��悤�ȗ��j�ɖ����c���A��V�g����`�̎句�҂�T���f�B�J��
�X�g�̋��c������Ɏ��������̂ł͂Ȃ������B���҂ɂ��A������́A�o�������
�͂����������}���҂ƑΌ����āA���̌��͂�œ|���邱�Ƃ�ڎw���Ă����B�����āA������
�ŏI�I�Ȍ��Ђ͑g�����ɋA�����Ă���ƐM���Ă�܂Ȃ��������A�����ɑ����Ď��{�Ƒł�
���������Ęb�������A�Ë�����Ƃ��������Ƃ͍l�����Ȃ����Ƃł������(67�߰��)�B
�@20���I�ɓ���ƁA�J���g�������肵���g�D�ƂȂ�A���x�I�ȑ��݂ɂȂ�ɂ�āA�g������
�̎w���H���̈Ⴂ������ɂ����ɂȂ��Ă���B���łɂ݂��^�A�J���҂̃X�g���C�L�́A����
�̑Ό���`�҂̈�l������A������̑g�D���Ⴍ�Ď�̂ɂ�������炸�A�₽�狭����
�Ă݂��ɂ����Ȃ�������Ɣ��Ȃ��Ă���悤�ɁA�J����O���畂���オ���Ă����B�����A����
�`�҂͂��̓꒣��ɂ����āA����Ȃ�̐��ʂ��グ����Ɏ���ɖ������A���ꂪ�J����
�O�Ƃ̍a��[�߂邱�ƂɂȂ�Ƃ͎v�������Ȃ��������ɂ݂���B���̎��_�������Ďw���H����
�Ⴂ�����g�������̘A�т͏I���B����ɓ������āA�E�B���\���͑����ɁA���x�d����
�H���ɓ˂��i��ł䂭�B
�E�B���\���́A�X�g���C�L��g�D���邩�����A���ł�1910�N����C�^�Y�Ƃɂ�����S���J�g
�@�\���Ă��Ă������A1911�N�X�g���C�L�𐬌�������ƁA����ɂ��̎��M��[�߂Ă������B��
�̎��M�́A����̒�Ă������J���I�ȑD�傪�������邱�Ƃɂ������B�������A����
��l�̃����V�}��(�D���A�D��A���@�c���A����)�������悤�ɁA������D��Ɋ��x�ƂȂ��A�E�B��
�\���Ƙa������悤�����������ʁA�����̐l�X�������v���悤�ɂȂ������A�C�^�A���ɂ͑S�̂�
���ĕΌ������т���Ă���A��\�҉�c�̓E�B���\���Ɠ������߉�100������ނ��Q��Ă���
�ɂ�������炸�A�����F�m���邱�Ƃ�����ł����(68�߰��)�B�������ANSFU�̑g���������A
1912�N�g�D�ΏۑD����3����2�ɓ�����71,000�l�ɂ��Ȃ�ƁA���͂△���ł��Ȃ��Ȃ�B
2)�@�푈�ɂ��Ë��̎Y���ANMB
�@1914�N8���A��1�����E��킪�u������B�����ɁANSFU�͊C�R�Ȃ����p���邢�͗p�D����
�����D�̔z��ɂ��ċ��͂��邱�ƂƂ��A�����ȂƂ̂������Ŋo�������ԁB�������A�l�W�߂�
������A���x���E�D���N����B1915�N�ɂȂ�ƁA�C�R�Ȃ͢���v�͂��������D����
������̂́A���̒���ɉ��D���Ă��܂��A�o����x�������Ă���c�c�A�������v���肩�A�D
���̋K���ᔽ�ɂ���Ē���A�퓬���W�Q����Ă���B�����ŁA���D���̑S�D���������C�R
�̗\�����ɒ��p���āA�C�R�̋K���ɂ������킹�邱�Ƃɂ�������ƒ�Ă��Ă����B����ɑ�
�āANSFU�͢�D���̈����S�ɉ����𒅂�����̣�A�����Ģ�s��������������D���A�Œ��
������������ꂽ�A����[�ߐ��C�R��]�D�������������K�z�́w�Q��D�x���v���N������
�飂Ƃ��Ċ拭�ɔ����A�����P����(78�߰��)�B
�@�����A�D�������͊J�펞�A�C�R�ȂƂ̋���Ō�1����ނ̈��グ�͂��������A������܂މ�
�P�͒x�X�Ƃ��Đi�܂Ȃ������B����ɑ��āA�C�^�A���͢�D�傽���͂�������҂��ł��邪�A
�����~�����킯�ł͂Ȃ��B�ߋ�2�N�Ԃ����������̂ŁA����ߍ��킹�Ă���ɉ߂���
����Əq�ׂĂ���(78�߰��)�B����ł��A�D���̎����ɑ���N���A���J���A�⑰�⏞��A�D��
�S�������ꍇ�A1���������܂��̓C�M���X�ɋA������܂œ�����v�Z���������́A�����ꂩ��
���������A�܂��⎸�i�̕⏞�������錠�����A���Ƃ��m������B
�@1917�N�A�A�����J�����ɎQ�킷��ƁA���̊��J�g�͗L�\���v����щΕv�ɑ�����ृ{�[
�i�X��1����90��ق܂���18����ނɈ��グ(�C�M���X�D�ł́A10�����)�A����ɃA�����J�̍`�ɓ�
��O���D�ɏ�D���Ă���D���ɑ��Ģ���D���錠�����F�߂��B����ɂ��A�A�����J�̍`��
�������C�M���X�l�D���͑勓���ĒE�D����悤�ɂȂ����B�C�M���X���{�́A�J��Ɠ����ɁA�C�^
�Y�Ƃɂ����鋦�c�@�ւ�ݒu���Ă������A���ʂ��Ȃ������B1917�N8���ɂȂ��āA������ݍ�
�܂�������Ȃ��Ȃ�A�C������ψ����ݗ����邪�A����͒����ɂ͓������Ƃ͂��Ȃ������B��
���낪�A���o�v�[���Œ��グ��v�����Ē�D���͂��܂�ANSFU�̓������鐨�����݂��͂�
�߂����߁A������ψ���͓��ʂ̒��グ�ƑS�������̐�������������Ȃ��Ȃ����B��
���āA���N11���ɂȂ��āA�C��������(NMB)���ݗ�����邱�ƂƂȂ�B
�@����̋@�\�̖����́A�����̗\�h�ƒ��ق���ѕW�������̐ݒ�ƌٗp�̋K���ɂ���Ɩ���
�����ꂽ�B���̋c���A���c���A�����ǒ��́A�C�^�ė����Ƃ��ꂼ��̃O���[�v�|���v��Εv�A
�@�֎m�A�q�C�m�A��������i�~���|�̓K�i�g�D�̑�\����w������邱�ƂƂȂ����B�c�c�C��
������́A�`���ɁA�J���g���ƊC�^�A�����w������n���������z�u���邱�ƂƂ����B����
�E���́A�J��������K�Ɋm�ۂ��A�e�D�̏o����x�������Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃɂ������B����
���A�����̖{���̎d���͕��c�����߂邱�Ƃɂ������B�w�ӌ��̕s��v�╴�����������ꍇ�A
�n����������邢�͕K�v�ȏꍇ�A�n���܂��͒����̊C��������ɏƉ�s�Ȃ��A���̏�
�����R�������܂ŁA��ƒ�~�͍s�Ȃ�Ȃ��x�B����ł��������Ȃ��ꍇ�A�Ō�̎�i�Ƃ���
�C�^�ė����ɏƉ���o�����Ƃ��ł��邪�A���ꂪ���������ق��J�g�����ӂ��Ȃ�����L���Ƃ�
�Ȃ��Ƃ��Ă����(83�߰��)�B
�@���̐펞NMB�́A����1919�N�ɘJ�g�̔C�Ӌ@�ւƂ��Ă�NMB�ɕς�邪�A���̐����ɂ�
���āA���҂͢NSFU�ƊC�^�A���Ƃ̂������ɋ��͊W���������B����̓E�B���\���ƘJ���g��
�̓w�͂̂Ȃ���Z�ł�������Əq�ׂĂ���(83�߰��)�B�����������ƂƂ��ɁA�푈�Ƃ�����@�̂���
�ŁA���{���J�g�Η���������悤�Ƃ��āA����ɉ������������Ȃ��������Ƃ����ڂ̌_�@�Ƃ�
��A��������������Ȃ������̂�NSFU�̗͂ł������Ƃ����悤�y1�z�B
�m���n
�@�y1�z�@���� ���w�C�M���X�Y�ƕʑg�������j�|�S���J���g���𒆐S�Ƃ��ā|�x�A�~�l�����@��
�[�A1971�ɂ́A�S���J�g�W�ɂ����Ă��A�������ANMB�Ɠ��l�ȋ@�ւ��ݗ����ꂽ���Ƃ��L
�q�������B
�y2�z�@�A������n�b�g���A���c�����q��w�C�M���X�J���^���j�x�A130�߰�ށA���_�Ђɂ́A1928
�N�̘J���g����c(TUC)���ɂ����āA���̑��]�c�TUC�ƌٗp�҂Ƃɂ��S���Y�Ƌ��c
��Ƌ����ٔ����̐ݗ��Ɋւ�������Ă������ƂɊ֘A���āA�����́A�̃n���@���b�N�
�E�B���\�������D�����{�̗����傳���A�C���ɂ����������e�Ղɂ��邽�߂Ɉďo��
���A�U����p�g����`�Ƃ����I���Ȑ��x[NMB�̂���]���A��ʂɂ����Ђ�߂悤�Ƃ�����̂̂�
���ɂ݂�����Ɖ�����Ă���B
�@5�@1906�N�C�^�@�����Ƌc���E�B���\���̗���
�@���5�� �n�x���b�N��E�B���\���ƘJ���^�� �P��́A�E�B���\����20���N�ԁA���@�c���Ƃ��āA�c
��ɂ����đD���@���̉��P�ɓw�͂��A�����A�J���}�ɎЉ��`�̉e�����y�Ԃ��Ƃɔ�����
�Η����A�����đ�1�����E���ɂ����Ĉ����h�^����i�߂����Ƃ��A�L�q����Ă���B������
�́A�c���E�B���\���Ƃ��Ă̐��ʂł���C�^�@�����ƁA�c���E�B���\���̓��قȐ����M���ɂ�
���Ăӂ��B
1)�@1906�N�C�^�@�����̓w��
�C�M���X�̑D���́A�c��ɂ�����D���i��҂Ƃ��Ă��łɂ݂��v�����]�������ł������A
���ꂪ���ނ���ƃW���Z�t��`�����o�����ɕς���B�����āA1890�N�ォ��́A�E�B���\������A
�D���̋c���\�ƂȂ�B�E�B���\�����A�ǂ̂悤�ȓ��@�ʼn��@�c���ɂȂ낤�Ƃ������́A���炩
�ɂ���Ă��Ȃ��B����́A1890�N�̏�����ɂ����闎�I�ȗ��A1892�N�̃~�h���Y�u���ł̏���
�I�A1922�N�̃T�E�X�V�[���Y�ł̗��I�܂ŁA�~�h���Y�u������Y���[�X�A�T�E�X�V�[���Y�I
�o�̉��@�c���Ƃ��āA5�I���Ă���B�Ȃ��A���̊ԁA1��̗���⎫�ނ�3��̗��I������
���B
���������ł������W���Z�t��`�����o�����́A��o�[�M���K���̎��ƉƂ��琭���Ƃɓ]�g����
�����̂ŁA�v�����]���̂悤�ɁA�S�̒ꂩ��Љ�`�������オ��Ƃ�������ɂ͂����Ȃ�
��������A�C�^�W�@�̉����ɓw�͂��Ă���(92)�B�߰��1880�N�ɂ͈��S�Ȑςݕt�����m�ۂ�
�鍒���ϕt�@�A�����O�n�̔p�~�Ɖ��D���̒����S�z�x�������߂��D�������@�A1885�N
�ɂ͖��ڋh�����̕\����̍쐬�A1890�N�ɂ͂��̕\���̋����A1892�N�ɂ͂��̕s�K����
�\���D��H���̐ςݍ��݂̎����܂�Ȃǂɂ��Đ��ʂ��グ�Ă����B
�@�E�B���\���������I�����Ƃ��A����͢�E�����ɂ����錠���s�g�s�\�A����D���̊O���`��
��̖{���ւ̑��ҁA�D�����Z�{�݁A�L�\�D���̊i�t���A[�C�O�ł�]�D���̈���A�q�C���ɋ�
�������H������p�i�A�D���̔z�搔�A�����̔z���A�C�^�ǂ̑g�D���v�Ƃ������ۑ裂��
���Ă���(93�߰��)�B�����̋c��r�C�X�g�Ƃ��Ă̂����́A[�Љ���ǎ�`��ڎw���t�F�r�A
�������]�E�G�b�u�v�w�̐������������̂��������B���̍s���͏�ɋ����ł������B�������A
���������ɂ͂��ǂ�Ȃ����߁A�����̂����ɕs�����ł������Ƃ����(92�߰��)�B
�@���̐��ʂ̈�Ƃ��āA1897�A1906�N�ɊC�^�@������������B1906�N�@�ł͢�W���H���\
�����肳��A�H���̌����͋�������A�O�q�D�ɂ͗L���i�������̔z�悪�`���Â���ꂽ�B
���O�q�D�𗯒u����͈͂́A�ߐς݂�s���ύڂ���łȂ��A���̌��ׂɂ��L����ꂽ�B
���ڋi�����͏��^�̉��C�D�ɂ��K�p����邱�ƂɂȂ����B�����̕s���ύڂ̋K��͊O���D
�ɂ��L�����A�܂��ޖ̍b�ς݂̓C�M���X�D�A�O���D���킸�A�ē���邱�ƂȂ����B
�O���l�D���́A�C�M���X����g�����Ȃ��Ȃ���Όٗp�����Ȃ����ƂɂȂ����(94�߰��)�B
�@���̖@���́A���̌�A��70�N�ɂ킽��L�����葱���邱�ƂɂȂ邪�A���̐��ʂɂ��āA�m�[
�X�C�[�X�^���K�Z�b�g���͢�E�B���\���̂������A������O�̊���ƈ�v���������ł͂Ȃ��A��
�ǂ̑D�傽����E�C�Â����B�����D��́A�����S�������Ă�葽���̗��v���グ��ɂ́A�H
���ɕs�����Ȃ炵�A�����������Ƃ����āA���������Ȏd�������₢�₳�����A[��������
�P����]�L�\�ȑD�����W�߁A�����Ȏd��������������悢�ƍl���Ă����B�C�M���X�̈̑傳�͊C
�^�Ƃɕ����Ă��邪�A�E�B���\���͉ߋ����猻�݂܂ŁA�������т��ĒNjy���Ă����l���ł�
�飂ƁA���t��s�����ď^�����Ƃ���(95�߰��)�B
�@�������A�E�B���\���͎��炪�������ʂɂ��āA�����Ė������Ă��Ȃ������B���҂ɂ��A
�NMB���ݗ�����Ă���́A�����ɂ��đD�傽���̉e���͂ɍ��E����A������摗�肷��A
�茩�̂Ȃ��c���������o�����Ƃ�����A�c�̌������p����A�悢�d�����ł���
�Ɗm�M����悤�ɂȂ�����Ƃ���(191�߰��)�BNMB�ݗ��Ȍ�A�E�B���\�����C�^�@�����Ɏ��g
�l�q�͂Ȃ��A1920�N��ILO�ɂ����đD���̏T48���Ԑ������˂苭���l�����悤�Ƃ�����
���Ȃ��B���̂��߁A��q����悤�ɁA�Ⴆ�ΑD���̘J�����Ԗ@���͗����藧���x��A�܂��C
�^�@���O�ߑ�I�Ȉ╨���c�����ƂƂȂ����Ƃ�����B����͐��E�̑D���ɂƂ��āA���Ȃ�s�K
�Ȃ��Ƃł������Ƃ�����y1�z�B
2)�@���Љ��`�I�ȘJ���g����`
�@�C�M���X�ł́A1860�N�㖖�ɂȂ��ĘJ���ґ�\�̉��@�c���𑗂荞�ޑg�D�����܂�邪�A
�����̘J���g���͎��R�}��ʂ��āA���̐����I�v�����������悤�Ƃ��Ă����B���������J����
��\�͎��R=�J���h�ƌĂꂽ�B�����A1868�N�i�V���i���Z���^�[�Ƃ��Đݗ����ꂽ�J���g��
��c(the Trades Union Congress�A�ȉ��ATUC)�͋c��ψ����ݒu���āA�����ɖ]��ł����B
1893�N�A�������̎Љ��`�c�̂̑�\���W�܂�A�Ɨ��J���}�����������B�������ATUC��
�����B��̘J���Ґ��}�Ƃ͂��Ȃ������B1900�N�ɂȂ��āATUC�̉����g���ƓƗ��J���}��
�ǂ��A�����ĘJ����\�ψ����ݒu����B���ꂪ1906�N�ɘJ���}�Ɖ��̂���A1918�N�ɂ͎�
���`�j�̂��쐬����B
�@�E�B���\���́A��1�����E���O�͊�{�I�Ɏ��R=�J���h���邢�͎��R�}���Ƃ��āA�����
��͈����h�̋c���Ƃ��ē��I���Ă���B���̑I���ɓ������āA�E�B���\���ƓƗ��J���}��J��
��\�ψ���A�J���}�ƁA�����������J��Ԃ������肩�A�J���^���̐����I�Ȏ嗬�Ƒg�݂���
���Ƃ͂��Ȃ������B��������������Ƃ邱�Ƃɂ��āA������͘J���g����`�҂ł���A�܂�����
�Ƃł������Ƃ��Ă��A�D����C�^�̖��Ɋւ��āA��������R�Ȏ������Ɉς˂悤�Ƃ��鎩
�R�}���ł��A�܂��K��������{�̋K���̂�����ɂ������悤�Ƃ��钆���c���ł��Ȃ����
��(87�߰��)�A�܂����̋c���ɑ��Ģ�ǂ��������}�h�ɑ����Ă��悤�ƁA���̋c�����D���̗��Q
�̂��߂ɍs�����܂��c�����Ă��ꂳ������A����ł悢��Ƃ����ԓx���Ƃ��Ă���(90�߰��)�B
�@����ɁA��E�B���\���́A�c��ɑg����\�𑗂荞��A�܂��w�J���g������������J���}�x
�Ƃ������l�����ɔ��ł������킯�ł͂Ȃ��B�������c�c�Љ��`�҂�т��炢���A������
�J���^�����w�����鎑�i��^���邱�Ƃ���Ɍx�����Ă����B�܂��A�J���g���͐����̂Ȃ��ŁA
�����Ȓn�ʂ��߂�ׂ����ƍl���Ă����B�c�c�J���Ǝ��{�͗��v�̔z�����߂����Č�������
���Ƃ͓��R�̌����ł���A�����ł��邪�A���������J���g���̋@�\�͑��葤�����₷�邱�Ƃ�
�ړI�Ƃ��Ȃ��ꍇ�Ɍ���A�L���ł���Ɗ����Ă�����̂ł���(97-98�߰��)�B�E�B���\�����A����
���`�I�ȘJ���g����`�����߂Ă����ɂ�A�Ɨ��J���}��J���}�A�Љ��`�҂���A����
�G�Ƃ݂���悤�ɂȂ�B
�@�������A�E�B���\�����������������M���������Ă����ɂ�������炸�A�J���^���̂�����Ɛ�
���傫���ATUC�̂Ȃ��Ɉ��̎x���҂������Ă������Ƃ������āA1889�N����9�N�ԁATUC�̋c
��ψ���́A�܂�1918�N�ɂ͘J����\�ψ���̈���ɑI�o����Ă���B�܂��ANSFU�ɂ�����
���A����̐����M���ɒ����ł������킯�ł͂Ȃ��A1922�N�ɂ͑g�������[���s���A�K�v����
����[�ł����āA�J���}�ɒc�̉������Ă���B�����������Ƃ́ATUC������̐����M���ɂƂ�
��ꂽ�i�V���i���Z���^�[�ł͂Ȃ��A�܂��J���}���Љ��`�c�̂ƒc�̉����̘J���g���̘A
���̂ł���Ƃ������i�������Ă��邱�Ƃɂ��݂���悤�ɁA������`�I�ɕ������������Ă���
���Ƃ���C�M���X�l�̎Љ�I�ȑԓx�Ɋ�Â����̂ł��낤�B
�m���n
�@�y1�z�@�R�[���O�f���R�A55�߰�ނ́A1906-9�N�ɂ����āA�����̎Љ���ǖ@�Ă��ʉ߂��Ă���
���A���̈�тƂ���1906�N�C�^�@�����肳�ꂽ�Ƃ��Ă���B
�@6�@1920�N��̒������ATUC����̏���
�@���6�� �n�x���b�N��E�B���\���ƘJ���^�� �Q��́A���ۘJ���@��(ILO)���D���̏T48���Ԑ���
����̑����Ȃ������o�߁ANMB�ɂ�����D�������Ƃ��ꂪ�ʂ����������A1920�N��ɂ�����
�������������Ƃ�����߂����ʑg�����̔��Ή^���ANUS�̃��C�o���g���̖v���AITF��^
�A�J���ҘA������̒E�ށA�Y�z�����g�����x���������Ƃɂ��TUC����̏����A�����ăE�B��
�\���̎��S���L�q����Ă���B�����ł́ANMB�ɂ�����D�������Ƃ��ꂪ�ʂ����������A1920
�N��ɂ�����������������Ƃ�����߂����ʑg�����̔��Ή^���A�����ăE�B���\���̐���
�M���ɂ��g�D�Η��ɂ��Ăӂ��B
1)�@NMB�̑D�������Ƃ��̖���
�E�B���\���̒��N�̖ڕW�ł������D�����������Ǘ��́A�펞NMB��ʂ��Ď�������B����
�́A������Ȃ̑S���D���o�^���x�ƁA�C�^�A�������NSFU�̑�\�ō\�������n�������
�����s���鎑�i�ؖ��A���邢�͏A�ƑO�Ɏ擾����PC5��(Port Consultant 5)�ƌ��т��Ă�
���B���̎d�g�݂́A������̑g���ɂ����v�������͂��ł������B���ANSFU�͢���������
�Ȃ��֗^���Ȃ��V���Ȑ��x�Ƃ��Čp�������APC5��o�^�Əؖ��̋@�\�����˔��������ނƂ�
��悤��Ă���B����ɂ���āANSFU�͂��ꂼ��̍`�̑D���\�Ƌ��͂Ƃ��āA���E�D����
�Ȃ�����A�N���ٗp���邱�Ƃ��K���������߂�悤�ɂȂ�A�X�^���v�������������ꂽPC5��
�D��Ƒg�����A�J�K�C�҂Ƃ��ĔF�m�������Ƃ��������̂ƂȂ����B���̍ہA�ł��d�v�Ȃ��Ƃ́A
PC5�̔��s��NSFU���s�����ɂ��g��������̓_���Ɍ��т���ꂽ���Ƃł������B��
�̌��ʁANSFU�̎��s���������E�҂̂Ȃ�����A�N��I�Ԃ������߂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�
���(115-116�߰��)�B
�@����PC5�̔����́ANSFU�Ɍ���ꂽ�����ł͂Ȃ��������A�E�B���\���͂���𗘗p����
����s�����ɁA�wNSFU�̑g�����ɂȂ�Ȃ�����APC5�͎��Ȃ��ƁA�D�������ɂ͂���
��Ɠ`����x�Ɛ\���n���Ă����B����ɂ���āA�g�����͖ڗ����đ������A�܂��������c���ł�
�����B�D��������NSFU�̑g�����Ȃ邱�Ƃ�]�ނ悤�ɂȂ�A[���Ƃ������Ă�����Ƃ�]���ꂪ
�D���Ȃ邱�Ƃ����҂��āA�g������x�����悤�ɂȂ�����B��������NSFU���D��������Ɛ肵�A��
���B��̑D���g�D�ɂ��悤�Ƃ��铮���́A���R�̂悤�Ƀ��C�o���g�����甽�������������
���Ȃ������B����͑��̑g���̌�����N�Q������̂��Ƃ��āATUC�ɂ����Ď�グ���A
NSFU���������ׂ��ł���Ƃ������c�_���o��Ƃ���ƂȂ����B�������A���łɑ吨�͌����Ă�
��A����܂ʼn��Ƃ��ێ�����Ă������C�o���g�����A�����Ɏ����đ��̍����~�߂��邱�ƂƂ�
��B
�@�����������ʂɂ��āA���҂͒��ړI�ȉ���������Ă͂��Ȃ����A����ł݂��������疾
�炩�Ȃ悤�ɁA���̑D�������������x�͑D��̌ٗp�����ɑ����āANSFU���D���̋������
�肵�Ă������x�Ƃ��Ċm�������B����ɂ��ANSFU�͑D��ɑ���c�̌��͂����߂邱�Ƃ�
�Ȃ�A�܂��D���ɑ��Č���I�ȓ����͂����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B���̓�̋@�\
���A�ǂ̂悤�ɔ�������邱�ƂɂȂ������́A�����ɂ݂�ʂ�ł���B
�@���{��NMB�́A1926(�吳15)�N�ɊC��������Ƃ������Őݗ������B����́A�C���g����
ILO���ɑ����ĐE�ƏЉ���l�����悤�Ƃ����^�����뜜�������{���A�D���������Đݒu
�����@�\�ł������B����́A�����P�ɐE�ƏЉ�Ƃ���łȂ��A��ҋ��Ɋւ��鎖���̋��c
���裁A��D��A�D���Ԃ̑��c�̗\�h�y���⣂�ڎw�������̂ł������B����ɁA����ɓ�������
�E���̑g�D�ł���C������ƂƂ��ɁA�C���g���͓Ɛ�I�Ȓn�ʂ�^�����邱�ƂƂȂ����B��
���̓��{�̘J�g�W�ɂ����Ă͉���I�Ȑ��x�ł������B����̓C�M���X��NMB���قڂ�����
��ؗp�������̂ł��������A�����}��Ƃ���C���g���̖������قړ����悤�Ȍo�߂����ǂ邱
�ƂƂȂ�B
2)�@�������������Ƃ��̔��Ή^��
�@1920�N��ɓ���ƁA�C�^�s�����[���Ȃ�A���ƑD����������B�E�B���\���́A�D�������̌�
�z�̓���������������ł������A����1921�NNMB�̉�c�ɂ����Č��z2����ނ̌��z��g��
���ɒʒm����Ɣ��\����B����ɑ����āA1922�N��2���āA1923�N��1����ނ����z���A1924�N
�ɂ�1����ނ������邪�A1925�N��1����ތ��z����B�����������͑D�傩��̗v���ł�
�Ȃ��ANSFU����̒�Ăɂ����̂ł������B�����ŁA��E�B���\���̉߂��́A���̔ᔻ�҂���A
���������z�������Ƃł͂Ȃ��A����Ɠ������ƂȂ����ӂ������Ƃɂ��飂Ƃ����(112�߰��)�B����
�ŁA���������X�g���C�L�Ə����h�^�����N����B
�@���̂��߂̑g�D�Ƃ��āA�1921�N�ɂ͎�v�ȍ`�ɁA��ʑD���́w���q�ψ���x(vigilance
committee)�������B�����̖ړI�́w���v�x�ɂ���A���̎x���҂�2�̐w�c�ɕ������
�����B���̈�́A�����u���͂Ȃ����ANSFU���邢��1926�N�ɉ�������NUS(the National
Union of Seamen)�̊O���ɂ����āA�w��̑傫�ȑg���x���������邱�Ƃ��w���v�x�ƍl���Ă���
�A���ł������B���̈�́A�R�~���j�X�g�Ƃ��̒��Ԃł���A�����̖ڕW�͈�ʑD����g�D��
�āANUS�̓�������A�E�B���\���₻�̈�h�̎w���ɔ������邱�Ƃɂ������B�����āA�g���^
�c�͈�ʑD���Ɉς˂���ׂ��ł���Ƃ��A���̂��߂ɂ́w������̂̎��s������Ǖ���
�āA��O�̓���ƕ�����ڎw�����łȊ�Ղɍ��ւ���x���Ƃ�ڎw���Ă����B��҂̃O���[
�v�́A1924�N����v���t�B���e����(�ԐF�J���g���C���^�[�i�V���i��)�D������̏��L�ł���
���W���[�W��n�[�f�B�̊NJ��̂��Ƃɂ���A���̉e�������D�������h�^���Ƃ��Ă������
�����(120�߰��)�B
�@1925�N�̒������̏ꍇ�A������h�^���̃��[�_�[�����́A�D���������������ė����オ��
���ANSFU�̎w������Ǖ�����@�����Ă����Ɗ������ɂ͂����Ȃ��ƂȂ����B�X�g���C
�L�����������B�����h���h�b�N�ł́A�����̑D���������ٓ��_��ɏ������邱�Ƃ����݁A����F
�X�g���C�L�ψ����ݒu�����B8��8���A��W��W���[�W��n�[�f�B�̌Ăт����ɂ��ƂÂ��|�v
���^�E���z�[���ŊJ����AC.W.�n���X���\�Ƃ���15�l�̃X�g���C�L�ψ���ݒu���ꂽ�B�n
�[�f�B�͂����āA�n���X�̃A�V�X�^���g�ɂȂ��Ă����B��D�̃`�����X�ł������B�w��������A
�����h�^���Ƌ��Y�}�͑S�͂��グ�āA�D�������ɓ��������Ă����x�(122�߰��)�B����ɑ�
�āA�17,000�l�ȏ�̑D�����A�C�^�A���̎�ł����炱���炩��W�߂��A�C�M���X���`���o��
����D�ɕ�[����A��3,000�l�����̍`�Ɉڂ��ꂽ��ŁA�X�g���C�L���̑D���Ɠ���ւ����
����Ƃ���(123�߰��)�B���Ȃ킿�ANSFU�̈Öق̎x���̂��ƂŁA�X�g�j�肪��������ANSFU�ɔ�
�R����D���Ƃ̓���ւ����s��ꂽ�̂ł���y1�z�B
�@���{�ɂ����Ă��A1920�N��A�D�呤����������̓������N����A����ɑ��Č���D���͔�
�Ή^�����N�����B����ɑ��āA�C���g���͌��F�A����F���c���d�������Ė]�ށB1925(�吳
14)�N�ɂ̓C�M���X�̏����h�^���ɑ�������C�����V���������A���N����F�Ƃ��ė}����
��鏬�M�C�����c�A���N���{�X�D���c���N����B���̌�A���łɂ݂��悤�ɁA�C���g����
1928�N�呈�c�𐬌������邪�A1931(���a3)�N�C��������ɂ����Ē����������F����B������
���o�߂́A�C�M���X�Ƃ��̎����A���e�Ƃ��قڈ�v���Ă���A������̊C���g�����قړ����H
������݂������̂ł���B
3)�@�E�B���\���̐����M���Ƒg�D�Η�
�@�����������Ƃ���A������NSFU�ɂ��āA�ߔN�̘_���ɂ����Ă��A��������ł��A�C��������
(NMB)���ێ����Ă������Ƃ���M�]�́A������R�~���j�Y���̖h�g��ɂ��悤�Ƃ��鐭���I�ȗ�
�R�����܂�ɂ�A���̑S���g����������A�D�傽���̉�Бg���ɂ��Ă��܂�����Ƃ������]
����^�����邱�ƂƂȂ��Ă���(105�߰��)�B
�@NSFU�́A1919�N�Č����ꂽITF�ɉ���炸�A��ꎟ���E��풆�Ƀh�C�c�l���Ƃ����߂���
�킹�邽�߁A1918�N���ۑD���A���Ƃ����g�D��ݗ�����B����́AITF�̋����g�D�ƂȂ�B
1925�N�ɂ�ITF�ɉ������邪�A��L�̒��������X�g���C�L�Ɋ֘A���Ă��A���N�ɂ͒E�ނ�
��B�܂��A1921�N�ɂ́ANSFU����������F�߂����ƂɍR�c���āA�X�g���C�L�ɓ��������C�o��
�g�����A�ŏ�����e���łȂ������S���^�A�J���ҘA�����x�������Ƃ��āA���ꂩ��E�ނ���B
���̂悤�ɁANSFU�͐�O����A�т��Ă����g�D�����������Ă����̂ł���B
�@1926�N�ATUC�͢1920�N�̃C�M���X���Y�}�̐ݗ������o�[�ŁA1923�N�ȍ~�Y�z�����h�^��
�ɉe���͂������Ă����A.J.�N�b�N���w������X�g���C�L���x�����邽�߁A�[�l�����X�g���C�L��
�Ăт����邪���s�ɏI���B�Y�z�J���҂̓X�g�s�������̂́A����ɕ�����݂��͂���
��B���̃[�l�X�g�ɓ������āANSFU�͑g�����̈�ʓ��[���s���Ă���ɓ��������A�܂���
���I�ȒY�z�����g�D�ɑg�D�I�A�����I�Ȏx��������悤�ɂȂ�B�����������Ƃ��߂����āA
NSFU�ɂ����ē����Η����N���A���L���ȂNJ�������C�����B�����āA1928�N�ANSFU�͕�
���g�D���x�������Ƃ��āATUC���珜�������B�������A��������NSFU�̓����́A�E�B���\����
�����M���Ƒg���^�c�ɕ����Ă����̂ŁA����̎��S�������ďI���y2�z�B
�@�E�B���\���ɂ���ĉ�C���ꂽ���L���f�[�r�X�D���́A�������Ȃ��E�B���\���^���҂ł���A
��������łȔ��R�~���j�X�g�ł������B������E�B���\���h���A�i��ŁA����ɒ������
�������A�����C�Â������Ƃ́A�g�����̈ӌ��ɋt�炦�A�N������킸�A����̌��t�ł���
�w�M���𗁂т���������x�Ƃ������Ƃł���������A�܂�������L���̃W���[�W��K�j���O����
���悤�ɁA�w�D������o����閽�߂ɂ͂����������x�A�w���̑g���̃��[�_�[�͈�l�����ŁA��
��͂��̑g�����������ĂȂ��Ƃ���x�A�w���̑g�����͐�ł���̂ŁA�����邱�Ƃ𓊂���
���ĉ�����x���Ƃ��A����Ƃ���Ă����̂ł��飁B�܂��A���҂ɂ���n�x���b�N��E�B���\����
�ӔN�́A���I�ȑg����`�ƎY�ƕ��a�ւ̋��M�A������]�����Ăł��g����������
��Ƃ����A���ꂪ���˂Ă�����s���Ă������ӁA�����Ď����ɑ��鈣��݂�߂��݂Ƃ��A��
�������ɂȂ��čʂ��Ă������ɂ݂��飂Ƃ����Ă���(128�߰��)�B
�@1929�N�A���łɈȑO����a�����Ă����E�B���\���͎������A�S������Ŏ��S����B69�ł�
�����B����ɂ́A���łɖ��_�M��(CH)�A�㋉�M�m(CBE)���^�����Ă����B�W���[�W�X���ƃ��A
���[���܂���A�E�B���\���v�l�Ɉ����̎莆�������Ă����B�C�^�A���̃T���_�X�����́A
��w�J���g���^���̂Ȃ��ŁA���ݓI�ȍl���������������Ȃ��l���̈�l�ł������x�ƌ�����B�J
���g���ɂ����ẮA����̏����̑g�D�I�ȋƐт��^���͂������̂́A���ꂪ�ӔN�܂ő���
�Ȃ��������Ƃ��c�O��������Ƃ����(130�߰��)�B����̈ꐶ�ɂ��āA����ȏォ��������
�͎֑��Ƃ����悤�B�Ȃ��A���̑g���ɂ����āA�E�B���\���̎���A�g�����Ƃ������͎̂g���
���A�g���̃g�b�v�͏��L���ƂȂ�B
�m���n
�@�y1�z�@�R�[���O�f���R�A237�߰�ނɂ́A1923�N�������̍ۂɍs��ꂽ����F�X�g���C�L���s
�k�������Ƃ��A�����ӂ���Ă���B
�@�y2�z�@�����O�O�f���A241�߰�ނɂ́ANSFU���Y�z�����g�����x������C�^�Y�Ƃɂ�����
��p�g���Ƃ��ĕ`����Ă���B
�@7�@����E��펞�̑D����Q�Ɛ����v
�@���7�� �E�B���\���̈�Y��́A1930�N�Y�z�J���g�D�Ƙa������TUC�A�܂�1933�N�J���}�� ��
�ĉ����A1930�N�̍��ۖ��ڋh������c�A1932�N���E���Q�̂��Ƃł̒������Ƃ��̉A
1936�NILO�C������ɂ����鑽�l�ȏ��Ɗ����̍̑��A������ẴC�M���X�����ł�1��
8���ԏT48���ԂƏT�x���̊l���A����E���ɂ�����D���̓����Ɣ�Q�A���̂��Ƃł�
�J�������̉��P�A���ۑD�����͂̐���A�D����u���x�̊m�����L�q����Ă���B�����ł́A
���E��풆�̑D���̓����Ɣ�Q�A���ۑD�����͂̐���ƑD����u���x�̊m���ɂ��Ăӂ�
��B
1)�@�D���̎����I�Ζ��A���S��50%
�@�E�B���\���ƌ�サ�����L���{�u��X�y���X(1876-1954)�́ANUS�����₩�ȊC�ɓ������Ƃ���
�Ƃ����B1932�N�A���E���Q�̂��ƂŁA�Ăђ�������]�V�Ȃ������B����ɂ��āA�NUS��
�g�����́ANMB���肪����Ȃ��Ȃ������Ԃ��ANMB�����͂�������z��J�������؉�����
��i�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��Ȃ����Ɣ��f���Ă����BNMB�͑��݂��̂��̂���@�ɕm������
���(140�߰��)�B���̎��A�X�y���X�́A���̑g���ł͂��߂Ĉ�ʑg�����ɂ����ʑ�c�����
���J���āA������������Ă���B����ɁA1937�N�܂łɂ����S�z���A���̌�2�z����
����B
�@1939�N9���A�C�M���X�͂��Ԃ��ԃh�C�c�ɐ푈��z������B�������ɂ�āA�D���͑�ꎟ
���E���̌o�����ĂьJ��Ԃ����Ɗ�����悤�ɂȂ������A�D���~�߂�킯�ɂ͂����Ȃ���
���B�1941�N5��26���A���p�߂����D���ɂ��K�p����邱�ƂƂȂ����B1936�N�Ȍ�A���D���ɋ�
���������Ƃ̂���18����60�܂ł̒j�������o�^���邱�Ƃ����߂��A����ɉ�����11,000
�l��1941�N�̎c��̊��Ԃ�1942�N���ɊC��ɕ��A���Ă�����B���ꂪ���܂��������̂́A����
�ɂ͢���D����1��ȏ�A�ٓ��_��������Ƃ̂���j���������������B�c�c�����̑���
�́A�R�l��薯�Ԑl���D��ł������A�������������Ƃ������ƂŁA�C��ɕ��A���Ă������
��ł�����(150�߰��)�B
�@�������A1941�N�H�ɂȂ�ƁA���{�͏��D���̏�g���Ƃ��ĕK�v�Ȑ��̒j�����������W�߂邽
�߁A�H���̑��z��펞�蓖�̎x���Ƃ���������g���ȊO�ɕ��@���Ȃ��Ȃ����B����ɁA�d�v��
���ƂƂ��āA����D���܂��͋x�ɒ��̑D�������͏��D�\�����v�[���ɕғ�����A���̊��ԁA��
��̒������x������邱�ƂƂȂ����B�����āA�����͏�D����1�����ɂ�2���A�m����2.5��
�̋x�ɂ��^�����邱�ƂƂȂ����B1943�N7��1�����A����D���̓C�M���X�ɋA������܂ł�
���ԁA���邢�͑��D�ɏ�D���邩�A����z��v�[���ŋΖ���\���n�����܂ł̊��ԁA�펞
�댯�蓖���܂މғ������S�z���ۏႳ��邱�ƂƂȂ����B���̂悤�ɂ��āA�����D��ʂ��āA��
�����p�����Ďx������悤�ɂȂ�������Ƃ��グ����(150�߰��)�B
�@�������ē������ꂽ�D�����A���̐푈�Ţ�ǂꂾ���̖�������ꂽ���𐳊m�ɂ������Ƃ͂�
��قǗe�Ղł͂Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��A26,000�l�������ނˋ����őD�����v�������Ɏ���ł���B
����ɉ����A��1,000�l���~���D���q�Ƃ��ď��D�ɏ���Ă��āA����炪�G�̍U���Œ���
���Ɏ���ł���B����ɁA�Փ˂ɂ��A�܂��펞�ߗ����e���₻�̑��푈�ɂ�鎖����5,000
�l������ł���̂ŁA���v32,000�l�ƂȂ�B�����������Ƃ���ł͂Ȃ��A�푈�ɋ��o���ꂽ��
�Ƃɂ���đ����ɂ�����A�ċN�s�\�ɂȂ����肵���l������B������܂߂�ƁA38,000�l�߂��l
�����Ƃ݂���B�G�̍U���ɑ��āA�D�����v�����ہA���̏�g���̐�������5�N�Ԃ�
�푈��ʂ��āA2����1�ȉ��Ƃ݂�悢�B�����舫���N���������B�܂��ɁA���C�ɂ������
�ʎE�l�ł�������Ƃ���(149�߰��)�B�폟���ł��A�s�퍑�ł��A�D���͌R�l�ȏ�ɁA����Ƃ��
�������̂ł���B
�@����ɑ��āA�㉺���@�́A1945�N11���A����D���̎m���ƕ������A�s���̐��_�ŐH���⎑
�ނ̔��~�A�����ČR����R�������̗A���ɓ���A����ɖ��Ԑl�ł���Ȃ���E���ɓG�̍U��
�Ɍ������Ă��������ƣ�Ɋ��ӂ��錈�c���̌�����(152�߰��)�B�����������ƂŁA�D��������
��킯�͂Ȃ������B
2)�@���ۑD�����͂̐���ƑD����u���x�̊m��
�@����E���Ƃ��̐��́A�O���Ƃ͈قȂ��Ă����B��푈���A�J���^���͈�v�c����
�āA�푈���x�����Ă������A�����鐭��ɂ��Ď��₳��Ă����B�c�c���{�����邢��
�ٗp�ґ�����A�J���^�����l���������̂����Ԃ����Ƃ����A���v���I�ȓ�������݂���
�������(152�߰��)�B
�@1943�N�A�푈�̂��Ȃ��ɂ�������炸�A�����A������10�����̑D����\���W�܂�A���ۑD
����c���J�Â���B���̗��N�ɂ́A���ۑD�����͂ƌĂ�颒������A�x���A�T�J�����ԁA
�ٗp�p���A�����Ĉ�Õۏ�Ɋւ���Œ��̃��X�g����쐬���A������́A���ۓI�Ɍ�
�p�����͏��炳���ׂ�����ƍl���Ă��邵�A���̓x�̐푈�𐬌��ɓ����ɓ���A�D��������
���]���ɑ��钼�ړI�ȏ�����v�����飂��ƂƂ���(153�߰��)�B���̗v���Ƃ��āA����z�Œ�
����16���ؽ����ށA���m�q�C�D�̍b���A�@�֕��D���ɂ���1��8���ԁA�T56���ԁA����
�D���ɂ���1��8���ԁA�T48���Ԃ������ނˑÓ��Ƃ���Ă����B����ɁA�L���x��12���A�D
���������̎��i�ؖ��A�N���A�ǎ��ȑD���ݔ���l�X�ȕX�A�����č��ӂ��ꂽ���ۊ�ɏ�
�����Ȃ��������̑D���ɑ��āA�����������X�̍`�ɂ����Đωׂ�g�ׂ����ۂ��邱�Ƃ��t
��������ꂽ�B�������������邱�Ƃɂ���āA�w�D���E�Ƃ���蒼���A�q�������ɂƂ��đD��
���V�E�ɂȂ��Ă���邱�Ƃ����҂��Ă����x��Ƃ���(154�߰��)�B
�@���ꂪ�A1946�N�̃V���g��ILO�C������Ɏ������܂�A9�̏���4�̊����Ƃ��Č�����
��B���̂Ȃ��ł��A�d�v�ȏ��͑�76�������A�J�����ԋy�ђ�����A��72���L���x�ɏ�
��A��70���Љ�ۏ�(�D��)���A��71���D���N�����A��75���D���ݔ����ł������B���E
�̑D���́A��1�����E���Ƃ͈���āA�J�����v����������Ǝ�荞�̂ł���B����́A��
���̋]���̏����Ƃ��Ă���ł͂Ȃ��A���ɂ����鐢�E�̐�����f���Ă���B
�@1942�N�A�`���[���Y��W���[�}��(1893-1947)�́A�{�u��X�y���X�ƌ�サ�ď��L����s�ƂȂ�A
�풆�A��㏈�������āA1947�N54�Ŏ��S����BNUS�́A�펞���D�\�����v�[����D����u
���x�Ƃ��Ĕ��W������B����́A��ٓ��_��̊��Ԃ�2�N�Ƃ��A�������ԂōX�V�ɂ��āA�ٓ�
���Ԓ��ɁA�D����m���A�������C�^�Y�Ɠ��̕s����܂��͓���̉�Ђɂ����ċΖ�����
���邱�Ƃ��ꍇ�A�����F�߂�B�O�҂́w��ʏ�u�D���x�A��҂́w��Џ�u�D���x��
�Ă��悤�ɂȂ����B��u�D���ɂ́A�w�ٓ��_�������A�D���̋Ζ����Ȃ��Ȃ��Ă��x�A��
�̑D�̎w�����鎑�i��^�����A�����āw��u�蓖�x���x������悤�ɂȂ����(157�߰
��)�B
�@����̏�u���x�́A�ٗp�̌p����⏞����ƂƂ��ɁA�S���ɂ��Ăł͂Ȃ����A�����̑D����
���ĐE�ʏ��i�̋@���t�^���邱�Ƃɂ������B�c�c�`���[���Y��W���[�}���́w�D�����A����
�l�������J�������͂���炪�l���̂Ȃ��ŗ\�z���ɂ��Ȃ��������̂ł���x�Ɣ������Ă���B
�܂������A���̒ʂ�ł����āA��u���x��NUS�ɂƂ��ċP���������ʂ̈�ɐ����邱�Ƃ��ł�
��B����́A1890�N�㏉�߁A������NSFU�������c���������������A1920�N��n�x���b�N�
�E�B���\�����J���g���^���̓����ɔ��������ƈȏ�ɁA�l�X�ɐ��_�I�ȃV���b�N��^�������
�����㕨�ł�����(156�߰��)�y1�z�B
�@���{�ɂ����Ă��A�푈�̎Y���Ƃ��āA1939(���a14)�N�D���ی��@�����肳��A�펞�����@��
�̑D���^�c��ɂ�����p���ٗp�����̗\�������x�ƂȂ�A�����v�Ƃ��ĐV�D���@����
�肳���B�����́A���E�̑D���J���^���̐��ʂ̂��ׂĂł͂Ȃ����A���̂��Ȃ�̕�����
��荞���̂ƂȂ����B
�m���n
�@�y1�z�@�ٍe��C�M���X�C�^�ɂ�����D���ٗp�|���̗��j�I�T�ρ|��A�C���Y�ƌ�������182�A
1981.8�́A�ߐ��ȍ~�ɂ�����D���ٗp�Ƃ��̐��x�����Ă���B�R�{�ד¢�C�M���X�D����
�u���x�̐��x�I������A�w�o�όo�c�����x15(2)�A1965.3�́A����͂��Ă���B
�@8 ����F�X�g���C�L�Ƃ��̑Ή�
�@���8�� ��ʑg�����^����́A�S�����̐��ނƐE����̑䓪���݂��邪�A���̂Ȃ���
�����ĊC�^�J�g�W�͈��萫��ۂ��Ă����Ƃ͂����A1940�N�㖖����NUS�ɂ����Ă���ʑg
�����^��������Ȃ�ɂ݂��A1955�A1960�N�ɂ͔���F�X�g���C�L���N����A������w������
���v�ψ���Ƃ̒��������߂��A�D����\�����̗p����邱�ƂɂȂ�ߒ��Ȃǂ��L�q�����
����B�����ł́A��ʑg�����̕s���Ƃ��̉^���g�D�A����F�X�g���C�L�A����т���ɑ���
�g�������̑Ή��A�D����\���̗̍p�ɂ��Ăӂ��B
1)�@1947�A55�A60�N����F�X�g���C�L
�@���C�M���X�ł́A�S�����A�S������A��Ύ��s���Ƃ��������x���J�g�W�̋K���͂�
�����A�E����A�E�ꋦ��A�E��ψ�����������đ���悤�ɂȂ�B���̂Ȃ��ɂ����āA
�n�x���b�N��E�B���\���������ɂ܂ō��グ�Ă����NMB�ƊC�^�@�̂��ƂŒz���ꂽ�����V
�X�e���́A��������Ƒg���Ă��Ă����̂ŁA���ꂪ�g�ւ���ꂻ���ɂ��Ȃ��������A������Ƃ�
���Ƃł͊C�^�Y�ƑS�̂̂Ȃ�킢���ς肻���ɂ��Ȃ������(161�߰��)�B����ɂ�������炸�A
��ʑg�����^���ƃX�g���C�L���N����B
�@1947�N�H�A�}�[�W�T�C�h��ʑg�����^���ψ���g�D����A����F�X�g���C�L���s���B����
���~����������B���̏����Ƃ��āANUS�ɢ���ׂĂ̎�v�ȍ`�����ʑg������\��I�сA
�������ٗp�҂ƐڐG������ψ���̍\�����ɉ����A�܂���u���x���߂����Đ����镴�c
�����̑�\�ɂ��R�������邱�ƣ�����ꂳ����(163�߰��)�B
�@1955�N�A���o�v�[���Œ�����q�D�̔���F�X�g���C�L���n�܂�B���̃X�g���C�L�ɂ��āA��
���@�ւ͢���Y�}�ɐ������܂ꂽ��ң�ɂ��Ԕ����������Ƃ����A���������s���ɏo
�����Ƃɖ�������ʂ��̂�����Ƃ��Ă����B���̗v����NMB�Ŏ�グ��������Ȃ��Ȃ�B����
���A�����̕s���̂����A��g���w�����̌���D���̖����A��I�ȉ^�c�A�Ƃ�悪��A����
�Đ����ȗv���̔M�̂Ȃ����グ����ɂ��ẮA�������̂܂̂Ă����ꂽ(166�߰��)�B
�@1960�N�A����F�X�g���C�L���N���邪�A����͂��܂܂łɂȂ��g�D���������̂ł������B����
���A�S���̎�v�ȍ`�Ŕ���F�X�g���C�L�ψ���ݒu����A���������S���D�����v�^
��(the National Seamen's Reform Movement�A�ȉ��ANSRM)�Ƃ����g�D���ݗ������B���̃�
�[�_�[�́A��w�ԁx����łȂ������B�Î���������A�V�����������A��ɑg�����ƂȂ�W����X
���[�^�[���܂܂�Ă����B���̂���͖k���C�݂ʼn��v�^���ƂƂ��Ċ��Ă������Y�}����
�͂��������A����ΐ����h�̋��Y�}���̎͂悭�Ȃ������Ƃ����B
�@�����̗v���́A�1 ���ׂĂ̑D���ɂ��āA�T44���ԁB���z����4����ވ��グ�B2 ���j��
������j���܂�1��8���ԁA�T40���ԁB3 ���j���̂��ׂĂ̘J�����ԂɁA���ԊO�蓖�̎x���B
4 ��g�����I�o����D����\�̓����A[�����]�E��ψ��Ɠ��������̕t�^�B5 �N���L���x��
24���A��s�x�Ɠ��ɑ���Љ�X��ƒ됶���̌����̕⏞(���ʁA�N���X�}�X�̓��Ɛ���
�j��)�B6 [����F�X�g���C�L�ɑ���]�D��ɂ����فANUS�ɂ�铝���̋��ۣ�ƂȂ��Ă���
(170�߰��)�B�������A����̖{���̖ړI�́A�g�����v���̂��̂ɂ������B�w�X�g���C�L�ɎQ������
����C�M���X���D�D���́A�J���������s���ɂȂ��Ă��錴�����ANUS�̑̎��ɂ���ƍl���Ă�
��BNUS�����邱�Ƃ��A�܂������čŏd�v�ȖڕW�Ƃ��Ď��グ�Ă���x��Ƃ݂��Ă���
(168�߰��)�B
2)�@�g�������̑Ή��A�D����\���̗̍p
�@1948�N�A�`���[���Y��W���[�}���ɑ����ď��L���ƂȂ����g����G�[�c(1896-1978)�́A����
���̊J�n��TUC�̋��Y�}���̉e���r���Ɍĉ����āA��ʑg�����^���̉��������݂�}��B
1955�N�X�g���C�L�ɓ������ẮA�C�^�A�����Čٗp�����ۂ��鐺�����o�����ANUS�͂����
�ǔF����B�������A1960�N�X�g���C�L�ɓ������āA�D���o�g�ł͂��߂�TUC�̋c���ɂȂ��Ă���
�G�[�c�͂��낢�닭�����Ă݂����̂́A���̐������������邱�Ƃ��ł����A�W����X���[�^�[��
�������k������������Ȃ������BNUS�́A�X�g�Q���҂ɒ��~���Ăт�������A���̊C�^�@��
���������u�o�^�̎�������ٔF�����肷�����ŁANSRM�̗v���ɑ����āA���N8���A
NMB�ɂ����Ģ���グ7.5%�A�q�C���T�J����5.5���A���`���T44���ԁA�����Ď��ԊO�蓖����
���グ�Ƃ����A�w�Z���Ԃ̌��ŒB�����ꂽ�ő勉�̐��ʁx����グ��(169�߰��)�B�������A
NSRM�͂���ɖ��������A���N7������͂��܂����X�g���C�L��9�����܂ő����B
�@���̃X�g���C�L�ɂ���āANSRM�̗v���̂����o�ϗv���͂��Ȃ�B�����ꂽ�B�������A�g����
�v�ɂ��Ă͢����l���ł��Ȃ��������ANUS�w�����̐M���x�������������A����NUS��
�����߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������BNUS�����܂܂Ŏ��{���Ă������@�ɑ���s���́A������Ƃ�����
���̈Ⴂ�ɂ��s���Ƃ��������̂ł͂Ȃ������̂ŁA�w���̂�������ǂ��ς��Ă������ɂ�
�ģ��������������Ȃ�����(172�߰��)�B
�@����NUS�ɂƂ��čő�̔���F�X�g���C�L�����܂���1960�N���A���̑O�N�ɌM�ݎm(�i�C�g)��
�������Ă����G�[�c�͈��ނ�]�V�Ȃ������B����ɑ����āA�W����X�R�b�g(1900-1962)��
���L���ɂȂ�B���̑I���ɓ������āANSRM�ɂƂ��čD�ӓI�ł���Ƃ݂������Ƃ���A����ɑ�
���̎x���[���������邱�ƂɂȂ������A���l�͂܂������t�ł������B���̂�����A1962�N��
�}������B��������āA�r����z�[�K�X(1911-1973)�����L���ɂȂ邪�A���̑I���̓E�B���\
����40�N�O�ɍ̗p�����������[��(�Ⴆ�A�g����15�N�ȏ�̑g�����ɂ�4�[��^����)�ɂ�
�ƂÂ��čs���A30,879�[�ƂȂ��Ă������A�Η����̃W����X���[�^�[(1923-)��9,855�[�ł�
�����BNSRM�́A��O����\���Ȏx�������Ă���A�Η����������o���Ƃ���܂ŗ��Ă����̂�
����B
�@�������ď��L���ɂȂ����z�[�K�X�́A�O�C�҂̃X�R�b�g�Ɠ����悤�ɁA����ɔ��ł��������A
���N�̌��ĂƂȂ��Ă����D����\���N�̔N�����ɒ�Ă���Ɏ���B���̑D����\����
���āA�D��͢�J�g�W�ɑ���Ȕ�Q�������炵�A�C�^�Y�Ƃ⍑�Ƃ�j����V�X�e����
�����āA����͕s�K�v�ł�����肩�L�Q����Ƌ��ۂ���(177�߰��)�B�����Œ�����]�V�Ȃ���
��A�����NUS�Ƒg�����Ƃ̂������ɗ������ȏ����҂Ƃ��A���̂������̈ӎv�a�ʂ�}��
���ƣ��E���Ƃ��A���g���̋�����グ��ɂ������đg�������W��������A�����̑�\��
�Ȃ����肷�錠���͂Ȃ����̣�Ƃ��邱�ƂŁA�D��Ɏ��ꂳ����(178�߰��)�B���̑D����\
���ɂ���āA���ʑg�����Ǝ��s�����̂������̐M���W���č\�z���ꂽ���ƣ�ɂȂ����B����
���A���ꂪ��500�ǂőI�o����Ă����A1970�N���s�[�N�ɂ��Đ��ނ��Ă����y1�z�B
�@���{�̊C���g���ɂ����ẮA1946(���a21)�N�[�l�����X�g���C�L��A�����Η��������A�E�h
��������Дh�D���ƑË����Ďw����������B����ɂ���ĘJ�g�W�͈��肷��悤�ɂȂ�A�C
���g���͘J���g���^���̕���ɗ^���Ă����B�����͌���E�B���\������ƌ��܂��������
����B�������A1960(���a35)�N�A�J�������g����������肪�P�p���ꂽ���Ƃ��_�@�Ƃ��āA�C
�M���X�̈�ʑg�����^���ɑ�������A��(�ꕔ��_)�̐E��ψ��𒆐S�Ƃ������l�E���^��
���N����A�o�ϗv����g�������ɓ˂�����悤�ɂȂ�B������ł����A�g�������͑D��
�c�̂������������������Ȃ��Ȃ�B
�@�Ȃ��A�C�M���X�̑D����\�͓��{�̑D���ψ����ɑ������A���{�̐E��ψ��Ƃ͈قȂ�B��
�{�̐E��ψ��́A������1950(���a25)�N�ɁA��Дh�D���Ƒg�������Ƃ̑Ë��ɂ���Đ݂���
�ꂽ���̂ł������B����́A����ɂ����đg���@�ւƂƂ��ɋ����ɓ�����A�܂��e�ИJ��
�ψ���̑g�������ψ��Ɏw�������B���������ʂ̉�Ђ�D���ɂ�����g�������@��
�̔z�u�̌o�߂⎞���A���̖����Ȃǂ́A���{�ƃC�M���X�Ƃł͂��Ȃ�قȂ��Ă���B
�m���n
�@�y1�z�@H.A.�N���b�O���A�q��x�v����w�C�M���X�J�g�W���x�̔��W�x�A30-31�߰�ށA�~�l����
�@���[�A1988�ɂ́ANUS�ɂ�����V���b�v�V�`�����[�h���D����\�Ɍ�ނ��A��������v�h��
�����]�����Ă��Ȃ����Ƃ��Љ��Ă���B
�@9�@1966�N��X�g���C�L�ƊC�^�@����
�@���9�� 1966�N��X�g���C�L��́A1911�N�Ȍ�͂��߂čs��ꂽ�����X�g���C�L�̌o�߁A����
���߂���NUS�Ɛ��{�ATUC�Ƃ̊W�A�{�i�I�ȉ����ƂȂ���1970�N�C�^�@�A1971�N�J�g�W
�@�ɏ]��������TUC����̓�x�ڂ̏����������Ƃ��L�q����Ă���B�����ł́A��X�g��
�C�L�̌o�߂ƁA������߂���NUS�Ɛ��{�ATUC�Ƃ̊W�A����ъC�^�����@�̓��e�ƘJ�g�W
�@�ւ̑Ή��ɂ��Ăӂ��B
1)�@��������̂��Ƃł̑�X�g���C�L
�@1964�N�A�J���}���v���Ԃ�ɐ����ɂ����A�ێ�}�����̏�������������p���B���łɂ݂�
�悤�ɁA�D���̘J�����Ԑ���1960�N�㓖���A��̉��P���݂�ꂽ���A����J���҂Ƃ̂Ђ�
���͖��܂�Ȃ������BNUS�́A1966�N�L�\�D���̊�{�������z60����ށA�T40���Ԑ���v����
�Č��ɓ���B����ɓ������āA�ŏ�����A��������̐�������A�܂��X�g���C�L��������
���ƌ������Ă����B����ɑ��āA�D��͏T40���Ԑ���3�N�Ԃ����Ď��{���A���{�̃K�C�h���C
���Ɏ��߂�ΈĂ�p�ӂ��Ă����B�����NUS�̎��s�ψ���͋��ۂ��A���N5��16�����A����
�ɂ�����3�Ԗڂ�4�Ԗڂɒ����A47���Ԃɋy�ԃX�g���C�L�ɓ���B
�@���̃X�g���C�L��O�ɂ��āA�J����b���NUS�����ƐڐG���āA���̒��~��v������B�X
�g���C�L���͂��܂�����A�̢�n�����h��E�B���\���̓e���r��ʂ��Ēk�b�\���A�D����
�������̂����邪�ANUS�����{�̊������A�F�߂Ȃ���A�s��������U����āA��
��ɑR����������Ȃ��ƁA�����r���Čx�������BNUS�̗v�����������A�w������
��̊O�x�x�����߂��邱�ƂɂȂ�A������̋}�㏸��A�o�i�̍����ɂȂ���B�w����͍�
�ƂƎЉ�ɔ��R����X�g���C�L�ł���A����ꂪ�]�݂����߂����Ȃ�����ł���x�Əq�ׂ��
(184�߰��)�B
�@���̃X�g���C�L���I���7��1���ɂ́A�518�ǂ̉��C�D��373�ǂ̊O�q�D���C�M���X�̍`�Œ�
�D���A65,000�l�̑g�����̂���26,000�l���ӋƂ��Ă�����悤��(180�߰��)�A��X�g���C�L�̈З�
�͈���ɐ����邯�͂����Ȃ��A���{�������˂��������Ƃ��Ă��A�킯�Ȃ����˕Ԃ��ꂻ���ł�
������Ƃ���(184�߰��)�B5��22���ɂ́A��펖�Ԑ錾���o����A�s�A�\�����وψ���ݒu��
���B���ψ���́A�T40���Ԑ���2�N�Ԃł̎��{�����B�����NUS�͎���Ȃ��B��
�����ATUC�͒��ق��o�����ƁA�X�g���C�L�͗L�Q���Ƃ���悤�ɂȂ�A6��20���ɂ͂��������
����K�v�Ȃ��Ɖ����g���ɒʍ�����悤�ɂȂ�B���̓������ɁA�E�B���\���͉��@�ɂ���
�āA������I�ȓ��@���������j�������A���łȃO���[�v������āA�������s�ψ��̎��s������
�݂Ȃ炸�A���`�ɂ����Ă悭�g�D���ꂽ�X�g���C�L�ψ���ɉ����Ă��鈳�͂��A�����͌�
���I�ō����I�Ȃ��̂ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ���Ɣ�������(187�߰��)�B
�@��������NUS�̃X�g���C�L�͓D���ɓ��邪�ATUC�̎����Ɋ�Â��A�s�A�\�����c���Ƃ����J�g
��c��������A�s�A�\�����ق��C������`�őÌ�����B���̃X�g���C�L�̎Љ�I�ȈӋ`�ɂ�
�āA���҂͂܂Ƃ߂Ă��Ȃ����A����͏���������т����Ƃ��鐭�{�̔�펖�Ԑ錾�⢐Ԃ̗d
��������Ƃ��������������݂�(���������͂Ȃ�����)�A���̐��{���x������TUC�̕��j�ɋt��
���Ă܂ł��āA�����̃X�g���C�L�𑱂��A���ɐ��ʂ��グ�����Ƃ͒��ڂɑ傢�ɒl����B����
�g�D�I�ȈӋ`�ɂ��āA���҂͢�������s�ψ������I�Ȗ������ʂ����A�w���v�ҁx���邢
�͂��̓����҂Ƃ��������g�������킫���ɂƂǂ܂������Ɓc�c�E�B���\����g����G�[�c�A�W���
�X�R�b�g���A��ΐE�����]���āA���̂������v���ʂ�Ɍ��߂Ă����A�n���ȗ��̃X�^�C���Ƃ�
��������̂ł���������Ƃ��グ�Ă���(189�߰��)�B�v����ɁANUS�͂��̃X�g���C�L�ɂ����āA
�D���̘J�������̗��x��Ƃ������グ���ʑg�����^���̂��ƂŁANUS�͏]���̉�����
�^���H�����C�����ē��킴�邦�Ȃ��Ȃ�A����ɉ����č��c���őg�D�^�c����������Ȃ�����
���Ƃ��A���̃X�g���C�L�͎������Ƃ�����y1�z�B
�@�C�M���X���l�A���{�̊C���g���ɂ����Ă���ʑg�����^���͂܂��܂����g���A���̑Ή���
�߂����đg�������͈ꖇ�łȂ��Ȃ�A�g���^�c�̎哱���͎���ɋ��l�E���Ƃ�����x����
���ʑg�����Ɉڂ��Ă����B���̌��Z�Ƃ��āA�C�M���X�Ɠ�������1965-66�N��X�g���C�L�A����
��1972�N�����X�g���C�L����������B���̊ԁA�g�������̃��R�[���^���Ƒg�������`�m��
�^�����i�߂��A�啝�Ȓ��क़J�������̉��P��A�g���@�\�̉��v�����{����A����Ɍ���
�D���̒������s�ψ��̓��I��g���O���̎��C��X�R�A����ɑ��鍶�h�����̓o�ꂪ��
���A�`���I�Ȕ�����J�g�����H���͕��@����Ă����B����������ʑg�����^���̌`�Ԃ₻��
�����v���A����ɔ����o�߂͓��{�A�C�M���X�Ƃ��قړ���Ƃ����Ă������ĉߌ��ł͂Ȃ��A��
��ɂ�����J���g�����邢�͘J���^���̍Đ��̖@�����������Ă����Ƃ�����B
2)�@1970�N�C�^�����@�A�J�g�W�@�Ƃ̑Ή�
�@�s�A�\�����وψ���͑D���@���ɂ��Ă��������A�]���̊C�^�@�͢�D������ʎs���Ƃ�
�Ⴄ�Ƃ������Ƃ���A������Ƃ����ᔽ��ƍ߂Ƃ��Ĉ�������A���̌ٗp�҂ł���D�傽���ɑ�
�Ăł͂Ȃ��A���̑D�Ɍق��Ă���D���ɗl�X�ȐӔC�����Ԃ���[�Ƃ�����]�c�c����x���
�͍폜�����ׂ��ł���A�c�c20���I���A�����Ȃ̖@�߂�c�̌��ɂ���Ċm������
���s�ƈ�v������ׂ��ł��飂Ɗ������Ă���(192�߰��)�B���̎�|�����āA���ɖ�70�N�Ԃ�
�ɁA1970�N�ɊC�^�@����������邱�ƂƂȂ�B����͎�Ƃ��đD���K���̉����ł������B
�@1970�N�@�ɂ����āA��َ~�蒠�ɁwDecline to Report�x�Ƃ����������L�����邱�Ƃ͔p�~����A
��������������葱�͑啝�ɉ�������A�D������������邱�ƂɕύX���ꂽ�B1894�N�@��
�́A�E�D��x�ɂłȂ����͒�������ю���i�̖v���A�܂����������O�ŋN�����A10
�T�Ԃ̒����܂��͋łƂ��������ƂȂ��Ă����B1970�N�@�ł́A�����ȗ��R�ɂ�炸�A�D�ɏ�
��x�ꂽ���ʂƂ��Ă̌��͑�����100����ވȉ��̔����Ɉ���������ꂽ�B�@������߂閽
�߂ɕ��]���Ȃ������ꍇ�A1894�N�@�ł�12�T�Ԉȏ�̋ŌY�ɏ������邱�ƂɂȂ��Ă�
���B�x�d�Ȃ�s���]��k�}�ɂ��āA1970�N�@�ł́A����܂�100����ވȉ��̔����Ɉ�����
�����A������̕s���]�͑�����50����ވȏ�̔����ƂȂ����B����Ɠ��l�ȑ[�u���A�D��
��Ζ����ɋy�Ԍ��o�ɂ��̗p����邱�ƂƂȂ����B�D��r����������A�j��������A����ɏd��
�ȑ��Q��^�����ꍇ�A1970�N�@�ł�2�N�Ԃ̋ł��邢��200����ވȏ�̔����ƂȂ����(193
�߰��)�B
�@�܂��A��E�D�́A��250�N��ɂȂ��āA����Ɠ����悤�ɗ��E�Ɠ��`��Ƃ��Ĉ����邱�Ƃɂ�
�����B�w���̑D���Ɠk�}��g�x���ǂ����́A���ꂪ�C��Ŕ��������ꍇ�Ɍ����ēK�p�����
�������ƂɂȂ����B���������āA���`���w�@�I���߂ɕ��]�������Ȃ����߁x�k�}��g��ł��A����
���������Ȃ����ƂɂȂ����B����ɂ���āA���O�̍`�ŌW�����ł���A�w�X�g���C�L���錠���x
���F�߂��邱�ƂɂȂ����BNUS�́A����]���Ƃł͂Ȃ��������A������Y����1970�N�@
�Ɏc�邱�ƂɂȂ������Ƃɂ��āA�����̔p�~�ɂ͈��̎��Ԃ̌o�߂��K�v�ł���ƌ�����
���Ă����B����ɁA�Ⴆ�Ό����̈��S���������悤�ȕs���S�Ȏd���ɂ��āA�������������
���Ƃ͓��R�ƒN������F�߂Ă���Ƃ��āA1970�N�@�ɂ����āA���������ᔽ�̔�����200�����
����400����ށA�܂��^���J�[�ɂ�����i���̔�����10����ނ���20����ނɈ��グ��ꂽ��Ƃ���
��(193�߰��)�B�����������x�̉����ɁANUS�����������킯�ł͂Ȃ��������A�����F�߂����
���Ȃ������y2�z�B
3)�@�J�g�W�@�ɋ����ATUC����̏���
�@1970�N�A�ێ�}�������ɂ��ƁA���̃q�[�X�͘J���^���̉��������݂ɂ�����B�����
�������ĘJ�g�W�@�𐧒肵�A�J������ɖ@�I�S���͂���������A����F�X�g���C�L�̖���
�ӔC�͔F�߂Ȃ��A�X�g���C�L���[���`���Â���A���E�O�̃N���[�Y�h�V���b�v���֎~����Ȃǂ�
�����B����͘J���g���̑��݂��̂��̂̋��Ђł������B���̂Ȃ��ł��ANUS�ɂƂ��Ă͓��E�O
�̃N���[�Y�h�V���b�v�̋֎~�́A�D����u���x�̕���ɂȂ�����̂ł������B���̖@���ɑ�
���āATUC�͂��܂܂łɂȂ��������āA�g���o�^�̎������ȂǁA�{�C�R�b�g���ɏo���B
�@��������TUC�̕��j�ɁANUS�͔��ł͂Ȃ������B�������A�D����u���x���ێ����Ă�������
�ɂ́ANUS�ɂƂ��Ă͑g���o�^�𑱂��āA�F�N���[�Y�h�V���b�v�𐭕{���������K�v��
�������B��������NUS��TUC�Ƃ̑Η��́A�����炪�������s�ψ���ő傫�Ȑ��͂��߂Ă���
���Ƃ������āA���v�҂����ɂƂ��Ă��߂��������ƂȂ����B�����́A�q�[�X�̖@����Ŕj����
���߁ATUC���D��I�X�������߂��鎞�A����Ɉ��̋�����������������Ȃ���������
�ł���(194�߰��)�B
�@�1972�N1��10���ANUS��TUC�ɑ��āA�킪�g���̊��S�ȕ����h���ɂ͔F�N���[�Y�h�V
���b�v�����Ȃ��Ɗm�M���A3��9���C�M���X�C�^�A���Ɠ������āA�S���J�g�W�ٔ����ɋ����F
�\�������o����ƒʍ������B�c�c1972�N9��4���ANUS��TUC��������ɉ����g�D����r
������A���̑g����\�͖��납��폜����邱�ƂɂȂ����(197�߰��)�B�������������́ANUS
���͂���19�̑g�D�ł݂�ꂽ�B�Ȃ��A1974�N�ĂјJ���}�������ɕ��A���A�J�g�W�@���p�~
���ꂽ���ƂŁANUS��TUC�ɍĉ�������B
�@NUS��1966�N�X�g���C�L�ɑ��āATUC�͂��ꂪ�x������J���}�̐�����l�����āA���̉�
�������݂�}�����B�t�ɁA�J�g�W�@�ɓ������ẮANUS��TUC���j�ƈ�����s�������A��
�̔��Ή^����W�Q�����B�����́A�ǂ̂悤�ȘJ���g���ł����Ă��A���̍��̂��ׂĂ̘J����
�Ɋւ�闘�Q��i�삷�邱�ƂȂ����āA����̑g�����̗��Q��i�삷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ���
���A�X�̘J���g���ɂ����Ă͌ʎY�Ƃɂ�����͊W�A�ߋ�����̒~�ρA���ʂ̗v�����
��Ɋ�Â��čs������������Ȃ��ꍇ������B�C�M���X�ł́A���̎Љ�o�ς����������߂�
���邱�Ƃf���āA�J���^���������Ɋ֗^����܂łɈꉞ�A���B���Ă����ɂ�������炸�A
���{�I�ȎЉ���v�ւ̓W�]���Ȃ��ꍇ�A���̑S�̗̂��v�ƕ����̗��v����v���Ȃ��Ȃ��Ă�
�邱�Ƃ��������Ƃ�����B
�@�������A���������Η����ANUS��TUC�͍P�v�I�ȑg�D����ɂ܂Ŕ��W�����悤�Ƃ͂��Ă���
���B�C�M���X�J���g���́A���̗^����ꂽ�ɉ����āA���̑g�D�A�т̂������������`�I
�ɏ�������Ƃ����_��Ȏp�����A���̒��N�̊��s�ƂȂ��Ă��邩�̂悤�ł���B�C�M���X�ł́A
�قƂ�ǂ̘J���g�����P��̎Y�ƕʥ�E�ƕʑg�D�Ƃ��āA���̒n�ʂ��ێ����A�܂������ɘJ
���}��c�̉������Ă�����ꎖ�����Ƃ��Ă��A���������p������{�̘J���g�����w�ԂƂ�
�낪�Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��ł��낤�B
�m���n
�@�y1�z�@�y�����O�O�f���A312-313�߰�ނ́A1966�N�X�g���C�L�ɂ��āA����ȑO�̎w��������
�����������Ă������߁A�D���̘J�������������Ȃ��Ă����̂ŁA���̗v���ɂ͐�����������
���B�܂��A���{���g���Ɉ��͂��������̂͏�������̂��Ƃ����邪�A���̃X�g���C�L�ɂ����
�|���h��@���}���ɐi�W�������Ƃ�J����������ł���Ƃ��Ă���B
�@�y2�z�@1970�N�C�^�@�̖M��́A�w�p�����D�@(�D���Ɋւ���K��)�x�A�C���Y�ƌ������A1982
�ł���B
�@10�@�g����@�̂��Ƃł̑n��100���N
�@���10�� �C�^��J���s��ƑD����́A1970�N��㔼����g�����������������w�i�A�s�A�\
���A���b�`�f�[���̊C�^�Y�Ɖ��v�̒�N�y1�z�A�V�[���C�t�v��̍��܁A��������Ɉˑ���
�����グ��T40���Ԑ��̊l���A�Q���^�̑g�D�^�c�ւ̎��g�݁A�T�b�`���[���Y���̂��Ƃ�
�̊C�O�u�ЁAFOC�̍��ۋK���̍���A1981�N�̎��ԊO�蓖���グ�X�g���C�L�A�E��m�ۂ�
�����A�����đn��100���N�̏j���NUS�̍���L�q����Ă���B�����ł́A�V�����D�����x
�̍��܁A�C�O�u�Ђɂ��g�����̌����A�����đn��100���N�ɂ��Ď��グ��B
�@�Ȃ��A���� �o���n�ЂƂ̑Ό���́A�T�b�`���[���{�̌ږ����Ƃ���P&O���[���s�A����t
�F���[�ЂƂ̑�ʉ��ٔ��Γ������X�g�j��Ɛ��{�̑g�������ɂ���Ĕs�k���Ă����o�߂��L�q
����Ă��邪�A�����ł͏ȗ�����B
1)�@�V�����D�����x�̍���
�@1966�N�̃s�A�\���͊C�^�@�̉����ƊC�^�Y�Ƃ̘J�g�W�̍��V�ɂ��āA1970�N���b
�`�f�[���͊C�^�Y�Ƃ̑g�D�ƍ\���A���̌o�c�̎d���A�W�҂̎��ׂ��[�u�ɂ���
�������Ă����B�����́A���ʂ��āA��C�M���X�C�^���`���ɂƂ���A�V�Z�p��V�^�D�c
�c�����Č���I�Ȑl���Ǘ��̗̍p�����߂���Ă��邽�߁A���v�̔����Y�ƂȂ��Ă��܂��Ă�
��B�܂��A���̎Y�Ƃ́w�`������E��ł����A�琨�ɉ���Ă��邽�߁A�������݂��A���W�̋@��
��Njy������A����̗��v���ێ����邱�Ƃɂ��イ���イ�Ƃ��Ă���x��Ɣᔻ���Ă���(203�߰
��)�B
�@�����̒�ĂɁA�D��͐i��Ŗ�����������Ƃ͂��Ȃ������B����ł��A1960�N�㔼��
�́A�L���i�[�h�Ђ���E���Z�ʐ��x�(inter-departmental flexibility�AIDF)���̗p������A�܂��V�F
���Ђ̃^���J�[������ړI�z�搧�x�(general purpose manning�AGP)�ƌĂ��������s����
�肵�Ă����B�����̐V���x���A�J�g�o���������̎^�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B����ɂ�
���Ė��炩�ƂȂ������Ƃ́A�����Ƃ��������Ō��߂�Ƃ�����K�R�I��NMB�������Ă��錇��
��A�C�M���X�D�勦��Ɉ��̋����������ANMB�����B��̋���Ƃ݂͂Ȃ��Ȃ��A�C�^��
�Ђ́w�Ǝ����x���ۗ�������������������Ƃ����(206�߰��)�y2�z�y3�z�B
�@1975�N�A�ٗp�҂ƑD�����g���������Ŏx�����A�D�傪�o��S����V�[���C�t�v��Ƃ���
�@�\����������B���̖ړI�́A��C�M���X�C�^�Y�ƂŁA�C�M���X�D�������낤�Ƃ���C�㐶��
���A�J���͂̌��ʓI�ȗ��p���@�̊J����ʂ��āA��薣�͓I�Ȃ��̂ɂ��铹��T�邱�Ƃɂ���
����B���̌v�悪�I������1979�N�ɂ́A����łɍ��ۊC�^�s�����ؔ����������B�ǂ�����
�͏I���A�i�C��ނ��������ɋ��܂��Ă����B�V�[���C�t�v��̒��ڌo������邱�ƂȂ���A�D
�傽���̋^�S�ËS�ɉ����A���̉��v�Ă����{����ꍇ�A�\�z�O�̃R�X�g�������邱�Ƃ�����
���ƂȂ�����B�����āA��D���E���c�̂͂��̎x������艺���Ă��܂����B�D��̂Ȃ��ɂ�����
�v�M��҂������Ȃ��Ȃ�A�M���o�߂Ă�������̂ł���(207�߰��)�B
�@���̃V�[���C�t�ɂ��āANUS�͎��������ɂƂ��Ď����\�Ȓ�Ă��o���Ă��ꂽ�Ƃ݂Ă�
���B�������A���Ԃ͋}�W�J���Ă��܂��Ă����B���̃V�[���C�t�ł����A��C�M���X�C�R�Ɠ����悤
�ɁA���Ȃ�ߍ��ȏ����̂��Ƃœ����Ă��Ȃ���R�X�g�������Ƃ����C�M���X�l�D�����A�ǂ��
���̑D�ł����Ă��������Ƃ���R�X�g���Ⴂ�O���l�D���Ǝ��ւ���Ƃ����w���Ղȁx��������
��̗���ɂȂ����Ɗ뜜���Ă����B�ܘ_�A�V�[���C�t���Ӑ}�����킯�ł͂Ȃ����A����
�͉��v�̃V�O�i���ł͂Ȃ��A����̃V�O�i���ɂȂ��Ă��܂�����̂ł���(208�߰��)�y4�z�B
�@���̂悤�ɂ��āA�C�M���X�ł͓��{�ł����D�����x�̋ߑ㉻�͓��̖ڂ��݂邱�ƂȂ��A�C�M���X
�D�̊C�O�ڐЂւƂ����܂�������ɓ˂��i��ł������ƂƂȂ����B���{�ɂ����ẮA1970�N���
��D�����x���v�_�c���s���Ă������A�C�M���X���l�A���܂��������B�C�M���X�̃V�[���C�t
�̍��܂����炩�ƂȂ���1979(���a54)�N�A���J�g�w�̢�D�����x�ߑ㉻�ψ����������A��
�㉻�D�̎����Ǝ��p�Ɏ��g�݁A�C�M���X�ɔ�ׂ���̐��x���v���ꉞ�A�����Â����B��
�����A�X�u�БD(Flags of Convenience�A�ȉ��AFOC)�ɑR�ł�����{�D��҂ݏo���Ƃ���
�ڕW�́A���m�̂悤�ɁA���̔����̎��_�ŁA���łɂ��̊�Ղ������Ă����B���{���A���ʂ���
�݂�A�C�M���X�Ɠ����ƂȂ����B
2)�@�C�O�u�Ђɂ��g�����̌���
1970�N��ɓ���ƁA�C�M���X�ɂ����频D���̋����͕s���́ANUS�ɂƂ��Č��͂����߂���
���Ƃ����Ȃ��Ȃ����A�����ɁA����Ƃ͑Ώ̓I�Ȍ��ʁA���Ȃ킿��O���E�̍��X�ɋ��Z�����
�����J���҂��ٗp���鈳�͂�n�o�����飂��ƂɂȂ���(216�߰��)�B����ȑO��1965�N�ɁA
NMB�ɂ����Ă��̌ٗp�ʂ�����ێ��Ƃ���[���b�p�l�z�拦�肪����Ă����B1974�N
�ɂ́ANUS�͂���ɉ����āA�NMB����߂Ă�������������Ⴂ���[�g�ŁA�Z�D������
�p���Ă���NMB�\�����̑D��ɑ��āA�����D��1�l������N��15����ނ�NUS�ɔ[������
�悤�v������A�����F�߂�����(217�߰��)�B���̔N�A�J���}���{�͐l��W�@������ɂ���
�Ă����B���̖@�����A�D���ɂ�����������ʂ��������悤�Ƃ��Ă����̂ŁANUS�͂���ɔ���
�����B���̖����������邽�߁A�O�ҋ��c��ݒu����A1978�N�A����1982�N���܂łɒ���
�i����5�i�K�ɕ����ĉ������銩�����o�����B�������A���̖��́A1976�N�ɂ�490�ǂ̑D
����17,000�l�ȏ�̔Z�D������D���Ă������A1984�N�ɂȂ��137�ǂ�4,000�l���Ɍ���
�������Ƃ������āA�������̂܂ܕ��u����邱�ƂƂȂ����B
�@����͂��Ƃ̈�ʂł������B���łɁA1970�N��ɓ���ƁAFOC��{���̍��Ђɖ߂��āA����
�^���ȊǗ��̉��ɂ�������Ƃ�ڎw���Ă���ITF�ƒ��N�A��������ł������C�M���X�̑D�傽��
�́A���̍l����ς���悤�ɂȂ�B1976�N�̑�147��ILO���D(�Œ�)���́AFOC�����S
�����⏬�����������̌���ƂȂ����B�܂��A1980�N��A���A�f�ՊJ����c(UNCTAD)�����{
�ڕW�𓊂��̂ĂĂ��܂��B���L���X���[�^�[�́A1977�N������U��Ԃ��āA�ITF��������Ƃ�
���FOC�D���D�����A�w�u���[�T�[�e�B�t�B�P�[�g�x[ITF�����ӂ�������������Ă��邱�Ǝ���
�ؖ���]����点�AITF�����\��K�p�����邱�Ƃ��ł����͂��ł��飂Ƃ������Ƃ����B����ɑ�
���āA���҂͢�e�����{�������ύX���A������ĂѕύX���邱�Ƃ����ۂ��Ă��鎞�A�ǂ̒�
�x�A�B���ł����ł��낤��?�@���ꂪ�\���A�B������Ȃ����ƂŁA�J���g����FOC�Ƌ��������
�O�ɁAFOC�ɑ��ĉʂ����Ăǂ�قǂ̂��Ƃ��ł����Ƃ����悤��?��Əq�ׂĂ���(221�߰��)�B
�@�1970�N�㔼�A500���d�ȏ�̊O�q�D��1,700�ǂقǕۗL�A�o�^����Ă������A10�N���
��700�Ljȉ��Ɍ������A����Ɍ������悤�Ƃ��Ă����B1975�N����85�N�ɂ����āA�C�M���X�D��
�ǐ���3����2�A�g������4����3�����D�A��P�A���邢�͊C�O�ڐЂɂ���ď����ĂȂ��Ȃ��Ă�
���B�C�M���X�D�Ƃ��Đ����c�����̂́A�D���v��ז��Z�p�����ǂ��ď�g�������팸���A��
���D�����L�p���R�X�g���ʂ̂���D�Ɍ�����悤�ɂȂ����(218�߰��)�B����ɔ����āA
��C�^�Y�Ƃ̈�ʓI�Ȍٗp���͔j�ǓI�ȏ�ԂɂȂ���邱�Ƃ���R�Ƃ��Ă����B1979
�N�A�D����u�@�\�ɓo�^����Ă���D�������͖�29,000�l�ł��������A1987�N�ɂ�15,400�l
�ɂȂ��Ă����B�c�c�C�^�Y�Ƃ́A�����A�J���͂�f���I�Ɍٗp���悤�Ƃ���Y�Ƃ̈�ł�
��B�D�傽���́A�R�X�g���ŏ��ɂ��悤�Ƃ��āA���݂��ɔ�r�������Ȃ���A�J���͂����炷����
�ɐ�O���Ă����BNUS�́A���̑g�����ɏA�Ƌ@���^����K�v������Ƃ��āA�g�����ɔC��
���َ蓖�����邱�Ƃ����シ��Ƃ������A�ϑ��I�Ȏ��Ԃ��ׂ炴������Ȃ��Ȃ�����̂ł���
(220�߰��)�B
�@����ɑ��āANUS�͐E��m�ۂ̓�����g�D����B�������A����ɐ������Ă��Ȃ��B����ɂ�
���āA���҂͢�J���s��̊Ǘ���J�g�W���x�̈ێ���I�グ�ɂ�����ŁA�s�ꋣ���Ǝs��
�̗͂ɐM�����A����1970�N�セ�̕K�v�����F�߂�ꂽ�A�J���҂�J���g���̌������n
���I�ɏk�������Ă�������Ƃ�Njy����T�b�`���[���Y���̍U���ɂ��炳��(218�߰��)�A�J���^
�����S�̂Ƃ��đ傫����ނ��Ă����B�������A�O���l�D���Ƃ̢�����͖ڂɌ����Ă����B�C�M��
�X�̐����Ƃ��A�C�M���X�J���҂����܂܂ōs���Ă����d�����C�O�ɗA�o���Ă������A�D��ق�
�ɒ[�ł͂Ȃ������B�D���́A����̎{�݂Ƃ͈���āA���ɊȒP�Ɂw�t���O�A�E�g�x(�C�O�ڐ�)
���邱�Ƃ��ł��飂Ƃ�(202�߰��)�ANUS���ЂƂ蓬����������̂ł͂Ȃ������Ƃ����������̂�
���ł���B����ł́A�ǂ�����悩�����̂��B����͗\��O�Ƃ������Ƃł��낤���A��L��
FOC�Ɋւ���X���[�^�[�̔����ɑ���R�����g���炷��A����s���Ƃ��Ă݂邩�̂悤�ł�
��B
�@�Ȃ��A���{�̎���ɂ��ẮA���܂���������܂ł��Ȃ��B
3)�@�h���Ƌ�Y�̑n��100���N
�@1973�N�A�z�[�K�X������܂��}������B����ɑ����āA1974�N�W����X���[�^�[�����L����
�Ȃ�B��E�B���\������Ȍ��NUS�̗��j�́A�����ɂ킽����畏������Ƃ͂����A���ɗ�̂Ȃ�
�J���g����`�ւ̉ߒ��ł������B�g�����̈ӌ����ł�����蕷�������g�D�A���͂�g�D��
�Ȃ��ɕ��U�������g�D�A�����Ė����`�I�ɐ���𗧈Ă��A�ӎv�����肵�Ă����g�D���낤�Ƃ�
���B���������ύX�́A���ׂāA���̑g���̌�p���L���̑ԓx�ƐӔC�ɕ����Ƃ��낪�傫���B�r
����z�[�K�X�́A��ʑg�����^���̈��͂̂��ƂŁA�E�B���\���̎��ォ��`���ƂȂ��Ă�����
�i��`�𐳎��Ɋɘa���悤�Ƃ��āA�l�X�ȓw�͂������ŏ��̐l���ł������B�������A���L����
�g�����̓����ł���A���̑�\���Ƃ����l���ɂ��������āA���S���ӐU�镑���悤�ɂȂ�����
�́A�X���[�^�[�ɂ����ĂȂ���Ƃ����(213�߰��)�B
�@�X���[�^�[�́ANUS��g�����̂��߂̑g����ɂ��悤�Ƃ��āA�g���@�\�̍ĕҐ��A�I�����x
�̉��P�A�������[���̔p�~�A�D���x���̓����A�@�֎��ҏW�҂⌤���E���̗̍p�A����T�[
�r�X�̉��P�Ȃǂ̑[�u���u����ƂƂ��ɁA1976�N�̏T40���Ԑ��̊l���A�D����u�@�\�̉�
�P�A1978�N�̋��o�N�����x�̓����A1979�N�̑D���K���ᔽ�̔������̔p�~�Ȃǂ̐��ʂ���
����B�����A���s�����ɂ����Ă��A����K�̑g�����̗v�]�ɓ����邱�Ƃ����R�ƍl���A��������
���ԓx�Ŏ����悤�ɂȂ����B����ɁA������NUS�����炻�̂��̂Ǝ~�߁A����̗��Q��
�g�������ɂ�荶�E�����Ɣ��f����悤�ɂȂ����B���̌��ʂƂ��āA�g�����̌����͔���
�ł܂����v�̂ł���(217�߰��)�B
�@1986�N�A��W����X���[�^�[�̓n�x���b�N��E�B���\���Ȍ�A�͂��߂Ă�NUS�g�����ƂȂ����B��
�������h�_�������̂́A100���N���߂Â��Ă��邱�Ƃ����������A���ꂪ�����]������Ă�����
��ł���B�X���[�^�[�̌�p�҂̓T����}�N���X�L�[(1932-)�ȊO�ɂ��Ȃ��ƁA�N������݂���
�����B�c�c����́A�D���g���������̋����A�g�������̈ӎv�a�ʂ̉��ǁA���s�����̖K�D
�����̏���A�����Ēc�̌��ւ̊C��g�����̒��ڎQ�����ێ��A���W�������Ƃ��A����Ɂw�g
�����������̕�炵�̂��߂ɕK�v���ƔF�߂�A�ǂ�Ȃ��Ƃ����Ă�������������Ă݂���x��
�t�����������Ƃ������āA���|�I�Ȏx�����A���L���ɓ��I�����(226�߰��)�B
�@1960�N��̑D�����v�^���̊����Ƃ��A������g�����Ə��L���ɂȂ�A���̑g�����E�B���\
������̂���ł͂Ȃ��Ȃ����A�܂��ɂ��̂Ƃ��ANUS�͑n��100���N���}����B1987�N9��18
���A�}���^�C���n�E�X�ɢ�x����\�A�N�������ҁA���s�����A�g���E���A�����ĘJ���^���A�g
���^���̗��o�Ȃ�300�l����Q�W���āA�j��̉����J�����(226�߰��)�B�}�N���X�L�[�́A�C��
�ɂ���g�����ɢ�w�����̑g���́A100�N�O�A�D���ɂƂ��čŗǂ̘J���������邽
�ߐݗ����ꂽ���A���܂₻�̑g���̐����c��������ē��킴������Ȃ��Ȃ��Ă���x�B���ՂȎ�
��͉߂������Ă���A�C�M���X���D���𐊑ނ����Ă����ՂƁA�J���g���^���ɑ��鐭�{��
�G�ӂ��A�����ɂ���B����炪����ɋ��܂낤�Ƃ��Ă���B����́ANUS���Ǝ��̑g�D�Ƃ��Ă�
�������̂��̂̋��ЂƂȂ��Ă���A���̍Đ��������đ��̑g���Ƃ̍������l����������Ȃ���
������ƁA���b�Z�[�W�𑗂���(224�߰��)�B
�@NUS�́A1950�N��10���l�̑g���������ւ��Ă������A1987�N�ɂ�24,405�l�܂ŗ��������
�����B�����ANUS��1990�N9��10���A�S�����S���g���ƍ������āA�S����C����^�A�J���ґS
���g��(the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, RMT)�̈ꕔ��ƂȂ�B
�@���{�̊C���g���ɂ����Ă��A1972�N�̒����X�g���C�L��A���h�����̎w�����Ȃ���Ȃ�ɂ�
�m�����Ă����B������뜜���āA1975(���a50)�N�A���{�D�勦��̋e�r��͂�����e�r
�\�z(FOC�̔F�m�A�D�����x�̋ߑ㉻�A�J�g�����̊m��)�\����B����Ɍĉ����āA��
�N�A���Ђ𒆐S�Ƃ�����Дh�D���ɂ��C�����^�����N����A�E�h�����ƂƂ��ɁA���̊���
�Ԃ������������߂邱�ƂƂȂ�B���̐���s���Ƃ��āA�����܂ŁA�D�����x�̋ߑ㉻�A���{�D��
�C�O�u�ЁA�����ɔ������{�l�D���̌������ٗp�������i�߂��邱�ƂɂȂ������Ƃ́A���m
�̂Ƃ���ł���B����ɂ���āA���{�̊C���g�����O�q����Ɍ���A�C�M���X�Ɠ��l�̌���
�ƂȂ��Ă���Ƃ�����B
�@�C�M���X�ɂ����ẮA�T�b�`���[���Y���Ƃ����J���g����������̂��ƂŁA���̊C���g������
�ނ���������Ȃ��Ȃ������A����ɑ��ē��{�ł͉�Дh�D���̍����ɂ���āA���̓�������
�J���^������ނ��Ă��������ƂƂ͂���߂đΏ̓I�ł���A�C�M���X�ł͓���l�����Ȃ�����
�ł��낤�B���̂������ɂ����āA�J���҂̈ӎ���g�������̎����ɂ��Ȃ�̈Ⴂ�����邱�Ƃ�
�݂�������Ȃ��B
�@�Ȃ��A�������������ȗސ��ł��邪�A���̎�����ƐсA�l���ɂ����ăC�M���X�̑g�����G�[
�c�͓��{�̑g�����A�R��⒆�n�F���A�܂��z�[�K�X�͓�g���ԖL�A�X���[�^�[�͑���s��
��y��ꐴ�ɂȂ��炦�邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B
�m���n
�@�y1�z�@�s�A�\������у��b�`�f�[���̂����ނ˂̖M��́A�w�C�M���X�C��J�����|����
�����ψ����1��|�x�A�C���Y�ƌ������A1966�A�w�p���s�A�\���ψ����(�C�^�Y��
�̏����ɂ��Ă̒����ψ���̍ŏI��)�x�A���{�D�勦��A1967�A�w�C�^�����ψ���
��(���b�`�f�[����)�x��1�A��2�����A�C���Y�ƌ������A1972�A1974�ł���B
�@�y2�z�@�ٍe��C�M���X�D���̑��ړI�z�搧�x�|���̌��������̏Љ�Ƙ_�]�|��A�w�C�^�x583�A
1976.4�́A�^�Ђɂ����錋�ʂ̕��͂̏Љ�ł���B
�y3�z�@�N���b�O�O�f���A55-56�߰�ނ́A�s�A�\�������p���āANMB�ɂ����ă^���J�[���
�̈ӌ����������ꂽ���ƁA���̑��ړI�z�搧�x�ɂ������̏�悹�ANMB�����������
��Ђ̌ʋ���ɂ��Ăӂ�Ă���B
�@�y4�z�@�V�[���C�t�̈ꕔ�ɂ��ẮA1977�N���_�̑D���ٗp�ƑD����u���x�̎��Ԃ�
�������ٍe�w�C�^���O���ɂ�����D���̌ٗp���x�Ɋւ��钲�������|�C�M���X�ɂ�����D��
�ٗp�̎��ԂƐ��x�ɂ��ā|�x��A�C��J���Ȋw�������A1981�A�؏C����w���D�D���̈�
���������x�Ɋւ��錤���x�A���{�C�Z����A1982������B
�R�@�wNUS100�N�j�x��NUS100�N�̕]��
�@1�@�wNUS100�N�j�x�̓����Ɛ���
1)�@���̓���
�@���́wNUS100�N�j�x�̎��M�˗��ɓ������āA�}�N���X�L�[���L���́A�����ŁA���҂����ɑg
���̋L�^�����܂����ƂȂ���I���A��킪�g���̊C��ł͂Ȃ�����ɂ�����^���̊T���I�ȕ]
���ƁA���L���ׂ��j����`�����o���Ă��炤���Ƃɂ������B���̏ꍇ�ł����Ă��A���R�̂��Ƃ�
����A�����d�v�ł��邩�A�ǂ��]�����ׂ����ɂ��āA�킽���⒇�Ԃ����̊ϓ_�ł͂Ȃ��A��
���̊ϓ_�ł����Č��߂Ă��������Ƃ����B
�@���҂����́A�܂������ɂ����āA��J���g���̗��j�́A�����T���߂Ȏp���ŏ������Ƃ��]�܂�
��B�J���g���̂Ȃ��ɂ́A���̘J�g�W���܂߁A�Ɠ��ȐF�����⌾�t�g���𑽂������Ă���
�ꍇ�����邪�A�C�M���X�C���g���ɂ͂����������̂͂Ȃ��B�������A�C�^�Y�Ƃɂ͂���Ȃ��
���ꐫ������ �c�c�S�̂�ʂ��āA���̑g�����J���^�������]�Ȑ܂̂Ȃ��ɁA�ǂ̂悤�Ɉʒu
�Â����邩�������Ȃ���A���̑g���̕��j�⓬�����ǂ̂悤�ɓW�J���������������悤��
������Ƃ��Ă���B
�@���������˗��⎷�M�̈Ӑ}�́A100�N�j�Ƃ��������̗��j�������A���������������Ȃ��ɂ�
������炸�A�\���ɉʂ�����Ă���Ƃ�����B���̂Ȃ��ł��A�`�L��Ƃ��爵���ɂ����A�٘_��
�o�₷��NUS�̑n�ݎ҃n�x���b�N��E�B���\���ɂ��āA�����̌������Ɩ����ʁA�D�]�ƕs�]
�ȂǁA���炢���炢�`���o�����ƣ�ɐ������Ă���B����ƂƂ��ɁANUS���C�^�A���ƍR�����Ȃ�
��A�J�g�W���x���m������ߒ��A�g���̕��j�⓬���ɂ��đg���������ǂ̂悤�ȗ��O��
�����Ă������A������߂����Ăǂ̂悤�ȑΗ������������A�Ȃ��ł���ʑg�����^�����ǂ̂�
���ɍs��ꂽ���ɂ��āA�����̐����ɐ������Ă���B
�@����ɓ������āA���{�I�Ȍ����g���j�Ƃ͈���Ă���Ƃ���́A���ꂼ��̎���̑g������
���ʑg�����̏،���L�^�A���邢�͐V���L�����ӂ�Ɏ�荞�܂�Ă��邱�Ƃł���B
���̂��߁A�����͓�����l�ƂȂ������̂悤�ɁA���̏�O���Ɏv�������ׂ邱�Ƃ�
�ł���B���̍����́A�����̑g�����������͂������c���A�܂��g���L�^����ɕۑ�����Ă�
��A�������������W�����ĕۑ����Ă����Z���^�[(�Ⴆ�A���[�E�B�b�N��w���㎑���Z���^
�[)�����邱�Ƃɂ��B�����������Ƃ́A�C�M���X�l������̗��j�Ɏ��M�ƐӔC�������Ă��邱��
�ɂ�낤�B
�@����ł���Ȃ���A���҂������������ŏq�ׂĂ���悤�ɁA�C�^�Y�Ƃɂ�����J�g�W��
���j�Ɋւ��镶���͖R�����B���̂Ȃ��ŁA���グ���Ă�����̂Ƃ��āA���L�̂��̂�����B
Havelock Willson,My Stormy Voyage Through Life, Co-operative Printing Society,
1925.
Edward Tupper,Seamen's Torch, Hutchinson, 1938.
F.J.Lindop, A History of Seamen's Trade Union to 1929, M.Phil. Thesis, London School of
Economics, 1972.
Basil Mogrides,Militancy and Inter-union Rivery in British Shipping 1911-1929,
International Review of Social History, Vol.6, No.3, 1961. L.H.Powell, The Shipping
Federation:A History of the First Sixty Years,1890-1950,Shipping Federation, 1950.
2)�@���̐���
�@�����������҂����́A�ǎ҂ɔ��f���ς˂悤�Ƃ��鎷�M�p���́A�C�M���X�ɂ�������j�Ƃ�
��̗���ł��邪�A���{�l�̂悤�ɐ��}�ȍ����ɂƂ��Ă͕�����Ȃ����̂ƂȂ��Ă���B����
���A�������A����Ȃ�Ɏj���ɂ��ĕ]����^���Ă���킯�ł����āA�����ɂ��Ă͖���
�����Ȃ���A������Ă����B�܂��A��ʓI�ȃC�M���X�J���^���j�̕��������p���Ȃ���A��
���⋭���Ă����B���̂Ȃ��ł��A1960�N��̈�ʑg�����^���̔�����ANUS�͑傫���ω���
�Ă������Ƃ݂��邪�A���̕ω��̐��i�Ƃ��ꂪ�����E�ɂ��Ď�藧�ĂċL�q����Ă���
�����Ƃ́A����̐��E�̊C���g���^����W�]���悤�Ƃ���Ƃ��A��ρA�ɂ��܂��B
�@���҂����́ANUS�ɂ��Ă͓��ꐫ��F�߂Ă��Ȃ����A�C�^�Y�Ƃɂ͂����F�߂Ă���B��
��ɏ]���A��҂��O�҂�J�g�W�ɉe�����y�ڂ��Ȃ������悤�ɓǂݎ��邱�ƂɂȂ邪�A
�͂����Ă����ł��낤���B�Ⴆ�A���Y�P�ʂ�����ł����������Z�p�����̑D���ɁA�D������
�Ɖ��f�I�Ɉړ����Ȃ���A�Ƃ���Ƃ������ꐫ����A�ۗ����ĎY�Ɖ��f�I�ȘJ�g�W���x��
�m�������Ƃ݂��邪�A���̂��Ƃɂ����đD�����C�O�u�Ђɂ���ĊO���l�D���ɒu���������
��ƁA����炪�ꋓ�Ɍ`�[�����Ă��܂��Ă�����݂�Ƃ��A���҂������J�g�W�_�̐��
�Ƃł��邾���ɕs�v�c�Ƃ�����B���̊֘A�ɂ��čŏ�����O���ɂȂ�������������Ȃ��B
�@����͂��Ă����A���҂����͈˗��͈̔͂ɒ����ł��������߂��A���邢�͎����̐��������
�Ă��A�C�M���X���{��`�Ȃ��ł����̊C�^�o�ς̔��B�ƑD���J���Ƃ̊֘A�Â����R�����B��
�̂��߁A�Ⴆ�Δ��D����D�D�ɕω��������Ƃɂ���āA�D���̘J����i�A����ɘJ���^����
����悤�ɁA�ǂ̂悤�ȉe�����������̂��A�܂����܂����j�ƂȂ��Ă��Ȃ���������Ȃ����A�C�M
���X�D�̊C�O�u�Ђɂ��āANUS���ǂ̂悤�ȕ��j�������A�ǂ����������ɂ��Č@�艺����
��Ă��Ȃ����Ƃ͎c�O�ł���B
�@����ɁA���ꂼ��̎���̒��क़J��������J�����Ԃɂ��Ăӂ��Ƃ��낪���Ȃ��B����
���߁A��ꎟ���E����ANUS���J�g�W���x���m�������ɂ�������炸�A�����Ԃɂ���
�Ē��क़J�������ɖڗ��������P���Ȃ��������ƁA����ɂ���ב���E����A���Ɉ��
�g�����^���̔�����ɂ����Ėڗ��������P�����������Ƃɂ��āA�N���ɎƂ�Ȃ�����
��������B
�@���́wNUS100�N�j�x�́A�����āA�j�����ɂ��Ȃ���A�����]�����邱�Ƃ��Ȃ�ׂ�������
�Ƃ����A���҂����̊�{�I�Ȏp���Ɋ�Â��ď����ꂽ�g���j�Ƃ�����B���������āA���R�̐�
��s���Ƃ��āA���{�ŋc�_����Ă���悤�ȁA�Ƃ��Ƃ��Ĕ��ׂɉ߂���Ƃ�������A�C�M���X�J��
�^���j�̘_�_���������ꂽ�g���j�����Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�����[�߂�̂́A���̐l�X�̉�
��ƂȂ��Ă���B
1)�@���̓���
�@���́wNUS100�N�j�x�̎��M�˗��ɓ������āA�}�N���X�L�[���L���́A�����ŁA���҂����ɑg
���̋L�^�����܂����ƂȂ���I���A��킪�g���̊C��ł͂Ȃ�����ɂ�����^���̊T���I�ȕ]
���ƁA���L���ׂ��j����`�����o���Ă��炤���Ƃɂ������B���̏ꍇ�ł����Ă��A���R�̂��Ƃ�
����A�����d�v�ł��邩�A�ǂ��]�����ׂ����ɂ��āA�킽���⒇�Ԃ����̊ϓ_�ł͂Ȃ��A��
���̊ϓ_�ł����Č��߂Ă��������Ƃ����B
�@���҂����́A�܂������ɂ����āA��J���g���̗��j�́A�����T���߂Ȏp���ŏ������Ƃ��]�܂�
��B�J���g���̂Ȃ��ɂ́A���̘J�g�W���܂߁A�Ɠ��ȐF�����⌾�t�g���𑽂������Ă���
�ꍇ�����邪�A�C�M���X�C���g���ɂ͂����������̂͂Ȃ��B�������A�C�^�Y�Ƃɂ͂���Ȃ��
���ꐫ������ �c�c�S�̂�ʂ��āA���̑g�����J���^�������]�Ȑ܂̂Ȃ��ɁA�ǂ̂悤�Ɉʒu
�Â����邩�������Ȃ���A���̑g���̕��j�⓬�����ǂ̂悤�ɓW�J���������������悤��
������Ƃ��Ă���B
�@���������˗��⎷�M�̈Ӑ}�́A100�N�j�Ƃ��������̗��j�������A���������������Ȃ��ɂ�
������炸�A�\���ɉʂ�����Ă���Ƃ�����B���̂Ȃ��ł��A�`�L��Ƃ��爵���ɂ����A�٘_��
�o�₷��NUS�̑n�ݎ҃n�x���b�N��E�B���\���ɂ��āA�����̌������Ɩ����ʁA�D�]�ƕs�]
�ȂǁA���炢���炢�`���o�����ƣ�ɐ������Ă���B����ƂƂ��ɁANUS���C�^�A���ƍR�����Ȃ�
��A�J�g�W���x���m������ߒ��A�g���̕��j�⓬���ɂ��đg���������ǂ̂悤�ȗ��O��
�����Ă������A������߂����Ăǂ̂悤�ȑΗ������������A�Ȃ��ł���ʑg�����^�����ǂ̂�
���ɍs��ꂽ���ɂ��āA�����̐����ɐ������Ă���B
�@����ɓ������āA���{�I�Ȍ����g���j�Ƃ͈���Ă���Ƃ���́A���ꂼ��̎���̑g������
���ʑg�����̏،���L�^�A���邢�͐V���L�����ӂ�Ɏ�荞�܂�Ă��邱�Ƃł���B
���̂��߁A�����͓�����l�ƂȂ������̂悤�ɁA���̏�O���Ɏv�������ׂ邱�Ƃ�
�ł���B���̍����́A�����̑g�����������͂������c���A�܂��g���L�^����ɕۑ�����Ă�
��A�������������W�����ĕۑ����Ă����Z���^�[(�Ⴆ�A���[�E�B�b�N��w���㎑���Z���^
�[)�����邱�Ƃɂ��B�����������Ƃ́A�C�M���X�l������̗��j�Ɏ��M�ƐӔC�������Ă��邱��
�ɂ�낤�B
�@����ł���Ȃ���A���҂������������ŏq�ׂĂ���悤�ɁA�C�^�Y�Ƃɂ�����J�g�W��
���j�Ɋւ��镶���͖R�����B���̂Ȃ��ŁA���グ���Ă�����̂Ƃ��āA���L�̂��̂�����B
Havelock Willson,My Stormy Voyage Through Life, Co-operative Printing Society,
1925.
Edward Tupper,Seamen's Torch, Hutchinson, 1938.
F.J.Lindop, A History of Seamen's Trade Union to 1929, M.Phil. Thesis, London School of
Economics, 1972.
Basil Mogrides,Militancy and Inter-union Rivery in British Shipping 1911-1929,
International Review of Social History, Vol.6, No.3, 1961. L.H.Powell, The Shipping
Federation:A History of the First Sixty Years,1890-1950,Shipping Federation, 1950.
2)�@���̐���
�@�����������҂����́A�ǎ҂ɔ��f���ς˂悤�Ƃ��鎷�M�p���́A�C�M���X�ɂ�������j�Ƃ�
��̗���ł��邪�A���{�l�̂悤�ɐ��}�ȍ����ɂƂ��Ă͕�����Ȃ����̂ƂȂ��Ă���B����
���A�������A����Ȃ�Ɏj���ɂ��ĕ]����^���Ă���킯�ł����āA�����ɂ��Ă͖���
�����Ȃ���A������Ă����B�܂��A��ʓI�ȃC�M���X�J���^���j�̕��������p���Ȃ���A��
���⋭���Ă����B���̂Ȃ��ł��A1960�N��̈�ʑg�����^���̔�����ANUS�͑傫���ω���
�Ă������Ƃ݂��邪�A���̕ω��̐��i�Ƃ��ꂪ�����E�ɂ��Ď�藧�ĂċL�q����Ă���
�����Ƃ́A����̐��E�̊C���g���^����W�]���悤�Ƃ���Ƃ��A��ρA�ɂ��܂��B
�@���҂����́ANUS�ɂ��Ă͓��ꐫ��F�߂Ă��Ȃ����A�C�^�Y�Ƃɂ͂����F�߂Ă���B��
��ɏ]���A��҂��O�҂�J�g�W�ɉe�����y�ڂ��Ȃ������悤�ɓǂݎ��邱�ƂɂȂ邪�A
�͂����Ă����ł��낤���B�Ⴆ�A���Y�P�ʂ�����ł����������Z�p�����̑D���ɁA�D������
�Ɖ��f�I�Ɉړ����Ȃ���A�Ƃ���Ƃ������ꐫ����A�ۗ����ĎY�Ɖ��f�I�ȘJ�g�W���x��
�m�������Ƃ݂��邪�A���̂��Ƃɂ����đD�����C�O�u�Ђɂ���ĊO���l�D���ɒu���������
��ƁA����炪�ꋓ�Ɍ`�[�����Ă��܂��Ă�����݂�Ƃ��A���҂������J�g�W�_�̐��
�Ƃł��邾���ɕs�v�c�Ƃ�����B���̊֘A�ɂ��čŏ�����O���ɂȂ�������������Ȃ��B
�@����͂��Ă����A���҂����͈˗��͈̔͂ɒ����ł��������߂��A���邢�͎����̐��������
�Ă��A�C�M���X���{��`�Ȃ��ł����̊C�^�o�ς̔��B�ƑD���J���Ƃ̊֘A�Â����R�����B��
�̂��߁A�Ⴆ�Δ��D����D�D�ɕω��������Ƃɂ���āA�D���̘J����i�A����ɘJ���^����
����悤�ɁA�ǂ̂悤�ȉe�����������̂��A�܂����܂����j�ƂȂ��Ă��Ȃ���������Ȃ����A�C�M
���X�D�̊C�O�u�Ђɂ��āANUS���ǂ̂悤�ȕ��j�������A�ǂ����������ɂ��Č@�艺����
��Ă��Ȃ����Ƃ͎c�O�ł���B
�@����ɁA���ꂼ��̎���̒��क़J��������J�����Ԃɂ��Ăӂ��Ƃ��낪���Ȃ��B����
���߁A��ꎟ���E����ANUS���J�g�W���x���m�������ɂ�������炸�A�����Ԃɂ���
�Ē��क़J�������ɖڗ��������P���Ȃ��������ƁA����ɂ���ב���E����A���Ɉ��
�g�����^���̔�����ɂ����Ėڗ��������P�����������Ƃɂ��āA�N���ɎƂ�Ȃ�����
��������B
�@���́wNUS100�N�j�x�́A�����āA�j�����ɂ��Ȃ���A�����]�����邱�Ƃ��Ȃ�ׂ�������
�Ƃ����A���҂����̊�{�I�Ȏp���Ɋ�Â��ď����ꂽ�g���j�Ƃ�����B���������āA���R�̐�
��s���Ƃ��āA���{�ŋc�_����Ă���悤�ȁA�Ƃ��Ƃ��Ĕ��ׂɉ߂���Ƃ�������A�C�M���X�J��
�^���j�̘_�_���������ꂽ�g���j�����Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�����[�߂�̂́A���̐l�X�̉�
��ƂȂ��Ă���B
�@2�@NUS100�N�̕]��
�@���́wNUS100�N�j�x���炦��NUS100�N�ɂ��āA�����Ȋ��z���q�ׂ邱�ƂŁA���ʂ̕]����
�������B���̖{���I�ȕ]���͍���Ɏc�����B
1)�@�D���̑�O�g�D�Ƃ��Ă�NUS
�܂������āA�J���g���͎��{��o�c�ɑ��ċ��ʂ̗��Q���������A���͈̘͂J���҂�g�D
���A������g�����Ƃ��Ēc�������A�g�����������ꂼ��̎����g�����̗v���ɑ�������
�O����j�������Ďw�����Ȃ���A�g�����̗��v�����コ���Ă����^���̂ł���B���̏ꍇ�A�J
���g���͂��ȘJ���҂���̏W�c�Ƃ��đg�D���āA�͂��߂ė͂�������B��������
�āA�܂��J���g���͂ǂ̂悤�Ȕ͈̘͂J���҂��A�ǂ̂悤�Ȍ`�ԂŁA�������ǂꂭ�炢�̐���g
�D���Ă����ǂ����������B
�@NUS�́A�C�M���X�D�ɏ��g�ޑD���A�Ȃ��ł�������g�D�͈͂Ƃ��A���̑S���K�͂̒P��g
�D���Ȃ킿�Y�ƕʘJ���g�����������A������ێ����邱�Ƃ�ڎw���Ă����BNUS�́A���̌���
�ŁA�����ނː��������߂Ă����Ƃ�����B
�@�������A���̑g�������ɂ͏���������A���ꂪ�ł���ނ����̂́ANUS�̑O�g�ł���NAS&
FU���D��g�D�̍U���ɂ��炳��A1893�N�ɔC�Ӊ��U�������Ƃ��グ����B������Č����A
1911�N�X�g���C�L�ɐ������A1919�N���NMB�̊m���ȍ~�A�g���������}���ɑ��₵�A1920�N
�ɂ�100�N�̗��j�̂Ȃ��ōő��99,321�l�A�g�D����70-80�l�ƂȂ����Ƃ݂���B�������A��
���Ԃ̊C�^�s���̂��ƂŁA���ꂪ���炴������Ȃ��������A���C�o���g���̌�ނ̂��ƂŁA
���̑g�������z�����ĒP��g�D�ƂȂ����B���ɂ����ẮA1957�N��97,517�l�_�ɂ��āA
�C�M���X�C�^�̌�ށA����ɔ����C�M���X�D�̌����A����ɋZ�p�v�V�ɂ���g�����̌�����
�Ȃ��ŌX���I�Ɍ������͂��߁A�����ăC�M���X�D�̊C�O�u�Ђ̒ǂ��ł�������A1970�N��50,
000�l����1987�N�ɂ�24,405�l�Ɍ������Ă��܂����B���̌������Ă��܂����g�����̂Ȃ��ŁA��
�v�ȕ���ƂȂ��Ă����t�F���[�D����P&O���[���s�A���t�F���[���c���s�k�������ƂŁA���݂�
��Ɍ��������Ƃ݂���B
�@NUS�ɂ́A1900�N�ォ��1920�N��܂ŁAthe National Union of Ships' Stewards, Cooks,
Butchers and Bakers�Athe British Seafarers' Union�� the Amalgamated Marine Workers'
Union (�����̍Ő����̑g�������́A���ꂼ��1920�N��25,970�l�A1913�N��7,605�l�A1923
�N��12,392�l)�Ƃ��������C�o���g�����������B�����́A��Ƃ��Ďi�~�����̑g�D�ł�����
���A������NUS�Ƃ̑Η��́A�܂��P��g�D���m�����悤�Ƃ���E�B���\���̕��j�ɂ������
�āA�����D���̑g�D�����Ƃ��Ă͂��܂�A����ɃE�B���\���̓ƑP�I�ȑԓx��J�g�����I��
�p���ւ̔����ƂȂ��Ă����B����烉�C�o���g���́A�D��I�ȉ^����W�J���邱�ƂɂȂ邪�A
NUS����v�ȕ�����g�D���Ă��܂��Ă����̂ŁA����ɑ����̑D���Ɍ��W����Ƃ���Ƃ͂Ȃ��
�������B����烉�C�o���g���́A���łɂ݂��悤�ɁANMB�ɂ�����D�������Ǘ��̊m���̂���
�ŁA1920�N�㖖�ɂ͏��������Ă����B
�@NUS���D���̒P��g�D���肦���̂́A�C�M���X�ɂ����čł����ł��D��I�ȘJ���c�̂�
�������Ƃ����C�^�A���ɁA�E�B���\�����R�����������Ƃɂ���B�������A���̒P��g�D�̐�
�ʂł���NMB���m�������ƁANUS�͂�����C�^�A���Ƃ̗ǍD�ȊW�̂��Ƃňێ����悤�Ƃ�
��悤�ɂȂ�B������߂�����́A��q����Ƃ��āA����ł݂��悤�ɁA���̌��NUS�͂�
�̌����ɂ܂ŗ���������Ȃ��܂܁A�C�^�s����ٗp�\���̕ω��ɂ��炳��A���̑g��������
�j�œI�Ɍ������Ă��܂��A�Ō�ɂ͓Ɨ��g�D�Ƃ��Ĉێ����邱�Ƃ�������ƂȂ��Ă��܂����B��
��ɂ�������炸�A�C�M���X�C�^��Ƃ��S�[�C���O�R���T�[�����葱���Ă���Ƃ��A����100�N
��NUS�Ƃ��̑g����=�D���ɂƂ��āA���ł������̂��B
�@���̌��ʂ���݂�悭������悤�ɁA�܂��D���ɂƂ��Ă͘J���͂Ƃ��āA�C�M���X�C�^�o�c
�ɂƂ��ĕK�v�s���ł����Ă��A���ꂪ�R�X�g�v�f�Ƃ��ĕs�K���ɂȂ�Ȃ�����Ōٗp���ꑱ��
�邪�A�����łȂ��Ȃ�A���ł���ւ����ׂ��Ώۂł������B�����āANUS�͑D����s�K��
�ȃR�X�g�v�f�Ƃ��Ă��܂�������̂���g�D�Ƃ��Ė{���A�s�K�v�ł��������ANUS�����������g
�D�ɂȂ�Ȃ�����ɂ����ĒP��g�D�Ƃ��āA�܂��D�����̂��̂������Ȃ�Ȃ����Ԃɂ����đD
���g�D���肦���Ƃ�����B���������W�J�́A�J���g�������{��`�o�ς̂��Ƃł̌o�ώ���c
�̂ɂƂǂ܂����ɂ����āA��̖@���I�Ȑ���s�����������̂ł������Ƃ�����B�����NUS
�݂̂Ȃ炸�A���܂��̘J���g�����u����Ă��闧��Ƃ�����B
2)�@�D���̖���g�D�Ƃ��Ă�NUS
�@�J���g���͑�O�g�D�ł���̂ŁA���ꂪ�g�D���Ă���X�̑g�����̌o�ϓI�ȗ��Q�
���I�ȗ��ꂪ��v���Ă���Ƃ͌���Ȃ��̂ŁA�����̑�����āA�g�������c����������
�������ǂ����������B���̒c���͂��A�g�����̎��R�����I�Ȉӎ����������A�ړI�ӎ��I
�Ȉӎ��̊l����ʂ��Ă���ꂽ���̂ł��������ǂ����������B����ɁA���ꂪ�g��������
���s�������ʑg�����Ƃ̂������ɂ�����ӌ���v�z�̑�����\���ɒ����A���ꂵ�����
�́A�܂��������K��A�g�D�A�^�c�ɂ����ď\���ɕۏႵ����ł̂��̂ł��������A�ꌾ�ł�
���Αg�������`���т���Ă������ǂ����������
�@NUS100�N�j�̑O�����̓E�B���\���̉ƕ������x�z�̂��Ƃɂ�����A���̌㔼���͂��ꂪ
����ɉ��߂�ꂽ���j���Ƃ����Ă悢�B���������ƕ������x�z�́A�E�B���\���̎��_�Ɋ�Â���
�̂ł��������A����������Ă��܂��q�ϓI�ȑg�D�����܂������Ƃ��Ȃ��B�D���J���̓��ꐫ
�Ƃ��āA�D���͂��Ȃ蕪�U���đ����̑D���ɔz�u����A����ɂ����D�������̊C�ɎU�J��
�čq�C���A�������D���̓��E��ސE�₻�̑D�Ԃ̈ړ����������Ƃ��A�D����g�D���邱�Ǝ�
�́A��ςȍ�������A�����g�D�����Ƃ��Ă��A������ێ����Ȃ���K�ȑg���^�c���s��
���Ƃɂ͊i�i�̍H�v���K�v�ƂȂ�B
�@�����������ꐫ���������悤�Ƃ���A������đg�����̈ӎ��̐����𑣂��[�u��A���̈�
���f�����A���邢�͑g���@�ւɎQ��������[�u���s���ł���B�������A�����������Ƃ́A
�E�B���\���ɂ����Ă͊S�̊O�ɂ������Ƃ݂���B���ꂪ�ANUS�ɂ����Ď��グ����悤
�ɂȂ�̂́A1960�N���ʑg�����^�����邢�͑D�����v�^�����������Ă���ł���B���̐�
�ʂƂ��āA���łɂ݂��悤�ɁA�l�X�ȑg�D���v���s���A�g��������NUS�͖���g�D�ƂȂ���
�Ǝ�������܂łɂȂ�B�������A���̉��v�̈�ł������D����\�������A�����̑D���Ŕz�u
���ꂽ���̂́A10�N�������Ȃ������ɐ��ނ��Ă��������Ƃ́A��̓��ꐫ�����邱�ƂȂ���A�g
�����̈ӎ��̐����𑣂��Ȃ���A������c���͂����߂Ă������Ƃɂ��āA�K��������������
����Ƃ͂����Ȃ����Ƃ������Ă���B
�@NUS�ɂ����ẮA�����������Ƃɓw�͂�������A�g�����𗤏ォ��̎w���ɏ]�킹�邱��
�ŁA�c���͂��ێ����Ă������Ƃ���X�����x�z�I�ł������B���̌X���́A���łɂ݂��悤��NMB
�Ƃ������x���m�����ANUS�����������̑g�D���ێ����邱�ƂƓ��`�Ƃ���悤�ɂȂ�������
�ŁA������݂̂悤�ɂȂ�B���̊���������`�ɑ��āA1920�N��ɂ͑D�������h�^���A1960
�N��ɂ͈�ʑg�����^�����邢�͑D�����v�^�����N����B����ɓ������āA����������
���A���क़J�������̉��P�Ƃ��������Ƃ��f�����邪�A���̓��Ȃ�ړI�͌o�ϗv���̊l��
�̑O��Ƃ��Ă̑g�����v���邢�͑g�����剻�ɂ������B�����^�����A���h�̉^���Ƃ��Ă���
�N���Ȃ��������Ƃ͒��ڂ��ׂ��ł��邪�A���ꂪ�P�ɊO�����玝�����܂�Ă������ł͐���
�����邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@�������A1960�N��ȍ~�̉^���́ANUS�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��悤�ł��邪�A����ɓ�������
�̉^���Ƃ��čs����悤�ɂȂ�A��ʑg�����̎x�����L����悤�ɂȂ�B���̌��ʁA�C�M���X
�J���g���̂Ȃ��ɂ����đg�������������łƂ݂��Ă���NUS�ɂ����Ă��A�g�����Q���^��
�g���^�c���s�킴������Ȃ��Ȃ�A���̂��ƂŃX�g���C�L�ɂ���Čo�ϗv�����l������Ƃ����悤
�ɕω�����B�������A���̉^���̃��[�_�[���g�������ƂȂ�A���h�g���̈����`������܂�
�ɂȂ�B���̓_����ANUS100�N���݂�ƁA���҂����������Ă���悤�ɁA�E�B���\���̉ƕ�����
�x�z�Ɗ���������`���m�����A���̂��Ƃőg�����͒����������������ꑱ���Ă������A����
�g�������g���������Ԃ������āA������悤�₭�������A����ɑg���̘H������j���߂���
�āA�g�������Ǝ��s�������ʑg�����Ƃ̓��ꂪ����Ȃ�ɂ�����悤�ɂȂ������j�Ƃ���
��B
�@���̏ꍇ�A���{�Ɣ�r���Č���I�ɈႤ�Ƃ���́A��Ǝ�`�I�ȉ^�����������܂�Ă��Ȃ�
�_�ł���B����͂Ƃ������ANUS�ɑg�������`���m���������_�ɂ����āANUS�����S�̊�@
�ɂ��炳�ꂽ���Ƃ́A���j�̔���Ƃ��킴������Ȃ����A���E�̑D���ɂƂ��Ă��c�O�Ȃ��Ƃł�
�����B
3)�@�o�ώ���c�̂Ƃ��Ă�NUS
�J���g���́A���͈̘͂J���҂�g�D���邱�Ƃł����āA�J���s��ɂ�����X�̘J����
�̘J���͏��i�̌ʎ���𐧌����A�����̏W�c����҂ƂȂ�B���̂��Ƃ��ʊ�ƂɔF��
��������ŁA�J���͏��i�̋����Ƃ��̏����ɂ��Ď�����s���A���̂��Ƃ�ʂ��đg������
���क़J���������ێ��A���P���Ă������Ƃ���^���̂ł���B���̏ꍇ�A���̏W�c������p��
�I�Ȋ��s����x�Ƃ��A����ɂ�葽���̌ʊ�Ƃ��S�����邱�Ƃ��ł���A�����̐��ʂ���
������B���������āA�J���g���́A�ʊ�ƂƂ��̏W�c�Ƃ̂������ŁA�ǂ̂悤�Ȓc�̌���
���s����x��z���Ă������A�����ʂ��āA�ǂ̂悤�ȘJ���͂̋������s����悤�ɂȂ���
���A�܂��ʊ�ƂƂ��̏W�c����A�g�����̌ٗp�̈�����͂��߁A�ǂ̂悤�Ȏ���������l
��������������邱�ƂƂȂ�B
�@NUS�́A�C�^��Ƃ�C�^�A���̊���ȑg���ے�̑ԓx�ɍЂ�����A�����Ɏ����F�m��
���A�c�̌��Ɉ������ނ��ƂɁA�܂������̓w�͂Ƌ]����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̊�
�s���ANMB�Ƃ�����̈��肵�����x�Ƃ��Ĕ��W�����邽�߂ɂ́A����܂���1���A��2�����E
���Ƃ�������Ȃ�]�����K�v�ł������BNUS���A���ׂĂ̊C�^��Ƃ��������c�̌���
�x�ƘJ���͋����@�\�Ƃ��Ă�NMB���l���������Ƃ́A�o�ώ���c�̂Ƃ��Ă̑傫�Ȑ��ʂł���
���B���̐��x�����{�ɂ��A�����ꂽ���Ƃł����炩�Ȃ悤�ɁA���ꂪ�Ȃ���ΐ��E�̊C�^�J�g
�W�̏����x�͂��ڂ��Ȃ����̂ɂȂ��Ă����ł��낤�B�������A����NMB�́ANUS�ɂƂ��Ă�
���̒P��g�D���ێ����Ă����_�ł͂���߂čD�s���Ȑ��x�ł��������A�D���ɂƂ��Ă͌���
�̓�ʐ����͂�ނ��̂ƂȂ����B
�@NUS���A1920�N��A�E�B���\���̉ƕ������x�z�̂��Ƃɂ�����A�c�̌����x�Ƃ��Ă�NMB
���Ă��ɂ��Ē��������s�Ȃ�ꂽ��A�܂����क़J�������̐����������č����Ƃ͂����Ȃ���
���ANMB�͘J�g�����@�\�Ƃ݂Ȃ��ꂴ������Ȃ��Ȃ����B�܂��A�J���͋����@�\�Ƃ��Ă�NMB
�́A���ꂪ�D���{���K�͂Ɗ֘A�Â���ꂽ���Ƃɂ����āA���E�K�����邢�͋����K���̖���
���ʂ����A���̌���őD���̌ٗp����ɂ���Ȃ�Ɋ�^�����Ƃ�����B�������A����ȏ���̂�
�͌����ĂȂ��A�C�^�J�g�ɂƂ��ĕs�s���ȑD����I�ʂ���t�B���^�[�ƂȂ�A�C�^�s���ɓ�����
�Ď��Ɩh�~�̋@�\���ʂ������Ƃ��Ȃ��A�܂��D���̊C�O�u�Ђɓ������āA����ɔ����ٗp����
��e�Ղɂ��Ă����Ƃ�����B�����������Ƃ́A����Ȃ�̏W�c����@�\���������ꂽ�Ƃ��Ă��A
���{��`�o�ς̂��Ƃł́A���ꂪ���炩���ߎ����Ă�����E�����������̂Ƃ�����B
�@�C�M���X�l�D���̒��क़J�������̊�{�I�ȕ����́A�Y�ƕʑS������Ƃ��Ă�NMB�����
����Č��肳��Ă������A���̐����͑�2�����E����Ɍ����Ă݂Ă��A��ʑg�����^����
������Ă��̉��P�ɓ��ݐ�Ƃ��A�@�ւ����̌o�ϗv���R�Ƃ݂Ȃ��Ďx�������
���A���ɋߔN�ɂ����ď�������𗘗p���Ȃ�����P���Ă����Ƃ��������݂Ă킩��悤�ɁA
����J���҂ɔ�ׂď�Ɍ�ǂ��I�ł��������A�܂��C�M���X�C�^�̒n�ʂ̒ቺ���֘A���Ă�
���Ƃ��Ă��A���E�Ɍւ����̂ł͂Ȃ������B����́ANUS���g���������d�����ANMB�����
���萫�ɉߓx�Ɉˑ����Ă������ʂƂ�����B����ɔ��������́A�܂������Ĉ�ʑg�����^��
�̔����Ƃ��āA�܂��}�N���X�L�[���L���������ł����Ă���悤�ɁA������̒���������
�́A�����̌ʋ���̍U�����Ă���B���̋���́A����G�l���M�[�Y�Ƃɂ���ĉ^�c
����Ă���A�V�Q�̉�Ђ���łȂ��A�`���I�ȊC�^��Ђł�����Ă���B�܂��A�D��͊C
�^�Y�Ƃ������Ă���D�������@�\����A����Ɏ���������飂Ƃ��������ԂƂ��Č��ꂴ
����Ȃ������B
4)�@�Љ���v�c�̂Ƃ��Ă�NUS
�@�J���҂́A�o�ϓI�ȗ��Q����łȂ��A�l�X�ȎЉ�I�A�����I�ȗ��Q�������Ă���B�J���g
���́A�����̌���Ɏ��g�܂�������Ȃ��B�����̌���́A���Y�Y�Ƃ̘J�g�̗͊W��
�Ƃǂ܂炸�A�ꍑ�ɂ�����J�g�̗͊W����т����ƍ��ƂƂ̊W�ɂ���č��E�����B��
����ʓI�ɂ��A�S�̓I�ɂ��L���ɂ��邽�߁A�J���g���͑��̘J���g������łȂ��A�J��
�Ґ��}�A�e�틦���g���ȂǂƘA�т��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̌o�ϓI�A�Љ�I�A�����I�ȗv��
�����ƂɎ����o���Ă����F�߂����A����ɐi��Ŏ���ɂƂ��Ė]�܂���������Njy���������
�Ȃ��B���������āA�J���g���͌o�ώ���c�̂ɂƂǂ܂肦���A�Љ���v�c�̂Ƃ��ĉ^��������
�����Ȃ��B�����ŁA���Y�J���g�����ǂ̂悤�ȘJ���ҘA�т��s���Ȃ���A�Љ���v�^���ɎQ��
���Ă������A���̏ꍇ�A���Y�J���g�����ǂ̂悤�Ȑ����I�ȗ������j�ł����āA����ɖ]��
�ł������A���̌��ʂƂ��āA�ǂ̂悤�Ȑ��ʂ��グ�Ă�����������邱�ƂƂȂ�B����������
�_�ɂ��ĉ������̂ɂ́A�j�����s�\���ł͂��邪�A���̂��Ƃ͊m���ɂ�����B
�@NUS�́A19���I�Ō�̎l�����ɂ�����V�g���^���̈ꗃ���`�����A�J���ҘA�т��L���A��
�̍��g�ɍv�����Ă������A���ۓI�ɂ�ITF�̐ݗ��ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă����B���̂��Ƃɂ�
���āA�E�B���\���͒����ȑg�������Ƃ��Ė����͂����B�������A��1�����E����ANUS�̒n��
��NMB�̐ݗ��ɂ����܂��Ĉ��肷��悤�ɂȂ�A�܂��J���}���Љ��`�j�̂��̑����ATUC��
�D��I�ɂȂ��Ă���ƁANUS�͂����̉^���ɔ����闧����Ƃ�A�����g�����x������܂�
�ɂȂ��Ă����B����́A�E�B���\���̘J�g��������Љ��`�Ƃ����v�z��M���Ɋ�Â����̂ł���
���B�������A1930�N��ATUC�ƘJ���}���E�������ƂŁANUS�ɂ����������̂ƂȂ�
�Ă������B���������o�߂��݂�ƁA�E�B���\���͂����������Ԃ���肵�Ă������ƂɂȂ�B
�@���̌�ANUS�̓C�M���X�J���^���̗���ɉ������������݂���ɂƂǂ܂�A�܂���g���ɂ�
����炸�A���̎嗬�ɗx��o�邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă������B�������A�������Ȃ�o�߂���1960�N
��A��ʑg�����^�����N����Ȃ��ŁANUS�͑傫���ω����A�J���}���{�̐����TUC�̎w��
�ɔ�����s�����Ƃ�悤�ɂȂ�B�܂��A�E�B���\�����炷��Γ{��̑ΏۂƂ������鍶�h������
�g���g�b�v�ƂȂ�ANUS�̓C�M���X�J���g���̂Ȃ��ō��h�g���Ɩق����܂łɂȂ�B��������
NUS���g�̕ω���1970�N��O��̘J���^���̍D�퉻�̂��ƂŁA�E�B���\������̕��̈�Y��
���Ē������������A���̐������Ȃ���Ή�������邱�Ƃ̂Ȃ��C�^�@���啝�ɉ�����
��Ă����B�������A���̌�ɂ����āANUS�����i�ɍD��I�ȕ��j���̗p���Ă���킯�ł͂Ȃ���
���ł���B
�@���{��`���Ɛ�i�K�ɓ���ƁA�ʑg����i�V���i���Z���^�[�͍��{�I�ɎЉ���v��i��
�悤�Ƃ���H���ƑQ�i�I�ɎЉ���v��i�߂悤�Ƃ���H���̂ǂ��炩�̐F���������悤�ɂ�
��A���̂������őΗ����N����B�������ANUS�̗��j���݂�悤�ɁA�J���g���͈��̘H����
��������̂ł͂Ȃ��A�ϖe�𐋂���B���̕ϖe���A�ǂ̂悤�Ȍ_�@�ŋN���邩�́ANUS�̗�
�j���݂Ă����炩�Ȃ悤�ɁA�܂������Ĉ�ʑg�����̓����ɂ������Ă���A������\������g
���������g�������Ɉ���Ă��邩�ǂ����ɂ������Ă���悤�ł���B�܂��A�ߔN�ɂ�����NUS
��TUC�Ƃ̑Η����݂�Ƃ��A�ʑg���̓i�V���i���Z���^�[�̘H���ƈ�v���Ȃ��Ă����킴���
���Ȃ��B����炪�S�����x���ň�v���邱�Ƃ́A�ŋ߂̕��G�Ȑ����o�Ϗ̂��Ƃł͍��
�𑝂����邩�ɂ݂��邪�A������������邱�ƂȂ����āA���̂ǂ���̑��ɂ��W�]���Ȃ���
�Ƃ��������Ƃ�����B
5)�@NUS100�N�̋��P
�@�Ō�ɁANUS��100�N�̗��j�ɂƂ��āA�܂����E�̑D���ɂƂ��Ă��A�ő�̖��ł���Ȃ�
��A����ɑΉ��ł��Ȃ��������Ƃɂ��Ăӂ�A���߂�����Ƃ������B���ꂪNUS100�N�ɂƂ���
�́A�܂�����ɂȂ��鋳�P�Ƃ�������̂ł���B����͂����܂ł��Ȃ��A�Z�O���l�D����
�X�u�БD(FOC)�̖��ł���B�����̖��ɂ��āA�wNUS100�N�j�x�ɂ����Ă͖��m�ȋL
�q���݂��Ȃ��͎̂c�O�ȂƂ���ł��邪�A���悻�A���̂悤�ɂ�����B
�@NUS�ɂƂ��ẮA�C�M���X�D�ɂ�����Z�D���̂����A���[���b�p�l�ɂ��ẮA�����g
�D���邱�Ƃ�ʂ��āA���̘J���������C�M���X�l�Ɠ���ɂ��邱�Ƃŏ������Ă����B���C���h�l
���Ă͂����g�D������A�܂����̘J�������ɂ��Ċ֗^���悤�Ƃ����l�q�͂Ȃ��B��1����
�E����A���[���b�p�l�D�����������Ă��܂��A�܂����C���h�l�D���̐E�킪�ŏ���������
�����̂ł��������߁ANUS�͂��̖{�i�I�ȏ��������Ȃ��ł��܂��Ă����B�����ɂ́A��p�鍑
�̐A���n�x�z�Ƃ�������I�w�i���Ђ����Ă����Ƃ݂���B���������o�߂��A�����P�ɃC�M��
�X����łȂ��A���E�ɂ�����Z�D���̖��A�����FOC�̖����������Ă����ɓ�������
�́A�傢�Ȃ�Ѝ��ƂȂ����Ƃ�����B
�@NUS�ɂƂ��āAFOC�̖��́A�C�M���X�C�^���O���ԊC�^�Ƃ��Đ������Ă�������ŏd��Ȗ�
��ł���A�܂����E�̊C���g���̃��[�_�[�Ƃ��Ă��A���̏����͎���ɉۂ���ꂽ�傫�Ȗ��
�ł������B����ɑ��āANUS��ITF��FOC�{�C�R�b�g�^����ITF��������^���ɂ��āA����
���S�I�������ʂ����Ă����B�����́A�����Њ�Ƃɑ�����I�ȍ��ۘA�щ^���Ƃ��āA
���Ȃ�̐��������߂����̂Ƃ��ĕ]�����ꂤ����̂ł���B�������A1970�N��㔼�AFOC������
�Ă̐�i�C�^���ɖ������悤�Ƃ��Ă��Ƃ��ANUS�̑g��������ڂ��Ă���悤�ɁA���E�̊C��
�g���Ɍx����炵�A�V�������j��ł��o���āA�f�ł��铬���܂Ȃ��������Ƃ��ANUS��
�݂Ȃ炸��i�C�^���̊C���g���̒����̌����ɂȂ����Ƃ�����B���̐ӔC�͂ЂƂ�NUS�ɋA
�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�����ANUS��1960�N��ȍ~�A�ϖe�����Ƃ݂���ɂ�������炸�A�����
�͂Ȃ�����Ȃ�ϖe���K�v�ł��������Ƃ�m�肤��B
�@��������NUS�̌��E�́A����܂��ЂƂ�NUS�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��A��i�C�^���̊C���g����
�܂߁A���E�̘J���^���������E�ł�����B���̌��E�Ƃ͉����B���̓����́ANUS100�N��
���j�ɂ����āA���łɗ^�����Ă���B�C�M���X�D(�ȉ��A���{�ɒu�������Ă��悢)���C�O�u
�Ђ���FOC�ƂȂ�A����ɓr�㍑�l�D�����z�悳���悤�ɂȂ������ƂŁANUS�͂��̑g����
�������I�Ɍ��������A���̉^�A�J���g���ƍ�������������Ȃ��Ȃ����B����́A�C�^��Ƃ���
�X�u�ЂƂ����s�����Ȑ��x�𗘗p����悤�ɂȂ������Ƃɂ���āA�C�M���X�l�D�����J���s��
�ɂ�����r�㍑�l�D���Ƃ̏A�J�����ɔj��ANUS���o�ώ���c�̂Ƃ��Ă̗����D��ꂽ��
�Ƃɂ���B����́A���ۓI�ɂ͒P���Ȍo�Ϙ_���ɂ������������̂̂悤�ɂ݂��邪�A�����Ă���
�ł͂Ȃ��A���{��`�o�ς����Ƃ₻�̐��x�ɂ���Ĉێ�����Ă��邱�Ƃ̈�ł���A�o�ϊO
�I���x��}��Ƃ����o�Ϙ_���ɂ������������̂ł���B���������Ӗ��ł̌o�Ϙ_���ɖ|�M����
�����Ă����̂��ANUS��100�N�Ƃ�����B
�@���܁A������������悤�Ƃ���ANUS����łȂ����E�̊C���g�����P�Ȃ�o�ώ���c��
���葱���Ă������Ƃ���E�炵�A�Љ���v�c�̂Ƃ��Ă��傫���������邱�ƂȂ����Ă��肦�Ȃ���
�ƂƂȂ�B���̂��Ƃ��ANUS�͂��̗��j�ɂ����ďؖ����Ă݂����Ƃ�����B���E�̑D���́A����
�����P�Ƃ��āA�V���ȓ����������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̈�̓����́AUNCTAD�̉^��
���������V���ۊC�^�����ł��낤�B����́A��i���A�r�㍑�̘J���^���̋��ʂȉۑ�Ƃ��āA
�܂������A���ۂɂ����铯�����ȉ^���Ƃ��Ď������Ă����ɈႢ�Ȃ��y1�z�B
�m���n
�y1�z�@���̎�̃q���g�́A�ٍe�����C�^�̓W�]�Ɖۑ裎��z��A�J�{�m�i�Ғ��w����C
�^�_�x�A237-247�߰�ށA�Ŗ��o������A1991�Ɏ����Ă���B
���o�����F���薼�A�w�C���Y�ƌ�������x 319,322,327�@1993�N1��,4��,9��
 �z�[���y�[�W�� |
 �ڎ��ɖ߂� |
 �擪�ɖ߂� |