 �z�[���y�[�W�� |
 �ڎ��ɖ߂� |
| |
���X�N�]��̓������@������L��
�@�w�������@����s�L�x�́A�Ō�̎g�߂ƂȂ������a�̌����g�̈�s�ɁA���v�m�Ƃ��ĎQ�������A�~�m�i���m�A794-864�j�̎��M���L�ł���B�Ȃ��A���v�m�͒Z���Ԃ̓����������ł���A�����؍݂̗��w�m�i�w��m�j�Ƌ�ʂ��ꂽ�B
�@�ނ̗����́A�u���������̓V��@�̑m�B�(�������)�͎��o��t�B����(������)�̐l�B15����b(�Ђ���)�R(���)�ɂ̂ڂ�A�Ő��Ɏt�������B838�N(���a5)�����A�g�B�A�����ȂNJe�n��������V��w���܂ȂԁB847�N(���a14)��560�����܂�̌o�T�������ċA���B���̌�͑�3��̓V�����(����)�ƂȂ�A�V�䖧���̊�b��z�����v�iMicrosoft�@Corporation�@Encyclopedia2001�j�B
�@���̓��L�͊����ł���B���̂��ߌ���Ƃ��Ă͖��K�v�ƂȂ�B���̕W�����́A�~�m���A������Z�A�����Ǔ��⒍�w�������@����s�L�x�P�A�Q�A���}�Г��m����157�A442�A 1970�A1985�i�ȉ��A�����w�����L�x�Ƃ���j�ł���B
�@���̑������͒���̕���̂ƂȂ��Ă���A����Ɍ���́i�����j�̖��K�v�ƂȂ�B ���̖Ƃ��Ď��̂��̂����p����Ă���B�~�m���A�[�J�����w�������@����s�L�x�A�� �����ɁA1990�i�ȉ��A�[�J��w����s�L�x�Ƃ���j�B����͌����Ƃ̑Ζ�ƂȂ��Ă���B
�@�w�������@����s�L�x�͑S4���ƂȂ��Ă��邪�A�����w�����L�x�ł�23�̏͗��Ă��s��� �Ă���B�ȉ��A���̏͗��Ăɑ����āA��v�ȊC���������グ��B
�@��܂��ȗ���́A�����́y���a�����g�N�\�z���A�Q�Ƃ��ꂽ���B
�@�w�������@����s�L�x�́A�Ō�̎g�߂ƂȂ������a�̌����g�̈�s�ɁA���v�m�Ƃ��ĎQ�������A�~�m�i���m�A794-864�j�̎��M���L�ł���B�Ȃ��A���v�m�͒Z���Ԃ̓����������ł���A�����؍݂̗��w�m�i�w��m�j�Ƌ�ʂ��ꂽ�B
�@�ނ̗����́A�u���������̓V��@�̑m�B�(�������)�͎��o��t�B����(������)�̐l�B15����b(�Ђ���)�R(���)�ɂ̂ڂ�A�Ő��Ɏt�������B838�N(���a5)�����A�g�B�A�����ȂNJe�n��������V��w���܂ȂԁB847�N(���a14)��560�����܂�̌o�T�������ċA���B���̌�͑�3��̓V�����(����)�ƂȂ�A�V�䖧���̊�b��z�����v�iMicrosoft�@Corporation�@Encyclopedia2001�j�B
�@���̓��L�͊����ł���B���̂��ߌ���Ƃ��Ă͖��K�v�ƂȂ�B���̕W�����́A�~�m���A������Z�A�����Ǔ��⒍�w�������@����s�L�x�P�A�Q�A���}�Г��m����157�A442�A 1970�A1985�i�ȉ��A�����w�����L�x�Ƃ���j�ł���B
�@���̑������͒���̕���̂ƂȂ��Ă���A����Ɍ���́i�����j�̖��K�v�ƂȂ�B ���̖Ƃ��Ď��̂��̂����p����Ă���B�~�m���A�[�J�����w�������@����s�L�x�A�� �����ɁA1990�i�ȉ��A�[�J��w����s�L�x�Ƃ���j�B����͌����Ƃ̑Ζ�ƂȂ��Ă���B
�@�w�������@����s�L�x�͑S4���ƂȂ��Ă��邪�A�����w�����L�x�ł�23�̏͗��Ă��s��� �Ă���B�ȉ��A���̏͗��Ăɑ����āA��v�ȊC���������グ��B
�@��܂��ȗ���́A�����́y���a�����g�N�\�z���A�Q�Ƃ��ꂽ���B
 |
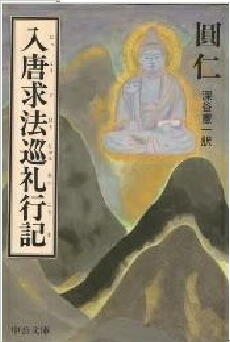 |
�������o�����āA���]�͌��ɕY����
�@�u��P��1�@�����g���̉ߊC�v�͔����o�����璷�]�͌��Y���܂ł̍q�C���܂Ƃ߂��Ă���B
�@���̏��a�̌����g�́A���ł�836�N�A����ɗ��N�ɁA�n�C�����݂������s���Ă����B�l�̑D�����A��3���͏o���O�ɓ�j���ėp���Ȃ����A�܂���2���͕��g����⹂̕a�C�i���͉��a�A��D�����A�Z���̉��������ƂȂ�j�𗝗R�ɏo���ł��Ȃ������y��1�z�B���̂��߁A��1���Ƒ�4�����������q���邱�ƂƂȂ�A�O�҂Ɍ�����g������k�A�~�m�i���o��t�j�Ȃǂ��捞�ށB
�@838�i���a5�j�N6��13���A��s�͔����ŏ�D���邪����������ꂸ�A3���ԑؑD����B18���u�����܂ōs�����A������5���ԕ��҂�����B22���ܓ��̉F�v���ɒ����A�����u�����œ��ɍs�����Ɠ��{�ɗ��܂�҂��݂��ɕʂꂽ�B�ߌ�6���ɂȂ邱��A�����グ��C��n��ׂ��o�q�����B�k���̕��������A��ɂȂ��ĈÂ��Ȃ���i�B��1���Ƒ�4����2�D�͂��݂��ɉΓ�₽���܂������A���ΐM�������킵�������v�i�[�J��w����s�L�x�Ap.20�j�B���́u���{�ɗ��܂�ҁv�͒P�Ȃ錩����l�ł���B
�@6��24���ɂ͍q�s���S�F�肪�s��ꂽ�B��1���͑�4�����������B27���ɂ́u�D�̂̋��p��������Ɏg���Ă���S�̔��A�g�̏Ռ��őS���E�����Ă��܂����v�i�[�J��w����s�L�x�Ap.22�j�B���̓S�́u�v����ی삷�邽�߂ɁA�\�ʂ����̓S�Ёv�ƒ��߂���Ă���i�����w�����L�x�P�Ap.12�j�B28���A�o���㑁����5���ڂɑ嗤���݂ɐڋ߂������悤�ŁA�C���͉��D�����ƂȂ�B���̂Ƃ��A�V���l�ʖ�̋����삪�����Ɖ͌��ɂ��Đ������s���Ă���B��g�́A���[��5�q�i9Ұ�فj�ƂȂ�A���ʂ������B
�@�u�����������Ă��邤���ɁA������̕���������ɐ����Ă��đ召�̔g�������҂藧���A���͋}������o���đ��x�𑝂��A�Ƃ��Ƃ��ɂ̂�グ�Ă��܂����B����Ăӂ��߂��Ă����ɔ������낵�����A�ǂ�2�x�ɂ킽���Ă������܂�A�g�����Ɛ��̗�������݂��ɓ˂��Ă��Ĕ����X�����B�ǂ��͊C��ɒ����A����䃁i�㕔�j�͂��܂�܂��ɔj�ꊄ���悤�Ƃ��Ă���B�����ŁA��ނȂ����������đǂ��̂ĂĂ��܂��ƁA���͑�g�ɂ��������ĕY�����͂��߂��v�B����ɁA�u�D���i�A�J�j���D���ɂ��ӂ�o���A�Ƃ��Ƃ����͒���ō��y�̏�ɏ���Ă��܂����B�D��ɂ͊����E�����̂��ꂱ�ꂪ�D���̂܂ɂ܂ɕ����蒾�肵�Ă���v�Ƃ����L�l�ƂȂ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.24-5�j�B
�@�V��2���A�挭���Ă����ˎ�i�x�����j�y��2�z�p���J�R���A���Ă��āA���]�͌��̗g�B�C�ˌ��������K�c�S�����L���ɓ������Ă��邱�Ƃ�����B�u�������ɁA���m���ȁn�q�D�ɓ��{������̍v�������ڂ��A�^��1�l�A�m��D���i�D�Ǘ����j2�l�A�w��m�~�ځi�~�m�Ɠ������A�Ő��̒�q�j��ȉ��A27�l�����l�ɏ��ڂ�A����ڎw���ďo�������v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.28�j�B
�@�����A�u�ߑO2�����뒪�������Ă���B�q�H��m���Ă��鐅��ē��D�ɑO����U������A�@�`���ɂ������B�ߑO10�����딒�����ɒ����ƁA���̋t��������߂Č������B�哂�l3�l�Ɠ��{�̐����炪�D�𗤏ォ��g���ė��������݂ɓ����A�Ƃ��ÂȂ�����ł��炭�̊ԁA���������Ă����̂�҂����v�Ƃ���B�����ő�4�����R�������k���̟݊C�ɕY���������Ƃ��i�[�J��w����s�L�x�Ap.32�j�B
�@�u��P��1�@�����g���̉ߊC�v�͔����o�����璷�]�͌��Y���܂ł̍q�C���܂Ƃ߂��Ă���B
�@���̏��a�̌����g�́A���ł�836�N�A����ɗ��N�ɁA�n�C�����݂������s���Ă����B�l�̑D�����A��3���͏o���O�ɓ�j���ėp���Ȃ����A�܂���2���͕��g����⹂̕a�C�i���͉��a�A��D�����A�Z���̉��������ƂȂ�j�𗝗R�ɏo���ł��Ȃ������y��1�z�B���̂��߁A��1���Ƒ�4�����������q���邱�ƂƂȂ�A�O�҂Ɍ�����g������k�A�~�m�i���o��t�j�Ȃǂ��捞�ށB
�@838�i���a5�j�N6��13���A��s�͔����ŏ�D���邪����������ꂸ�A3���ԑؑD����B18���u�����܂ōs�����A������5���ԕ��҂�����B22���ܓ��̉F�v���ɒ����A�����u�����œ��ɍs�����Ɠ��{�ɗ��܂�҂��݂��ɕʂꂽ�B�ߌ�6���ɂȂ邱��A�����グ��C��n��ׂ��o�q�����B�k���̕��������A��ɂȂ��ĈÂ��Ȃ���i�B��1���Ƒ�4����2�D�͂��݂��ɉΓ�₽���܂������A���ΐM�������킵�������v�i�[�J��w����s�L�x�Ap.20�j�B���́u���{�ɗ��܂�ҁv�͒P�Ȃ錩����l�ł���B
�@6��24���ɂ͍q�s���S�F�肪�s��ꂽ�B��1���͑�4�����������B27���ɂ́u�D�̂̋��p��������Ɏg���Ă���S�̔��A�g�̏Ռ��őS���E�����Ă��܂����v�i�[�J��w����s�L�x�Ap.22�j�B���̓S�́u�v����ی삷�邽�߂ɁA�\�ʂ����̓S�Ёv�ƒ��߂���Ă���i�����w�����L�x�P�Ap.12�j�B28���A�o���㑁����5���ڂɑ嗤���݂ɐڋ߂������悤�ŁA�C���͉��D�����ƂȂ�B���̂Ƃ��A�V���l�ʖ�̋����삪�����Ɖ͌��ɂ��Đ������s���Ă���B��g�́A���[��5�q�i9Ұ�فj�ƂȂ�A���ʂ������B
�@�u�����������Ă��邤���ɁA������̕���������ɐ����Ă��đ召�̔g�������҂藧���A���͋}������o���đ��x�𑝂��A�Ƃ��Ƃ��ɂ̂�グ�Ă��܂����B����Ăӂ��߂��Ă����ɔ������낵�����A�ǂ�2�x�ɂ킽���Ă������܂�A�g�����Ɛ��̗�������݂��ɓ˂��Ă��Ĕ����X�����B�ǂ��͊C��ɒ����A����䃁i�㕔�j�͂��܂�܂��ɔj�ꊄ���悤�Ƃ��Ă���B�����ŁA��ނȂ����������đǂ��̂ĂĂ��܂��ƁA���͑�g�ɂ��������ĕY�����͂��߂��v�B����ɁA�u�D���i�A�J�j���D���ɂ��ӂ�o���A�Ƃ��Ƃ����͒���ō��y�̏�ɏ���Ă��܂����B�D��ɂ͊����E�����̂��ꂱ�ꂪ�D���̂܂ɂ܂ɕ����蒾�肵�Ă���v�Ƃ����L�l�ƂȂ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.24-5�j�B
�@�V��2���A�挭���Ă����ˎ�i�x�����j�y��2�z�p���J�R���A���Ă��āA���]�͌��̗g�B�C�ˌ��������K�c�S�����L���ɓ������Ă��邱�Ƃ�����B�u�������ɁA���m���ȁn�q�D�ɓ��{������̍v�������ڂ��A�^��1�l�A�m��D���i�D�Ǘ����j2�l�A�w��m�~�ځi�~�m�Ɠ������A�Ő��̒�q�j��ȉ��A27�l�����l�ɏ��ڂ�A����ڎw���ďo�������v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.28�j�B
�@�����A�u�ߑO2�����뒪�������Ă���B�q�H��m���Ă��鐅��ē��D�ɑO����U������A�@�`���ɂ������B�ߑO10�����딒�����ɒ����ƁA���̋t��������߂Č������B�哂�l3�l�Ɠ��{�̐����炪�D�𗤏ォ��g���ė��������݂ɓ����A�Ƃ��ÂȂ�����ł��炭�̊ԁA���������Ă����̂�҂����v�Ƃ���B�����ő�4�����R�������k���̟݊C�ɕY���������Ƃ��i�[�J��w����s�L�x�Ap.32�j�B
 |
| |
���g�B�Ɉړ��A��g�A�����Ɍ�������
���ł͋���������Ă���̂ŕ������Â炢����݂��ɑ傫�Ȑ����o�������A���Ȃ葁�����x���i�ށB�^�͂̕���2��]�i��6Ұ�فj�A�Ȃ��邱�ƂȂ��^�������ɗ���Ă���B���ꂪ�A���̗L�����@�̏�邪�@���炵�����̂ł���v�Ə����c���i�ȏ�A�[�J��w����s�L�x�Ap.35-6�j�B
�@������g���當�������āA�u����̕Y�����ɔj��������1���͕X�̂��莟��A���ǒn������ԕ����ɊĎ����Ă��炢�A���̔��̏��g�݂̐����͐����������߂āA�S���㗤�o��������B�c������҂������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ����Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.37-8�j�B
�@�u3�@��t���͊J�����Ɋ�h���āA�V��R�Ɏ���Ƃ𐿂��v�́A������g���~�m�����̓��R�����ɔ[�߁A�����Ɍ����o������܂ł̋L���ł���B
�@���N8��8���A���łɗ��Ă������ɉ����A�u��4���͂Ȃ��D�̏�ɋ���A���܂��ɒ┑���������Ă��Ȃ��B���{������̍v���i���܂��^�їg�����Ă��Ȃ��B���̔��̒���͂͂��ꗎ���āA�D���͓D���łقƂ�Lj�t�ɂȂ�A���̊����ɂ��������đD�q�̐����Ђ��āA���͓D�̏��ɏ�����萅���ɒ���ŁA�قƂ�Ǎq�C�̖��ɂ͗����Ȃ��Ȃ��Ă���B���@�m�i�~�s�m799-852�n�E��Łj��͂܂��㗤���Ă��Ȃ��B�D���̔����i�����P��j�͏㗤���ĊC�ӂ̋��t�̉Ƃɂ���B�D���̐l5�l�͑̂��ӂ����Ŏ��v���Ƃ��m�炳���i�[�J��w����s�L�x�Ap.52�j�B
�@8��10���A�V���l�ʖ�̖p��������A�o�������Ă�����2�����C�B�i�]�h�ȓ��C���j�ɒ������Ƃ����莆���A��1���̋�����̂��Ƃɗ���B��q�̒ʂ�A���̑�2���݂̂����낤���ē��{���A�蒅���B���̏�D�҂̊��l��������g��s�ƍ����������ɂ݂��邪�A���炩�łȂ��B
�@8��17���A�ԗ��ɂ������Ă����A�D�t�i�D���j�������������ʁB��i�͏]�҂Ɏ�������B�����A��1���ɔh�����Ă������D���̗k���C���}���A���ė��āA���v�������S�p���@�`�Ŏ���ł����Ƃ����B8��24�A��4���̔�����s��30�ǂقǂ̏��D�ɏ���Ă���Ă���B
�@10��5���A������g��͗g�B���Ɍ����o�����邪�A�u�������銯�l�͑�g1�l�i�������b��k�j�A���������i���������j�A���������i�����P��j�A���x�^���i���x�S���j�A��_�^���i��_�@�Y�j�A���ʎ��i���N�Y�j�A�ʐ��v���i���ʌ������j���{��Y�A�^�����v�m�~�s��A����ɎG�E�i�e��̐E�����j�ȉ�35�l�A���D��5�z�v�ł������i�[�J��w����s�L�x�Ap.70�j�B
���J�����Ɋ�h�A�n���[�a�������遥
�@�u4�@��g�̋A�҂܂ŊJ�����ɂ���ē��V��R�̒�����҂v�̓��e�̓^�C�g���ʂ�ł���B
�@�~�m�́A10��22�������A�n���[�a���i����74.7�N�A[�ʏ�͖�76�N������]�j������B�������A�u���ɂȂ��ĕ�������o�āA���̜a��������ƁA����̋�̋��ɂ����Ă��̔��͐����w���Ă���A���͂���߂ăn�b�L���ƌ������B�������炱���]����ƁA���̒����͑S�̂�10��i��30Ұ�فj���������B�ǂ̐l���F�A����͕����m�����n�̌����Ӗ�������̂ɈႢ�Ȃ��ƌ������v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.77-8�j�B���̌���A�ނ͓��H�A���H�A���Ƌ����̐ڋ߂Ȃǂ̓V�����ۂɂ��т��ё������Ă���B
�@���{���o�������N��12��18���A�������V���l�̒ʖ����������āA�u���H�̑�1���E��4���̔j���̓x���傫�������̂ŁA�������g�̋A���̑D�����߂邽�߂ɁA�^�B�i�̂��̟̈��j�Ɍ��������o���v�����Ă���B���̒���Ɍ�����g�������ɒ������Ƃ����A��������i�[�J��w����s�L�x�Ap.102�j�B
�@�����āA�N�����܂���839�i���a6�j�N�̉[����4���ɂ́A�u�V���l�̒ʖ������̗v���ōw�������D���C�������邽�߂ɁA�H���̊ēA��H�A�D�H�A�b�H�i�������j��36�l��^�B�Ɍ����o���������v�Ƃ���i�[�J��w����s�L�x�Ap.120�j�B���̈���A���̗����ɂ́u���{�̒��v��1���ɐ������Ă�������A�ˎ��60�]�l�̒N���ނ����A�F�a���ɓ|��ꂵ��ł���v�Ƃ���i�[�J��w����s�L�x�Ap.121�j�B
�@1��8���A���{�ꂪ���ɂ悭�킩��u�V���l�̉����Ƃ����҂�����ė����̂ʼn�����B�ނ͓��{�̍O�m10�N�i819�j�ɏo�H�̍��ɗ��ꒅ�������̐l���o�ς�Ɠ����D�ɏ���Ă����Ƃ����B�Y������������ƁA�����������B�w���낢��ȕ�����{�ƌ������邽�߂ɁA���̗g�B�𗣂�đ��C��n�������A�����܂��\���ɋ����ė�����邱��3�����A�o�H�̍��i�R�`���j�ɕY�������B�������o�όZ��2�l�͂܂��ɏo�q���悤�Ƃ���Ƃ��ɂȂ��āA2�l�Ƃ������悤�ɑD����E�����o�H�̍��ɋ������Ă��܂����B���ǂ��͖k�o�H���甭���Ėk�C�i���{�C���j���q�C���A�K���ɂ��D���Ɍb�����15���Œ���̍��i�R�����j�ɗ��ꒅ�����v�Ƃ����b�ł������i�[�J��w����s�L�x�Ap.110�j�B
�@�u���̐l���o�ς�v�Ƃ��i�V���l�Ƃ݂Ă悢�j�A�u�o�H�̍��i�R�`���j�ɕY�������v�Ƃ��A�u�D����E�����c�c���������v�Ƃ��������A�����g��s�������˂��Ă̌��t�g���ł��낤�B�V���l���l�͖k��B�݂̂Ȃ炸�A���k�̍����Ƃ���Ζ��f�Ղ��s���Ă������Ƃ��������B
���V���D��9�Ǎw�����āA�A���̉^�тɁ�
�@�u5�@�����g�͒�����\�킸���đ^�B�ɋA��C�B���ߊC���v�̓^�C�g���ʂ�ŁA�~�m�����u��f�O�����邦�Ȃ��ƂȂ������Ƃ�������Ă���B
�@2��6���A�g�B�̖������V�q�̒��ɂ��������āA�����g�ߒc�̗g�B�c����270�l���ꂼ��ɁA�������琅��Ɏ���܂Ť��5�D(1�D=12Ұ��)��\(��)�Ƃ��Ďx�����Ă����Ƃ��������270�l�́A���̎��_�ŗg�B�Ɋ��Ă�����1���Ƒ�4���̏�D�҂ł����āA������^�B�Ȃǂɔh������Ă������̂͊܂܂�Ă��Ȃ��B�Ȃ��A��2���͂��łɂ݂��C�B�i�]�h�ȓ��C���j�ɗ��܂��Ă����Ƃ݂��邪�A���D�̔��������L���͒����Ŏ��S�������ƂɂȂ��Ă���B
�@�����g��838�i���a5�j�N12��3�������ɓ������A��839�i���a6�j�N1��13���Q�����A�[1��4�������𗣂�A2��12���^�B�ɖ߂��Ă����B�������A�~�m�ɂƂ��Ė��O�Ȃ��ƂɁA���{�m�����̋��A�����Ă͉~�ڂ݂̂��V��R�ɓ��邱�Ƃ�������A�~�m�Ȃǂ��ׂĂ̑m�͖{���ɋA�҂�����̂�����Ƃ����A�����ƂȂ��Ă����B28���A�~�ڂƂ��̏]��2�l�͈�s�ƕʂ�A�V��R�Ɍ������B������A�ނ�40�N�����ɗ��܂�A877�N�A���̍ۂɑ���Ď��S����B
�@�g�B�ɂƂǂ܂��Ă������l��m�����́A10�ǂɕ��悵�đ�^�͂��g���đ^�B�܂ōs���āA��g��s�ƍ������邱�ƂƂȂ����B�����O�ɂ��āA���N2��22����4���̎ˎ�1�l�A����2�l�����l���\�s�����Ƃ��đߕ߁A���u���ꂽ���Ƃ��͂��߂Ƃ��āA�����g��s�̉��l���������Ղ��߂����Ă������̃g���u�����N����i�ڍׂ͌�q����j�B�ߕ߁A���u���ꂽ�l�X�����Ƃ���A2��22���A�o������i�[�J��w����s�L�x�Ap.134�j�B
�@�����g�́A�V�q����9�ǂ̑D���ق��ďC�����邱�Ƃ�F�߂��Ă������A������Z����̎w�E�ɂ��A����Ɍ������V���D���w�������悤�ł���B�~�m�́A�u3��17���B�g�ѕi���^��ő�2���i���n�����̐V���D�j�ɍڂ��A���������Ɠ��D���邱�ƂɂȂ����B�g�ߒc�̈�s�͂����9���̑D�ɕ��悵�A�e�D�͂��ꂼ��̑D���m�w�����n���w�����������B�D���͓��{�l�̐��������ق��A����ɐV���l�ŊC�H���悭�m���Ă����60�]�l���ق�����A�D���Ƃɂ��邢��7�l�A���邢��6�l�Ƃ�5�l��z�u�����v�i�[�J��w����s�L�x�Ap.147�j�B�ނ�͑ǎ��␅�v�ŁA��������A�V���ɋA�����Ă���B
�@�A���D���V���D���ّD�łȂ��w���ƂȂ����̂��A���ꂪ9�ǂƂȂ�A������������e�Ղɒ��B�������̂��B���������D�̍w�����͂��߁A�ʖ��D���̌ٗp�A����ɓ����D�̏o�����܂߁A�V���ˑ��ɂ��Ă͌����ɒl����B
�@3��22���A�~�m���������2�����͂���9�ǂ̋A���D���A���̊đ������̑D�Ɍ�����Ȃ���A�C�B�Ɍ������ďo������B���̓r���A���C�R�i�_��R�j�߂��̘A�_�`�ɂ����āA2���ɂ킽���āA������g�͋A���D���犯�l���W�߂ēn�C�̕��@�ɂ��ċ��c���邪�A�܂Ƃ܂�Ȃ��B4��3���A��2�A��3�A��5�A��7�A��9����5�ǂ͏o�����邱�Ƃ����߂�B4��5���ɂȂ�A�c���1�A��4�A��6�A��8����4�ǂ��܂��A�����̐����������o�����Ƃ��ďo�����邱�ƂɂȂ�B�����ʼn~�m�͌v����т����ƂƂ���B
�@����́A���łɁu�^�B�ɑ؍݂��Ă����ہA�V���̒ʖ������Ɩd���āA���B�̒n�ɍs�����Ȃ��Ώ㗤���Đl�Ƃɔ����A���̊Ԃɒ��v�D�����{�Ɍ����o�������Ȃ�ΎR���ɉB��Ă��āA��������V��R�Ɍ������A�����Ē����ɍs���v�Ƃ����v��ł������B�u��g�����̌v��ɔ�����Ȃ������v�B������肩�A����܂ł̑��^�ɉ����u��g�͋�20�嗼����������B�l�X���ʂ�ɗՂ��Ŕ߂��܂Ȃ��҂͂Ȃ������B�m4��5���n�ߑO8���ɂȂ邱��A9�ǂ̑D�͔����グ�ďo�����A���Ɉ����ē��k���w���Ă܂������ɐi��ōs�����B�݂̍������ɏオ���Ė]����ƁA�����͂����ƊC�̔ޕ��ɑ����Ă���B�m��4�l�m���v�m�̉~�m�ƁA�Ґ��A�ҋłƂ����m�A���v�̒��Y���n�͎R�݂����܂����v�̂ł���i�[�J��w����s�L�x�Ap.160�j�B
�@�Ȃ��A�~�m�̓��L�ł͖�������Ă��Ȃ����A�A���D�̈�c�ɓ�����2��������������ƂŁA����10�ǂƂȂ��Ă����B
���A���D�Ɂu����v����A�ݗ����ʂ�����
�@�u6�@��t�̗��Z�̖d�v�͐��炸�@��2�D�ɏ悹���ĉߊC�̓r�ɏA���v�ł́A����Ζ����������s���A�A���D�ŋ������҂���邱�ƂɂȂ������Ƃ��������B
�@�����������~�m�����́A�V���m�Ə̂��ė��𑱂��悤�Ƃ��邪���o���A�x�������ɕ߂炦���A�C�B�ɖ�ɑ��v�����B�����A�o���������̓���4��5���锼�̖\���ɂ���āA�A���D�͂�������ƂȂ����B�����A4��8���A�O���������S�������Ƃŏ��i���āA������2���̑D���ƂȂ����Ǜ������������a�C�ɂȂ������߁A���C�R�̊C�����_�ɗ��܂��Ă����B���̑D�ɂ͖@���@�̐��v�m������V���l�ʖ�������Ă����B
�@�����ŁA�~�m�����͗Ǜ������Ɉ������킳��A4��10�����̑�2���ɏ�D���ċA���������邱�ƂƂȂ����B���̌�8���ԍq�C�𑱂��邪�A�o�B���������z�����̓�ӂɕY�����Ă��܂��B�Ȃ��A����8���Ԃɤ2�l�̐��肪���S�A�����ɂӂ���Ă���B�܂��A��������1���ɂ��A��l2���A�]�҂␅���1.5���x�����ꂽ���A���X���ɂ�1���Ɍ���Ƃ����L��������i1�ޗǏ�0.72د�فA1����0.59د�فj�B
�����ė��āA����������D���̍b�͎߂ɂ悶��ނ�����ꂽ�v�B���̗��������u���߂đ��肩����ׂ�����A�������Ƃ����Ăं��̍ޖ������ŋ}�ɓ��肷�邱�Ƃ͍���v�Ƌc�_�����������A�u��̐��ɏ]���Ĥ�����o�����悤�Ƃ������ƂɂȂ����v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.206-7�j��܂��A6��23���ԎR�Y�Y�����A�u���͑啗�̂��߂ɐ���������čr��ɂԂ��������̔��j����������ɂ͂���2�ǂ����ꂭ�����Ă��܂��Ă���v��u�D��̑����̐l�͋C���]�|���ĐH�����̂ǂɓ��炸��܂�Ŕ����̏�Ԃ̂悤�ł���v������A�u�D���͎蕪�����Ă�����ɂ�����̂��ė�������܂�������ޖ�T�������v�Ƃ���i�[�J��w����s�L�x�Ap.215-6�j�
�@���̌�A���炾��ƕ��҂����Ă����B�Ƃ��낪�A�u7��16���������ԎR�@���牺�肽������̓r���ʼn�����l�̌����Ƃ���łͤ�A�������2���͍���o�������Ƃ�����O���܂őD���┑���Ă������ɍs���āA���̎p��T�������ǂ��ɂ����̎p�͂Ȃ������䩑R�Ƃ��Ă��炭�͊ݓ��ɗ����������v�Ƃ������ԂƂȂ�����u�����ŕ��o���̖����ɕ��邽�ߏo�Ă�������@���̘V�����Ⴋ���A�~�m�炪�Ƃ�c���ꂽ���Ƃ���ɂӂ����Ɏv���A�e�ɈԂ߂Ă��ꂽ�v�Ƃ���i�[�J��w����s�L�x�Ap.221�j�����͙F��ł����Ȃ������ł��낤�B
�@����5�����7��21���ߌ�4������A������2�����l�A���ɖ|�M���ꂽ�炵���A���ł�3�����O���A�����Ă����͂��́u������g�ȉ��̏����9�ǂ̑D������ė��āA���̐ԎR�Y�ɒ┑�����v���ł��顁u�����ŁA�Ґ�������đ�g�̂��@�����������킹��c�c��g�͋ߍ]�����m�̌I�c�ƌp�m�Ȃǂ��n�c�c�h�����Ă��Đ��v�m���Ԗ₳�ꤓ����ɐ�ɂ��̒n����o��������2������������Ƃɂ��Ď��₪�������v�i�[�J��w����s�L�x�Ap.223�j�
�@���̗��X���́u7��23���������ԎR�̏ォ��A���̂��܂őD�c���┑���Ă����Ƃ����]�������9�ǂ̑D�̎p�͂�����������Ȃ������Ť���̂����ɂ݂ȏo�q�������Ƃ�m�����̂ł������v��u�ԎR�̓��k����C�̔ޕ�100�S��(��55��Ұ��)�قǂ̂Ƃ���ɗy���ɎR��������v�B�u�~�m��Ґ���ҋł�3�l�̑m�͂��ЂƂ��V��R�ɍs��������S�Ť���{�ɋA�肽���Ƃ����C����Y�����褐ԎR�@�ɂӂݗ��܂��Ă���v�Ə����i�[�J��w����s�L�x�Ap.223�j�
�@���a�̌����g�̋A���D�́A������2���������������߁A10�ǂƂȂ����B������g�ɓ��s�����A���D9�ǂ���8�ǂ��A�����A1�ǂ݂̂�������i���̑D���͕s���j�B����ɐ攭����������2���́A���ς�炸������������A��p���ӂő����B���̐����҂͎c�[�Ő��ǂ̏��D������ċA������i��q����j�B����͑傢�ɏ̎^�ɒl���悤�B���̑D�ɉ~�m������Ă���Ζ����������ɈႢ�Ȃ��B
�@�������āA�����g�̎l�̑D�͂����������ĊC�̑����ƂȂ������A�~�m������������D���܂߁A�A���V���D�͏��^�ł���Ȃ���A����Ȃ�ɍq�C���܂��Ƃ����Ă���A�V���l�����̍q�C�E���D�p�̍��������Ď���y��3�z�y��4�z�B
���~�m�ݗ��E�A���̋��͎ҁE�V���l������
�@��g�͉~�m�����Ɉꏏ�ɋA�����悤�Ƃ��A�܂��͉~�m��������g�Ɉꏏ�ɋA���������Ƃ������Ȃ������B�������č��ӂ́u����v�ɂ���ĉ~�m�����͔O����ʂ������ƂƂȂ����B
�@�~�m���ݗ����邱�Ƃɐ��������̂́A�ނ̈�r�Ȏv������ł͂Ȃ��B������Z���́A�u��g��9�ǂ��ԎR�Y�ɓ��Y��������܂����u���Ă��̘Ԕ�������������ɑ�t���ͤ�܂��������v�g�ɒu�����Ĥ�ԎR�@�ԉ@�ɗ��Z���邱�ƂƂȂ��������͂������A�ɗz�ɉ����d�v�ł����Ĥ��t�̕s���̈ꓞ�S�ͤ�Q�����Z�̖ړI���ѓO��������������A�D��̏����l��ё�g���������V�����̒ʎ����ɥ���r�縑����c������P������V���l�̉���ɐ��邱�Ƃ͐����ł���v�Ɖ�����Ă���i�����w�����L�x�P�Ap163�j�
�@��̓I�ɂ́A�R�������܂ł̍q�C�̓�a��ؑD���A�~�m�ɂƂ��čݗ��H��̊��ԂƂȂ��Ă����̂ł���B839�i���a6�j�N4��29���A������Q���́u�V���l�ʖ�̓����ɤ���̒n�ɗ��܂邱�������܂��������̂��ǂ���������������������͑��̐V���l�Ƃ���ɂ��đ��k���ċA���ė��Č����ɂ́A�w���܂錏�͂��܂����������ł���x��ơ5��1���A�u���̑��ɉ~�m�����܂邱�Ƃ��ł��邩������������v�ƁA���̐��b�����P�炪�����ɂ͢���������܂邱�Ƃ���]����̂ł���Τ�������ꐶ�����a���̂����b���������܂��傤��a���͋����ē��{�ɋA��ɂ͋y�т܂���]�X��Ƃ�����u��2�������̎^���������Ȃ��̂ŁA�܂��ݗ��̌��S�����Ȃ��v�Ƃ���i�[�J��w����s�L�x�Ap.195�j�
�@5��16���A�Ռ��̉��ɂ̎g���������̂𗘗p���āA�u���v�m�͓��ɗ��܂肽���Ƃ����|�̏����������āA���l�̑����Ɏ������A�ё�l(��ɏq�ׂ钣��)�̉Ƃɓ͂������Ă���v�i�[�J���w����s�L�x�Ap.201�j������ɁA�ԎR�Y�┑���ɖ@�ԉ@�Ȃǂ�K��A�h���܂ł���悤�ɂȂ�A������6��29���ɂ́u�閾������m�ʖ�n����苗��Ƌq���ɓ��褓����ɑ؍݂��邱�Ƃɂ��đ��k�����v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.219�j�B
| �@�u2�@�@�`���g�B�Ɍ������v�́A�^�͂𗘗p���āA�@�`����g�B�܂ňړ�����Ƃ��̋L�^�ł���B �@7��14���A�}���̑D��҂����ɁA�u��g1�l�A����2�l�A�^��1�l�A�m��D���i�D���̊Ǘ����A�^���̎��̈ʁj1�l�A�j���i�L�^�W�j1�l�A�ˎ�A����i���v�j��A����30�l�����H����D�Ō����Ɍ������āv���܂��B���̌�A�u7��18���B�����A�����̍��������₢�D�ɉ^�B�^���ȉ��A����ȏ�̎҂͐��H����D�ŗg�B�{�ڎw���Đi��ł������v�B �@�^�͂ł̉^���́A�u����2�����m���߂͂Ȃ����A1�g������ŁA�Ƃ������Ƃł��낤�n40�]�ǂ̂��₢�D���Ȃ��������ς�B���邢��3�ǂ����ɕ��ׂ�1�D�Ƃ��A���邢��2�ǂ����ɕ��ׂ�1�D�Ƃ��A�Ƃ��ÂȂłȂ��ł���B�O�� |
 |
| |
�@������g���當�������āA�u����̕Y�����ɔj��������1���͕X�̂��莟��A���ǒn������ԕ����ɊĎ����Ă��炢�A���̔��̏��g�݂̐����͐����������߂āA�S���㗤�o��������B�c������҂������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ����Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.37-8�j�B
�@�u3�@��t���͊J�����Ɋ�h���āA�V��R�Ɏ���Ƃ𐿂��v�́A������g���~�m�����̓��R�����ɔ[�߁A�����Ɍ����o������܂ł̋L���ł���B
�@���N8��8���A���łɗ��Ă������ɉ����A�u��4���͂Ȃ��D�̏�ɋ���A���܂��ɒ┑���������Ă��Ȃ��B���{������̍v���i���܂��^�їg�����Ă��Ȃ��B���̔��̒���͂͂��ꗎ���āA�D���͓D���łقƂ�Lj�t�ɂȂ�A���̊����ɂ��������đD�q�̐����Ђ��āA���͓D�̏��ɏ�����萅���ɒ���ŁA�قƂ�Ǎq�C�̖��ɂ͗����Ȃ��Ȃ��Ă���B���@�m�i�~�s�m799-852�n�E��Łj��͂܂��㗤���Ă��Ȃ��B�D���̔����i�����P��j�͏㗤���ĊC�ӂ̋��t�̉Ƃɂ���B�D���̐l5�l�͑̂��ӂ����Ŏ��v���Ƃ��m�炳���i�[�J��w����s�L�x�Ap.52�j�B
�@8��10���A�V���l�ʖ�̖p��������A�o�������Ă�����2�����C�B�i�]�h�ȓ��C���j�ɒ������Ƃ����莆���A��1���̋�����̂��Ƃɗ���B��q�̒ʂ�A���̑�2���݂̂����낤���ē��{���A�蒅���B���̏�D�҂̊��l��������g��s�ƍ����������ɂ݂��邪�A���炩�łȂ��B
�@8��17���A�ԗ��ɂ������Ă����A�D�t�i�D���j�������������ʁB��i�͏]�҂Ɏ�������B�����A��1���ɔh�����Ă������D���̗k���C���}���A���ė��āA���v�������S�p���@�`�Ŏ���ł����Ƃ����B8��24�A��4���̔�����s��30�ǂقǂ̏��D�ɏ���Ă���Ă���B
�@10��5���A������g��͗g�B���Ɍ����o�����邪�A�u�������銯�l�͑�g1�l�i�������b��k�j�A���������i���������j�A���������i�����P��j�A���x�^���i���x�S���j�A��_�^���i��_�@�Y�j�A���ʎ��i���N�Y�j�A�ʐ��v���i���ʌ������j���{��Y�A�^�����v�m�~�s��A����ɎG�E�i�e��̐E�����j�ȉ�35�l�A���D��5�z�v�ł������i�[�J��w����s�L�x�Ap.70�j�B
���J�����Ɋ�h�A�n���[�a�������遥
�@�u4�@��g�̋A�҂܂ŊJ�����ɂ���ē��V��R�̒�����҂v�̓��e�̓^�C�g���ʂ�ł���B
�@�~�m�́A10��22�������A�n���[�a���i����74.7�N�A[�ʏ�͖�76�N������]�j������B�������A�u���ɂȂ��ĕ�������o�āA���̜a��������ƁA����̋�̋��ɂ����Ă��̔��͐����w���Ă���A���͂���߂ăn�b�L���ƌ������B�������炱���]����ƁA���̒����͑S�̂�10��i��30Ұ�فj���������B�ǂ̐l���F�A����͕����m�����n�̌����Ӗ�������̂ɈႢ�Ȃ��ƌ������v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.77-8�j�B���̌���A�ނ͓��H�A���H�A���Ƌ����̐ڋ߂Ȃǂ̓V�����ۂɂ��т��ё������Ă���B
�@���{���o�������N��12��18���A�������V���l�̒ʖ����������āA�u���H�̑�1���E��4���̔j���̓x���傫�������̂ŁA�������g�̋A���̑D�����߂邽�߂ɁA�^�B�i�̂��̟̈��j�Ɍ��������o���v�����Ă���B���̒���Ɍ�����g�������ɒ������Ƃ����A��������i�[�J��w����s�L�x�Ap.102�j�B
�@�����āA�N�����܂���839�i���a6�j�N�̉[����4���ɂ́A�u�V���l�̒ʖ������̗v���ōw�������D���C�������邽�߂ɁA�H���̊ēA��H�A�D�H�A�b�H�i�������j��36�l��^�B�Ɍ����o���������v�Ƃ���i�[�J��w����s�L�x�Ap.120�j�B���̈���A���̗����ɂ́u���{�̒��v��1���ɐ������Ă�������A�ˎ��60�]�l�̒N���ނ����A�F�a���ɓ|��ꂵ��ł���v�Ƃ���i�[�J��w����s�L�x�Ap.121�j�B
�@1��8���A���{�ꂪ���ɂ悭�킩��u�V���l�̉����Ƃ����҂�����ė����̂ʼn�����B�ނ͓��{�̍O�m10�N�i819�j�ɏo�H�̍��ɗ��ꒅ�������̐l���o�ς�Ɠ����D�ɏ���Ă����Ƃ����B�Y������������ƁA�����������B�w���낢��ȕ�����{�ƌ������邽�߂ɁA���̗g�B�𗣂�đ��C��n�������A�����܂��\���ɋ����ė�����邱��3�����A�o�H�̍��i�R�`���j�ɕY�������B�������o�όZ��2�l�͂܂��ɏo�q���悤�Ƃ���Ƃ��ɂȂ��āA2�l�Ƃ������悤�ɑD����E�����o�H�̍��ɋ������Ă��܂����B���ǂ��͖k�o�H���甭���Ėk�C�i���{�C���j���q�C���A�K���ɂ��D���Ɍb�����15���Œ���̍��i�R�����j�ɗ��ꒅ�����v�Ƃ����b�ł������i�[�J��w����s�L�x�Ap.110�j�B
�@�u���̐l���o�ς�v�Ƃ��i�V���l�Ƃ݂Ă悢�j�A�u�o�H�̍��i�R�`���j�ɕY�������v�Ƃ��A�u�D����E�����c�c���������v�Ƃ��������A�����g��s�������˂��Ă̌��t�g���ł��낤�B�V���l���l�͖k��B�݂̂Ȃ炸�A���k�̍����Ƃ���Ζ��f�Ղ��s���Ă������Ƃ��������B
���V���D��9�Ǎw�����āA�A���̉^�тɁ�
�@�u5�@�����g�͒�����\�킸���đ^�B�ɋA��C�B���ߊC���v�̓^�C�g���ʂ�ŁA�~�m�����u��f�O�����邦�Ȃ��ƂȂ������Ƃ�������Ă���B
�@2��6���A�g�B�̖������V�q�̒��ɂ��������āA�����g�ߒc�̗g�B�c����270�l���ꂼ��ɁA�������琅��Ɏ���܂Ť��5�D(1�D=12Ұ��)��\(��)�Ƃ��Ďx�����Ă����Ƃ��������270�l�́A���̎��_�ŗg�B�Ɋ��Ă�����1���Ƒ�4���̏�D�҂ł����āA������^�B�Ȃǂɔh������Ă������̂͊܂܂�Ă��Ȃ��B�Ȃ��A��2���͂��łɂ݂��C�B�i�]�h�ȓ��C���j�ɗ��܂��Ă����Ƃ݂��邪�A���D�̔��������L���͒����Ŏ��S�������ƂɂȂ��Ă���B
�@�����g��838�i���a5�j�N12��3�������ɓ������A��839�i���a6�j�N1��13���Q�����A�[1��4�������𗣂�A2��12���^�B�ɖ߂��Ă����B�������A�~�m�ɂƂ��Ė��O�Ȃ��ƂɁA���{�m�����̋��A�����Ă͉~�ڂ݂̂��V��R�ɓ��邱�Ƃ�������A�~�m�Ȃǂ��ׂĂ̑m�͖{���ɋA�҂�����̂�����Ƃ����A�����ƂȂ��Ă����B28���A�~�ڂƂ��̏]��2�l�͈�s�ƕʂ�A�V��R�Ɍ������B������A�ނ�40�N�����ɗ��܂�A877�N�A���̍ۂɑ���Ď��S����B
�@�g�B�ɂƂǂ܂��Ă������l��m�����́A10�ǂɕ��悵�đ�^�͂��g���đ^�B�܂ōs���āA��g��s�ƍ������邱�ƂƂȂ����B�����O�ɂ��āA���N2��22����4���̎ˎ�1�l�A����2�l�����l���\�s�����Ƃ��đߕ߁A���u���ꂽ���Ƃ��͂��߂Ƃ��āA�����g��s�̉��l���������Ղ��߂����Ă������̃g���u�����N����i�ڍׂ͌�q����j�B�ߕ߁A���u���ꂽ�l�X�����Ƃ���A2��22���A�o������i�[�J��w����s�L�x�Ap.134�j�B
�@�����g�́A�V�q����9�ǂ̑D���ق��ďC�����邱�Ƃ�F�߂��Ă������A������Z����̎w�E�ɂ��A����Ɍ������V���D���w�������悤�ł���B�~�m�́A�u3��17���B�g�ѕi���^��ő�2���i���n�����̐V���D�j�ɍڂ��A���������Ɠ��D���邱�ƂɂȂ����B�g�ߒc�̈�s�͂����9���̑D�ɕ��悵�A�e�D�͂��ꂼ��̑D���m�w�����n���w�����������B�D���͓��{�l�̐��������ق��A����ɐV���l�ŊC�H���悭�m���Ă����60�]�l���ق�����A�D���Ƃɂ��邢��7�l�A���邢��6�l�Ƃ�5�l��z�u�����v�i�[�J��w����s�L�x�Ap.147�j�B�ނ�͑ǎ��␅�v�ŁA��������A�V���ɋA�����Ă���B
�@�A���D���V���D���ّD�łȂ��w���ƂȂ����̂��A���ꂪ9�ǂƂȂ�A������������e�Ղɒ��B�������̂��B���������D�̍w�����͂��߁A�ʖ��D���̌ٗp�A����ɓ����D�̏o�����܂߁A�V���ˑ��ɂ��Ă͌����ɒl����B
�@3��22���A�~�m���������2�����͂���9�ǂ̋A���D���A���̊đ������̑D�Ɍ�����Ȃ���A�C�B�Ɍ������ďo������B���̓r���A���C�R�i�_��R�j�߂��̘A�_�`�ɂ����āA2���ɂ킽���āA������g�͋A���D���犯�l���W�߂ēn�C�̕��@�ɂ��ċ��c���邪�A�܂Ƃ܂�Ȃ��B4��3���A��2�A��3�A��5�A��7�A��9����5�ǂ͏o�����邱�Ƃ����߂�B4��5���ɂȂ�A�c���1�A��4�A��6�A��8����4�ǂ��܂��A�����̐����������o�����Ƃ��ďo�����邱�ƂɂȂ�B�����ʼn~�m�͌v����т����ƂƂ���B
�@����́A���łɁu�^�B�ɑ؍݂��Ă����ہA�V���̒ʖ������Ɩd���āA���B�̒n�ɍs�����Ȃ��Ώ㗤���Đl�Ƃɔ����A���̊Ԃɒ��v�D�����{�Ɍ����o�������Ȃ�ΎR���ɉB��Ă��āA��������V��R�Ɍ������A�����Ē����ɍs���v�Ƃ����v��ł������B�u��g�����̌v��ɔ�����Ȃ������v�B������肩�A����܂ł̑��^�ɉ����u��g�͋�20�嗼����������B�l�X���ʂ�ɗՂ��Ŕ߂��܂Ȃ��҂͂Ȃ������B�m4��5���n�ߑO8���ɂȂ邱��A9�ǂ̑D�͔����グ�ďo�����A���Ɉ����ē��k���w���Ă܂������ɐi��ōs�����B�݂̍������ɏオ���Ė]����ƁA�����͂����ƊC�̔ޕ��ɑ����Ă���B�m��4�l�m���v�m�̉~�m�ƁA�Ґ��A�ҋłƂ����m�A���v�̒��Y���n�͎R�݂����܂����v�̂ł���i�[�J��w����s�L�x�Ap.160�j�B
�@�Ȃ��A�~�m�̓��L�ł͖�������Ă��Ȃ����A�A���D�̈�c�ɓ�����2��������������ƂŁA����10�ǂƂȂ��Ă����B
���A���D�Ɂu����v����A�ݗ����ʂ�����
�@�u6�@��t�̗��Z�̖d�v�͐��炸�@��2�D�ɏ悹���ĉߊC�̓r�ɏA���v�ł́A����Ζ����������s���A�A���D�ŋ������҂���邱�ƂɂȂ������Ƃ��������B
�@�����������~�m�����́A�V���m�Ə̂��ė��𑱂��悤�Ƃ��邪���o���A�x�������ɕ߂炦���A�C�B�ɖ�ɑ��v�����B�����A�o���������̓���4��5���锼�̖\���ɂ���āA�A���D�͂�������ƂȂ����B�����A4��8���A�O���������S�������Ƃŏ��i���āA������2���̑D���ƂȂ����Ǜ������������a�C�ɂȂ������߁A���C�R�̊C�����_�ɗ��܂��Ă����B���̑D�ɂ͖@���@�̐��v�m������V���l�ʖ�������Ă����B
�@�����ŁA�~�m�����͗Ǜ������Ɉ������킳��A4��10�����̑�2���ɏ�D���ċA���������邱�ƂƂȂ����B���̌�8���ԍq�C�𑱂��邪�A�o�B���������z�����̓�ӂɕY�����Ă��܂��B�Ȃ��A����8���Ԃɤ2�l�̐��肪���S�A�����ɂӂ���Ă���B�܂��A��������1���ɂ��A��l2���A�]�҂␅���1.5���x�����ꂽ���A���X���ɂ�1���Ɍ���Ƃ����L��������i1�ޗǏ�0.72د�فA1����0.59د�فj�B
| �@�u��Q��7�@�C���q�@�}���Ē��v�D�ɝX�p�����@ �ԎR�@�ԉ@�ɗ��Z���v�ł́A�A���D�ɂ���Έ���� �ꂽ���Ƃ���ڈ���ƂȂ�A�V��R���R��ڎw����� ���ɂȂ������Ƃ��������B �@�A���D�́A4��5���n�C���邱�ƂƂȂ������A���̌� ���������Ȃ����ߗ����痣��邱�Ƃ��ł����A7�� 23���ɂȂ��Ă悤�₭�R�������̕��o�����C�q���� ��݂̐ԎR�Y����A�����邱�ƂƂȂ�B������2���ͤ 4��18���O�x�A���R�Y�̐����ɕY������B���̊ԁA�V ��͉v�X�������ƂɂȂ�A�ǎ�A���v�i�����̂܂� �Ă���j�A�m���������������ʁB �@���̑�2���̍q�C�̓�a�Ԃ�́A��̓I�ɂ͎��̂� ���Ȃ��̂ł������B5��27���A�u��������傫�ȗ����}�� |
 |
| |
�@���̌�A���炾��ƕ��҂����Ă����B�Ƃ��낪�A�u7��16���������ԎR�@���牺�肽������̓r���ʼn�����l�̌����Ƃ���łͤ�A�������2���͍���o�������Ƃ�����O���܂őD���┑���Ă������ɍs���āA���̎p��T�������ǂ��ɂ����̎p�͂Ȃ������䩑R�Ƃ��Ă��炭�͊ݓ��ɗ����������v�Ƃ������ԂƂȂ�����u�����ŕ��o���̖����ɕ��邽�ߏo�Ă�������@���̘V�����Ⴋ���A�~�m�炪�Ƃ�c���ꂽ���Ƃ���ɂӂ����Ɏv���A�e�ɈԂ߂Ă��ꂽ�v�Ƃ���i�[�J��w����s�L�x�Ap.221�j�����͙F��ł����Ȃ������ł��낤�B
�@����5�����7��21���ߌ�4������A������2�����l�A���ɖ|�M���ꂽ�炵���A���ł�3�����O���A�����Ă����͂��́u������g�ȉ��̏����9�ǂ̑D������ė��āA���̐ԎR�Y�ɒ┑�����v���ł��顁u�����ŁA�Ґ�������đ�g�̂��@�����������킹��c�c��g�͋ߍ]�����m�̌I�c�ƌp�m�Ȃǂ��n�c�c�h�����Ă��Đ��v�m���Ԗ₳�ꤓ����ɐ�ɂ��̒n����o��������2������������Ƃɂ��Ď��₪�������v�i�[�J��w����s�L�x�Ap.223�j�
�@���̗��X���́u7��23���������ԎR�̏ォ��A���̂��܂őD�c���┑���Ă����Ƃ����]�������9�ǂ̑D�̎p�͂�����������Ȃ������Ť���̂����ɂ݂ȏo�q�������Ƃ�m�����̂ł������v��u�ԎR�̓��k����C�̔ޕ�100�S��(��55��Ұ��)�قǂ̂Ƃ���ɗy���ɎR��������v�B�u�~�m��Ґ���ҋł�3�l�̑m�͂��ЂƂ��V��R�ɍs��������S�Ť���{�ɋA�肽���Ƃ����C����Y�����褐ԎR�@�ɂӂݗ��܂��Ă���v�Ə����i�[�J��w����s�L�x�Ap.223�j�
�@���a�̌����g�̋A���D�́A������2���������������߁A10�ǂƂȂ����B������g�ɓ��s�����A���D9�ǂ���8�ǂ��A�����A1�ǂ݂̂�������i���̑D���͕s���j�B����ɐ攭����������2���́A���ς�炸������������A��p���ӂő����B���̐����҂͎c�[�Ő��ǂ̏��D������ċA������i��q����j�B����͑傢�ɏ̎^�ɒl���悤�B���̑D�ɉ~�m������Ă���Ζ����������ɈႢ�Ȃ��B
�@�������āA�����g�̎l�̑D�͂����������ĊC�̑����ƂȂ������A�~�m������������D���܂߁A�A���V���D�͏��^�ł���Ȃ���A����Ȃ�ɍq�C���܂��Ƃ����Ă���A�V���l�����̍q�C�E���D�p�̍��������Ď���y��3�z�y��4�z�B
���~�m�ݗ��E�A���̋��͎ҁE�V���l������
�@��g�͉~�m�����Ɉꏏ�ɋA�����悤�Ƃ��A�܂��͉~�m��������g�Ɉꏏ�ɋA���������Ƃ������Ȃ������B�������č��ӂ́u����v�ɂ���ĉ~�m�����͔O����ʂ������ƂƂȂ����B
�@�~�m���ݗ����邱�Ƃɐ��������̂́A�ނ̈�r�Ȏv������ł͂Ȃ��B������Z���́A�u��g��9�ǂ��ԎR�Y�ɓ��Y��������܂����u���Ă��̘Ԕ�������������ɑ�t���ͤ�܂��������v�g�ɒu�����Ĥ�ԎR�@�ԉ@�ɗ��Z���邱�ƂƂȂ��������͂������A�ɗz�ɉ����d�v�ł����Ĥ��t�̕s���̈ꓞ�S�ͤ�Q�����Z�̖ړI���ѓO��������������A�D��̏����l��ё�g���������V�����̒ʎ����ɥ���r�縑����c������P������V���l�̉���ɐ��邱�Ƃ͐����ł���v�Ɖ�����Ă���i�����w�����L�x�P�Ap163�j�
�@��̓I�ɂ́A�R�������܂ł̍q�C�̓�a��ؑD���A�~�m�ɂƂ��čݗ��H��̊��ԂƂȂ��Ă����̂ł���B839�i���a6�j�N4��29���A������Q���́u�V���l�ʖ�̓����ɤ���̒n�ɗ��܂邱�������܂��������̂��ǂ���������������������͑��̐V���l�Ƃ���ɂ��đ��k���ċA���ė��Č����ɂ́A�w���܂錏�͂��܂����������ł���x��ơ5��1���A�u���̑��ɉ~�m�����܂邱�Ƃ��ł��邩������������v�ƁA���̐��b�����P�炪�����ɂ͢���������܂邱�Ƃ���]����̂ł���Τ�������ꐶ�����a���̂����b���������܂��傤��a���͋����ē��{�ɋA��ɂ͋y�т܂���]�X��Ƃ�����u��2�������̎^���������Ȃ��̂ŁA�܂��ݗ��̌��S�����Ȃ��v�Ƃ���i�[�J��w����s�L�x�Ap.195�j�
�@5��16���A�Ռ��̉��ɂ̎g���������̂𗘗p���āA�u���v�m�͓��ɗ��܂肽���Ƃ����|�̏����������āA���l�̑����Ɏ������A�ё�l(��ɏq�ׂ钣��)�̉Ƃɓ͂������Ă���v�i�[�J���w����s�L�x�Ap.201�j������ɁA�ԎR�Y�┑���ɖ@�ԉ@�Ȃǂ�K��A�h���܂ł���悤�ɂȂ�A������6��29���ɂ́u�閾������m�ʖ�n����苗��Ƌq���ɓ��褓����ɑ؍݂��邱�Ƃɂ��đ��k�����v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.219�j�B
 |
�@�R�������̕��o�����J���ԎR���ɐԎR�@�ԉ@�Ƃ�����������A�~�m�͂����ɒ����Ɋ�h�� �邱�ƂƂȂ�B�����́A�u�������Ƃ͒����ŏ��Ɍ��Ă��Ƃ���ł���c�c�~�͖@�Ԍo���u�` ����Ă�8���̋������o���u�`������̂Ť���̍u�`�͒��N���킽���čs�Ȃ��Ă����c�c�� �܂͐V���l�̒ʖ�ŌR������(�x������)�̒��r����їё�g(����)����̒��V�̉��P�炪 ���S�ɊǗ����Ă���v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.214�j��Ȃ��A���̎��͔�b�R�[����{�� �ԎR�T�@�⤋��s�k�x�ԎR���_�̋N���ƂȂ���� �@���Ɋւ�����́A4��2���A����2�D�̎w���������h���m�����n���i�H����Ɗ֘A�� ���āA�u�V���͒��Ɨ��������݂��ɐ���Ă���v�Əq�ׂĂ���B����ɁA4��20����R������ �ɕY������ƁA�V���l�����D�ɏ���đ�������ė���B���̔ނ���~�m�́A�����{���� [�݈�838-39]��ł��|�����ߐ_����[�݈�839]�Ƌ��͂��A�ނ����Ƃ��邱�Ƃɐ����������Ƃ�m ��B�Ȃ��A���̗����̓R�����ʂ�ł���B |
| |
| |
�@�V���̗E���ɂ��ĕێH��|����|�b�Ƃ��̂��顁w�O���j�L�x��w�O���⎖�x��w�V�����x�V���`��S�ϓ`��w�����{���I�x���Ɍ���B
�@���ߓ��ɓ����ď��B�R�������ƂȂ褋A���ĐV��������[�݈�826-36]�ɉy����m828�N�S���쓹�Γ��ɒu���ꂽ�n���C����g�ɔC����������l��^����ꐴ�C�k�R���ȓ��[�l�ɒ������߂�題���{���������m�Ɂn�����ęӈʂ��m���ʂ�ӒD���悤�Ƃ���n� �@�������̑��q�S���ͤ�Ȏq�Ƌ��ɐ��C�ɓ��ꤕɗ����ĕ��w��d�顕͑�5000�����킵�������āA���Ƃ��Ƃ����̓}�ނ��E������k�w�������@����s�L�x��5��839�i���a6�j�N�l4��2���̏��ɒ������ĐV���Ɛ키������ͤ����Ȃ� �@�����ɒ��͗S����V�����̑��q�ɕ������̂ł��顑����A�S���m�́n���ʂ��Đ_�����Ə̂�������̌�����������̏��m���n��[��Ĕ܂ƂȂ��Ƃ��� �@������ɤ���Ő_�����a������㉤������[�݈�839-57]�͂��̖��H��Łm�ӂ܂��ān���܂ƂȂ���Ƃ���������ɌQ�b�͂��́m�ނ́n���G�Ȃ���Ȃ��Ē���������{��A���C�ɋ����Ĕ�����������삱��𐪂��邱�Ɣ\�킸����a8�N(841)11���Ɏ���A���͎h�q腒��ɈÎE����ꂽ�y��5�z� �@���́A���C���x���̊O�Ɍ��ՑD��h�����Ĥ�L���C��Ɋ�����w�����{��I�x�Ɍ����A�䂪���ɒʏ������߂��̂��A���̎��ł��顂܂��A�ԎR�ɖ@�ԉ@�����āA��t�̗��Z�����삵�����ऐ���̑�ł��顂��ƂɐԎR�@�ԉ@�̑ؗ�������̉��t��R�̏���A�҂̉ߊC�ɁA�n�I�ُ�Ȃ鉇����������钣���ɤ�����n�i���́A�F���̟����̐l�X�ł��� �@���o��t�ͤ���ɕ{���o������ۤ�}�O���珬�웨��m����⹂̈ꑰ�n�̏Љ������Ă���(�w�������@����s�L�x��9�́m840�i���a7�j�N�n2��17����)��͓��{�֓n�q�������Ƃ����褑��ɕ{�̖�l�Ɩʎ�������������ł����Ƃ����B |
�@�u6��27��������Ƃ���ɂ��Ƥ���C������g�̖f�ՑD2�ǂ��U(�Ԃ�)�R�Y�ɓ��������v��܂��A�~�m�́u6��28����哂�̓V�q���V�������ʂ��������Ԗ�̂��߁A�V���ɔh������g�ҐB���n�g�c�c��Ǝ��m�ԎR�@�ԉ@�n�̒��ʼn������镪�ɂȂ��āA���͑哂�����g(�V�����瓂�֕��i�������炷�g��)�̛����n���g(���̔z�������̒�\��Y)�����ɂ��킵�ė��Ĥ��������Ԗ₵�Ă��ꂽ�v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.218�j�
�@���̂Ƃ��A���͂ǂ��ɂ����̂��͂Ƃ������i�����A�V���ł��낤�j�A�V���̎��͎҂Ƃ��ē����[���ւ��A�R�������������I�Ȍ������ӂ���Ă������Ƃ͖��炩�ł���B�ނ́A���̔z���������Ă��āA�~�m�ɐe�ɉ��ڂ��Ă����̂ł���B�ނ̎x���ɂ���ĉ~�m�̍ݗ����͂��߂Č��܂����Ƃ�����B���������ĉ~�m�ɂƂ��Ē��͋��@����s�̉��l�Ƃ�����B���̔ނ́A�~�m�̒����؍ݒ��A�ÎE�����B
���ܑ�R���o�Ē����ւ́A���@����̗���
| �@�u8�@�ԎR�@�ԉ@�̛����A9�@�����邪�ׂɐ��B�Ɍ������A10�@�����Čܑ�R�Ɍ������A11�@�ܑ�R�ɓ����Ԍ����ɓ���A��R��12�@�|�ю��Ƒ�Ԍ����A13�@����A����A�k��A��������V���A14�@�����Ɍ������Ĕ����A���ɓo��A15�@�����ɓ���s���A16�@�������Ɋ�Z���Ē����̏������Ɋw�ԁv�������B �@�����́A�~�m�͊��߂������ēV��R���R��������߁A�����i���s�����j�����Čܑ�R���o�Ē����Ɏ���܂ł́A���@����̗��������c���������ł���A���̓��L�̖{�̂ł���B���̊��Ԃ́A839�i���a6�j�N7������845�i���a12�j�N6���܂ŁA����5�N�ɂ킽��B���̗��s�͓��R���H������Ă���A���ʂ���C�����͂����������ĂȂ����A���ڂ��ׂ��L���͎��̒ʂ�ł���B |
 |
| |
�@�����āA�u�~�m�͌̋��̓��{�𗣂��Ƃ���ނ���Œ}�O��炩�珑���ʂ�a���������Ă��āA��g�ɍ����グ���͂��ł�����Ƃ��낪�A���̒n��ڑO�ɂ��đD���ɍ��ʤ���v����������\�����Ȃ��o�����ɂ�������낢��ȕ��𗬎����܂���������̂Ƃ�������Ă���������g�ɂ�����C��ɒ��ݗ����Ă��܂��܂����c�c�ǂ������������Ɛӂ߂��܂���悤�A���肢���鎟��ł��c�c�����@��ɂ��ڂɂ����肽���Ɗ肤�S���������ł��v�Ƙl�т�i�[�J��w�����s�L�x�Ap.275�j�B���̓��{�Ɗւ�肪�����ɉ��[������m�肤��B
�@840�i���a7�j�N2��22���A���̕��@(�݈�826-40�j�����������Ƃ��B4��1���A���������āA����R�Ɍ������B�����āA8��22���A�~�m�͑����������ɓ���B��841�i���a8�j�N1���A���@�i�݈�840-46�j�̑��ʂɂ��A���̔N�����J�������ɉ��܂�B����842�i���a9�j�N3���ɂ́A�E�C�O���������̗̓��ɐN�����Ă���B8���A�~�m�͋A���̈ӌ���R�炷�B���̍�����A��̔p���ƌ���镐�@�̕������Q�̂��������݂���B
�@842�i���a9�j�N5��25���A�V��R�������ɓ������~�ڂ̏]�ґm�m�ς����āA�莆������������炷�B���̂Ȃ��ɂ́A������g������k�͋A���������̂̎��S�����Ƃ��A�����u��2���͓�̗��l�̍��ɕY�����A���͔j����l���������Q���o����������R�ɂ�30�l�قǂ͖����������āA�j�������傫�Ȕ��������ď��D����褂���ɂ���ē��{�ɋA�蒅�����Ƃ��ł����v�Ƃ���^�B�ɏZ�ސV���l�ʖ�̗��T���̂Ƃ���ɁA���ψ�苗����������u���{����̏���ƍ���24�����v���a������Ă���Ƃ��i�ʖg������ł��܂��j�A�u�b�Ԙa���͕֑D�𗘗p���đ^�B�ɒ�������łɌܑ��R������I���c�c���ד��l�Y�̑D�ɕ֏悵�Ė��B(�ƍ]�ȐV�Ό�)������{�ɋA��v����ł������A�^�B����A�邱�ƂɂȂ邾�낤�Ƃ��ł������i�[�J��w����s�L�x�Ap.505�j�B
����̔p���ɂ���č��O�Ǖ��ƂȂ遥
�@�u17�@�m��̓����A��S��18�@���@�̖\���A19�@���@�����ɓM�f���đm�k�𔗊Q���A20�@�����������A�A���ęďB�ɓ���A21�@�o�B���o���ɒ��������v�́A��̔p�����N����A�~�m���������O�Ǖ��ƂȂ�A���̍ʼnʂĂ܂Œ����i�w������j�����ߒ�����L�Ƃ��Ă���B
�@842�i���a9�j�N10��9���A��̔p�����͂��܂�B�m��́A���̗����ɂ���Ċґ������߂��A���Y��v������邱�ƂƂȂ�A������̊O�o�֎~�ƂȂ����B��843�i���a10�j�N1���A�m��̊ґ����͒��������ł�3591�l���y�B1��28���A�O���m�͌R�q�ɏW�߂��A���̐���C���h�l5�l�A�k�C���h�l�A�Z�C�����l�A�N�`���l���ꂼ��1�l�A�����ē��{�l3�l�ȂǁA����21�l�ł������B7��24���A��q�̈ҋł������a�̌�S���Ȃ�B8��13���A�A���̋������߂�B12���A�~�ڂ̒�q�m2�l���V���l�ʖ�̗��T���̎�z�ŁA���{�ɋA�q�����Ƃ����莆����B
�@�~�m�́A844�i���a11�j�N�������A����3���A���@�̏@���ςɂ��Ĕނ́u�ЂƂ��ɓ�����M���ĕ��@���ɂ��ޡ�m�̎p�����邱�Ƃ��������@�m�O��̋�����������Ȃ��c�c�o���������������j������̑m���{������ǂ��o���āA�߂��߂����A�����鎛�ɋA���Ă��܂���������āA������ɂ͓����̓V���ƘV�q�̑������u������m�ɖ����ē����̌o�T��ǂ܂��A�����̏p���C�������Ă���v�Əq�ׂĂ���i�[�J��w����s�L�x�Ap.542�j�����ɁA7��15���u�S���̎R�ю��@����ʉ@(����҂̂��߂̏h����)�����������̈�ˤ���̋��{���Ȃǂ�200�Ԗ����̂��̂Ƥ���I�ɓo�^����Ă��Ȃ����͔j������ɑ�����m���m��͂��ׂċ����I�Ɋґ������ĎG���ɏ[�Ă�v�Ƃ����������������i�[�J��w����s�L�x�Ap.549�j�B
�@845�i���a12�j�N�ɓ����Ă��A���@�̕������Q�͐����Ȃ��B���łɁA�~�m�����͋A���肢���A841�i���a8�j�N����100�]��ɂ킽���ĕ������Q�S���̌����g�i!?�A�@�������j�ɏo���Ă������A������������Ȃ��B���łɁA�O���m�ɑ���g�����ׂ�Ăяo�����s���Ă������A���ɒ�������A�u�m�����ȗ畔�n�K���̏ؖ����������Ă��Ȃ�A�m�����m�Ɓn���l�ɋ����I�Ɋґ������āA�w�����ɏo�g���ɋA���v�A�u����ɏ]��Ȃ����͎̂��Y�v�Ƃ������ƂɂȂ����B�~�m����Z���鎑�����ɂ͏ؖ����������Ă��Ȃ����̂��A�ނ���܂�39�l�������B
�@�~�m�����͐����̎p�ƂȂ��āA���x�x�Ɏ�肩����A5��15�����m�̐l�X�Ɍ������Ē������o��B�����A�嗝���i�i�@�����j�k�h�V�̏Љ���������ߒ��d�Ɉ����A�ďB�i���A�J���j�A���B�A�g�B���o�āA7��3���^�B�ɒ����B
�@�^�B�ł́A�u�܂��A�V���V(�V���l�X)�ɍs���āA�y��(���Ǥ�������c��)�ł��̏B�̓��\��(���ԕ����������Z)���L�F�ƐV���l�ʖ�̗��T���ɉ�����2�l�͂������}���Đe�ɂ˂������Ă��ꂽ�v��ނ�́u���{���̒��v�g�͋A���̍ۤ�F��������D�ɏ���đ�C��n��A���{�ɋA���܂�����~�m��͉w�����ɑ����āA�������炱���ɗ��܂�����A������ɂ͂ǂ����A���������C��n�点�Ă�������������Ɛ\���q�ׁA�܂��u���T���͎��猧�̖����ɍs����d�G���g���āA�����������܂������悤�v����߂��炵���v������m�����痹���������Ȃ������i�[�J��w����s�L�x�Ap.592�j�B
�@7��3���^�B���o�����A�V���l�̂Ă����ǂ�Ȃ���A�C�B�A���B���o�āA8��16���o�B�ɒ����B����ɁA�o�B�̕��o���Ɉړ�����B���܂�A�~�m�����́u�R���z�����n���Ĉߕ��͂ڂ�ڂ���j��g���ʂ���������̖����ɍs������(���̒���)�ɉ��w�����̓��[�ɂ�������V����(���J���ɂ���V���������̐��b��)�ɍs���āA�H�ו������ߌ�Ă����������ׂȂ�����̊Ԃ�����M�����߂ē��{���ɋA�炵�Ăق����x�Ɛ��肵���v�Ƃ�����ԂɂȂ��Ă����i�[�J��w����s�L�x�Ap.609�j�
�@�u�o�B�͑哂�̍ł����k�̊U�̒n��ł��顖k�C�ɓ˂��o���C�ɗՂ�ŏB��m�H���邩�n���������c�c�s���牓�����ꂽ�Ƃ���ł�����������߂ɂ��@�K�ɂ���đm��������ґ��������@��j��o�̏������ւ��A���������킵�A���̏��L�������ɖv�����邱�Ƃͤ�����̓s�Ɖ����ς��Ƃ��낪�Ȃ���܂��ĕ����̏�ɂ��Ă���������A���S����ł��ӂ��āA���̖ڕ����͂���Ƃ͂܂��ɉ��Ƃ����������ɂ܂������Ƃł��顓V���̓��S�̕�����̕��͂ǂ�قǐ�������̂���M�d�Ȃ��̂��킩���Ă���̂ɤ���ɏ]���Ă��ׂĔj�낵�s�����Ă����̋����ɂ��Ă��܂����v�i�[�J��w����s�L�x�Ap.607�j�B
�@�Ȃ��A��̔p���͕������c�̕��s��������e���A�E�ŖړI�őm��ɂȂ����莛�ɓ��邱�Ƃ�����邱�Ƃɂ������B���̂��ƂŌ����Ƃɐ������c���ꂽ���A�p����4600���A�ґ��҂�26���l�ɋy�Ƃ����B
��3�N�����A����D��T���āA�A���ց�
| �@ �u22�@�ԎR�Ɋ�����A����D���K�߂ċA����d��v�́A��������3�N�ԎR�Y�Ɋ��������A����D��T���ċA���̓r�ɂ��Ƃ����L�^�ł���B �@8��27���A�~�m�����͌����V�����ɒ����āA�R�����ɂ̒��r�ƍĉ�A���ɂ˂������B�~�m�����͍ĂѐԎR�@�ԉ@�̏��@�Ɋ�Z���A���ɕ{��8�N�ԏZ�݁A�������ɘA��ė����V���l�ґ��m�����M�b��ʖ�ɂ���B �@���r�́A�B���Ɂu�ނ�͉w�����ɗ��𑱂��Ă��āA���̌��ɓ���������V�����ɗ��Č�H���Ă܂ł����������Ȃ�����{���ɓn��s���D�̂���̂�҂��ċA���������Ɛ\���o�Ă��題��ݤ���̉Y(�ԎR�Y)�ɑ؍����Ă��飂ƕ����B����ɑ��āA9���u���̑m������炭�������邱�Ƃ�C���悤��������{���ɓn�C���Ă����D�����������Ȃ�Τ���R�ɏo�������Ă悢��Ƃ��ꂽ�i�[�J��w����s�L�x�Ap.611-2�j� �@�����������Ă��邤���ɁA�N��846�i���a13�j�N�ɉ�����B����3��23���ɕ��@�����������Ƃ�m��B�������蕧���͕�������B3��9�����r����莆�����āA�ŋ߁u���{����m1�l�ƈ�ʐl4�l���c�c���ܗg�B�������Ă��褓��{������̎莆�m�������̕����Ȃǁn�Ɨa���������Ă������蕨�Ȃǂ��g���āA�����ɐ��v�m�~�m��q�ˋ��߂Ă��飂Ƃ���������̑m�́A���łɂ݂����ד��̑D�ɏ���đ^�B�ɂ����A�~�m����q�̐��C�ł������B�ނ��Ăъ邱�ƂƂȂ�A10��2���ɂȂ��ėg�B�������ė���B |
 |
| �Z�g��c�M�A���s�E�^���Ɋy���� �]�ˎ���O�� �w���o��t�~�m�Ƃ��̖���x���� NHK�v�����[�V����, 2007 |
�@�[3��10���A����ɍ�����������B�V�����̌����g�߂̕��g��ɁA����̖��`���g���ĉ������̐l�𑗂�o�����Ƃ��ď���ɑD���Ă���Ȃ��礒��삩��h�����ꂽ�g�߂ɑ��Ă͂�������Ă��}�����ڑ҂��傤�Ƃ����Ȃ���ƁA���r��槌�������̂��o���B�u���g��́A���̍����������āA����g�̍s����[�����Ԃ��褕������o���Č����ɂ́w���̋������褑D�����R�ɔh�����ċq�l�𑗂�͂��A��C��n��Ȃǂ̎��͋�����Ȃ��x�Ǝw�E�����v�y��6�z�
�@�u����ւ́A�ނ�ɂǂ����Ă������̍l�����咣���邱�Ƃ͂�������g�̕��������ۂ���悤�����Ƃ͂��Ȃ�����������������Ƃ����������߁A���o���̒n�����C��n���āA�m���r�̑D�ʼn~�m�������n���{�ɋA��Ƃ����v��͎������Ȃ�����������ő��k���āA���B(�J�g)�ɍs���āA���{�����_���m��_���Ƃ������O�n��̑D��ǂ����߂ċA�����悤�Ƃ������ƂɂȂ����v����܂⒣�r�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A�u����D���K�߂ām���Ƃ߂ān�A����d��v���ƂƂȂ�i�ȏ�A�[�J��w�����s�L�x�Ap.627-8�j�B
�@���r�́A������Z���̖ɂ��A�u�V���l�ɂĂ��ƒ��̕����̏��Ȃ衒���ḌR���x����\������o�B���R�����ɂ́A���̓V�q������D�����ɂ��Ĥ�����ɂ��炸������̗��㤐C���̑�g�ƂȂ褐V�������������Ĥ���o���o�B�Ɋւ��鎖���ǂ���v�Ƃ����i�����w�����L�x�Q�Ap.307�j����łɂ݂��悤�ɁA���͗���̏��a8�N(841)11���A���Ȃ킿�~�m�̒����؍ݒ��A�ÎE����Ă���B�~�m�͒��r�𗊂݂Ƃ��ċA�����悤�Ƃ������A���łɏ�͑傫���ω����A����}�̐��͂͌��ނ��Ă����Ƃ݂���B
�@�[3��17���A���B����D��[��5�D]���āA6��5���^�B�ɍs�������B�����ŎO�x�A���T���ɉ����A�u��������o�q���ē��{�ɋA���ł���悤�͂����Ăق����v�Ɨ��ށB6��9���A�V���l�̋��������A���{�����̑D�ɉ~�m�������悹�Ă悢�Ƃ��āA�ԎR�Y�Ɍ��������Ƃ�����������y��7�z�B���̑D�ƍs���Ⴂ�ƂȂ��Ă����̂ł���B�����ŁA6��18���~�m�����͐V���V�̉����̑D�ɏ���Ė߂낤�Ƃ���B�������ǂ������Ȃ��A�����������߁A7��13���]�Ғ��Y���𗤘H�A�ԎR�Y�ɘA���ɑ��点�A�o�q��҂��Ă����悤���łi�ȏ�A�[�J��w����s�L�x�Ap.629-37�j�B
�@�悤�₭�ǂ��������āA�u7��20���B���R�̒��̉Y�ɒ������B������̑D���������Ƃ��ł����B�����ɐl��ו����ڂ��āA��D��܂��Ȃ��o�������v�B���̒i���ɁA�[�J���ꎁ�͉~�m�炪�u�����ɋ����̑D�ɏ�D�A�o�q�������ƂŁA�ށm���Y���n�͒u������ɂ��ꂽ��ނ͂̂��A������~��(�q�ؑ�t��m814-91�A�V��@��h�J�c�n�A853�N����)�̒ʖ�Ƃ��čē���������ł��ĉ~�m��������ّ����E����@�������@���̖@�S�a���ɋ��R���ނ��~�m�̌��]�҂ł��邱�Ƃ�m���āA�@�S�����삷�邭���肪����(�~�������E���o���^�w�s�����x�j�v�Ƃ������L�����Ă���i�ȏ�A�[�J��w����s�L�x�Ap.637�j�B
���V���D�A�S���쓹�o�R�A�����ɒ�����
�@�u23�@�ԎR�Y���Ĕ�O�������Ɉ������v�̓^�C�g���ʂ�ł���B
�@7��21���A�o�B�ɗ��āA�D���~�߂�ƁA�����V���g�̒��r���D�ɂ���ė���B���̌�A�悤�₭�u9��2���B���߁A�ԎR�Y�����C��n��n�߁c�c�^���Ɍ������čs���v�B�������A�u9��4���B�������Ɏ����ē��̕����ɎR�������顂��邢�͍������邢�͒Ⴍ�A�i���Ȃ��Đڂ��A�Ȃ��Ă���v�B�����́A�V���̐��̌F�B(�����쓹�j�ł������B�u��10�������O����ړ�(�S���쓹�����̐�)�ɒ������┑�����v��u9��6���B�ߑO6������B(���B)�̓���̈�ɂ��鉩�����m�u�����Ƃ������n�̓D�Y�������┑�����v�i�ȏ�A�[�J��w����s�L�x�Ap.638-41�j�
�@�����āA9��9���A�S���쓹�Γ��ɎU�݂���哇�ɒ����Ă��炭�x��A�쓌�ɐi�ނƁA�u9��10�����������邱�뤓��̕����y���ɑΔn�̓��e�����������12������A�O���ɓ��{�̍����R�������Ă���������琼��ɂ����ĘA�Ȃ��Ă͂�����ƌ����題ߌ�8������ɂȂ��āA��O�̍��̏��Y�S�k���̎����m��������n�ɓ�����┑�����v�B
�@�����u�閾���ɁA�}�O�̍��̒O�����̉Ɛb��a���������̒��ƂƂ��ɂ���ė��ĉ������ނ�����A����܂����{���̎�����m�����v�9��15���A�k�Y�i�ꏊ�s���j���o�R������A���Ɂu9��17���B�����̐���(���k�̌�肩)�\�����̉��ɓ�����┑�����v�̂ł���B��18���ɂ́A���e���ɓ���A�؍݂��邱�ƂƂȂ�i�ȏ�A�[�J��w����s�L�x�Ap.645-6�j�B
�@�u10��6������ɂ��猦80�D�Ɛ^��200�Ԃ���邱�Ƃ��ł����̂Ť�D���44�l�ɓ~�߂��x�������6���ɐ����̗ƂƂ��ĕ�10�������Ă����v(1�D�͌�4��12.4Ұ�٤1�Ԃ͐^��2�ݽ�A1����72�۸��сj�B����炪�^���i���̈ꕔ�j�Ȃ̂��A�ܗ^�Ȃ̂��A�z�~�i�Ȃ̂����炩�ł͂Ȃ��B����͂Ƃ����������̑D�̏�g����44�l�ł��邱�Ƃ�������B���̌�A�u10��19����������̒������������ɕ{�ɗ��������ɂ́w�~�m��5�l�����݂₩�ɓ�����������̐l�m�V���l�Ƃ͂����Ă��Ȃ��n������44�l�ɂ͏\���ɕ�V���x�����邱�Ƃ��A��ɕ{�ɖ�����x�Ƃ������v�i�ȏ�A�[�J��w����s�L�x�Ap.643-7�j�B
�@�Ȃ��A�u�~�m��5�l�v�Ɋւ��āA�u��q�Ґ�����Y����ԎR�Y��蓯�D�ŋA�������鐫�C�@�t�A�v4�l�1�l�s�ڂȂ�v�Ƃ����A�����Ǔ����̕⒍������i�����w�����L�x�Q�Ap.325�j�A���Y���͒u������ɂ���Ȃ������悤�ɂȂ��Ă���A�܂��s�ڎ҂͐��C�̓����D�̓���҂ł��Ȃ��悤�ł���
�@���̂悤�ɁA�~�m������847�i���a14�j�N7��20���ɋ����̐V���D�ɏ������A��2�����Ŕ����ɖ߂��ė��āA838�i���a5�N�j6��13������ق�9�N�ɂ킽�铂�ւ̋��@����̗����I����B�������]�Ȑ܂͌v��m��Ȃ����̂��������킯�ŁA���S���ʂł������͂��ł���B�������A���̋A�H�ƋA���ɂ��āA���L�͋ɂ߂ĒW���ŁA���i�̊��z�͂Ȃ��B
���͂����Đ��E�̎O�嗷�s�L��?!��
 |
 |
| ��掛�i���Ɂj���A �i����E���{���F�������q�y�� �V�䍂�m����1�O���̂P�j ��������A11���I�㔼 |
�ԎR�T�@�i���s�j�� |
�@�����̐l�X���A�w�������@����s�L�x��|��E��������E.O.���C�V�����[�i1910-90�j�̏����̂�������A��}���R��|�[���m�w���������^�x�n�̏ꍇ�ɂ��Ă����Τ���s���I���Ă̂����N���o�Ĥ���ӂ̔ނ��ނ̖`�������ڂ��ɓ`�������̂ł��邩�礔���䩔��Ƃ������̂����顂�������~�m�̕ω��ɕx�ތo���ɂ��Ĥ1��1�������ɋL�������L�͐��E�j�ɂ����铖���̃��j�[�N�������ł���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�����ȊO�ɁA�u�ł��悭�m��ꂽ���̂�1�́A�̑�Ȓ����m�ŗ��s�Ƃł��錺���m600-64�n�́m629-645�N���s���n�������w�哂����L�x�ł���v���A������u�~�m�̓��L�Ɍ�����悤�ȏڍׂ��Ƥ�������F�ʤ����l�ԓI�L�^�Ɍ�����_�����邱�Ƃ��ۂ߂Ȃ��ł��낤��ȂǂƂ������������A���p����i�����w�~�m�@���㒆���ւ̗��x�Ap.3�A10�A�����[�A1984�j�B
�@�����Ǔ����������悤�ɁA�u�ނ̂��̂悤�Ȕ����ɂ���Ĥ�������{���́w���������^�x��w�哂����L�x�ƂƂ��ɐ��E�̎O�嗷�s�L�Ƃ����悤�ɂȂ����v�悤�ł���Ƃ��A����ɋ^��𓊂������A399�N����412�N�ɂ�����C�𗷍s�����@���́w��V�V���L�`�x�܂��́w�@���`�x��671�N����695�N�ɂ����ĕ��Ղ�q�˂��`��(635-712)�́w��C��A���@�`�x4����w�哂���拁�@���m�`�x2���Ȃǂ������Ƃ��顂���ɁA���{�ł͒q�ؑ�t�~����853�N����858�N�ɂ����ē��������w�s�����x������A���q�i1011-81)�́w�Q�V��d�R�L�x4���͉~�m�̂���ɔ䌨����Ƃ���i�����w�����L�x�P�Ap.323-4�j�B
�@���C�V�����[�������̂�������m��Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�����ƃ}���R��|�[���Ƃ��ꂱ ��ƑΔ䂵�Ă�܂Ȃ��B�ނ�m�̋L�^�͋��@�Ƃ������ʂ̖ړI�������Ă���A���ꂪ�Ȃ��}�� �R��|�[���ƑΔ䂷��̂͂��������؈Ⴂ�Ƃ������̂ł���B�}���R��|�[���̂���͒P�Ȃ闷 �s�L�ł���i����ɂ��Ă�Web�y�[�W�y�u�}���R�E�|�[�����������^�v��ǂށz�Q�Ɓj�B������ ������C�V�����[�����グ�Ă��Ȃ��A����ȊO�Ɉ̑�ȋ��@���s�L�Ƃ�����̂́A�C�H�C���h���������C���h�S����߂����Ă���y���V�A�A�����A�W�A�A�����ċA�r�A���ւƑ嗷�s�� ���A�~�m��������̐V���m�̌d���i704-87�j�́w���ܓV�����`�x�ł��낤�B�����āA����͉����邪�A�����b�R�̃C�X���[�����k�̖@���C�t���E�o�b�g�E�[�^�i1304-1368/9�j�́w�嗷�s�L�x�i����ɂ��Ă�Web�y�[�W�y�u�C�t���E�o�b�g�E�[�^�̑嗷�s�L�v��ǂށz�Q�Ɓj�ł��낤�B
�@�~�m�́w�������@����s�L�x���Ȃ߂����͂��炳��Ȃ����A����͉~���A���q�Ƃ��ǂ��A���̓��e�͂��Ă����āA���{�Ɩk�����Ƃ����ɂ߂Č��肳�ꂽ�n��ɂ����鋁�@����s�L�ɂƂǂ���B���������āA�A�W�A�̎O�嗷�s�L��1�ł��Ȃ��A���E�̎O�嗷�s�L��1�ł�����ɂȂ��B���̗��s�͈̔͂���ԁA����ɓ��e����݂āA�ō��̐��E�嗷�s�L�Ƃ��Ă܂���������̂́u�C�t���E�o�b�g�E�[�^�̑嗷�s�L�v�ł��邱�Ƃ����͖��炩�ł��낤�B
�@��}���R�E�|�[�����������^�v�͌��q�M�L����A������������̍�ׂ�������Ă���A�����ĕ]���̍����Ȃ��B�����������̗��s�L�������ɂ��āA�w�������@����s�L�x�𐢊E�̑嗷�s�L�̂����Ɏ����グ�邢�������́A�ނ���~�m���Ȃ߂邱�ƂƂȂ낤�B�f���ɁA�w�������@����s�L�x�́A�������̒������������]�����ƂȂ������c�����A��P���̋��@����L�ł���Ƃ����ׂ��ł������B
�������g�D�̏�D�҂Ƃ��̋A���ҁ�
�@�����Ǔ����́A�w�������@����s�L�x�̓��e�͂��āA���̎�v�Ȏ������u1�@���a�����g�A2�@�n�q��M�s�A3�@�n���I�ώ@�A4�@�o�ϓI�ώ@�A5�@���̊����A6�@�����ɂ�����V���l�A7�@���O�̍s���Ƒ��M�A8�@���㒆���̎��@�A9�@�����s���ƋV��A10�@�ܑ�R�����A11�@�����̕����A12�@�p���̑̌��A13�@���{�Ñ㎑���v�ɕ����ĉ�����Ă���B�@���̂����A�u2�@�n�q��M�s�v�́u1100�N�O�̓����D�̍\����@�\���g���̍\������^�͏M�s���u�D�ȂǁA�D���̎�ނ�D�s�@�Ȃ���m�肤�邵��܂������⍿�ʂɂ���D�݂̂Ȃ炸��r�C�̐��X�����L�^�⏇����҂����������礓����̓n�C�������Ɋ댯���Ƃ��Ȃ���ł����������킩�顂��̎��R�̋��|�ɑ��āA�_���ɋF�����鐔�X�̕��@���݂���B�M�s��ʂ��Ē����嗤�Ɍ@��߂��炳�ꂽ�^�͂̂��Ƥ���̏M�s�̏ڂ��������͖w��ǐ��m�ł���A�͐��s�W�̕ϑJ���悭���������v�B
�@�u4�@�o�ϓI�ώ@�v�́A�u�����g��s�̕��i���դ���֥���S�Ȃǂ̔����֎~���礊e�n�̍��ނ����i��ݍւ̔�p����T��@�߂̉��i��ʌo�̒��घO�t���ݔ車����醂�n�M�̒����܂ŋM�d�ȋL�^���c���Ă��邵����w�m�ɗ^����ꂽ��p�̒f�ГI�L�q����ओ����҂̌o�ϓI������������
�@�u6�@�����ɂ�����V���l�v�́A�u���̗��s�L�ɓo�ꂷ��V���l�̐��ͤ�����l�ɕC�G���顐V���l�ʖ�͌����g�̈���ł��炠�褌����g�̋A�҂ɂ������Čٗp����9�ǂ̑D��60�]���̐��v�ͤ���C�Ŋ������Ă���l�����ł�����������A���݂̐V���f�Ղɂ��Ă͒f�ГI�ȋL�q������������V�������̌R���I�����ƂƂ��ɤ�������V���Ԃ̖f�Ղɏ]���������y�т��̉e�����̐V���l�Ƃ̐ڐG�ͤ���y�ɂ�����~�m�̉^������ς����ƌ��ʓI�ɂ͔��f�ł��顒����V���l�̋����n�ł���ԎR�Ɍ��Ă��@�؉@�y�т��̑m�����̋L�q�⤊e�n�̐V���@�̂��Ƃ��Ǥ�����̓��ɂ�����V���l�̍s���̋L�^�͑S�����ɗ���݂Ȃ������ł����Ĥ���ڂɉ�����������v�悤�ɂȂ��Ă���i�ȏ�A�����w�����L�x�P�Ap.326-7�j�
�@��������������݂�ƁA���ꂼ��ɏڍׂȓ��e����������ċL�^����Ă��邩�Ɏ��ꂩ�˂Ȃ��B�������A�����͂����łȂ��A�l�X�ȓ����ɒf�ГI�ɂ���߂��Ă���ɂƂǂ܂�B
�@�Ⴆ�A�u�����D�̍\����@�\���g���̍\���v�Ƃ������A�����g�D�����{�����ǂ��������������炩�łȂ��B�����g�̕Ґ��ɓ������đ��D�g���C������Ă���̂ŁA����炪�����Ō������������ɂ݂��邪�A�肩�łȂ��B�}���R�E�|�[���̂悤�ɑD�̍\���ɂ��Đ������Ă���킯�ł������B
�@���܁A��D�҂̍\�����~�m�̓��L���琮������ƁA���̂悤�ɂȂ�B�g�߂Ƃ��Ă̑�g�i�D��=�w�����j�A���g�̑��ɁA�����Ƃ��Ă̔����i�s�����j�A�^���i�鏑���j�A�y�����A�y�^���A�m��D���i�č��M�A�ωǗ����j�A�ʎ��i�ʖ�j�A�j���i���L�j�Ƃ��������l�������B�����Ɍق�ꂽ���t�A�蕔�i�Վҁj�A��ƁA�ˎ�i�x�����j�A�G�E�Ƃ������l�X�������B���w�҂Ƃ��āA���v�m�A�w���m�A���j���A�V�����A�A�z���A�������A��y�������悵�Ă����B�����āA�^�q���Ƃ��āA�D�t�A�y�D�t�A���蒷�A����A�s���i�����j�A�ԏ��i��H�j�A�D�H�A�b�H�A�E�l�����g��ł����B
�@�~�m�̓��L����́A�����g�D���ꂼ��̑傫����A��D�Ґ��Ƃ��̑����͂قڂ܂������������łȂ��B836�N�o�����̏�D�ґ����́A�w�����{��L�x�ɂ���600�]�l�A�w�鉤�ҔN�L�x�ɂ����651�l�Ƃ���A1�Ǔ�����̕��Ϗ�D�Ґ��͖�150-163�l�ƂȂ�B�ŏ��̑���ŁA��3�D�̏��D�҂���110�l�قǂ����S�����Ƃ����B�܂��A�A�����̑���œ�����2�D�̏�D�҂�140�l���ǂ����S�����Ƃ����B���̑��A�~�m�̓��L�ł�13�l���a���Ă���B���ꂾ���ŁA���S�҂͎���270�l��ƂȂ�A�o������D�҂�40�߰��Ă�����B�Ȃ��A�A����A���삩��h�_�����҂�391�l�ƂȂ��Ă���̂ŁA���̎��S�Ґ��͏��������B
���X���ɂ����鎄���Ղ̋֎~�A���^�E������
�@�����g���܂����v�ł������B����͒P�ɒ����c��ɑ��Đb���̗���Ƃ邾���łȂ��A������O��Ƃ������v���Ղ��܂ނ��̂ł������B����ɁA����𗘗p���Ď����Ղ��s��ꂽ�Ƃ����B���̎����Ղ͕��i�̔�������łȂ��A���̑��^�E������ʂ��Ă��s����B
�@�������A�~�m�̓��L���݂邩����A���a�̌����g�ɂ����钩�v���Ղ͂قƂ�ǖ��炩�ɂȂ�����y��8�z�B�������A�����g�̈�s�������̌��Օi����������ł������Ɩ��炩�ł���B���łɂ����悤�ɁA838�i���a5�j�N7�����]�͌�����g�B�Ɍ������ہA40�]�ǂ̂��₢�D�Ɋ����̍������^�ѓ��ꂽ�Ƃ����B���̗ʂ͗e�Ղɐ��@�����Ȃ����A1�Ǔ�����̐ωׂ�1�݂Ƃ���ƁA���ʂ�40�݁A����Ɋւ��l����200�l�Ƃ���ƁA1�l������0.2�݂ƂȂ�B
�@����͂Ƃ������A�~�m�̓��L���������A�X���ɂ����鎄���Ղ͌����A�֎~�ƂȂ��Ă����悤������B�~�m�������A�g�B����^�B�܂ōs���đ�g��s�ƍ������悤���Ă����A839�i���a6�j�N2��20���u���߂��뤐�ɒ������ɓ������g�߂̂����A�č��M(���v���Ǘ���)�̏t���h�H�i���ƎG�g(�G���W)�R��g�i��ˎ�̏㋳�p����������̏]�Ҕ���������������10�]�l��1�̑D�ɏ���Ă���ė����c�c��g��s�͍���12���^�B(�̂��̟̈�)�ɓ�����؍ݒ��ł��顒����̓s�ł����̔������ł��Ȃ������̂Ť�O�L�̐l�������A�G�����m���킹��n����(�g�B��)�h�����ė����̂ł��飡����ȑO�̓����ɂ����Ă��A�u�����g�S���̌R���Z���F�^�́c�c�i���炪����������̂�����������ۂ�ł��炵�Ă����v�Ƃ����
�@�����A�u��4���̊č��M�ł��鐛�������ƒʖ�(�p����?)�����߂ŋւ����Ă���i�������Ƃ������ƂŤ�m�ߓx�g�́n���������T�͐l�����킵�ė��ď������m�Ă��n���2�l�͎g���̎҂ɐ����ďB�����ɓ����Ă������c�c�������ɂȂ��ċ�����āc�c����߂��ė�������������̏]�Ҕ��������������Ɗw���̎l�l�́A�������i�����Ƃ��đD������Ďs�X�ɍs������W���Ɏ�����ׂ��200�т̑K�m����ł���n���̂Ăē����������3�l�������A���Ă����v�i�ȏ�A�[�J��w����s�L�x�Ap.133-4�j�B�����āA22���ɂ��A�����悤�ȃg���u������������B
�@���̂悤�ɁA��4���̏�D�҂��肪�����Ղ������Ƃ��Ă��p�ɂȂ��Ă���̂́A�ނ炪��ɑ��g��s�ɐ����������ߋ֗߂���炳�ꂽ����ł��낤�B����ȊO�̋��c��g�͂��łɂ��ꂱ����������Ղ����Ă����Ƃ݂���B�Ȃ��A838�i���a5�j�N7��18���A�u��Ӓ����ۂ��������Ă����������͂��̍��̂Ȃ�킵�Ť�x��̐l�����Ċ��̕�����邽�߂ɁA��ɂȂ�Ƒ��ۂ�ł̂ł���v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.37�j�����͕\�����ł����āA�����̍����̎����Ղ��Ď��������߂ɂ������Ƃ݂���B
�@�����g��s���A�ǂ̂悤�Ȋ����̍����𓂂Ɏ��������͕s���ł��邪�A�����̑��^���������͖��炩�ƂȂ�B���łɂ݂��悤�ɁA������g������k�͉~�m�����Ɋw���^�i�⏕�j���Ă���i����͊����Ƃ݂���j�B�Ⴆ�A839�i���a6�j�N2��27���A�~�ڂ��V��R�Ɍ������ɓ������āA�u�����܌�(�֓��Y�̌�)35�D(1�D��4�䤖�12Ұ��)���^��10�����ˤ�����^��65��(1�Ԃ�6���223.8����)�����25�嗼(1�嗼��3����)�����킵�^�����A�w��̎����ɂ��Ă������v�Ƃ���i�[�J��w����s�L�x�Ap.142�j�B
�@�~�m���A�����l�X�Ȑl�X�ƕ��i���ӗ炠�邢�͓y�Y�����S�ʕi�Ƃ��đ��^�������Ă���B�Ⴆ�A���N3��22���A�����A���D���o���ɓ������āA�ݗ��̐��b�������V���l�ʖ�̗��T�����u������2���Ƒ�⍘�сi�����������сj��^�����v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.148�j�B�������A�~�m�̓��L���������A�ނ͑��^����邱�Ƃ������A���^�������̂͂킸���ł���B�������A�ނ̑��^�i�͒P�ɓy�Y���Ə̂������̂������A��̓I�Ȃ��̂͋�̑������{�����i�C�t����Ѥ�M�̃Z�b�g������̎쐔�������@���L��H�p�̊C���Ƃ��������ׂȂ��̂ł������B
���~�m�����������A�����o�T�╧��Ȃǁ�
�@����ɑ��āA�~�m�����^���ꂽ���̂́A���푽�l�ō��z�ȋ��i�ł������B�Ⴆ�A�~�m������845�i���a12�j�N5��15�����m�̑m���A�哿�A�����̑��ʂ��āA������ދ�����ہA�������S�ʕi������Ă���B�Ⴆ�A�E���Y���E�k�D�m�́u�ȑO�Ɍ���ѐD���̔����ނ≺�т��ǂ��{���Ă��ꂽ���Ƃ���������ނ́A���܁c�c�S�ʂƂ��Č�2�D(��25Ұ��)��֒���(�l��ȉ�B�Y����)2��(��1.2�۸���)��c��1����K2�ѕ�(2000��)�𑗂��Ă����v�Ƃ��A����E����������u����(�h�B�n���ŐD��������)10�D��h����1�{���h�ō�����g�їp����2����a��(���낢��ȍ������킹������)1�т���5�҂̔��ܗ��i�����@��)1�¥�t�F���g�̖X�q2�¥�⎚�̋����o1�����炩������1����K2�ѕ����ł������v�i�ȏ�A�[�J��w����s�L�x�Ap.580-1�j�B
�@�~�m�����́A��g��s�������ɏo�����Ă���ԁA�g�B�ɑ؍݂��Ă������A���̒n�ɂ����Ă��Ȃ�̌o�T�╧����w�����Ă����悤�ł���B�����g�A���D10�ǂ��A������ɓ������āA�~�m�����͈���ōݗ��̊�Ă�i�߂Ȃ���A������839�i���a6�j�N4��5���A�u�����ŋ��ߓ����o���̓������|����1��������E��ّ��E�����̙֑ɗ���d�l(���d�̗l��)�Ȃǂ���ꂽ��̑唠1���A��8�D�̎w�������h�H�Ɋ����������Đg�̉��̕����ˑ����Ă����v�̂ł���i�[�J��w����s�L�x�Ap.160�j�
�@����ɁA�~�m�����͒����ɓ����āA���̒����ɂ킽��؍ݒ��A�o�T�╧����w�����A�������ʌo�A�͎ʂ����Ă������B��������ދ���]�V�Ȃ������ƁA�u�������x�x�ɂ�����A������ʂ��������o�_������V�O��֑ɗ�������肵�āA�S������I���������ނƈߕ��͍��킹��4��(���Â�)������������ŁA3����途n���āA���̌��菑������̂�҂�����ґ��������邱�Ƃ��S�z�������̂ł͂Ȃ�����������ʂ����������(�T�Ђ╧��)��g�ɂ��āA���{�Ɏ����čs�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ邱�Ɓc�c�A���r���̏��B��{�̓_���ʼnו��̒����������邱�Ƃ����ꂽ�v�������Ă���i�[�J��w����s�L�x�Ap.573�j�
�@�~�m���������ꂽ���Ԃ͉w������̂Ȃ��ő傢�ɂ��������A�����̍����̏Љ���V���l�̋��͂ŖƂ�邪�A��@�ꔯ�������Ƃ�����B����͕��@������ł��ꂽ����ł������B845�i���a12�j�N7��5���A�^�B����o�B�ɑ�����ہA�V���l�ʖ�̗��T���Ƒ��k���āA�u�k�Ɍ������r���̏B���̐l�S�͑e�\�ň�������c�c�ᒺ�̍߂ɋy�Ԃ��ƂɂȂ낤�c�c���������玝���ė����c�c����4�̂Â�́A���炭���T���ʖ�̉Ƃɗa����������ʖ�ɊǗ����邱�Ƃ𗊂����v����ʖ�́u�s������ʂ̏ꏊ�ɂ��܂��Ă��ꂽ��m���̏�n�L��g��3���̑��܂��{���Ă������ʖ�͌�9�D�ƐV���̏���10�{(�䔯�p)�����5������̑����Ȃ���ʂ��̂��{���Ă��ꂽ�v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.596�j�
�@���@�̎���A846�i���a13�j�N2��5���N�A�~�m�����͒��Y����D�ő^�B�Ɍ����킹�A�a�����������̂�����ė������邱�ƂƂ����B�u6��29������Y�����߂��ė�������킹�đ^�B�̎{�嗫�T���̎莆������������ɂ��Ƥ��ɗa�������Ă�������╶���̂�����ّ�����������̑��֑ɗ��ŋɍʐF�̕t�������̂ͤ�̓�ߓx�g�̒��ɏ]�����ʒ������ɂ��т��������̂Ť�T�������łɏĂ��ď������Ă��܂����Ƃ����B���̑��̒��F�̂Ȃ�����╶���Ȃǂ͂��ׂĉ^�ю����ė��邱�Ƃ��ł����v�i�[�J��w����s�L�x�Ap.624�j�B�ʖT���́A���{���痈���~�m�ւ̑������g������ł���A���̗a����i�̏ċp�������ɂ킩�ɂ͐M�p�ł��Ȃ��B
�@���̌�A���������x���D�ɐςݑւ��Ȃ�����{�Ɏ����A�����킯�ł��邪�A�����̏����i�̃��X�g�A�ז���A���̌o�߂ɂ��ẮA���L�͌��Ȃ��B�[�J���ꎁ�́A�u�����V���������^�v��t�^�Ƃ��Ď����Ă���Ă���B���̓��e�́u������ܑ�R����їg�B�Ȃǂŋ��߂��o�_��O�u�̖@�储��я͑`��`�L�����ׂČv584���802����ّ�����������̑�֑ɗ�����я����̒d����ɗ��Ȃ�тɍ��m�̐^�e�ȂǍ��킹�Čv50�_�v�ƂȂ��Ă���i�[�J��w����s�L�x�Ap.658�j�B
�@����ȊO�ɁA�l�X�ȕ����Y��A�ґ�i�������A�����ł��낤�B�����������Ȃ�����A�܂������A�z�{�A�ٗp�A�p���Ȃǂɓ������āA�~�m�����͂��ꂱ��̓y�Y���ł͎����肸�A���{���瑊���ʂ̍�������������ŁA����ɓ��Ă��Ƃ݂���B���@�m�͏��l���o�Ȃ��ɁA���@����̗��͂ł��Ȃ������ł��낤�B���̗��͌��Ղ̗��ł��������ł��낤�B
�@�����Ǔ����������悤�ɁA�u�ނ̂��̂悤�Ȕ����ɂ���Ĥ�������{���́w���������^�x��w�哂����L�x�ƂƂ��ɐ��E�̎O�嗷�s�L�Ƃ����悤�ɂȂ����v�悤�ł���Ƃ��A����ɋ^��𓊂������A399�N����412�N�ɂ�����C�𗷍s�����@���́w��V�V���L�`�x�܂��́w�@���`�x��671�N����695�N�ɂ����ĕ��Ղ�q�˂��`��(635-712)�́w��C��A���@�`�x4����w�哂���拁�@���m�`�x2���Ȃǂ������Ƃ��顂���ɁA���{�ł͒q�ؑ�t�~����853�N����858�N�ɂ����ē��������w�s�����x������A���q�i1011-81)�́w�Q�V��d�R�L�x4���͉~�m�̂���ɔ䌨����Ƃ���i�����w�����L�x�P�Ap.323-4�j�B
�@���C�V�����[�������̂�������m��Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�����ƃ}���R��|�[���Ƃ��ꂱ ��ƑΔ䂵�Ă�܂Ȃ��B�ނ�m�̋L�^�͋��@�Ƃ������ʂ̖ړI�������Ă���A���ꂪ�Ȃ��}�� �R��|�[���ƑΔ䂷��̂͂��������؈Ⴂ�Ƃ������̂ł���B�}���R��|�[���̂���͒P�Ȃ闷 �s�L�ł���i����ɂ��Ă�Web�y�[�W�y�u�}���R�E�|�[�����������^�v��ǂށz�Q�Ɓj�B������ ������C�V�����[�����グ�Ă��Ȃ��A����ȊO�Ɉ̑�ȋ��@���s�L�Ƃ�����̂́A�C�H�C���h���������C���h�S����߂����Ă���y���V�A�A�����A�W�A�A�����ċA�r�A���ւƑ嗷�s�� ���A�~�m��������̐V���m�̌d���i704-87�j�́w���ܓV�����`�x�ł��낤�B�����āA����͉����邪�A�����b�R�̃C�X���[�����k�̖@���C�t���E�o�b�g�E�[�^�i1304-1368/9�j�́w�嗷�s�L�x�i����ɂ��Ă�Web�y�[�W�y�u�C�t���E�o�b�g�E�[�^�̑嗷�s�L�v��ǂށz�Q�Ɓj�ł��낤�B
�@�~�m�́w�������@����s�L�x���Ȃ߂����͂��炳��Ȃ����A����͉~���A���q�Ƃ��ǂ��A���̓��e�͂��Ă����āA���{�Ɩk�����Ƃ����ɂ߂Č��肳�ꂽ�n��ɂ����鋁�@����s�L�ɂƂǂ���B���������āA�A�W�A�̎O�嗷�s�L��1�ł��Ȃ��A���E�̎O�嗷�s�L��1�ł�����ɂȂ��B���̗��s�͈̔͂���ԁA����ɓ��e����݂āA�ō��̐��E�嗷�s�L�Ƃ��Ă܂���������̂́u�C�t���E�o�b�g�E�[�^�̑嗷�s�L�v�ł��邱�Ƃ����͖��炩�ł��낤�B
�@��}���R�E�|�[�����������^�v�͌��q�M�L����A������������̍�ׂ�������Ă���A�����ĕ]���̍����Ȃ��B�����������̗��s�L�������ɂ��āA�w�������@����s�L�x�𐢊E�̑嗷�s�L�̂����Ɏ����グ�邢�������́A�ނ���~�m���Ȃ߂邱�ƂƂȂ낤�B�f���ɁA�w�������@����s�L�x�́A�������̒������������]�����ƂȂ������c�����A��P���̋��@����L�ł���Ƃ����ׂ��ł������B
�������g�D�̏�D�҂Ƃ��̋A���ҁ�
�@�����Ǔ����́A�w�������@����s�L�x�̓��e�͂��āA���̎�v�Ȏ������u1�@���a�����g�A2�@�n�q��M�s�A3�@�n���I�ώ@�A4�@�o�ϓI�ώ@�A5�@���̊����A6�@�����ɂ�����V���l�A7�@���O�̍s���Ƒ��M�A8�@���㒆���̎��@�A9�@�����s���ƋV��A10�@�ܑ�R�����A11�@�����̕����A12�@�p���̑̌��A13�@���{�Ñ㎑���v�ɕ����ĉ�����Ă���B�@���̂����A�u2�@�n�q��M�s�v�́u1100�N�O�̓����D�̍\����@�\���g���̍\������^�͏M�s���u�D�ȂǁA�D���̎�ނ�D�s�@�Ȃ���m�肤�邵��܂������⍿�ʂɂ���D�݂̂Ȃ炸��r�C�̐��X�����L�^�⏇����҂����������礓����̓n�C�������Ɋ댯���Ƃ��Ȃ���ł����������킩�顂��̎��R�̋��|�ɑ��āA�_���ɋF�����鐔�X�̕��@���݂���B�M�s��ʂ��Ē����嗤�Ɍ@��߂��炳�ꂽ�^�͂̂��Ƥ���̏M�s�̏ڂ��������͖w��ǐ��m�ł���A�͐��s�W�̕ϑJ���悭���������v�B
�@�u4�@�o�ϓI�ώ@�v�́A�u�����g��s�̕��i���դ���֥���S�Ȃǂ̔����֎~���礊e�n�̍��ނ����i��ݍւ̔�p����T��@�߂̉��i��ʌo�̒��घO�t���ݔ車����醂�n�M�̒����܂ŋM�d�ȋL�^���c���Ă��邵����w�m�ɗ^����ꂽ��p�̒f�ГI�L�q����ओ����҂̌o�ϓI������������
�@�u6�@�����ɂ�����V���l�v�́A�u���̗��s�L�ɓo�ꂷ��V���l�̐��ͤ�����l�ɕC�G���顐V���l�ʖ�͌����g�̈���ł��炠�褌����g�̋A�҂ɂ������Čٗp����9�ǂ̑D��60�]���̐��v�ͤ���C�Ŋ������Ă���l�����ł�����������A���݂̐V���f�Ղɂ��Ă͒f�ГI�ȋL�q������������V�������̌R���I�����ƂƂ��ɤ�������V���Ԃ̖f�Ղɏ]���������y�т��̉e�����̐V���l�Ƃ̐ڐG�ͤ���y�ɂ�����~�m�̉^������ς����ƌ��ʓI�ɂ͔��f�ł��顒����V���l�̋����n�ł���ԎR�Ɍ��Ă��@�؉@�y�т��̑m�����̋L�q�⤊e�n�̐V���@�̂��Ƃ��Ǥ�����̓��ɂ�����V���l�̍s���̋L�^�͑S�����ɗ���݂Ȃ������ł����Ĥ���ڂɉ�����������v�悤�ɂȂ��Ă���i�ȏ�A�����w�����L�x�P�Ap.326-7�j�
�@��������������݂�ƁA���ꂼ��ɏڍׂȓ��e����������ċL�^����Ă��邩�Ɏ��ꂩ�˂Ȃ��B�������A�����͂����łȂ��A�l�X�ȓ����ɒf�ГI�ɂ���߂��Ă���ɂƂǂ܂�B
�@�Ⴆ�A�u�����D�̍\����@�\���g���̍\���v�Ƃ������A�����g�D�����{�����ǂ��������������炩�łȂ��B�����g�̕Ґ��ɓ������đ��D�g���C������Ă���̂ŁA����炪�����Ō������������ɂ݂��邪�A�肩�łȂ��B�}���R�E�|�[���̂悤�ɑD�̍\���ɂ��Đ������Ă���킯�ł������B
�@���܁A��D�҂̍\�����~�m�̓��L���琮������ƁA���̂悤�ɂȂ�B�g�߂Ƃ��Ă̑�g�i�D��=�w�����j�A���g�̑��ɁA�����Ƃ��Ă̔����i�s�����j�A�^���i�鏑���j�A�y�����A�y�^���A�m��D���i�č��M�A�ωǗ����j�A�ʎ��i�ʖ�j�A�j���i���L�j�Ƃ��������l�������B�����Ɍق�ꂽ���t�A�蕔�i�Վҁj�A��ƁA�ˎ�i�x�����j�A�G�E�Ƃ������l�X�������B���w�҂Ƃ��āA���v�m�A�w���m�A���j���A�V�����A�A�z���A�������A��y�������悵�Ă����B�����āA�^�q���Ƃ��āA�D�t�A�y�D�t�A���蒷�A����A�s���i�����j�A�ԏ��i��H�j�A�D�H�A�b�H�A�E�l�����g��ł����B
�@�~�m�̓��L����́A�����g�D���ꂼ��̑傫����A��D�Ґ��Ƃ��̑����͂قڂ܂������������łȂ��B836�N�o�����̏�D�ґ����́A�w�����{��L�x�ɂ���600�]�l�A�w�鉤�ҔN�L�x�ɂ����651�l�Ƃ���A1�Ǔ�����̕��Ϗ�D�Ґ��͖�150-163�l�ƂȂ�B�ŏ��̑���ŁA��3�D�̏��D�҂���110�l�قǂ����S�����Ƃ����B�܂��A�A�����̑���œ�����2�D�̏�D�҂�140�l���ǂ����S�����Ƃ����B���̑��A�~�m�̓��L�ł�13�l���a���Ă���B���ꂾ���ŁA���S�҂͎���270�l��ƂȂ�A�o������D�҂�40�߰��Ă�����B�Ȃ��A�A����A���삩��h�_�����҂�391�l�ƂȂ��Ă���̂ŁA���̎��S�Ґ��͏��������B
���X���ɂ����鎄���Ղ̋֎~�A���^�E������
�@�����g���܂����v�ł������B����͒P�ɒ����c��ɑ��Đb���̗���Ƃ邾���łȂ��A������O��Ƃ������v���Ղ��܂ނ��̂ł������B����ɁA����𗘗p���Ď����Ղ��s��ꂽ�Ƃ����B���̎����Ղ͕��i�̔�������łȂ��A���̑��^�E������ʂ��Ă��s����B
�@�������A�~�m�̓��L���݂邩����A���a�̌����g�ɂ����钩�v���Ղ͂قƂ�ǖ��炩�ɂȂ�����y��8�z�B�������A�����g�̈�s�������̌��Օi����������ł������Ɩ��炩�ł���B���łɂ����悤�ɁA838�i���a5�j�N7�����]�͌�����g�B�Ɍ������ہA40�]�ǂ̂��₢�D�Ɋ����̍������^�ѓ��ꂽ�Ƃ����B���̗ʂ͗e�Ղɐ��@�����Ȃ����A1�Ǔ�����̐ωׂ�1�݂Ƃ���ƁA���ʂ�40�݁A����Ɋւ��l����200�l�Ƃ���ƁA1�l������0.2�݂ƂȂ�B
�@����͂Ƃ������A�~�m�̓��L���������A�X���ɂ����鎄���Ղ͌����A�֎~�ƂȂ��Ă����悤������B�~�m�������A�g�B����^�B�܂ōs���đ�g��s�ƍ������悤���Ă����A839�i���a6�j�N2��20���u���߂��뤐�ɒ������ɓ������g�߂̂����A�č��M(���v���Ǘ���)�̏t���h�H�i���ƎG�g(�G���W)�R��g�i��ˎ�̏㋳�p����������̏]�Ҕ���������������10�]�l��1�̑D�ɏ���Ă���ė����c�c��g��s�͍���12���^�B(�̂��̟̈�)�ɓ�����؍ݒ��ł��顒����̓s�ł����̔������ł��Ȃ������̂Ť�O�L�̐l�������A�G�����m���킹��n����(�g�B��)�h�����ė����̂ł��飡����ȑO�̓����ɂ����Ă��A�u�����g�S���̌R���Z���F�^�́c�c�i���炪����������̂�����������ۂ�ł��炵�Ă����v�Ƃ����
�@�����A�u��4���̊č��M�ł��鐛�������ƒʖ�(�p����?)�����߂ŋւ����Ă���i�������Ƃ������ƂŤ�m�ߓx�g�́n���������T�͐l�����킵�ė��ď������m�Ă��n���2�l�͎g���̎҂ɐ����ďB�����ɓ����Ă������c�c�������ɂȂ��ċ�����āc�c����߂��ė�������������̏]�Ҕ��������������Ɗw���̎l�l�́A�������i�����Ƃ��đD������Ďs�X�ɍs������W���Ɏ�����ׂ��200�т̑K�m����ł���n���̂Ăē����������3�l�������A���Ă����v�i�ȏ�A�[�J��w����s�L�x�Ap.133-4�j�B�����āA22���ɂ��A�����悤�ȃg���u������������B
�@���̂悤�ɁA��4���̏�D�҂��肪�����Ղ������Ƃ��Ă��p�ɂȂ��Ă���̂́A�ނ炪��ɑ��g��s�ɐ����������ߋ֗߂���炳�ꂽ����ł��낤�B����ȊO�̋��c��g�͂��łɂ��ꂱ����������Ղ����Ă����Ƃ݂���B�Ȃ��A838�i���a5�j�N7��18���A�u��Ӓ����ۂ��������Ă����������͂��̍��̂Ȃ�킵�Ť�x��̐l�����Ċ��̕�����邽�߂ɁA��ɂȂ�Ƒ��ۂ�ł̂ł���v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.37�j�����͕\�����ł����āA�����̍����̎����Ղ��Ď��������߂ɂ������Ƃ݂���B
�@�����g��s���A�ǂ̂悤�Ȋ����̍����𓂂Ɏ��������͕s���ł��邪�A�����̑��^���������͖��炩�ƂȂ�B���łɂ݂��悤�ɁA������g������k�͉~�m�����Ɋw���^�i�⏕�j���Ă���i����͊����Ƃ݂���j�B�Ⴆ�A839�i���a6�j�N2��27���A�~�ڂ��V��R�Ɍ������ɓ������āA�u�����܌�(�֓��Y�̌�)35�D(1�D��4�䤖�12Ұ��)���^��10�����ˤ�����^��65��(1�Ԃ�6���223.8����)�����25�嗼(1�嗼��3����)�����킵�^�����A�w��̎����ɂ��Ă������v�Ƃ���i�[�J��w����s�L�x�Ap.142�j�B
�@�~�m���A�����l�X�Ȑl�X�ƕ��i���ӗ炠�邢�͓y�Y�����S�ʕi�Ƃ��đ��^�������Ă���B�Ⴆ�A���N3��22���A�����A���D���o���ɓ������āA�ݗ��̐��b�������V���l�ʖ�̗��T�����u������2���Ƒ�⍘�сi�����������сj��^�����v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.148�j�B�������A�~�m�̓��L���������A�ނ͑��^����邱�Ƃ������A���^�������̂͂킸���ł���B�������A�ނ̑��^�i�͒P�ɓy�Y���Ə̂������̂������A��̓I�Ȃ��̂͋�̑������{�����i�C�t����Ѥ�M�̃Z�b�g������̎쐔�������@���L��H�p�̊C���Ƃ��������ׂȂ��̂ł������B
���~�m�����������A�����o�T�╧��Ȃǁ�
�@����ɑ��āA�~�m�����^���ꂽ���̂́A���푽�l�ō��z�ȋ��i�ł������B�Ⴆ�A�~�m������845�i���a12�j�N5��15�����m�̑m���A�哿�A�����̑��ʂ��āA������ދ�����ہA�������S�ʕi������Ă���B�Ⴆ�A�E���Y���E�k�D�m�́u�ȑO�Ɍ���ѐD���̔����ނ≺�т��ǂ��{���Ă��ꂽ���Ƃ���������ނ́A���܁c�c�S�ʂƂ��Č�2�D(��25Ұ��)��֒���(�l��ȉ�B�Y����)2��(��1.2�۸���)��c��1����K2�ѕ�(2000��)�𑗂��Ă����v�Ƃ��A����E����������u����(�h�B�n���ŐD��������)10�D��h����1�{���h�ō�����g�їp����2����a��(���낢��ȍ������킹������)1�т���5�҂̔��ܗ��i�����@��)1�¥�t�F���g�̖X�q2�¥�⎚�̋����o1�����炩������1����K2�ѕ����ł������v�i�ȏ�A�[�J��w����s�L�x�Ap.580-1�j�B
�@�~�m�����́A��g��s�������ɏo�����Ă���ԁA�g�B�ɑ؍݂��Ă������A���̒n�ɂ����Ă��Ȃ�̌o�T�╧����w�����Ă����悤�ł���B�����g�A���D10�ǂ��A������ɓ������āA�~�m�����͈���ōݗ��̊�Ă�i�߂Ȃ���A������839�i���a6�j�N4��5���A�u�����ŋ��ߓ����o���̓������|����1��������E��ّ��E�����̙֑ɗ���d�l(���d�̗l��)�Ȃǂ���ꂽ��̑唠1���A��8�D�̎w�������h�H�Ɋ����������Đg�̉��̕����ˑ����Ă����v�̂ł���i�[�J��w����s�L�x�Ap.160�j�
�@����ɁA�~�m�����͒����ɓ����āA���̒����ɂ킽��؍ݒ��A�o�T�╧����w�����A�������ʌo�A�͎ʂ����Ă������B��������ދ���]�V�Ȃ������ƁA�u�������x�x�ɂ�����A������ʂ��������o�_������V�O��֑ɗ�������肵�āA�S������I���������ނƈߕ��͍��킹��4��(���Â�)������������ŁA3����途n���āA���̌��菑������̂�҂�����ґ��������邱�Ƃ��S�z�������̂ł͂Ȃ�����������ʂ����������(�T�Ђ╧��)��g�ɂ��āA���{�Ɏ����čs�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ邱�Ɓc�c�A���r���̏��B��{�̓_���ʼnו��̒����������邱�Ƃ����ꂽ�v�������Ă���i�[�J��w����s�L�x�Ap.573�j�
�@�~�m���������ꂽ���Ԃ͉w������̂Ȃ��ő傢�ɂ��������A�����̍����̏Љ���V���l�̋��͂ŖƂ�邪�A��@�ꔯ�������Ƃ�����B����͕��@������ł��ꂽ����ł������B845�i���a12�j�N7��5���A�^�B����o�B�ɑ�����ہA�V���l�ʖ�̗��T���Ƒ��k���āA�u�k�Ɍ������r���̏B���̐l�S�͑e�\�ň�������c�c�ᒺ�̍߂ɋy�Ԃ��ƂɂȂ낤�c�c���������玝���ė����c�c����4�̂Â�́A���炭���T���ʖ�̉Ƃɗa����������ʖ�ɊǗ����邱�Ƃ𗊂����v����ʖ�́u�s������ʂ̏ꏊ�ɂ��܂��Ă��ꂽ��m���̏�n�L��g��3���̑��܂��{���Ă������ʖ�͌�9�D�ƐV���̏���10�{(�䔯�p)�����5������̑����Ȃ���ʂ��̂��{���Ă��ꂽ�v�Ƃ����i�[�J��w����s�L�x�Ap.596�j�
�@���@�̎���A846�i���a13�j�N2��5���N�A�~�m�����͒��Y����D�ő^�B�Ɍ����킹�A�a�����������̂�����ė������邱�ƂƂ����B�u6��29������Y�����߂��ė�������킹�đ^�B�̎{�嗫�T���̎莆������������ɂ��Ƥ��ɗa�������Ă�������╶���̂�����ّ�����������̑��֑ɗ��ŋɍʐF�̕t�������̂ͤ�̓�ߓx�g�̒��ɏ]�����ʒ������ɂ��т��������̂Ť�T�������łɏĂ��ď������Ă��܂����Ƃ����B���̑��̒��F�̂Ȃ�����╶���Ȃǂ͂��ׂĉ^�ю����ė��邱�Ƃ��ł����v�i�[�J��w����s�L�x�Ap.624�j�B�ʖT���́A���{���痈���~�m�ւ̑������g������ł���A���̗a����i�̏ċp�������ɂ킩�ɂ͐M�p�ł��Ȃ��B
�@���̌�A���������x���D�ɐςݑւ��Ȃ�����{�Ɏ����A�����킯�ł��邪�A�����̏����i�̃��X�g�A�ז���A���̌o�߂ɂ��ẮA���L�͌��Ȃ��B�[�J���ꎁ�́A�u�����V���������^�v��t�^�Ƃ��Ď����Ă���Ă���B���̓��e�́u������ܑ�R����їg�B�Ȃǂŋ��߂��o�_��O�u�̖@�储��я͑`��`�L�����ׂČv584���802����ّ�����������̑�֑ɗ�����я����̒d����ɗ��Ȃ�тɍ��m�̐^�e�ȂǍ��킹�Čv50�_�v�ƂȂ��Ă���i�[�J��w����s�L�x�Ap.658�j�B
�@����ȊO�ɁA�l�X�ȕ����Y��A�ґ�i�������A�����ł��낤�B�����������Ȃ�����A�܂������A�z�{�A�ٗp�A�p���Ȃǂɓ������āA�~�m�����͂��ꂱ��̓y�Y���ł͎����肸�A���{���瑊���ʂ̍�������������ŁA����ɓ��Ă��Ƃ݂���B���@�m�͏��l���o�Ȃ��ɁA���@����̗��͂ł��Ȃ������ł��낤�B���̗��͌��Ղ̗��ł��������ł��낤�B
| |
|
|
|
| 834 | ���a�� | 1 | ������g�ɓ�����k����g�ɏ���⹂�C������(��17�������g)� |
| 836 | ���a3 | 5 7 8 9 |
�����g��s���Â̒Â��o����\���J�ɂ���������g�D4�Ǥ�ےÂ̍��֓c�̔��ɔ��� �����g�D4�Ǥ�����̒Â��o�����1�D���4�D�Y�����āA��O�̍��ɋA��� ��2�D�͔�O�̍����Y�S�ʓ��ɋA�����������D�̔j���B ��3�D��������16�l����őΔn���̓�Y�ɕY������̌㤑�3�D�̏����x��9�l����O�����ɕY����Ԃ��Ȃ���3�D�3�l���悹�đΔn���̓�Y�ɕY����������҂��킹28������v�҂������O�ҕ��Y�ȉ�110��� ������g������k���������ߓ���Ԋҡ |
| 837 | ���a4 | 3 4 7 8 |
������g������k��o���̂��߁A���ɕ{������� ������g������k�̑�1�D��啽�ǣ�ɏ]�܈ʉ�������� �����g�D�3�ǂ������̒Â��o��� ������1�D���4�D���ɕY�����2�D�͒l�Ó��ɕY����D�̔j�����Ĥ�Ăѓn�C�Ɏ��s���� |
| 838 | ���a5 | 4 6 7 9 12 |
�����g�̏o�����Ñ����邽�߁A�����g�������ɕ{�ɔh��� �����g�D��o������ �������g�����n�q���ۂ̒m�点���顑�1�D���4�D�̌����g��s��g�B�ɒ�������D�����A���g�ɏ��߂��D�̔j����A�r�̏A�q�s�\�ƂȂ� �~�m�������2�D���C�B�ɒ��������⹂���D���Ȃ��������Ƃ�� ��g��s������ɓ��褗��N��������@�ɉy����g�B�Ɏc�����Ă����V���������줋A���D�p�ӂ̂��߁A�^�B����������N�[������V���D9�ǂ��ق������ |
| 839 | ���a6 | 1 3 4 8 9 10 |
�����B��̍��ɔz������� ��g��s�9�ǂ̐V���D�ő^�B���o����̉͂�����C�B������� �C�B���o����A���̓r�ɂ�� �����g��s��V���D9�ǂɕ��悵�ċA��1�D�͔����7�D�͔�O�̍����Y�S�������ɓ��`�����1�D�ƌ�����2�D�̏����͕s��� ������g������k��ߓ���Ԋҡ���̒������m�ې��n�����ǖ[�Ɏ�������������題������w�m��Ť�������@���������� �����^���R�㎁�v�炪����Ă������̐V���D1�Ǥ�����̒ÂɋA�顓������Ղ̂��߂̊��s�������O�ɐݒu� |
| 840 | ���a7 | 2 4 6 |
�����z����̉B����A���ɌĂт��ǂ���� ������2�D�ɏ���Ă����m��D�����������礑���̍��ɋA�顓��D�͢��C�̑��n��ɕY����D�͔̂j������M�������Ҥ���n�ŎE���ꂽ�ҁA���킹��140�]���4��23�����g�������k���������ɁA�Q�c����ُ]�O�ʡ ������2�D�ɏ���Ă��������y�����Ǜ�������A����̍��ɋA�顊�����u��C�̑��n��œ���5�ڂ̖g1���Ȃǂ̕�������� |
| 841 847 894 |
���a8 ���a14 ����6 |
�H 9 8 9 |
�w��b�Ԃ�������顕֏悵���D�͐V���D�����D��Ȍ㤓��D��V���D�̓����Ԃ̉�����p�ɂɂȂ� �������v�m�~�m��V���l�����̑D�ŋA������ �������^��������g��I���J�Y�g�ɔC������(��18�������g)� �����g�̔������~� |
�o���F�����L�����w�Ō�̌����g�x�Ap.197�A�u�k�АV���A1978�B
�y��1�z�@���g����⹂͕a�C�𗝗R�ɏ�D���ۂ����Ƃ���Ă��邪�A�����L�����͌�����g������k����D���Ă����D���ŏ��̑���Ŕj���������߁A⹂���D���Ă����D�ɏ�芷�����Ƃ����u��l���I�Ȃ������U���������肩������g���߂��钩�c�̗D�_�s�f���ɂ����т����ᔻ�̖ڂ��������ł����v���A�܂����łɐV����݊C�Ƃ̌��ՂŁA�������e�Ղɓ���ł���̉��ŁA���łɌ����g���Č����������������̂ł͂Ȃ����ƌ��Ă���i�����L�����w�Ō�̌����g�x�Ap.16�A�u�k�АV���A1978�j�B�Ȃ��A������g������k��16��������g���얃�C�̑�7�q�A���g����⹂�5��O���c�͌��@�g�̖��q�ŁA�ꑰ�͌��V���g�A���݊C�g�̑�g�ł������B���̊Ԃ̊m�����������ƌ�����B
�y��2�z
�@835�i���a2�j�N2���̑��D�g2�l�̔C������A1���N�]�Ō����D�̊������߂Â��A100�l���̕���z�������B�����������̂͊e�D25�l�̎ˎ�ȂǏ�g���ł������Ƃ݂��B
�y��3�z
�@�V���D����\�����g�Ɋ�����\���g�𗽂�i�킽��j�s������Ƃ��m���A�~�m���u���݂�ɑ��裂Ƌ����Ă���A�A���V���D9�ǂ�1�ǂ��x���������̂̋�B�Ɉ����������Ƃɑ��āA�����g�D��4�ǂƂ��j�ӂ������Ƃɂ��āA�����L���������̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�u�����猭���g�D�̑��D�Z�p�͂����Ԃ�x��Ă��褂܂��q�C�p���ٗ�ł������Ƃ����]�������������v�B�u�������A�����g�D�ƐV���D�Ƃ��y�U�ɂ����点�Ĥ���̗ǔۂ肷��̂ͤ�ǂ����Ԉ���Ă���̂ł͂Ȃ��낤��������160�70�l�����g�߂��^�D�������40�50�l�����悷�钆�^�D�ł������v�B
�@�u�����g�D�̍\�����ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������ͤ�قƂ�ǂ킩���Ă��Ȃ�������A���N�S�ς̗p���m�ρn�̏��\���D�Ť����p�ނƂ��Đڍ�������^�̑D�Ť�����ƘE���������p����Ă����160�70�l�̏���1000�Η]��̉ݕ�����ڂ���傫�ȑD�̂����ɤ����g�̂����肪�傫����g�Q���Ђǂ���Τ�ڍ����������������w��䃁i�ւ����ƂƂ��j�Ƃ������ꕪ����ɂȂ��Ă��܂��ꍇ�����������v�
�@�u����ɔ����Ĥ�V���D�͒��^�D�ł��������礑���p�ނƂ��Đڍ�����K�v�̂Ȃ��\���ł������ł��낤�����g����D�̖ʐς�����������g�ɖ|�M����ĂऑD�̂̑����͍ŏ����ł��͂��ł��題����g�D�̍q�C�̖��l���ͤ���̑D�̂̑傫���������ƂɌ��������������Ƃ͊m���ł���v�i�ȏ�A�����O���Ap.152-4�j�B
�y��4�z
�@�����L�����́A�����g�D�̑���̗��R�́A�u���łɖ؋{�t�F����ɂ���Ďw�E����Ă���悤�ɤ�����g�D�̍q�H���傫���W���Ă������߂��낤�v�Ƃ����A���ꂪ�����g��1���i����-�V�q���j�̖k�H��A��2���i����-�~�m���j�̓쓇�H�łȂ��A��3���i���m���ȍ~�j��H���Ƃ�悤�ɂȂ��Ă���A����ڗ����đ����Ȃ����B�������A�u���łɏq�ׂ��悤�ɤ���̍ő�̌����ͤ�����g�D�̑�^�����Ђ����Ă����Ƃ����l�����Ȃ��B��1���̌����g�́A1�ǂ̏����120�l���2���ɂ�140�50�l���3���ɂȂ��160�70�l�Ɛl���͖c�ꂠ���顏���̑����ɂƂ��Ȃ��A�ύڕ����̑�����n���ɂȂ�����D�̑�^���͔������Ȃ����������ɔ�Ⴕ�ĊC��̊댯���͍����Ȃ��Ă����v�Ɛ�������i�ȏ�A�����O���Ap.157-9�j�B
�y��5�z
�@�����L�����́A���̔����ƎE�Q�ɂ��Ĥ�u�P�ɖ������܂Ƃ�����肢�������ł��Ȃ��������߂̕s���̔������͎Ƃ�Ȃ������J�O�Y���ɂ��Τ���������N����3�N�O�ɤ�V���͓��̕�Ḑߓx�g�ɓz�X�褓z�X�����ɔ������i�ǂ��������ߓx�g�͓��̐��{�̎w������������������{�͂�����݂Ƃ߂Ȃ���������̐��{���z�X�̔������݂Ƃ߂Ȃ��������ɂ͒��̌����������߂炵�����������������l���ɓ����Ƥ�z�X�̔�����]�ފC�㐨�͂Ƥ����������Ƃ낤�Ƃ���V���M���Ƃ����g��Ť�ނ�̍s���ɔ����Ă������E�������Ƃ��l�����������(�u�����O���̓C���ƑΑ嗤�C���ʖf�գ)��Ƃ���Τ���̔����ͤ�ł���������ꂽ���́v�Ƃ���i�����O���Ap.150�j�B
�y��6�z
�@�����ŁA�����A�~�m�͐_���̑D�ŋA�����悤�ƍl�������A���N6��9�����ɂ��Ƥ�t���Y��_��Y��͖��B�̒��x�M�̑D�ŋA�����Ă��܂����Ƃ����m�点�������Ĥ�~�m�͋A���֑̕D���������A�����L�����͂��́u�_��䂽���̑D�c�c�ͤ���{�D�̂悤�ɂ�����ꂪ����������̑D�͐_��Y���������g���x�M�̑D�Ɠ����ł���ƍl�����ق��������v�Ƃ����i�����O���Ap.169�j�B
�@�܂��A���̐_���i��_�h�H����j�́u�O�N�ɐ��C�̐����҂Ƃ��Ĥ�~�m�ւ̕����^���̊Ǘ����Ƃ�����ڂ�т��āA���ߐ��{���瓂���킳�ꂽ�̂ł��낤����̌㤔ނ͈ɗ\�������Z�ʏ�̊��ʂɂ܂ł̂ڂ褍�������߂ɓ������킳��Ă���v������A�t���Y�́u�d�����ڑ叉�ʏ�Ƃ���c�c�t����Ɠ���l�Łv�A�݊C�ʎ��Ƃ��Ċ��Ă����Ƃ����i�����O���Ap.173�j�
�y��7�z
�@���a�����g��A�~�m�̂悤�ɁA�m�����͂��������V���D�A����ɓ��D�𗘗p����悤�ɂȂ�B�~����853�N�V���l�ԗ���̑D�œn�����858�N���l�����l�̑D�ŋA�����Ă���B�b�Ԃ�841�N�ȗ�3�x�������邪�A�ŏ��̉��q�̐V���D���O�A���̌�͂��ׂē��D�𗘗p���Ă���
�y��8�z
�@�u���a�̂���̍��ɂͤ���s���͂Ă悤�Ƃ��Ă��邠�肳�܂ł�������ɂ�������炸����ւ̔h���͋��s���ꂽ�v���ł��邪�A�u�����g�̔h���ɂ͔���Ȕ�p�v���������Ă���A�u���Ƃ��Τ���̓V�q�ւ̑��������łऋ��500������D��������200�D����Z��������200�D��ׂ�������300�D�����������300�D�����������300�D��דԖ�1000�ԂȂǂȂǤ������̂ɔς킵���قǂ̍����ł�����������g��s�ɂ��A��g�ɂ͂�������60�D���150�ԥ�z150�[����g�ɂ͂�������40�D���100�ԥ�z100�[�Ƃ������悤�ɤ�S���ɂ������ʥ�ȂȂǂ�����Ƃ��Ďx������額q�C���̐H����(�ق�����)��400�߂����K�v�ł��題�����g�ɂ͍���200������g�ɂ�150���̑؍ݎ��������x�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����v���◯�w���ւ̗��w����傫���v�Ƃ����i�����O���Ap.189�j�
�y��2�z
�@835�i���a2�j�N2���̑��D�g2�l�̔C������A1���N�]�Ō����D�̊������߂Â��A100�l���̕���z�������B�����������̂͊e�D25�l�̎ˎ�ȂǏ�g���ł������Ƃ݂��B
�y��3�z
�@�V���D����\�����g�Ɋ�����\���g�𗽂�i�킽��j�s������Ƃ��m���A�~�m���u���݂�ɑ��裂Ƌ����Ă���A�A���V���D9�ǂ�1�ǂ��x���������̂̋�B�Ɉ����������Ƃɑ��āA�����g�D��4�ǂƂ��j�ӂ������Ƃɂ��āA�����L���������̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�u�����猭���g�D�̑��D�Z�p�͂����Ԃ�x��Ă��褂܂��q�C�p���ٗ�ł������Ƃ����]�������������v�B�u�������A�����g�D�ƐV���D�Ƃ��y�U�ɂ����点�Ĥ���̗ǔۂ肷��̂ͤ�ǂ����Ԉ���Ă���̂ł͂Ȃ��낤��������160�70�l�����g�߂��^�D�������40�50�l�����悷�钆�^�D�ł������v�B
�@�u�����g�D�̍\�����ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������ͤ�قƂ�ǂ킩���Ă��Ȃ�������A���N�S�ς̗p���m�ρn�̏��\���D�Ť����p�ނƂ��Đڍ�������^�̑D�Ť�����ƘE���������p����Ă����160�70�l�̏���1000�Η]��̉ݕ�����ڂ���傫�ȑD�̂����ɤ����g�̂����肪�傫����g�Q���Ђǂ���Τ�ڍ����������������w��䃁i�ւ����ƂƂ��j�Ƃ������ꕪ����ɂȂ��Ă��܂��ꍇ�����������v�
�@�u����ɔ����Ĥ�V���D�͒��^�D�ł��������礑���p�ނƂ��Đڍ�����K�v�̂Ȃ��\���ł������ł��낤�����g����D�̖ʐς�����������g�ɖ|�M����ĂऑD�̂̑����͍ŏ����ł��͂��ł��題����g�D�̍q�C�̖��l���ͤ���̑D�̂̑傫���������ƂɌ��������������Ƃ͊m���ł���v�i�ȏ�A�����O���Ap.152-4�j�B
�y��4�z
�@�����L�����́A�����g�D�̑���̗��R�́A�u���łɖ؋{�t�F����ɂ���Ďw�E����Ă���悤�ɤ�����g�D�̍q�H���傫���W���Ă������߂��낤�v�Ƃ����A���ꂪ�����g��1���i����-�V�q���j�̖k�H��A��2���i����-�~�m���j�̓쓇�H�łȂ��A��3���i���m���ȍ~�j��H���Ƃ�悤�ɂȂ��Ă���A����ڗ����đ����Ȃ����B�������A�u���łɏq�ׂ��悤�ɤ���̍ő�̌����ͤ�����g�D�̑�^�����Ђ����Ă����Ƃ����l�����Ȃ��B��1���̌����g�́A1�ǂ̏����120�l���2���ɂ�140�50�l���3���ɂȂ��160�70�l�Ɛl���͖c�ꂠ���顏���̑����ɂƂ��Ȃ��A�ύڕ����̑�����n���ɂȂ�����D�̑�^���͔������Ȃ����������ɔ�Ⴕ�ĊC��̊댯���͍����Ȃ��Ă����v�Ɛ�������i�ȏ�A�����O���Ap.157-9�j�B
�y��5�z
�@�����L�����́A���̔����ƎE�Q�ɂ��Ĥ�u�P�ɖ������܂Ƃ�����肢�������ł��Ȃ��������߂̕s���̔������͎Ƃ�Ȃ������J�O�Y���ɂ��Τ���������N����3�N�O�ɤ�V���͓��̕�Ḑߓx�g�ɓz�X�褓z�X�����ɔ������i�ǂ��������ߓx�g�͓��̐��{�̎w������������������{�͂�����݂Ƃ߂Ȃ���������̐��{���z�X�̔������݂Ƃ߂Ȃ��������ɂ͒��̌����������߂炵�����������������l���ɓ����Ƥ�z�X�̔�����]�ފC�㐨�͂Ƥ����������Ƃ낤�Ƃ���V���M���Ƃ����g��Ť�ނ�̍s���ɔ����Ă������E�������Ƃ��l�����������(�u�����O���̓C���ƑΑ嗤�C���ʖf�գ)��Ƃ���Τ���̔����ͤ�ł���������ꂽ���́v�Ƃ���i�����O���Ap.150�j�B
�y��6�z
�@�����ŁA�����A�~�m�͐_���̑D�ŋA�����悤�ƍl�������A���N6��9�����ɂ��Ƥ�t���Y��_��Y��͖��B�̒��x�M�̑D�ŋA�����Ă��܂����Ƃ����m�点�������Ĥ�~�m�͋A���֑̕D���������A�����L�����͂��́u�_��䂽���̑D�c�c�ͤ���{�D�̂悤�ɂ�����ꂪ����������̑D�͐_��Y���������g���x�M�̑D�Ɠ����ł���ƍl�����ق��������v�Ƃ����i�����O���Ap.169�j�B
�@�܂��A���̐_���i��_�h�H����j�́u�O�N�ɐ��C�̐����҂Ƃ��Ĥ�~�m�ւ̕����^���̊Ǘ����Ƃ�����ڂ�т��āA���ߐ��{���瓂���킳�ꂽ�̂ł��낤����̌㤔ނ͈ɗ\�������Z�ʏ�̊��ʂɂ܂ł̂ڂ褍�������߂ɓ������킳��Ă���v������A�t���Y�́u�d�����ڑ叉�ʏ�Ƃ���c�c�t����Ɠ���l�Łv�A�݊C�ʎ��Ƃ��Ċ��Ă����Ƃ����i�����O���Ap.173�j�
�y��7�z
�@���a�����g��A�~�m�̂悤�ɁA�m�����͂��������V���D�A����ɓ��D�𗘗p����悤�ɂȂ�B�~����853�N�V���l�ԗ���̑D�œn�����858�N���l�����l�̑D�ŋA�����Ă���B�b�Ԃ�841�N�ȗ�3�x�������邪�A�ŏ��̉��q�̐V���D���O�A���̌�͂��ׂē��D�𗘗p���Ă���
�y��8�z
�@�u���a�̂���̍��ɂͤ���s���͂Ă悤�Ƃ��Ă��邠�肳�܂ł�������ɂ�������炸����ւ̔h���͋��s���ꂽ�v���ł��邪�A�u�����g�̔h���ɂ͔���Ȕ�p�v���������Ă���A�u���Ƃ��Τ���̓V�q�ւ̑��������łऋ��500������D��������200�D����Z��������200�D��ׂ�������300�D�����������300�D�����������300�D��דԖ�1000�ԂȂǂȂǤ������̂ɔς킵���قǂ̍����ł�����������g��s�ɂ��A��g�ɂ͂�������60�D���150�ԥ�z150�[����g�ɂ͂�������40�D���100�ԥ�z100�[�Ƃ������悤�ɤ�S���ɂ������ʥ�ȂȂǂ�����Ƃ��Ďx������額q�C���̐H����(�ق�����)��400�߂����K�v�ł��題�����g�ɂ͍���200������g�ɂ�150���̑؍ݎ��������x�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����v���◯�w���ւ̗��w����傫���v�Ƃ����i�����O���Ap.189�j�